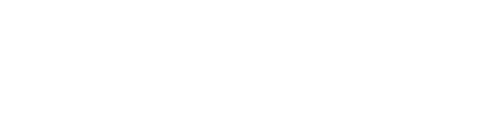つもり、つもり、あいがふりつもり
「俺の話も、聞いてくれますか?」
「ああ、聞かせてくれ」
迷いを打ち払うかのように俺の問いに力強く頷いてくれる護さんの優しい声に、俺の話をすることを再度決心した。
どこから話すべきだろうかと一瞬迷って、すぐに全部話そうと思った。護さんが俺に話してくれたから、俺もそれに応えたいと心から思えたから。
「俺の家は、周りよりも少し裕福だったと思います。家族は両親と妹。父は男らしくあれ、母は後ろ指さされない人生を歩みなさいと何度も言われてきました」
「厳しいな」
「はい、とっても……友だちと交遊するよりも家で勉強しなさいも口癖でした」
「妹にも厳しかったのか?」
「いえ。2番目だったからか女の子だったからか、父も母も妹には少し過保護だと思うほど可愛がられていました。俺よりも要領がいいということもあったんでしょうけれどね」
「ふうん……確かに男と女で気を使うことが違うだろうけれど、理一にだけ厳しいのは納得いかねえ」
「……そう言ってくれたのは、祖母だけでした。俺、こんな見た目だし好きなことはビーズ集めとか裁縫で……女々しいとお父さんには鼻で笑われてきましたが、祖母は嬉しそうに一緒にビーズのブレスレットを作ったりしていました」
「そうか、おばあさんは理一のこと大事にしていたんだな」
妹には甘く俺には厳しかった両親の話のときに棘々した空気が、祖母との大事な思い出の話をすると口調が和らいだ護さんにきゅっと胸が締め付けられた。
「……はい。俺の全部を受け止めてくれた唯一の人、でした」
「ぜんぶ?」
「俺、その……同性愛者、なんです」
「!そう、なのか」
驚いた様子を見せながらもそれでも俺を傷つけないように大げさな反応をしないでくれる護さんの優しさが嬉しい。同性が好きと知っただけで遠ざかるような人もいるのに、護さんは俺から身体を離さないでいてくれるのが、勘違いしてしまいそうになるけれど、今だけはこの甘い疼きをそのままに話を続けた。
「父にも母にも誰にも言えずに、ついにおばあちゃんに俺は打ち明けました。護さんと同じようにそうかいとだけ言って、後は深く聞きはしませんでした。普通に受け入れられたことが俺は何よりも嬉しくて、おばあちゃんの前では本当の俺でいれました。……男らしく、後ろ指さされない人生を重んじていた両親には到底受け入れがたいものだと言うのは、よくわかっていましたから」
幼い頃からそう言われ続けてきたのだ。自分の男らしくない見た目もどちらかというと女性的な部類に入る趣味も、異性の胸の膨らみよりも同性のゴツゴツした血管の浮いた手に目が向くことも、全てが両親が求める自分と本来の自分は違うのだと嫌でも分かって全てに罪悪感を覚えた。
とはいえいつまでも誤魔化せるものではないことも何となく分かっていた。どこまでも普通の男として幸せを掴んでほしい両親にとって結婚して子どもを作りなさいといつか求めることを察していた。そのときにはきっと俺も成人していて一人でそれなりに生きていける年齢になっているだろうから、そのときは戦うときなのだろうと考えていた。
まさか、あんな最悪のタイミングでバレるだなんて少しも思わなかった。
「ということは……浮気をされた、というのは」
「初めての彼氏に、ですね。俺が大学2年生、相手は大学1年生だったかな。名前はもう忘れちゃいましたね」
でも見た目は少し覚えている。護さんとは似ても似つかない、ナンパな雰囲気で髪を金に染めてツンツンとワックスで尖らせた、ちょっと生意気で強引な人だった。彼女欲しいと騒いでいたのに俺に告白したのだから驚いたなあ。俺の恋人になれとそんな俺様発言の割には身体がガチガチに緊張してて、顔も赤くて真剣な顔をしていたから、つい頷いてしまった。今となっては思えば俺なんかを好きになってくれたという喜びばかりで彼のことはすきじゃなかったと断言できる。それでも、当時はそれを本当に恋だと思っていた。だから俺なりに大事にしていたつもり、だった。
「大学からは一人暮らしになったので家族からの監視の目が緩んで、単位さえ何とかしていれば結構自由だったので、交遊してみたり、恋人を作ったりしたんですけれど……いつの間にか孤立していて、俺には彼氏しかいない状態になって。で、そんな中で浮気が発覚しまして……」
「この傷も……そのことを気に病んでのことか?」
「んっ」
突然人差し指と中指でゆるりと左手首の内側から肘の方まで辿られて、ぞくっとして変な声が出る。あまり触れられないところだからか、切り傷の痕のせいなのか、変に過敏になっていることを今初めて知った。
「あ、いえ、それは……ちょっときっかけ?事件?がありまして」
息が切れそうになりながらも、何とか続きの話しをする。護さんの手から逃れて右手で左の二の腕を掴む。あれは忘れることはできないだろう。きっと、永遠に。
「俺その人のこと本当に好きなつもりだったんですけれど……でも、やっぱり、浮気されたらもう愛想が尽きるものじゃないですか」
「そうだな」
「だから、別れようと言ったんです。気持ちがないまま付き合っても悲しくなるだけだから、て。でも、何故かすごいごねられたんです」
「浮気した奴の方がなんで別れるのを嫌がるんだろうな……。こっちは別れないって高を括っているんかね」
「そうかもしれませんね。俺少し依存気味だったから、彼はそう思っていたのかもしれません。それで、暫く別れる別れないの平行線だったんですが、その……刃物で切りかかられまして」
「切り……っ!?」
「はい。大学から家に帰るまでの道を待ち伏せされて……ここを」
抑える二の腕に視線を落とす。深く切られたせいで俺の身体に未だ残ったままのそれ。今も熱い血が自分の体内から流れていくのとは逆に体温がどんどん下がっていったことを思い出す。
「幸い命に別状はなかったです。が、何となく、そのことがきっかけで自傷が癖になったんです。誰かに同情されたいわけではなかったんですが、こう辛いこと思い出したり、行き場のない息苦しさにどうしようもなくなったときとかに、つい切ってしまうようになりました」
袖を肘ぐらいまでまくると、そこにはもう切っていないところのほうが少なく、切り傷の痕でまみれた柔い皮膚。どうして護さんがこれを知っていたのか不思議だったけれど、そういえば初めて会ったときナミの身体を温めるために上着を脱いでいたから、そのとき護さんにこの汚い傷を見られたのかもしれない。
「俺が孤立したのは彼が俺の悪い噂を流していたのが原因でした。事件後にそれが発覚して何人かメッセージで謝罪されましたが、俺は返事もせずにブロックしました」
護さんの顔は見れないまま早口で説明した。どうして突然冷たくなったのかと考えていた原因こそその恋人だったのだと分かった時、もう俺は何も感じなかった。それ以上に大変なことが起こってしまったから構っている暇がない、と言った方が正しいのかもしれない。
「なんで相手をそうして傷つけるぐらいそんなに好きなくせに浮気なんて馬鹿なことをしたんだ、そいつ」
「嫉妬してほしかったとか、俺しか見えなくしたかったとか、言っていた気がします」
「わかんねえな……。しかも、周りの奴らもお前の話を聞けよ。なんでそいつの言葉だけ信じるんだよ」
護さんが怒ってくれている。彼だけではなく、周りの人間にも怒ってくれる。なんだか、当時の俺も救われたような気持ちになって、胸が少しまた軽くなった。
「傷害事件になって……そこで彼との関係も、どうしてそうなってしまったのか……俺が同性愛者であることを両親にバレてしまいました」
駆けつけてきた両親は最初こそ心配してくれたけれど、細かい事情を知って驚愕へ、そして怒りと悲しみに変貌した。今まで隠し通していたものがバレてしまった。恐怖に怯えると同時に、酷く開放的な気持ちになった。
「それで……大学を辞めさせられて、10年は軽く生活できるだけの金の入った通帳とクレジットカードを渡されて……この家……おばあちゃんの家に連れてこられました。この家から出るも出ないも好きにしていいが、出てきたとしてもこちらに接触してくるな、と言われました。実質絶縁ですね」
あと1年で卒業だったから勿体ないと思った。でも、それだけだった。すっかり人間不信になって誰にも心を打ち明けるつもりもなくなった俺にとってもう学校に行かずにこの家にいるだけでよかったことにすっかり安堵してしまった。
「おばあさんは、どうしてたんだ?」
「……高校2年生のとき。倒れてそのまま……」
「……そうか。おばあさんが生きていたら、きっと、お前のこと何も言わずに受け入れてくれたんだろうな」
「そうだと思います。ずっと、ちゃんと俺の話を聞いてあげてと両親に言ってくれていましたからね。……本当に、優しい人だった」
おばあちゃんが倒れたと聞いたとき、そしてすぐに亡くなったのだと聞いたとき、棺桶から見るおばあちゃんの顔、火葬場へ連れて行かれるところ、骨だけになってしまったところ。俺はずっと泣いていた記憶しかなかった。大好きなおばあちゃん。
「理一ちゃんの人生なんだから、自分のために生きなさい」
「え?」
「おばあちゃんと最後に会ったとき、言ってくれた言葉です」
亡くなる2ヶ月前夏休みに泊まりに行って帰るとき、しわしわの手でぎゅっと俺の手を握って言ってくれたおばあちゃん。その顔はとても優しくてずっとこの家にいたいと思った。怖いばかりの家にいたくないとそう心から思った。
「その通りに生きてみたら、こうなってしまいましたけれどね。でも、俺こうなって家族との輪からも社会との縁とも遠ざかってしまったけれど、後悔はそこまでしていないんですよ。あのまま隠し通すことも考えたんですけれど、どうあがいたって俺にとって苦しいことばかりだった。それなら、もういいか、と。そう思ったと同時に穏やかに笑うおばあちゃんの言葉を思い出して……どうせバレたのだから、と。全部ぶちまけました」
「なんて?」
護さんは宥めるよう優しく問いかけてくれる。涙ながらに弱々しく訴えたと思われたのかもしれない。今まで情けない姿ばかり見せていたからそうイメージされても仕方ないけれど、そんな可愛らしいものじゃないので、幻滅されてしまうかもと少し怯えながら当時両親に向けたときと同じように俺は顔を上げて、そのとき言った言葉を口から吐き出す。
「俺は男とハンドメイドと裁縫が好きで、嫌いなのは勉強とあんたらと浮気野郎だ」
「え……」
「……そう言ったらまあ、修羅場でしたね。怒鳴られるわ泣かれるわ……だけれど、言いたいことを言えてスカッとしました。結果縁切られちゃいましたけれど」
「……そう、か」
「そんなことを言う俺に護さんは、幻滅、しましたか?」
驚いた様子の護さんに心配になって問いかけてしまう。家族に幻滅される分ならすっきりするだけだから構わないけれど、護さんには嫌われたくなかった。嫌な汗が掌に滲む。
「いいや。理一もはっきり言えてどちらかと言うと安心している。言いたいこと、言えたんだな。よかったな」
「!は、い。はい、そうです。俺はずっと両親言ってやりたかったんです。あんなに怖いと思っていたふたりも久しぶりだったから、俺も身長が父ぐらいになったからか、あまり怖くなかったんです」
「そうか。頑張ったな」
「はい、俺は……がんばったんです。がんばったんですよ、護さん」
「そうかそうか」
頭をくしゃくしゃと撫でられて、照れとともに喜びが生まれる。凝り固まった自分の感情をぶつけた俺の胸の中はどこか空っぽになったような虚しさがあった。虚無感と閉塞感。深く沈んでしまうときがあってそのときに俺は痛みで穴を埋めようとしていた。言いたいことを言えたことに後悔なんてないなのに妙な虚しさ。それは本当に言ってしまってよかったという自責の念。それを肯定されたことで暖かいもので埋まって、満たされたような気持ちになる。そっか、俺は、親に反抗したことを誰かに受け止めて頑張ったことを認めてもらいたかったんだとやっと理解した。しばらくナミを撫でるように両手で俺の頭を掻きまわしていた護さんだが、ふと気が付いたようにつぶやいたことで再度俺の頭から血の気が引く。
「ところで、どうして俺に電話をしてくれたんだ?随分と切羽詰まっている様子だったが……」
「……」
「もしかして、その元カレとか両親とかが来たのか?」
顔色を変えた俺にハッとしたように護さんが問いかける。今までの話を聞けば確かに、元カレか両親が訪れたと考えるのも無理はないだろう。だが、元カレのことも両親のことも割り切ったようなことを俺は言っていたのでどうしてこんなに俺が怯えているのか不思議そうにしている。そう、護さんが思う通り多分元カレが来て復縁を求めたとしても鼻で笑えるだろうし、あり得ないだろうけれど両親が和解を求めたとしても突っぱねている自信がある。襲来してきたのはその三人の誰でもない。今の俺の説明だけではほとんど存在感のないあの子。
「いえ、妹です」
「妹?ああ、そういやいたな……。要領がよくて両親も甘かったな。そいつが何かしたのか?」
「俺にとって、妹の理香が一番怖いんです」
4つも離れている女の子を恐れているだなんて情けないことこの上ないが、俺だけではあの子への恐怖心を払しょくできない。意を決して伝えても両親が信じてくれなかったことを、俺は護さんに話すことに決めた。声が震えてしまうのを堪えてどうして俺が妹を恐れているのか、説明する。
「理香は物心ついたときから俺に執着していました。それが実の兄に向ける妹の独占欲を超えた執着でした。両親に見えないところで気が付かない程度に怪我をさせてきました。好奇心だと痕にならない程度に首を絞められたこともあります。何もしていないのに俺がイタズラをしていたと先生や両親に嘘をついてそれに落ち込む俺を私だけはお兄ちゃんの傍にいるからね、と抱きしめてきたり。俺の教室で飼っていた金魚やメダカを殺したり……おばあちゃんと作った思い出のアクセサリーもわざと無くされたり切り刻まれたりもしました。このことは誰も信じてくれませんでした。おばあちゃんでさえも……理香の外面に騙されていましたから」
アクセサリーを無くされた、そう言うとおばあちゃんは悲しそうにしながらもわざとじゃないのだから理香ちゃんのことを責めてはいけないよと宥められた。傷ついた顔をさせたくなかったから俺は切り刻まれたことを打ち明けることはできないままだった。
「な、んで。兄である理一を、理香はそんなに苦しめるんだよ」
「……俺が苦痛に歪んでいる顔が好き、傷つけることが一番心に刻ませられるから、と言ってましたよ。俺と理香は顔立ちがよく似ているから、もしかしたらナルシストの一種かもしれません」
呆然と呟く護さんに内心俺こそ理香に聞きたいと呟きながらも、かつて泣きながら問いかけて答えられたそれを護さんに共有した。昔から本当は動物が好きだった。けれど、理香によってその小さな命も踏みにじられてきたから、ひとりになっても飼いたいと思わなかった。ただ、自分を傷つけて自堕落に生きるばかり。それを望んでいたわけではないのに、そうして生きてきた。
「来るはずのないあの子、理香が家を訪れたとき、ナミになにかあったらどうしよう。俺もどうなるんだろうと考えたくないのに考えてしまって、何をしても手が付かなくて……護さんに無意識に電話していました」
やっと、俺が護さんに電話した理由を告げることが出来た。理由だけならそれで充分なのに、護さんが自分の今までのことを教えてくれたから、俺もつい全部話してしまっていた。最後だけ説明していれば十分だったろう。でも護さんは全部真剣に受け止めて聞いてくれた。聞いてくれただけで、俺はよかった。
「俺はこれから一人で、生きていこうと。そう決めたんですけれど、ね」
朝、教室で無残に水槽ごと床に打ち付けられた動かなくなった金魚とメダカ。誰も俺の言葉を信じてくれなかった絶望。俺のことを認めてくれなかった両親、傷つけるばかりの恋人、俺の言葉が届かない他人、異様な執着心を見せてくる妹。理解者に近かったおばあちゃんもすでにこの世にいない。これからの人生をひとりでいようと決めるのには充分だった。腐ったまま生きていくのだと、砂浜の俺だけの足跡を見てはそう毎日決心を新たにして過ごしてきた。でも、でも。ほんとうは。
「ごめんな、俺は理一を一人にはもうさせたくない」
「っ」
暖かいものに身体を全身が包み込まれる。力強く締め付けてくる腰と肩の感触に泣きたくなるのは苦しいだけではない。護さんに抱き込まれ、耳元でぐずっと鼻を啜る音が聞こえて、一度唇を噛んで震える声のまま本心を告げる。
「はい、おれも、もう、ひとりにはなろうと思いません。ナミと……護さんがいてくれるから。いてほしい、です」
「ああ。当たり前だ。理一、おまえ、がんばったんだなあ。えらいよ、ほんとうに……っ」
彼の声は嗚咽で掻き消される。泣いてくれている、俺の話を聞いて泣いた彼の声がとても嬉しくて、苦しくて、でもやっぱりどうしようもないぐらいの喜びで溢れて、それが涙になって頬を伝う。
「っは……い、はい、おれ、がんばりました。ずっと、生きるのが嫌になって、それでも死ぬことはできなくて、する気も起きなくて、それでいいのかな、て、ずっと、おれは、くるしくて、え……!」
「ああ、それでいい、それがいい。りいち、生きていてくれて、ありがとう。これからも、生きて、くれ。ナミのために……おれのために!」
「はい、はいッ……!まもるさんも、ずっと、おつかれさま、でした」
「!ああ、ありがとう、ありがとうな」
居間に響くのは男ふたりのすすり泣く声。成人した男二人抱き合いながらお互い泣くなんてきっと酷い光景なのだろう。誰かがいたら男なのに情けないと眉を顰めて冷たくそう言い放つのかもしれない。でも、ここにいるのは泣き出す俺たちに気付いて心配してかしめった鼻で俺の背中をつつく犬の女の子のナミだけ。謂れのない責めを受けなくていい空間。俺たちは散々誰かに傷つけられてきた。傷つくのは男女も人間も動物も関係ない。自分のために泣いてくれる人に暖かい気持ちで満たされて涙することが悪だとは思わない。時折ナミを撫でながらそれでも俺たちはずっと泣き続けた。水分が枯れ果ててしまうのではないかと思うほど、涙を零し続けた。
「……ひどい顔だ」
「……護さん、こそ」
「……はは」
「……あははっ」
「わうんっ」
電気も暖房もつけっぱなしで、泣いているうちに眠ってしまった俺たち瞼は腫れ頬には畳の痕がついてしまい酷いもので、お互い笑い合う。ナミもつられて笑うように泣くものだからさらに笑みが零れる。そのまま順番にお風呂に入っていつものよりも少し遅めの朝食ととって、朝の散歩にしても昼の散歩にしても中途半端になってしまったけれど昨日から散歩に行けなかったのでナミもうずうずしっぱなしだったので、護さんとともに外に出た。ウミたちの墓にも挨拶した。心配していたけれど無事に相変わらずの質素な墓があって安心した。
昨夜のことにお互い触れずに、それでも護さんは俺からあまり離れることなくナミもそれを察してかいつもよりもゆったりと歩く。いつもの海辺に着くと、先客がいることに気が付く。彼女……理香だ。
「あいつって」
「……」
「う”ーーー!!」
固まる俺に小声で問いかける護さんに無言で頷いた。ナミも理香を見て唸っている。その声に気が付いたように理香はこちらを振り返る。
「……」
「あれ、お前……」
「理香……」
氷のように無表情だったナミは俺を見て口角だけをあげた……かと思えば隣にいる護さんの存在が視界に入ってギッと目を吊り上げ、指を差して波の音に負けずに叫ぶ。
「お前のせいで!お兄ちゃんは可愛くなくなったのよ!どうしてくれるのよ!」
きいん、と耳と頭に響く声に顔を強張らせる。ううん、とナミも煩そうに唸った。理香の存在に手に汗がにじむ。でも、その手を護さんがリードを持っていない手で握ってくれたからとても安心した。そして気が付いたことがあってそっと問いかける。
「あの、護さん、理香に会ったことあるんですか?」
「最近会社前でうろうろしている奴だよ。職場の奴が騒いでいたから横目で見ただけで話したことはなかったが、少しだけ理一に似ていたから印象に残ってんだ」
「そう、だったんですね」
話したこともないと言われてホッとする。護さんには言っていなかったけれど、元カレが浮気した理由は理香が接触したことから。……理香とは浮気とまでは行かなかったけれど、元々の彼は普通の異性愛者だったから。
俺と理香は血の繋がったれっきとした兄妹で顔立ちがよく似ていて……結局、女の子の方が良いとでも思ったのかもしれない。いつだって、俺が仲良くなった人は理香の方が皆好きになっていたから。護さんとは直接的な接触がなかったことに心から安心する。
「無視するな!!」
いつまでも理香への反応を示すことなくひそひそと話す俺たちに、痺れを切らした理香がまた叫んだ。理香が怒りを露わにしてじっとりと睨んでいる。いつもの何を考えているか分からない、ただただ俺を傷つけることに対して愉悦に浸っていた妹しか知らない俺は偽りの無邪気さでも優しく振舞う嘘くさい笑顔でもない、年相応の女の子の素顔の妹を初めて見た。そのぐらい焦っているということなのかもしれない。取り繕うこともできないぐらいに。
(……こんな、感じだったっけ)
記憶よりも華奢で、余裕の欠片も見当たらない彼女の姿にどこか拍子抜けに近い気持ちで見つめていると護さんが俺にリードを手渡し、俺とナミを理香から庇うように前に立った。
「無視すること言っている意味がよく分かんねえよ。可愛くないって?理一は可愛いだろうが」
「護さん?!」
突然そんなことを言うから顔が熱くなった。こんな、背ばかり伸びた男の俺に言う言葉ではないと驚いたが、護さんは平然としたまま理香と対峙して問いかける。
「お前は本当に何がしたいんだ?理一はお前の兄なんだよな。ずっと陥れることをして。苦しめることをして何が楽しいんだよ」
真っすぐな問いかけだった。俺がずっと聞くのが怖くて聞けなかったことをあっさりと護さんが聞いてくれた。俺も理香を見てその答えを待った。
「お兄ちゃんは苦しむ顔が一番かわいいの!」
あっさりと理香は答えた。答えはあまりに単純で幼稚、かつ訳の分からない返答に俺も護さんも呆気にとられた。ナミですらきょとんとしているように見えた。誰よりも先に言われた意味を理解してリアクションが出来たのは護さんだった。
「はあ、その価値観全然わかんねえよ……好きな奴には幸せにしたいし、笑っていてほしいだろうが」
「そんなものよりもお兄ちゃんは苦痛に歪んでいる表情のほうがいいのに。ひとりでいる方が可哀想で可愛い顔をするのよ?笑顔なら私の顔を見れば十分だもの。そのために今まで私は頑張ってきた。……なのに、お前のせいで」
理香は今までの俺のことを思い出したのか、目を細めて初恋に身を任せたような恍惚とした表情を浮かべていたのに、目の前の俺たちを敵でも見るような鋭い目つきで睨んできた。
「せっかく今まで馬鹿なジジイもババアもだましてひとりにさせていたのに!可哀そうなお兄ちゃんを見たくて周りの奴らも騙して孤立させたのに!一人暮らしを勝手にして、恋人まで作って……許せるわけないじゃない。
あんな男お兄ちゃんにふさわしくないのに、ひとり占めするなんて許せなかった。少し私が誘っただけで他の人間に行くような男なんて……!それだけしてもお兄ちゃんは私のところに帰ってこなかったから……自分の無力さを味わってほしかった。だから、わざとお兄ちゃんが見えるところに犬を弱らせて捨てたのに」
「!ちょ、待って」
最後のポツリと呟いた言葉に俺は焦って声を荒げて待ったをかけた。理解しがたいことを言われた。どうしても聞き流すことなんてできないことを。
「理香、犬を捨てたのは……もしかして」
「うん、そうだよ。お兄ちゃん」
「なんて、こと……なんで、俺がここにいるって……」
「あは。そうその顔!それが見たかったのよ……犬一匹も救えないことに絶望し尽くした貴方の顔が見たかった。ジジイとババアに聞き出したの。今年の夏に入る少し前ぐらいだったかな?やっと口を割ってくれたの。今まで私が未成年だからって教えてくれなかったから。それで何度か家の方に様子を見に行ったら外に大体同じぐらいの時間にこの海に散歩に来ていることを知ったから。だから、お兄ちゃんが大好きな動物が目の前で死んでいたら……これ以上ないぐらい悲しんでくれるかなって。なのに……まさか犬の一匹を助けることに成功することも、また悪い虫がつくなんて。驚いたしすごく目障り。またお兄ちゃんを可愛くさせようと思ったのに。ああ、憎たらしい」
「っ、お前は……」
「……おにいちゃん?」
どうして何も悪いと思っていないかのような表情なんだ。俺の傷ついた顔が他の命を犠牲にするほどの価値なんて無いだろう。どこから犬を捕まえてきたのか分からないけれど、よくもウミに、カイに、アオに、ナミに……そんな非道なことをしたのか。いつも理解不能だった妹。俺への異様な執着と底知れぬ不気味さへの恐ろしさが勝って何も言えなかった。でも、腕の中で冷えていく体温と助かってほしいと何度も願ったナミのことと、狭くて冷たいあの段ボールのなかで命を落としたウミたちのことを考えれば考えるほど怒りが込みあげてくる。俺の表情に理香は戸惑った様子を見せるけれどそれどころじゃない。
(護さんが、声をかけてくれなかったら、ナミも……)
俺の顔を見上げてくる無垢な瞳が視界に入る。あの日、助けることが出来なかったら、ナミはここにいない。
もしものことを考えれば考えるほどに、言い様もない気持ちと湧き上がる激動に身を焦がす。俺は口を開く。なんて言うか考えていない。ただただ激情のままに叫んで罵って、少し怯えたような顔をする俺とよく似た女を傷つけてやりたかった。
「う、わっ?」
だが、それはできなかった。手を引かれ暖かいものと密着したかと思えば視界が突然真っ暗になった。焦る俺に隣から低い声が響いた。
「理一、ごめん。少し待ってくれ」
「、まもる、さん?」
近くから聞こえる護さん声に驚いて少しだけ冷静になると同時に、目を覆うのは護さんの大きな手でほとんど抱き寄せられている状態になっていることにさっきとは別の意味でカッと身体が熱くなる。ドギマギしている場合ではないと気を引き締めていると、護さんがいつも通りに低くも少し冷たく言葉を発した。
「なあ。今の発言、誰にも聞かれたくないよな」
「はあ?」
理香は護さんに対して心底嫌そうに話を聞く気も無さそうな生意気な声を上げたが、そのあとすぐに少しノイズ混じりの理香と俺の音声が聞こえてきた。先ほどのやり取りそのままの内容。不思議に思っていると視界を塞いでいた手が外され、見えたのは空いている片手にスマホ護さん。どうやら、さっきの会話を録音したものを流していたらしいと気が付いた。理香も目を見開いて凝視していた。
「……、……」
「理一から話を聞いた限り、お前って要領が良くて両親から可愛がられて、周囲にもいい顔しているらしいな。もしも、このやり取り聞いたら……どうなると思う?」
何も言えなくなっている理香に、護さんはスマホを口元に寄せて淡々と問いかけた。
「……私を脅すというの。そんなの、だれも信じないわよ」
「人聞きの悪いことを言うなよ。ただの交渉だよ。昨日理一から色々聞いたけれど、おまえ随分猫被っているみたいじゃねえか。これを聞かれたら……どうなるんかね?」
「……」
「理一とナミ。……ついでに俺に近寄るな。動物愛護団体に訴えたっていいんだぜ。……胸糞悪いが、大した罪にはならないだろうけれど『周囲からの評判は』どうなるんだろうな?見たところ大学生っぽいし……学校に流したらどうなるのか……試したっていいんだぜ。これでも社会人でそれなりの役職にもついてて、貯金もまあまああるんだ。理一の力を借りなくてもそれなりに根回しも追い詰めることも出来るんだ。俺だってまだ大学も卒業もしていない若者を追い詰めることなんてしたくないんだ。だから、もう何もしないでいてくれ」
いつの間にか護さんは俺の手を握っていた。何も心配しなくていい、そう言ってくれるようだった。俺のことを第一に考えてくれる誰かなんて知らなった。
「理一とナミを守るためなら。俺はどんな手を使うからな」
傍から見ると、まだ成人したばかりの女の子を脅している男の図にしか見えないだろう。
理香は華奢で兄としての贔屓目も抜きにして守ってあげたくなるような容姿の女の子だ。稀に俺と妹の違和感に気付く人がいても、理香の容姿にこんなことしないと思い込んでそれ以上深入りしようとする人はいなかった。どれだけ。俺のことを守ろうとしてくれる姿に今までの辛かった俺の全部が救われた気持ちになったか、教えることは生涯を以てでも無理だろうと思った。
「理香」
「……おにいちゃん」
ナミと俺のためにならどんな手を使ってくれるという護さんの言葉だけですっかりと落ち着いた気持ちになった。事実を知って冷静になっても、燻る感情は、きっと理香に伝えなくてはいけないことだ。怖いから、と逃げるのは俺もやめる。
「生まれたとき。俺は理香のことが可愛かった。守ってあげたいと、本当にそう思った。気が付いたら異性よりも同性のことを目に追っていた俺だけれど……理香のことは、本当に純粋に兄として好きだったよ。きっと、特別だった」
本当に、天使のようだった。まだ毛もなくてお猿さんのような理香。手を伸ばすと、きゅっと指を掴んで笑ってくれた。どこもかしこも柔らかくて暖かかった。ずっと、覚えている。どんなに酷いことをされてもどんなに怖がらせられても、その記憶だけは忘れられなかった。
「もしも……俺が理香に似ていなければ、理香が俺に似ていなければ、理香がそこまで歪むことはなかったのかもしれない。俺は本当に、そういう意味はないけれど、理香のことを愛していたよ。家族として……。
きっと、理香は俺に望むのはその愛じゃなかったとしても、酷いことをされても、理香を今まで心から嫌いにっはなれなかったんだ」
今思えば、恥を捨てれば誰かに助けを求めることが出来た。でもそれは理香が悪い子になると同意義だったから、言えなかった。馬鹿な兄は自分を傷つける妹を守ろうとしてしまった。愛していた。妹として。いつか関係が修復できるという望みを捨てきれなくてここまでずるずると来てしまった。俺は、何もできないのに。
「でも。もう、俺はあんたのことが嫌いだ」
きっと、間違えた。理香も、俺も。ちゃんと向き合うべきだったんだ。悪いことは悪いのだとどんなものを敵にしてもちゃんとぶつかっていくべきだったんだ。そうすれば……こんなに歪んで修復不可能なところまでいかなくて済んだかもしれない。
「俺を傷つけるだけなら、構わなかったよ。辛くても妹のために好きにさせてあげようと、そう思った。だけど、超えてはいけないところまで来たんだよ。……本当は金魚たちが殺されたときに決断するべきだった。それは俺への、理香への、甘さだった。ひとりになるのが怖くて、怖いのに俺に執着する理香が恐れても唯一俺個人に向けられた愛だったから」
理香は信じられないと言わんばかりの表情で、潤んだ目を見開いて今にも涙を零しそうになっている。少しだけ胸が痛むけれど、撤回する気はなかった。
「さっきの話を聞いて。俺はもうあんたのことを許せそうにない。二度と、護さんの前にもナミと俺の前にも姿を現さないでほしい。……それが、俺が理香という妹への最初で最後の心からのお願いだ」
「おにい」
「ごめん。ちゃんと理香と向き合うことができなかったお兄ちゃんで。でも、お願い。もう、俺たちに近寄らないで。顔を見せないでほしい」
手を俺に伸ばして近付いてこようとする理香に対して俺は明確に拒絶する。これ以上近付かないでほしいという気持ちが通じたようでぴたりと動きを止めて縋るように俺を見る、愛おしかった、妹。
「これ以上、妹を……理香を、憎みたくないんだよ。おねがい」
天使ようだと、守りたいと思った昔の理香まで憎みたくない。ここまでされてもまだ完全には妹を憎めない自分の甘さに呆れるけれど、でも本当に、これ以上はだめだと思う。俺に近づく以上にナミと……護さんに害を与えるとするのなら、この平穏の日常を脅かしてくるのであれば、俺は何をするかわからない。そのぐらい、この日々が俺には大事なモノになっていた。もはや、家族のことも以前生活していた日々すらもどうでもよくなるぐらいに。
「……」
「わん」
暫く誰も言葉を発することができない空間、波の音とナミの声が一度響いた。
「ごめんなさい」
俺の願いに、理香は頭を下げた。その今まで見たことのないしおらしさに目を白黒させたが、理香はこちらを見ずに構わずに続ける。
「お兄ちゃんが望む愛と、私の愛は……ううん、私がきっとみんなと違い過ぎるんだね。今更気が付いても遅いけれど。だから……バイバイする。今まで、私のわがまま。受け入れてくれてありがとう。ごめんね。私、ちゃんとお兄ちゃんを普通に愛せたらよかったのにね。そうすればきっと……ううん。今までごめん。ナミちゃんも、護さんも。どうか、私を許さないでね」
そう言って顔を上げて笑った理香の顔は、昔に見たものとよく似ている気がして、背を向けていくその哀愁漂う姿に駆け出して行きたくなってしまったけれど、足に擦り寄ってくれるナミと力強く俺の手を握ってくれる護さんに阻まれる。ここが、俺の居場所なのだとそう言ってくれているふたりを振り払うことはできないし、するつもりもなかった。
「あの」
理香が去って行ったあと、いつも通りをみんなで装って散歩をして俺の家に帰っていつものクッションでのんびりと眠るナミを護さんとふたりで囲うように好きに撫でる和やかな時間。午後3時。いつもなら散歩に行っている時間だけれど今日は遅かったうえナミも護さんと十分に遊んだからか満足したようですっかり熟睡しているようだ。「ううんっ」なんてたまに寝言を言ったり、夢でも見ているのか足を動かしているのを見て笑い合っていると、ふと、俺は想いが沸き上がって、そのまま声となって形になった。
「おれ、護さんのことが、好きです」
「!」
自然と俺は告白していた。緊張は少ししたけれど、恐怖はなかった。俺の気持ちを受け入れてもらえるという自信があったから伝えたわけでなくて、ただ、何となく、伝えたくなって伝えた。受け入れてもらえなくても護さんは気持ち悪がられることはないだろうという安心感と隠していても意味がないだろうなという妙な諦観があってことだった。同性愛者ということを言っても変に大きなアクションが無かったことも、また護さんへの信頼になったのかもしれない。……とはいえ、いつまでも固まられていると心配になる。
「あの、いつも通りで大丈夫ですよ。特別な関係……は少し求めていますけれど、無理をさせたいわけではないんです。だから、またたまにこうして遊んでくれるだけで、俺は満足……」
「いやだ!」
「わんっ!?」
「あ、わるい」
突然大きな声が響いて俺が驚くよりも先に眠っていたナミがむくっと起き上がり吠えたので、ふたりで宥めるようにふわふわの身体を撫でていると落ち着いたようでまた寝っ転がってため息を吐き、もっと撫でろと言わんばかりにお腹をこちらにむけてくるのでわしわしと撫でた。
「その、あー格好悪い……」
「護さん?」
「……ちゃんと、言わせてくれ」
びょーんと伸びるナミの身体に微笑ましくてしていると顔を赤くした護さんがいつもよりも口ごもりながらそれでも意を決したように膝をついて俺を見下ろし、肩に手を置いて少しだけ上擦った声でこう言ってくれた。
「俺も。好き、だ。理一のことがずっと……本当は、あの日会う前から俺は理一を知ってた」
「!そう、だったんですか?え、え?もしかして、そのときから……?」
「いや、そのときは恋ではなかった。遠くから理一のことを見ていただけで、顔も分かっていなかった。でも、あの日……ナミを助けるために必死になる理一という人間を知って。何もかもを晒してでも捨てられた子犬を助けることに必死になって、助けられなかった子犬たちのことも忘れずにいる理一が、俺は好きになったんだ」
細かくはまた今度話させてくれ。そう微笑まれて俺は何も考えずに頷いた。その頬が赤くなっていて、嬉しくなった。
「護さんって、格好いいですけれど……可愛い」
「いや、そんなこと初めて言われたわ。というか可愛いのは理一の方だろ」
「えっ」
「はは、顔赤い」
可愛いだんて言われ、熱くなる顔を熱のこもった目で見つめながら、愛おしそうに頬を包まれてコツンと額同士を合わせてきた。
「俺の前では何でも晒してほしい。どんな理一も好きなのは変わらないから。できれば笑っていてほしいけれど、無理してほしくなんてないから。……もう、一人で生きようなんて悲しいこと思わないでくれよ」
近すぎる距離の位置に護さんの顔があるせいか、それとも別の理由か、視界がぼやける。頬に添えられる熱い手に俺の手を重ねる。かさついていて太い血管のある大きな手が俺の手の中にある喜び。俺が好きな人がどんな俺のことも好きだといってくれるなんて、夢にも見たことはなかった。ただ隣にいさせてくれるだけで満足だと思っていたのに、それ以上を望んでいいと受け入れてくれる。
一人で、生きていくつもりだった。
家族を含めた世界中の人間は俺を傷つけるか無関心かのどちらかで、人間以外の生き物はいつかいなくなる恐怖ばかりで、いつしか俺も望むことすら諦めてきた。唯一味方と感じていたおばあちゃんですら妹のことを庇っていたから……俺自身が特別なのだと訴えてくれるのがとても嬉しい。
「これから、よろしくお願いします。護さんも、俺にはぜんぶ、見せてくださいね」
砂浜に出来る俺一人だけの足跡を見て毎日覚悟を新たにしていた日々には、誰のことも好きになったりしないと決めていた日常にはもう戻れない。後戻りができない少しの恐怖と、これからの優しい日常への期待に身体が震え、それに気が付いた護さんがゆっくりと抱きしめてくれた。
俺もその逞しい背中に腕を回して、目を閉じてその体温と鼓動を感じた。
「ああ、聞かせてくれ」
迷いを打ち払うかのように俺の問いに力強く頷いてくれる護さんの優しい声に、俺の話をすることを再度決心した。
どこから話すべきだろうかと一瞬迷って、すぐに全部話そうと思った。護さんが俺に話してくれたから、俺もそれに応えたいと心から思えたから。
「俺の家は、周りよりも少し裕福だったと思います。家族は両親と妹。父は男らしくあれ、母は後ろ指さされない人生を歩みなさいと何度も言われてきました」
「厳しいな」
「はい、とっても……友だちと交遊するよりも家で勉強しなさいも口癖でした」
「妹にも厳しかったのか?」
「いえ。2番目だったからか女の子だったからか、父も母も妹には少し過保護だと思うほど可愛がられていました。俺よりも要領がいいということもあったんでしょうけれどね」
「ふうん……確かに男と女で気を使うことが違うだろうけれど、理一にだけ厳しいのは納得いかねえ」
「……そう言ってくれたのは、祖母だけでした。俺、こんな見た目だし好きなことはビーズ集めとか裁縫で……女々しいとお父さんには鼻で笑われてきましたが、祖母は嬉しそうに一緒にビーズのブレスレットを作ったりしていました」
「そうか、おばあさんは理一のこと大事にしていたんだな」
妹には甘く俺には厳しかった両親の話のときに棘々した空気が、祖母との大事な思い出の話をすると口調が和らいだ護さんにきゅっと胸が締め付けられた。
「……はい。俺の全部を受け止めてくれた唯一の人、でした」
「ぜんぶ?」
「俺、その……同性愛者、なんです」
「!そう、なのか」
驚いた様子を見せながらもそれでも俺を傷つけないように大げさな反応をしないでくれる護さんの優しさが嬉しい。同性が好きと知っただけで遠ざかるような人もいるのに、護さんは俺から身体を離さないでいてくれるのが、勘違いしてしまいそうになるけれど、今だけはこの甘い疼きをそのままに話を続けた。
「父にも母にも誰にも言えずに、ついにおばあちゃんに俺は打ち明けました。護さんと同じようにそうかいとだけ言って、後は深く聞きはしませんでした。普通に受け入れられたことが俺は何よりも嬉しくて、おばあちゃんの前では本当の俺でいれました。……男らしく、後ろ指さされない人生を重んじていた両親には到底受け入れがたいものだと言うのは、よくわかっていましたから」
幼い頃からそう言われ続けてきたのだ。自分の男らしくない見た目もどちらかというと女性的な部類に入る趣味も、異性の胸の膨らみよりも同性のゴツゴツした血管の浮いた手に目が向くことも、全てが両親が求める自分と本来の自分は違うのだと嫌でも分かって全てに罪悪感を覚えた。
とはいえいつまでも誤魔化せるものではないことも何となく分かっていた。どこまでも普通の男として幸せを掴んでほしい両親にとって結婚して子どもを作りなさいといつか求めることを察していた。そのときにはきっと俺も成人していて一人でそれなりに生きていける年齢になっているだろうから、そのときは戦うときなのだろうと考えていた。
まさか、あんな最悪のタイミングでバレるだなんて少しも思わなかった。
「ということは……浮気をされた、というのは」
「初めての彼氏に、ですね。俺が大学2年生、相手は大学1年生だったかな。名前はもう忘れちゃいましたね」
でも見た目は少し覚えている。護さんとは似ても似つかない、ナンパな雰囲気で髪を金に染めてツンツンとワックスで尖らせた、ちょっと生意気で強引な人だった。彼女欲しいと騒いでいたのに俺に告白したのだから驚いたなあ。俺の恋人になれとそんな俺様発言の割には身体がガチガチに緊張してて、顔も赤くて真剣な顔をしていたから、つい頷いてしまった。今となっては思えば俺なんかを好きになってくれたという喜びばかりで彼のことはすきじゃなかったと断言できる。それでも、当時はそれを本当に恋だと思っていた。だから俺なりに大事にしていたつもり、だった。
「大学からは一人暮らしになったので家族からの監視の目が緩んで、単位さえ何とかしていれば結構自由だったので、交遊してみたり、恋人を作ったりしたんですけれど……いつの間にか孤立していて、俺には彼氏しかいない状態になって。で、そんな中で浮気が発覚しまして……」
「この傷も……そのことを気に病んでのことか?」
「んっ」
突然人差し指と中指でゆるりと左手首の内側から肘の方まで辿られて、ぞくっとして変な声が出る。あまり触れられないところだからか、切り傷の痕のせいなのか、変に過敏になっていることを今初めて知った。
「あ、いえ、それは……ちょっときっかけ?事件?がありまして」
息が切れそうになりながらも、何とか続きの話しをする。護さんの手から逃れて右手で左の二の腕を掴む。あれは忘れることはできないだろう。きっと、永遠に。
「俺その人のこと本当に好きなつもりだったんですけれど……でも、やっぱり、浮気されたらもう愛想が尽きるものじゃないですか」
「そうだな」
「だから、別れようと言ったんです。気持ちがないまま付き合っても悲しくなるだけだから、て。でも、何故かすごいごねられたんです」
「浮気した奴の方がなんで別れるのを嫌がるんだろうな……。こっちは別れないって高を括っているんかね」
「そうかもしれませんね。俺少し依存気味だったから、彼はそう思っていたのかもしれません。それで、暫く別れる別れないの平行線だったんですが、その……刃物で切りかかられまして」
「切り……っ!?」
「はい。大学から家に帰るまでの道を待ち伏せされて……ここを」
抑える二の腕に視線を落とす。深く切られたせいで俺の身体に未だ残ったままのそれ。今も熱い血が自分の体内から流れていくのとは逆に体温がどんどん下がっていったことを思い出す。
「幸い命に別状はなかったです。が、何となく、そのことがきっかけで自傷が癖になったんです。誰かに同情されたいわけではなかったんですが、こう辛いこと思い出したり、行き場のない息苦しさにどうしようもなくなったときとかに、つい切ってしまうようになりました」
袖を肘ぐらいまでまくると、そこにはもう切っていないところのほうが少なく、切り傷の痕でまみれた柔い皮膚。どうして護さんがこれを知っていたのか不思議だったけれど、そういえば初めて会ったときナミの身体を温めるために上着を脱いでいたから、そのとき護さんにこの汚い傷を見られたのかもしれない。
「俺が孤立したのは彼が俺の悪い噂を流していたのが原因でした。事件後にそれが発覚して何人かメッセージで謝罪されましたが、俺は返事もせずにブロックしました」
護さんの顔は見れないまま早口で説明した。どうして突然冷たくなったのかと考えていた原因こそその恋人だったのだと分かった時、もう俺は何も感じなかった。それ以上に大変なことが起こってしまったから構っている暇がない、と言った方が正しいのかもしれない。
「なんで相手をそうして傷つけるぐらいそんなに好きなくせに浮気なんて馬鹿なことをしたんだ、そいつ」
「嫉妬してほしかったとか、俺しか見えなくしたかったとか、言っていた気がします」
「わかんねえな……。しかも、周りの奴らもお前の話を聞けよ。なんでそいつの言葉だけ信じるんだよ」
護さんが怒ってくれている。彼だけではなく、周りの人間にも怒ってくれる。なんだか、当時の俺も救われたような気持ちになって、胸が少しまた軽くなった。
「傷害事件になって……そこで彼との関係も、どうしてそうなってしまったのか……俺が同性愛者であることを両親にバレてしまいました」
駆けつけてきた両親は最初こそ心配してくれたけれど、細かい事情を知って驚愕へ、そして怒りと悲しみに変貌した。今まで隠し通していたものがバレてしまった。恐怖に怯えると同時に、酷く開放的な気持ちになった。
「それで……大学を辞めさせられて、10年は軽く生活できるだけの金の入った通帳とクレジットカードを渡されて……この家……おばあちゃんの家に連れてこられました。この家から出るも出ないも好きにしていいが、出てきたとしてもこちらに接触してくるな、と言われました。実質絶縁ですね」
あと1年で卒業だったから勿体ないと思った。でも、それだけだった。すっかり人間不信になって誰にも心を打ち明けるつもりもなくなった俺にとってもう学校に行かずにこの家にいるだけでよかったことにすっかり安堵してしまった。
「おばあさんは、どうしてたんだ?」
「……高校2年生のとき。倒れてそのまま……」
「……そうか。おばあさんが生きていたら、きっと、お前のこと何も言わずに受け入れてくれたんだろうな」
「そうだと思います。ずっと、ちゃんと俺の話を聞いてあげてと両親に言ってくれていましたからね。……本当に、優しい人だった」
おばあちゃんが倒れたと聞いたとき、そしてすぐに亡くなったのだと聞いたとき、棺桶から見るおばあちゃんの顔、火葬場へ連れて行かれるところ、骨だけになってしまったところ。俺はずっと泣いていた記憶しかなかった。大好きなおばあちゃん。
「理一ちゃんの人生なんだから、自分のために生きなさい」
「え?」
「おばあちゃんと最後に会ったとき、言ってくれた言葉です」
亡くなる2ヶ月前夏休みに泊まりに行って帰るとき、しわしわの手でぎゅっと俺の手を握って言ってくれたおばあちゃん。その顔はとても優しくてずっとこの家にいたいと思った。怖いばかりの家にいたくないとそう心から思った。
「その通りに生きてみたら、こうなってしまいましたけれどね。でも、俺こうなって家族との輪からも社会との縁とも遠ざかってしまったけれど、後悔はそこまでしていないんですよ。あのまま隠し通すことも考えたんですけれど、どうあがいたって俺にとって苦しいことばかりだった。それなら、もういいか、と。そう思ったと同時に穏やかに笑うおばあちゃんの言葉を思い出して……どうせバレたのだから、と。全部ぶちまけました」
「なんて?」
護さんは宥めるよう優しく問いかけてくれる。涙ながらに弱々しく訴えたと思われたのかもしれない。今まで情けない姿ばかり見せていたからそうイメージされても仕方ないけれど、そんな可愛らしいものじゃないので、幻滅されてしまうかもと少し怯えながら当時両親に向けたときと同じように俺は顔を上げて、そのとき言った言葉を口から吐き出す。
「俺は男とハンドメイドと裁縫が好きで、嫌いなのは勉強とあんたらと浮気野郎だ」
「え……」
「……そう言ったらまあ、修羅場でしたね。怒鳴られるわ泣かれるわ……だけれど、言いたいことを言えてスカッとしました。結果縁切られちゃいましたけれど」
「……そう、か」
「そんなことを言う俺に護さんは、幻滅、しましたか?」
驚いた様子の護さんに心配になって問いかけてしまう。家族に幻滅される分ならすっきりするだけだから構わないけれど、護さんには嫌われたくなかった。嫌な汗が掌に滲む。
「いいや。理一もはっきり言えてどちらかと言うと安心している。言いたいこと、言えたんだな。よかったな」
「!は、い。はい、そうです。俺はずっと両親言ってやりたかったんです。あんなに怖いと思っていたふたりも久しぶりだったから、俺も身長が父ぐらいになったからか、あまり怖くなかったんです」
「そうか。頑張ったな」
「はい、俺は……がんばったんです。がんばったんですよ、護さん」
「そうかそうか」
頭をくしゃくしゃと撫でられて、照れとともに喜びが生まれる。凝り固まった自分の感情をぶつけた俺の胸の中はどこか空っぽになったような虚しさがあった。虚無感と閉塞感。深く沈んでしまうときがあってそのときに俺は痛みで穴を埋めようとしていた。言いたいことを言えたことに後悔なんてないなのに妙な虚しさ。それは本当に言ってしまってよかったという自責の念。それを肯定されたことで暖かいもので埋まって、満たされたような気持ちになる。そっか、俺は、親に反抗したことを誰かに受け止めて頑張ったことを認めてもらいたかったんだとやっと理解した。しばらくナミを撫でるように両手で俺の頭を掻きまわしていた護さんだが、ふと気が付いたようにつぶやいたことで再度俺の頭から血の気が引く。
「ところで、どうして俺に電話をしてくれたんだ?随分と切羽詰まっている様子だったが……」
「……」
「もしかして、その元カレとか両親とかが来たのか?」
顔色を変えた俺にハッとしたように護さんが問いかける。今までの話を聞けば確かに、元カレか両親が訪れたと考えるのも無理はないだろう。だが、元カレのことも両親のことも割り切ったようなことを俺は言っていたのでどうしてこんなに俺が怯えているのか不思議そうにしている。そう、護さんが思う通り多分元カレが来て復縁を求めたとしても鼻で笑えるだろうし、あり得ないだろうけれど両親が和解を求めたとしても突っぱねている自信がある。襲来してきたのはその三人の誰でもない。今の俺の説明だけではほとんど存在感のないあの子。
「いえ、妹です」
「妹?ああ、そういやいたな……。要領がよくて両親も甘かったな。そいつが何かしたのか?」
「俺にとって、妹の理香が一番怖いんです」
4つも離れている女の子を恐れているだなんて情けないことこの上ないが、俺だけではあの子への恐怖心を払しょくできない。意を決して伝えても両親が信じてくれなかったことを、俺は護さんに話すことに決めた。声が震えてしまうのを堪えてどうして俺が妹を恐れているのか、説明する。
「理香は物心ついたときから俺に執着していました。それが実の兄に向ける妹の独占欲を超えた執着でした。両親に見えないところで気が付かない程度に怪我をさせてきました。好奇心だと痕にならない程度に首を絞められたこともあります。何もしていないのに俺がイタズラをしていたと先生や両親に嘘をついてそれに落ち込む俺を私だけはお兄ちゃんの傍にいるからね、と抱きしめてきたり。俺の教室で飼っていた金魚やメダカを殺したり……おばあちゃんと作った思い出のアクセサリーもわざと無くされたり切り刻まれたりもしました。このことは誰も信じてくれませんでした。おばあちゃんでさえも……理香の外面に騙されていましたから」
アクセサリーを無くされた、そう言うとおばあちゃんは悲しそうにしながらもわざとじゃないのだから理香ちゃんのことを責めてはいけないよと宥められた。傷ついた顔をさせたくなかったから俺は切り刻まれたことを打ち明けることはできないままだった。
「な、んで。兄である理一を、理香はそんなに苦しめるんだよ」
「……俺が苦痛に歪んでいる顔が好き、傷つけることが一番心に刻ませられるから、と言ってましたよ。俺と理香は顔立ちがよく似ているから、もしかしたらナルシストの一種かもしれません」
呆然と呟く護さんに内心俺こそ理香に聞きたいと呟きながらも、かつて泣きながら問いかけて答えられたそれを護さんに共有した。昔から本当は動物が好きだった。けれど、理香によってその小さな命も踏みにじられてきたから、ひとりになっても飼いたいと思わなかった。ただ、自分を傷つけて自堕落に生きるばかり。それを望んでいたわけではないのに、そうして生きてきた。
「来るはずのないあの子、理香が家を訪れたとき、ナミになにかあったらどうしよう。俺もどうなるんだろうと考えたくないのに考えてしまって、何をしても手が付かなくて……護さんに無意識に電話していました」
やっと、俺が護さんに電話した理由を告げることが出来た。理由だけならそれで充分なのに、護さんが自分の今までのことを教えてくれたから、俺もつい全部話してしまっていた。最後だけ説明していれば十分だったろう。でも護さんは全部真剣に受け止めて聞いてくれた。聞いてくれただけで、俺はよかった。
「俺はこれから一人で、生きていこうと。そう決めたんですけれど、ね」
朝、教室で無残に水槽ごと床に打ち付けられた動かなくなった金魚とメダカ。誰も俺の言葉を信じてくれなかった絶望。俺のことを認めてくれなかった両親、傷つけるばかりの恋人、俺の言葉が届かない他人、異様な執着心を見せてくる妹。理解者に近かったおばあちゃんもすでにこの世にいない。これからの人生をひとりでいようと決めるのには充分だった。腐ったまま生きていくのだと、砂浜の俺だけの足跡を見てはそう毎日決心を新たにして過ごしてきた。でも、でも。ほんとうは。
「ごめんな、俺は理一を一人にはもうさせたくない」
「っ」
暖かいものに身体を全身が包み込まれる。力強く締め付けてくる腰と肩の感触に泣きたくなるのは苦しいだけではない。護さんに抱き込まれ、耳元でぐずっと鼻を啜る音が聞こえて、一度唇を噛んで震える声のまま本心を告げる。
「はい、おれも、もう、ひとりにはなろうと思いません。ナミと……護さんがいてくれるから。いてほしい、です」
「ああ。当たり前だ。理一、おまえ、がんばったんだなあ。えらいよ、ほんとうに……っ」
彼の声は嗚咽で掻き消される。泣いてくれている、俺の話を聞いて泣いた彼の声がとても嬉しくて、苦しくて、でもやっぱりどうしようもないぐらいの喜びで溢れて、それが涙になって頬を伝う。
「っは……い、はい、おれ、がんばりました。ずっと、生きるのが嫌になって、それでも死ぬことはできなくて、する気も起きなくて、それでいいのかな、て、ずっと、おれは、くるしくて、え……!」
「ああ、それでいい、それがいい。りいち、生きていてくれて、ありがとう。これからも、生きて、くれ。ナミのために……おれのために!」
「はい、はいッ……!まもるさんも、ずっと、おつかれさま、でした」
「!ああ、ありがとう、ありがとうな」
居間に響くのは男ふたりのすすり泣く声。成人した男二人抱き合いながらお互い泣くなんてきっと酷い光景なのだろう。誰かがいたら男なのに情けないと眉を顰めて冷たくそう言い放つのかもしれない。でも、ここにいるのは泣き出す俺たちに気付いて心配してかしめった鼻で俺の背中をつつく犬の女の子のナミだけ。謂れのない責めを受けなくていい空間。俺たちは散々誰かに傷つけられてきた。傷つくのは男女も人間も動物も関係ない。自分のために泣いてくれる人に暖かい気持ちで満たされて涙することが悪だとは思わない。時折ナミを撫でながらそれでも俺たちはずっと泣き続けた。水分が枯れ果ててしまうのではないかと思うほど、涙を零し続けた。
「……ひどい顔だ」
「……護さん、こそ」
「……はは」
「……あははっ」
「わうんっ」
電気も暖房もつけっぱなしで、泣いているうちに眠ってしまった俺たち瞼は腫れ頬には畳の痕がついてしまい酷いもので、お互い笑い合う。ナミもつられて笑うように泣くものだからさらに笑みが零れる。そのまま順番にお風呂に入っていつものよりも少し遅めの朝食ととって、朝の散歩にしても昼の散歩にしても中途半端になってしまったけれど昨日から散歩に行けなかったのでナミもうずうずしっぱなしだったので、護さんとともに外に出た。ウミたちの墓にも挨拶した。心配していたけれど無事に相変わらずの質素な墓があって安心した。
昨夜のことにお互い触れずに、それでも護さんは俺からあまり離れることなくナミもそれを察してかいつもよりもゆったりと歩く。いつもの海辺に着くと、先客がいることに気が付く。彼女……理香だ。
「あいつって」
「……」
「う”ーーー!!」
固まる俺に小声で問いかける護さんに無言で頷いた。ナミも理香を見て唸っている。その声に気が付いたように理香はこちらを振り返る。
「……」
「あれ、お前……」
「理香……」
氷のように無表情だったナミは俺を見て口角だけをあげた……かと思えば隣にいる護さんの存在が視界に入ってギッと目を吊り上げ、指を差して波の音に負けずに叫ぶ。
「お前のせいで!お兄ちゃんは可愛くなくなったのよ!どうしてくれるのよ!」
きいん、と耳と頭に響く声に顔を強張らせる。ううん、とナミも煩そうに唸った。理香の存在に手に汗がにじむ。でも、その手を護さんがリードを持っていない手で握ってくれたからとても安心した。そして気が付いたことがあってそっと問いかける。
「あの、護さん、理香に会ったことあるんですか?」
「最近会社前でうろうろしている奴だよ。職場の奴が騒いでいたから横目で見ただけで話したことはなかったが、少しだけ理一に似ていたから印象に残ってんだ」
「そう、だったんですね」
話したこともないと言われてホッとする。護さんには言っていなかったけれど、元カレが浮気した理由は理香が接触したことから。……理香とは浮気とまでは行かなかったけれど、元々の彼は普通の異性愛者だったから。
俺と理香は血の繋がったれっきとした兄妹で顔立ちがよく似ていて……結局、女の子の方が良いとでも思ったのかもしれない。いつだって、俺が仲良くなった人は理香の方が皆好きになっていたから。護さんとは直接的な接触がなかったことに心から安心する。
「無視するな!!」
いつまでも理香への反応を示すことなくひそひそと話す俺たちに、痺れを切らした理香がまた叫んだ。理香が怒りを露わにしてじっとりと睨んでいる。いつもの何を考えているか分からない、ただただ俺を傷つけることに対して愉悦に浸っていた妹しか知らない俺は偽りの無邪気さでも優しく振舞う嘘くさい笑顔でもない、年相応の女の子の素顔の妹を初めて見た。そのぐらい焦っているということなのかもしれない。取り繕うこともできないぐらいに。
(……こんな、感じだったっけ)
記憶よりも華奢で、余裕の欠片も見当たらない彼女の姿にどこか拍子抜けに近い気持ちで見つめていると護さんが俺にリードを手渡し、俺とナミを理香から庇うように前に立った。
「無視すること言っている意味がよく分かんねえよ。可愛くないって?理一は可愛いだろうが」
「護さん?!」
突然そんなことを言うから顔が熱くなった。こんな、背ばかり伸びた男の俺に言う言葉ではないと驚いたが、護さんは平然としたまま理香と対峙して問いかける。
「お前は本当に何がしたいんだ?理一はお前の兄なんだよな。ずっと陥れることをして。苦しめることをして何が楽しいんだよ」
真っすぐな問いかけだった。俺がずっと聞くのが怖くて聞けなかったことをあっさりと護さんが聞いてくれた。俺も理香を見てその答えを待った。
「お兄ちゃんは苦しむ顔が一番かわいいの!」
あっさりと理香は答えた。答えはあまりに単純で幼稚、かつ訳の分からない返答に俺も護さんも呆気にとられた。ナミですらきょとんとしているように見えた。誰よりも先に言われた意味を理解してリアクションが出来たのは護さんだった。
「はあ、その価値観全然わかんねえよ……好きな奴には幸せにしたいし、笑っていてほしいだろうが」
「そんなものよりもお兄ちゃんは苦痛に歪んでいる表情のほうがいいのに。ひとりでいる方が可哀想で可愛い顔をするのよ?笑顔なら私の顔を見れば十分だもの。そのために今まで私は頑張ってきた。……なのに、お前のせいで」
理香は今までの俺のことを思い出したのか、目を細めて初恋に身を任せたような恍惚とした表情を浮かべていたのに、目の前の俺たちを敵でも見るような鋭い目つきで睨んできた。
「せっかく今まで馬鹿なジジイもババアもだましてひとりにさせていたのに!可哀そうなお兄ちゃんを見たくて周りの奴らも騙して孤立させたのに!一人暮らしを勝手にして、恋人まで作って……許せるわけないじゃない。
あんな男お兄ちゃんにふさわしくないのに、ひとり占めするなんて許せなかった。少し私が誘っただけで他の人間に行くような男なんて……!それだけしてもお兄ちゃんは私のところに帰ってこなかったから……自分の無力さを味わってほしかった。だから、わざとお兄ちゃんが見えるところに犬を弱らせて捨てたのに」
「!ちょ、待って」
最後のポツリと呟いた言葉に俺は焦って声を荒げて待ったをかけた。理解しがたいことを言われた。どうしても聞き流すことなんてできないことを。
「理香、犬を捨てたのは……もしかして」
「うん、そうだよ。お兄ちゃん」
「なんて、こと……なんで、俺がここにいるって……」
「あは。そうその顔!それが見たかったのよ……犬一匹も救えないことに絶望し尽くした貴方の顔が見たかった。ジジイとババアに聞き出したの。今年の夏に入る少し前ぐらいだったかな?やっと口を割ってくれたの。今まで私が未成年だからって教えてくれなかったから。それで何度か家の方に様子を見に行ったら外に大体同じぐらいの時間にこの海に散歩に来ていることを知ったから。だから、お兄ちゃんが大好きな動物が目の前で死んでいたら……これ以上ないぐらい悲しんでくれるかなって。なのに……まさか犬の一匹を助けることに成功することも、また悪い虫がつくなんて。驚いたしすごく目障り。またお兄ちゃんを可愛くさせようと思ったのに。ああ、憎たらしい」
「っ、お前は……」
「……おにいちゃん?」
どうして何も悪いと思っていないかのような表情なんだ。俺の傷ついた顔が他の命を犠牲にするほどの価値なんて無いだろう。どこから犬を捕まえてきたのか分からないけれど、よくもウミに、カイに、アオに、ナミに……そんな非道なことをしたのか。いつも理解不能だった妹。俺への異様な執着と底知れぬ不気味さへの恐ろしさが勝って何も言えなかった。でも、腕の中で冷えていく体温と助かってほしいと何度も願ったナミのことと、狭くて冷たいあの段ボールのなかで命を落としたウミたちのことを考えれば考えるほど怒りが込みあげてくる。俺の表情に理香は戸惑った様子を見せるけれどそれどころじゃない。
(護さんが、声をかけてくれなかったら、ナミも……)
俺の顔を見上げてくる無垢な瞳が視界に入る。あの日、助けることが出来なかったら、ナミはここにいない。
もしものことを考えれば考えるほどに、言い様もない気持ちと湧き上がる激動に身を焦がす。俺は口を開く。なんて言うか考えていない。ただただ激情のままに叫んで罵って、少し怯えたような顔をする俺とよく似た女を傷つけてやりたかった。
「う、わっ?」
だが、それはできなかった。手を引かれ暖かいものと密着したかと思えば視界が突然真っ暗になった。焦る俺に隣から低い声が響いた。
「理一、ごめん。少し待ってくれ」
「、まもる、さん?」
近くから聞こえる護さん声に驚いて少しだけ冷静になると同時に、目を覆うのは護さんの大きな手でほとんど抱き寄せられている状態になっていることにさっきとは別の意味でカッと身体が熱くなる。ドギマギしている場合ではないと気を引き締めていると、護さんがいつも通りに低くも少し冷たく言葉を発した。
「なあ。今の発言、誰にも聞かれたくないよな」
「はあ?」
理香は護さんに対して心底嫌そうに話を聞く気も無さそうな生意気な声を上げたが、そのあとすぐに少しノイズ混じりの理香と俺の音声が聞こえてきた。先ほどのやり取りそのままの内容。不思議に思っていると視界を塞いでいた手が外され、見えたのは空いている片手にスマホ護さん。どうやら、さっきの会話を録音したものを流していたらしいと気が付いた。理香も目を見開いて凝視していた。
「……、……」
「理一から話を聞いた限り、お前って要領が良くて両親から可愛がられて、周囲にもいい顔しているらしいな。もしも、このやり取り聞いたら……どうなると思う?」
何も言えなくなっている理香に、護さんはスマホを口元に寄せて淡々と問いかけた。
「……私を脅すというの。そんなの、だれも信じないわよ」
「人聞きの悪いことを言うなよ。ただの交渉だよ。昨日理一から色々聞いたけれど、おまえ随分猫被っているみたいじゃねえか。これを聞かれたら……どうなるんかね?」
「……」
「理一とナミ。……ついでに俺に近寄るな。動物愛護団体に訴えたっていいんだぜ。……胸糞悪いが、大した罪にはならないだろうけれど『周囲からの評判は』どうなるんだろうな?見たところ大学生っぽいし……学校に流したらどうなるのか……試したっていいんだぜ。これでも社会人でそれなりの役職にもついてて、貯金もまあまああるんだ。理一の力を借りなくてもそれなりに根回しも追い詰めることも出来るんだ。俺だってまだ大学も卒業もしていない若者を追い詰めることなんてしたくないんだ。だから、もう何もしないでいてくれ」
いつの間にか護さんは俺の手を握っていた。何も心配しなくていい、そう言ってくれるようだった。俺のことを第一に考えてくれる誰かなんて知らなった。
「理一とナミを守るためなら。俺はどんな手を使うからな」
傍から見ると、まだ成人したばかりの女の子を脅している男の図にしか見えないだろう。
理香は華奢で兄としての贔屓目も抜きにして守ってあげたくなるような容姿の女の子だ。稀に俺と妹の違和感に気付く人がいても、理香の容姿にこんなことしないと思い込んでそれ以上深入りしようとする人はいなかった。どれだけ。俺のことを守ろうとしてくれる姿に今までの辛かった俺の全部が救われた気持ちになったか、教えることは生涯を以てでも無理だろうと思った。
「理香」
「……おにいちゃん」
ナミと俺のためにならどんな手を使ってくれるという護さんの言葉だけですっかりと落ち着いた気持ちになった。事実を知って冷静になっても、燻る感情は、きっと理香に伝えなくてはいけないことだ。怖いから、と逃げるのは俺もやめる。
「生まれたとき。俺は理香のことが可愛かった。守ってあげたいと、本当にそう思った。気が付いたら異性よりも同性のことを目に追っていた俺だけれど……理香のことは、本当に純粋に兄として好きだったよ。きっと、特別だった」
本当に、天使のようだった。まだ毛もなくてお猿さんのような理香。手を伸ばすと、きゅっと指を掴んで笑ってくれた。どこもかしこも柔らかくて暖かかった。ずっと、覚えている。どんなに酷いことをされてもどんなに怖がらせられても、その記憶だけは忘れられなかった。
「もしも……俺が理香に似ていなければ、理香が俺に似ていなければ、理香がそこまで歪むことはなかったのかもしれない。俺は本当に、そういう意味はないけれど、理香のことを愛していたよ。家族として……。
きっと、理香は俺に望むのはその愛じゃなかったとしても、酷いことをされても、理香を今まで心から嫌いにっはなれなかったんだ」
今思えば、恥を捨てれば誰かに助けを求めることが出来た。でもそれは理香が悪い子になると同意義だったから、言えなかった。馬鹿な兄は自分を傷つける妹を守ろうとしてしまった。愛していた。妹として。いつか関係が修復できるという望みを捨てきれなくてここまでずるずると来てしまった。俺は、何もできないのに。
「でも。もう、俺はあんたのことが嫌いだ」
きっと、間違えた。理香も、俺も。ちゃんと向き合うべきだったんだ。悪いことは悪いのだとどんなものを敵にしてもちゃんとぶつかっていくべきだったんだ。そうすれば……こんなに歪んで修復不可能なところまでいかなくて済んだかもしれない。
「俺を傷つけるだけなら、構わなかったよ。辛くても妹のために好きにさせてあげようと、そう思った。だけど、超えてはいけないところまで来たんだよ。……本当は金魚たちが殺されたときに決断するべきだった。それは俺への、理香への、甘さだった。ひとりになるのが怖くて、怖いのに俺に執着する理香が恐れても唯一俺個人に向けられた愛だったから」
理香は信じられないと言わんばかりの表情で、潤んだ目を見開いて今にも涙を零しそうになっている。少しだけ胸が痛むけれど、撤回する気はなかった。
「さっきの話を聞いて。俺はもうあんたのことを許せそうにない。二度と、護さんの前にもナミと俺の前にも姿を現さないでほしい。……それが、俺が理香という妹への最初で最後の心からのお願いだ」
「おにい」
「ごめん。ちゃんと理香と向き合うことができなかったお兄ちゃんで。でも、お願い。もう、俺たちに近寄らないで。顔を見せないでほしい」
手を俺に伸ばして近付いてこようとする理香に対して俺は明確に拒絶する。これ以上近付かないでほしいという気持ちが通じたようでぴたりと動きを止めて縋るように俺を見る、愛おしかった、妹。
「これ以上、妹を……理香を、憎みたくないんだよ。おねがい」
天使ようだと、守りたいと思った昔の理香まで憎みたくない。ここまでされてもまだ完全には妹を憎めない自分の甘さに呆れるけれど、でも本当に、これ以上はだめだと思う。俺に近づく以上にナミと……護さんに害を与えるとするのなら、この平穏の日常を脅かしてくるのであれば、俺は何をするかわからない。そのぐらい、この日々が俺には大事なモノになっていた。もはや、家族のことも以前生活していた日々すらもどうでもよくなるぐらいに。
「……」
「わん」
暫く誰も言葉を発することができない空間、波の音とナミの声が一度響いた。
「ごめんなさい」
俺の願いに、理香は頭を下げた。その今まで見たことのないしおらしさに目を白黒させたが、理香はこちらを見ずに構わずに続ける。
「お兄ちゃんが望む愛と、私の愛は……ううん、私がきっとみんなと違い過ぎるんだね。今更気が付いても遅いけれど。だから……バイバイする。今まで、私のわがまま。受け入れてくれてありがとう。ごめんね。私、ちゃんとお兄ちゃんを普通に愛せたらよかったのにね。そうすればきっと……ううん。今までごめん。ナミちゃんも、護さんも。どうか、私を許さないでね」
そう言って顔を上げて笑った理香の顔は、昔に見たものとよく似ている気がして、背を向けていくその哀愁漂う姿に駆け出して行きたくなってしまったけれど、足に擦り寄ってくれるナミと力強く俺の手を握ってくれる護さんに阻まれる。ここが、俺の居場所なのだとそう言ってくれているふたりを振り払うことはできないし、するつもりもなかった。
「あの」
理香が去って行ったあと、いつも通りをみんなで装って散歩をして俺の家に帰っていつものクッションでのんびりと眠るナミを護さんとふたりで囲うように好きに撫でる和やかな時間。午後3時。いつもなら散歩に行っている時間だけれど今日は遅かったうえナミも護さんと十分に遊んだからか満足したようですっかり熟睡しているようだ。「ううんっ」なんてたまに寝言を言ったり、夢でも見ているのか足を動かしているのを見て笑い合っていると、ふと、俺は想いが沸き上がって、そのまま声となって形になった。
「おれ、護さんのことが、好きです」
「!」
自然と俺は告白していた。緊張は少ししたけれど、恐怖はなかった。俺の気持ちを受け入れてもらえるという自信があったから伝えたわけでなくて、ただ、何となく、伝えたくなって伝えた。受け入れてもらえなくても護さんは気持ち悪がられることはないだろうという安心感と隠していても意味がないだろうなという妙な諦観があってことだった。同性愛者ということを言っても変に大きなアクションが無かったことも、また護さんへの信頼になったのかもしれない。……とはいえ、いつまでも固まられていると心配になる。
「あの、いつも通りで大丈夫ですよ。特別な関係……は少し求めていますけれど、無理をさせたいわけではないんです。だから、またたまにこうして遊んでくれるだけで、俺は満足……」
「いやだ!」
「わんっ!?」
「あ、わるい」
突然大きな声が響いて俺が驚くよりも先に眠っていたナミがむくっと起き上がり吠えたので、ふたりで宥めるようにふわふわの身体を撫でていると落ち着いたようでまた寝っ転がってため息を吐き、もっと撫でろと言わんばかりにお腹をこちらにむけてくるのでわしわしと撫でた。
「その、あー格好悪い……」
「護さん?」
「……ちゃんと、言わせてくれ」
びょーんと伸びるナミの身体に微笑ましくてしていると顔を赤くした護さんがいつもよりも口ごもりながらそれでも意を決したように膝をついて俺を見下ろし、肩に手を置いて少しだけ上擦った声でこう言ってくれた。
「俺も。好き、だ。理一のことがずっと……本当は、あの日会う前から俺は理一を知ってた」
「!そう、だったんですか?え、え?もしかして、そのときから……?」
「いや、そのときは恋ではなかった。遠くから理一のことを見ていただけで、顔も分かっていなかった。でも、あの日……ナミを助けるために必死になる理一という人間を知って。何もかもを晒してでも捨てられた子犬を助けることに必死になって、助けられなかった子犬たちのことも忘れずにいる理一が、俺は好きになったんだ」
細かくはまた今度話させてくれ。そう微笑まれて俺は何も考えずに頷いた。その頬が赤くなっていて、嬉しくなった。
「護さんって、格好いいですけれど……可愛い」
「いや、そんなこと初めて言われたわ。というか可愛いのは理一の方だろ」
「えっ」
「はは、顔赤い」
可愛いだんて言われ、熱くなる顔を熱のこもった目で見つめながら、愛おしそうに頬を包まれてコツンと額同士を合わせてきた。
「俺の前では何でも晒してほしい。どんな理一も好きなのは変わらないから。できれば笑っていてほしいけれど、無理してほしくなんてないから。……もう、一人で生きようなんて悲しいこと思わないでくれよ」
近すぎる距離の位置に護さんの顔があるせいか、それとも別の理由か、視界がぼやける。頬に添えられる熱い手に俺の手を重ねる。かさついていて太い血管のある大きな手が俺の手の中にある喜び。俺が好きな人がどんな俺のことも好きだといってくれるなんて、夢にも見たことはなかった。ただ隣にいさせてくれるだけで満足だと思っていたのに、それ以上を望んでいいと受け入れてくれる。
一人で、生きていくつもりだった。
家族を含めた世界中の人間は俺を傷つけるか無関心かのどちらかで、人間以外の生き物はいつかいなくなる恐怖ばかりで、いつしか俺も望むことすら諦めてきた。唯一味方と感じていたおばあちゃんですら妹のことを庇っていたから……俺自身が特別なのだと訴えてくれるのがとても嬉しい。
「これから、よろしくお願いします。護さんも、俺にはぜんぶ、見せてくださいね」
砂浜に出来る俺一人だけの足跡を見て毎日覚悟を新たにしていた日々には、誰のことも好きになったりしないと決めていた日常にはもう戻れない。後戻りができない少しの恐怖と、これからの優しい日常への期待に身体が震え、それに気が付いた護さんがゆっくりと抱きしめてくれた。
俺もその逞しい背中に腕を回して、目を閉じてその体温と鼓動を感じた。