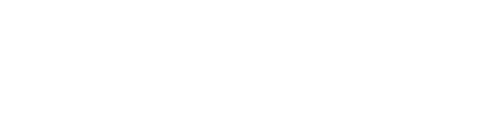つもり、つもり、あいがふりつもり
「ワンッ!」
「うぶっ」
高い声とともに胸に訪れる衝撃のおかげで、意識が現実に戻る。幼い頃からある時計を見ると午前6時にはまだ届いていない。前の俺なら寝ている時間、万が一起きたとしても時計を見ることなく二度寝を決め込んでいたけれど、今の俺は瞼をこじ開けることを選んだ。
「おはよう……ナミ」
「わうん!」
キラキラとした澄んだ海のような目で俺の挨拶に返すように元気に吠えるナミの姿に自然と笑みが零れる。べろべろと顔を舐めまわされる前に起き上がり、散歩の準備を始める。起きたらまずは散歩、それが分かっているナミは俺の後ろを付いて回る。以前あまりに足元でうろちょろするものだから彼女の身体を蹴っ飛ばしそうになるのを阻止するために避けようとしたら、バランスを崩して尻もちをついたことがあって痛みに暫く悶絶していることがあって以来、ちゃんと邪魔にならない程度についてくるから賢い子だとここのところナミが付いてくるたびに感心している。用を足して出てくるとぱあっと顔を明るくさせてくるんとした尻尾をぶんぶん振ってくる。ほんの少しだけ顔を合わせないだけで熱烈な歓迎だなあ、なんて思いながらしゃがんでその頭と頬を撫でくり回す。その暖かさに少しだけ泣きそうになるのもいつものことだ。
「おはよう。ウミ、カイ、アオ」
首輪にしっかりとリードを繋ぎ、外に出てまず向かうのは自分の家の庭……ホームセンターで買った平べったい木材に名前を俺の手書きで素っ気なく乗せられている墓と呼ぶには随分と簡素なそれらの前に一本ずつ線香を立てしゃがんで手を合わせて名前を呼ぶ。あの子たちからすると海に対してあまりいい思い出がないだろうから連想させる名前をつけるなんて酷いのかもしれないけれども、それでも僕の乏しい語彙力で名前をつけるにはこれしか思いつかなかった。如何せん、ちゃんとした顔立ちもどんな子だったのかも性別も、ナミと一緒にいたけれど彼女と血が繋がっているのかも俺には分からないんだ。ごめんね。もう少し落ち着いたらちゃんとした石造りのお墓を買ってあげるからね。
不思議といつもはちゃかちゃかと動き回るナミもウミたちの前だと俺の隣でじっとお座りをして待ってくれる。犬にも分かるのだろうか。そこに、助けられなかった子たちが埋められていることを。それともただ僕がしゃがんでいるからそうしているだけなのか。できることなら、分かっていてほしいと願うのはエゴなのかな。
「はやい、はやいって!ナミっ」
「ワンっ!」
苦しむ俺を尻目にランランと砂浜を走るナミ。おかげで足腰が鍛えられる日々だ。獣医さんが言うのはナミは今生後4か月か5ケ月ぐらいらしい。人で言うと小学校下級生ぐらいの年齢らしく、とにかく元気で溢れている時期らしい。とにかく好奇心旺盛で走ってご飯を食べて眠る。遊ぶのも大好きだ。いいことだ、とても健やかな絵にかいたような犬って感じの犬だ。ただ、問題がひとつ。
「はあ、ほんと、もうほんと、無理……だ!」
「ウウン」
「ごめんってば、ゴホッ」
運動とかあまりせず、ナミを迎え入れるまでは買い物か散歩に出るぐらいしか外に出ることが無く夜更かしして昼に起きるを繰り返していたほとんど引きこもりのような生活をしてきた俺にとってナミのスピードについてこれず、こうして膝を折り、不満そうな唸りを受けながら謝るばかりだ。ぜえはあ、と肩で息をしているとポケットにしまっていたスマホが震えて取り出すと、液晶に映された名前を見て違う意味でドッと心臓が脈打ち、顔が熱くなる。
『護さん』の名前を見るだけでざわついてしまう心を落ち着かせてメッセージアプリを開く。
『一時頃にそっちに着く』
素っ気ないメッセージの後に可愛らしい犬が駆けだしているスタンプが送られてつい笑みが零れた。
『分かりました。お気をつけて』
そう送った後少し悩んで扉の前で座って待っている犬のスタンプを送ってポケットにしまい込む。そしてフンッと鼻を鳴らしてるナミの頭を撫でながら、良いことを教えてあげる。
「今日も護さん、来るってさ。よかったねえ」
「わん!」
俺の言っていることが分かっているかのように嬉しそうに鳴くナミ。いつも行く俺との散歩よりも週末に訪れる護さんとの散歩の方がナミは好きみたいだ。そうだろうね、なんたって護さんは俺と違って明らかに身体が鍛えられている運動好きそうな人だから、ナミの全力散歩についていってくれるからね。俺みたいにひょろっとしたもやし体系よりもがっしりとしている男らしい人の方が素敵だと思う。……俺の場合は、ナミと違って少しだけ、邪な目で見ているけどさ。少し体力が回復してまたナミとともに砂浜を駆け出した。
すぐにまた息が切れてしまい、彼女には呆れたように息をつかれてしまった。
ピンポーン。12時50分、軽快な音が家中に響き渡り俺の足元で眠っていたナミがガバッと起き上がりチャチャチャ!と音を立てて廊下を駆け出していく。俺も持っていたペンチを置き、作業を中断して玄関のカギを開けるために少し早足で向かう。
「いらっしゃい。暑かったでしょう?」
「少し外に出ただけで汗が噴き出してきたわ……よう、ナミ。まーた大きくなったか?」
「ワン!くうん、きゅんきゅん」
「甘えた声出しちゃって。良かったね」
「……」
「?どうしました?」
「あ、あー……いや。理一は体調大丈夫か?」
「、大丈夫ですよ。ああ、ちょいちょい筋肉痛に苦しめられていますけれどね」
「若いのに何言ってんだよ」
「護さんだって若いでしょうよ」
「4歳っていうのは大きいんだぜ……」
「?へえ」
疲れたようにそう言う護さんに首を傾げ適当な相槌を打つことしかできない俺。苦笑いをされた。俺も護さんぐらいの年になればその言葉の意味が分かるのかな。……4年後の俺なんて全く想像できないけれども。
7月のあの日以来ほぼ毎週訪れている護さんはすでに家の配置の大体を知っている。迷いなく居間へとナミとともに俺より先に向かい、畳に座ってナミと戯れる。冷蔵庫から水出し麦茶を取り出し、氷を二個入れたコップに注ぎ年季の入ったちゃぶ台の上に置いた。
「良かったらどうぞ」
「ああ、ありがとうな」
額を擦り付けてくるナミをそのままに太い腕を伸ばしてしっかりとした首を逸らして隆起した喉仏を晒してゴクリゴクリと麦茶を飲み干す姿からつい目を逸らして台所前にある脚の長いテーブルの上に散らばっているものを片付けるべく手を動かす。カチャカチャと音を立てていたせいで何をしているのかと護さんが声をかけてきた。
「今日も作業か。大変だなあ」
ペンチや半端に切られたり曲げられた針金やビーズが散乱しているのを、護さんはもう不思議そうにしたりなんてしない。俺がアクセサリーやストラップ、たまにぬいぐるみなどの裁縫をしたり……所謂ハンドメイド作家であることを知っているからである。
「いえ、好きでやっていることですから」
「俺にはできねえな。やっぱりすごいな」
護さんはナミを転がして撫でまわしながら感心したようにそう言うけれど、謙遜ではなく本当に大したことないのだ。正直あまり売れていないしとてもじゃないけれどこの道一本で食っていけるようなものじゃなく、昔ながらの趣味みたいなものだ。だから、すごいなんて呼べるものじゃないのだ。この話題になると、護さんに褒められるのは嬉しいけれど困ってしまう。
「そんな……。あ、何か食べてきましたか?」
「いや、まだだな」
「俺たちもまだなんですよ。素麺でよければ食べません?」
「おお、ありがてえ。素麺がいいなあ」
「分かりました。今用意しますね」
半ば誤魔化しに近い話題だったが、まだ食べていないという返答に安心して机の上の片づけもそこそこに(どうせこっちのテーブルはこの作業でしか使わないのだから)鍋に水を入れ火を点けて沸騰するのを待ちながら、引き出しから素麺を取り出したところである考えが浮かんだ。
(なんか、同棲しているみたいだ)
そんな浮ついたことを考えてしまい、小さく首を振って慌ててその思考を飛ばした。冷房が効いているのに火をつけたせいか顔が少し熱い。まさか、護さんも同じようなことを考えていただなんてお互い思いもよらなかったけれども。
「できましたよ」
「ああ、悪い。ありがとうな」
「いえいえ。いただきます」
「いただきます」
「わん!」
ちゃぶ台にまで氷を浮かべ、適当に麺つゆをかけた素麺を入れた二人分の器と箸を持っていって啜った。もちろんナミにもふやかしたドックフードを与える。先に食べ終えたナミが物欲しそうにねだるような視線が突き刺さり、なにかあげたくなるけれど、心を鬼にして無視する。まだ子犬であるナミに人間の食べ物は早い……いや、味の濃い人間の食べ物を動物にあげること自体よくないことだと分かっている。いずれ根負けして何かしらあげてしまいそうな自分が怖い。
「ほら、新しいおもちゃだぞー」
「また買ってきてくれたんですか?」
「面白くねえ?」
「……うなぎ?」
「ああ。ナミが咥えたら可愛いだろうな、て……あ」
「ふがふがっ」
「……」
「……」
「なかなか袋には勝てませんね」
「くそ……ほら、こっちであそべ!」
「わうん?」
「あははは」
少し遅めの昼食を終えて使い終えた食器を洗うのは何となく護さんの役割になっていて、片づけを終えた護さんはバックの中から袋に入ったおもちゃを取り出した。ここに来るたびに増えていくおもちゃは居間を華やかにしていく。だが、最初にナミが興味を示すのはおもちゃ本体ではなく残念ながら袋の方だ。袋の中に頭を突っ込んでいるところを必死に護さんがおもちゃに興味を惹かせるように誘うのを僕は思わず笑いながら見ていた。
暫く攻防戦(護さん不利の)を観戦した後、俺は台所前のテーブルに向かう合い、先ほどの続きを再開した。
少しの間熱中し、ただの一つの棒だった針金を魚の形にいくつかしたところで少しだけ手を止めてそっとナミと何とかうなぎの玩具で遊ばせることに成功している護さんを観察する。楽しそうに笑っている彼の姿にぎゅっと胸が締め付けられる。一緒にいるとなぜか逃げたくなるのに、どうしても一緒にいたいという変な気持ち。またこんな気持ちになるなんて考えてなかった。甘くて少し辛い苦しみに胸をきゅっと抑えた。
「理一」
「!はい」
名前を呼ばれるだけで心臓が飛び出そうになった。慌てていつの間にか顔を机に突っ伏していたのを起き上がり返事をする。あまりの俺の焦り様に護さんとナミは同じように驚いた表情をしていた。
「ああ、悪い。驚かせたか?そろそろ散歩の時間かと思ったんだが」
「あ、そ、そうですね。そろそろ行きましょうか」
時計を見るといつの間にか14時半を少し過ぎていた。椅子から立ち上がる俺に護さんが心配そうに声をかけてくる。
「大丈夫か?区切りが良くないんだったら俺だけでも」
「いえ!一緒に行きたいんです!」
「そ、そうか」
「っあ、あ、じゅ、準備してきますっ」
自分だけで行く、と言おうとする護さんの言葉を最後まで言わせたくなくて必死に遮ったことで妙な空気が生まれて、こけそうになりながらリードとポリ袋を取り出してウェストポーチに突っ込んだ。護さんの顔がどこか赤くなっていたように見えたのは、きっと俺にとって都合よく見えただけだと何度も茹だる頭に言い聞かせた。
「おおー元気だなあ。ナミ」
「わうんっ」
「はあ、ハアッ」
「おーい、無理するなよー」
「す、いません。先行っててください……」
「おう、理一は待ってろー。うおっ!待て、ナミ」
「ワンワンワンッ!」
駆け出すナミについていく護さんは俺よりも断然体力がある。暑さと身体を動かしたことでじわりと滲む額の汗を夏用のパーカーの袖で拭う。冷房の効いた室内ではともかく、熱気の立ち込める外ではいくら夏用と言えど少しでも布を減らして、脱いでしまいたい衝動に駆られるが堪えて苦し紛れに胸元をパタパタと上下に動かして風を得ようとした。
ふと、振り返った。砂浜にはいくつもの足跡がある。前を見るとフリフリと尻尾を揺らしながら懸命に走るナミと、時折声をかけているのかナミの方を見る護さんの後ろ姿。なんだか、胸がいっぱいになって、呼吸が一瞬止まる。
「ゴホ」
肺に酸素が行き渡らなくて身体が限界を迎えて咳が出る。もう一度振り返り、足跡を眺める。もう数時間もすれば完全に消えてしまう足跡たち。
今まで……と言っても、家から追い出されてまだ3年ぐらいだけれど、ずっと一人で暮らしていた俺にとって犬と……ナミと暮らすことになって、誰かと……護さんと知り合うことも想像もしていなかったことだった。
3年前から好きなときに眠って好きなときに起きて、何か作るか本を読むかして時間を潰して15時ぐらいに近くの海で散歩して、適当に買い物して夕飯を食べて適当に時間を潰してずっと生きてきた。誰とも関わらず暮らしてきた俺、たまに孤独感を覚えることもあったけれどたまに作ったものが売れてレビューを貰えただけで全部チャラになる。この繰り返しだった。誰かがいる家や周囲の目を気にするよりも一人の方が断然気楽だった。これからも、一人で生きていくんだろうな。そう思いながら海を散歩していた。
だが、2か月前ナミを拾ったことで環境は一変した。たまたまドライブしていた護さんに助けてもらって……その次の日に提案に甘えてナミを迎え入れるための準備の手伝いとアドバイスも貰って、そのときに護さんが1時間半かけてここまで来ていることを知ってしまい、申し訳なさがあふれて慌てる俺を面白そうに笑いながら「俺がしたいことだから気にするな」と頭を撫でられた瞬間に一気に胸が高鳴ってしまった。暫く体調が安定しなかったナミのことが心配で不安な俺を獣医さんと護さんが支えてくれた。護さんは毎日のようにメッセージを送ってくれて、時間があるときには通話をしてくれた。今もナミの様子を見たいからと遊びに来てくれる。すっかり、護さんが来るのがナミと同じ、いや、それ以上に楽しみにしている自分がいた。
(俺も、懲りないや)
自嘲する。もう誰かを好きになろうと思わなかったのに。好きになりたくなかったのに。
砂浜に俺だけしかつかない足跡が俺の人生を表しているのだと言い聞かせてきたのに。今は小さな四つの肉球のついた足と俺よりも少し大きな足がある。二人と一匹分の足跡。しあわせ、の四文字が浮かんだあと。ふあんの三文字が思い浮かんだ。いずれ、また俺一人しかなくなると思うと怖くてたまらなくなって身体が勝手に震えてぎゅっと自分を抱きしめる。
「……一人で生きていくつもりだったのになあ」
心の中で呟いていたつもりだったそれは、声に出ていて、波の音に掻き消されることなく妙に響いてしまった。慌てて口元を抑えたが、零れ落ちたものを戻すことはできない。悲しみに暮れる自分の声の響きが何とも情けなくて嫌になった。誰にも聞かれていなくてよかった。肩の力を抜くと同時に足元に衝撃が走ってよろめく。
「ワンッ」
「あ、ナミ?……っ!」
下を見るとハッハッと息を切らしながらまるで笑っているかの顔で俺を見上げるナミがいて、衝撃の正体に納得するよりも先ににゅっと前から誰かが現れぎゅっと両手首を握られた。
「えっと、あの、護、さん?」
俺の手首を掴んでいるのは、やっぱり護さんだった。突然拘束されて驚く俺に、護さんはにこりと笑う。痛くないけれど、力強く振りほどくことは不可能だと分かる。そもそも、抵抗したいなんて思えない。好きな人に触れられている。それだけで身体が心臓になってしまったような感覚で恥ずかしくなる。
「残念だったな、もう一人じゃなくなってよ」
「え、あ、あの、あつい、です」
「うん。俺も」
まるで悪戯が成功した子どものような笑顔を間近で見てカーッと顔が熱くて仕方ない。さっきの言葉は聞こえていると分かってしまったし、何を言えばいいのか分からなくなってつい思ったことを声に出しても力強く握ってくる手とは真逆に眼差しは優しくて混乱する。
顔があつい。握られる手首もあつい。護さんの掌もあつい気がする。あついと訴えても、あっさりと受け止められた挙句、俺に向けてくる眼差しは優しくて頼りがいのあるいつものものなのに、ぞくぞくするぐらいあつくて、はく、と火傷をした魚のように唇を動かすしかできなかった。
「理一、俺は……」
「っ」
厚くて大きな唇が言葉を紡ぐ。声にも熱気が入っているような気がしてどうしていいのか分からず、きゅっと乾いた唇を濡らし、視線を彷徨わせることしかできなかった。護さんが一つ息を吸って吐いて、笑みを消した赤い顔で意を決したように再度口を開いた。
ヴ――――、ヴ―――――。
そのとき、護さんの言葉をこれ以上言わせないようにと言わんばかりにバイブレーションが聞こえてきた。暫くの間この姿勢のままお互いに固まって護さんは気を取り直して言おうとしたことを続けようとしたようだったけれど、鳴りやまないバイブレーションの音に鬱陶しくなったのか息を吐いてパッと手が放し。瞬間膝に力が抜けてしゃがみこんだ。ふんふんと足の間に入ってくる無邪気なナミのふわふわな尻尾が今が現実だと思い知らせてくる。
(いまの、なに)
今されたことがじわじわと理解できて胸まで熱くなった。誤魔化すようにナミの背中を撫でて気を落ち着かせようとしていたとき。
「チッ……裕美子……あいつ」
(!)
背後から聞こえた苛立ちまかせの舌打ちとともに聞こえてきた名前に身体は震えて、見上げると乱暴にスマートフォンをポケットに仕舞う護さんと目が合ってたじろぐ。
「あの、出なくて大丈夫だったんですか?仕事のこととか……」
「仕事じゃないからいい。なんだよ、出てほしかったのか?」
「え、いいえっ」
「そうか。……よかった」
「はい?」
「いや?そろそろ戻るか」
「そ、うですね」
揶揄うような問いかけに首を振る。仕事なら諦めも付くけれどそうじゃないのなら、どうか俺じゃなくてもいいからナミとの時間を優先してほしい。醜い独占欲を無垢なるナミに押し付けてしまったようで少し罪悪感を覚えるけれど、俺の答えに嬉しそうな護さんを見ると、こう、勘違いしてしまいそうになる。
結局護さんはいつも通り夜ご飯を食べて20時ごろに帰っていった。先ほどバイブレーションが鳴る前に言いかけた続きも……『裕美子』って、誰ですかという疑問を飲み込んだ。前者は何となく聞いてしまえば最後な考えがあってのこと。後者は……俺に聞く勇気が無かったのと聞く資格が無かったから。明らかに女性の名前の主とどんな関係性なのか聞きたくなかった。もしも彼女と言われたのならまたしてもこの心地よい恋心を失うことになるのが怖かった。そして……そもそも、護さんと俺の関係性が分からない。知り合いにしては冷たく、友達と呼ぶには近すぎる。護さんに俺はどう思われているのだろうか。
「……寝よっか。ナミ」
「わんっ」
声をかけると布団の隣にごろりとナミが転がる。犬と言うのは予想以上に臭いが強くて毛むくじゃらで人よりも高い体温を持っていて熱いことをナミを飼って初めて知った。そして、その存在が心地よいことも。
ふわふわの頭を撫でてると気持ちよさそうに目を閉ざすナミを見習って俺も瞼を閉じる。
(好きになってほしいなんて高望みはしない。せめて、もう少しだけ俺の傍にいて)
その日見た夢は護さんが俺とナミに目を向けずに女性と笑い合っているというもので、目覚めはとても最悪なものだった。
あれから。特に何の変化もなく9月10月が過ぎ去り、11月に入っていた。少しずつ冬に向かっていき、風も随分と冷たくなった。ナミの体温が心地よくなる時期である。抱きしめると迷惑そうにされる。動物っていうのは人間とは違って表情が大きく変わらない割にはちゃんと『表情』があるのだと理解する。
平穏そのものの日々。俺はいつしか日常と呼んでいた。だが、最近その日常が以前のようにはいかなくなっていた。メッセージアプリの通知とともに現れる名前に浮かれるけれど、その内容にすぐに萎んだ。
『当分そっちに行けそうにないかもしれない』
『そうですか、仕事が忙しいんですか?』
『ああ。ちょっと部下がミスしてな……来月には絶対に行くから、ちゃんと家にいてくれよ』
『はい、待ってます。どうか体調にはお気をつけて』
『ありがとう。理一もな』
おやすみなさい、とスタンプを送ってスマホを放り投げてクッションで眠るナミに無遠慮に抱き着いて嘆いた。
「ナミちゅーん、護さん来れないってさあ」
「ふう」
呆れたようにため息を吐いた。ショック。それでもされるがままになっている優しい子。
すっかり身体が大きくなり顔こそまだ幼さが残るもののほとんど成犬に近いナミはほんの数か月前が嘘のようにふてぶてしい態度を取るようになってきた。なんだよ、ナミ。お前護さんとの態度と随分違うじゃないか。
「ナミも会いたいよなあ。俺も会いたいなあ……」
最近仕事が忙しいらしくてたまに来れない週末があったりしたけれど、しばらく、と書いてあった。このしばらくってどのぐらい?一週間?二週間?ひと月?そんなことも聞けない。だって、ただの同性の……きっと俺のことを弟ぐらいにしか見えていない護さんにこんなこと聞いたらまた『重い』だなんて冗談でも言われるのは嫌だ。ずっと変わらない。相変わらず、あの日の続きの言葉も、裕美子という女性のことも聞けていない。ナミの身体が大きくなって丈夫になっていくのとは真逆で、俺たちの関係は全く変わらない。きっと護さんは異性愛者だから、仕方がない。俺とは違う人間なのだ。だからこそ俺に構ってくれている。虚しさを紛らす安堵とともに日々を過ごす。俺は畳の上でそのままナミとともに眠ってしまい、身体の痛みで起きることになってしまった。やっぱり、俺と護さんはどこまでも立場が違いすぎる。部下を持つ苦労も会社での大変さも俺には分からないこと。俺なんてハンドメイド作家なんて名前だけみたいなもので、ほとんどニートみたいなものだ。ナミがいなければ俺の生活は相変わらず堕落の一途をたどるだけだっただろう。ああ、だめだ。このまま家にいると沈む一方だ。
「散歩行こうか」
「わん!」
随分とクールな表情をすることが増えて後ろを付いてくることが減ったナミだけれど、散歩の一言には変わらないキラキラとした顔をするし、ウミたちのところに行くと大人しく座っているのも変わっていないことに安心する。いつもの土曜日なら護さんが来てくれたけれど、明日も来ないんだと思うと落胆の気持ちがあふれてため息をひとつ吐いた。15時でも冷え込む時期になって厚手のクリーム色のカーディガンを着て外に出て……身体が固まる。玄関を出た先の門に立ち竦む姿に風を浴びたときよりも身体が冷えて勝手に震えた。
俺の反応に気付いたナミがう”ーーーと唸る。そんな俺たちの反応なんてどうでもいいかのように深紅のスカートを舞わせて俺に一歩、茶色のパンプスを響かせて近寄ってくる。無理矢理パーマをかけた……俺とよく似た顔の少女の姿。良く知った、華奢で守ってあげたくなるような可愛らしさの皮を被った恐ろしい子。
「見ーつけた」
とろりと頬を歪ませる。少女は本当に嬉しそうに不気味なほどに美しくて、怖い。
「おにいちゃん」
恍惚とした顔でつるりとした唇を動かす。また俺に近寄ろうとするのをナミが「ワン、ワンワン!!」警戒心むき出して吠えた後、牙をむき出しにして威嚇する。すると楽しそうな笑みが消え失せて冷たくナミを見下ろす彼女の変化に気が付いてその大きくなった身体を抱き上げて急ぎ、扉を閉めた。ナミが戸惑った様子を見せるが気遣う余裕もなく鍵をかけた。
「開けてよ。おにいちゃん。私だよ、理香だよ。会いたかったの。お兄ちゃんも会いたかったよね?開けてよ。開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて。開けろよ!おい!!」
語りかけるような声はだんだん語気が強くなり、扉を叩く音も最初は控えめだったのに平手でバンバンと叩きつけるようにする豹変に、恐怖でいっぱいになる頭の中で相変わらずなにも変わっていないなと呟いた。
「きゅーん……」
「だいじょうぶ、だいじょうぶだよ、ナミ……ごめん、おさんぽ、いけないや」
ふわふわな毛に顔を埋めて俺はナミに謝るばかりだった。今が夏の時期じゃなくてよかった。全部戸締りしている。そうじゃなかったら俺とよく似た少女……理香は、家に入り込んでナミにどんな危害を加えていたのか。想像もしたくなかった。バンバンバン、高くて濁った怒鳴り声と小さな手が力の限り玄関の戸を叩く音が永遠のように続いて、俺はただ目の前の暖かな存在を抱きしめて耐えることしかできなかった。俺でも助けることができた、尊い存在。いつの間にかこんなにナミといることが俺の救いになっていたことに今気付いた。
「……、聞こえなくなった……?」
「きゅうん……」
いつの間にか理香は外からいなくなっていたようだったけれど、どこにいるか分からないあの子に怯えて結局確認することはおろかその日外に出ることが出来なかった。散歩が好きなナミは不満に思っているだろうか。ストレスを与えてしまったことが申し訳なくて、ただただ俺の顔を心配そうに見ているナミに謝りながらそのたびに抱きしめたり身体を撫でる。少しだけ、気持ちを落ち着かせることができたけれど、変わらない理香の様子にぞっと鳥肌が立つ。
「あ」
パキン、音を立てて針金が切れてパラリと机に落ちた。俺の声に反応した足元にいるナミが驚いたように起き上がりこちらを見てきて「大丈夫だよ」と声をかけてもまだ純粋無垢な瞳が俺を映していたけれど、いたたまれなくて見ないふりをして、またペンチと針金を睨む。
気を紛らわしたくて無心になろうとハンドメイドをしようと机に向かったまでは良かったが、ペンチを握る手が震えて力加減を間違えてぱっきりと折れてしまうの繰り返しで心が乱れてどうしようもなくなってやりきれない気持ちのまま俺はスマホを取り出した。ほとんど無意識のことだった。今の俺にとって一番頼りになる……護さんに通話ボタンを押していたのは。着信音が鳴ったところでハッとした。
(馬鹿だ……!)
どうせ出ない。足元で目を閉じるナミを見た後時計を見ればいつの間にか21時を指していて、忙しくて明日も来れないと護さんにこんな時間に電話をかけるだなんて迷惑だろう。家に帰ってひと段落着いたころかもしれない、遅めの夕食をとっているかもしれない。……彼女と、会っているかもしれない。
(嫉妬だなんて、俺がする資格なんてない)
独占欲が現れる自分を恥じて、首を振って切ろうとした。後でメッセージで間違えて電話をかけてしまったとでも送ろう。スマホから顔を離そうとした。
プツリと音が聞こえたと同時に『もしもし』と電話越しだからか低く聞こえるけれど、恋するその人の声が鼓膜を揺らして、理香と再会したときとはまた違う意味で身体が震える。
「護、さん」
『どうした?』
「……っ」
『理一?』
その声に酷く安心して、涙がじわりと零れる。嗚咽を漏らさないように口を抑え衝動に耐え『なんでもないです』と言おうとした。心配そうに俺の名前を呼んでくれた。それだけで充分だと思った。これからもきっと頑張れる。そう思った。そう思ったのは、本当なんだ。
『まもるう、どうしたのお?』
『おま、裕美子、黙ってろ!』
「――……」
女性の高く甘い声が護さんの名前を親し気に呼ぶ声が聞こえた後に護さんが呼んだ名前に一気に頭が冷えた。あの日電話をかけた『裕美子』さんという女性と一緒にいる。そう分かった瞬間、何も考えずとも言葉が零れ落ちる。
「なんでも、ないです」
『ちょ、違うんだ!りい……』
「邪魔して、ごめんなさい」
護さんが何か言おうとしていたけれど、これ以上傷つくことを恐れて無理矢理通話を切ってスマホの電源を切った。何度か通知音が響いていた気がしたけれど聞こえないことにした。
「……」
涙は、不思議と出てこなかった。防衛本能が働いてくれたおかげだろうか。それとも、諦めを学んだからだろうか。どちらにしても俺が傷つかないようにするための術を行使した。
分かっていたことじゃないか。傷だらけの腕をぎゅっと抱きしめる。
(どう思われてしまっただろうか。突然電話をかけてきておいてすぐに切って。俺のことを心配してくれたのに。今怒っているのかな。もう、ここには来てくれないのかな)
「くうん、きゅーん、きゅん」
「……俺のせいでごめんね、ナミ」
悲しそうに鳴いているナミと目線が同じになるように椅子から降りてそのまま寝転び、テーブルの下に潜り込む。ペロペロと傷を癒すように頬を舐めてくる優しいナミに申し訳なく感じた。体力のない俺よりも護さんと散歩する方が楽しかっただろうに。今日の俺の行動で、もう護さんが来てくれないかもしれない。そう考えるとどんどん気持ちが落ち込んでいく。ごろりと仰向けになると視界はテーブルの裏側だけになる。
(俺が女の子だったら。もしくは異性愛者なら。理香が見た目通りの性格だったのなら)
俺は幸せになれたのかな。ああ、でも。その幸せだとしたら、ナミと暮らすことになることも、護さんと出会うこともないのだとしたら……今の俺の価値観からすると、不幸かもしれないや。
とりとめのないことを考えながら目を閉じる。どうしようもないどこまでも追いかけてくる現実から少しでいいから逃げたくなった。
――ピンポーン。
「……ん……?ふぁ、くっしゅん!」
「わんっ!」
響くインターフォンの音によって意識が浮上したと同時にくしゃみをした。どちらの音に驚いたのか分からないけれどナミがむくりと起き上がって一度吠えたあと、チャチャチャと玄関へと走っていく。俺は意識が覚醒しきれていないままナミの後を追いかけた。何故外に出れなかったことも忘れ、玄関を開けろと立ち上がり前足をカリカリと引っ掻くその姿に微笑ましく感じながら、戸を開ける。
「わうん、わんわん!」
「おーナミ。今日もふさふさだなあ」
玄関先にいたその人物にナミは警戒心などなくぴょんっと飛び出し、ふんふんと鼻を鳴らしながら地面に転がってお腹を見せ、わしわしと男らしい手が無防備なふわふわな毛で覆われているところも覆われていないところも撫でまわすのをぼんやりと眺める。
(あれ。護さんがいる)
暫く来ることができないと言っていたのに。なぜかスーツを着た護さんがここにいる。
「あれ、今日、というかしばらく来れないんじゃ……?」
「うーん……ほら、今の時間見て見ろ」
「時間……?」
どこかの海の景色のスマホのロック画面。その真ん中に堂々と書いてあるのは今現在の時間。誰のスマホの画面なのかも考えつかないまま、言われるがままに表示されている時刻をぼーっと眺める。
『22:47』と出ているそれ。ただの数字の羅列だと最初は思った。なんの数字だろうとまじまじと見て、今さっき言われた『時間』という単語を思い出し……ハッとする。
「あっ」
ただの数字じゃない。今の時間を指している。もう日付が変わるまで1時間と少ししかないぐらい遅い時間で今日はまだ土曜日じゃない。辺りを見れば真っ暗で朝すら来ていないことが分かる。ずっとナミと護さんしか見えてなかった。そんな自分が恥ずかしいと思うよりも先に、さあっと青ざめた。指先が寒さとは違う理由で冷たくなるのが分かる。だって、俺は、勝手に電話しておいて、女性の声が聞こえて気が動転して、勝手に切った。それを思い出してしまった。顔色が変わった俺に護さんは色々察したようでゆっくりと立ち上がり俺の正面にやってきた。
「俺は今から行くってメッセージで伝えていたけれどな。まあ、見ていないのを知ってて、勝手に来たんだけどよ。寝てたのか?じゃあ、悪いことしたな。つい、気になって来ちまったんだわ。俺、理一の話を聞きたいんだ。電話してくれた理由を、あんな声を出していた理由を、聞きたい」
「えっと、あの」
「何かあった……んだよな」
手を握られてもはや疑問ではなく確信の問いかけに、身体が震える。その手に縋るように両手をぎゅっと握る。俺の手は情けなく細いのに、護さんの手は頼もしく太くて暖かった。なぜか泣きたくなる。
「ごめ、んなさい。おれ、そんな、邪魔なんてつもりじゃなくて……」
「……俺からも、色々言いたいことあるんだ。中に入ってもいいか?」
「っ、は、い」
何を話せばいいのか。分からくなった俺は護さんからの提案に何も考えずに頷いた。
チャッチャッチャ。ナミのご機嫌なステップだけが聞こえ、俺たちは無言で廊下を歩く。後ろから聞こえる護さんの足音は何度も来ているから足取りに迷いも躊躇いない。今のこの家の主である俺が一番、ここから逃げたくなる。
ナミは居間に着くといつも通りのクッションにころんと転がってすぐに寝息を立ててしまった。間にいてほしかったのに護さんが来たからもう大丈夫だと思ったのか普通に眠たかったのか、とにかくナミは夢の中へと旅立ってしまった。
「……」
「……」
ちゃぶ台の前にふたり対面するように座り、そのまま気まずい沈黙が流れる。生憎今日はテレビも付けておらず、夜であることも相まって酷く静かだった。心臓はバクバクだったけれども。
(……暖かいお茶を出した方がいいかな)
行動していないと落ち着かなくて、俺の電話のせいでこんな寒い時間にここまで来てくれたのだからお茶ぐらい用意しないと、と誰にしているのか分からない言い訳をして立ち上がろうとした。けれども、強く腕を引かれバランスを崩し、ぎゅうっと抱き込まれる。厚い胸の感触。
「!」
「……とりあえず、倒れているとかじゃなくて安心した。理一、すごい苦しそうな声を出すから、体調が悪かったんじゃないかって。連絡しても出ないし、返信もないし」
「っ、ごめんなさい」
「いい。……変に気を使わせたみたいで、悪い」
耳元で聞こえる低い声、微かに香る煙草とコーヒーの香り、スーツの硬い感触と伝わる熱に頭がくらくらする。
やめてほしい。
勘違いしてしまいたくなる。
けれど、拒絶なんてできない。だって、俺は、護さんが好きだから。
護さんが俺のことをそう思っていなくとも好きな人から抱きしめられると嬉しくてたまらない。こんな状況でも心臓が勝手に鳴って護さんに聞こえないか心配になった。
少ししてすっと身体を放されて少しだけ熱が恋しくなるけれど、少し怖いぐらいの真剣な表情でこちらを見る護さんにまたドキドキする。至近距離の護さんの顔につい顔が熱くなるけれどその空気が目を逸らすことを許されない。ただ護さんの言葉を待った。
「まず、説明させてくれ。さっきまで一緒にいた女の声は裕美子っていうやつなんだが……あいつとは何でもない。彼女とかじゃない」
「彼女じゃない……?」
「ああ」
護さんの言葉をオウム返しのように問いかけると強く頷かれる。決して、護さんの言葉を信用していないわけじゃない。嘘だなんて思わない。でも、電話越しから聞こえた裕美子さんの声が彼氏でも何でもない人にしては随分と甘く媚びるように護さんの名前を呼んでいたこと、遅い時間に二人でいたことから、恋人関係ではなくともそれに近しいものではないかと邪推してしまう。そんな俺の考えを読み取ったように護さんは重いため息を吐いて、心底嫌そうに唇をこじ開けて細かく説明をしようと決めたような顔をした。
「いや。正確に言うと『もう』なんでもない奴、か。……俺の元婚約者だ」
「!婚約者……」
「違う。元、だ。元。今は全然違うから。今はもう赤の他人。俺の気持ちはもう無い。そこは間違えないでくれ、頼むから」
「は、はあ、わかりました……?」
まさかの単語に驚く俺に、両肩を掴んであまりに必死に『元』を強調してくる護さんの迫力に負け、つい頷いた。とにかく、今は関係ないというのは伝わってきた。少なくとも、護さんからは。裕美子さんの方はそうでもなさそうだったけれど……説明してくれるとそう言ってくれたので、怖いけれど聞く。このままじゃもやもやした気持ちが残ったままになりそうで、こんな気持ちでは多分、お互いにもう一緒にいられない気がした。
「でも、どうして?さっき、護さんのことを親し気に呼んでいましたよね。あと、あんな時間で二人で……?」
あ、なんか重いかも。そう思ったのは言葉にした後のこと。護さんとは兄弟でもそういう関係でもないのにこんなこと聞くなんて。浮気を問い質している女々しい人のような自分に引いた。
「……」
俺の変な質問に護さんは目を泳がせて言いあぐねる様子を見せる。でもそれは俺を軽蔑しているでも引いているわけでもなく、どう答えたらいいものかと考えているようだった。少しすると整理がついたのか口を開いてくれた。
「あーそれはな……ちょっと長い話になるんだが、いいか?」
「は、はい」
護さんの話ならいくらでも聞きたい。俺の返事に一度うーんと唸って、護さんはぽつりぽつりと話し始める。
「もう一年前の話になるのか。去年の夏ぐらいから婚約していたにも関わらず、浮気してたんだよ。しかもあっちは不倫。そのことを責めた俺のことを身長も器も心も狭い男だなんて罵ってくれた挙句、浮気相手の方が好きだとか言いやがって……」
「浮気、ですか……」
「ああ。丁度このぐらいの時期だったか……両家顔合わせも終えていたのに、仕事が忙しいとかいって会えなくなって。何か雰囲気も前よりも明るくなって派手な格好が増えて怪しいと思ってたら友達が知らない男とホテルに入っていくのを見た、と言われてな。問い詰めたらあっさりと認めて、あっちから婚約破棄を申し出てきた。どうやら、浮気相手は金持ちだったみたいで慰謝料をぽんと貰ってそんでお終い。まあ、ここ何か月前から連絡がまた来るようになってなんか色々話していたが、まあ今浮気相手との家族と上手くいっていないから俺とやり直そうと縋ってきててな。さっき一緒にいたのはいい加減ケリをつけたくて友達を交えて三人で話してた。だから二人きりでもなかったんだよ。既成事実でも作りそうな勢いだったからその対策としてな」
「そう、だったんですね」
知りたかったことのすべてを護さんがすらすらと答えてくれる。そういえば護さんは裕美子さんに対して冷たかったことを思い出した。電話では分からなかったけれど他にも誰かがいて決して二人きりではなかった。そのことが分かって心底安心した。諦めることには慣れていても、好んでいるわけじゃない。俺はその説明に安心したけれど、護さんの様子が少し違っていた。笑っているけれど笑っていないような、そんな顔。
「情けねえ男だよな。浮気相手に嗤われたよ。女ひとりも捕まえておけないつまらなくて情けない男ってさ。浮気した方が絶対に悪い。そう思っていたが……実際されてみると、なんだろうな。プライドが傷つけられた?っていうんかね。俺にも原因があったのかな、て思うこともあったんだ」
少しの沈黙の後悲しそうに力なく笑う護さんの手を握って、首を振って否定した。
「そんなことない!護さんは悪いことなんてしてない、悪いのは浮気した方だ!」
あまりに必死な声だった。自分のことなのに俺が驚いてしまった。でも、本音だから目を離さない。護さんの何が嫌なのか俺には分からない。まだ出会って半年も経っていないから見えていないところもあるのかもしれない。それでも、結局悪いのは浮気した方であって、護さんに落ち度があるようには到底見えなかった。
護さんも突然大声を張り上げた俺を目を見開いていたけれど、赤い顔のままそれでも真剣だと伝わってほしいと訴える視線をどう受け取ったのか、少ししてふにゃりと笑う。
「……ありがとうな」
その笑い顔は少しだけ幼く見えた。
「そんな、話し合いの中で電話をして、ごめんなさい」
「話し合いも終盤だったから気にすんな。いつまでも帰らないあいつに疲弊していたし……」
またひとつため息を零した。心底不愉快そうな、嫌そうなそんな雰囲気。
「護さんは、裕美子さん?に未練は無かったんですか?婚約まで、していた仲だったんですよね。落ち込んだ、んじゃないんですか?」
いくら浮気をされたとはいえ、俺みたいに引き摺ってしまう人間もいる。名前を出すことすらしんどくて、でも憎むまではまだいけていない俺にとってあまりに護さんが忌々しそうにしているのが、少しだけ疑問だった。浮気は許せないし別れることを選ぶとは思うけれど、切り捨てることはまだできそうにない俺からすると護さんがとても強い人に思えてつい質問してしまった。聞きようによってはとても失礼なことだったのに、護さんはどこまでも真摯に答えてくれた。
「うーん……確かに凹んだし落ち込んで食事も喉を通らなかったぐらいだったんだが……それは裏切られたショックや、正直、浮気に気付いた地点でもう愛情は消え失せてたからな。もしも、浮気と問い詰めたときに縋られても切り捨てられたと思う」
「そうなんですね」
そのあっさりとした返答に護さんはやっぱり俺とは違う強い人なんだなあ、とつい感心してしまう俺に何故か言い淀む様子を見せてくる彼に首を傾げた。
「あー……うん。理一なら話してもいいか」
「?」
「俺な、父子家庭なんだ。物心ついたときには母親はいなかった」
「えっ」
「まあ、祖父母と一緒に暮らしていたから男手一つで育てられたわけではないんだけどな。片親の苦労みたいなのはあまり感じなかった。たまに同級生とか先生からからかわれることがあったが、あんまり気にならなかったよ。祖父母も親父もちゃんと俺を育ててくれたからな。高校生になってから親父に母親がいない理由を教えてもらった。
まだ一人で歩くこともできない俺を置いて、どっかの男と駆け落ちして行方不明になったんだと。
……高校生になった俺に「私がお母さんよ、会いたかった」と痩せこけた虚ろな目をした女が腕を広げて会ったことを親父に伝えて暫くしてから教えてもらったことだ。
親父は俺の結婚が無かったことよりも変な女に引っかかる己の遺伝子をしっかり受け継いだ俺を悲しんでたな……」
「……」
俺は護さんの過去の話を聞いて何も言えなかった。無言になってしまった俺の頬を撫でながらぽつりと零してくれた。俺はじっと見つめて続きを待った。
「今思えば……俺は母親がいない理由を聞いたときから、女に対して苦手意識を覚えていたのかもしれない。裕美子とは社会人になってから知り合って付き合いだしたけれど、嫌いじゃないけれど好きでもなかった。付き合いたいと言われたからそうした。結婚したいと言われたから結婚しようと思った。そのぐらいの感覚だったんだ。もしかしたら、そんな心無い態度があいつを浮気に走らせた理由のひとつだったのかもしれない。さっきもそのことを責められていたんだ」
「それでも、浮気をして、罵って、自分のしたことを棚上げに復縁を迫るようなことは、してはいけないと思います」
「ああ、俺もそう思うよ。まず話し合いだよな。まさかそんな母親と似た女だっただんんて見抜けなかったことが一番落ち込んだんだが……でも、理一が俺と同じ価値観で嬉しいな」
「俺も」
「ん?」
「俺も、浮気された側、でしたから……」
価値観が同じなのは当然だ。だって、俺も護さんと同じように浮気された立場の人間だったから。言いたいことも自分のことが情けなくなることも、浮気をされたから別れを切り出したのに未練がましくされる不思議と鬱陶しさも、全部じゃなくても理解できる。誰かに話したいと思わなかったし、そんな親しい人も俺にはいなかったから、このことを言ったのは3年ぶりになるのだろうか。もう3年も経っているに今も変わらずに覚えている。脳にも、身体にも、刻み込まれたこと。
「うぶっ」
高い声とともに胸に訪れる衝撃のおかげで、意識が現実に戻る。幼い頃からある時計を見ると午前6時にはまだ届いていない。前の俺なら寝ている時間、万が一起きたとしても時計を見ることなく二度寝を決め込んでいたけれど、今の俺は瞼をこじ開けることを選んだ。
「おはよう……ナミ」
「わうん!」
キラキラとした澄んだ海のような目で俺の挨拶に返すように元気に吠えるナミの姿に自然と笑みが零れる。べろべろと顔を舐めまわされる前に起き上がり、散歩の準備を始める。起きたらまずは散歩、それが分かっているナミは俺の後ろを付いて回る。以前あまりに足元でうろちょろするものだから彼女の身体を蹴っ飛ばしそうになるのを阻止するために避けようとしたら、バランスを崩して尻もちをついたことがあって痛みに暫く悶絶していることがあって以来、ちゃんと邪魔にならない程度についてくるから賢い子だとここのところナミが付いてくるたびに感心している。用を足して出てくるとぱあっと顔を明るくさせてくるんとした尻尾をぶんぶん振ってくる。ほんの少しだけ顔を合わせないだけで熱烈な歓迎だなあ、なんて思いながらしゃがんでその頭と頬を撫でくり回す。その暖かさに少しだけ泣きそうになるのもいつものことだ。
「おはよう。ウミ、カイ、アオ」
首輪にしっかりとリードを繋ぎ、外に出てまず向かうのは自分の家の庭……ホームセンターで買った平べったい木材に名前を俺の手書きで素っ気なく乗せられている墓と呼ぶには随分と簡素なそれらの前に一本ずつ線香を立てしゃがんで手を合わせて名前を呼ぶ。あの子たちからすると海に対してあまりいい思い出がないだろうから連想させる名前をつけるなんて酷いのかもしれないけれども、それでも僕の乏しい語彙力で名前をつけるにはこれしか思いつかなかった。如何せん、ちゃんとした顔立ちもどんな子だったのかも性別も、ナミと一緒にいたけれど彼女と血が繋がっているのかも俺には分からないんだ。ごめんね。もう少し落ち着いたらちゃんとした石造りのお墓を買ってあげるからね。
不思議といつもはちゃかちゃかと動き回るナミもウミたちの前だと俺の隣でじっとお座りをして待ってくれる。犬にも分かるのだろうか。そこに、助けられなかった子たちが埋められていることを。それともただ僕がしゃがんでいるからそうしているだけなのか。できることなら、分かっていてほしいと願うのはエゴなのかな。
「はやい、はやいって!ナミっ」
「ワンっ!」
苦しむ俺を尻目にランランと砂浜を走るナミ。おかげで足腰が鍛えられる日々だ。獣医さんが言うのはナミは今生後4か月か5ケ月ぐらいらしい。人で言うと小学校下級生ぐらいの年齢らしく、とにかく元気で溢れている時期らしい。とにかく好奇心旺盛で走ってご飯を食べて眠る。遊ぶのも大好きだ。いいことだ、とても健やかな絵にかいたような犬って感じの犬だ。ただ、問題がひとつ。
「はあ、ほんと、もうほんと、無理……だ!」
「ウウン」
「ごめんってば、ゴホッ」
運動とかあまりせず、ナミを迎え入れるまでは買い物か散歩に出るぐらいしか外に出ることが無く夜更かしして昼に起きるを繰り返していたほとんど引きこもりのような生活をしてきた俺にとってナミのスピードについてこれず、こうして膝を折り、不満そうな唸りを受けながら謝るばかりだ。ぜえはあ、と肩で息をしているとポケットにしまっていたスマホが震えて取り出すと、液晶に映された名前を見て違う意味でドッと心臓が脈打ち、顔が熱くなる。
『護さん』の名前を見るだけでざわついてしまう心を落ち着かせてメッセージアプリを開く。
『一時頃にそっちに着く』
素っ気ないメッセージの後に可愛らしい犬が駆けだしているスタンプが送られてつい笑みが零れた。
『分かりました。お気をつけて』
そう送った後少し悩んで扉の前で座って待っている犬のスタンプを送ってポケットにしまい込む。そしてフンッと鼻を鳴らしてるナミの頭を撫でながら、良いことを教えてあげる。
「今日も護さん、来るってさ。よかったねえ」
「わん!」
俺の言っていることが分かっているかのように嬉しそうに鳴くナミ。いつも行く俺との散歩よりも週末に訪れる護さんとの散歩の方がナミは好きみたいだ。そうだろうね、なんたって護さんは俺と違って明らかに身体が鍛えられている運動好きそうな人だから、ナミの全力散歩についていってくれるからね。俺みたいにひょろっとしたもやし体系よりもがっしりとしている男らしい人の方が素敵だと思う。……俺の場合は、ナミと違って少しだけ、邪な目で見ているけどさ。少し体力が回復してまたナミとともに砂浜を駆け出した。
すぐにまた息が切れてしまい、彼女には呆れたように息をつかれてしまった。
ピンポーン。12時50分、軽快な音が家中に響き渡り俺の足元で眠っていたナミがガバッと起き上がりチャチャチャ!と音を立てて廊下を駆け出していく。俺も持っていたペンチを置き、作業を中断して玄関のカギを開けるために少し早足で向かう。
「いらっしゃい。暑かったでしょう?」
「少し外に出ただけで汗が噴き出してきたわ……よう、ナミ。まーた大きくなったか?」
「ワン!くうん、きゅんきゅん」
「甘えた声出しちゃって。良かったね」
「……」
「?どうしました?」
「あ、あー……いや。理一は体調大丈夫か?」
「、大丈夫ですよ。ああ、ちょいちょい筋肉痛に苦しめられていますけれどね」
「若いのに何言ってんだよ」
「護さんだって若いでしょうよ」
「4歳っていうのは大きいんだぜ……」
「?へえ」
疲れたようにそう言う護さんに首を傾げ適当な相槌を打つことしかできない俺。苦笑いをされた。俺も護さんぐらいの年になればその言葉の意味が分かるのかな。……4年後の俺なんて全く想像できないけれども。
7月のあの日以来ほぼ毎週訪れている護さんはすでに家の配置の大体を知っている。迷いなく居間へとナミとともに俺より先に向かい、畳に座ってナミと戯れる。冷蔵庫から水出し麦茶を取り出し、氷を二個入れたコップに注ぎ年季の入ったちゃぶ台の上に置いた。
「良かったらどうぞ」
「ああ、ありがとうな」
額を擦り付けてくるナミをそのままに太い腕を伸ばしてしっかりとした首を逸らして隆起した喉仏を晒してゴクリゴクリと麦茶を飲み干す姿からつい目を逸らして台所前にある脚の長いテーブルの上に散らばっているものを片付けるべく手を動かす。カチャカチャと音を立てていたせいで何をしているのかと護さんが声をかけてきた。
「今日も作業か。大変だなあ」
ペンチや半端に切られたり曲げられた針金やビーズが散乱しているのを、護さんはもう不思議そうにしたりなんてしない。俺がアクセサリーやストラップ、たまにぬいぐるみなどの裁縫をしたり……所謂ハンドメイド作家であることを知っているからである。
「いえ、好きでやっていることですから」
「俺にはできねえな。やっぱりすごいな」
護さんはナミを転がして撫でまわしながら感心したようにそう言うけれど、謙遜ではなく本当に大したことないのだ。正直あまり売れていないしとてもじゃないけれどこの道一本で食っていけるようなものじゃなく、昔ながらの趣味みたいなものだ。だから、すごいなんて呼べるものじゃないのだ。この話題になると、護さんに褒められるのは嬉しいけれど困ってしまう。
「そんな……。あ、何か食べてきましたか?」
「いや、まだだな」
「俺たちもまだなんですよ。素麺でよければ食べません?」
「おお、ありがてえ。素麺がいいなあ」
「分かりました。今用意しますね」
半ば誤魔化しに近い話題だったが、まだ食べていないという返答に安心して机の上の片づけもそこそこに(どうせこっちのテーブルはこの作業でしか使わないのだから)鍋に水を入れ火を点けて沸騰するのを待ちながら、引き出しから素麺を取り出したところである考えが浮かんだ。
(なんか、同棲しているみたいだ)
そんな浮ついたことを考えてしまい、小さく首を振って慌ててその思考を飛ばした。冷房が効いているのに火をつけたせいか顔が少し熱い。まさか、護さんも同じようなことを考えていただなんてお互い思いもよらなかったけれども。
「できましたよ」
「ああ、悪い。ありがとうな」
「いえいえ。いただきます」
「いただきます」
「わん!」
ちゃぶ台にまで氷を浮かべ、適当に麺つゆをかけた素麺を入れた二人分の器と箸を持っていって啜った。もちろんナミにもふやかしたドックフードを与える。先に食べ終えたナミが物欲しそうにねだるような視線が突き刺さり、なにかあげたくなるけれど、心を鬼にして無視する。まだ子犬であるナミに人間の食べ物は早い……いや、味の濃い人間の食べ物を動物にあげること自体よくないことだと分かっている。いずれ根負けして何かしらあげてしまいそうな自分が怖い。
「ほら、新しいおもちゃだぞー」
「また買ってきてくれたんですか?」
「面白くねえ?」
「……うなぎ?」
「ああ。ナミが咥えたら可愛いだろうな、て……あ」
「ふがふがっ」
「……」
「……」
「なかなか袋には勝てませんね」
「くそ……ほら、こっちであそべ!」
「わうん?」
「あははは」
少し遅めの昼食を終えて使い終えた食器を洗うのは何となく護さんの役割になっていて、片づけを終えた護さんはバックの中から袋に入ったおもちゃを取り出した。ここに来るたびに増えていくおもちゃは居間を華やかにしていく。だが、最初にナミが興味を示すのはおもちゃ本体ではなく残念ながら袋の方だ。袋の中に頭を突っ込んでいるところを必死に護さんがおもちゃに興味を惹かせるように誘うのを僕は思わず笑いながら見ていた。
暫く攻防戦(護さん不利の)を観戦した後、俺は台所前のテーブルに向かう合い、先ほどの続きを再開した。
少しの間熱中し、ただの一つの棒だった針金を魚の形にいくつかしたところで少しだけ手を止めてそっとナミと何とかうなぎの玩具で遊ばせることに成功している護さんを観察する。楽しそうに笑っている彼の姿にぎゅっと胸が締め付けられる。一緒にいるとなぜか逃げたくなるのに、どうしても一緒にいたいという変な気持ち。またこんな気持ちになるなんて考えてなかった。甘くて少し辛い苦しみに胸をきゅっと抑えた。
「理一」
「!はい」
名前を呼ばれるだけで心臓が飛び出そうになった。慌てていつの間にか顔を机に突っ伏していたのを起き上がり返事をする。あまりの俺の焦り様に護さんとナミは同じように驚いた表情をしていた。
「ああ、悪い。驚かせたか?そろそろ散歩の時間かと思ったんだが」
「あ、そ、そうですね。そろそろ行きましょうか」
時計を見るといつの間にか14時半を少し過ぎていた。椅子から立ち上がる俺に護さんが心配そうに声をかけてくる。
「大丈夫か?区切りが良くないんだったら俺だけでも」
「いえ!一緒に行きたいんです!」
「そ、そうか」
「っあ、あ、じゅ、準備してきますっ」
自分だけで行く、と言おうとする護さんの言葉を最後まで言わせたくなくて必死に遮ったことで妙な空気が生まれて、こけそうになりながらリードとポリ袋を取り出してウェストポーチに突っ込んだ。護さんの顔がどこか赤くなっていたように見えたのは、きっと俺にとって都合よく見えただけだと何度も茹だる頭に言い聞かせた。
「おおー元気だなあ。ナミ」
「わうんっ」
「はあ、ハアッ」
「おーい、無理するなよー」
「す、いません。先行っててください……」
「おう、理一は待ってろー。うおっ!待て、ナミ」
「ワンワンワンッ!」
駆け出すナミについていく護さんは俺よりも断然体力がある。暑さと身体を動かしたことでじわりと滲む額の汗を夏用のパーカーの袖で拭う。冷房の効いた室内ではともかく、熱気の立ち込める外ではいくら夏用と言えど少しでも布を減らして、脱いでしまいたい衝動に駆られるが堪えて苦し紛れに胸元をパタパタと上下に動かして風を得ようとした。
ふと、振り返った。砂浜にはいくつもの足跡がある。前を見るとフリフリと尻尾を揺らしながら懸命に走るナミと、時折声をかけているのかナミの方を見る護さんの後ろ姿。なんだか、胸がいっぱいになって、呼吸が一瞬止まる。
「ゴホ」
肺に酸素が行き渡らなくて身体が限界を迎えて咳が出る。もう一度振り返り、足跡を眺める。もう数時間もすれば完全に消えてしまう足跡たち。
今まで……と言っても、家から追い出されてまだ3年ぐらいだけれど、ずっと一人で暮らしていた俺にとって犬と……ナミと暮らすことになって、誰かと……護さんと知り合うことも想像もしていなかったことだった。
3年前から好きなときに眠って好きなときに起きて、何か作るか本を読むかして時間を潰して15時ぐらいに近くの海で散歩して、適当に買い物して夕飯を食べて適当に時間を潰してずっと生きてきた。誰とも関わらず暮らしてきた俺、たまに孤独感を覚えることもあったけれどたまに作ったものが売れてレビューを貰えただけで全部チャラになる。この繰り返しだった。誰かがいる家や周囲の目を気にするよりも一人の方が断然気楽だった。これからも、一人で生きていくんだろうな。そう思いながら海を散歩していた。
だが、2か月前ナミを拾ったことで環境は一変した。たまたまドライブしていた護さんに助けてもらって……その次の日に提案に甘えてナミを迎え入れるための準備の手伝いとアドバイスも貰って、そのときに護さんが1時間半かけてここまで来ていることを知ってしまい、申し訳なさがあふれて慌てる俺を面白そうに笑いながら「俺がしたいことだから気にするな」と頭を撫でられた瞬間に一気に胸が高鳴ってしまった。暫く体調が安定しなかったナミのことが心配で不安な俺を獣医さんと護さんが支えてくれた。護さんは毎日のようにメッセージを送ってくれて、時間があるときには通話をしてくれた。今もナミの様子を見たいからと遊びに来てくれる。すっかり、護さんが来るのがナミと同じ、いや、それ以上に楽しみにしている自分がいた。
(俺も、懲りないや)
自嘲する。もう誰かを好きになろうと思わなかったのに。好きになりたくなかったのに。
砂浜に俺だけしかつかない足跡が俺の人生を表しているのだと言い聞かせてきたのに。今は小さな四つの肉球のついた足と俺よりも少し大きな足がある。二人と一匹分の足跡。しあわせ、の四文字が浮かんだあと。ふあんの三文字が思い浮かんだ。いずれ、また俺一人しかなくなると思うと怖くてたまらなくなって身体が勝手に震えてぎゅっと自分を抱きしめる。
「……一人で生きていくつもりだったのになあ」
心の中で呟いていたつもりだったそれは、声に出ていて、波の音に掻き消されることなく妙に響いてしまった。慌てて口元を抑えたが、零れ落ちたものを戻すことはできない。悲しみに暮れる自分の声の響きが何とも情けなくて嫌になった。誰にも聞かれていなくてよかった。肩の力を抜くと同時に足元に衝撃が走ってよろめく。
「ワンッ」
「あ、ナミ?……っ!」
下を見るとハッハッと息を切らしながらまるで笑っているかの顔で俺を見上げるナミがいて、衝撃の正体に納得するよりも先ににゅっと前から誰かが現れぎゅっと両手首を握られた。
「えっと、あの、護、さん?」
俺の手首を掴んでいるのは、やっぱり護さんだった。突然拘束されて驚く俺に、護さんはにこりと笑う。痛くないけれど、力強く振りほどくことは不可能だと分かる。そもそも、抵抗したいなんて思えない。好きな人に触れられている。それだけで身体が心臓になってしまったような感覚で恥ずかしくなる。
「残念だったな、もう一人じゃなくなってよ」
「え、あ、あの、あつい、です」
「うん。俺も」
まるで悪戯が成功した子どものような笑顔を間近で見てカーッと顔が熱くて仕方ない。さっきの言葉は聞こえていると分かってしまったし、何を言えばいいのか分からなくなってつい思ったことを声に出しても力強く握ってくる手とは真逆に眼差しは優しくて混乱する。
顔があつい。握られる手首もあつい。護さんの掌もあつい気がする。あついと訴えても、あっさりと受け止められた挙句、俺に向けてくる眼差しは優しくて頼りがいのあるいつものものなのに、ぞくぞくするぐらいあつくて、はく、と火傷をした魚のように唇を動かすしかできなかった。
「理一、俺は……」
「っ」
厚くて大きな唇が言葉を紡ぐ。声にも熱気が入っているような気がしてどうしていいのか分からず、きゅっと乾いた唇を濡らし、視線を彷徨わせることしかできなかった。護さんが一つ息を吸って吐いて、笑みを消した赤い顔で意を決したように再度口を開いた。
ヴ――――、ヴ―――――。
そのとき、護さんの言葉をこれ以上言わせないようにと言わんばかりにバイブレーションが聞こえてきた。暫くの間この姿勢のままお互いに固まって護さんは気を取り直して言おうとしたことを続けようとしたようだったけれど、鳴りやまないバイブレーションの音に鬱陶しくなったのか息を吐いてパッと手が放し。瞬間膝に力が抜けてしゃがみこんだ。ふんふんと足の間に入ってくる無邪気なナミのふわふわな尻尾が今が現実だと思い知らせてくる。
(いまの、なに)
今されたことがじわじわと理解できて胸まで熱くなった。誤魔化すようにナミの背中を撫でて気を落ち着かせようとしていたとき。
「チッ……裕美子……あいつ」
(!)
背後から聞こえた苛立ちまかせの舌打ちとともに聞こえてきた名前に身体は震えて、見上げると乱暴にスマートフォンをポケットに仕舞う護さんと目が合ってたじろぐ。
「あの、出なくて大丈夫だったんですか?仕事のこととか……」
「仕事じゃないからいい。なんだよ、出てほしかったのか?」
「え、いいえっ」
「そうか。……よかった」
「はい?」
「いや?そろそろ戻るか」
「そ、うですね」
揶揄うような問いかけに首を振る。仕事なら諦めも付くけれどそうじゃないのなら、どうか俺じゃなくてもいいからナミとの時間を優先してほしい。醜い独占欲を無垢なるナミに押し付けてしまったようで少し罪悪感を覚えるけれど、俺の答えに嬉しそうな護さんを見ると、こう、勘違いしてしまいそうになる。
結局護さんはいつも通り夜ご飯を食べて20時ごろに帰っていった。先ほどバイブレーションが鳴る前に言いかけた続きも……『裕美子』って、誰ですかという疑問を飲み込んだ。前者は何となく聞いてしまえば最後な考えがあってのこと。後者は……俺に聞く勇気が無かったのと聞く資格が無かったから。明らかに女性の名前の主とどんな関係性なのか聞きたくなかった。もしも彼女と言われたのならまたしてもこの心地よい恋心を失うことになるのが怖かった。そして……そもそも、護さんと俺の関係性が分からない。知り合いにしては冷たく、友達と呼ぶには近すぎる。護さんに俺はどう思われているのだろうか。
「……寝よっか。ナミ」
「わんっ」
声をかけると布団の隣にごろりとナミが転がる。犬と言うのは予想以上に臭いが強くて毛むくじゃらで人よりも高い体温を持っていて熱いことをナミを飼って初めて知った。そして、その存在が心地よいことも。
ふわふわの頭を撫でてると気持ちよさそうに目を閉ざすナミを見習って俺も瞼を閉じる。
(好きになってほしいなんて高望みはしない。せめて、もう少しだけ俺の傍にいて)
その日見た夢は護さんが俺とナミに目を向けずに女性と笑い合っているというもので、目覚めはとても最悪なものだった。
あれから。特に何の変化もなく9月10月が過ぎ去り、11月に入っていた。少しずつ冬に向かっていき、風も随分と冷たくなった。ナミの体温が心地よくなる時期である。抱きしめると迷惑そうにされる。動物っていうのは人間とは違って表情が大きく変わらない割にはちゃんと『表情』があるのだと理解する。
平穏そのものの日々。俺はいつしか日常と呼んでいた。だが、最近その日常が以前のようにはいかなくなっていた。メッセージアプリの通知とともに現れる名前に浮かれるけれど、その内容にすぐに萎んだ。
『当分そっちに行けそうにないかもしれない』
『そうですか、仕事が忙しいんですか?』
『ああ。ちょっと部下がミスしてな……来月には絶対に行くから、ちゃんと家にいてくれよ』
『はい、待ってます。どうか体調にはお気をつけて』
『ありがとう。理一もな』
おやすみなさい、とスタンプを送ってスマホを放り投げてクッションで眠るナミに無遠慮に抱き着いて嘆いた。
「ナミちゅーん、護さん来れないってさあ」
「ふう」
呆れたようにため息を吐いた。ショック。それでもされるがままになっている優しい子。
すっかり身体が大きくなり顔こそまだ幼さが残るもののほとんど成犬に近いナミはほんの数か月前が嘘のようにふてぶてしい態度を取るようになってきた。なんだよ、ナミ。お前護さんとの態度と随分違うじゃないか。
「ナミも会いたいよなあ。俺も会いたいなあ……」
最近仕事が忙しいらしくてたまに来れない週末があったりしたけれど、しばらく、と書いてあった。このしばらくってどのぐらい?一週間?二週間?ひと月?そんなことも聞けない。だって、ただの同性の……きっと俺のことを弟ぐらいにしか見えていない護さんにこんなこと聞いたらまた『重い』だなんて冗談でも言われるのは嫌だ。ずっと変わらない。相変わらず、あの日の続きの言葉も、裕美子という女性のことも聞けていない。ナミの身体が大きくなって丈夫になっていくのとは真逆で、俺たちの関係は全く変わらない。きっと護さんは異性愛者だから、仕方がない。俺とは違う人間なのだ。だからこそ俺に構ってくれている。虚しさを紛らす安堵とともに日々を過ごす。俺は畳の上でそのままナミとともに眠ってしまい、身体の痛みで起きることになってしまった。やっぱり、俺と護さんはどこまでも立場が違いすぎる。部下を持つ苦労も会社での大変さも俺には分からないこと。俺なんてハンドメイド作家なんて名前だけみたいなもので、ほとんどニートみたいなものだ。ナミがいなければ俺の生活は相変わらず堕落の一途をたどるだけだっただろう。ああ、だめだ。このまま家にいると沈む一方だ。
「散歩行こうか」
「わん!」
随分とクールな表情をすることが増えて後ろを付いてくることが減ったナミだけれど、散歩の一言には変わらないキラキラとした顔をするし、ウミたちのところに行くと大人しく座っているのも変わっていないことに安心する。いつもの土曜日なら護さんが来てくれたけれど、明日も来ないんだと思うと落胆の気持ちがあふれてため息をひとつ吐いた。15時でも冷え込む時期になって厚手のクリーム色のカーディガンを着て外に出て……身体が固まる。玄関を出た先の門に立ち竦む姿に風を浴びたときよりも身体が冷えて勝手に震えた。
俺の反応に気付いたナミがう”ーーーと唸る。そんな俺たちの反応なんてどうでもいいかのように深紅のスカートを舞わせて俺に一歩、茶色のパンプスを響かせて近寄ってくる。無理矢理パーマをかけた……俺とよく似た顔の少女の姿。良く知った、華奢で守ってあげたくなるような可愛らしさの皮を被った恐ろしい子。
「見ーつけた」
とろりと頬を歪ませる。少女は本当に嬉しそうに不気味なほどに美しくて、怖い。
「おにいちゃん」
恍惚とした顔でつるりとした唇を動かす。また俺に近寄ろうとするのをナミが「ワン、ワンワン!!」警戒心むき出して吠えた後、牙をむき出しにして威嚇する。すると楽しそうな笑みが消え失せて冷たくナミを見下ろす彼女の変化に気が付いてその大きくなった身体を抱き上げて急ぎ、扉を閉めた。ナミが戸惑った様子を見せるが気遣う余裕もなく鍵をかけた。
「開けてよ。おにいちゃん。私だよ、理香だよ。会いたかったの。お兄ちゃんも会いたかったよね?開けてよ。開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて開けて。開けろよ!おい!!」
語りかけるような声はだんだん語気が強くなり、扉を叩く音も最初は控えめだったのに平手でバンバンと叩きつけるようにする豹変に、恐怖でいっぱいになる頭の中で相変わらずなにも変わっていないなと呟いた。
「きゅーん……」
「だいじょうぶ、だいじょうぶだよ、ナミ……ごめん、おさんぽ、いけないや」
ふわふわな毛に顔を埋めて俺はナミに謝るばかりだった。今が夏の時期じゃなくてよかった。全部戸締りしている。そうじゃなかったら俺とよく似た少女……理香は、家に入り込んでナミにどんな危害を加えていたのか。想像もしたくなかった。バンバンバン、高くて濁った怒鳴り声と小さな手が力の限り玄関の戸を叩く音が永遠のように続いて、俺はただ目の前の暖かな存在を抱きしめて耐えることしかできなかった。俺でも助けることができた、尊い存在。いつの間にかこんなにナミといることが俺の救いになっていたことに今気付いた。
「……、聞こえなくなった……?」
「きゅうん……」
いつの間にか理香は外からいなくなっていたようだったけれど、どこにいるか分からないあの子に怯えて結局確認することはおろかその日外に出ることが出来なかった。散歩が好きなナミは不満に思っているだろうか。ストレスを与えてしまったことが申し訳なくて、ただただ俺の顔を心配そうに見ているナミに謝りながらそのたびに抱きしめたり身体を撫でる。少しだけ、気持ちを落ち着かせることができたけれど、変わらない理香の様子にぞっと鳥肌が立つ。
「あ」
パキン、音を立てて針金が切れてパラリと机に落ちた。俺の声に反応した足元にいるナミが驚いたように起き上がりこちらを見てきて「大丈夫だよ」と声をかけてもまだ純粋無垢な瞳が俺を映していたけれど、いたたまれなくて見ないふりをして、またペンチと針金を睨む。
気を紛らわしたくて無心になろうとハンドメイドをしようと机に向かったまでは良かったが、ペンチを握る手が震えて力加減を間違えてぱっきりと折れてしまうの繰り返しで心が乱れてどうしようもなくなってやりきれない気持ちのまま俺はスマホを取り出した。ほとんど無意識のことだった。今の俺にとって一番頼りになる……護さんに通話ボタンを押していたのは。着信音が鳴ったところでハッとした。
(馬鹿だ……!)
どうせ出ない。足元で目を閉じるナミを見た後時計を見ればいつの間にか21時を指していて、忙しくて明日も来れないと護さんにこんな時間に電話をかけるだなんて迷惑だろう。家に帰ってひと段落着いたころかもしれない、遅めの夕食をとっているかもしれない。……彼女と、会っているかもしれない。
(嫉妬だなんて、俺がする資格なんてない)
独占欲が現れる自分を恥じて、首を振って切ろうとした。後でメッセージで間違えて電話をかけてしまったとでも送ろう。スマホから顔を離そうとした。
プツリと音が聞こえたと同時に『もしもし』と電話越しだからか低く聞こえるけれど、恋するその人の声が鼓膜を揺らして、理香と再会したときとはまた違う意味で身体が震える。
「護、さん」
『どうした?』
「……っ」
『理一?』
その声に酷く安心して、涙がじわりと零れる。嗚咽を漏らさないように口を抑え衝動に耐え『なんでもないです』と言おうとした。心配そうに俺の名前を呼んでくれた。それだけで充分だと思った。これからもきっと頑張れる。そう思った。そう思ったのは、本当なんだ。
『まもるう、どうしたのお?』
『おま、裕美子、黙ってろ!』
「――……」
女性の高く甘い声が護さんの名前を親し気に呼ぶ声が聞こえた後に護さんが呼んだ名前に一気に頭が冷えた。あの日電話をかけた『裕美子』さんという女性と一緒にいる。そう分かった瞬間、何も考えずとも言葉が零れ落ちる。
「なんでも、ないです」
『ちょ、違うんだ!りい……』
「邪魔して、ごめんなさい」
護さんが何か言おうとしていたけれど、これ以上傷つくことを恐れて無理矢理通話を切ってスマホの電源を切った。何度か通知音が響いていた気がしたけれど聞こえないことにした。
「……」
涙は、不思議と出てこなかった。防衛本能が働いてくれたおかげだろうか。それとも、諦めを学んだからだろうか。どちらにしても俺が傷つかないようにするための術を行使した。
分かっていたことじゃないか。傷だらけの腕をぎゅっと抱きしめる。
(どう思われてしまっただろうか。突然電話をかけてきておいてすぐに切って。俺のことを心配してくれたのに。今怒っているのかな。もう、ここには来てくれないのかな)
「くうん、きゅーん、きゅん」
「……俺のせいでごめんね、ナミ」
悲しそうに鳴いているナミと目線が同じになるように椅子から降りてそのまま寝転び、テーブルの下に潜り込む。ペロペロと傷を癒すように頬を舐めてくる優しいナミに申し訳なく感じた。体力のない俺よりも護さんと散歩する方が楽しかっただろうに。今日の俺の行動で、もう護さんが来てくれないかもしれない。そう考えるとどんどん気持ちが落ち込んでいく。ごろりと仰向けになると視界はテーブルの裏側だけになる。
(俺が女の子だったら。もしくは異性愛者なら。理香が見た目通りの性格だったのなら)
俺は幸せになれたのかな。ああ、でも。その幸せだとしたら、ナミと暮らすことになることも、護さんと出会うこともないのだとしたら……今の俺の価値観からすると、不幸かもしれないや。
とりとめのないことを考えながら目を閉じる。どうしようもないどこまでも追いかけてくる現実から少しでいいから逃げたくなった。
――ピンポーン。
「……ん……?ふぁ、くっしゅん!」
「わんっ!」
響くインターフォンの音によって意識が浮上したと同時にくしゃみをした。どちらの音に驚いたのか分からないけれどナミがむくりと起き上がって一度吠えたあと、チャチャチャと玄関へと走っていく。俺は意識が覚醒しきれていないままナミの後を追いかけた。何故外に出れなかったことも忘れ、玄関を開けろと立ち上がり前足をカリカリと引っ掻くその姿に微笑ましく感じながら、戸を開ける。
「わうん、わんわん!」
「おーナミ。今日もふさふさだなあ」
玄関先にいたその人物にナミは警戒心などなくぴょんっと飛び出し、ふんふんと鼻を鳴らしながら地面に転がってお腹を見せ、わしわしと男らしい手が無防備なふわふわな毛で覆われているところも覆われていないところも撫でまわすのをぼんやりと眺める。
(あれ。護さんがいる)
暫く来ることができないと言っていたのに。なぜかスーツを着た護さんがここにいる。
「あれ、今日、というかしばらく来れないんじゃ……?」
「うーん……ほら、今の時間見て見ろ」
「時間……?」
どこかの海の景色のスマホのロック画面。その真ん中に堂々と書いてあるのは今現在の時間。誰のスマホの画面なのかも考えつかないまま、言われるがままに表示されている時刻をぼーっと眺める。
『22:47』と出ているそれ。ただの数字の羅列だと最初は思った。なんの数字だろうとまじまじと見て、今さっき言われた『時間』という単語を思い出し……ハッとする。
「あっ」
ただの数字じゃない。今の時間を指している。もう日付が変わるまで1時間と少ししかないぐらい遅い時間で今日はまだ土曜日じゃない。辺りを見れば真っ暗で朝すら来ていないことが分かる。ずっとナミと護さんしか見えてなかった。そんな自分が恥ずかしいと思うよりも先に、さあっと青ざめた。指先が寒さとは違う理由で冷たくなるのが分かる。だって、俺は、勝手に電話しておいて、女性の声が聞こえて気が動転して、勝手に切った。それを思い出してしまった。顔色が変わった俺に護さんは色々察したようでゆっくりと立ち上がり俺の正面にやってきた。
「俺は今から行くってメッセージで伝えていたけれどな。まあ、見ていないのを知ってて、勝手に来たんだけどよ。寝てたのか?じゃあ、悪いことしたな。つい、気になって来ちまったんだわ。俺、理一の話を聞きたいんだ。電話してくれた理由を、あんな声を出していた理由を、聞きたい」
「えっと、あの」
「何かあった……んだよな」
手を握られてもはや疑問ではなく確信の問いかけに、身体が震える。その手に縋るように両手をぎゅっと握る。俺の手は情けなく細いのに、護さんの手は頼もしく太くて暖かった。なぜか泣きたくなる。
「ごめ、んなさい。おれ、そんな、邪魔なんてつもりじゃなくて……」
「……俺からも、色々言いたいことあるんだ。中に入ってもいいか?」
「っ、は、い」
何を話せばいいのか。分からくなった俺は護さんからの提案に何も考えずに頷いた。
チャッチャッチャ。ナミのご機嫌なステップだけが聞こえ、俺たちは無言で廊下を歩く。後ろから聞こえる護さんの足音は何度も来ているから足取りに迷いも躊躇いない。今のこの家の主である俺が一番、ここから逃げたくなる。
ナミは居間に着くといつも通りのクッションにころんと転がってすぐに寝息を立ててしまった。間にいてほしかったのに護さんが来たからもう大丈夫だと思ったのか普通に眠たかったのか、とにかくナミは夢の中へと旅立ってしまった。
「……」
「……」
ちゃぶ台の前にふたり対面するように座り、そのまま気まずい沈黙が流れる。生憎今日はテレビも付けておらず、夜であることも相まって酷く静かだった。心臓はバクバクだったけれども。
(……暖かいお茶を出した方がいいかな)
行動していないと落ち着かなくて、俺の電話のせいでこんな寒い時間にここまで来てくれたのだからお茶ぐらい用意しないと、と誰にしているのか分からない言い訳をして立ち上がろうとした。けれども、強く腕を引かれバランスを崩し、ぎゅうっと抱き込まれる。厚い胸の感触。
「!」
「……とりあえず、倒れているとかじゃなくて安心した。理一、すごい苦しそうな声を出すから、体調が悪かったんじゃないかって。連絡しても出ないし、返信もないし」
「っ、ごめんなさい」
「いい。……変に気を使わせたみたいで、悪い」
耳元で聞こえる低い声、微かに香る煙草とコーヒーの香り、スーツの硬い感触と伝わる熱に頭がくらくらする。
やめてほしい。
勘違いしてしまいたくなる。
けれど、拒絶なんてできない。だって、俺は、護さんが好きだから。
護さんが俺のことをそう思っていなくとも好きな人から抱きしめられると嬉しくてたまらない。こんな状況でも心臓が勝手に鳴って護さんに聞こえないか心配になった。
少ししてすっと身体を放されて少しだけ熱が恋しくなるけれど、少し怖いぐらいの真剣な表情でこちらを見る護さんにまたドキドキする。至近距離の護さんの顔につい顔が熱くなるけれどその空気が目を逸らすことを許されない。ただ護さんの言葉を待った。
「まず、説明させてくれ。さっきまで一緒にいた女の声は裕美子っていうやつなんだが……あいつとは何でもない。彼女とかじゃない」
「彼女じゃない……?」
「ああ」
護さんの言葉をオウム返しのように問いかけると強く頷かれる。決して、護さんの言葉を信用していないわけじゃない。嘘だなんて思わない。でも、電話越しから聞こえた裕美子さんの声が彼氏でも何でもない人にしては随分と甘く媚びるように護さんの名前を呼んでいたこと、遅い時間に二人でいたことから、恋人関係ではなくともそれに近しいものではないかと邪推してしまう。そんな俺の考えを読み取ったように護さんは重いため息を吐いて、心底嫌そうに唇をこじ開けて細かく説明をしようと決めたような顔をした。
「いや。正確に言うと『もう』なんでもない奴、か。……俺の元婚約者だ」
「!婚約者……」
「違う。元、だ。元。今は全然違うから。今はもう赤の他人。俺の気持ちはもう無い。そこは間違えないでくれ、頼むから」
「は、はあ、わかりました……?」
まさかの単語に驚く俺に、両肩を掴んであまりに必死に『元』を強調してくる護さんの迫力に負け、つい頷いた。とにかく、今は関係ないというのは伝わってきた。少なくとも、護さんからは。裕美子さんの方はそうでもなさそうだったけれど……説明してくれるとそう言ってくれたので、怖いけれど聞く。このままじゃもやもやした気持ちが残ったままになりそうで、こんな気持ちでは多分、お互いにもう一緒にいられない気がした。
「でも、どうして?さっき、護さんのことを親し気に呼んでいましたよね。あと、あんな時間で二人で……?」
あ、なんか重いかも。そう思ったのは言葉にした後のこと。護さんとは兄弟でもそういう関係でもないのにこんなこと聞くなんて。浮気を問い質している女々しい人のような自分に引いた。
「……」
俺の変な質問に護さんは目を泳がせて言いあぐねる様子を見せる。でもそれは俺を軽蔑しているでも引いているわけでもなく、どう答えたらいいものかと考えているようだった。少しすると整理がついたのか口を開いてくれた。
「あーそれはな……ちょっと長い話になるんだが、いいか?」
「は、はい」
護さんの話ならいくらでも聞きたい。俺の返事に一度うーんと唸って、護さんはぽつりぽつりと話し始める。
「もう一年前の話になるのか。去年の夏ぐらいから婚約していたにも関わらず、浮気してたんだよ。しかもあっちは不倫。そのことを責めた俺のことを身長も器も心も狭い男だなんて罵ってくれた挙句、浮気相手の方が好きだとか言いやがって……」
「浮気、ですか……」
「ああ。丁度このぐらいの時期だったか……両家顔合わせも終えていたのに、仕事が忙しいとかいって会えなくなって。何か雰囲気も前よりも明るくなって派手な格好が増えて怪しいと思ってたら友達が知らない男とホテルに入っていくのを見た、と言われてな。問い詰めたらあっさりと認めて、あっちから婚約破棄を申し出てきた。どうやら、浮気相手は金持ちだったみたいで慰謝料をぽんと貰ってそんでお終い。まあ、ここ何か月前から連絡がまた来るようになってなんか色々話していたが、まあ今浮気相手との家族と上手くいっていないから俺とやり直そうと縋ってきててな。さっき一緒にいたのはいい加減ケリをつけたくて友達を交えて三人で話してた。だから二人きりでもなかったんだよ。既成事実でも作りそうな勢いだったからその対策としてな」
「そう、だったんですね」
知りたかったことのすべてを護さんがすらすらと答えてくれる。そういえば護さんは裕美子さんに対して冷たかったことを思い出した。電話では分からなかったけれど他にも誰かがいて決して二人きりではなかった。そのことが分かって心底安心した。諦めることには慣れていても、好んでいるわけじゃない。俺はその説明に安心したけれど、護さんの様子が少し違っていた。笑っているけれど笑っていないような、そんな顔。
「情けねえ男だよな。浮気相手に嗤われたよ。女ひとりも捕まえておけないつまらなくて情けない男ってさ。浮気した方が絶対に悪い。そう思っていたが……実際されてみると、なんだろうな。プライドが傷つけられた?っていうんかね。俺にも原因があったのかな、て思うこともあったんだ」
少しの沈黙の後悲しそうに力なく笑う護さんの手を握って、首を振って否定した。
「そんなことない!護さんは悪いことなんてしてない、悪いのは浮気した方だ!」
あまりに必死な声だった。自分のことなのに俺が驚いてしまった。でも、本音だから目を離さない。護さんの何が嫌なのか俺には分からない。まだ出会って半年も経っていないから見えていないところもあるのかもしれない。それでも、結局悪いのは浮気した方であって、護さんに落ち度があるようには到底見えなかった。
護さんも突然大声を張り上げた俺を目を見開いていたけれど、赤い顔のままそれでも真剣だと伝わってほしいと訴える視線をどう受け取ったのか、少ししてふにゃりと笑う。
「……ありがとうな」
その笑い顔は少しだけ幼く見えた。
「そんな、話し合いの中で電話をして、ごめんなさい」
「話し合いも終盤だったから気にすんな。いつまでも帰らないあいつに疲弊していたし……」
またひとつため息を零した。心底不愉快そうな、嫌そうなそんな雰囲気。
「護さんは、裕美子さん?に未練は無かったんですか?婚約まで、していた仲だったんですよね。落ち込んだ、んじゃないんですか?」
いくら浮気をされたとはいえ、俺みたいに引き摺ってしまう人間もいる。名前を出すことすらしんどくて、でも憎むまではまだいけていない俺にとってあまりに護さんが忌々しそうにしているのが、少しだけ疑問だった。浮気は許せないし別れることを選ぶとは思うけれど、切り捨てることはまだできそうにない俺からすると護さんがとても強い人に思えてつい質問してしまった。聞きようによってはとても失礼なことだったのに、護さんはどこまでも真摯に答えてくれた。
「うーん……確かに凹んだし落ち込んで食事も喉を通らなかったぐらいだったんだが……それは裏切られたショックや、正直、浮気に気付いた地点でもう愛情は消え失せてたからな。もしも、浮気と問い詰めたときに縋られても切り捨てられたと思う」
「そうなんですね」
そのあっさりとした返答に護さんはやっぱり俺とは違う強い人なんだなあ、とつい感心してしまう俺に何故か言い淀む様子を見せてくる彼に首を傾げた。
「あー……うん。理一なら話してもいいか」
「?」
「俺な、父子家庭なんだ。物心ついたときには母親はいなかった」
「えっ」
「まあ、祖父母と一緒に暮らしていたから男手一つで育てられたわけではないんだけどな。片親の苦労みたいなのはあまり感じなかった。たまに同級生とか先生からからかわれることがあったが、あんまり気にならなかったよ。祖父母も親父もちゃんと俺を育ててくれたからな。高校生になってから親父に母親がいない理由を教えてもらった。
まだ一人で歩くこともできない俺を置いて、どっかの男と駆け落ちして行方不明になったんだと。
……高校生になった俺に「私がお母さんよ、会いたかった」と痩せこけた虚ろな目をした女が腕を広げて会ったことを親父に伝えて暫くしてから教えてもらったことだ。
親父は俺の結婚が無かったことよりも変な女に引っかかる己の遺伝子をしっかり受け継いだ俺を悲しんでたな……」
「……」
俺は護さんの過去の話を聞いて何も言えなかった。無言になってしまった俺の頬を撫でながらぽつりと零してくれた。俺はじっと見つめて続きを待った。
「今思えば……俺は母親がいない理由を聞いたときから、女に対して苦手意識を覚えていたのかもしれない。裕美子とは社会人になってから知り合って付き合いだしたけれど、嫌いじゃないけれど好きでもなかった。付き合いたいと言われたからそうした。結婚したいと言われたから結婚しようと思った。そのぐらいの感覚だったんだ。もしかしたら、そんな心無い態度があいつを浮気に走らせた理由のひとつだったのかもしれない。さっきもそのことを責められていたんだ」
「それでも、浮気をして、罵って、自分のしたことを棚上げに復縁を迫るようなことは、してはいけないと思います」
「ああ、俺もそう思うよ。まず話し合いだよな。まさかそんな母親と似た女だっただんんて見抜けなかったことが一番落ち込んだんだが……でも、理一が俺と同じ価値観で嬉しいな」
「俺も」
「ん?」
「俺も、浮気された側、でしたから……」
価値観が同じなのは当然だ。だって、俺も護さんと同じように浮気された立場の人間だったから。言いたいことも自分のことが情けなくなることも、浮気をされたから別れを切り出したのに未練がましくされる不思議と鬱陶しさも、全部じゃなくても理解できる。誰かに話したいと思わなかったし、そんな親しい人も俺にはいなかったから、このことを言ったのは3年ぶりになるのだろうか。もう3年も経っているに今も変わらずに覚えている。脳にも、身体にも、刻み込まれたこと。