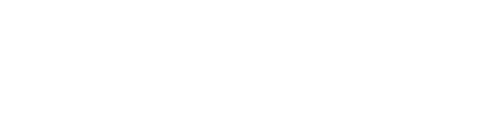つもり、つもり、あいがふりつもり
煙草とライターを胸ポケットに入れたことを確認し、コンビニで買った缶コーヒーを片手に車を降りるとべたついた潮風が俺の皮膚を撫でる。防波堤に近づいて缶コーヒーを置いて肘をコンクリートに乗せれば水平線が視界いっぱいに広がる。生憎梅雨の時期らしく晴天とは言い難い天候なため、求めている青なんてものは無い。だが、俺が求めているのは鮮やかな青でも曇天の下の薄暗い灰色でもなかった。今の俺にとってただの風景でしかない。
どんな天気だろうとどんな場所であろうとそれら全ては『彼』を引き立てるものとしか考えていない。
(よかった。今日もいたな)
安堵とともに今日も感動した。歩くたびにパーマのかかった赤茶色の髪をふわふわと揺らす『彼』の今日の恰好は長めの淡い水色のカーディガンとは逆に下は黒のスキニージーンズと赤いシューズ。
一歩一歩砂浜を軽やかに踏んでいく『彼』の顔は正直遠目からでは分からないが、すっと伸びた背筋やカーディガンが風にあおられるたびに見える凹凸のない胴体に、細く長い脚に横からでも分かる高い鼻と形のいい唇に、勝手に『彼』がイケメンの類だろうと想像している。
時折自分のつけた足跡を確認するように振り返る姿さえ様になった。
(相変わらず絵になるな)
海を眺めるふりをして『彼』を見ながら、煙草を咥えて火を点ける。煙を吸ってゆっくりと吐き出してからコーヒーに口をつける。
彼を見つけたのは半年前、新しい趣味にドライブを組み込んで暫くしてのこと。ふと海に行こうかという思いつきだった。まだ年が明けたばかりの寒い時期だった。オフシーズンの海なんて行ったことがなかったし、あることが理由で鬱屈するようなことばかりだったから解放感を味わいたかった。これで吹っ切れるかもしれないと心の底ではそう思っていたのかもしれない。おすすめの海をまずスマホで調べて出てきたのはここではない少し離れた海水浴場だった。カーナビに住所を打ち込んで案内のままに走らせて1時間半ほどでその辺りに着いたのだが、車の窓から見える青い海を何となくもう少し見たくなって車を走らせればふと何も止められていない素っ気ない駐車場を見つけてここで海でも眺めようかと車から降りた。穏やかな天気とは真逆の気温とともに底冷えするような波風が容赦なく肌を刺して来たことですぐに暖かい空調のきいた車に入りたくなったが、せっかくここまで来たのだから、と海を覗き込んだ。つもりだった。
寒さなんてものともせずに、堂々と砂浜を歩いている『彼』を見たのだ。『彼』からするとただ普通に散歩しているだけに過ぎないのかもしれないけれど、どういうことか俺の目にはとても美しいものに映った。輝く青の海も目が覚めるような空も、彼の装飾品にしか思えなくなったのだ。伸びた背筋が風格を表しているようにも、華奢な肩が寂し気にも映る。はっきりと顔も見えていないのに、服が汚れるかもしれないとも靴が濡れるかもしれないことも考えずに砂浜を歩き、足跡を作っていく『彼』の姿が美しいと思った。
それからの俺は出来る限り初めて見たときと同じ15時頃にここに着くよう努力した。何度か同じ時間に着いて覗き込むとまるで示し合わせたかのように『彼』は砂浜で足跡をつけていたのだから、午後15時前後にはここにいると分かったからだ。16時になったら確実にいない。……なんだか、ストーカーみたいだが、断じて違う。綺麗だと思うものを見たいと努力するのは普通だろ。
煙草一本が吸い終わりポケット灰皿に吸い殻共々突っ込み、残ったコーヒーを飲み干して車に戻り発進させる。最後まで眺めていたいのが本音だが、俺という存在を『彼』に認知されたくなかった。変な目的なんて無くとも毎週散歩しているところを見ていたのだと知られたら、怖がられるだろう。平穏を壊したいわけじゃない。俺も自然体の彼を見たい。知られるべきではないと分かっている。だから、煙草一本吸い終わったらお終い。
勝手にそんなルールをつけている俺は気持ち悪いのだろう。ストーカーではないけれど、一歩手前まで来ているような気がしているのを、見て見ないふりをして今日も誤魔化した。
一度、同僚に性別を言わずにこのことを話してみた。まるで恋でもしているようじゃないか、声をかけてみればと笑われ茶化されたが、そんなつもりは毛頭ない。関わるつもりなんてない。ただ、見ていたいだけだ。
スマホに映る美しい画像の数々がある。俺にとって砂浜を歩く『彼』の姿がそれなだけだ。スマホに映る画像のつもりでしかない。今もこれからも。スマホの画像の『彼』と、スマホ越しに見る俺は交わることはない。
俺は自分の家へと真っすぐに帰った。
仕事して上司との付き合いで興味もないキャバクラに行って二日酔いに苦しめられたり、理不尽なクレームに追われているうちに雨の多い時期が終わり、カラッとした暑さがこれでもかと増していく時期になった。ここ数年過去最高記録を更新し続けている夏にうんざりしながらもあの海へと向かう。車から出た瞬間から襲ってくる熱気に車内に戻りたくなるのを堪えた。さすがにこの暑さで火を見たくなくて煙草とライターを車内に置いて、コンビニのアイスコーヒー片手にコンクリートで出来た防波堤に触れず『彼』の姿を探した。……のだが。
「……今日は、いないのか」
午後15時ぴったりにも関わらず『彼』の姿らしき存在はどうやっても見当たらない。いや、状況が変わっているせいだろうか。以前なら『彼』とせいぜい遠くでサーフィンを趣味にしている人ぐらいしかいなかった浜辺には夏が始まったとは思えないほどの暑さに耐えかねてか海開きには少し早い7月上旬にも関わらず、それなりの人で賑わっていた。ついにオンシーズンの訪れである。いつもよりも足跡の多い砂浜にげんなりする。ここで『彼』を見つけたところでもう自分だけしか知らない『彼』ではなくなってしまったのだという少し冷めた感情が生まれてしまった。随分勝手なことを考えていると自分でも思う。……というか、そもそも、俺は名前どころか『彼』のことを正面から見たこともない、赤の他人だ。
「別の楽しみを見つけるべきだな」
冷めたことでのぼせていた頭もクリアになって今まで自分がしていたことは犯罪ではないにしても、結構やばいことをしていたのではないか、通報されるよりも前に気付くことが出来てよかった。炎天下にも関わらず冷や汗が出た。本当に『彼』に気付かれなくてよかった。同性とはいえ観察されているだなんてすぐにSNSに上げられて特定されて…………うん、考えるのはやめよう。とりあえず帰ろう。きっともうここに来ることは無いだろう。よくほぼ毎週1時間半かけてここに来たもんだと変に感心してしまう。今度は山……いや、温泉もいいかもしれない。独り身なのだから金はそれなりにあるんだ。ドライブ以外のことにも目を向けるのも良い頃合いだろう。
あれだけ熱をあげていた『彼』のことを忘れ、すぐに切り替えて次どこに行くかを考えながら車のドアを開ける。
「っは、はあ、ハアッ!」
「!」
突然、駐車場のところまで駆け上がり息を切らしている青年が現れた。肩で息をしながら周囲を見回す青年のことを周囲は怪訝そうにしていた。不審者かと遠目から青年を眺めていると、その腕の中に大事に抱え込んでいる存在に気付く。
「その子、きみの飼っている子?」
「いえっ、ちがいます……」
問いかけておいて何だけれど、飼っているわけではないと分かっていた。青年の腕の中にいる存在……ずぶぬれで汚れなのか真黒になっている子犬が「クゥ……キュウ、ン」と波にもかき消されそうな声で鳴いている。
「段ボールの中に……動いていたのは、この子だけ、で」
「とりあえず、病院行こう。乗ってくれ」
「!ありがとう、ございますっ」
声を詰まらせながら状況を訴えてくる青年に俺の車に乗るよう指示すると迷いなく助手席に乗った。ここで俺が極悪人だったらどうするんだと一瞬思ったが、そんなことよりも小さな命を救うことが最優先なのは俺も青年も同じだ。青年は車に乗ると自分の来ていた淡い水色の上着を汚れることも構わずに子犬包んでゴシゴシと水滴を落として温めるために抱きしめるの繰り返しをしていた。俺は付けていた冷房を暖房に変えながら土日もやっている近くにある動物病院をスマートフォンで調べるがどこも予約でいっぱいでとにかくしらみつぶしに電話をかけて何とかひとつ「今から来なさい」と診てもらえるところを見つけ、カーナビに入力して車を発進させた。
「大丈夫、大丈夫だからね、がんばって。おねがい、もうすこしだからね、がんばって」
青年は何度も何度もそう言った。狭い車内では小さい声でもよく聞こえた。その言葉は子犬に向けてというよりは、自分自身へ向けているように聞こえた。
炎天下の中の車内は何もしなくても暑いのに子犬を温めるために暖房を入れていたために自分たちの方が脱水症状になりそうだったことを獣医に叱られながらも診断が続く。どのぐらい経っていたのかよく覚えていない。ただただ間近にある小さな生命が助かるのかどうかばかり気になっていた。それは隣で座っている青年も同じだったろう。永遠ともいえる長い時間、待合室にいた俺たちを受け付けの女性が呼び、緊張しながら診察室へ入った。そこには診察台で目を閉じている先ほどの子犬の姿で、間に合わなかったのかと腹の底が冷えた。
「……うん。暫く入院は必要だけれど、命は無事だよ」
白髪交じりの男性の言葉が一瞬理解できずに固まり、目を凝らしてみるとぐったりとしたままの子犬の膨らみのある腹が上下に動いていることが確認できたことで、やっと獣医の言葉に肩の力を抜くことができた。
「……はあーーーー……」
「よ、よかったああ……」
深く安堵のため息を吐いたのとほぼ同時に隣の青年が今にも泣き出しそうな声でこう言った。最初に子犬を見つけた青年が一番気が気ではない状態だっただろう。
「良かったな……」
「はいっ、よかった、ほんとうに……よかったあ、ぐず」
俺の言葉に反応した青年の方から鼻を啜るような音がしていて、実際泣いていたのかもしれない。ただただ小さな生命が目の前で助かったのだという感動と安堵に子犬から目を離すことができず、青年の方を見ることができなかったので確認はできなかったが。
「この子どこにいたの?」
「……海の、防波堤に上る階段の近くで……段ボールがあって何だろうと思ったら、少し動いていたように見えて、確認したら押し込まれるように数匹いて……動いていたのはこの子だけ、でした」
「そっか……酷いことをする人がいるね。きみのおかげでこの子は助かったんだよ、よかったよ」
獣医は悲しそうに眉を顰めた後、青年の肩にぽんと手を乗せて優しく微笑みかけたことで今度こそ青年は泣いた。それを俺はただ見ていることしかできなかった。
会計で俺は目を剥いたが青年はあっさりと支払いを終えて外に出た。外はまだ明るかったが、スマートフォンを見ると17時になっていた。青年に向けて家まで送ろうかと声をかけようと振り向くと、こちらを戸惑いがちにでも真剣な表情で見ていた。それを見て何となく、俺に何か頼もうとしていることと、その頼もうとしている内容が何となく察した。
「あの」
「うん」
「厚かましいお願いなのですが……海に戻っていただいてもよろしいでしょうか」
「他の子犬たちのところか?」
「はい。せめて、埋めてあげたいんです」
「分かった。行こう」
「えっ」
二つ返事でまるで言われたことが分かったように了承する俺こそ青年にとって予想外だったのか、頼んだ本人が躊躇っているのが少し笑えた。
「この流れで俺に頼みたいことなんて察しが付くだろ。ほら、乗りなよ」
「!ありがとうございます」
パッと笑う顔は花のようで、見惚れそうになるのを抑えて車に乗り込んだ。
この後、海に戻り青年は階段を下りすぐに戻ってきた。一度濡れて乾いたせいか皺のよった段ボールを抱えて。
「あの子たちは、俺の家の庭に埋めようと思うんです」
「じゃあ家まで送っていくよ」
「え、いえ、そこまでは……」
移動中青年がそう言った。そして酷く遠慮して申し訳無さそうにしていた。俺の車の中が汚れてしまうかもしれないことと……冷たくなった犬たちの臭いのことを気にしてのことだろうか。そんなこと、気を使わなくていいんだ。
「俺がそうしたいから。最後まで見送らせてほしい」
汚れたなら拭けばいい、臭いが残るのなら換気すればいい。それでも取れなければシートを変えるなり、車ごと買い換えればすればいいだけのことだ。車は値段さえ気にしなければいくらでも替えが聞く。だが、亡くなった生命たちは替えのきかないものだ。何よりも優先されるべきものだろう。
そもそも、青年がいつも着ていた水色のカーディガンを汚して生命を繋ごうと必死に行動に出なければ俺は近くで死んでいく子犬たちのことに気付くこともできなかったのだから。その罪に比べれば大したことなんて無い。青年は俺の言葉に少しの間を置いた後小さく頷いた。
車の中で青年は段ボールを大事に抱え込んだ。青年の自宅は海からそう遠くないところにあった。着いてすぐに庭へと向かいスコップを借りて隅に穴を掘っていく。既に冷たくなって結構な時間が経っているせいか、酷い異臭を放ち虫の集る小さな身体を一匹一匹を抱いた後俺の掘った穴にそれぞれ入れ、埋葬した。
「……」
三匹目の子も埋め終えて二人で手を合わせた。少しして目を開けると青年は静かに手を合わせたままなので、そっと立ち上がり数歩後ずさった。そして周囲を見回した。
庭には雑草だらけの鉢植えと使われなくなって随分経っていそうな水が溜まった緑色のじょうろ。先程借りたスコップもよく見れば錆だらけで元の色が分からないほどだった。見るところまだ20代そこそこの青年にしては、木造の平屋とは言えど海に近い庭付きの一軒家に住んでいるのか少し不思議に思ったが、以前の宿主から譲ってもらったのかもしれない。診察代と入院費もあっさりと出しているところを見るに裕福な家の出なのかもしれない。なんて邪推した。
「あの」
祈りが済んだらしい青年に声をかけられて振り向く。青年はパーマがかけられている赤茶色の髪を揺らし、ペコリとお辞儀した。
「ありがとうございました。俺、車以前に免許とかなくて、あなたがいなければ見殺しにしてしまうところでした。本当に、ありがとうございます」
「いや……いいんだ。俺もきみのおかげで視野が狭いことに気付けたよ」
「視野、ですか?」
「きみが気付かなかったら、きっとあの子……いや、あの子たちは狭い段ボールに詰められたまま、いつまでも誰にも発見されないままだったろうから」
救える生命を救うことができた。救えなかった子たちもあの暗い段ボールで終わらせずにちゃんと埋葬してくれたのだ。こちらの自己満足とは言えど……かつてちゃんと生きていたあの子たちがゴミとして終わるよりは、きっと、悪くないと思うんだ。俺がそう言うと青年は涙目になったが、取り繕うようにこう言った。
「あの。俺、|門田理一《かどたりいち》と言います。あなたは?」
「|高山護《たかやままもる》だ。門田はあの子を飼うのか?」
「そうですね、拾ったのは俺ですから……ああ、そうだ。あの子のために色々買ってあげないと」
「動物は飼ったことあるのか?」
「いえ、実は無くて……これからいろいろ調べないと」
「良かったら、明日にでも一緒に見て回らないか?実家にいたとき犬を飼っていたから少しは力になれると思うから」
「!いえ、そんな、そこまでは……」
「俺がしたいから。……あ、もちろん門田が迷惑と言うなら辞めるが……」
「そんなことありません!」
「じゃあ決まりな。明日昼くらいに来る」
予想以上に強く反論されて少し驚くが、それをいいことに半ば強引に約束を取り付けた。
すると、しばらく落ち着かなそうに手を動かすが、反対要素が思いつかなかったように諦めたように動きを止めて顔を赤くした。
「なにからなにまで……本当にありがとうございます。高山さん。そうだ、連絡先交換しませんか?」
車を走らせて15分ほど経っただろうか。何度目かの青信号に潜った辺りから誤魔化すことはもうできないと察した。
ドッドッド。心臓の存在が勝手に俺に訴えかけてきて酷くやかましい。
ハンドルを握る手に汗が滲んでくるのも不愉快だった。
子犬が大丈夫だと分かったときから青年が15時頃に砂浜で散歩をしている『彼』だと気付いた。それどころではなかったから最初こそ何とも感じなかったが、徐々にその存在感に心がざわめくのが分かった。こんな状況なのになんて人間なんだと思いながらも気持ちが勝手に熱を帯びていくことにどうやって抵抗していいのか分からない。
俺から見る『彼』は、スマホに映る画像のつもりだった。交わることのない人間だと思っていた。知り合いたいなんて考えたこともなかった。
カーディガンを脱いだありのままの彼の肌は遠目で見ていたときよりも白く見えたこと。
肌には汗がにじんでいたこと。その腕には数えきれないほどの切り傷の痕があったこと。
遠くから見た横顔から想像していた顔よりも幼い顔立ちをしていること。目は大きくて少し垂れていたこと。
俺よりも身長が高くて、でも俺よりも体重がなさそうなこと。一人称が俺だということ。声は男にしては少し高めなこと。
礼儀正しかったこと。車も免許も持っていないこと。名前は門田理一ということ。
笑う顔が可愛かったこと。
全部遠くから見ていただけでは分からないことばかりだった。今日で『彼』を眺めるのはやめようと思っていたのに、まさか知り合うことになるだなんて。
助手席に今存在しているのはスマートフォン。本当に門田理一という男がさっきまでいたのかと疑問を覚えたと同時にスマートフォンが震えた。信号が赤であることを確認して画面を見た。メッセージアプリの通知と……門田理一の名前が表示されていることに、また心臓が騒がしくなる。
『今日は本当にありがとうございました。気を付けてお帰りください』
自分の身を案じる言葉に、お世辞だと思いながらも舞い上がった。なんだこれ。これじゃあ、まるで。
パアーーーー!
「!」
後ろからクラクションを鳴らされ、前を見ると信号が青になっていて焦ってアクセルを踏んだ。だが、自覚したそれをもう無視なんてできやしない。
俺も、理一も。スマホに映る画像じゃない、ただの人間であり、知り合うこともできた。
顔が熱くなるのを、窓から入ってくる温い風のせいにはできなかった。
「まじかよ……」
スマホに映る画面のつもりだったのに。まさかこんな年になってこういう気持ちになるなんて少しも想像もしてなかった。
1/4ページ