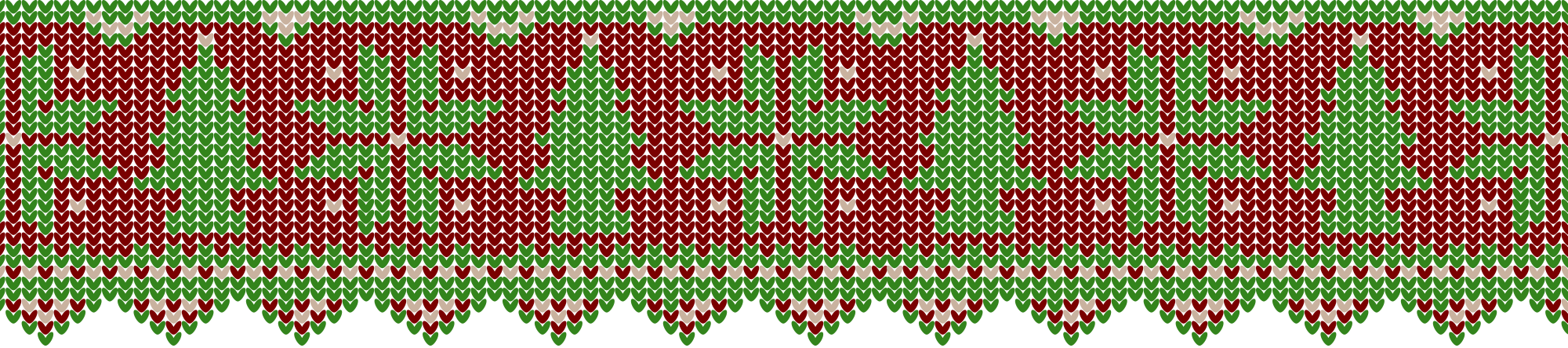アドレナリン=LOVE
ある日、降谷は、首元の不快な痒みに気が付いた。
「え、なんだ、これ」
鏡を見ると、ぷつぷつと赤い発疹が広がっている。
「…蕁麻疹?」
食べた物を思い出す。
今朝はトーストと卵。バナナも添えた。卵もバナナも怪しい。昼は蕎麦だ。これも怪しい。夕飯のグリーンカレー。怪しい。
「病院、行くか」
幸い、有給を取れ取れとせっつかれていた所だ。降谷は、珍しく、病院を受診することにした。
ところが、これが大事の始まりだった。
降谷が予約したのは当然、皮膚科だ。ちょっと塗り薬を貰いに行くだけの積りだったのだ。それが何故かあちこちの診療科をたらい回しだ。
これは降谷が悪い。以前、入院した時の術後経過観察等々を悉くサボっていたからだ。
眼科、X線検査、整形外科、形成外科。外来をぐるっと巡った頃には、時計の針はとっくに昼を回っていた。腹ペコである。
そして、何故か、最後には、総合診療科という新しい科を受診させられたのだった。
「降谷さん、血液検査の結果が出ましたが、所謂アレルギーの原因は見つけられませんでした」
総合診療科なる未知の外来科にて、降谷を診てくれたのは小児科主任の名札を下げた医師だった。
小児科?何故?降谷はれっきとした成年男性だ。否、既におっさんの部類に入る年頃だというのに。
「しかし、他の因子が発見されました」
向いに座る医師のメガネがキラリと光った。
「嘘です」
「嘘?」
何故、この医師は嘘を?降谷は首を傾げた。
「貴方は、もう一生分の嘘を吐いてしまったんです」
「………」
いや、嘘その物が因子か。なるほど。
いや、何だそれ。
一瞬、納得し掛けたが、やはりおかしい。
「は?」
「これ以上嘘を吐くことに体が拒否反応を起こしているんです」
「はぁ」
卵や蕎麦とは訳が違う。免疫反応は、そんな物に働かない。
嘘だと?嘘なんてもんは、息をする様に吐いてきた。こちとら元潜入捜査官だぞ。いや、だからこそ、もう一生分の嘘を吐いてしまったという事なのか。
「あの、じゃあ、これは、精神的な物だと?」
降谷は恐る恐る問いかけた。
何度も言うが、降谷は潜入捜査をやり遂げた男だ。メンタルの頑丈さには自信がある。
「いや、アレルギーですよ」
「へ?」
「なので、服薬と塗り薬でよくなります。勿論、嘘を吐くのはやめなくてはなりませんが、なぁに、一生嘘を吐けないわけではありません。免疫療法を始めましょう」
医者の言うことは、全く理解できなかった。
それでも、降谷は自分の体や心に不具合があるのだと納得した。だが、悲観的にはならなかった。
とにかく、自分は病気だ。まず、それを認めなくては始まらない。どうせ、病院から上司に報告される。あとは、部下にどう伝えるかだが…。
よし、部下には、このアレルギーを隠そう。
降谷は、軽い気持ちで、そう決めたのだった。
翌日からの生活は、これまで通りのようで、少し違った。
「降谷さん、お身体は大丈夫なんですか?」
そう部下に聞かれたら、いつもなら「ちょっと風邪気味だったようだ」とかなんとか誤魔化すが、これからはそうはいかない。
「通院が必要みたいだ。できるだけ、みんなに迷惑をかけない様にするよ」
申し訳ない気持ちで言ったら、部下たちはやけに張り切りだした。
これまで、先頭の自分がバリバリやる姿を見せることが使命だと感じていたが、もしかしたら、下は頼られたいと待っていたのだろうか。
少しばかり、部下の自主性を侮っていたかもしれない。
確かに、このアレルギーとの付き合い方は難しい。降谷だとて警察組織の一員だ。上には思ってもない世辞を言わなくてはならない事もある。プツプツと腹に蕁麻疹が出る。トイレでこっそり薬を塗る事もある。急に病院に駆け込むこともある。仕方ない。そうやって、やり過ごして行くしかない。そんな降谷にとって、部下たちの成長は頼もしかった。
免疫療法も始めた。
毎日、少しだけ嘘を吐くのだ。
最初は嘘とも言えない様な嘘から始めて、アレルギーへの抗体を作る。
初日の嘘は「今朝は、寝坊したよ」だった。職場では「降谷さんが珍しいですね」なんて、ほのぼのと受け取られた。当然、寝坊なんてしてない。蕁麻疹も出なかった。
ちょこちょこと冗談めいた嘘を吐く。罪のない悪戯みたいな嘘だ。誰も気付かないし、傷付かない。寧ろ、場の空気が和むことすらある。降谷の中でも、嘘に対する意識が変わってきていた。
そんなある日の事だ。
数ヶ月ぶりに、FBIの一行が日本に来ることになったのだった。
日米が携わった大規模事件の後始末のためだ。掃討作戦から一年経っても、事件は終わりが見えていない。
そうなると、当然、降谷の天敵である赤井秀一も来日する。
降谷の心中は穏やかではなかった。
だが、そんな降谷の心中は考慮されるはずもなく。
「やぁ、降谷くん」
庁舎に現れた赤井は真っ先に降谷の方へとやって来るではないか。
あんまり、真っ直ぐに突き進んでくるから、その辺の者たちが跳ね飛ばされていたほどだ。
「久しぶりだな。君の顔が見れて嬉しいよ」
「おひ、お久しぶりです」
にこぉ
降谷は不器用に笑顔を作った。
「ん?」
赤井は首を傾げた。
降谷が突っかかってこないなんて、珍しいな。とそう言いたげな表情だった。
降谷も大人だ。気に食わないからといって、いつまでもツンケンしてはいられない。ましては、相手は他国の捜査官だ。実のところ、大変お世話なってる相手だ。寧ろ、熱烈に歓迎すべきなのだ。
だが、だが。
ショック死するかもしれない。
アナフィラキシーとか言うヤツだ。
降谷はこっそりと、まだ痒くない腹を撫でた。
赤井の滞在は数ヶ月に及ぶ。らしい。
それまでは、降谷は同じ事件の担当者だ。丁寧に親切に接しなくては。
初めは降谷もそんな殊勝なことを思っていた。
「降谷くん、この目撃証言のあった町だが、都内のどの辺だろうか」
「降谷くん、関係者の話を聞きたい。案内してくれ」
「降谷くん、あの資料はどこかな?」
「降谷くん」
「降谷くん」
ところが、赤井ときたら、四六時中、朝から晩まで、なんなら、おはようからおやすみまで、降谷の近くに居るのだ。
「あーーーっっ」
ゴンっ
降谷はトイレの壁を殴った。当然、拳が痛かった。
「何だ。何なんだ。何の嫌がらせだ、あいつ」
別に以前のような蟠りがあるわけじゃない。だが、いけ好かないのも仕方がない。だいたい、何でもかんでも降谷に意見を求める理由も分からない。自分だけで解決できるだろうに。
いや、日米での誤差は無いに越したことはない。そうだ、分かってる。しかし。しかし。
「距離がクソ近いし」
毎度毎度、ピタッと寄り添われるのだ。一つの書類を見ているから仕方ない?そうかもしれない。部下たちだって「不適切です」とは言わない。しかし、こっちは肩を抱かれそうで気が気でないのだ。
どうせ、降谷が突っかかるのを待っているのだろうが。
「あの野郎」
そっちがその気なら、降谷もやりようがある。
免疫療法の餌食にしてくれる。
降谷は決めた。毎日のささやかな嘘の犠牲者は赤井にしてやろうと。
次の日から、降谷は絶妙なタイミングで赤井を騙し始めた。
初日はジャブだ。
「今朝は、どうしてもパンが食べたくなって、仕方なく買いに行きました」
嘘だ。美味しい新米を食べた。しかし、赤井に知る由はない。「ほぉ、食に拘りがあるんだな」なんて感心していた。
「昨日、うっかり洗濯を外に干したままで。帰ったら湿ってましたよ」
これも嘘だ。降谷は洗濯物を外に干さない。いつも部屋干しだ。
「乾燥機を使わないのか?意外だな」
赤井は変なところに引っかかっていた。
「昨日の店の名前?なんだったかな。うっかり忘れてしまいました」
お手頃価格でお腹いっぱいになれる嶋田屋だ。忘れてない。
「酒は辞めてます。…だ、ダイエットしてて」
うっかり本当のことを言ってしまうこともある。薬を飲み始めてから、何となく酒は止めた。嘘を付け加える為、やってもないダイエットを理由にした。ちょうどいい嘘というのも、なかなか大変だ。
そんなこんなで二週間が経った。
相変わらず赤井は降谷にべったりで、些細な嘘には気付きもしない。すっかり信じているのだ。
初めは「阿呆め、何でも信じおって」なんて、ほくそ笑んでいた降谷だが、「君はパン派だったな」とか「まだダイエットを?君は今のままで完璧だが」とか、いちいち嘘を蒸し返されるので、だんだんと胸がチクチクし始めた。
「君には、すっかり世話になってるな。今度、お礼をさせて欲しい」
そして、そのチクチクが最高潮の時に、そんなことを言われたのだった。
「いえっ、本当に、お気遣いなく」
因みに、捜査上で湧き出た案件はまだまだ解決には程遠い。礼を言うにしてもまだ早過ぎる。
「実は、もう手配してるんだ。君、明日は休みだろう?部屋に伺うよ」
「え!」
「楽しみにしていてくれ」
「え?」
な、何故?
降谷は、己のささやかな嘘が、おかしな方向に向かっているのではと、この時やっと気がついたのだった。
そして、その翌日である今日。朝の十時、赤井は本当に『今から行く』とメッセージを寄越してきた。
降谷は洗濯物を外に干した所だった。休日だけの贅沢で、お日様の元、洗濯物を乾かせる。とても気分が良かったというのに。
『困ります。僕、用事があって、外に出てますから』
そうメッセージを返したと同時にインターホンがピンポーンと鳴った。
「うっそだろ」
慌てて玄関のドアを開ける。
「おはよう、降谷くん」
そこにいたのは、にっくき赤井秀一。休日モードらしく、ラフな格好だ。Vネックの薄手のニットにジーパン。こんな私服姿は初めて見たが、なかなか似合っているではないか。
「ランドリーは奥かな?」
ぼんやりしている間に、赤井はさっさと部屋に上がってしまった。
「あ、あのっ」
それを止める間もなく、外から玄関のドアが固定された。
「へ?」
「おはようございます」
知らない男に大きな声で挨拶された。
「おはようございます」
降谷は反射的に答えた。
「玄関、養生しますねー」
玄関では作業服の男が三人、テキパキと降谷の部屋に養生シートを貼り始める。
「毛布敷きまーす」
なんで?
問いかける隙も無い。狭くて短い廊下に大きな毛布が広げられた。
「設置は十分で終わりますから」
だから、なんの?
降谷はもう何も聞かなかった。何故ならもう、既に、すぐそこに見えていたからだ。
「乾燥機付き洗濯機」
真っ白な四角い、素敵な便利家電だ。
「だから、洗濯物が乾かなかったのは、嘘なんだって…」
降谷の呟きは、搬入の大騒ぎに紛れて、誰にも聞き止められなかった。
宣言通り、ものの十分で、降谷の洗濯機は新しい乾燥機付きに取り替えられた。手際が良すぎる。多分、唯の電機屋ではないのだろう。
後には、養生テープの一片すら残されてない。
降谷は恐る恐る、洗面所を覗くと、洗濯機の前で、赤井が取扱説明書を広げているところだった。
別に、奴が洗濯するわけでもあるまいに。
「あぁ、降谷くん。色を聞くのを忘れたんだが、君なら白を選ぶと思ってね」
赤井が振り返った。
なんで、この家を知ってるんだ?とか、この洗面所の広さまで把握してる?とか、色々と引っかかるが、それはもういい。
それより、なんで、こんな…。
洗面所の隅っこに、ピカピカのドラム式洗濯機がドンと鎮座している。
洗濯機が壊れたら次はドラム式かな?なんて考えていたが、他人から贈られるのは想定してなかった。
「貴方、なんで、こんなことしたんです」
無性に腹立たしかった。
怒鳴りたいのを抑えると、声が震えた。
「なんでって、礼だと言ったが」
「こんなの、欲しいなんて言ってないです。僕は、乾燥機は使いません。たまにしか外に干せなくても、それで良いんですっ。それを楽しみに休むんですよっ」
声が荒ぶる。感情が抑えられない。
赤井といると、いつもそうだ。いつも、いつも、心が揺れてしまう。だから、会いたくなかったのに。
「だいたい、なんなんだ。お前と仲良くなった覚えはないっ。べったり側に居られるのも迷惑だ」
いつも、降谷が何かを思い悩むタイミングで声を掛けてきて、難航している捜査にもこっちが納得するまで付き添うし、食事を忘れていれば外に連れ出して…。
「お前なんか」
まだ、日本に居る。ずっと近くにくっ付いている。アメリカに帰るまで、ずっと。
一人で残される降谷の気持ちも知らずに。
「お前なんか、迷惑なんだよ。もう僕に近付かないでください。さっさとアメリカに帰れっ」
降谷は怒鳴った。久しぶり大声を出したから、喉が痛んだ。
赤井は驚いて目を見開いていた。
「降谷くん、それは、どうしたんだ」
「だからっ」
「首に発疹が出てる」
赤井の手が降谷の喉元に触れた。
「へっ?」
降谷は慌てて鏡を見た。
首から胸元まで、赤い発疹がびっしりだ。
「な、な、なんで」
「息はできるか?薬は?」
アレルギー反応だ。
嘘を吐いた?どれが嘘だった?
側にいられると迷惑と言った。
もう近付くなとも言った。
アメリカに帰れ?
「とにかく病院に連れていく。大丈夫だ、俺が付いてるから」
ぎゅっと抱き寄せられた。降谷の心臓が急激に鼓動を速めた。
これは、アレルギーの反応なのか?
かつてないほどに至近距離にいる赤井に、降谷はどう接していいのかすら、分からなくなるのだった。
「え、なんだ、これ」
鏡を見ると、ぷつぷつと赤い発疹が広がっている。
「…蕁麻疹?」
食べた物を思い出す。
今朝はトーストと卵。バナナも添えた。卵もバナナも怪しい。昼は蕎麦だ。これも怪しい。夕飯のグリーンカレー。怪しい。
「病院、行くか」
幸い、有給を取れ取れとせっつかれていた所だ。降谷は、珍しく、病院を受診することにした。
ところが、これが大事の始まりだった。
降谷が予約したのは当然、皮膚科だ。ちょっと塗り薬を貰いに行くだけの積りだったのだ。それが何故かあちこちの診療科をたらい回しだ。
これは降谷が悪い。以前、入院した時の術後経過観察等々を悉くサボっていたからだ。
眼科、X線検査、整形外科、形成外科。外来をぐるっと巡った頃には、時計の針はとっくに昼を回っていた。腹ペコである。
そして、何故か、最後には、総合診療科という新しい科を受診させられたのだった。
「降谷さん、血液検査の結果が出ましたが、所謂アレルギーの原因は見つけられませんでした」
総合診療科なる未知の外来科にて、降谷を診てくれたのは小児科主任の名札を下げた医師だった。
小児科?何故?降谷はれっきとした成年男性だ。否、既におっさんの部類に入る年頃だというのに。
「しかし、他の因子が発見されました」
向いに座る医師のメガネがキラリと光った。
「嘘です」
「嘘?」
何故、この医師は嘘を?降谷は首を傾げた。
「貴方は、もう一生分の嘘を吐いてしまったんです」
「………」
いや、嘘その物が因子か。なるほど。
いや、何だそれ。
一瞬、納得し掛けたが、やはりおかしい。
「は?」
「これ以上嘘を吐くことに体が拒否反応を起こしているんです」
「はぁ」
卵や蕎麦とは訳が違う。免疫反応は、そんな物に働かない。
嘘だと?嘘なんてもんは、息をする様に吐いてきた。こちとら元潜入捜査官だぞ。いや、だからこそ、もう一生分の嘘を吐いてしまったという事なのか。
「あの、じゃあ、これは、精神的な物だと?」
降谷は恐る恐る問いかけた。
何度も言うが、降谷は潜入捜査をやり遂げた男だ。メンタルの頑丈さには自信がある。
「いや、アレルギーですよ」
「へ?」
「なので、服薬と塗り薬でよくなります。勿論、嘘を吐くのはやめなくてはなりませんが、なぁに、一生嘘を吐けないわけではありません。免疫療法を始めましょう」
医者の言うことは、全く理解できなかった。
それでも、降谷は自分の体や心に不具合があるのだと納得した。だが、悲観的にはならなかった。
とにかく、自分は病気だ。まず、それを認めなくては始まらない。どうせ、病院から上司に報告される。あとは、部下にどう伝えるかだが…。
よし、部下には、このアレルギーを隠そう。
降谷は、軽い気持ちで、そう決めたのだった。
翌日からの生活は、これまで通りのようで、少し違った。
「降谷さん、お身体は大丈夫なんですか?」
そう部下に聞かれたら、いつもなら「ちょっと風邪気味だったようだ」とかなんとか誤魔化すが、これからはそうはいかない。
「通院が必要みたいだ。できるだけ、みんなに迷惑をかけない様にするよ」
申し訳ない気持ちで言ったら、部下たちはやけに張り切りだした。
これまで、先頭の自分がバリバリやる姿を見せることが使命だと感じていたが、もしかしたら、下は頼られたいと待っていたのだろうか。
少しばかり、部下の自主性を侮っていたかもしれない。
確かに、このアレルギーとの付き合い方は難しい。降谷だとて警察組織の一員だ。上には思ってもない世辞を言わなくてはならない事もある。プツプツと腹に蕁麻疹が出る。トイレでこっそり薬を塗る事もある。急に病院に駆け込むこともある。仕方ない。そうやって、やり過ごして行くしかない。そんな降谷にとって、部下たちの成長は頼もしかった。
免疫療法も始めた。
毎日、少しだけ嘘を吐くのだ。
最初は嘘とも言えない様な嘘から始めて、アレルギーへの抗体を作る。
初日の嘘は「今朝は、寝坊したよ」だった。職場では「降谷さんが珍しいですね」なんて、ほのぼのと受け取られた。当然、寝坊なんてしてない。蕁麻疹も出なかった。
ちょこちょこと冗談めいた嘘を吐く。罪のない悪戯みたいな嘘だ。誰も気付かないし、傷付かない。寧ろ、場の空気が和むことすらある。降谷の中でも、嘘に対する意識が変わってきていた。
そんなある日の事だ。
数ヶ月ぶりに、FBIの一行が日本に来ることになったのだった。
日米が携わった大規模事件の後始末のためだ。掃討作戦から一年経っても、事件は終わりが見えていない。
そうなると、当然、降谷の天敵である赤井秀一も来日する。
降谷の心中は穏やかではなかった。
だが、そんな降谷の心中は考慮されるはずもなく。
「やぁ、降谷くん」
庁舎に現れた赤井は真っ先に降谷の方へとやって来るではないか。
あんまり、真っ直ぐに突き進んでくるから、その辺の者たちが跳ね飛ばされていたほどだ。
「久しぶりだな。君の顔が見れて嬉しいよ」
「おひ、お久しぶりです」
にこぉ
降谷は不器用に笑顔を作った。
「ん?」
赤井は首を傾げた。
降谷が突っかかってこないなんて、珍しいな。とそう言いたげな表情だった。
降谷も大人だ。気に食わないからといって、いつまでもツンケンしてはいられない。ましては、相手は他国の捜査官だ。実のところ、大変お世話なってる相手だ。寧ろ、熱烈に歓迎すべきなのだ。
だが、だが。
ショック死するかもしれない。
アナフィラキシーとか言うヤツだ。
降谷はこっそりと、まだ痒くない腹を撫でた。
赤井の滞在は数ヶ月に及ぶ。らしい。
それまでは、降谷は同じ事件の担当者だ。丁寧に親切に接しなくては。
初めは降谷もそんな殊勝なことを思っていた。
「降谷くん、この目撃証言のあった町だが、都内のどの辺だろうか」
「降谷くん、関係者の話を聞きたい。案内してくれ」
「降谷くん、あの資料はどこかな?」
「降谷くん」
「降谷くん」
ところが、赤井ときたら、四六時中、朝から晩まで、なんなら、おはようからおやすみまで、降谷の近くに居るのだ。
「あーーーっっ」
ゴンっ
降谷はトイレの壁を殴った。当然、拳が痛かった。
「何だ。何なんだ。何の嫌がらせだ、あいつ」
別に以前のような蟠りがあるわけじゃない。だが、いけ好かないのも仕方がない。だいたい、何でもかんでも降谷に意見を求める理由も分からない。自分だけで解決できるだろうに。
いや、日米での誤差は無いに越したことはない。そうだ、分かってる。しかし。しかし。
「距離がクソ近いし」
毎度毎度、ピタッと寄り添われるのだ。一つの書類を見ているから仕方ない?そうかもしれない。部下たちだって「不適切です」とは言わない。しかし、こっちは肩を抱かれそうで気が気でないのだ。
どうせ、降谷が突っかかるのを待っているのだろうが。
「あの野郎」
そっちがその気なら、降谷もやりようがある。
免疫療法の餌食にしてくれる。
降谷は決めた。毎日のささやかな嘘の犠牲者は赤井にしてやろうと。
次の日から、降谷は絶妙なタイミングで赤井を騙し始めた。
初日はジャブだ。
「今朝は、どうしてもパンが食べたくなって、仕方なく買いに行きました」
嘘だ。美味しい新米を食べた。しかし、赤井に知る由はない。「ほぉ、食に拘りがあるんだな」なんて感心していた。
「昨日、うっかり洗濯を外に干したままで。帰ったら湿ってましたよ」
これも嘘だ。降谷は洗濯物を外に干さない。いつも部屋干しだ。
「乾燥機を使わないのか?意外だな」
赤井は変なところに引っかかっていた。
「昨日の店の名前?なんだったかな。うっかり忘れてしまいました」
お手頃価格でお腹いっぱいになれる嶋田屋だ。忘れてない。
「酒は辞めてます。…だ、ダイエットしてて」
うっかり本当のことを言ってしまうこともある。薬を飲み始めてから、何となく酒は止めた。嘘を付け加える為、やってもないダイエットを理由にした。ちょうどいい嘘というのも、なかなか大変だ。
そんなこんなで二週間が経った。
相変わらず赤井は降谷にべったりで、些細な嘘には気付きもしない。すっかり信じているのだ。
初めは「阿呆め、何でも信じおって」なんて、ほくそ笑んでいた降谷だが、「君はパン派だったな」とか「まだダイエットを?君は今のままで完璧だが」とか、いちいち嘘を蒸し返されるので、だんだんと胸がチクチクし始めた。
「君には、すっかり世話になってるな。今度、お礼をさせて欲しい」
そして、そのチクチクが最高潮の時に、そんなことを言われたのだった。
「いえっ、本当に、お気遣いなく」
因みに、捜査上で湧き出た案件はまだまだ解決には程遠い。礼を言うにしてもまだ早過ぎる。
「実は、もう手配してるんだ。君、明日は休みだろう?部屋に伺うよ」
「え!」
「楽しみにしていてくれ」
「え?」
な、何故?
降谷は、己のささやかな嘘が、おかしな方向に向かっているのではと、この時やっと気がついたのだった。
そして、その翌日である今日。朝の十時、赤井は本当に『今から行く』とメッセージを寄越してきた。
降谷は洗濯物を外に干した所だった。休日だけの贅沢で、お日様の元、洗濯物を乾かせる。とても気分が良かったというのに。
『困ります。僕、用事があって、外に出てますから』
そうメッセージを返したと同時にインターホンがピンポーンと鳴った。
「うっそだろ」
慌てて玄関のドアを開ける。
「おはよう、降谷くん」
そこにいたのは、にっくき赤井秀一。休日モードらしく、ラフな格好だ。Vネックの薄手のニットにジーパン。こんな私服姿は初めて見たが、なかなか似合っているではないか。
「ランドリーは奥かな?」
ぼんやりしている間に、赤井はさっさと部屋に上がってしまった。
「あ、あのっ」
それを止める間もなく、外から玄関のドアが固定された。
「へ?」
「おはようございます」
知らない男に大きな声で挨拶された。
「おはようございます」
降谷は反射的に答えた。
「玄関、養生しますねー」
玄関では作業服の男が三人、テキパキと降谷の部屋に養生シートを貼り始める。
「毛布敷きまーす」
なんで?
問いかける隙も無い。狭くて短い廊下に大きな毛布が広げられた。
「設置は十分で終わりますから」
だから、なんの?
降谷はもう何も聞かなかった。何故ならもう、既に、すぐそこに見えていたからだ。
「乾燥機付き洗濯機」
真っ白な四角い、素敵な便利家電だ。
「だから、洗濯物が乾かなかったのは、嘘なんだって…」
降谷の呟きは、搬入の大騒ぎに紛れて、誰にも聞き止められなかった。
宣言通り、ものの十分で、降谷の洗濯機は新しい乾燥機付きに取り替えられた。手際が良すぎる。多分、唯の電機屋ではないのだろう。
後には、養生テープの一片すら残されてない。
降谷は恐る恐る、洗面所を覗くと、洗濯機の前で、赤井が取扱説明書を広げているところだった。
別に、奴が洗濯するわけでもあるまいに。
「あぁ、降谷くん。色を聞くのを忘れたんだが、君なら白を選ぶと思ってね」
赤井が振り返った。
なんで、この家を知ってるんだ?とか、この洗面所の広さまで把握してる?とか、色々と引っかかるが、それはもういい。
それより、なんで、こんな…。
洗面所の隅っこに、ピカピカのドラム式洗濯機がドンと鎮座している。
洗濯機が壊れたら次はドラム式かな?なんて考えていたが、他人から贈られるのは想定してなかった。
「貴方、なんで、こんなことしたんです」
無性に腹立たしかった。
怒鳴りたいのを抑えると、声が震えた。
「なんでって、礼だと言ったが」
「こんなの、欲しいなんて言ってないです。僕は、乾燥機は使いません。たまにしか外に干せなくても、それで良いんですっ。それを楽しみに休むんですよっ」
声が荒ぶる。感情が抑えられない。
赤井といると、いつもそうだ。いつも、いつも、心が揺れてしまう。だから、会いたくなかったのに。
「だいたい、なんなんだ。お前と仲良くなった覚えはないっ。べったり側に居られるのも迷惑だ」
いつも、降谷が何かを思い悩むタイミングで声を掛けてきて、難航している捜査にもこっちが納得するまで付き添うし、食事を忘れていれば外に連れ出して…。
「お前なんか」
まだ、日本に居る。ずっと近くにくっ付いている。アメリカに帰るまで、ずっと。
一人で残される降谷の気持ちも知らずに。
「お前なんか、迷惑なんだよ。もう僕に近付かないでください。さっさとアメリカに帰れっ」
降谷は怒鳴った。久しぶり大声を出したから、喉が痛んだ。
赤井は驚いて目を見開いていた。
「降谷くん、それは、どうしたんだ」
「だからっ」
「首に発疹が出てる」
赤井の手が降谷の喉元に触れた。
「へっ?」
降谷は慌てて鏡を見た。
首から胸元まで、赤い発疹がびっしりだ。
「な、な、なんで」
「息はできるか?薬は?」
アレルギー反応だ。
嘘を吐いた?どれが嘘だった?
側にいられると迷惑と言った。
もう近付くなとも言った。
アメリカに帰れ?
「とにかく病院に連れていく。大丈夫だ、俺が付いてるから」
ぎゅっと抱き寄せられた。降谷の心臓が急激に鼓動を速めた。
これは、アレルギーの反応なのか?
かつてないほどに至近距離にいる赤井に、降谷はどう接していいのかすら、分からなくなるのだった。
1/1ページ