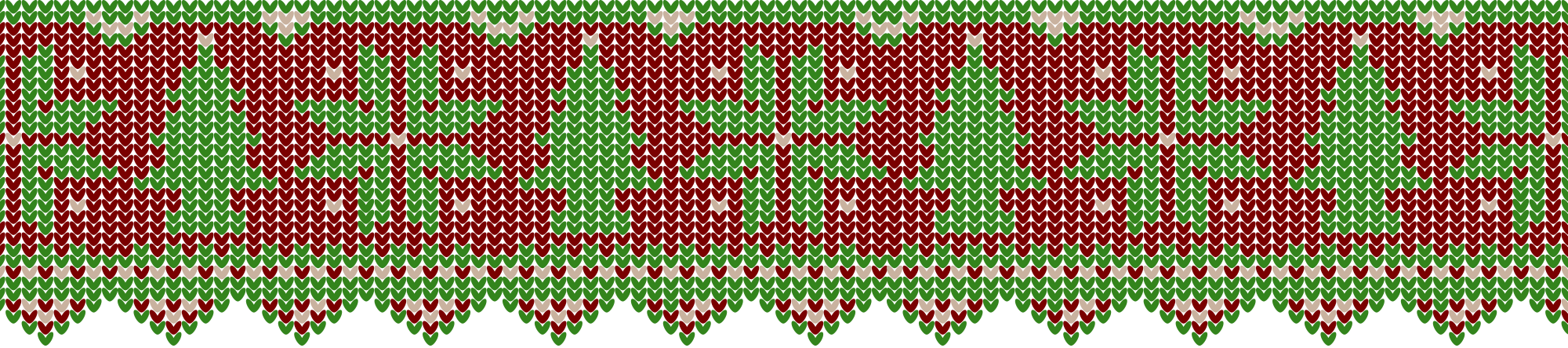鳴神
降谷が、その特別に上等な男と出会ったのは、数ヶ月前のことだ。
英会話の個人教師として週に何度か授業をして欲しいと同級生に頼まれ、出向いた喫茶店で待っていたのが、その特別製の男、赤井秀一であったのだ。
窓際の席に足を組んで座る姿はモデルみたいに素敵で、降谷は声を掛けるのにひどく緊張してしまったくらいだった。
「こ、こんにちは」
「やぁ」
その紳士が答えた。
陳腐だが、その時、降谷は自分に雷みたいな衝撃が走ったのを感じたのだった。
赤井は、主にビルの管理や警備をする会社の経営者だった。降谷が出会ったことのないタイプの大人の男だ。少し警戒して、それでも心のどこかで憧れに似たような感情を抱いた。
「実は、若いうちに起業してしまったから、語学も自己流でね」
そこで、ちゃんと学び直したいと個人教師を雇ったのだそうだ。
「でも、僕、実は法科の学生で…」
英語には自信があるが、所詮は学生レベルなのだ。降谷は、正直にそう言って一度断った。
「話に聞いた通りだ。君は責任感が強いとね。前の学生は、すぐに予定を変えたがるので困った物だった」
なるほど、それが、降谷にこの仕事を紹介した知人なのだろう。
「まぁ、プロに頼むことも考えたが、俺も若い頃は苦労したものでね、どうせなら学生さんに金を払いたい。君みたいなしっかりした子なら、なおいい」
「あ、ありがとうございます」
降谷は素直に礼を言って、この仕事を引き受けた。
苦学生の降谷には、この高額報酬で長期間のバイトはありがたかったのだ。
それから、週に三回、赤井との授業は続いた。
喫茶店で一時間半。赤井は優秀な生徒だった。自己流というが、発音も綺麗だ。それでも、授業を続けるのは、貧しい学生に仕事を与える為でもあるのだろう。
降谷は、いつの間にか、この紳士に心惹かれるようになっていた。
週に三度も会えば、気心も知れる。一度は、仕事が立て込んでいるからと、オフィスまで呼び出されたこともあった。「すまない、すまない」なんて慌てて出てきてくれたから、つい笑ってしまった。でも、傍の秘書だと言う美女にはチクッと胸が痛んだ。
あんな綺麗な人が側に居るのか、と。
降谷は自分のことを客観的に見てみた。
髪は自分で切ってるから、清潔感以外は保証できない。顔は、日本人らしくない派手さだ。昨今の美白ブームに思いっきりかけ離れた日焼け肌に、目が大きな幼顔。赤井氏の秘書は、真っ白な肌に、キリッとした切長の目が色っぽい人だった。なにより。
「……」
降谷は食費を切り詰めて痩せた身体にがっかりした。
いやいや、男の自分に、あの秘書みたいにおっきな胸が付いててもおかしい。
そう思い直しても、それでも、やっぱり、溜息ばかりが溢れた。
そんな、二人の仲が変わったのは、出会って半年目の事だった。
出向いたいつもの喫茶店が臨時休業だったのだ。
雨の日だった。
先についていた降谷は、赤井にメッセージを送り、店の軒先で返事を待った。
パパッ
クラクションを鳴らされ、一本後退る。
その目の前に、真っ赤な外車が停まった。
「降谷くん、乗って」
運転していたのは、赤井だった。
「え?え?」
降谷は戸惑いつつ、後部座席に乗り込んだ。
「すまないね。雨の中、待たせてしまった」
「いえ」
「後ろ、狭いだろ?ごめんね」
ごめんね⁉︎
やけに可愛い物言いに、降谷の胸はキュンと高鳴った。
「さて、どこに行こうか。俺の家でもいいかな?」
「え⁉︎」
「ここから近いんだ」
「は、はい」
とんでもないラッキーが舞い込んだ。
降谷はそう思った。
彼の私生活が垣間見えてしまうと。
「そういえば、降谷くんはどこで英語を?発音も完璧みたいだが」
「僕、キリスト教系の施設出身で、英国人の神父さんに英語を教わってたんです」
「そうなのか。苦労したんだな」
「あ、すみません、こんな話して」
「何故?君のことを知れて嬉しいよ」
ドキっとした。
胸の高鳴りの理由は自分でもよく分からなかった。
いつもの喫茶店からほんのワンブロックのところに、赤井の自宅マンションはあった。
降谷の古いアパートの何倍も大きい。
「一人暮らしでね、あまり、掃除も行き届いてないんだが」
赤井はそんな風に言ったが、通された部屋も広くて綺麗だった。
「雨に濡れなかったかな?」
確かめるように頭を撫でられた。
プライベートな空間での赤井は、ぐっと砕けた態度で降谷に接した。
店では向かい合っていたのに、部屋ではソファに隣り合って座った。赤井は上着を脱いで寛いでいたが、降谷はドキドキして、そちらを見ることもできなかった。
もしかしたら、自分はこの年上の男を好きになってしまったのだろうか。
恋の自覚は唐突だった。
その日から、授業は彼の部屋で行うことになった。例の喫茶店がそのまま休業してしまったからだ。
「君が来るからね、掃除したよ」
なんて、赤井は降谷に親しげな態度をとるようになっていた。
自宅に招くくらいだ、きっと、それなりに信頼されているのだろう。
降谷は、行儀良く、熱心に仕事に向き合った。
その間も、彼への恋心は少しずつ熟れていたが、勿論、それを打ち明ける気はなかった。
「そういえば、君、就職活動はどうしてるんだ?三年生だろう?」
赤井は、ある日の授業終わりに、降谷に聞いた。
「僕、警察官志望で。試験を受けるつもりです」
「ほぉ、警官になるのか」
「…身体検査で落とされるかも知れませんけど」
「何故?どこかに不調があるのか?」
赤井の目が降谷の頭から足まで辿る。どこも健康そのものだと、目が言っていた。
「こんな見てくれですから。僕は日本国籍を有してますけど、血筋は外国人なのだと思い知ります」
応募資格はあるが、こんなにはっきりと混血と分かる外見では、採用されるかどうか。
「実はな、俺もそうなんだ。混血だよ」
「え?」
赤井から、思いがけない言葉を聞かされ、聞き返してしまった。
「東洋系の顔をしてるから、目立たないがね。目や肌の色は純日本人とは違う」
ほらと示された目を見つめる。
「本当だ」
濃い緑と淡い緑とが複雑に組み合わさった瞳の色をしていた。
とても、不思議で綺麗な目だった。
「警察官になれなかったら、俺の専属になってくれると嬉しい」
その瞳に引きこまれて、うっかり頷いてしまいそうだ。
「でも、赤井さんは、既にかなり上手ですけど」
「おいおい、見捨てるのか?」
気弱になってる降谷への冗談だろうが、とても心強く嬉しかった。
「じゃ、赤井さんの会社の採用試験を受けます。面接官には、知り合いだと言っておいてくださいよ」
「即採用だ」
「本当に?」
「勿論」
降谷は笑った。
優しい人だなと、思った。
初めて会った時は、冷たく厳しそうな人だと思ったのに。
将来への不安は、当然ある。能力だけでは、どうにもならない事もあると、それも痛感している。
でも、もし、この人と、この先もこんな風に話せる間柄でいられたら、きっと降谷は絶望なんてしないで生きていられる。
ずっと…。
「君に、ずっと側にいて欲しい」
それを言ったのは赤井の方だった。
ソファの上で、降谷の手が取られた。
「駄目か?」
じっと見つめられて、降谷は意味を理解するより早く頷いた。
赤井の瞳は、さっきより明るい緑色に見えた。不思議な人だ。
あぁ、鼻と鼻がぶつかる。
降谷は心配したが、それより先に唇が触れた。初めのキスは、ふんわりと触れ合うだけの、淡くて甘いものだった。
その日、二人は恋人同士になった。
恋人同士になると、すぐに赤井から鍵を預けられた。
「好きに来ていい」
「え、でも」
「毎日、来てくれると嬉しい」
これまで紳士的に距離を保っていた男だが、付き合いだしたらあちこちにキスしてハグして降谷を見つめるようになった。
年上の紳士がこんなに甘えん坊だなんて。
それでも、降谷の恋は冷めるどころか燃え上がる一方だった。
「一緒に暮らすか?」
付き合い始めて十日目には、赤井は降谷の肩を抱いて、甘ったるく問いかけた。
「え?」
「ここに引っ越しておいで」
「でも」
「駄目か?」
じっと見つめられたら、首を横に振れなかった。
躊躇いつつコクンと頷く降谷に、赤井はにこりと見せたことがないような眩しい笑顔になった。
キスは、これまでとは違った。赤井の舌が降谷の舌に絡まり、あっという間に体から力を抜けさせた。口の中にも快楽を得る場所があると、生まれて初めて知った。
「可愛い。好きだよ」
「ぼ、僕も…好き」
愛を告げるのは恥ずかしくて、声が小さくなった。少しも恥ずかしいことじゃないのに、この世界中に彼を愛してると胸を張って言える筈なのに。
自分の意気地のなさの方が恥ずかしい。降谷は言葉でなく伝えたいと恋人を抱きしめた。
降谷は正真正銘の清童であったので、その先の事は恋人に導かれるしかなかった。
手を引かれて寝室に招かれ、抱きしめあってキスを交わし、一糸纏わぬ姿につるりと剥かれた。
「綺麗な体をしてたんだな」
誰にも見せたことのない部分を手で隠したのは、慣れてないから仕方ないことだろう。
「あの、赤井さん」
「名前で呼んで欲しい」
「秀一さん」
「うん」
「明かり、付けないで」
「あぁ」
赤井の指が降谷の胸乳を撫でた。びくりと、降谷は震えた。
「君はどこもかしこも可愛い」
既に舌を絡めるキスにも慣れた。そのままベッドに押し倒され、重くてみっしりした身体が覆い被さってくるのも、恐ろしいとは思わなかった。
その自分より一回り大きな体に押し潰されると安心したくらいだ。
「秀一さん、秀一さん…」
何度も呼んで、確かめた。
確かにこの人は自分を愛している。激しく求められ、無慈悲なまでに揺さぶられながら、降谷は自分が大海の小舟になったような心細さと心地よさを感じた。
「は…零、どうした?」
恋人は、荒い息の合間に降谷の目元から頬までを唇で辿ってくれた。そこで、降谷は自分が泣いていると気付いたのだった。
「幸せで、怖い」
それも言葉になったかどうか。降谷も息が絶え絶えだったのだ。
「馬鹿だな、何も怖くなんかないよ」
「あっ」
体の奥深くまで暴かれて、降谷は声を上げた。
もう、この人から離れられないだろう。
この毒のような快楽を一生忘れる事はできない。
一生に一度の恋を若くして知ってしまった。
降谷は、この先の人生、この人の為に生きるのだと悟った。
カチッ
小さな音で目が覚めた。
少し眠っていたらしい。
降谷は目を開けて、カーテンの隙間の窓から外を見た。星もない街の夜景が見えた。
まだ夜だ。
煙草の匂いがした。さっきのはライターの音だったらしい。
あの人が一服してるのだろう。
「えっ⁉︎」
明かりのない部屋、ベッドに腰掛ける背中を見て、降谷は反射的に起き上がった。
煙草を咥えたまま、男が振り返った。
「あぁ、煙たかったか、すまない」
火をつけたばかりの煙草は、惜しげも無く消された。
「あ、あ…」
筋肉が張り詰めた広い背中。さっき降谷がしがみついた背中だ。だが、そこには、一面を覆い隠すほどに大きく刺青が入っていたのだった。
「ら、雷神」
街の明かりが浮かび上がらせる背中に、恐ろしい形相の神がこちらを睨んでいる。その周りには、触れれば弾けそうな稲妻が走り、貫いた場所には真っ赤な椿の花が燃え立つように咲いていた。
タトゥーを入れた者なら知り合いにもいた。だが、こんな色鮮やかな和彫を背中に背負う者は、表街道の人間には居やしない。
「なんで…、だって、会社勤めだって」
何故、こんな物がこの人の背中に。
降谷は目の前のことが信じられない。
「あぁ、堅気だよ、今は」
赤井が振り返った。皮肉だが、正面から見た男は、至極真っ当な紳士にしか見えないのだ。
「所属していた組織が解体してね、肩書は本当に会社役員だ」
「肩書は?」
降谷は意味を噛み砕けずに繰り返した。
「性根の話をするなら、俺はこれだ」
赤井が己の肩越しに背中を見やる。
はっと息を飲む間に窓の向こうの空が掻き曇り、ゴロゴロとあちこちで雷がどよめき出す。
「無闇に触れる者には、怪我をさせてしまう」
「あ」
ドンと大きな音がして強烈な稲妻が閃く。真っ白な光が赤井の影を黒く浮かび上がらせた。その影は、降谷の知る男とはまるで別の、何か得体の知れない何かであった。
夢か幻か…。
恐ろしい異形だ。この男は、唯の人ではない。
漸くその事に気がついた。だが、もう手遅れだ。
「君だけだ、俺に触れても無事なのは」
赤井の手は、ベッドの上で縮こまる降谷の足を掴んだ。
指が這う。脹脛を撫でて、膝にまで伸びる。
びくりと、降谷の体は跳ねた。
たった一度の交わりで、降谷は己の身体がまるで変わってしまったと知った。
男が与える快楽に溺れかけている。
いや、そうじゃない。自分は、既にこの男を心底から愛してしまっていたのだ。
「可哀想に、こんな男に惚れて」
膝から脚の付け根まで男の手が撫で上げた。
「あっ」
降谷はあえかな声を上げ、抗いきれずに足を開いた。
赤井がのし掛かってくる。
真っ当な男じゃない。ヤクザ者だ。あの背中の紋々は洒落や酔狂で入れられるものじゃない。
分かってる。それでも、拒めやしなかった。
赤井の舌が降谷の喉を舐めて、甘く歯を立てた。
「あぁ」
殺されてもいい。この人の全部が欲しい。もう、離れられやしない。
降谷は赤井の頭を掻き抱き、その逞しい腰に足を絡めた。
窓の外では、激しい雨が降り、稲妻が閃いていた。
英会話の個人教師として週に何度か授業をして欲しいと同級生に頼まれ、出向いた喫茶店で待っていたのが、その特別製の男、赤井秀一であったのだ。
窓際の席に足を組んで座る姿はモデルみたいに素敵で、降谷は声を掛けるのにひどく緊張してしまったくらいだった。
「こ、こんにちは」
「やぁ」
その紳士が答えた。
陳腐だが、その時、降谷は自分に雷みたいな衝撃が走ったのを感じたのだった。
赤井は、主にビルの管理や警備をする会社の経営者だった。降谷が出会ったことのないタイプの大人の男だ。少し警戒して、それでも心のどこかで憧れに似たような感情を抱いた。
「実は、若いうちに起業してしまったから、語学も自己流でね」
そこで、ちゃんと学び直したいと個人教師を雇ったのだそうだ。
「でも、僕、実は法科の学生で…」
英語には自信があるが、所詮は学生レベルなのだ。降谷は、正直にそう言って一度断った。
「話に聞いた通りだ。君は責任感が強いとね。前の学生は、すぐに予定を変えたがるので困った物だった」
なるほど、それが、降谷にこの仕事を紹介した知人なのだろう。
「まぁ、プロに頼むことも考えたが、俺も若い頃は苦労したものでね、どうせなら学生さんに金を払いたい。君みたいなしっかりした子なら、なおいい」
「あ、ありがとうございます」
降谷は素直に礼を言って、この仕事を引き受けた。
苦学生の降谷には、この高額報酬で長期間のバイトはありがたかったのだ。
それから、週に三回、赤井との授業は続いた。
喫茶店で一時間半。赤井は優秀な生徒だった。自己流というが、発音も綺麗だ。それでも、授業を続けるのは、貧しい学生に仕事を与える為でもあるのだろう。
降谷は、いつの間にか、この紳士に心惹かれるようになっていた。
週に三度も会えば、気心も知れる。一度は、仕事が立て込んでいるからと、オフィスまで呼び出されたこともあった。「すまない、すまない」なんて慌てて出てきてくれたから、つい笑ってしまった。でも、傍の秘書だと言う美女にはチクッと胸が痛んだ。
あんな綺麗な人が側に居るのか、と。
降谷は自分のことを客観的に見てみた。
髪は自分で切ってるから、清潔感以外は保証できない。顔は、日本人らしくない派手さだ。昨今の美白ブームに思いっきりかけ離れた日焼け肌に、目が大きな幼顔。赤井氏の秘書は、真っ白な肌に、キリッとした切長の目が色っぽい人だった。なにより。
「……」
降谷は食費を切り詰めて痩せた身体にがっかりした。
いやいや、男の自分に、あの秘書みたいにおっきな胸が付いててもおかしい。
そう思い直しても、それでも、やっぱり、溜息ばかりが溢れた。
そんな、二人の仲が変わったのは、出会って半年目の事だった。
出向いたいつもの喫茶店が臨時休業だったのだ。
雨の日だった。
先についていた降谷は、赤井にメッセージを送り、店の軒先で返事を待った。
パパッ
クラクションを鳴らされ、一本後退る。
その目の前に、真っ赤な外車が停まった。
「降谷くん、乗って」
運転していたのは、赤井だった。
「え?え?」
降谷は戸惑いつつ、後部座席に乗り込んだ。
「すまないね。雨の中、待たせてしまった」
「いえ」
「後ろ、狭いだろ?ごめんね」
ごめんね⁉︎
やけに可愛い物言いに、降谷の胸はキュンと高鳴った。
「さて、どこに行こうか。俺の家でもいいかな?」
「え⁉︎」
「ここから近いんだ」
「は、はい」
とんでもないラッキーが舞い込んだ。
降谷はそう思った。
彼の私生活が垣間見えてしまうと。
「そういえば、降谷くんはどこで英語を?発音も完璧みたいだが」
「僕、キリスト教系の施設出身で、英国人の神父さんに英語を教わってたんです」
「そうなのか。苦労したんだな」
「あ、すみません、こんな話して」
「何故?君のことを知れて嬉しいよ」
ドキっとした。
胸の高鳴りの理由は自分でもよく分からなかった。
いつもの喫茶店からほんのワンブロックのところに、赤井の自宅マンションはあった。
降谷の古いアパートの何倍も大きい。
「一人暮らしでね、あまり、掃除も行き届いてないんだが」
赤井はそんな風に言ったが、通された部屋も広くて綺麗だった。
「雨に濡れなかったかな?」
確かめるように頭を撫でられた。
プライベートな空間での赤井は、ぐっと砕けた態度で降谷に接した。
店では向かい合っていたのに、部屋ではソファに隣り合って座った。赤井は上着を脱いで寛いでいたが、降谷はドキドキして、そちらを見ることもできなかった。
もしかしたら、自分はこの年上の男を好きになってしまったのだろうか。
恋の自覚は唐突だった。
その日から、授業は彼の部屋で行うことになった。例の喫茶店がそのまま休業してしまったからだ。
「君が来るからね、掃除したよ」
なんて、赤井は降谷に親しげな態度をとるようになっていた。
自宅に招くくらいだ、きっと、それなりに信頼されているのだろう。
降谷は、行儀良く、熱心に仕事に向き合った。
その間も、彼への恋心は少しずつ熟れていたが、勿論、それを打ち明ける気はなかった。
「そういえば、君、就職活動はどうしてるんだ?三年生だろう?」
赤井は、ある日の授業終わりに、降谷に聞いた。
「僕、警察官志望で。試験を受けるつもりです」
「ほぉ、警官になるのか」
「…身体検査で落とされるかも知れませんけど」
「何故?どこかに不調があるのか?」
赤井の目が降谷の頭から足まで辿る。どこも健康そのものだと、目が言っていた。
「こんな見てくれですから。僕は日本国籍を有してますけど、血筋は外国人なのだと思い知ります」
応募資格はあるが、こんなにはっきりと混血と分かる外見では、採用されるかどうか。
「実はな、俺もそうなんだ。混血だよ」
「え?」
赤井から、思いがけない言葉を聞かされ、聞き返してしまった。
「東洋系の顔をしてるから、目立たないがね。目や肌の色は純日本人とは違う」
ほらと示された目を見つめる。
「本当だ」
濃い緑と淡い緑とが複雑に組み合わさった瞳の色をしていた。
とても、不思議で綺麗な目だった。
「警察官になれなかったら、俺の専属になってくれると嬉しい」
その瞳に引きこまれて、うっかり頷いてしまいそうだ。
「でも、赤井さんは、既にかなり上手ですけど」
「おいおい、見捨てるのか?」
気弱になってる降谷への冗談だろうが、とても心強く嬉しかった。
「じゃ、赤井さんの会社の採用試験を受けます。面接官には、知り合いだと言っておいてくださいよ」
「即採用だ」
「本当に?」
「勿論」
降谷は笑った。
優しい人だなと、思った。
初めて会った時は、冷たく厳しそうな人だと思ったのに。
将来への不安は、当然ある。能力だけでは、どうにもならない事もあると、それも痛感している。
でも、もし、この人と、この先もこんな風に話せる間柄でいられたら、きっと降谷は絶望なんてしないで生きていられる。
ずっと…。
「君に、ずっと側にいて欲しい」
それを言ったのは赤井の方だった。
ソファの上で、降谷の手が取られた。
「駄目か?」
じっと見つめられて、降谷は意味を理解するより早く頷いた。
赤井の瞳は、さっきより明るい緑色に見えた。不思議な人だ。
あぁ、鼻と鼻がぶつかる。
降谷は心配したが、それより先に唇が触れた。初めのキスは、ふんわりと触れ合うだけの、淡くて甘いものだった。
その日、二人は恋人同士になった。
恋人同士になると、すぐに赤井から鍵を預けられた。
「好きに来ていい」
「え、でも」
「毎日、来てくれると嬉しい」
これまで紳士的に距離を保っていた男だが、付き合いだしたらあちこちにキスしてハグして降谷を見つめるようになった。
年上の紳士がこんなに甘えん坊だなんて。
それでも、降谷の恋は冷めるどころか燃え上がる一方だった。
「一緒に暮らすか?」
付き合い始めて十日目には、赤井は降谷の肩を抱いて、甘ったるく問いかけた。
「え?」
「ここに引っ越しておいで」
「でも」
「駄目か?」
じっと見つめられたら、首を横に振れなかった。
躊躇いつつコクンと頷く降谷に、赤井はにこりと見せたことがないような眩しい笑顔になった。
キスは、これまでとは違った。赤井の舌が降谷の舌に絡まり、あっという間に体から力を抜けさせた。口の中にも快楽を得る場所があると、生まれて初めて知った。
「可愛い。好きだよ」
「ぼ、僕も…好き」
愛を告げるのは恥ずかしくて、声が小さくなった。少しも恥ずかしいことじゃないのに、この世界中に彼を愛してると胸を張って言える筈なのに。
自分の意気地のなさの方が恥ずかしい。降谷は言葉でなく伝えたいと恋人を抱きしめた。
降谷は正真正銘の清童であったので、その先の事は恋人に導かれるしかなかった。
手を引かれて寝室に招かれ、抱きしめあってキスを交わし、一糸纏わぬ姿につるりと剥かれた。
「綺麗な体をしてたんだな」
誰にも見せたことのない部分を手で隠したのは、慣れてないから仕方ないことだろう。
「あの、赤井さん」
「名前で呼んで欲しい」
「秀一さん」
「うん」
「明かり、付けないで」
「あぁ」
赤井の指が降谷の胸乳を撫でた。びくりと、降谷は震えた。
「君はどこもかしこも可愛い」
既に舌を絡めるキスにも慣れた。そのままベッドに押し倒され、重くてみっしりした身体が覆い被さってくるのも、恐ろしいとは思わなかった。
その自分より一回り大きな体に押し潰されると安心したくらいだ。
「秀一さん、秀一さん…」
何度も呼んで、確かめた。
確かにこの人は自分を愛している。激しく求められ、無慈悲なまでに揺さぶられながら、降谷は自分が大海の小舟になったような心細さと心地よさを感じた。
「は…零、どうした?」
恋人は、荒い息の合間に降谷の目元から頬までを唇で辿ってくれた。そこで、降谷は自分が泣いていると気付いたのだった。
「幸せで、怖い」
それも言葉になったかどうか。降谷も息が絶え絶えだったのだ。
「馬鹿だな、何も怖くなんかないよ」
「あっ」
体の奥深くまで暴かれて、降谷は声を上げた。
もう、この人から離れられないだろう。
この毒のような快楽を一生忘れる事はできない。
一生に一度の恋を若くして知ってしまった。
降谷は、この先の人生、この人の為に生きるのだと悟った。
カチッ
小さな音で目が覚めた。
少し眠っていたらしい。
降谷は目を開けて、カーテンの隙間の窓から外を見た。星もない街の夜景が見えた。
まだ夜だ。
煙草の匂いがした。さっきのはライターの音だったらしい。
あの人が一服してるのだろう。
「えっ⁉︎」
明かりのない部屋、ベッドに腰掛ける背中を見て、降谷は反射的に起き上がった。
煙草を咥えたまま、男が振り返った。
「あぁ、煙たかったか、すまない」
火をつけたばかりの煙草は、惜しげも無く消された。
「あ、あ…」
筋肉が張り詰めた広い背中。さっき降谷がしがみついた背中だ。だが、そこには、一面を覆い隠すほどに大きく刺青が入っていたのだった。
「ら、雷神」
街の明かりが浮かび上がらせる背中に、恐ろしい形相の神がこちらを睨んでいる。その周りには、触れれば弾けそうな稲妻が走り、貫いた場所には真っ赤な椿の花が燃え立つように咲いていた。
タトゥーを入れた者なら知り合いにもいた。だが、こんな色鮮やかな和彫を背中に背負う者は、表街道の人間には居やしない。
「なんで…、だって、会社勤めだって」
何故、こんな物がこの人の背中に。
降谷は目の前のことが信じられない。
「あぁ、堅気だよ、今は」
赤井が振り返った。皮肉だが、正面から見た男は、至極真っ当な紳士にしか見えないのだ。
「所属していた組織が解体してね、肩書は本当に会社役員だ」
「肩書は?」
降谷は意味を噛み砕けずに繰り返した。
「性根の話をするなら、俺はこれだ」
赤井が己の肩越しに背中を見やる。
はっと息を飲む間に窓の向こうの空が掻き曇り、ゴロゴロとあちこちで雷がどよめき出す。
「無闇に触れる者には、怪我をさせてしまう」
「あ」
ドンと大きな音がして強烈な稲妻が閃く。真っ白な光が赤井の影を黒く浮かび上がらせた。その影は、降谷の知る男とはまるで別の、何か得体の知れない何かであった。
夢か幻か…。
恐ろしい異形だ。この男は、唯の人ではない。
漸くその事に気がついた。だが、もう手遅れだ。
「君だけだ、俺に触れても無事なのは」
赤井の手は、ベッドの上で縮こまる降谷の足を掴んだ。
指が這う。脹脛を撫でて、膝にまで伸びる。
びくりと、降谷の体は跳ねた。
たった一度の交わりで、降谷は己の身体がまるで変わってしまったと知った。
男が与える快楽に溺れかけている。
いや、そうじゃない。自分は、既にこの男を心底から愛してしまっていたのだ。
「可哀想に、こんな男に惚れて」
膝から脚の付け根まで男の手が撫で上げた。
「あっ」
降谷はあえかな声を上げ、抗いきれずに足を開いた。
赤井がのし掛かってくる。
真っ当な男じゃない。ヤクザ者だ。あの背中の紋々は洒落や酔狂で入れられるものじゃない。
分かってる。それでも、拒めやしなかった。
赤井の舌が降谷の喉を舐めて、甘く歯を立てた。
「あぁ」
殺されてもいい。この人の全部が欲しい。もう、離れられやしない。
降谷は赤井の頭を掻き抱き、その逞しい腰に足を絡めた。
窓の外では、激しい雨が降り、稲妻が閃いていた。
1/1ページ