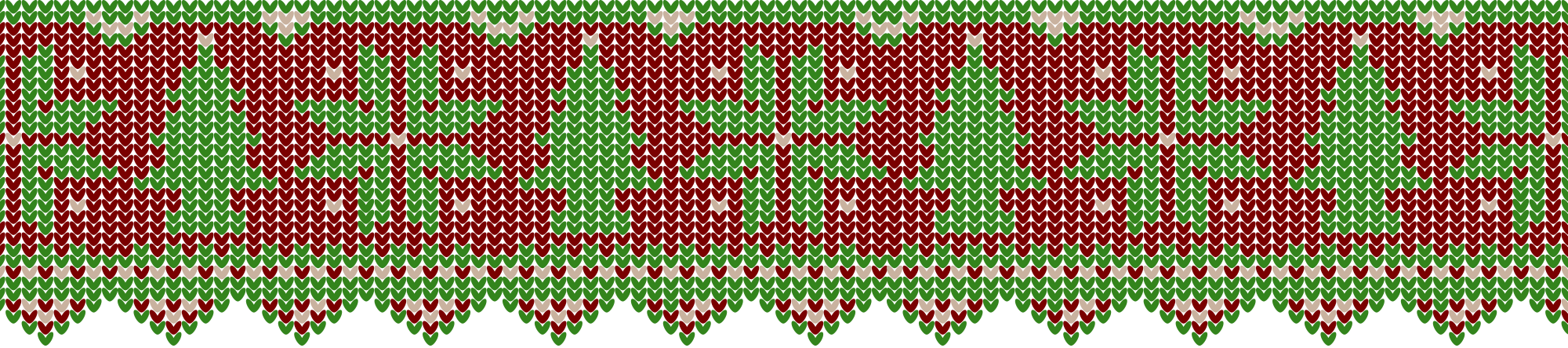またまた、抗う男
七月某日、日曜日。
降谷は、気合を入れて、関内駅に降り立った。
雨が降れば、なんて本気でない願いは天に届く筈もなく、本日も横浜は快晴である。
本日、ここで、降谷は勝負を決める。己の、この苦悩とどう向き合うのか。
悪足掻きと笑わば笑え。だが、本人は至って真面目だ。
待ち合わせ場所に着く前に、ちょいと髪を直す。今日の降谷は、柔らかい素材のシャツと薄手のパンツ。普段着だが、シャツはちょっと派手な柄にした。気負いすぎてない。いい感じに力を抜けた格好の筈だ。
気合いを入れても仕方ない。どうせ、待ち合わせの相手は、いつもの黒尽くめだ。
駅前で、その黒尽くめの大男を探す。だが、なんということか。
「あ、あ、赤井っ!」
先に来ていた相手は、今日に限って、白いTシャツにジーンズなんて、見たことのない格好をしていたのだ。
「はわわわ」
降谷は漫画のように口を開けた。
袖口が二の腕の筋肉で悲鳴をあげているではないか、なんというけしからん格好だ。まだ昼間だぞ!
「やぁ」
赤井が手を挙げる。
それだけで、周りの視線が奴に集中する。
致し方ない。何故なら、今日の赤井は、眩しいばかりにカッコいい。
「く、くそっ」
降谷は一人で悪態を吐いた。
絶対に、惚れたりしないっ。
降谷は己の脇腹をつねった。そうしないと、顔がにやけそうなのだ。
「お待たせしました」
「いや、俺も今着いたとこだ」
トレードマークのニット帽も夏素材だ。
アクセサリー類は付けない、サングラスだけを掛けていた。それが、憎らしいほどに似合っている。
元が良すぎるのだ。くそったれ。
脇腹がをつねり過ぎて痛い。降谷は歯を食いしばって耐えた。
「人が多いな」
「えぇ、皆、スタジアムに向かうのでは」
連れ立って歩き出すと、何故か、赤井は降谷を頭から足まで何度も目を往復させた。
「何か?」
まさか、この服に不備が?
「君は、何を着ても上品になるな」
「え?」
「こんな派手な柄、俺が着たらヤクザだ」
「あは、確かに。貴方、厳ついから」
笑ってみたら、降谷の強張った肩から少し力が抜けた。
初めから決めていたのだ。もし、赤井が、デーゲームに誘ってくれたら、それを受け入れて楽しもうと。
「…スタジアムで飲むビールが旨いんですよ。チケットのお礼に奢らせてください」
「誘ったのは俺だ。こっちが奢るべきでは?」
ほら、こんな因縁の相手なのに、まるで友人のように喋れる。
「日本のスタジアムの楽しみ方は、僕に任せてください」
気負いすぎるなよ。降谷は自分に言い聞かせつつも、今日のこの日をとことん楽しもうと決めたのだった。
さて、降谷がこの赤井という他国の捜査官を警戒するには理由があった。
先日、部下との会話で「結婚をするなら、偶然に何度も会うような、ささやかな縁を感じる相手かもしれない」とかなんとかと考えなしに言ったのだ。だが、これが良くなかった。
その後、やたらと赤井と顔を合わせるようになって、降谷は自分の言葉に雁字搦めになってしまったのだ。
うっかりすると惚れそうで、気が気でない。
なるべく避けて過ごして来たが、それも限界がある。
そして、今日、荒治療として、降谷は赤井とデーゲームに挑んだのであった。
結果としては、この行動は大成功だった。
「いやぁ、とても良い試合でしたね。地味な展開になったらどうしようかと思ってましたけど、終盤のホームランは痺れました」
試合は接戦でホームチームが勝ったのだが、なかなか手に汗握る展開だったのだ。
「あぁ、良い試合だった」
赤井も満足そうだ。
スタジアムでお互い二杯ずつビールを飲んだが、とてもじゃないか足りないと、目に付いた店に入ったところだった。
ここで本日三度目の乾杯を済ませ、今日のゲームに賞賛を贈っているところだ。
降谷はとても気分が良かった。
ピッチャーも良かった。良いプレイもあった。何よりホームランに痺れた。いつか、できることなら、例のスター選手をアメリカで応援したい。
降谷が興奮のままに言った戯言に、赤井は真面目な顔で頷いた。
「ふむ。なら、今度は、ロスのチケットを取ろう」
「あはは、アメリカまで野球を見に行くなんて、贅沢ですね」
でも、もし、それが実現したら…。
降谷は想像する。
二人で並んでゲームを見守って、良いところでスーパースターがホームランを打つのだ。降谷は立ち上がって歓声を上げる。赤井は、どうだろうか、きっと楽しそうに笑ってる気がする。
一緒に、そんな風に過ごせたら、とても楽しい。
目の前では、赤井が、ビールを片手に微笑んでいる。
そんな優しい顔、いつもしていただろうか。
「ん?」
先を促す「ん?」が、ちょっと甘い響きだった。
言ってみれば、唯の友人には聞かせないような、そんな甘さがあった。
いや、まさかな。
「うん。行ってみたいです。なかなかチケットも取れないそうですけど」
降谷は随分と素直にそう言った。
「任せろ、伝手がある」
「ふふ、本当に?貴方って、人付き合いなんてしなそうなのに」
「酷いな。人並みに、友人も知り合いもいるさ」
そこで、少しの沈黙。
周りの騒がしさが、心地よかった。ビールも美味い。赤井との会話も沈黙も、何もかもが悪くない。
そっと、テーブルの上の手が取られた。
赤井の手は、ビールの冷たさが移って、ひんやりしていた。
「もし、君が、俺の誘いを断らなかったら、言おうと決めてたんだが」
「ん?」
降谷の「ん?」も甘く掠れてしまった。
「君の恋人になりたい」
「……は、はぁ?」
何で今?何で、唐突に?
降谷の方は、赤井に傾きそうな心を制御するのに精一杯だというのに。
「こんな、騒がしい店で言うことじゃないな。すまない。焦っているようだ」
赤井はバツが悪そうに頭に手をやり俯いた。
「次の機会がないかもしれないと」
「…どれだけでもありますよ」
降谷は赤井の手を握り返した。
「どうしたって、あちこちで巡り合う運命なんですから」
だから、降谷も腹を括った。
有言実行は、己の信条だ。いや、今、信条になった。
自分の発言に責任持つ。こんな運命の相手なら、行く末までを考えようじゃないか。
「付き合うなら、結婚を前提になりますが、構いませんか?」
周りの喧騒に紛れないように、降谷ははっきりと言った。
赤井が顔上げた。目を見開いて、驚いているようだった。
「なんですか、その顔。まさか、貴方が日本にいる間の戯れの相手にしたかっただけですか?」
「いや、まさか。真剣だ」
「では、今日から婚約者です」
「あ、あぁ」
まるで狐に摘まれたような顔をして、赤井はぼんやり頷いた。
もしかして、尻込みしてるのか?ここまで来て?
今更、それはない。
降谷はもう覚悟が決まっているのだ。
「早速ですけど、僕の部屋に寄っていきます?」
ガタッ
赤井が立ち上がった。
「行く」
簡潔な返事だ。
では、僕の方はどうだ?覚悟、決まっているのか?
己に問いかけるが、よく分からない。
降谷は残ったビールを飲み干すと、勢いをつけて立ち上がった。
赤井と目が合った。お互い、戸惑っているのは分かっている。
それでも、ほんのりと芽生えた運命の何やらが、後押しをしてくれる。
「運命には逆らえないですね」
降谷は呟く。
「ん?」
赤井はまたもや甘やかに「ん?」と先を促す。
「いいえ、何でも」
だから、降谷も、もう何にも抗うことはしなかった。
つまり、どれほど抗っても、結局は恋に落ちたということだ。
運命とは、恋とは、実にままならないものなのであった。
降谷は、気合を入れて、関内駅に降り立った。
雨が降れば、なんて本気でない願いは天に届く筈もなく、本日も横浜は快晴である。
本日、ここで、降谷は勝負を決める。己の、この苦悩とどう向き合うのか。
悪足掻きと笑わば笑え。だが、本人は至って真面目だ。
待ち合わせ場所に着く前に、ちょいと髪を直す。今日の降谷は、柔らかい素材のシャツと薄手のパンツ。普段着だが、シャツはちょっと派手な柄にした。気負いすぎてない。いい感じに力を抜けた格好の筈だ。
気合いを入れても仕方ない。どうせ、待ち合わせの相手は、いつもの黒尽くめだ。
駅前で、その黒尽くめの大男を探す。だが、なんということか。
「あ、あ、赤井っ!」
先に来ていた相手は、今日に限って、白いTシャツにジーンズなんて、見たことのない格好をしていたのだ。
「はわわわ」
降谷は漫画のように口を開けた。
袖口が二の腕の筋肉で悲鳴をあげているではないか、なんというけしからん格好だ。まだ昼間だぞ!
「やぁ」
赤井が手を挙げる。
それだけで、周りの視線が奴に集中する。
致し方ない。何故なら、今日の赤井は、眩しいばかりにカッコいい。
「く、くそっ」
降谷は一人で悪態を吐いた。
絶対に、惚れたりしないっ。
降谷は己の脇腹をつねった。そうしないと、顔がにやけそうなのだ。
「お待たせしました」
「いや、俺も今着いたとこだ」
トレードマークのニット帽も夏素材だ。
アクセサリー類は付けない、サングラスだけを掛けていた。それが、憎らしいほどに似合っている。
元が良すぎるのだ。くそったれ。
脇腹がをつねり過ぎて痛い。降谷は歯を食いしばって耐えた。
「人が多いな」
「えぇ、皆、スタジアムに向かうのでは」
連れ立って歩き出すと、何故か、赤井は降谷を頭から足まで何度も目を往復させた。
「何か?」
まさか、この服に不備が?
「君は、何を着ても上品になるな」
「え?」
「こんな派手な柄、俺が着たらヤクザだ」
「あは、確かに。貴方、厳ついから」
笑ってみたら、降谷の強張った肩から少し力が抜けた。
初めから決めていたのだ。もし、赤井が、デーゲームに誘ってくれたら、それを受け入れて楽しもうと。
「…スタジアムで飲むビールが旨いんですよ。チケットのお礼に奢らせてください」
「誘ったのは俺だ。こっちが奢るべきでは?」
ほら、こんな因縁の相手なのに、まるで友人のように喋れる。
「日本のスタジアムの楽しみ方は、僕に任せてください」
気負いすぎるなよ。降谷は自分に言い聞かせつつも、今日のこの日をとことん楽しもうと決めたのだった。
さて、降谷がこの赤井という他国の捜査官を警戒するには理由があった。
先日、部下との会話で「結婚をするなら、偶然に何度も会うような、ささやかな縁を感じる相手かもしれない」とかなんとかと考えなしに言ったのだ。だが、これが良くなかった。
その後、やたらと赤井と顔を合わせるようになって、降谷は自分の言葉に雁字搦めになってしまったのだ。
うっかりすると惚れそうで、気が気でない。
なるべく避けて過ごして来たが、それも限界がある。
そして、今日、荒治療として、降谷は赤井とデーゲームに挑んだのであった。
結果としては、この行動は大成功だった。
「いやぁ、とても良い試合でしたね。地味な展開になったらどうしようかと思ってましたけど、終盤のホームランは痺れました」
試合は接戦でホームチームが勝ったのだが、なかなか手に汗握る展開だったのだ。
「あぁ、良い試合だった」
赤井も満足そうだ。
スタジアムでお互い二杯ずつビールを飲んだが、とてもじゃないか足りないと、目に付いた店に入ったところだった。
ここで本日三度目の乾杯を済ませ、今日のゲームに賞賛を贈っているところだ。
降谷はとても気分が良かった。
ピッチャーも良かった。良いプレイもあった。何よりホームランに痺れた。いつか、できることなら、例のスター選手をアメリカで応援したい。
降谷が興奮のままに言った戯言に、赤井は真面目な顔で頷いた。
「ふむ。なら、今度は、ロスのチケットを取ろう」
「あはは、アメリカまで野球を見に行くなんて、贅沢ですね」
でも、もし、それが実現したら…。
降谷は想像する。
二人で並んでゲームを見守って、良いところでスーパースターがホームランを打つのだ。降谷は立ち上がって歓声を上げる。赤井は、どうだろうか、きっと楽しそうに笑ってる気がする。
一緒に、そんな風に過ごせたら、とても楽しい。
目の前では、赤井が、ビールを片手に微笑んでいる。
そんな優しい顔、いつもしていただろうか。
「ん?」
先を促す「ん?」が、ちょっと甘い響きだった。
言ってみれば、唯の友人には聞かせないような、そんな甘さがあった。
いや、まさかな。
「うん。行ってみたいです。なかなかチケットも取れないそうですけど」
降谷は随分と素直にそう言った。
「任せろ、伝手がある」
「ふふ、本当に?貴方って、人付き合いなんてしなそうなのに」
「酷いな。人並みに、友人も知り合いもいるさ」
そこで、少しの沈黙。
周りの騒がしさが、心地よかった。ビールも美味い。赤井との会話も沈黙も、何もかもが悪くない。
そっと、テーブルの上の手が取られた。
赤井の手は、ビールの冷たさが移って、ひんやりしていた。
「もし、君が、俺の誘いを断らなかったら、言おうと決めてたんだが」
「ん?」
降谷の「ん?」も甘く掠れてしまった。
「君の恋人になりたい」
「……は、はぁ?」
何で今?何で、唐突に?
降谷の方は、赤井に傾きそうな心を制御するのに精一杯だというのに。
「こんな、騒がしい店で言うことじゃないな。すまない。焦っているようだ」
赤井はバツが悪そうに頭に手をやり俯いた。
「次の機会がないかもしれないと」
「…どれだけでもありますよ」
降谷は赤井の手を握り返した。
「どうしたって、あちこちで巡り合う運命なんですから」
だから、降谷も腹を括った。
有言実行は、己の信条だ。いや、今、信条になった。
自分の発言に責任持つ。こんな運命の相手なら、行く末までを考えようじゃないか。
「付き合うなら、結婚を前提になりますが、構いませんか?」
周りの喧騒に紛れないように、降谷ははっきりと言った。
赤井が顔上げた。目を見開いて、驚いているようだった。
「なんですか、その顔。まさか、貴方が日本にいる間の戯れの相手にしたかっただけですか?」
「いや、まさか。真剣だ」
「では、今日から婚約者です」
「あ、あぁ」
まるで狐に摘まれたような顔をして、赤井はぼんやり頷いた。
もしかして、尻込みしてるのか?ここまで来て?
今更、それはない。
降谷はもう覚悟が決まっているのだ。
「早速ですけど、僕の部屋に寄っていきます?」
ガタッ
赤井が立ち上がった。
「行く」
簡潔な返事だ。
では、僕の方はどうだ?覚悟、決まっているのか?
己に問いかけるが、よく分からない。
降谷は残ったビールを飲み干すと、勢いをつけて立ち上がった。
赤井と目が合った。お互い、戸惑っているのは分かっている。
それでも、ほんのりと芽生えた運命の何やらが、後押しをしてくれる。
「運命には逆らえないですね」
降谷は呟く。
「ん?」
赤井はまたもや甘やかに「ん?」と先を促す。
「いいえ、何でも」
だから、降谷も、もう何にも抗うことはしなかった。
つまり、どれほど抗っても、結局は恋に落ちたということだ。
運命とは、恋とは、実にままならないものなのであった。
1/1ページ