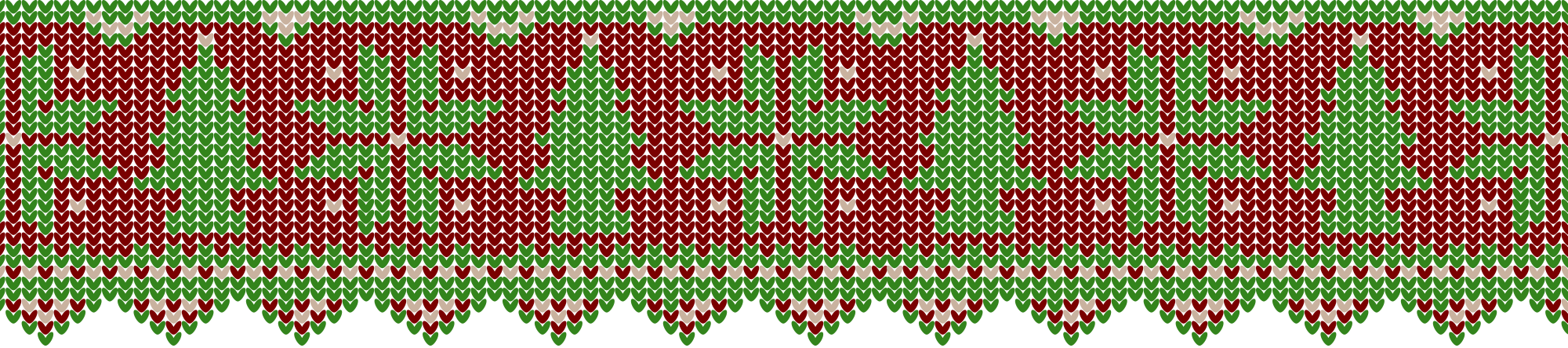抗う男、再び
あ、結婚式だ。
降谷は、買い物帰りの道の教会で、偶然、結婚式に巡り合わせた。
ドアから新郎と新婦が現れ、参列客が花弁を散らせている。「おめでとう」「おめでとう」たくさんの人たちに祝福され、二人は誇らしいだろう。
良いな、幸せそうだ。
降谷は、自分まで誇らしい気持ちになった。
「おや、結婚式か」
不意に背中から声を掛けられた。
この声は、知ってる。
恐る恐る振り返ると、やはり、悩みの種である赤井であった。
この男は、降谷にとっては因縁の相手で…それは、まぁいい。今は、腐れ縁が過ぎて、あちこちで偶然鉢合わせるような仲の男だ。
しかし、これが良くない。
「六月の花嫁か。幸せになれる」
違う!違うんだ。この鉢合わせは、何というか、お互いのテリトリーが被っていることによる必然的な物であって。
「それにしても、こんな所で会うとは偶然だな。君とは、不思議な縁があるようだ」
赤井がNGワードを出した。
縁も偶然も、ありえない。そうだ、これは、当たり前の事なのだ。
降谷は気を取り直し、必然を探すことにした。
「どうしたんですか、こんな所で」
「すぐそこのアパートメントに母が住んでいてな」
「……….そうですか」
それは、想定外だ。
降谷は歯噛みして己の太腿を叩いた。
「君こそ、どうした」
「この近くのパン屋さんが美味しくて」
「わざわざ?パンのために?」
「別に、いいでしょ」
有名店だ。赤井もそのパン目当てだったら、必然的なバッティングであったのに。
「君、電車か?」
「えぇ」
「車で来てる。送るよ」
「いやっ!」
降谷は反射的に断った。
「ん?嫌?」
「いや、その、昼ご飯を食べて帰るので」
「ちょうどよかった、俺もまだなんだ。昼時を逃してしまってな」
そんな、馬鹿な。
今、三時前だぞ。昼飯くらい食っとけ。
「この辺の店はもう閉まってるんだ。君に店を任せてもいいかな?」
よくない。よくないが、赤井とは、今は、同じチームで、つまり仲間であって。邪険にする必要もなくて。
「いいともー」
降谷は蚊の鳴くような声で答えたのだった。
実は、降谷には、パン屋の他にもこの町に目当ての店があるのだった。
その店が昼時は混むので、時間をずらしたのが運の尽きだ。おかげで赤井と鉢合わせた。
気を抜くなよ。降谷は自分に言い聞かせた。
「そういえば、さっき、結婚式に足を止めてたな。君も、考えているのか、結婚を」
一人でピリピリしている降谷に、赤井はのんびりと尋ねた。
「え、いえ、全然。でも、幸せそうで、つい」
「そうか。良かった」
何が良いのかは分からないが、赤井はにこっと珍しい笑顔を見せた。
「貴方は?そろそろそんな年齢ですけど」
「おいおい、今時、『そんな年齢』はないだろ」
「そうですけど」
「結婚なんて贅沢な望みだ」
赤井がふと遠くを見るような目をする。笑顔の次は物憂げな表情だ。
きゅん、降谷の胸は締め付けられた。
きゅん?きゅんってなんだ?
「さて、何を食わせてもらえるのかな?実は腹ペコだ」
「ワーッ!」
腹ペコって何だ!可愛すぎるだろうがっ!いや、間違えた。可愛くないぞ、可愛いわけない。可愛こぶるな、赤井のくせにっ。
己との戦いに、もうすでに負けそうだ。
さて、降谷がここまで赤井を警戒するには理由があった。
以前、「もし結婚するなら、偶然が重なるような、そんな縁のある相手だろうか」なんて言った事があったのだ。それから、やけに赤井との邂逅が重なって、気が気でない。
つまり、自分の言葉に縛られているのだった。
馬鹿らしい。お互い、生活のレベルが似ているだけだ。
バッティングは必然。そう納得しただろう。
「何か食べたい物があるんですか?」
気を取り直し聞いてみた。
「そうだな、せっかく君と一緒だから、日本食が食いたいかな。蘊蓄を聞かせてくれるんだろ?」
「まぁ、いいですけど」
では、当初からのお目当ての店に連れて行くことにしようか。
「あんまり、外国の方が喜ぶ感じでもないんですが」
降谷は駅裏のおばん菜の店に赤井を連れて行った。こういう店は、外国人には好まれないと分かっていたが、ものは試しだ。
「良いじゃないか!すごく、日本的だ」
赤井は店の構えを見ただけで、楽しそうだった。
「そう?」
それならと、中に入る。席も空いている。テーブル席に向かいに座った。
「普段、同僚たちはハンバーガーやステーキばかりなんだ。胸焼けする」
「へぇ、貴方も肉食かと」
「若い頃はな。今は、こういうのが恋しい」
「ここ、こ、恋しい?」
なんて、威力のある言葉選びだ。
参考になる。いや、なんの?
降谷は動揺を隠しつつ、注文をする。厚揚げの煮物が美味いので、それは二人分。他はあれこれと賑やかに。赤井が苦手なものは、降谷が食べればいい。卯の花や白和えは、初めてだろうか。きんぴらは好きそうだ。こんにゃくは苦手かな。
二人連れだから、いつもよりたくさん種類が頼めた。
偶には人と食事をするのも良いものだ。
降谷は、少し肩の力を抜いた。
赤井は機嫌が良さそうで、柔らかな表情をしていた。こんな風に、言い合いにもならず、静かに向き合っていられるのは、初めてかもしれない。
会話が途切れた。だが、降谷は話題を探さなかった。別に、意味のある会話なんて必要ないと、そう思った。
「そうそう、君、週末は空いてるか?」
「へぁ?」
ぼんやりとその顔を見ていたら、赤井が不意に言った。
「デーゲームのチケットを貰ってな、野球は好きかな?」
「好きですけど」
「一緒にどうだ?実は、あまり日本の選手に詳しくないんだ。隣で色々と教えてくれないか?」
来た。デーゲームだ。
降谷は前から決めていたのだ。赤井に誘われたら、まあ断るが、だが、もしそれがデーゲームなら、行ってしまおうと。
赤井との縁とは、実に頑固だ。
こうなったら、向き合って克服するしかない。そして、この呪縛を乗り越えるのだ。
「分かりました」
「ん?」
「僕も、腹を括りました。行きましょう、デーゲーム」
武士のように決死の顔つきになった降谷に、赤井は困惑しているようだった。
「君、野球を見るのに、戦場みたいな覚悟をするんだな」
「えぇ、戦場ですよ」
「ほぉ、筋金入りの野球好きか、誘って良かった」
くそっ。
気を抜くなよ、降谷。
デーゲームがどれだけ楽しかろうと、赤井に恋はしない。分かってるな?恋なんてのは、こんな簡単なもんじゃないんだ。もっと、こう、運命の…。
「今日、君と会えて良かった。これも運命かな」
「う、う、運命とか、言うなっ!」
降谷の戦は、既に負けが見えているのか?
だが、それでも、まだまだ降谷はこの運命とやらに抗うのであった。
降谷は、買い物帰りの道の教会で、偶然、結婚式に巡り合わせた。
ドアから新郎と新婦が現れ、参列客が花弁を散らせている。「おめでとう」「おめでとう」たくさんの人たちに祝福され、二人は誇らしいだろう。
良いな、幸せそうだ。
降谷は、自分まで誇らしい気持ちになった。
「おや、結婚式か」
不意に背中から声を掛けられた。
この声は、知ってる。
恐る恐る振り返ると、やはり、悩みの種である赤井であった。
この男は、降谷にとっては因縁の相手で…それは、まぁいい。今は、腐れ縁が過ぎて、あちこちで偶然鉢合わせるような仲の男だ。
しかし、これが良くない。
「六月の花嫁か。幸せになれる」
違う!違うんだ。この鉢合わせは、何というか、お互いのテリトリーが被っていることによる必然的な物であって。
「それにしても、こんな所で会うとは偶然だな。君とは、不思議な縁があるようだ」
赤井がNGワードを出した。
縁も偶然も、ありえない。そうだ、これは、当たり前の事なのだ。
降谷は気を取り直し、必然を探すことにした。
「どうしたんですか、こんな所で」
「すぐそこのアパートメントに母が住んでいてな」
「……….そうですか」
それは、想定外だ。
降谷は歯噛みして己の太腿を叩いた。
「君こそ、どうした」
「この近くのパン屋さんが美味しくて」
「わざわざ?パンのために?」
「別に、いいでしょ」
有名店だ。赤井もそのパン目当てだったら、必然的なバッティングであったのに。
「君、電車か?」
「えぇ」
「車で来てる。送るよ」
「いやっ!」
降谷は反射的に断った。
「ん?嫌?」
「いや、その、昼ご飯を食べて帰るので」
「ちょうどよかった、俺もまだなんだ。昼時を逃してしまってな」
そんな、馬鹿な。
今、三時前だぞ。昼飯くらい食っとけ。
「この辺の店はもう閉まってるんだ。君に店を任せてもいいかな?」
よくない。よくないが、赤井とは、今は、同じチームで、つまり仲間であって。邪険にする必要もなくて。
「いいともー」
降谷は蚊の鳴くような声で答えたのだった。
実は、降谷には、パン屋の他にもこの町に目当ての店があるのだった。
その店が昼時は混むので、時間をずらしたのが運の尽きだ。おかげで赤井と鉢合わせた。
気を抜くなよ。降谷は自分に言い聞かせた。
「そういえば、さっき、結婚式に足を止めてたな。君も、考えているのか、結婚を」
一人でピリピリしている降谷に、赤井はのんびりと尋ねた。
「え、いえ、全然。でも、幸せそうで、つい」
「そうか。良かった」
何が良いのかは分からないが、赤井はにこっと珍しい笑顔を見せた。
「貴方は?そろそろそんな年齢ですけど」
「おいおい、今時、『そんな年齢』はないだろ」
「そうですけど」
「結婚なんて贅沢な望みだ」
赤井がふと遠くを見るような目をする。笑顔の次は物憂げな表情だ。
きゅん、降谷の胸は締め付けられた。
きゅん?きゅんってなんだ?
「さて、何を食わせてもらえるのかな?実は腹ペコだ」
「ワーッ!」
腹ペコって何だ!可愛すぎるだろうがっ!いや、間違えた。可愛くないぞ、可愛いわけない。可愛こぶるな、赤井のくせにっ。
己との戦いに、もうすでに負けそうだ。
さて、降谷がここまで赤井を警戒するには理由があった。
以前、「もし結婚するなら、偶然が重なるような、そんな縁のある相手だろうか」なんて言った事があったのだ。それから、やけに赤井との邂逅が重なって、気が気でない。
つまり、自分の言葉に縛られているのだった。
馬鹿らしい。お互い、生活のレベルが似ているだけだ。
バッティングは必然。そう納得しただろう。
「何か食べたい物があるんですか?」
気を取り直し聞いてみた。
「そうだな、せっかく君と一緒だから、日本食が食いたいかな。蘊蓄を聞かせてくれるんだろ?」
「まぁ、いいですけど」
では、当初からのお目当ての店に連れて行くことにしようか。
「あんまり、外国の方が喜ぶ感じでもないんですが」
降谷は駅裏のおばん菜の店に赤井を連れて行った。こういう店は、外国人には好まれないと分かっていたが、ものは試しだ。
「良いじゃないか!すごく、日本的だ」
赤井は店の構えを見ただけで、楽しそうだった。
「そう?」
それならと、中に入る。席も空いている。テーブル席に向かいに座った。
「普段、同僚たちはハンバーガーやステーキばかりなんだ。胸焼けする」
「へぇ、貴方も肉食かと」
「若い頃はな。今は、こういうのが恋しい」
「ここ、こ、恋しい?」
なんて、威力のある言葉選びだ。
参考になる。いや、なんの?
降谷は動揺を隠しつつ、注文をする。厚揚げの煮物が美味いので、それは二人分。他はあれこれと賑やかに。赤井が苦手なものは、降谷が食べればいい。卯の花や白和えは、初めてだろうか。きんぴらは好きそうだ。こんにゃくは苦手かな。
二人連れだから、いつもよりたくさん種類が頼めた。
偶には人と食事をするのも良いものだ。
降谷は、少し肩の力を抜いた。
赤井は機嫌が良さそうで、柔らかな表情をしていた。こんな風に、言い合いにもならず、静かに向き合っていられるのは、初めてかもしれない。
会話が途切れた。だが、降谷は話題を探さなかった。別に、意味のある会話なんて必要ないと、そう思った。
「そうそう、君、週末は空いてるか?」
「へぁ?」
ぼんやりとその顔を見ていたら、赤井が不意に言った。
「デーゲームのチケットを貰ってな、野球は好きかな?」
「好きですけど」
「一緒にどうだ?実は、あまり日本の選手に詳しくないんだ。隣で色々と教えてくれないか?」
来た。デーゲームだ。
降谷は前から決めていたのだ。赤井に誘われたら、まあ断るが、だが、もしそれがデーゲームなら、行ってしまおうと。
赤井との縁とは、実に頑固だ。
こうなったら、向き合って克服するしかない。そして、この呪縛を乗り越えるのだ。
「分かりました」
「ん?」
「僕も、腹を括りました。行きましょう、デーゲーム」
武士のように決死の顔つきになった降谷に、赤井は困惑しているようだった。
「君、野球を見るのに、戦場みたいな覚悟をするんだな」
「えぇ、戦場ですよ」
「ほぉ、筋金入りの野球好きか、誘って良かった」
くそっ。
気を抜くなよ、降谷。
デーゲームがどれだけ楽しかろうと、赤井に恋はしない。分かってるな?恋なんてのは、こんな簡単なもんじゃないんだ。もっと、こう、運命の…。
「今日、君と会えて良かった。これも運命かな」
「う、う、運命とか、言うなっ!」
降谷の戦は、既に負けが見えているのか?
だが、それでも、まだまだ降谷はこの運命とやらに抗うのであった。
1/1ページ