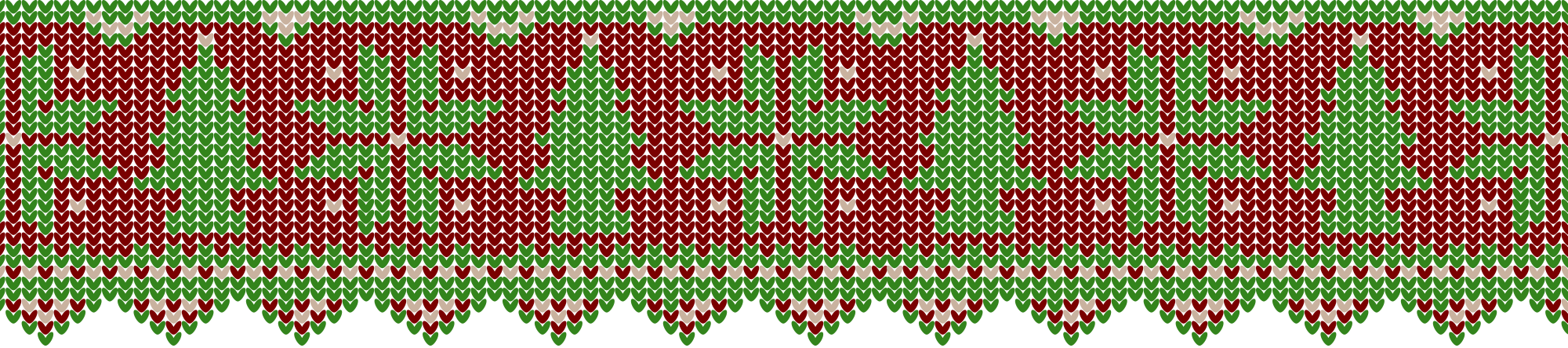神鳴り
運命だ。
その時、赤井はそう思った。
それは、赤井が日本を訪れた時のことだ。
赤井秀一なんて名前のくせに、生まれも育ちも英国人であるが、ふと父のルーツである国を旅したいと思い立った。
人生の岐路に立っている時分には、そういう心境にもなる。
これからどう生きるか、幾つかの道が拓けてはいる。それ以外の生き方もあるかもしれない。自分を見つめ直す旅だった。
それに、久々に弟にも会いたかった。
弟は日本でプロ棋士として生きている。若くして道を決めた。そして、既にトップ棋士たちの中に入っている。
「僕は、子どもの時に将棋に出会ったから」
弟の秀𠮷はそう言う。
だが、赤井だとて、子どもの頃から将棋もチェスもクリケットもやってきた。どれも好きだ。しかし、職業にしようとは思わなかった。
「うーん、兄さんは器用貧乏っていうか、なんでもできちゃうからなぁ」
秀𠮷は、赤井の悩みを言い当てた。
その通りだ。赤井は何でもできて、何でも優秀だ。だが、それだけなのだ。
今は、米国で不動産関係の仕事をしているのだが、このまま、その仕事を続けるかとなると、迷いが出た。
もしかして、自分にはやらなくてはならない事があるのでは?そんな焦りが、ずっと付き纏う。
そういう時期だと周りは言う。転職の誘いもひっきりなしだ。
だが、何を選ぶのか、決め手に欠ける。
「じゃあさ、僕の依頼を受けてくれない?」
秀𠮷は、さも名案のように言った。
「依頼?」
「そう。兄さんの子供の頃の夢は、探偵だったでしょ?」
「そんなの、忘れてたな」
「もし、これがうまく行くなら、日本で探偵をするって選択肢もあるんじゃないかな?」
突拍子もない。だが、エキセントリックな弟には、昔からこういう所があった。
「ふむ。まぁ、お前がそう言うなら」
久々に会った弟が変わりない事が嬉しくて、赤井はそんなおかしなお願いを聞いたのだった。
さて、秀𠮷の依頼だが、これが、シンプルな人探しだったのには、少し拍子抜けした。あの弟の言う事と構えてしまったのだ。
「実は、東都にとんでもない彫り師がいるらしいんだよ」
彫り師とは?赤井は暫し考え込み、それが刺青を彫る職人だと思い至った。
「お前、墨なんて入れる気か?母さんに殺されるぞ」
「あはは、大袈裟だな」
笑い事ではない。
弟は師匠の家に養子入りして、実母の怖さを忘れているらしい。
「感心せんな。お前のような立場なら、尚更」
一度は止めた。
「兄さん、刺青はヤクザ者ばかりが入れる物じゃない。僕は、僕の覚悟を刻みたい。その先生は、人の運命を彫るんだ。生半可な物じゃないんだよ」
だが、秀𠮷があんまりにも真っ直ぐにそういうものだから、赤井も探すだけならと請け負ってしまったのだった。
伝説の彫り師なんて大袈裟な通り名が付いたなら、探すのは楽だ。ネットのどこかに情報が残っている。
その手がかりを元に、素人探偵の赤井は、東都の中心街へと赴いた。
東都駅の周辺は華やかな繁華街だ。だが、そこから住宅街とは逆の飲み屋街へ進み、また、その裏路地となると丸切り別の顔を見せる。
赤井はネットで調べた住所を頼りにここに辿り着いた。勿論、彫り師の店とは書いてなかった。アートなんちゃらと濁していたが、少し掘り返したら刺青の写真が出てきたのだから、間違いない。
「おっと」
だが、ビルの前まで来て、から足を踏んだ。
看板がないのは想定済みだ。だが、その代わりに「売り物件」のプレートが掛けられていたのだ。
「一足遅かったか」
店を畳んだのだ。
仕方ない。この辺の暴力団や関連の組織は全て解散したそうだ。客が居なければ、仕事もない。
さて、そうなると、こういったアングラの店を探すのは人から聞き込むしかない。
「……!!!」
この辺りの飲み屋で聞き込みをしてみようかと表通りに戻ってきた赤井の耳に、何やら争い事の気配が届いた。
「…だ。頼むから。ほんの一点でも良い」
絶滅したと思っていたヤクザ者が、若い男に絡んでいたのだ。
情報源が向こうから来た。
絡まれている若いのは金髪だ。ホストというやつだろうか。
とにかく、これは良くない。
赤井は、ヤクザ者の手を掴んだ。
「おい、警察を呼ぶぞ」
「なんじゃ、ワレェ、邪魔すんな」
この東都で何故か関西訛りの脅し文句。絵に描いたようなヤクザである。
だが、ヤクザ者にしては着ているスーツの仕立てがいい。それに、指には金の指輪が並んでいるではないか。
落ちぶれたヤクザ崩れにしては、羽振が良い。
絶滅を免れたのか?それとも、こんな見てくれでヤクザではないのか?
「ぶん殴られたいんか、おぉう」
赤井より十センチは背が低いが、ガッチリした体つきが小型の戦車みたいな男だった。
「ほぉ」
これは、腕っぷしに覚えのある男と見た。
赤井は数年ぶりに道場以外でやり合うことに、心が湧き立つのを抑えられずに構えた。
ヤクザ者の方はボクシングを土台にした喧嘩スタイルだった。攻撃を喰らっても倒れないという自信があるから、ガードはしない。攻撃特化型の戦車である。
戦った事のないタイプだ。
だが、相手も、赤井のような相手は初めてだろう。
「な、なんや、その構え」
少しばかり怯んだのは、赤井のとったファイティングポーズが見慣れない形だったからだ。
截拳道はあちこちで見るような格闘技でないから仕方ない。
「急所を狙うぞ」
先に宣言して目に指を突きつける。
男が顔をガードした。反応が良い。
赤井は、ガラ空きの腹に思い切り拳をめり込ませた。
「グワっ」
ガタイ程には腹筋は固くない。ちょっとばかりトレーニング不足だ。
「あぁ、痛ぁ」
地べたに這いつくばったヤクザが呻く。
「うわぁ」
金髪の青年は憐れむような声を出した。
「社長さん、大丈夫ですか?」
「いた、痛た、ちょ、先生、救急車呼んでくれ」
「大丈夫そうですね。じゃ、ちゃんと予約の日に来てください。今度、勝手に来たら出禁ですよ」
「そんな。なぁ、先生、頼むわ」
縋り付くヤクザを無慈悲に払いのけ、青年は赤井にぺこりと頭を下げた。
「危ないところをありがとうございました」
もう、足元のヤクザには目もやらない。
なかなか大したタマだ。細身の嫋やかな風情に騙された。近くで見た青年は、しっかりした肩付きと、ビシッとした背筋の鍛えた体をしていたのだ。
別に赤井が助けずとも、なんとかしただろう。
それに、足元のヤクザとも初対面ではなさそうだった。
「いや、君ら知り合いだったのでは?」
「えぇ、お客様です」
それにしては、扱いが雑だ。
「何か、お礼をさせてください」
青年はにこりと微笑んだ。
その時、赤井は漸く、彼の顔をちゃんと確かめた。そうしたら、これが、滅多に拝めないような美貌であったのだ。
まず、目が美しい。淡い虹彩は憂いの薄墨色で、キラキラと輝いている。きゅっと引き締まった口元、キリッとした眉も、気の強さを現していて良い。それに、何より、赤井をじっと見つめる目が真っ直ぐなのだ。
こんなに、意思が強い瞳に出くわしたのは初めてだ。
赤井は暫し見惚れ、それから、はっと当初の目的を思い出した。
「なぁ、君」
彼の視線を裏路地へと促し、売り物件のビルを指差した。
「ここのビルに入っていた彫り師の店を知らないか?何か知っていたら教えて欲しいんだが」
青年がこの街の住人なのは間違いない。噂話でも構わないから何か聞き出したかった。
「貴方、どこでそれを?」
青年が、明らかに身構えた。
「弟に頼まれたんだ。どうやら、彫り物を入れたいらしくてね」
「…ヤクザ者ですか?」
このご時世、わざわざ彫り師を探してまで刺青を入れたいらしいとなると、そう思われるだろう。
「いや、棋士だ。そこそこ有名だから、知ってるかもな」
「ふぅん」
青年はそのまま先に歩き出す。それから、赤井を振り返った。
「まぁ、お茶くらい出しますよ」
目の前には古いビルがあった。
「上がって下さい。ここは僕の店です」
清風堂
厳しい看板に狭い間口の店だった。青年は、そこへ赤井を招いてくれたのだった。
古美術でも扱う店だろうか。
古めかしい店が珍しく、赤井は店の外を眺めてから中に入った。
店の中は上がり框が高い造りになっていた。そこで靴を脱ぐのだと、青年のやる様を真似た。
奥は畳敷きになっていて、赤井の想像したような掛け軸も屏風もない。
何の店だ?
店の中を見回しても、カレンダーとちゃぶ台くらいしかない。
「なぁ、ここは、なんの店だ?」
青年が座布団を出してくれたので、そこに腰を下ろす。
「なんの店だと思ったんですか?」
長過ぎる足がちゃぶ台に収まりきらないのを見て、青年が笑った。
「いや、先生なんて呼ばれてたから、アーティストか医師かと」
「僕が医者に見えます?」
「いや、ホストだと思ってた」
そう言うと、青年が「え」と呟き口をあんぐりと開けたのだった。
「…馬鹿正直な人だな」
それから、呆れたように言って、席を立った。
「お茶入れてきますね」
奥へと引っ込もうとする青年を眺めた赤井の目に、急に不思議なことが起こった。
青年の背中にたっぷりと豊かな尻尾が現れたのだ。
艶々の毛並みの尻尾は黄金色で、しかも数えたら九本も並んでいるではないか。
色の濃い部分もある。だが、尻尾の先は白い。ふさふさっとしたその尻尾は知っていた。
「狐?」
赤井の口からは、思い描いた動物の名前が出た。
「っ!」
青年が振り返った。
「な、なんで、それを」
「いや、今、君の後ろ姿に立派な尻尾が何本も見えてな」
見間違いというには、鮮やかな幻だった。
「……」
青年は黙り込み、何故かシャツのボタンを外し始めた。
「貴方、普通の人ではないんですね」
それから、徐に諸肌を脱いだ。
「これが、僕の正体です」
赤井の眼前に晒されたのは、色鮮やかな刺青の入った背中だった。
「狐か?」
肩からボトムに隠れた尻にまで、見事な刺青が施されている。
「僕の師匠が彫ってくれました。これが、僕の本質だと」
腰に狐の顔がある。尻尾の大きさに見合わないほどに小さな顔だ。背中の全ては、九本の尻尾が覆っており、それを紅葉と菊の花が飾っているのだ。
それが、まるで、青年本人の尾のようだった。
「綺麗だ」
その美しく緻密な毛の表現。触れば、ふっさりと柔らかそうですらある。
素晴らしい。
赤井は誘われるように立ち上がった。
「本当に?」
「あぁ、とても、綺麗だ」
「寂しい図柄だと言われます。でも、僕は、この九本の尻尾を背負っている事が、誇らしい」
「あぁ、誇るべきだ」
生きている背中に絵を描くとは、これほどまでに生き生きとするものなのか。
赤井はため息を吐き、飽きずにその背中を眺め続けた。
秋の野山に、この特別な狐が現れる。小川のせせらぎに舞い散る紅葉。身軽な狐は、小さな川くらいなら飛び越える。
美しい獣だ。だが、捕まえようとしても、人がどうにかできる相手ではない。
気高い獣だ。
赤井はそっと手を伸ばした。
青年の背中に、指が触れた。
ふさふさの毛並みではなく、滑らかな人の肌の感触だった。
「なぁ」
「はい?」
びくっと背中が震えた。
「俺に、彫ってくれないか?」
「え?」
青年が振り返った。
「さっきの男が縋り付くくらいだ、予約がいっぱいなんだろう?だが、何年待ってもいい、俺に、彫ってくれ」
考えて言ったんじゃない、気が付いたらそう言っていた。
「良いんですか、僕の腕を知らないのに」
「いや、きっと、君なんだろう?運命を彫るという、伝説の彫り師とは」
この時、赤井は弟のことなんて頭から抜けてしまっていて、ただ、この出会いは運命だと、そう思ったのだ。
そして、この目の前の青年になら、自分の人生を預けてみたいと、そう…。
「堅気の背中に、こんな紋紋は背負わせられない」
「おい」
「と言いたいところですけど、僕、貴方を見た瞬間から、彫ってみたくて仕方ない」
青年がにこっと幼い笑顔を見せた。
「貴方が社長を殴った時、シャツの皺が背中に寄って、その下の筋肉を想像しました。肩幅が広くて絵が映える。それに、黄味の少ない肌色も凄みがあっていい。そりゃあ最高の背中だろうと」
興奮気味にそこまで捲し立ててから、少しばかり遠慮がちに、青年が赤井を伺った。
「脱いでくれませんか?」
「あ、あぁ」
上半身だけとはいえ裸の美青年にそんな風に言われて、戸惑った。それでも、赤井はシャツを脱いだ。
「すごい、いい体ですね」
途端にぐるっと背中を向けさせられ、肩から背筋まで撫でられた。
「想像以上です。理想的な背中ですよ。これ以上何を背負いたいんです?麒麟でも龍でも貴方なら背負いきれるでしょうけど」
「何でもいい。君の思うままで」
背中を這う手が艶かしい。
「本当に?ここに、僕の思うままに?」
「あぁ」
この美しい男になら、翻弄されたい。
赤井の中に、人生に初めての破滅的な願望が生まれた。
「狐もいいな。君と揃いだ」
「いえ、雷神を彫ります」
ぐっと背中に這う手が強く背中を押した。
左肩から、背骨まで。
「貴方には、雷の一瞬の光や激しさが似合う」
それから、右肩。ここに、雷を彫ると言うのだ。
「稲妻は、貴方の肌に似合うように青と白で彫ります。さっきの貴方みたいに、荒々しくて、でも冷静で、触れれば弾けるような凄みを出したい。逆に花は紅梅か、椿。真っ赤で、鮮烈な」
手が腰に触れた。
赤井の背筋を電気が走った。
それは紛れもなく官能の震えだった。
「なぁ、君と会うのは初めてか?」
出会ってほんの数十分の仲だ。だが、赤井は、彼への誤魔化しきれない激情を感じていた。
「何でそんなこと聞くんですか?」
首を傾げる曖昧な角度。ちらりと流れる目元。ぐっとくるほどに艶っぽい男だ。
「君の名前を教えてくれ」
「零です。降谷零」
「レイ」
呼んでみると、まるで呼び慣れた名前のような気になった。
「やっぱり、どこかで会った気がするな」
「ふふ、下手な口説き文句ですね」
「確かにな」
下手なのは自分でも分かっていた。
「貴方は?」
「赤井秀一だ。好きに呼んでくれ」
「秀一さん、赤井さん?」
「何でもいい。好きに」
名前を呼ばれて気付く。この男は声も良い。
「仕上げるのに二、三ヶ月は掛かりますよ」
「あぁ。ちょうど休暇中だ」
これから、三ヶ月、この男と二人きりの時間を持てるのか。
その間に、下手ではない口説き文句を用意しなくては。
いや、赤井の背中が出来上がったら、必ずこの男はそれに惚れる。己が描いた最高傑作に、執着するだろう。
ゾクゾクするような歓喜だ。
人生とは、これほどまでにエキサイティングな物だったのか。
いつの間にか、赤井の中の焦りは無くなっていた。見つけるべきものが見つかったからだ。
運命の人だ。
三ヶ月後、赤井が導かれるのは破滅か栄光か。しかし、この美しい男も道連れだ。
「なぁ、出会ったばかりで、不躾だが」
赤井は背中にいた男を手繰り寄せた。
「君に恋人が居るなら、今すぐ別れてくれ」
裸の肌が触れ合った。
腕の中で零がぎょっと目を見開いている。
「さぁ、いつから始める?」
その一針で始まる。赤井の新しい人生が。
己の運命の人だ。
赤井は、零をきつく抱きしめた。
その時、赤井はそう思った。
それは、赤井が日本を訪れた時のことだ。
赤井秀一なんて名前のくせに、生まれも育ちも英国人であるが、ふと父のルーツである国を旅したいと思い立った。
人生の岐路に立っている時分には、そういう心境にもなる。
これからどう生きるか、幾つかの道が拓けてはいる。それ以外の生き方もあるかもしれない。自分を見つめ直す旅だった。
それに、久々に弟にも会いたかった。
弟は日本でプロ棋士として生きている。若くして道を決めた。そして、既にトップ棋士たちの中に入っている。
「僕は、子どもの時に将棋に出会ったから」
弟の秀𠮷はそう言う。
だが、赤井だとて、子どもの頃から将棋もチェスもクリケットもやってきた。どれも好きだ。しかし、職業にしようとは思わなかった。
「うーん、兄さんは器用貧乏っていうか、なんでもできちゃうからなぁ」
秀𠮷は、赤井の悩みを言い当てた。
その通りだ。赤井は何でもできて、何でも優秀だ。だが、それだけなのだ。
今は、米国で不動産関係の仕事をしているのだが、このまま、その仕事を続けるかとなると、迷いが出た。
もしかして、自分にはやらなくてはならない事があるのでは?そんな焦りが、ずっと付き纏う。
そういう時期だと周りは言う。転職の誘いもひっきりなしだ。
だが、何を選ぶのか、決め手に欠ける。
「じゃあさ、僕の依頼を受けてくれない?」
秀𠮷は、さも名案のように言った。
「依頼?」
「そう。兄さんの子供の頃の夢は、探偵だったでしょ?」
「そんなの、忘れてたな」
「もし、これがうまく行くなら、日本で探偵をするって選択肢もあるんじゃないかな?」
突拍子もない。だが、エキセントリックな弟には、昔からこういう所があった。
「ふむ。まぁ、お前がそう言うなら」
久々に会った弟が変わりない事が嬉しくて、赤井はそんなおかしなお願いを聞いたのだった。
さて、秀𠮷の依頼だが、これが、シンプルな人探しだったのには、少し拍子抜けした。あの弟の言う事と構えてしまったのだ。
「実は、東都にとんでもない彫り師がいるらしいんだよ」
彫り師とは?赤井は暫し考え込み、それが刺青を彫る職人だと思い至った。
「お前、墨なんて入れる気か?母さんに殺されるぞ」
「あはは、大袈裟だな」
笑い事ではない。
弟は師匠の家に養子入りして、実母の怖さを忘れているらしい。
「感心せんな。お前のような立場なら、尚更」
一度は止めた。
「兄さん、刺青はヤクザ者ばかりが入れる物じゃない。僕は、僕の覚悟を刻みたい。その先生は、人の運命を彫るんだ。生半可な物じゃないんだよ」
だが、秀𠮷があんまりにも真っ直ぐにそういうものだから、赤井も探すだけならと請け負ってしまったのだった。
伝説の彫り師なんて大袈裟な通り名が付いたなら、探すのは楽だ。ネットのどこかに情報が残っている。
その手がかりを元に、素人探偵の赤井は、東都の中心街へと赴いた。
東都駅の周辺は華やかな繁華街だ。だが、そこから住宅街とは逆の飲み屋街へ進み、また、その裏路地となると丸切り別の顔を見せる。
赤井はネットで調べた住所を頼りにここに辿り着いた。勿論、彫り師の店とは書いてなかった。アートなんちゃらと濁していたが、少し掘り返したら刺青の写真が出てきたのだから、間違いない。
「おっと」
だが、ビルの前まで来て、から足を踏んだ。
看板がないのは想定済みだ。だが、その代わりに「売り物件」のプレートが掛けられていたのだ。
「一足遅かったか」
店を畳んだのだ。
仕方ない。この辺の暴力団や関連の組織は全て解散したそうだ。客が居なければ、仕事もない。
さて、そうなると、こういったアングラの店を探すのは人から聞き込むしかない。
「……!!!」
この辺りの飲み屋で聞き込みをしてみようかと表通りに戻ってきた赤井の耳に、何やら争い事の気配が届いた。
「…だ。頼むから。ほんの一点でも良い」
絶滅したと思っていたヤクザ者が、若い男に絡んでいたのだ。
情報源が向こうから来た。
絡まれている若いのは金髪だ。ホストというやつだろうか。
とにかく、これは良くない。
赤井は、ヤクザ者の手を掴んだ。
「おい、警察を呼ぶぞ」
「なんじゃ、ワレェ、邪魔すんな」
この東都で何故か関西訛りの脅し文句。絵に描いたようなヤクザである。
だが、ヤクザ者にしては着ているスーツの仕立てがいい。それに、指には金の指輪が並んでいるではないか。
落ちぶれたヤクザ崩れにしては、羽振が良い。
絶滅を免れたのか?それとも、こんな見てくれでヤクザではないのか?
「ぶん殴られたいんか、おぉう」
赤井より十センチは背が低いが、ガッチリした体つきが小型の戦車みたいな男だった。
「ほぉ」
これは、腕っぷしに覚えのある男と見た。
赤井は数年ぶりに道場以外でやり合うことに、心が湧き立つのを抑えられずに構えた。
ヤクザ者の方はボクシングを土台にした喧嘩スタイルだった。攻撃を喰らっても倒れないという自信があるから、ガードはしない。攻撃特化型の戦車である。
戦った事のないタイプだ。
だが、相手も、赤井のような相手は初めてだろう。
「な、なんや、その構え」
少しばかり怯んだのは、赤井のとったファイティングポーズが見慣れない形だったからだ。
截拳道はあちこちで見るような格闘技でないから仕方ない。
「急所を狙うぞ」
先に宣言して目に指を突きつける。
男が顔をガードした。反応が良い。
赤井は、ガラ空きの腹に思い切り拳をめり込ませた。
「グワっ」
ガタイ程には腹筋は固くない。ちょっとばかりトレーニング不足だ。
「あぁ、痛ぁ」
地べたに這いつくばったヤクザが呻く。
「うわぁ」
金髪の青年は憐れむような声を出した。
「社長さん、大丈夫ですか?」
「いた、痛た、ちょ、先生、救急車呼んでくれ」
「大丈夫そうですね。じゃ、ちゃんと予約の日に来てください。今度、勝手に来たら出禁ですよ」
「そんな。なぁ、先生、頼むわ」
縋り付くヤクザを無慈悲に払いのけ、青年は赤井にぺこりと頭を下げた。
「危ないところをありがとうございました」
もう、足元のヤクザには目もやらない。
なかなか大したタマだ。細身の嫋やかな風情に騙された。近くで見た青年は、しっかりした肩付きと、ビシッとした背筋の鍛えた体をしていたのだ。
別に赤井が助けずとも、なんとかしただろう。
それに、足元のヤクザとも初対面ではなさそうだった。
「いや、君ら知り合いだったのでは?」
「えぇ、お客様です」
それにしては、扱いが雑だ。
「何か、お礼をさせてください」
青年はにこりと微笑んだ。
その時、赤井は漸く、彼の顔をちゃんと確かめた。そうしたら、これが、滅多に拝めないような美貌であったのだ。
まず、目が美しい。淡い虹彩は憂いの薄墨色で、キラキラと輝いている。きゅっと引き締まった口元、キリッとした眉も、気の強さを現していて良い。それに、何より、赤井をじっと見つめる目が真っ直ぐなのだ。
こんなに、意思が強い瞳に出くわしたのは初めてだ。
赤井は暫し見惚れ、それから、はっと当初の目的を思い出した。
「なぁ、君」
彼の視線を裏路地へと促し、売り物件のビルを指差した。
「ここのビルに入っていた彫り師の店を知らないか?何か知っていたら教えて欲しいんだが」
青年がこの街の住人なのは間違いない。噂話でも構わないから何か聞き出したかった。
「貴方、どこでそれを?」
青年が、明らかに身構えた。
「弟に頼まれたんだ。どうやら、彫り物を入れたいらしくてね」
「…ヤクザ者ですか?」
このご時世、わざわざ彫り師を探してまで刺青を入れたいらしいとなると、そう思われるだろう。
「いや、棋士だ。そこそこ有名だから、知ってるかもな」
「ふぅん」
青年はそのまま先に歩き出す。それから、赤井を振り返った。
「まぁ、お茶くらい出しますよ」
目の前には古いビルがあった。
「上がって下さい。ここは僕の店です」
清風堂
厳しい看板に狭い間口の店だった。青年は、そこへ赤井を招いてくれたのだった。
古美術でも扱う店だろうか。
古めかしい店が珍しく、赤井は店の外を眺めてから中に入った。
店の中は上がり框が高い造りになっていた。そこで靴を脱ぐのだと、青年のやる様を真似た。
奥は畳敷きになっていて、赤井の想像したような掛け軸も屏風もない。
何の店だ?
店の中を見回しても、カレンダーとちゃぶ台くらいしかない。
「なぁ、ここは、なんの店だ?」
青年が座布団を出してくれたので、そこに腰を下ろす。
「なんの店だと思ったんですか?」
長過ぎる足がちゃぶ台に収まりきらないのを見て、青年が笑った。
「いや、先生なんて呼ばれてたから、アーティストか医師かと」
「僕が医者に見えます?」
「いや、ホストだと思ってた」
そう言うと、青年が「え」と呟き口をあんぐりと開けたのだった。
「…馬鹿正直な人だな」
それから、呆れたように言って、席を立った。
「お茶入れてきますね」
奥へと引っ込もうとする青年を眺めた赤井の目に、急に不思議なことが起こった。
青年の背中にたっぷりと豊かな尻尾が現れたのだ。
艶々の毛並みの尻尾は黄金色で、しかも数えたら九本も並んでいるではないか。
色の濃い部分もある。だが、尻尾の先は白い。ふさふさっとしたその尻尾は知っていた。
「狐?」
赤井の口からは、思い描いた動物の名前が出た。
「っ!」
青年が振り返った。
「な、なんで、それを」
「いや、今、君の後ろ姿に立派な尻尾が何本も見えてな」
見間違いというには、鮮やかな幻だった。
「……」
青年は黙り込み、何故かシャツのボタンを外し始めた。
「貴方、普通の人ではないんですね」
それから、徐に諸肌を脱いだ。
「これが、僕の正体です」
赤井の眼前に晒されたのは、色鮮やかな刺青の入った背中だった。
「狐か?」
肩からボトムに隠れた尻にまで、見事な刺青が施されている。
「僕の師匠が彫ってくれました。これが、僕の本質だと」
腰に狐の顔がある。尻尾の大きさに見合わないほどに小さな顔だ。背中の全ては、九本の尻尾が覆っており、それを紅葉と菊の花が飾っているのだ。
それが、まるで、青年本人の尾のようだった。
「綺麗だ」
その美しく緻密な毛の表現。触れば、ふっさりと柔らかそうですらある。
素晴らしい。
赤井は誘われるように立ち上がった。
「本当に?」
「あぁ、とても、綺麗だ」
「寂しい図柄だと言われます。でも、僕は、この九本の尻尾を背負っている事が、誇らしい」
「あぁ、誇るべきだ」
生きている背中に絵を描くとは、これほどまでに生き生きとするものなのか。
赤井はため息を吐き、飽きずにその背中を眺め続けた。
秋の野山に、この特別な狐が現れる。小川のせせらぎに舞い散る紅葉。身軽な狐は、小さな川くらいなら飛び越える。
美しい獣だ。だが、捕まえようとしても、人がどうにかできる相手ではない。
気高い獣だ。
赤井はそっと手を伸ばした。
青年の背中に、指が触れた。
ふさふさの毛並みではなく、滑らかな人の肌の感触だった。
「なぁ」
「はい?」
びくっと背中が震えた。
「俺に、彫ってくれないか?」
「え?」
青年が振り返った。
「さっきの男が縋り付くくらいだ、予約がいっぱいなんだろう?だが、何年待ってもいい、俺に、彫ってくれ」
考えて言ったんじゃない、気が付いたらそう言っていた。
「良いんですか、僕の腕を知らないのに」
「いや、きっと、君なんだろう?運命を彫るという、伝説の彫り師とは」
この時、赤井は弟のことなんて頭から抜けてしまっていて、ただ、この出会いは運命だと、そう思ったのだ。
そして、この目の前の青年になら、自分の人生を預けてみたいと、そう…。
「堅気の背中に、こんな紋紋は背負わせられない」
「おい」
「と言いたいところですけど、僕、貴方を見た瞬間から、彫ってみたくて仕方ない」
青年がにこっと幼い笑顔を見せた。
「貴方が社長を殴った時、シャツの皺が背中に寄って、その下の筋肉を想像しました。肩幅が広くて絵が映える。それに、黄味の少ない肌色も凄みがあっていい。そりゃあ最高の背中だろうと」
興奮気味にそこまで捲し立ててから、少しばかり遠慮がちに、青年が赤井を伺った。
「脱いでくれませんか?」
「あ、あぁ」
上半身だけとはいえ裸の美青年にそんな風に言われて、戸惑った。それでも、赤井はシャツを脱いだ。
「すごい、いい体ですね」
途端にぐるっと背中を向けさせられ、肩から背筋まで撫でられた。
「想像以上です。理想的な背中ですよ。これ以上何を背負いたいんです?麒麟でも龍でも貴方なら背負いきれるでしょうけど」
「何でもいい。君の思うままで」
背中を這う手が艶かしい。
「本当に?ここに、僕の思うままに?」
「あぁ」
この美しい男になら、翻弄されたい。
赤井の中に、人生に初めての破滅的な願望が生まれた。
「狐もいいな。君と揃いだ」
「いえ、雷神を彫ります」
ぐっと背中に這う手が強く背中を押した。
左肩から、背骨まで。
「貴方には、雷の一瞬の光や激しさが似合う」
それから、右肩。ここに、雷を彫ると言うのだ。
「稲妻は、貴方の肌に似合うように青と白で彫ります。さっきの貴方みたいに、荒々しくて、でも冷静で、触れれば弾けるような凄みを出したい。逆に花は紅梅か、椿。真っ赤で、鮮烈な」
手が腰に触れた。
赤井の背筋を電気が走った。
それは紛れもなく官能の震えだった。
「なぁ、君と会うのは初めてか?」
出会ってほんの数十分の仲だ。だが、赤井は、彼への誤魔化しきれない激情を感じていた。
「何でそんなこと聞くんですか?」
首を傾げる曖昧な角度。ちらりと流れる目元。ぐっとくるほどに艶っぽい男だ。
「君の名前を教えてくれ」
「零です。降谷零」
「レイ」
呼んでみると、まるで呼び慣れた名前のような気になった。
「やっぱり、どこかで会った気がするな」
「ふふ、下手な口説き文句ですね」
「確かにな」
下手なのは自分でも分かっていた。
「貴方は?」
「赤井秀一だ。好きに呼んでくれ」
「秀一さん、赤井さん?」
「何でもいい。好きに」
名前を呼ばれて気付く。この男は声も良い。
「仕上げるのに二、三ヶ月は掛かりますよ」
「あぁ。ちょうど休暇中だ」
これから、三ヶ月、この男と二人きりの時間を持てるのか。
その間に、下手ではない口説き文句を用意しなくては。
いや、赤井の背中が出来上がったら、必ずこの男はそれに惚れる。己が描いた最高傑作に、執着するだろう。
ゾクゾクするような歓喜だ。
人生とは、これほどまでにエキサイティングな物だったのか。
いつの間にか、赤井の中の焦りは無くなっていた。見つけるべきものが見つかったからだ。
運命の人だ。
三ヶ月後、赤井が導かれるのは破滅か栄光か。しかし、この美しい男も道連れだ。
「なぁ、出会ったばかりで、不躾だが」
赤井は背中にいた男を手繰り寄せた。
「君に恋人が居るなら、今すぐ別れてくれ」
裸の肌が触れ合った。
腕の中で零がぎょっと目を見開いている。
「さぁ、いつから始める?」
その一針で始まる。赤井の新しい人生が。
己の運命の人だ。
赤井は、零をきつく抱きしめた。
1/1ページ