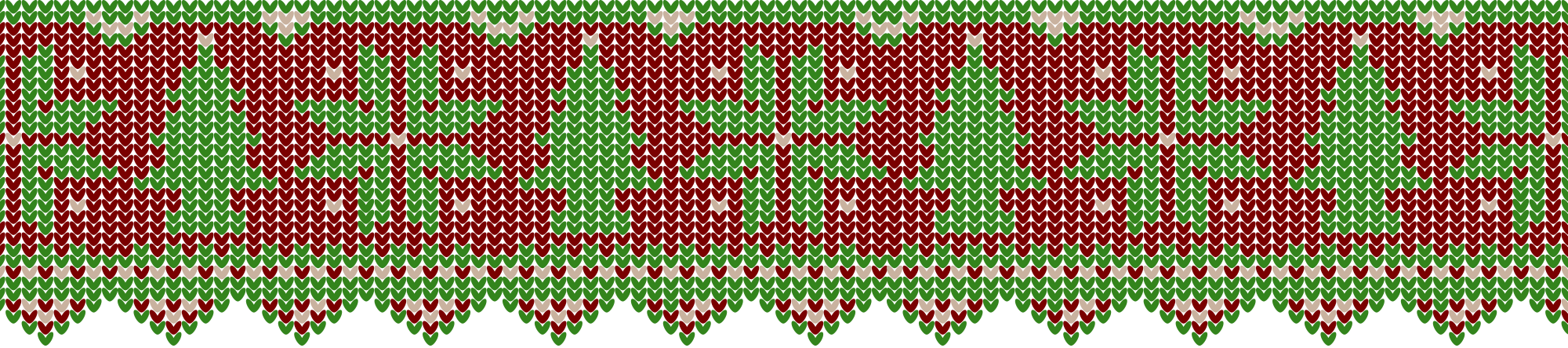抗う男
とあるスター選手は、妻との馴れ初めを「二週間の間に三度も偶然に会って」と言っていた。
降谷はプロなので、それは偶然か?と穿って考えてしまった。
彼の奥さんもスポーツ選手だ。同じような行動範囲であれば、それは必然なのでは?…まぁ、野暮な考えだ。
「やぁ、また会ったな」
なので、今、この何やらの縁も、たいした意味はない。
降谷は、ひょいと手を挙げて挨拶をよした男、赤井に会釈で返しつつ「これは、当たり前のことだ。こいつと僕は、近所に住んでて、同じような生活レベルで、なので、これは」とぐるぐるする思考を放棄した。
降谷と赤井は同業者だ。二人とも捜査官で、同じ事件を解決させた仲でもある。今は、お互いの組織が協力体制にあるので、チームメイトといったところだろうか。
仲が良いかは、微妙。どちらかが死ぬしかないとまで思い詰めたことを思えば良好だ。
「あら、お知り合い?相席でよろしい?」
居酒屋のお母さんが、そこで立っている降谷に聞いた。
よろしい?よろしくはない。しかし、金曜の夜の居酒屋は混み合っている。この男のテーブルでなくカウンターに座ったら、他の客を一人待たせる事になる。
つまり、それは、お母さんに迷惑だ。
「あ、じゃ、僕、ビールで」
降谷はにこっと笑い、赤井の対面に腰掛けた。
「偶然だな」
赤井は、全く屈託なく、降谷を自分のテーブルに迎え入れた。
「貴方、居酒屋ってタイプじゃないでしょ」
「あぁ、晩飯代わりにな」
「へぇ」
そう言われると、何も言い返せない。降谷も同じだからだ。この居酒屋で、晩飯代わりに一杯飲むのが、週末の楽しみなのだ。
「はい、ビール」
お母さんがビールとお通しの酢の物を降谷の前に置いた。
「あ、あと、冷やしトマトと刺し盛りお願いします」
手渡されたお絞りで手を拭きつつ、注文を。目の端で、赤井がふっと笑う気配を感じた。
「お疲れ様」
「はぁ、どうも」
ごにょごにょと降谷の口は動きが悪くなった。
言い訳をさせて貰うなら、普段の降谷は、こんなまごまごした男ではない。
「乾杯」
赤井がコップを掲げた。彼のはハイボールだ。
降谷はついついそれにコップをカチンとぶつけた。
居酒屋の喧騒に、降谷の密やかな溜息は紛れて消えた。
さて、降谷が赤井という男との邂逅を偶然ではない必然だと足掻くのには理由があった。
つい、先だってのことだ。降谷が部下たちに「降谷さんは、どんな人となら結婚を考えますか?」と聞かれ、ふと、例のスーパースターを思い出し「そうだな、運命的な出会いというよりは、何故か何度も顔を合わせてしまうような、そんな縁のある相手なら、考えてしまうな」とかなんとか答えたのだ。
当然、深い考えではない。しかし、好みだとかそんなものは持ち合わせて無い降谷が、咄嗟に答えたのだから、案外、それは真理だったかもしれない。
それ故に、これが、偶然であっては困るのだ。
赤井とは、この一週間で何度も何度も顔を合わせている。仕事場は、同じオフィスに出勤しているのだからノーカンだ。だが、昼メシ時の定食屋や、帰りに寄ったスーパーで顔を合わせるのは、どうだ?
いやいや、あの定食屋は、安くて美味い。顔を合わせて然るべきだ。
それならば、あのスーパーも、赤井の高級マンションと降谷のヴィンテージマンションの真ん中に位置するのだから、必然ではないか。
それで納得しよう。
降谷は、無理やり、自分の中の奇妙な焦燥感を落ち着けた。
「最近、よく会うな」
赤井の方は、そんな降谷の葛藤にはお構いなしだ。
「ですね」
「昨日も、駅前のコーヒー屋で見かけたよ。電話中のようだから、声はかけなかったが」
「へ⁉︎」
「ん?」
昨日、コーヒー屋に寄ったのは昼の三時頃というおかしな時間帯だ。何故、そんな時間に赤井が通りかかる?いや、通り掛かっただけだ。あり得る。
「あ、いや、声を掛けてくれれば、良かったのに、はは」
やばい。
降谷はメニューを見る振りで、赤井から目を逸らした。
やばい。なんだか、運命めいたものを感じてきた。
いやいや、切っても切れない因縁の相手だぞ、そりゃ、そうだろう。きっと死ぬまで、この男との縁は続く。いわゆる悪縁だ。
やばい。
自分で言った事に振り回され始めてる。
「最近、暑くなってきたな」
赤井が徐に年中被ってるニットギャップを取った。
はらりと前髪が額にかかる。
腕まくりの前腕、ボタンを二つ外した胸元、皮肉げな笑い方。
やばい。やけに赤井がセクシーに見えてきた。
「今年も暑そうですね。オフィスも、前倒しで、ノーネクタイを励行すべきかもしれません」
「あ、あぁ。なんで、君、ネクタイを締め直したんだ、暑いだろ」
「お気になさらず」
これは、少しも酔えないぞ。降谷は気を引き締め直した。
少しでも気を抜いたら、うっかり惚れてしまうかもしれない。
ほら、赤井の不思議そうに首を傾げる姿。ゴツい男のそんな仕草にすら、可愛げを感じている。
やばい。
テーブルには降谷の注文が届いた。
冷やしトマトに刺し盛り。暑くなってきたら、こういうものが食いたくなる。
対面で、赤井が、先程のようにふっと笑った。
「なんです?」
「君は気遣いができる人だから、取り分けやすそうなものを選んでくれたんだと思ってな」
無意識ですが!
意図せず、赤井の好感度を上げてしまった。
媚びてない!決して媚びてない!好かれようとしてない!
「そうだ、明日は休みだろう?」
「いやっ、仕事です」
仕事はない。しかし、言い切った。
明日、誘われでもしたら、決定打になるやもしれぬ。
絶対に、惚れたりしないからな!
「そうか、残念だ」
社交辞令でなく、本当に残念そうな赤井に、胸は痛むが、仕方ない。己の人生がかかっている。
あぁ、でも、何に誘ってくれるつもりだったのだろう。二人で、ドライブ?映画?意外と、デーゲームかも。それは楽しそうだ。
いやいや、行かないから。…でも、デーゲームなら行ってしまうかも。
いや、行かないって決めただろう。
でも、でも…。
降谷は全力で運命とやらに抗うのであった。
降谷はプロなので、それは偶然か?と穿って考えてしまった。
彼の奥さんもスポーツ選手だ。同じような行動範囲であれば、それは必然なのでは?…まぁ、野暮な考えだ。
「やぁ、また会ったな」
なので、今、この何やらの縁も、たいした意味はない。
降谷は、ひょいと手を挙げて挨拶をよした男、赤井に会釈で返しつつ「これは、当たり前のことだ。こいつと僕は、近所に住んでて、同じような生活レベルで、なので、これは」とぐるぐるする思考を放棄した。
降谷と赤井は同業者だ。二人とも捜査官で、同じ事件を解決させた仲でもある。今は、お互いの組織が協力体制にあるので、チームメイトといったところだろうか。
仲が良いかは、微妙。どちらかが死ぬしかないとまで思い詰めたことを思えば良好だ。
「あら、お知り合い?相席でよろしい?」
居酒屋のお母さんが、そこで立っている降谷に聞いた。
よろしい?よろしくはない。しかし、金曜の夜の居酒屋は混み合っている。この男のテーブルでなくカウンターに座ったら、他の客を一人待たせる事になる。
つまり、それは、お母さんに迷惑だ。
「あ、じゃ、僕、ビールで」
降谷はにこっと笑い、赤井の対面に腰掛けた。
「偶然だな」
赤井は、全く屈託なく、降谷を自分のテーブルに迎え入れた。
「貴方、居酒屋ってタイプじゃないでしょ」
「あぁ、晩飯代わりにな」
「へぇ」
そう言われると、何も言い返せない。降谷も同じだからだ。この居酒屋で、晩飯代わりに一杯飲むのが、週末の楽しみなのだ。
「はい、ビール」
お母さんがビールとお通しの酢の物を降谷の前に置いた。
「あ、あと、冷やしトマトと刺し盛りお願いします」
手渡されたお絞りで手を拭きつつ、注文を。目の端で、赤井がふっと笑う気配を感じた。
「お疲れ様」
「はぁ、どうも」
ごにょごにょと降谷の口は動きが悪くなった。
言い訳をさせて貰うなら、普段の降谷は、こんなまごまごした男ではない。
「乾杯」
赤井がコップを掲げた。彼のはハイボールだ。
降谷はついついそれにコップをカチンとぶつけた。
居酒屋の喧騒に、降谷の密やかな溜息は紛れて消えた。
さて、降谷が赤井という男との邂逅を偶然ではない必然だと足掻くのには理由があった。
つい、先だってのことだ。降谷が部下たちに「降谷さんは、どんな人となら結婚を考えますか?」と聞かれ、ふと、例のスーパースターを思い出し「そうだな、運命的な出会いというよりは、何故か何度も顔を合わせてしまうような、そんな縁のある相手なら、考えてしまうな」とかなんとか答えたのだ。
当然、深い考えではない。しかし、好みだとかそんなものは持ち合わせて無い降谷が、咄嗟に答えたのだから、案外、それは真理だったかもしれない。
それ故に、これが、偶然であっては困るのだ。
赤井とは、この一週間で何度も何度も顔を合わせている。仕事場は、同じオフィスに出勤しているのだからノーカンだ。だが、昼メシ時の定食屋や、帰りに寄ったスーパーで顔を合わせるのは、どうだ?
いやいや、あの定食屋は、安くて美味い。顔を合わせて然るべきだ。
それならば、あのスーパーも、赤井の高級マンションと降谷のヴィンテージマンションの真ん中に位置するのだから、必然ではないか。
それで納得しよう。
降谷は、無理やり、自分の中の奇妙な焦燥感を落ち着けた。
「最近、よく会うな」
赤井の方は、そんな降谷の葛藤にはお構いなしだ。
「ですね」
「昨日も、駅前のコーヒー屋で見かけたよ。電話中のようだから、声はかけなかったが」
「へ⁉︎」
「ん?」
昨日、コーヒー屋に寄ったのは昼の三時頃というおかしな時間帯だ。何故、そんな時間に赤井が通りかかる?いや、通り掛かっただけだ。あり得る。
「あ、いや、声を掛けてくれれば、良かったのに、はは」
やばい。
降谷はメニューを見る振りで、赤井から目を逸らした。
やばい。なんだか、運命めいたものを感じてきた。
いやいや、切っても切れない因縁の相手だぞ、そりゃ、そうだろう。きっと死ぬまで、この男との縁は続く。いわゆる悪縁だ。
やばい。
自分で言った事に振り回され始めてる。
「最近、暑くなってきたな」
赤井が徐に年中被ってるニットギャップを取った。
はらりと前髪が額にかかる。
腕まくりの前腕、ボタンを二つ外した胸元、皮肉げな笑い方。
やばい。やけに赤井がセクシーに見えてきた。
「今年も暑そうですね。オフィスも、前倒しで、ノーネクタイを励行すべきかもしれません」
「あ、あぁ。なんで、君、ネクタイを締め直したんだ、暑いだろ」
「お気になさらず」
これは、少しも酔えないぞ。降谷は気を引き締め直した。
少しでも気を抜いたら、うっかり惚れてしまうかもしれない。
ほら、赤井の不思議そうに首を傾げる姿。ゴツい男のそんな仕草にすら、可愛げを感じている。
やばい。
テーブルには降谷の注文が届いた。
冷やしトマトに刺し盛り。暑くなってきたら、こういうものが食いたくなる。
対面で、赤井が、先程のようにふっと笑った。
「なんです?」
「君は気遣いができる人だから、取り分けやすそうなものを選んでくれたんだと思ってな」
無意識ですが!
意図せず、赤井の好感度を上げてしまった。
媚びてない!決して媚びてない!好かれようとしてない!
「そうだ、明日は休みだろう?」
「いやっ、仕事です」
仕事はない。しかし、言い切った。
明日、誘われでもしたら、決定打になるやもしれぬ。
絶対に、惚れたりしないからな!
「そうか、残念だ」
社交辞令でなく、本当に残念そうな赤井に、胸は痛むが、仕方ない。己の人生がかかっている。
あぁ、でも、何に誘ってくれるつもりだったのだろう。二人で、ドライブ?映画?意外と、デーゲームかも。それは楽しそうだ。
いやいや、行かないから。…でも、デーゲームなら行ってしまうかも。
いや、行かないって決めただろう。
でも、でも…。
降谷は全力で運命とやらに抗うのであった。
1/1ページ