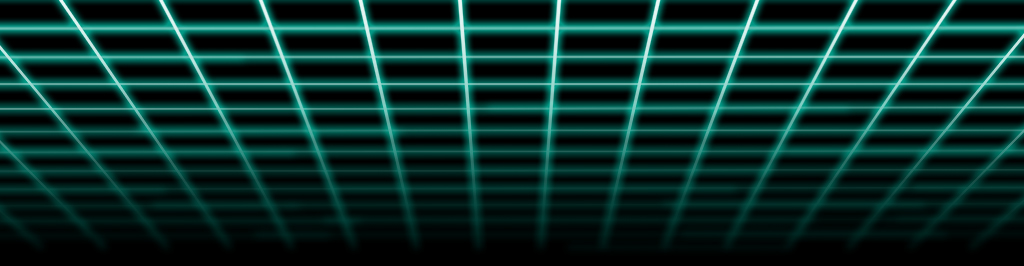黙示録の幻魔
件の『HAZAMA』というアプリは、正規のルートで配信されているわけではないらしく、すでにパソコンに落としてあったものをタブレット端末へとコピーした。一昨日、クタニが見つけたというアプリの解説動画を確認しながら、ひとつひとつ、手順を踏んで検証を進めていく。『HAZAMA』のアプリそのものは、シンプルな操作画面だったため、これにはそれほど時間をかけずにすんだ。
アプリを介してゲームのIDとパスワードを打ちこみ、ログインする。ほどなくして、画面の上部にファイルをダウンロードしていることを示す矢印が表示された。
「拡張子は……ePUGか。たしかに、電子魔術書だな」
コトハの後ろから端末の画面をのぞきこみ、フジイが言った。
「ファイルのダウンロードが終わったら、パソコンに送って。こっちで術式を見てみるから」
「わかりました」
クタニの指示どおりにすると、すぐにパソコンの画面が切り替わる。コトハには何がなんだかさっぱりわからない、奇妙な文字列が映しだされていた。電子魔術書の中身とは、こうなっているらしい。これまでは見ようと思ったこともなかったため、見るのは初めてだ。パソコンの画面に目を走らせていたマコトが、ぽつりと言った。
「この術式をざっと見たところだと、まずMANAで特殊な元素を生成してるな。もっと詳しく読み解かないと詳細はわからないが、地球上には存在しないものか」
「マコトさん。それって、つまり」
「作中でいうところの魔素、かもしれないな」
肩をすくめてにやりとしたマコトに、クタニの目がかがやく。とたん、フジイが鼻で笑った。
「ずいぶんと凝った演出してんなあ。どおりで術式読み解いただけで、ホンモノと勘違いする奴らがいるわけだ」
「あんたは、またそんなことを。まだわからないでしょ。本当に発動するかもしれない」
「バーカ。寝言は寝て言えってんだ。MANAだって、所詮はナノマシンなんだぜ? 魔術が現実になったって、科学の力さまさまだろうが。異世界の存在なんて信じられるか」
どうやら、このサークルも一枚岩というわけではないらしい。フジイと呼ばれていた男は、ちらとコトハを見やって哀れむように笑った。
「妹さんも大変だなあ。こんな茶番に付き合わされて」
「え、あ、いえ……それは、べつに」
しどろもどろになって、コトハは目をそらした。まさか、高校生にもなって、自分の育てた『使い魔』に会ってみたいだなんて、そんな子どもじみた夢想を口にできるわけもない。フジイに失笑されるだけだ。
「フジイ」
しびれをきらしたかのように、マコトが口を開いた。
「茶番呼ばわりは結構だが、検証中に結果を決めつけるもんじゃない。前にも言ったはずだぞ」
びくりと、フジイの肩がはねる。
「わ、わかってますよ……マコトさん」
マコトの機嫌をこれ以上そこねまいとして笑うフジイに、クタニがにやりとした。
「ははは、怒られた」
「うっせ」
小声でそんな応酬をする二人を、コトハがはらはらと見ていると、マコトが言った。
「コトハ、検証続行だ。とりあえず、さっきの電子魔術書をアプリから発動してくれ。お前の使い魔を召喚するんだ」
その声には、もう先ほどの苛立ちは残っていない。こういった切り替えの早さは、人に慕われる所以なのだろう。兄のようすに胸を撫でおろし、コトハはうなずいた。
「えっと、幻魔ハチフサ、幻魔メフィスの召喚をオーダーします」
そう宣言し、専用アプリから電子魔術書を開く。端末の画面を光の曲線が走った。魔術を行使するための魔方陣が、描きだされていく。ふいに、周囲の空気が変わった――そんな気がした。
光かがやく魔方陣が、画面を離れて宙へと浮かびあがる。同時、部室の床にも光る魔方陣が生じた。異なる紋様の陣が、ふたつ。閉めきられた部屋の中で、光の粒子をはらんだ風が、うずを巻いて吹き荒れる。コトハは息をのんだ。予感がした。これは、間違いなく、幼い日の自分が夢みた――
突如として、虎ほどはあろう体躯の白い犬が魔方陣の上に躍り出る。それに続いて、もうひとつの魔方陣にも人影が浮かんだ。寝間着のような白い服をまとう幼い少年だった。
少年の、癖のある黒髪が風に揺れ、赤い双眸が開かれる。同じくして、こうべを垂れていた犬が首をもたげる。ふたつの視線が、まっすぐにコトハを見つめる。どちらも、コトハにとっては馴染み深いものだった。
「きみが、コトハだよね?」
たしかな息づかいをともなって、少年が問いかけてくる。けれど、瞬きもできずにいるコトハをよそに、少年は無邪気に笑った。
「ずっと会ってみたかったんだ。ハジメマシテ、マスター」
少年――メフィスが、コトハの手を握る。その手は、おどろくほど冷たかったけれど、子どもらしい柔らかさと、肌のなめらかさがある。そして、なにより、質量があった。大きな身体をすり寄せてくるハチフサの動きだって、作りものめいたぎこちなさはない。夢ではない。幻でもない。ここに、たしかに、コトハの『使い魔』は存在している――
「マジかよ」
愕然として、フジイがこぼす。
「ほらほら、何か言うことあるんじゃないの」
にんまりしたクタニが肘でつつくと、フジイはしかめっ面になった。
「けど、そんな非現実的なこと」
「現実になってるんだから非現実ではないよな」
「……それは、そうですけど」
マコトの言葉にも言葉をにごすフジイは、よっぽど納得がいかないのか。それとも、自尊心が邪魔をして素直になれないだけなのか。初対面のコトハには、よくわからない。ただ、今こうしてコトハの目の前にいて、息をしている『使い魔』たちの存在を否定されるのは、なんだか悲しい。
三人のやりとりを眺めて立ち尽くすコトハの頬に、ふいに生温かい何かがふれた。ぎょっとして振り返る。湿っぽいそれは、犬型の幻魔――ハチフサの舌だった。
「ハチフサ……?」
コトハが目を丸くするかたわらで、ハチフサは鋭い牙の並ぶ口から舌を出して、じっと見つめてくる。メフィスが、くすりとした。
「元気を出してって、ハチフサが」
「え?」
「マスター、せっかく会えたのに悲しい顔をしてるから――それとも、マスターはぼくたちと会えてうれしくない?」
「そんなことない!」
思わず、声が大きくなってしまった。メフィスがきょとりと目を丸くして、それから、またにこりとする。
「うん、知ってる。マスターの想いは、ちゃんと伝わってたもの」
「私の、想い?」
「そうだよ」
と、メフィスは言った。
「ぼくたちを召喚の生贄にしなかったことも、今ここに召喚してくれたことも、すべてはマスターがぼくたちを好きでいてくれるからだ」
だからマスターには笑ってほしいんだ、ぼくもハチフサもマスターのことが大好きなんだもの――
しばらく、コトハは言葉が出てこなかった。ふくれあがった気持ちが、胸につかえて言葉にならない。こみあげそうになるものを隠すように、コトハは両手で『使い魔』たちを抱きしめた。
ああ、やっと。やっと、子どものころからの願いが、叶ったんだ。
胸のうちで呟いたそのとき、ふいにフジイが動いた。
「クタニ、俺にも『HAZAMA』アプリ送って」
「いいけど……何、どういう風の吹き回し?」
「ちょっとね」
そう言葉をにごしたと思うと、フジイはアプリから電子魔術書を書きだしていく。フジイのタブレット端末から、光る魔方陣が浮かびあがったとき。不敵に笑うフジイの目が、コトハを見た。
「ねえ、妹さん。俺の『使い魔』たちと演習してくれない?」
コトハは、目を瞬かせた。一方で、マコトの表情が硬くなる。
「お前、課金プレイヤーだろ。ランクはいくつだ」
「Bランクです。妹さんのランクより、二つくらいは上なんじゃないですかね」
ぎょっとして、コトハは声をあげた。
「私、まだEランクですよ」
「ああ、そうなの? それじゃ、三つは上になるのか」
なんてことのないように言って、フジイは床に浮かびあがる巨大な魔方陣を眺めた。
「このゲームって、同じランク帯のプレイヤーとしか演習できないでしょ。ここの人たち、ほとんど課金しないからランクあがるの遅くってさ。もうずっと演習できなくて、つまらなかったんだよね」
「そんな、だからって、実体のある『使い魔』で実際に戦ったりなんかしたら……」
魔方陣の中に、大きな影が揺らめきだす。知らず、コトハの身体は強ばった。けれど、フジイのオーダーが取り消されることはない。ハチフサが、庇うようにコトハの前へと出た。低い、うなり声が響く。しかし、フジイはそれを笑い飛ばした。
「たかだか初期幻魔が、俺の育てた『使い魔』に勝てるとでも思ってんのかね」
「おい、フジイ!」
マコトが声を荒げた。
「すぐにオーダーを取り消せ! これ以上は今回の検証内容に入ってない!」
「はは。マコトさんも、お兄さんですもんね。妹はかわいいですか」
「……フジイ、お前」
きつく、マコトの拳が握りしめられる。その瞬間だった。
突然、魔方陣を形成していた光が、弾ける。中に閉じこめられていた巨大な影が、フジイへと飛びかかった。フジイは受け身を取る間もなく転倒し、影の下敷きになる。部室にいる全員が、息を呑んだ。
フジイに襲いかかった「それ」は、まるでヘドロのかたまりのようだった。どろどろとしていて、いろんな絵の具をぐちゃぐちゃに混ぜたような、そんな色をしている。フジイの『使い魔』というのは、こんな姿をしていたのだろうか。だけれど、コトハはこんな幻魔をゲーム内で見たことがない――
「なんだよ、これ……! できそこないじゃねえか!」
「できそこない?」
奇怪な「それ」から逃れようともがくフジイを見つめ、メフィスは不思議そうに首をかしげた。
「それはきみのほうだよ。魔素が足りない状態で、ぼくたちを召喚しようとしたって、身体を生成できるはずがないんだから」
異様なほどに、その声は無邪気だった。「てめえ」と、フジイがメフィスを睨みあげる。
はっとして、クタニが叫んだ。
「そうか、コトハちゃんの召喚で周囲のMANAをほとんど消費しきったんだ! だから、魔素が生成できずに不完全な状態で」
「おい馬鹿、分析してる場合か! 早くなんとかしねえと、フジイが危ねえぞ!」
マコトが声を荒げ、手近にあった椅子をつかむ。大きく振りあげた椅子で、思いきり「それ」を殴りつけた。けれど、魔術によって呼びだされた「それ」――なりそこないの幻魔は、びくともしない。あわてたようすのクタニもハサミを手に立ち向かった。だが、ハサミを突き立てたところで、やはりなんの変化もない。まるで、呑みこもうとでもするかのように、幻魔はフジイへと覆いかぶさっていく。
業を煮やしたマコトが、力尽くで引きはがしにかかった。クタニも、あとに続く。
「フジイから離れろ!」
怒鳴りながら未知の生物と格闘する兄。そして、その後輩。それは、あまりにも現実味のない光景だった。呆然と立ち尽くすコトハの袖を、ふいにメフィスが引っぱる。
「ねえマスター、魔素をちょうだい」
「え……」
「ぼく、彼とは友達だったんだ。こんな姿になってしまっているのは、見ていられないよ」
メフィスの言う「彼」とは、あの幻魔のことだろうか。とはいえ、魔素を生成するだけのMANAがこの部屋に残っているとは思えない。部室を出ようにも、出入り口となるドアは幻魔の身体によってふさがれている――
逡巡し、コトハはふとハチフサを見た。その背はコトハの腰よりも高いが、馬ほど高くはない。ならば、あるいは。
意を決して、コトハはハチフサの背にまたがった。
「ハチフサ、お願い。私を部屋の外に連れていって」
「コトハ?」
マコトがおどろいた顔で振り返る。しかし、続く言葉はハチフサの遠吠えによってかき消された。
床を蹴って跳躍したハチフサが、窓を突きやぶって外へと飛び出す。無数のガラス片が、周囲を飛び散った。鋭い切っ先が、コトハの肌をすべっていく。コトハは左腕で顔を庇いながら、眼下十数メートル下の裏庭を見やった。日の当たらないそこに今、人の姿はない。
ハチフサの背にしがみついたまま、手帳型のタブレット端末を開いた。周囲のMANA濃度を示す数値が、一気にあがっていく。片手で魔素の生成をオーダーし、コトハは叫んだ。
「メフィス!」
――ありがとう、マスター。
ささやくようなメフィスの声が、耳もとで聞こえたような気がした。
振りあおいだ部室の窓から、どす黒い靄のようなものがあふれ出す。けれども、それは刹那の閃光とともに、消え去った。
ハチフサが着地し、その衝撃でコトハは地面に転げ落ちた。頭をしたたかに打ちつけ、意識が飛びそうになる。ぐらぐらと、世界が揺れているようだった。ハチフサが鼻を鳴らし、コトハの顔を覗きこんでくる。心配してくれているのだろうか。コトハは薄く笑って、手を伸ばした。
「ありがと」
青空を背に、校舎の窓から誰かが手を振っている。おいコトハ無事か――
※
病院でコトハの目が覚めたとき。そこにはもう、ハチフサもメフィスもいなかった。
付き添ってくれていたマコトの話によれば、なりそこないの幻魔はメフィスの手によって消滅し、二体の幻魔たちはコトハの無事だけを確認して、もとの世界へと帰ったらしい。
「ぼくたちの姿を、ほかの人間に見られたら、きっときみたちも困るだろうからね」
メフィスは、そう意味深に笑っていたという。
「フジイのほうは外傷もなかったからな、今ごろはもう家に帰ってるはずだ」
「そっか、よかった」
ベッドの上で、ぽつりとコトハがこぼせば、マコトは眉根を寄せた。
「お前なあ、あんな目にあわされといて、なんでフジイの心配なんかしてんだよ」
たしかに、マコトの言うことはもっともなのだろうと思う。もっと、コトハは怒っていいし、怖がってもいいのだろう。だけど、
「あれは……あの電書魔術は、私がずっとあこがれてた『ほんとうの魔法』だから」
だから、その『魔法』で誰かが傷ついたりしてほしくない――
「だって、『魔法』はみんなを幸せにするようなものでなくちゃ。そうでしょ、お兄ちゃん」
そう言って、コトハは笑う。すると、マコトは呆れたような、困ったような、そんな顔で笑った。
「お前も大概馬鹿だよな」
そうして、「医者を呼んでくる」と立ちあがり、ふと思い出したようにコトハを振り返った。
「ああ、そうだ。お前に言伝がある」
「え? 誰から?」
しかし、マコトは答えない。先ほどまでいたという両親からかとコトハが聞けば、黙って首を横に振る。では、誰だろうか。包帯を巻かれた頭を傾けていたら、マコトはにやりとした。
「また呼んでくれる日を待ってるね、だとさ――『マスター』?」
アプリを介してゲームのIDとパスワードを打ちこみ、ログインする。ほどなくして、画面の上部にファイルをダウンロードしていることを示す矢印が表示された。
「拡張子は……ePUGか。たしかに、電子魔術書だな」
コトハの後ろから端末の画面をのぞきこみ、フジイが言った。
「ファイルのダウンロードが終わったら、パソコンに送って。こっちで術式を見てみるから」
「わかりました」
クタニの指示どおりにすると、すぐにパソコンの画面が切り替わる。コトハには何がなんだかさっぱりわからない、奇妙な文字列が映しだされていた。電子魔術書の中身とは、こうなっているらしい。これまでは見ようと思ったこともなかったため、見るのは初めてだ。パソコンの画面に目を走らせていたマコトが、ぽつりと言った。
「この術式をざっと見たところだと、まずMANAで特殊な元素を生成してるな。もっと詳しく読み解かないと詳細はわからないが、地球上には存在しないものか」
「マコトさん。それって、つまり」
「作中でいうところの魔素、かもしれないな」
肩をすくめてにやりとしたマコトに、クタニの目がかがやく。とたん、フジイが鼻で笑った。
「ずいぶんと凝った演出してんなあ。どおりで術式読み解いただけで、ホンモノと勘違いする奴らがいるわけだ」
「あんたは、またそんなことを。まだわからないでしょ。本当に発動するかもしれない」
「バーカ。寝言は寝て言えってんだ。MANAだって、所詮はナノマシンなんだぜ? 魔術が現実になったって、科学の力さまさまだろうが。異世界の存在なんて信じられるか」
どうやら、このサークルも一枚岩というわけではないらしい。フジイと呼ばれていた男は、ちらとコトハを見やって哀れむように笑った。
「妹さんも大変だなあ。こんな茶番に付き合わされて」
「え、あ、いえ……それは、べつに」
しどろもどろになって、コトハは目をそらした。まさか、高校生にもなって、自分の育てた『使い魔』に会ってみたいだなんて、そんな子どもじみた夢想を口にできるわけもない。フジイに失笑されるだけだ。
「フジイ」
しびれをきらしたかのように、マコトが口を開いた。
「茶番呼ばわりは結構だが、検証中に結果を決めつけるもんじゃない。前にも言ったはずだぞ」
びくりと、フジイの肩がはねる。
「わ、わかってますよ……マコトさん」
マコトの機嫌をこれ以上そこねまいとして笑うフジイに、クタニがにやりとした。
「ははは、怒られた」
「うっせ」
小声でそんな応酬をする二人を、コトハがはらはらと見ていると、マコトが言った。
「コトハ、検証続行だ。とりあえず、さっきの電子魔術書をアプリから発動してくれ。お前の使い魔を召喚するんだ」
その声には、もう先ほどの苛立ちは残っていない。こういった切り替えの早さは、人に慕われる所以なのだろう。兄のようすに胸を撫でおろし、コトハはうなずいた。
「えっと、幻魔ハチフサ、幻魔メフィスの召喚をオーダーします」
そう宣言し、専用アプリから電子魔術書を開く。端末の画面を光の曲線が走った。魔術を行使するための魔方陣が、描きだされていく。ふいに、周囲の空気が変わった――そんな気がした。
光かがやく魔方陣が、画面を離れて宙へと浮かびあがる。同時、部室の床にも光る魔方陣が生じた。異なる紋様の陣が、ふたつ。閉めきられた部屋の中で、光の粒子をはらんだ風が、うずを巻いて吹き荒れる。コトハは息をのんだ。予感がした。これは、間違いなく、幼い日の自分が夢みた――
突如として、虎ほどはあろう体躯の白い犬が魔方陣の上に躍り出る。それに続いて、もうひとつの魔方陣にも人影が浮かんだ。寝間着のような白い服をまとう幼い少年だった。
少年の、癖のある黒髪が風に揺れ、赤い双眸が開かれる。同じくして、こうべを垂れていた犬が首をもたげる。ふたつの視線が、まっすぐにコトハを見つめる。どちらも、コトハにとっては馴染み深いものだった。
「きみが、コトハだよね?」
たしかな息づかいをともなって、少年が問いかけてくる。けれど、瞬きもできずにいるコトハをよそに、少年は無邪気に笑った。
「ずっと会ってみたかったんだ。ハジメマシテ、マスター」
少年――メフィスが、コトハの手を握る。その手は、おどろくほど冷たかったけれど、子どもらしい柔らかさと、肌のなめらかさがある。そして、なにより、質量があった。大きな身体をすり寄せてくるハチフサの動きだって、作りものめいたぎこちなさはない。夢ではない。幻でもない。ここに、たしかに、コトハの『使い魔』は存在している――
「マジかよ」
愕然として、フジイがこぼす。
「ほらほら、何か言うことあるんじゃないの」
にんまりしたクタニが肘でつつくと、フジイはしかめっ面になった。
「けど、そんな非現実的なこと」
「現実になってるんだから非現実ではないよな」
「……それは、そうですけど」
マコトの言葉にも言葉をにごすフジイは、よっぽど納得がいかないのか。それとも、自尊心が邪魔をして素直になれないだけなのか。初対面のコトハには、よくわからない。ただ、今こうしてコトハの目の前にいて、息をしている『使い魔』たちの存在を否定されるのは、なんだか悲しい。
三人のやりとりを眺めて立ち尽くすコトハの頬に、ふいに生温かい何かがふれた。ぎょっとして振り返る。湿っぽいそれは、犬型の幻魔――ハチフサの舌だった。
「ハチフサ……?」
コトハが目を丸くするかたわらで、ハチフサは鋭い牙の並ぶ口から舌を出して、じっと見つめてくる。メフィスが、くすりとした。
「元気を出してって、ハチフサが」
「え?」
「マスター、せっかく会えたのに悲しい顔をしてるから――それとも、マスターはぼくたちと会えてうれしくない?」
「そんなことない!」
思わず、声が大きくなってしまった。メフィスがきょとりと目を丸くして、それから、またにこりとする。
「うん、知ってる。マスターの想いは、ちゃんと伝わってたもの」
「私の、想い?」
「そうだよ」
と、メフィスは言った。
「ぼくたちを召喚の生贄にしなかったことも、今ここに召喚してくれたことも、すべてはマスターがぼくたちを好きでいてくれるからだ」
だからマスターには笑ってほしいんだ、ぼくもハチフサもマスターのことが大好きなんだもの――
しばらく、コトハは言葉が出てこなかった。ふくれあがった気持ちが、胸につかえて言葉にならない。こみあげそうになるものを隠すように、コトハは両手で『使い魔』たちを抱きしめた。
ああ、やっと。やっと、子どものころからの願いが、叶ったんだ。
胸のうちで呟いたそのとき、ふいにフジイが動いた。
「クタニ、俺にも『HAZAMA』アプリ送って」
「いいけど……何、どういう風の吹き回し?」
「ちょっとね」
そう言葉をにごしたと思うと、フジイはアプリから電子魔術書を書きだしていく。フジイのタブレット端末から、光る魔方陣が浮かびあがったとき。不敵に笑うフジイの目が、コトハを見た。
「ねえ、妹さん。俺の『使い魔』たちと演習してくれない?」
コトハは、目を瞬かせた。一方で、マコトの表情が硬くなる。
「お前、課金プレイヤーだろ。ランクはいくつだ」
「Bランクです。妹さんのランクより、二つくらいは上なんじゃないですかね」
ぎょっとして、コトハは声をあげた。
「私、まだEランクですよ」
「ああ、そうなの? それじゃ、三つは上になるのか」
なんてことのないように言って、フジイは床に浮かびあがる巨大な魔方陣を眺めた。
「このゲームって、同じランク帯のプレイヤーとしか演習できないでしょ。ここの人たち、ほとんど課金しないからランクあがるの遅くってさ。もうずっと演習できなくて、つまらなかったんだよね」
「そんな、だからって、実体のある『使い魔』で実際に戦ったりなんかしたら……」
魔方陣の中に、大きな影が揺らめきだす。知らず、コトハの身体は強ばった。けれど、フジイのオーダーが取り消されることはない。ハチフサが、庇うようにコトハの前へと出た。低い、うなり声が響く。しかし、フジイはそれを笑い飛ばした。
「たかだか初期幻魔が、俺の育てた『使い魔』に勝てるとでも思ってんのかね」
「おい、フジイ!」
マコトが声を荒げた。
「すぐにオーダーを取り消せ! これ以上は今回の検証内容に入ってない!」
「はは。マコトさんも、お兄さんですもんね。妹はかわいいですか」
「……フジイ、お前」
きつく、マコトの拳が握りしめられる。その瞬間だった。
突然、魔方陣を形成していた光が、弾ける。中に閉じこめられていた巨大な影が、フジイへと飛びかかった。フジイは受け身を取る間もなく転倒し、影の下敷きになる。部室にいる全員が、息を呑んだ。
フジイに襲いかかった「それ」は、まるでヘドロのかたまりのようだった。どろどろとしていて、いろんな絵の具をぐちゃぐちゃに混ぜたような、そんな色をしている。フジイの『使い魔』というのは、こんな姿をしていたのだろうか。だけれど、コトハはこんな幻魔をゲーム内で見たことがない――
「なんだよ、これ……! できそこないじゃねえか!」
「できそこない?」
奇怪な「それ」から逃れようともがくフジイを見つめ、メフィスは不思議そうに首をかしげた。
「それはきみのほうだよ。魔素が足りない状態で、ぼくたちを召喚しようとしたって、身体を生成できるはずがないんだから」
異様なほどに、その声は無邪気だった。「てめえ」と、フジイがメフィスを睨みあげる。
はっとして、クタニが叫んだ。
「そうか、コトハちゃんの召喚で周囲のMANAをほとんど消費しきったんだ! だから、魔素が生成できずに不完全な状態で」
「おい馬鹿、分析してる場合か! 早くなんとかしねえと、フジイが危ねえぞ!」
マコトが声を荒げ、手近にあった椅子をつかむ。大きく振りあげた椅子で、思いきり「それ」を殴りつけた。けれど、魔術によって呼びだされた「それ」――なりそこないの幻魔は、びくともしない。あわてたようすのクタニもハサミを手に立ち向かった。だが、ハサミを突き立てたところで、やはりなんの変化もない。まるで、呑みこもうとでもするかのように、幻魔はフジイへと覆いかぶさっていく。
業を煮やしたマコトが、力尽くで引きはがしにかかった。クタニも、あとに続く。
「フジイから離れろ!」
怒鳴りながら未知の生物と格闘する兄。そして、その後輩。それは、あまりにも現実味のない光景だった。呆然と立ち尽くすコトハの袖を、ふいにメフィスが引っぱる。
「ねえマスター、魔素をちょうだい」
「え……」
「ぼく、彼とは友達だったんだ。こんな姿になってしまっているのは、見ていられないよ」
メフィスの言う「彼」とは、あの幻魔のことだろうか。とはいえ、魔素を生成するだけのMANAがこの部屋に残っているとは思えない。部室を出ようにも、出入り口となるドアは幻魔の身体によってふさがれている――
逡巡し、コトハはふとハチフサを見た。その背はコトハの腰よりも高いが、馬ほど高くはない。ならば、あるいは。
意を決して、コトハはハチフサの背にまたがった。
「ハチフサ、お願い。私を部屋の外に連れていって」
「コトハ?」
マコトがおどろいた顔で振り返る。しかし、続く言葉はハチフサの遠吠えによってかき消された。
床を蹴って跳躍したハチフサが、窓を突きやぶって外へと飛び出す。無数のガラス片が、周囲を飛び散った。鋭い切っ先が、コトハの肌をすべっていく。コトハは左腕で顔を庇いながら、眼下十数メートル下の裏庭を見やった。日の当たらないそこに今、人の姿はない。
ハチフサの背にしがみついたまま、手帳型のタブレット端末を開いた。周囲のMANA濃度を示す数値が、一気にあがっていく。片手で魔素の生成をオーダーし、コトハは叫んだ。
「メフィス!」
――ありがとう、マスター。
ささやくようなメフィスの声が、耳もとで聞こえたような気がした。
振りあおいだ部室の窓から、どす黒い靄のようなものがあふれ出す。けれども、それは刹那の閃光とともに、消え去った。
ハチフサが着地し、その衝撃でコトハは地面に転げ落ちた。頭をしたたかに打ちつけ、意識が飛びそうになる。ぐらぐらと、世界が揺れているようだった。ハチフサが鼻を鳴らし、コトハの顔を覗きこんでくる。心配してくれているのだろうか。コトハは薄く笑って、手を伸ばした。
「ありがと」
青空を背に、校舎の窓から誰かが手を振っている。おいコトハ無事か――
※
病院でコトハの目が覚めたとき。そこにはもう、ハチフサもメフィスもいなかった。
付き添ってくれていたマコトの話によれば、なりそこないの幻魔はメフィスの手によって消滅し、二体の幻魔たちはコトハの無事だけを確認して、もとの世界へと帰ったらしい。
「ぼくたちの姿を、ほかの人間に見られたら、きっときみたちも困るだろうからね」
メフィスは、そう意味深に笑っていたという。
「フジイのほうは外傷もなかったからな、今ごろはもう家に帰ってるはずだ」
「そっか、よかった」
ベッドの上で、ぽつりとコトハがこぼせば、マコトは眉根を寄せた。
「お前なあ、あんな目にあわされといて、なんでフジイの心配なんかしてんだよ」
たしかに、マコトの言うことはもっともなのだろうと思う。もっと、コトハは怒っていいし、怖がってもいいのだろう。だけど、
「あれは……あの電書魔術は、私がずっとあこがれてた『ほんとうの魔法』だから」
だから、その『魔法』で誰かが傷ついたりしてほしくない――
「だって、『魔法』はみんなを幸せにするようなものでなくちゃ。そうでしょ、お兄ちゃん」
そう言って、コトハは笑う。すると、マコトは呆れたような、困ったような、そんな顔で笑った。
「お前も大概馬鹿だよな」
そうして、「医者を呼んでくる」と立ちあがり、ふと思い出したようにコトハを振り返った。
「ああ、そうだ。お前に言伝がある」
「え? 誰から?」
しかし、マコトは答えない。先ほどまでいたという両親からかとコトハが聞けば、黙って首を横に振る。では、誰だろうか。包帯を巻かれた頭を傾けていたら、マコトはにやりとした。
「また呼んでくれる日を待ってるね、だとさ――『マスター』?」
2/2ページ