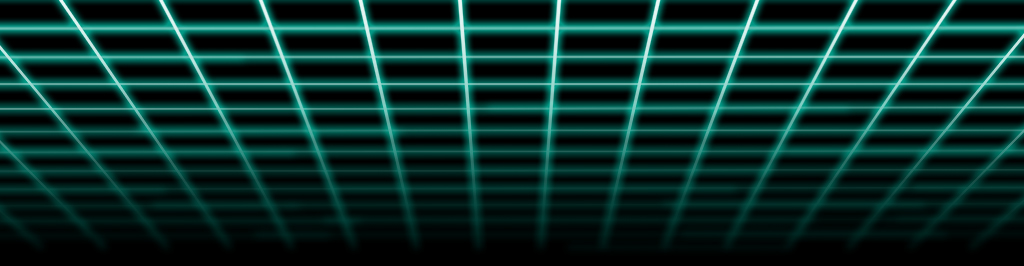黙示録の幻魔
遠くから、鐘の鳴る音がする。書物から顔をあげて耳を澄ませば、打ち鳴らされる鐘は短い間隔できっちり五回。演習の時間を報せる合図だ。
もうそんな時間なのかと思いながら、青年は魔導書を閉じる。かたわらで丸くなっていた猫型の幻魔が、緑色の瞳を瞬かせた。言葉を発することのできない動物型の下級幻魔だが、ある程度付き合いが長くなると、言わんとすることくらいはわかるようになる。青年は壁にかけた外套を羽織って、帽子を目深にかぶった。
「今日の演習には参加する。このままでは月別課題が達成できない」
軽く身支度を整え、未だに身体を丸めている黒猫を目で急かす。これを受けて、ようやく黒猫の幻魔も身体を起こした。
学院都市から貸し与えられた魔導工房を出て、空を仰ぐ。頭上では、黒い影が円を描くように飛んでいた。指笛を鳴らし腕を掲げてやれば、力強い羽音とともに鳥の姿をした幻魔が舞い降りる。
「準備は整ったな」
誰にともなく呟き、青年は自らが使役する二体の幻魔を引き連れ、演習場へと向かった。
ところが、到着した演習場で青年が引き合わされたのは、大よそ学院の生徒とは思えない幼い子どもだった。見たところでは、齢十にも満たない少年。連れているのは、白い犬型の幻魔が一体のみ――足もとの黒猫が相手方の幻魔を見て不機嫌そうにしっぽを揺らしたが、青年はそれを黙殺した。
両手で大切そうに小型の電子端末を持つ少年が、青年を見あげる。赤い瞳が、ひとつ瞬きをした。
「ふうん。そっちの使い魔は二体なんだ? このランク帯だと少ないほうだけど……もしかして、魔素の生成が追いつかないの?」
本来なら異界に存在する幻魔を召喚し、この物質世界に留めておくには、魔素とよばれる力が必要不可欠となる。魔素自体は、自然界にも多かれ少なかれ存在しているものの、魔導で使用される魔素のほとんどは術者の体内で生成されるものだ。そのため、魔素の生成量は、しばしば術者の力量を測るための目安として扱われる。
おそらく、少年には深い意図などなかったのだろうが、挑発とも取られかねない発言に、青年は密かに眉を寄せた。
主人を馬鹿にされたと思ったのだろう。肩に留まる鳥型幻魔が、憤慨したようにくちばしを鳴らす。不思議そうに、少年が首をかしげた。青年は苛立つ幻魔を手で制して、少年に言葉を向ける。
「滅多なことは言わないほうがいい――そういうお前の使い魔は、一体だけなのか」
すると、少年は青年へと視線を移して、かぶりを振った。
「残念だけれど、使い魔は一体だけじゃないよ」
青年の頭に、疑問が浮かんだ。目だけで周囲を見渡してみるも、それらしき姿は見当たらない。
「どこにいるんだ」
怪訝に思って問えば、少年は表情ひとつ変えることなく答えた。「ここだよ」
小さな手のひらを自らの胸に当てて、少年が屈託なく笑う。
「ぼくは、幻魔メフィス。そこにいる幻魔ハチフサと同じ、使い魔だよ」
そうして、自らを幻魔であると名乗った少年は、にこにこと言うのだ。そうだ、せっかくだからぼくたちのマスターも紹介するね――
青年へと向けられる、電子端末。煌々と光を放つ端末の画面には、ひとつの名前が表示されていた。
※
「コトハ」
名前を呼ばれて、コトハは顔をあげた。タブレット端末の画面に伸ばしていた指が、宙で止まる。
「あれ、お兄ちゃん」
バス停に並ぶコトハの横には、いつの間にか、年の離れた兄マコトの姿があった。思わず、目を瞬かせる。
「なんでこんなとこにいるの、大学は?」
「教授の用事で今日は午前まで」
返ってきた答えに、コトハは「はあ」と、気のない返事をするしかなかった。
マコトは、隣町の大学に通う院生だ。コトハが通っている高校前に設けられたバス停になんて、とんと用などないはずの人間である。ましてや、今日は大学が午前中までときているのだから、偶然出くわしただけ、とは考えられない。
コトハが怪訝な顔をしていれば、マコトは肩をすくめた。
「久しぶりに外食したいって、おふくろが」
「ああ、それで迎えにきてくれたんだ」
「そ。すぐそこの駐車場に車とめてあるんだけど、駅でおやじも拾うらしい」
なるほどそういうことならと、コトハはバス待ちの列から抜ける。後ろに並んでいた生徒がすぐに間を詰め、マコトはコトハが手にしたままの端末を見やった。
「お前んとこの使い魔、何体になった?」
「んー、まだ二体」
端末の画面に目を落とせば、起動しているゲームアプリが他プレイヤーとの戦闘処理をおこなっている。画面に表示されたこちらの『使い魔』を確認して、マコトは「マジで二体しかいねえ」と、呆れた風に笑った。
「だって、魔素がなかなか溜まらなくて」
「幻魔召喚に魔素だけしか使わないとか、どんな縛りプレイだよ」
からかうような口ぶりに、コトハは眉根を寄せる。
「いいの。こっち、中級幻魔いるから」
「言ってろ」
今度はマコトが眉を寄せて、言った。
「大体、生贄も課金アイテムも使ってないくせに、なんでお前んとこだけ中級が出るんだよ。おかしいだろ」
「ほら、ビギナーズラック」
「黙れ。事前登録組み」
サービス始まってから何ヶ月経ったと思ってんだよ。そう半目になるマコトに、けれど、コトハはへらりと笑って返す。直後、生意気だなんだと理由をつけられ、軽くデコピンをされた。どう考えても、未だに中級幻魔を手に入れられない人間の八つ当たりである。
「乱暴だなあ」
額をおさえてぼやきながら、コトハは端末の画面に映る自分の『使い魔』を見る。気づけば、戦闘はとっくに終了していた。珍しいことに、今回の戦績は芳しくない。どうやら、このランク帯では強いプレイヤーに当たってしまったらしかった。
災難だったなあと、胸のうちでひとりごつ。そうして、コトハは労わるように端末の画面をそっと撫でた。
※
工房の地下室で、うずくまるハチフサを背もたれにしながら、メフィスは手にした端末を眺める。暗がりで青く発光する画面には、演習の成績が映しだされている。結果は時間切れによる引き分けとして終わったのだけれど、メフィスの意識はそこにはなかった。頭に浮かぶのは、今回の演習相手の姿。
二体の幻魔を従えた、この学院の生徒。黒い外套と帽子をかぶった、黒づくめの青年。鋭い目つきと、落ち着いた雰囲気が印象的な人間だった。
この小さな端末越しに、いつも指示を出してくる自分たちの主人は、一体どんな人間なのだろう。
ふれることはおろか、言葉を交わすこともできない相手。どんな姿をしていて、どんな声でしゃべって、どんな考え方をするのか――メフィスにもハチフサにも、何ひとつわからない。はっきりとわかっているのは、「コトハ」という、その名前だけだ。
「ねえ、ハチフサ。ぼくたちのマスターは、どんなヒトだと思う?」
なんとはなしに、問いかける。同じ幻魔であるメフィスとハチフサの間に、人の言葉は必要ない。けれども、問いかけに対して答えあぐねているのか、ハチフサが応じる気配はない。メフィスは顔をあげ、机の上に積みあげられた課題報告用の紙を、じっと見つめた。
ここでは毎日、学院からいくつかの課題が出される。決まった数だけ演習に参加するというものであったり、学院外からの依頼をこなすというものであったり、その内容は多岐に渡る。端末に映しだされる指示は、いつだって課題の達成を優先としていた。メフィスやハチフサが知る限り、この主人が日課として出されるそれらを怠ったことはない――ただ、ひとつの課題をのぞいて。
手を伸ばし、メフィスは白紙の報告用紙を手に取る。とうに有効期限切れとなったそれには、メフィスとハチフサの主人が、頑ななまでに手をつけようとしなかった課題内容が記されていた。
――使役幻魔を生贄として、上級幻魔を召喚せよ。
強力な幻魔を従えて力をふるう「幻魔召喚師」にとって、下級幻魔を生贄にした召喚の儀式は日常的に行われている。幻魔召喚師になるべくして学院で魔導を学ぶ他の生徒たちだって、当たり前のように繰り返していることだ。
だのに、メフィスとハチフサの主人は、それをしない。学院の課題であっても、決して、それだけは指示しないのだ。中級幻魔であるメフィスが召喚されたときでさえ、生贄を使わず、膨大な魔素を代償としていた――
最初は、ただただ疑問でしかなかった。召喚師にとって、使い魔となった幻魔はただの道具でしかないだろうに、何を思って自分たちの主人は召喚の手段として生贄を選ばないのか。理解ができなかった。もとより、会話をすることもままならない相手なのだから、なおさらだ。
だけれど、最近になって思うことがある。
「この端末の向こうにいるヒトは、きっと、やさしいんだね」
ぽつりとメフィスが呟けば、ハチフサも今度は同意を示して、小さく吠えた。
※
外食先は、コトハがまだ小さかったころによく訪れたファミリーレストランだった。当時、コトハの両親は共働きだったため、仕事で帰りが遅くなったときは、よく家族でここへ来たものだった。十年ほど前に母が会社を辞め、専業主婦になってからというもの、もうずっと来ていない。自然と、思い出話に花が咲いた。あのころは大変だった、二人にはさびしい思いをさせた、マコトはコトハの面倒をよく見ていたね、兄妹仲がいいとご近所さんからは羨ましがられたものよ――
食事を終えたあとも、ドリンクバーで居座りながら、一家の団欒は続いた。そうして、ひとしきり思い出を語り合い、両親がトイレに立つ。ふいに、マコトが声をひそめて言った。
「お前、『HAZAMA』ってアプリ知ってるか?」
「ハザマ?」
コトハは、思わずきょとんとした。「ううん、知らないけど」
聞くところによると、それはコトハやマコトが遊んでいるゲーム――『黙示録の幻魔』と連動するアプリであるらしい。そのアプリを使用して、ゲームアカウントにログインすると、自動でゲームの進行状況が読み取られ、所持している幻魔の召喚術式をePUG形式の電子魔術書として書きだせるというのだ。
「それって、ハッキングじゃ」
「そうともいう」
しれっと返され、コトハは閉口した。悪びれる風もないのだから、いっそ潔いといえばいいのだろうか。
コトハはストローでジュースをかき混ぜながら、マコトを見た。
「でも、それってただの噂なんでしょ? あくまであれはゲームなんだし、実際に幻魔を召喚するなんてこと、できるわけないよ」
「まあな。ただ、幻魔が実在するかしないかはともかくとして、MANAを消費すれば幻魔を再現することは可能なはずだろ」
「うーん。そうなのかなあ」
全世界で、MANAと呼ばれるナノマシンが大量散布されたのは、数年前。特殊なSIMが搭載された端末からMANAに命令――オーダーをすることで、これまでおとぎ話の産物でしかなかった魔術を使えるようになったのは、本当に最近のことだ。正直なところ、電書魔術というもので、どれほどのことができるのか、コトハには皆目見当がつかない。
けれど、ネット上ではそのアプリ経由で幻魔を召喚したという書きこみが少なからずあるのだと、マコトは言った。
「俺の出入りしてるサークルでも、理論的には可能だろうって結論が出てる。だから、今度これを試してみようって話になってるんだ」
「ふうん」
院生というのは、案外、暇なものなのだろうか。そんなことを思いながら、コトハはジュースをひとくち飲んだ。甘酸っぱい柑橘類の味が口に広がる。
「それで、なんで私にそんな話するの?」
なるだけ、コトハは平静を装った。マコトが、にやりと笑う。
「不本意ながら、俺もサークル連中もリアルラックが極めて低くてな。どうせ召喚するなら中級以上の高位幻魔がいいだろ?」
なるほど。つまるところ、そういうことであるらしい。
かくして、コトハは噂の真偽を確かめんとする兄の手により、所属してもいないサークルの人柱として祭りあげられたのである。
この翌日。十三日の金曜日という、あまりにも不吉な日付もなんのその。善は急げをモットーとするマコトは、軽自動車に乗って校門までコトハを迎えに来た。「早く乗れ」と急かされ、コトハが助手席に滑りこめば、シートベルトをしめるよりも先に車が発進する。
「待ってよ、まだシートベルトしめてない!」
「そんなもの走りながらでいいだろ。誰も見てねえよ」
コトハの非難の声など、おかまいなしだった。運転中とはいえ、視線のひとつも寄こさない。兄からのぞんざいな扱いに、自然と眉が寄った。
「シートベルトは安全のためにつけるものなの。おまわりさん対策じゃないの」
「安心しろ。こんなところで事故るほど馬鹿じゃない」
マコトが一蹴した。
「それより、ちゃんと端末持ってるだろうな? 教室に置いてきたとか言うなよ?」
「ちゃんと持ってるよ」
制服のポケットから手帳型の端末を取り出して言うと、ここでようやくマコトの目が向く。コトハの手にある端末を確認して、「よしよし」と満足そうに笑った。
「サークルの連中も、楽しみにしてるからな。がっかりさせたくないんだよ」
「……成功する保証もないのに?」
「何事も興味をもって挑戦することに意義があるのさ。結果なんて二の次でいいんだよ。誰かと一緒になって、あれこれ準備しているときのほうが楽しいもんだ」
「ふうん」
窓の外へと目をやりながら、コトハはぽつりと呟いた。「そんなものかなあ」
かつて兄が所属し、院生になった今も頻繁に出入りしているそこは、「電書魔術サークル」という。その名のとおり、電書魔術に関係した活動をしているらしいのだが、コトハはあまりよく知らない。
というのも、コトハはマコトと違って、電書魔術にさほどの興味をもっていない。正しく言うのならば、もう、興味をもっていない。興味を、なくしてしまった。
もともと、コトハはゲームやファンタジー小説が大好きだった。魔法にあこがれ、ありもしない不思議なできごとを空想する。そんな子どもだった。だからこそ、試験運用されているという電書魔術の存在を知ったときには、それはもうすごいはしゃぎようだった。自分が大きくなるころには魔法が使えるようになる。そう思った。MANAが世界中で散布される日を、ただただ心待ちにしていた。
そうして、魔術というものが現実となった日。小学生だったコトハは、電書魔術に失望したのだ。現実となった魔術は、あまりにも想像とかけ離れていた。濡れたものを一瞬で乾かす魔術、付着した汚れを分解する魔術――たしかに便利ではあったけれど、どれも時間をかければ誰にでもできることばかり。不可能を可能にするような、幼いころからあこがれていた心躍る魔法なんて、どこにもなかった。
本音をいうのなら、コトハは今回の噂が本当であってほしいと、そう思っていた。ゲームを通し、愛着をもって育てた使い魔たちを召喚し、本当にふれあうことができたのなら。そうしたのなら、それこそ、遠い日のコトハが夢みた魔法の実現になるのに――
兄の通う大学を訪れるのは、二年前の学園祭以来だった。電書魔術サークルの部室は、第一校舎から少し歩いた先にあるメディア棟、その三階にあるのだという。おのぼりさんよろしく、コトハがキャンパス内をきょろきょろとしていると、「恥ずかしいからやめろ」と怒られた。しかたがなく、先をゆくマコトの背に顔を固定したものの、コトハの目はせわしなく動いてしまう。
「学園祭のときとは雰囲気が違うね」
「当たり前だろ。学生の本分は勉強だぞ? 毎日、あんなお祭り騒ぎでたまるか」
「でも、お兄ちゃん、今すごく浮かれてるのに」
とたん、頭に拳骨が降ってきた。
「いたい! なにするの!」
「キジも鳴かずば撃たれまいにってな」
素知らぬ顔で、しゃあしゃあとマコトは言い放つ。理不尽だ。コトハは、兄の背を恨みがましくねめつけた。
エレベーターで三階まであがると、マコトは部室と思しき部屋の戸を開けて中へと入る。コトハがあとに続けば、二人の学生が視線を寄こしてきた。おさげの女子学生と、眼鏡をかけた男子学生が、それぞれ一人ずつ。「あれ」と、マコトは声をあげた。
「なんだ。今日はアマクサはいないのか」
「アマクサだったら、バイト先の店長に呼びだされたとかで先に帰りましたよ」
「あいつ、とことん運がねえよなあ」
おさげの学生に続き、眼鏡の学生が言う。
「そうなのか」
マコトは小さく呟いたものの、「いないならしかたない」と、改めて部室を見渡した。
「まあ、事前にも伝えたように、今日は『HAZAMA』アプリの検証をおこなう。内容は、ゲームアプリと連動して電子魔術書を書きだせるか、そして、書きだされた電子魔術書が実際に活用できるかというものだ」
きびきびと説明をしていくマコトの姿は、家で見ている人物とはまるで別人である。「質問は?」と続けられた問いに、コトハは思わず、また余計なことを口走りそうになり、あわててこらえた。誰からも質問がないと見て取ると、マコトはコトハを振り返る。
「では、今回の検証の協力者を紹介させてもらう。俺の妹のコトハだ。召喚に魔素しか使わないというわけのわからん縛りプレイをしているくせに、中級幻魔を所持している」
「お兄ちゃん!」
余計なことまで暴露されて、思わず声をあげる。とたん、部員の二人が笑いだして、コトハは赤面した。
「その――コトハです。今日は、よろしくお願いします」
「こちらこそよろしくね、コトハちゃん」
おさげの学生が穏やかに言った。
「私はクタニ。あっちの眼鏡は、フジイだよ」
「どうも眼鏡です。よろしくね、妹さん」
ポケットにつっこんでいた片手をひらりと振って、眼鏡の学生が笑う。緊張しながらも、コトハはもう一度、二人に向かって頭をさげた。胸が、どきどきと高鳴っていた。
もうそんな時間なのかと思いながら、青年は魔導書を閉じる。かたわらで丸くなっていた猫型の幻魔が、緑色の瞳を瞬かせた。言葉を発することのできない動物型の下級幻魔だが、ある程度付き合いが長くなると、言わんとすることくらいはわかるようになる。青年は壁にかけた外套を羽織って、帽子を目深にかぶった。
「今日の演習には参加する。このままでは月別課題が達成できない」
軽く身支度を整え、未だに身体を丸めている黒猫を目で急かす。これを受けて、ようやく黒猫の幻魔も身体を起こした。
学院都市から貸し与えられた魔導工房を出て、空を仰ぐ。頭上では、黒い影が円を描くように飛んでいた。指笛を鳴らし腕を掲げてやれば、力強い羽音とともに鳥の姿をした幻魔が舞い降りる。
「準備は整ったな」
誰にともなく呟き、青年は自らが使役する二体の幻魔を引き連れ、演習場へと向かった。
ところが、到着した演習場で青年が引き合わされたのは、大よそ学院の生徒とは思えない幼い子どもだった。見たところでは、齢十にも満たない少年。連れているのは、白い犬型の幻魔が一体のみ――足もとの黒猫が相手方の幻魔を見て不機嫌そうにしっぽを揺らしたが、青年はそれを黙殺した。
両手で大切そうに小型の電子端末を持つ少年が、青年を見あげる。赤い瞳が、ひとつ瞬きをした。
「ふうん。そっちの使い魔は二体なんだ? このランク帯だと少ないほうだけど……もしかして、魔素の生成が追いつかないの?」
本来なら異界に存在する幻魔を召喚し、この物質世界に留めておくには、魔素とよばれる力が必要不可欠となる。魔素自体は、自然界にも多かれ少なかれ存在しているものの、魔導で使用される魔素のほとんどは術者の体内で生成されるものだ。そのため、魔素の生成量は、しばしば術者の力量を測るための目安として扱われる。
おそらく、少年には深い意図などなかったのだろうが、挑発とも取られかねない発言に、青年は密かに眉を寄せた。
主人を馬鹿にされたと思ったのだろう。肩に留まる鳥型幻魔が、憤慨したようにくちばしを鳴らす。不思議そうに、少年が首をかしげた。青年は苛立つ幻魔を手で制して、少年に言葉を向ける。
「滅多なことは言わないほうがいい――そういうお前の使い魔は、一体だけなのか」
すると、少年は青年へと視線を移して、かぶりを振った。
「残念だけれど、使い魔は一体だけじゃないよ」
青年の頭に、疑問が浮かんだ。目だけで周囲を見渡してみるも、それらしき姿は見当たらない。
「どこにいるんだ」
怪訝に思って問えば、少年は表情ひとつ変えることなく答えた。「ここだよ」
小さな手のひらを自らの胸に当てて、少年が屈託なく笑う。
「ぼくは、幻魔メフィス。そこにいる幻魔ハチフサと同じ、使い魔だよ」
そうして、自らを幻魔であると名乗った少年は、にこにこと言うのだ。そうだ、せっかくだからぼくたちのマスターも紹介するね――
青年へと向けられる、電子端末。煌々と光を放つ端末の画面には、ひとつの名前が表示されていた。
※
「コトハ」
名前を呼ばれて、コトハは顔をあげた。タブレット端末の画面に伸ばしていた指が、宙で止まる。
「あれ、お兄ちゃん」
バス停に並ぶコトハの横には、いつの間にか、年の離れた兄マコトの姿があった。思わず、目を瞬かせる。
「なんでこんなとこにいるの、大学は?」
「教授の用事で今日は午前まで」
返ってきた答えに、コトハは「はあ」と、気のない返事をするしかなかった。
マコトは、隣町の大学に通う院生だ。コトハが通っている高校前に設けられたバス停になんて、とんと用などないはずの人間である。ましてや、今日は大学が午前中までときているのだから、偶然出くわしただけ、とは考えられない。
コトハが怪訝な顔をしていれば、マコトは肩をすくめた。
「久しぶりに外食したいって、おふくろが」
「ああ、それで迎えにきてくれたんだ」
「そ。すぐそこの駐車場に車とめてあるんだけど、駅でおやじも拾うらしい」
なるほどそういうことならと、コトハはバス待ちの列から抜ける。後ろに並んでいた生徒がすぐに間を詰め、マコトはコトハが手にしたままの端末を見やった。
「お前んとこの使い魔、何体になった?」
「んー、まだ二体」
端末の画面に目を落とせば、起動しているゲームアプリが他プレイヤーとの戦闘処理をおこなっている。画面に表示されたこちらの『使い魔』を確認して、マコトは「マジで二体しかいねえ」と、呆れた風に笑った。
「だって、魔素がなかなか溜まらなくて」
「幻魔召喚に魔素だけしか使わないとか、どんな縛りプレイだよ」
からかうような口ぶりに、コトハは眉根を寄せる。
「いいの。こっち、中級幻魔いるから」
「言ってろ」
今度はマコトが眉を寄せて、言った。
「大体、生贄も課金アイテムも使ってないくせに、なんでお前んとこだけ中級が出るんだよ。おかしいだろ」
「ほら、ビギナーズラック」
「黙れ。事前登録組み」
サービス始まってから何ヶ月経ったと思ってんだよ。そう半目になるマコトに、けれど、コトハはへらりと笑って返す。直後、生意気だなんだと理由をつけられ、軽くデコピンをされた。どう考えても、未だに中級幻魔を手に入れられない人間の八つ当たりである。
「乱暴だなあ」
額をおさえてぼやきながら、コトハは端末の画面に映る自分の『使い魔』を見る。気づけば、戦闘はとっくに終了していた。珍しいことに、今回の戦績は芳しくない。どうやら、このランク帯では強いプレイヤーに当たってしまったらしかった。
災難だったなあと、胸のうちでひとりごつ。そうして、コトハは労わるように端末の画面をそっと撫でた。
※
工房の地下室で、うずくまるハチフサを背もたれにしながら、メフィスは手にした端末を眺める。暗がりで青く発光する画面には、演習の成績が映しだされている。結果は時間切れによる引き分けとして終わったのだけれど、メフィスの意識はそこにはなかった。頭に浮かぶのは、今回の演習相手の姿。
二体の幻魔を従えた、この学院の生徒。黒い外套と帽子をかぶった、黒づくめの青年。鋭い目つきと、落ち着いた雰囲気が印象的な人間だった。
この小さな端末越しに、いつも指示を出してくる自分たちの主人は、一体どんな人間なのだろう。
ふれることはおろか、言葉を交わすこともできない相手。どんな姿をしていて、どんな声でしゃべって、どんな考え方をするのか――メフィスにもハチフサにも、何ひとつわからない。はっきりとわかっているのは、「コトハ」という、その名前だけだ。
「ねえ、ハチフサ。ぼくたちのマスターは、どんなヒトだと思う?」
なんとはなしに、問いかける。同じ幻魔であるメフィスとハチフサの間に、人の言葉は必要ない。けれども、問いかけに対して答えあぐねているのか、ハチフサが応じる気配はない。メフィスは顔をあげ、机の上に積みあげられた課題報告用の紙を、じっと見つめた。
ここでは毎日、学院からいくつかの課題が出される。決まった数だけ演習に参加するというものであったり、学院外からの依頼をこなすというものであったり、その内容は多岐に渡る。端末に映しだされる指示は、いつだって課題の達成を優先としていた。メフィスやハチフサが知る限り、この主人が日課として出されるそれらを怠ったことはない――ただ、ひとつの課題をのぞいて。
手を伸ばし、メフィスは白紙の報告用紙を手に取る。とうに有効期限切れとなったそれには、メフィスとハチフサの主人が、頑ななまでに手をつけようとしなかった課題内容が記されていた。
――使役幻魔を生贄として、上級幻魔を召喚せよ。
強力な幻魔を従えて力をふるう「幻魔召喚師」にとって、下級幻魔を生贄にした召喚の儀式は日常的に行われている。幻魔召喚師になるべくして学院で魔導を学ぶ他の生徒たちだって、当たり前のように繰り返していることだ。
だのに、メフィスとハチフサの主人は、それをしない。学院の課題であっても、決して、それだけは指示しないのだ。中級幻魔であるメフィスが召喚されたときでさえ、生贄を使わず、膨大な魔素を代償としていた――
最初は、ただただ疑問でしかなかった。召喚師にとって、使い魔となった幻魔はただの道具でしかないだろうに、何を思って自分たちの主人は召喚の手段として生贄を選ばないのか。理解ができなかった。もとより、会話をすることもままならない相手なのだから、なおさらだ。
だけれど、最近になって思うことがある。
「この端末の向こうにいるヒトは、きっと、やさしいんだね」
ぽつりとメフィスが呟けば、ハチフサも今度は同意を示して、小さく吠えた。
※
外食先は、コトハがまだ小さかったころによく訪れたファミリーレストランだった。当時、コトハの両親は共働きだったため、仕事で帰りが遅くなったときは、よく家族でここへ来たものだった。十年ほど前に母が会社を辞め、専業主婦になってからというもの、もうずっと来ていない。自然と、思い出話に花が咲いた。あのころは大変だった、二人にはさびしい思いをさせた、マコトはコトハの面倒をよく見ていたね、兄妹仲がいいとご近所さんからは羨ましがられたものよ――
食事を終えたあとも、ドリンクバーで居座りながら、一家の団欒は続いた。そうして、ひとしきり思い出を語り合い、両親がトイレに立つ。ふいに、マコトが声をひそめて言った。
「お前、『HAZAMA』ってアプリ知ってるか?」
「ハザマ?」
コトハは、思わずきょとんとした。「ううん、知らないけど」
聞くところによると、それはコトハやマコトが遊んでいるゲーム――『黙示録の幻魔』と連動するアプリであるらしい。そのアプリを使用して、ゲームアカウントにログインすると、自動でゲームの進行状況が読み取られ、所持している幻魔の召喚術式をePUG形式の電子魔術書として書きだせるというのだ。
「それって、ハッキングじゃ」
「そうともいう」
しれっと返され、コトハは閉口した。悪びれる風もないのだから、いっそ潔いといえばいいのだろうか。
コトハはストローでジュースをかき混ぜながら、マコトを見た。
「でも、それってただの噂なんでしょ? あくまであれはゲームなんだし、実際に幻魔を召喚するなんてこと、できるわけないよ」
「まあな。ただ、幻魔が実在するかしないかはともかくとして、MANAを消費すれば幻魔を再現することは可能なはずだろ」
「うーん。そうなのかなあ」
全世界で、MANAと呼ばれるナノマシンが大量散布されたのは、数年前。特殊なSIMが搭載された端末からMANAに命令――オーダーをすることで、これまでおとぎ話の産物でしかなかった魔術を使えるようになったのは、本当に最近のことだ。正直なところ、電書魔術というもので、どれほどのことができるのか、コトハには皆目見当がつかない。
けれど、ネット上ではそのアプリ経由で幻魔を召喚したという書きこみが少なからずあるのだと、マコトは言った。
「俺の出入りしてるサークルでも、理論的には可能だろうって結論が出てる。だから、今度これを試してみようって話になってるんだ」
「ふうん」
院生というのは、案外、暇なものなのだろうか。そんなことを思いながら、コトハはジュースをひとくち飲んだ。甘酸っぱい柑橘類の味が口に広がる。
「それで、なんで私にそんな話するの?」
なるだけ、コトハは平静を装った。マコトが、にやりと笑う。
「不本意ながら、俺もサークル連中もリアルラックが極めて低くてな。どうせ召喚するなら中級以上の高位幻魔がいいだろ?」
なるほど。つまるところ、そういうことであるらしい。
かくして、コトハは噂の真偽を確かめんとする兄の手により、所属してもいないサークルの人柱として祭りあげられたのである。
この翌日。十三日の金曜日という、あまりにも不吉な日付もなんのその。善は急げをモットーとするマコトは、軽自動車に乗って校門までコトハを迎えに来た。「早く乗れ」と急かされ、コトハが助手席に滑りこめば、シートベルトをしめるよりも先に車が発進する。
「待ってよ、まだシートベルトしめてない!」
「そんなもの走りながらでいいだろ。誰も見てねえよ」
コトハの非難の声など、おかまいなしだった。運転中とはいえ、視線のひとつも寄こさない。兄からのぞんざいな扱いに、自然と眉が寄った。
「シートベルトは安全のためにつけるものなの。おまわりさん対策じゃないの」
「安心しろ。こんなところで事故るほど馬鹿じゃない」
マコトが一蹴した。
「それより、ちゃんと端末持ってるだろうな? 教室に置いてきたとか言うなよ?」
「ちゃんと持ってるよ」
制服のポケットから手帳型の端末を取り出して言うと、ここでようやくマコトの目が向く。コトハの手にある端末を確認して、「よしよし」と満足そうに笑った。
「サークルの連中も、楽しみにしてるからな。がっかりさせたくないんだよ」
「……成功する保証もないのに?」
「何事も興味をもって挑戦することに意義があるのさ。結果なんて二の次でいいんだよ。誰かと一緒になって、あれこれ準備しているときのほうが楽しいもんだ」
「ふうん」
窓の外へと目をやりながら、コトハはぽつりと呟いた。「そんなものかなあ」
かつて兄が所属し、院生になった今も頻繁に出入りしているそこは、「電書魔術サークル」という。その名のとおり、電書魔術に関係した活動をしているらしいのだが、コトハはあまりよく知らない。
というのも、コトハはマコトと違って、電書魔術にさほどの興味をもっていない。正しく言うのならば、もう、興味をもっていない。興味を、なくしてしまった。
もともと、コトハはゲームやファンタジー小説が大好きだった。魔法にあこがれ、ありもしない不思議なできごとを空想する。そんな子どもだった。だからこそ、試験運用されているという電書魔術の存在を知ったときには、それはもうすごいはしゃぎようだった。自分が大きくなるころには魔法が使えるようになる。そう思った。MANAが世界中で散布される日を、ただただ心待ちにしていた。
そうして、魔術というものが現実となった日。小学生だったコトハは、電書魔術に失望したのだ。現実となった魔術は、あまりにも想像とかけ離れていた。濡れたものを一瞬で乾かす魔術、付着した汚れを分解する魔術――たしかに便利ではあったけれど、どれも時間をかければ誰にでもできることばかり。不可能を可能にするような、幼いころからあこがれていた心躍る魔法なんて、どこにもなかった。
本音をいうのなら、コトハは今回の噂が本当であってほしいと、そう思っていた。ゲームを通し、愛着をもって育てた使い魔たちを召喚し、本当にふれあうことができたのなら。そうしたのなら、それこそ、遠い日のコトハが夢みた魔法の実現になるのに――
兄の通う大学を訪れるのは、二年前の学園祭以来だった。電書魔術サークルの部室は、第一校舎から少し歩いた先にあるメディア棟、その三階にあるのだという。おのぼりさんよろしく、コトハがキャンパス内をきょろきょろとしていると、「恥ずかしいからやめろ」と怒られた。しかたがなく、先をゆくマコトの背に顔を固定したものの、コトハの目はせわしなく動いてしまう。
「学園祭のときとは雰囲気が違うね」
「当たり前だろ。学生の本分は勉強だぞ? 毎日、あんなお祭り騒ぎでたまるか」
「でも、お兄ちゃん、今すごく浮かれてるのに」
とたん、頭に拳骨が降ってきた。
「いたい! なにするの!」
「キジも鳴かずば撃たれまいにってな」
素知らぬ顔で、しゃあしゃあとマコトは言い放つ。理不尽だ。コトハは、兄の背を恨みがましくねめつけた。
エレベーターで三階まであがると、マコトは部室と思しき部屋の戸を開けて中へと入る。コトハがあとに続けば、二人の学生が視線を寄こしてきた。おさげの女子学生と、眼鏡をかけた男子学生が、それぞれ一人ずつ。「あれ」と、マコトは声をあげた。
「なんだ。今日はアマクサはいないのか」
「アマクサだったら、バイト先の店長に呼びだされたとかで先に帰りましたよ」
「あいつ、とことん運がねえよなあ」
おさげの学生に続き、眼鏡の学生が言う。
「そうなのか」
マコトは小さく呟いたものの、「いないならしかたない」と、改めて部室を見渡した。
「まあ、事前にも伝えたように、今日は『HAZAMA』アプリの検証をおこなう。内容は、ゲームアプリと連動して電子魔術書を書きだせるか、そして、書きだされた電子魔術書が実際に活用できるかというものだ」
きびきびと説明をしていくマコトの姿は、家で見ている人物とはまるで別人である。「質問は?」と続けられた問いに、コトハは思わず、また余計なことを口走りそうになり、あわててこらえた。誰からも質問がないと見て取ると、マコトはコトハを振り返る。
「では、今回の検証の協力者を紹介させてもらう。俺の妹のコトハだ。召喚に魔素しか使わないというわけのわからん縛りプレイをしているくせに、中級幻魔を所持している」
「お兄ちゃん!」
余計なことまで暴露されて、思わず声をあげる。とたん、部員の二人が笑いだして、コトハは赤面した。
「その――コトハです。今日は、よろしくお願いします」
「こちらこそよろしくね、コトハちゃん」
おさげの学生が穏やかに言った。
「私はクタニ。あっちの眼鏡は、フジイだよ」
「どうも眼鏡です。よろしくね、妹さん」
ポケットにつっこんでいた片手をひらりと振って、眼鏡の学生が笑う。緊張しながらも、コトハはもう一度、二人に向かって頭をさげた。胸が、どきどきと高鳴っていた。
1/2ページ