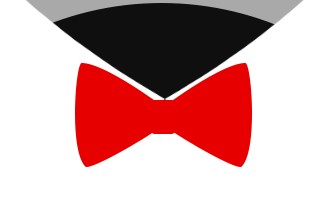フェイジュニ
【箱庭のヒュプノス】
こちらに来てすぐの夜、クソDJと一緒に眠ったチビDJが、今度はおれのベッドで寝たいと言い始めたのが始まりだった。
その提案に紛いなりにもおれのカレシであるクソDJは嫌そうな顔をしたが、それに関しては自分がリトルを甘やかしたのが発端だし、なによりリトルもクソDJなんだから問題はないはずだ。招き入れると「あったかいね」と満足そうに笑ってふよふよと寝息を立てるリトルの体温につられて、おれもいつの間にか眠ってしまっていた。
チビDJが過去に帰ってからというもの、アイツはいままでより少しだけ甘えたになった。
その最たることが「一緒のベッドで寝たい」というもので、付き合っているにしても毎日同じベッドだと身体が休まらないのではないかという心配を他所に、あれから毎晩おれとクソDJは同じベッドで眠っているのであった。
まだチビがいた頃「三人は狭いから無理だ」と拒否されたのが堪えたようで、重なり合って脚だってろくに伸ばせていないくせに「二人だとちょうどいいね」なんて強がる姿が可愛くて笑ってしまった。
「狭くて勝手悪いだろ」
「リトルが許されてたのに俺と寝るのは拒否するつもり?」
なんてあの頃と同じ甘い顔で言われてしまえば、それ以上反対する気も起きない。一緒に眠るようになって二週間。人肌を感じながら眠ることにすっかり慣れてしまったおれは、クソDJの腕枕を定位置としてぐっすり入眠できるまでになっていた。
毎朝起きると、ルベライトを秘めた長いまつ毛と通った鼻筋が目に入る。確かに青年じみた成長を見せながらも、リトルの頃から変わらない端正な顔立ちはいつもおれの心を掻き乱した。
◇◇◇
一週間の泊まりがけの任務が入ったのは、ちょうどその頃だった。
カジノへの潜入任務を経験していたおれは今回も意気揚々と任務地へと赴いたが、人肌のないビジネスホテルのベッドで眠れない夜を越してからは、普段通り部屋で過ごしているであろう恋人のことを思い出してしまっていた。寂しい。会いたい。温かい鼓動を感じながら、一緒に眠りたい。
キースに喝を入れられながらなんとか毎日を過ごしながらも、頭を締めるのはクソDJが愛おしそうにこちらを見る瞳だった。
アイツがいないとろくに眠れもしないなんて、恥ずかしい。帰ったら揶揄われないように、今晩だけでもどうにか眠れますように、と最後の夜を過ごした。
帰り着いて一番に感じたのは、違和感。フェイスはまだパトロール中で、長期任務から帰ってきたおれだけが部屋の中にいる。一週間前には何も感じなかった部屋の中をぐるりと見回して違和感の正体を探る。
乱雑に投げられたフェイスの部屋着に、机の上に放置されたままのショコラの空き箱。二人分のグラス。それから、嗅いだことのない女物の香水の匂い。見ちゃダメだって思ったのについ見てしまった、片方のグラスにべったりと付いた口紅。
おれと付き合い始めてから、女の子とはきっぱり別れたと聞いていた。実際にカノジョたちの影を感じることは無かったし、おれのことを本気で好きなのも本当なはずだ。だからこそ、アイツが浮気していると即座に弾き出した脳みそをブンブンと横に振った。まだ分からない。少し話しただけかもしれないし。
冷静になってアイツが帰ってくるのを待とう。そう思ってクソDJのベッドに腰掛けた瞬間、目に入ってしまったのだ。枕元に落ちている赤毛は、おれのものでも、ましてやクソDJのものでもない。
このベッドの中で、リトルと同じ顔で「あったかいね」とはにかんだクソDJが思い浮かぶ。おれも、アイツの中では満たされないものを埋める女の子たちと同じだったんだろうか。嘘だと思いたい心を、たった一週間留守にしただけの部屋中から否定されているようで、どうしようもなく泣きたくなった。
フェイスはそれからすぐに部屋に帰ってきた。まだ日も高い時間だ。「早かったな」と声をかけると驚いたようで、びくりと肩が跳ねる。
「おチビちゃんこそ、早かったね。帰ってくるの夜かと思ってた」
「思ってたより早く終わったんだ。それより、これ」
コイツ相手にまわりくどく話を切り出しても勝てるわけがない。世間話もそこそこに直球で話しかけると、ふいと目を逸らされた。机に放置されたクソDJお気に入りのショコラの空き箱と、空のグラスが一ミリだって動かずに答えを待っている。
「ああそれ、おチビちゃんとキースがいない間にディノとパーティしたんだよ。帰ってくる前に片付けようと思ってたんだけど」
「へえ、ディノにいいルージュ付けてるなって言っといてくれよ」
隠そうとしたその態度が、どうしようもなく悲しかった。お前がいないとうまく眠れなかった、なんて笑い話にするつもりだった。おれが眠れなかったその間中、コイツは“赤毛のディノ”とグースカ寝てたっていうのに。
「ごめん、ゴメン…。おねがい、ゆるして」
コイツの口から出たのは、想像していたより弱々しい謝罪と懇願の言葉だった。舌ったらずなそれは、いつかのリトルを思い出させて心が痛んだ。
「許せないよ。おれはもうお前と眠れない」
いやだ、と駄々っ子のような呟きは聞こえないふりをした。嫌だと言いたいのはおれの方だ。おれの心の中に勝手に入ってきたかと思えば、身も心も虜にして、挙句には浮気して。女の子とは全部縁を切ったと、そんな言葉を鵜呑みにしたのがバカだったのだ。
「眠るために女の子と寝てた過去があるのは事実。これからもそれは変えられないし、今回もそのつもりだった。黙ってればバレないだろうって…でも」
言い訳がましいその言葉を聞きたくなくて目を逸らそうとした瞬間、普段は血色がいい顔にうっすらとクマが浮かんでいるのが見えた。泣き腫らしたのか、遊び人の二つ名が逃げ出しそうなほど瞼は重くなっていて、異様とも言えるその姿に驚いてしまった。
「おチビちゃんじゃないと、とっくに眠れなくなってた」
あ、と小さな声が漏れた。おれの代わりに、女の子を連れ込んだのは本当に許せない。だけどいざ眠ろうとして、どんな手を使っても、おれ以外の誰と寝ようとしてもうまく眠れないコイツの姿を想像しただけで、どうしようもなく愛おしいという感情が溢れてしまった。
この大きな恋人は、駄々をこねておれのベッドに潜り込んできたあの幼な子と結局のところ同じなのだ。自分一人ではどうしたらいいか分からなくて、誰かの温もりが欲しくて、気軽に手を取ってくれる相手に助けを求めてしまう。
リトルがブラッドの温もりを欲していたように、クソDJはおれのことを求めてくれていたんだと考えると、上手くは言えないけれど信じてあげたいと思うのだ。それと同時に、眠れなかったのはおれだけじゃなかったんだと、名付けようもない欲のようなものが満たされるのを感じていた。
「…もう二度とすんなよ」
「お願いされたってしないよ」
おれをぎゅっと抱きしめたフェイスは、そのまま自分のベッドに倒れ込む。さっきまで冷たくなっていたそこは、すぐにクソDJの香りと体温で満たされる。
安心した途端、一週間分の寝不足が身体を襲う。ゆっくりと閉じていく瞼の向こう側には、あどけない恋人の安らかな寝顔が見えた。ああどうか、コイツがこんな顔を見せてくれるのは今後おれの前だけでありますように。
こちらに来てすぐの夜、クソDJと一緒に眠ったチビDJが、今度はおれのベッドで寝たいと言い始めたのが始まりだった。
その提案に紛いなりにもおれのカレシであるクソDJは嫌そうな顔をしたが、それに関しては自分がリトルを甘やかしたのが発端だし、なによりリトルもクソDJなんだから問題はないはずだ。招き入れると「あったかいね」と満足そうに笑ってふよふよと寝息を立てるリトルの体温につられて、おれもいつの間にか眠ってしまっていた。
チビDJが過去に帰ってからというもの、アイツはいままでより少しだけ甘えたになった。
その最たることが「一緒のベッドで寝たい」というもので、付き合っているにしても毎日同じベッドだと身体が休まらないのではないかという心配を他所に、あれから毎晩おれとクソDJは同じベッドで眠っているのであった。
まだチビがいた頃「三人は狭いから無理だ」と拒否されたのが堪えたようで、重なり合って脚だってろくに伸ばせていないくせに「二人だとちょうどいいね」なんて強がる姿が可愛くて笑ってしまった。
「狭くて勝手悪いだろ」
「リトルが許されてたのに俺と寝るのは拒否するつもり?」
なんてあの頃と同じ甘い顔で言われてしまえば、それ以上反対する気も起きない。一緒に眠るようになって二週間。人肌を感じながら眠ることにすっかり慣れてしまったおれは、クソDJの腕枕を定位置としてぐっすり入眠できるまでになっていた。
毎朝起きると、ルベライトを秘めた長いまつ毛と通った鼻筋が目に入る。確かに青年じみた成長を見せながらも、リトルの頃から変わらない端正な顔立ちはいつもおれの心を掻き乱した。
◇◇◇
一週間の泊まりがけの任務が入ったのは、ちょうどその頃だった。
カジノへの潜入任務を経験していたおれは今回も意気揚々と任務地へと赴いたが、人肌のないビジネスホテルのベッドで眠れない夜を越してからは、普段通り部屋で過ごしているであろう恋人のことを思い出してしまっていた。寂しい。会いたい。温かい鼓動を感じながら、一緒に眠りたい。
キースに喝を入れられながらなんとか毎日を過ごしながらも、頭を締めるのはクソDJが愛おしそうにこちらを見る瞳だった。
アイツがいないとろくに眠れもしないなんて、恥ずかしい。帰ったら揶揄われないように、今晩だけでもどうにか眠れますように、と最後の夜を過ごした。
帰り着いて一番に感じたのは、違和感。フェイスはまだパトロール中で、長期任務から帰ってきたおれだけが部屋の中にいる。一週間前には何も感じなかった部屋の中をぐるりと見回して違和感の正体を探る。
乱雑に投げられたフェイスの部屋着に、机の上に放置されたままのショコラの空き箱。二人分のグラス。それから、嗅いだことのない女物の香水の匂い。見ちゃダメだって思ったのについ見てしまった、片方のグラスにべったりと付いた口紅。
おれと付き合い始めてから、女の子とはきっぱり別れたと聞いていた。実際にカノジョたちの影を感じることは無かったし、おれのことを本気で好きなのも本当なはずだ。だからこそ、アイツが浮気していると即座に弾き出した脳みそをブンブンと横に振った。まだ分からない。少し話しただけかもしれないし。
冷静になってアイツが帰ってくるのを待とう。そう思ってクソDJのベッドに腰掛けた瞬間、目に入ってしまったのだ。枕元に落ちている赤毛は、おれのものでも、ましてやクソDJのものでもない。
このベッドの中で、リトルと同じ顔で「あったかいね」とはにかんだクソDJが思い浮かぶ。おれも、アイツの中では満たされないものを埋める女の子たちと同じだったんだろうか。嘘だと思いたい心を、たった一週間留守にしただけの部屋中から否定されているようで、どうしようもなく泣きたくなった。
フェイスはそれからすぐに部屋に帰ってきた。まだ日も高い時間だ。「早かったな」と声をかけると驚いたようで、びくりと肩が跳ねる。
「おチビちゃんこそ、早かったね。帰ってくるの夜かと思ってた」
「思ってたより早く終わったんだ。それより、これ」
コイツ相手にまわりくどく話を切り出しても勝てるわけがない。世間話もそこそこに直球で話しかけると、ふいと目を逸らされた。机に放置されたクソDJお気に入りのショコラの空き箱と、空のグラスが一ミリだって動かずに答えを待っている。
「ああそれ、おチビちゃんとキースがいない間にディノとパーティしたんだよ。帰ってくる前に片付けようと思ってたんだけど」
「へえ、ディノにいいルージュ付けてるなって言っといてくれよ」
隠そうとしたその態度が、どうしようもなく悲しかった。お前がいないとうまく眠れなかった、なんて笑い話にするつもりだった。おれが眠れなかったその間中、コイツは“赤毛のディノ”とグースカ寝てたっていうのに。
「ごめん、ゴメン…。おねがい、ゆるして」
コイツの口から出たのは、想像していたより弱々しい謝罪と懇願の言葉だった。舌ったらずなそれは、いつかのリトルを思い出させて心が痛んだ。
「許せないよ。おれはもうお前と眠れない」
いやだ、と駄々っ子のような呟きは聞こえないふりをした。嫌だと言いたいのはおれの方だ。おれの心の中に勝手に入ってきたかと思えば、身も心も虜にして、挙句には浮気して。女の子とは全部縁を切ったと、そんな言葉を鵜呑みにしたのがバカだったのだ。
「眠るために女の子と寝てた過去があるのは事実。これからもそれは変えられないし、今回もそのつもりだった。黙ってればバレないだろうって…でも」
言い訳がましいその言葉を聞きたくなくて目を逸らそうとした瞬間、普段は血色がいい顔にうっすらとクマが浮かんでいるのが見えた。泣き腫らしたのか、遊び人の二つ名が逃げ出しそうなほど瞼は重くなっていて、異様とも言えるその姿に驚いてしまった。
「おチビちゃんじゃないと、とっくに眠れなくなってた」
あ、と小さな声が漏れた。おれの代わりに、女の子を連れ込んだのは本当に許せない。だけどいざ眠ろうとして、どんな手を使っても、おれ以外の誰と寝ようとしてもうまく眠れないコイツの姿を想像しただけで、どうしようもなく愛おしいという感情が溢れてしまった。
この大きな恋人は、駄々をこねておれのベッドに潜り込んできたあの幼な子と結局のところ同じなのだ。自分一人ではどうしたらいいか分からなくて、誰かの温もりが欲しくて、気軽に手を取ってくれる相手に助けを求めてしまう。
リトルがブラッドの温もりを欲していたように、クソDJはおれのことを求めてくれていたんだと考えると、上手くは言えないけれど信じてあげたいと思うのだ。それと同時に、眠れなかったのはおれだけじゃなかったんだと、名付けようもない欲のようなものが満たされるのを感じていた。
「…もう二度とすんなよ」
「お願いされたってしないよ」
おれをぎゅっと抱きしめたフェイスは、そのまま自分のベッドに倒れ込む。さっきまで冷たくなっていたそこは、すぐにクソDJの香りと体温で満たされる。
安心した途端、一週間分の寝不足が身体を襲う。ゆっくりと閉じていく瞼の向こう側には、あどけない恋人の安らかな寝顔が見えた。ああどうか、コイツがこんな顔を見せてくれるのは今後おれの前だけでありますように。