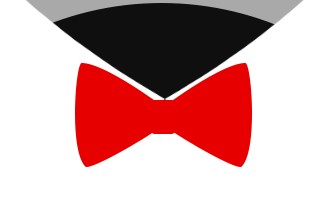フェイジュニ
【唇から、愛】
二人でホラー映画を観る夜が少しずつ変わっていったのは、つい最近のことだ。フェイスの告白を機に変化した二人の関係性のように身体の距離感まで変わってしまった。隣同士、絶妙な距離を開けて座っていたのは遠い昔。だんだん近づいて、手が触れて、肩にもたれて、髪の毛先まで存在を感じられるくらい近く。そして今回は、フェイスの脚の間にジュニアがすっぽりと収まっている。正しく恋人同士のティーンらしいその距離感を気に入っているのはお互い同じだった。
ゾンビパニックものに無意味に挟まるラブシーンを惚けて観ていると、ふとジュニアの肩越しにフェイスの顔が近付いた。ジュニアよりも深い吐息が、うなじを掠めてくすぐったい。身をよじると気を良くしたのか、腹に回された腕の力が増したような気さえする。
「おい…」
「ねえおチビちゃん、ショコラ取ってくれない?」
“そういう雰囲気”になるのかと思って身構えたジュニアに投げられた言葉は、予想外のものだった。映画のおともにと机に並べられた様々なお菓子の中の、フェイスが気に入っているショコラ。届くくせに、面倒くさいときにはこうしてジュニアに取らせようとしてくるのだ。自分ばかり昂まっていく熱が恥ずかしくて、ジュニアは普段よりも粗雑にショコラを差し出した。
「ほらよ」
「アハ、そうじゃなくて」
箱ごと寄越してきたジュニアの手首ごと掴んで、ショコラを一度机に戻す。映画の叫び声が響く中、フェイスがショコラの箱を開ける音がやけに大きくジュニアの耳に届いた。ミニショコラの中の一つ、フェイスが特に気に入っているものをジュニアに摘ませる。呆けているうちに近づいてきたのは、何度見ても見慣れないフェイスの整った顔だった。
「いただきます」
少年然としたジュニアの指ごと、フェイスの形の良い唇の中に吸い込まれていく。ショコラを咀嚼する音、それから指に残ったパウダーを全て舐めとろうとする淫靡な舌先の動きは、ジュニアの幼い情欲を刺激していく。指先に当たる熱い舌はまるで意志を持った生き物のようだ。関節の間までねっとりとなぶって、ジュニアの指を性感帯のように仕上げていく。
とさりと押し倒されたのはソファの上だった。下から見るフェイスの顔は見たことのない男の表情で、本能のままに逃げ出してしまいたくなる。獣のように荒い息が近くで聞こえたかと思うと、そのまま貪るように唇を奪われた。ジュニアの口から小さく声が漏れ出るたび、太腿の辺りに押しつけられる熱の塊が怖くて。だけどどうしようもない期待に昂っていく自分の中心に気付くと、そんな恐怖なんて頭の隅にも残らないんだと気付いてしまった。
舌は、人差し指の付け根まで降りてきている。フェイスの唾液でてらてらと濡れる指は自分のものじゃないみたいで、ジュニアは思わず目を逸らした。それを許さないとでも言うように、今度はじゅるりと品のない音を立てて、手のひらが蹂躙されていく。顔を赤くしたジュニアをばっちりと見ていたのは、妖しく光るルベライト。夜の闇に慣れたその光が、まっすぐに射抜いている。
「ねえおチビちゃん、いいよね」
ごくりと欲望を飲み込んだ音がした。開始の合図を待つようにもう一度長く舐められた手のひらが、急激に熱を帯びていく。手招くようにして、唇を寄せる。フェイスがさっき食べたショコラの甘い味が口の中に広がって、脳内から順に犯されていくような錯覚。「いいよ」と小さく返事をして、ジュニアは愛をくれる唇にその身を委ねた。
二人でホラー映画を観る夜が少しずつ変わっていったのは、つい最近のことだ。フェイスの告白を機に変化した二人の関係性のように身体の距離感まで変わってしまった。隣同士、絶妙な距離を開けて座っていたのは遠い昔。だんだん近づいて、手が触れて、肩にもたれて、髪の毛先まで存在を感じられるくらい近く。そして今回は、フェイスの脚の間にジュニアがすっぽりと収まっている。正しく恋人同士のティーンらしいその距離感を気に入っているのはお互い同じだった。
ゾンビパニックものに無意味に挟まるラブシーンを惚けて観ていると、ふとジュニアの肩越しにフェイスの顔が近付いた。ジュニアよりも深い吐息が、うなじを掠めてくすぐったい。身をよじると気を良くしたのか、腹に回された腕の力が増したような気さえする。
「おい…」
「ねえおチビちゃん、ショコラ取ってくれない?」
“そういう雰囲気”になるのかと思って身構えたジュニアに投げられた言葉は、予想外のものだった。映画のおともにと机に並べられた様々なお菓子の中の、フェイスが気に入っているショコラ。届くくせに、面倒くさいときにはこうしてジュニアに取らせようとしてくるのだ。自分ばかり昂まっていく熱が恥ずかしくて、ジュニアは普段よりも粗雑にショコラを差し出した。
「ほらよ」
「アハ、そうじゃなくて」
箱ごと寄越してきたジュニアの手首ごと掴んで、ショコラを一度机に戻す。映画の叫び声が響く中、フェイスがショコラの箱を開ける音がやけに大きくジュニアの耳に届いた。ミニショコラの中の一つ、フェイスが特に気に入っているものをジュニアに摘ませる。呆けているうちに近づいてきたのは、何度見ても見慣れないフェイスの整った顔だった。
「いただきます」
少年然としたジュニアの指ごと、フェイスの形の良い唇の中に吸い込まれていく。ショコラを咀嚼する音、それから指に残ったパウダーを全て舐めとろうとする淫靡な舌先の動きは、ジュニアの幼い情欲を刺激していく。指先に当たる熱い舌はまるで意志を持った生き物のようだ。関節の間までねっとりとなぶって、ジュニアの指を性感帯のように仕上げていく。
とさりと押し倒されたのはソファの上だった。下から見るフェイスの顔は見たことのない男の表情で、本能のままに逃げ出してしまいたくなる。獣のように荒い息が近くで聞こえたかと思うと、そのまま貪るように唇を奪われた。ジュニアの口から小さく声が漏れ出るたび、太腿の辺りに押しつけられる熱の塊が怖くて。だけどどうしようもない期待に昂っていく自分の中心に気付くと、そんな恐怖なんて頭の隅にも残らないんだと気付いてしまった。
舌は、人差し指の付け根まで降りてきている。フェイスの唾液でてらてらと濡れる指は自分のものじゃないみたいで、ジュニアは思わず目を逸らした。それを許さないとでも言うように、今度はじゅるりと品のない音を立てて、手のひらが蹂躙されていく。顔を赤くしたジュニアをばっちりと見ていたのは、妖しく光るルベライト。夜の闇に慣れたその光が、まっすぐに射抜いている。
「ねえおチビちゃん、いいよね」
ごくりと欲望を飲み込んだ音がした。開始の合図を待つようにもう一度長く舐められた手のひらが、急激に熱を帯びていく。手招くようにして、唇を寄せる。フェイスがさっき食べたショコラの甘い味が口の中に広がって、脳内から順に犯されていくような錯覚。「いいよ」と小さく返事をして、ジュニアは愛をくれる唇にその身を委ねた。