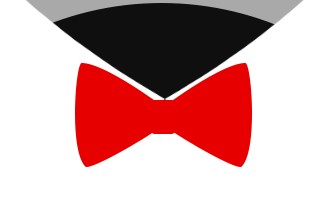フェイジュニ
【キスから始まるエトセトラ】
「お前さ、キスするの好き?」
恒例の映画タイムで隣に座るジュニアがぽつりと零したのは、そんな言葉だった。ホラー映画に挟まれたひとときのラブシーン。そんな一瞬に充てられたのかと思ったが、どこか悩ましげな表情はそんな感じにも見えない。
「キスが嫌いな男なんていないんじゃない」
「そう、だよな」
珍しく歯切れの悪い響きを残してまたジュニアが黙り込んだので、部屋には映画の音楽だけが流れている。
ぼうっと画面を眺めていると、ラブシーンは佳境に。素肌を重ねて甘い言葉を吐き合う男女。色を纏った横顔が近づいていきーーー唇が触れる直前にフェイスの瞳に映ったのは、やけに真剣なジュニアの表情と、普段からは想像もつかないほど官能的に揺れる薄い唇だった。初めて重なった唇は、あたたかさと柔らかな感覚が印象的で。音も立てずに離れていったのを少し残念に思った。
「じゃあさ、俺とキスできるか?」
「アハ…もうしちゃったんだけど」
正直なところ、フェイスとしてはジュニアのことを憎からず思っていた。女の子と遊んでいる最中にも顔を思い出すことがあるし、クラブ帰りの暗い夜道では子犬のように吠える賑やかな姿に早く会いたいな、なんて思うこともある。それが恋愛としての好意かは分からないが、ジュニアが言うように「キスができるか」と聞かれたら、できると答えられるくらいには心を許していることは事実だった。
フェイスには、それが精一杯の告白に見えていた。経験のなさそうなジュニアがキスから入ったのは予想外だったが、それも背伸びした結果だと思うと好ましいし、好意が自分に向いていると思えばらしくなく心が躍った。だから、その次に告げられた言葉は少しだけーーーいや、かなり想定外のもので、その後のフェイスの心を大きく乱れさせる原因になったのだった。
「俺とキスフレンドになってほしい」
ジュニアが言うように「キスフレンド」という関係になってから、早いもので二ヶ月が過ぎていた。事前に口酸っぱく訴えてきたように、ジュニアは外では絶対にそういった関わりを持とうとはしなかった。代わりに自分たちの暮らす部屋の中ではまるで恋人同士のようにーーーこれには少しフェイスの願望も含まれているかもしれないがーーーくっついてきて、キスをねだった。甘やかなものから、激しく深いものまで、さまざまなキスを交わしてきたが、いざその先へなし崩そうとすると途端に自分のテリトリーへ逃げてしまう。フェイスとしては限界に近い状態だった。現状女の子たちよりも興味を惹く好ましい存在がキスをくれるというのに、その他大勢で欲を発散する理由はない。そう思ってジュニアとのキスフレに甘んじてきたが、その我慢もいよいよ限界に近かった。
そしてなにより、ジュニアがフェイス以前に築いてきた経験が垣間見える瞬間も不愉快だった。バードキスを重ねるともっととねだる瞳が、試すように口内を犯す舌に挑戦的に絡んでくる熱い舌先が。全てがジュニアのそれまでの経験を物語っているようで、冷静ではいられなくなるのだ。
「おチビちゃんはさ、もしかして精通してない?それとも俺のことただのキスしてくれる人形だと思ってる?」
「ぴっ!?せい……人形…?」
フェイスの感情を一度に浴びたジュニアは混乱しているようで言葉にならない声を断続的に上げ、最後にはフェイスの瞳に燃える熱情を感じて押し黙ってしまった。
無言をいいことにソファに押し倒して唇を貪る。歯列の裏の性感帯を舌でなぞると、ジュニアの小さな身体がふるりと震えた。「や、やだ…」蚊の鳴くような声はらしくなくて、自分がそんな声を出させているのだと思うと嬉しくて、少しだけ悲しくて今度は唇の端に小さく触れるだけのキスを落とした。それは優しくしたいという精一杯の表現だったが、混乱しているジュニアに届いていたのかは分からない。
唇は、触れたことのない首筋へ。筋張ったそこは嗅ぎ慣れた男の子の匂いがして、それすらもフェイスを興奮させるひとつとなっていた。音を立てて所有の証がつけられていく。そのたびに小さく上がる喘ぎ声は嘘じゃないようで、ジュニアの中心が徐々に熱を帯びてきていることにフェイスは気付いていた。性を感じさせる口付けで頭がいっぱいになっているジュニアが気付いているかは分からない。けれど知ってほしくて、同じように熱を持った自分のそれをぐりっと押しつけるとジュニアの喉奥からは小さな悲鳴が上がった。
「お、おまえそれ…」
「気づいた?」
男のものにしては未発達で、柔らかささえある太ももに擦り付ける。
「知らなかったなら教えてあげるよ」
ジュニアの手を自分の中心に導くと、どくどくと脈打つ昂りが痛いほどに主張している。ハジメテよりも興奮していることに気付いて、思わず自嘲めいた溜息が漏れた。
「大人の恋はさ、キスだけじゃ終わらないんだよ」
「こ、恋って…」
この期に及んで逃げようとするヘテロクロミアをキスで捕らえる。その目に混ざるのは未知の感情に対する畏怖に見えて、思わず口角が上がる。本気の恋なんて面倒くさい、なんて曰っていた過去の自分に見せてやりたい姿だ。自分よりも小さくて幼い存在に、これだけ感情を揺さぶられている。
「おチビちゃんにその気がなくても、俺をその気にさせた責任はとってもらうよ」
夜は長い。ジュニアが知らないそんな常識を教え込めることがひどく嬉しい。これからすぐ手に入れることができるジュニアの「はじめて」を想像して、フェイスは口の端を小さく舐めた。
「お前さ、キスするの好き?」
恒例の映画タイムで隣に座るジュニアがぽつりと零したのは、そんな言葉だった。ホラー映画に挟まれたひとときのラブシーン。そんな一瞬に充てられたのかと思ったが、どこか悩ましげな表情はそんな感じにも見えない。
「キスが嫌いな男なんていないんじゃない」
「そう、だよな」
珍しく歯切れの悪い響きを残してまたジュニアが黙り込んだので、部屋には映画の音楽だけが流れている。
ぼうっと画面を眺めていると、ラブシーンは佳境に。素肌を重ねて甘い言葉を吐き合う男女。色を纏った横顔が近づいていきーーー唇が触れる直前にフェイスの瞳に映ったのは、やけに真剣なジュニアの表情と、普段からは想像もつかないほど官能的に揺れる薄い唇だった。初めて重なった唇は、あたたかさと柔らかな感覚が印象的で。音も立てずに離れていったのを少し残念に思った。
「じゃあさ、俺とキスできるか?」
「アハ…もうしちゃったんだけど」
正直なところ、フェイスとしてはジュニアのことを憎からず思っていた。女の子と遊んでいる最中にも顔を思い出すことがあるし、クラブ帰りの暗い夜道では子犬のように吠える賑やかな姿に早く会いたいな、なんて思うこともある。それが恋愛としての好意かは分からないが、ジュニアが言うように「キスができるか」と聞かれたら、できると答えられるくらいには心を許していることは事実だった。
フェイスには、それが精一杯の告白に見えていた。経験のなさそうなジュニアがキスから入ったのは予想外だったが、それも背伸びした結果だと思うと好ましいし、好意が自分に向いていると思えばらしくなく心が躍った。だから、その次に告げられた言葉は少しだけーーーいや、かなり想定外のもので、その後のフェイスの心を大きく乱れさせる原因になったのだった。
「俺とキスフレンドになってほしい」
ジュニアが言うように「キスフレンド」という関係になってから、早いもので二ヶ月が過ぎていた。事前に口酸っぱく訴えてきたように、ジュニアは外では絶対にそういった関わりを持とうとはしなかった。代わりに自分たちの暮らす部屋の中ではまるで恋人同士のようにーーーこれには少しフェイスの願望も含まれているかもしれないがーーーくっついてきて、キスをねだった。甘やかなものから、激しく深いものまで、さまざまなキスを交わしてきたが、いざその先へなし崩そうとすると途端に自分のテリトリーへ逃げてしまう。フェイスとしては限界に近い状態だった。現状女の子たちよりも興味を惹く好ましい存在がキスをくれるというのに、その他大勢で欲を発散する理由はない。そう思ってジュニアとのキスフレに甘んじてきたが、その我慢もいよいよ限界に近かった。
そしてなにより、ジュニアがフェイス以前に築いてきた経験が垣間見える瞬間も不愉快だった。バードキスを重ねるともっととねだる瞳が、試すように口内を犯す舌に挑戦的に絡んでくる熱い舌先が。全てがジュニアのそれまでの経験を物語っているようで、冷静ではいられなくなるのだ。
「おチビちゃんはさ、もしかして精通してない?それとも俺のことただのキスしてくれる人形だと思ってる?」
「ぴっ!?せい……人形…?」
フェイスの感情を一度に浴びたジュニアは混乱しているようで言葉にならない声を断続的に上げ、最後にはフェイスの瞳に燃える熱情を感じて押し黙ってしまった。
無言をいいことにソファに押し倒して唇を貪る。歯列の裏の性感帯を舌でなぞると、ジュニアの小さな身体がふるりと震えた。「や、やだ…」蚊の鳴くような声はらしくなくて、自分がそんな声を出させているのだと思うと嬉しくて、少しだけ悲しくて今度は唇の端に小さく触れるだけのキスを落とした。それは優しくしたいという精一杯の表現だったが、混乱しているジュニアに届いていたのかは分からない。
唇は、触れたことのない首筋へ。筋張ったそこは嗅ぎ慣れた男の子の匂いがして、それすらもフェイスを興奮させるひとつとなっていた。音を立てて所有の証がつけられていく。そのたびに小さく上がる喘ぎ声は嘘じゃないようで、ジュニアの中心が徐々に熱を帯びてきていることにフェイスは気付いていた。性を感じさせる口付けで頭がいっぱいになっているジュニアが気付いているかは分からない。けれど知ってほしくて、同じように熱を持った自分のそれをぐりっと押しつけるとジュニアの喉奥からは小さな悲鳴が上がった。
「お、おまえそれ…」
「気づいた?」
男のものにしては未発達で、柔らかささえある太ももに擦り付ける。
「知らなかったなら教えてあげるよ」
ジュニアの手を自分の中心に導くと、どくどくと脈打つ昂りが痛いほどに主張している。ハジメテよりも興奮していることに気付いて、思わず自嘲めいた溜息が漏れた。
「大人の恋はさ、キスだけじゃ終わらないんだよ」
「こ、恋って…」
この期に及んで逃げようとするヘテロクロミアをキスで捕らえる。その目に混ざるのは未知の感情に対する畏怖に見えて、思わず口角が上がる。本気の恋なんて面倒くさい、なんて曰っていた過去の自分に見せてやりたい姿だ。自分よりも小さくて幼い存在に、これだけ感情を揺さぶられている。
「おチビちゃんにその気がなくても、俺をその気にさせた責任はとってもらうよ」
夜は長い。ジュニアが知らないそんな常識を教え込めることがひどく嬉しい。これからすぐ手に入れることができるジュニアの「はじめて」を想像して、フェイスは口の端を小さく舐めた。