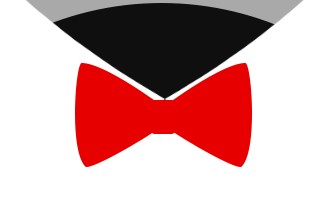フェイジュニ
【ハニーステップ】
いまをときめくモデルがバッチリとポーズをとっているその雑誌がジュニアの部屋にあるのは、偶然というほかなかった。
パトロール中やけに仲睦まじいカップルが目についたのも、黄色い声を飛ばしてくる女の子たちにやけに腹が立ったのも、隣を歩くヘッドホン野郎がなかなか手を出してこないからだ。休憩に抜けたとき、本屋に並んでいた雑誌のとある文章がやけに目について、誰にもバレないようにひっそりをそれを買った。隣を歩く男は、相も変わらずヘラヘラした笑みを振りまいている。
ジュニアとその男…フェイスがいわゆるお付き合いを始めて二ヶ月が経った。その間の触れ合いといえば、付き合い始めて二週目に人目を忍んで手を繋ぎ、さらに一ヶ月が経った頃には唇が触れ合うだけのキスをした。これはおかしい。そう思ったのはその子どものようなキスが一週間続いた頃だ。
そもそも、手を繋ぐだけからキスに移るまでが異様に長いなとは思っていた。ジュニアだって思春期の男だから、経験がなくたってそれなりにそういうことに対するビジョンは持っている。童貞同士ならまだしも、イエローウエストの女なら名前を知らない者はいないフェイス・ビームスが相手ともなれば、もっと性急にことが進んでいくものだと思っていたのだ。まあ俺は男だからな。キスをするまでは心の準備が必要だったのかもしれないし、キスまで進めば、もうあとはあれだ、なし崩し的に展開していくのでは?と、思っていた時期が俺にもありました。誰に聞かせるわけでもないのに、ご丁寧にそう言い訳して雑誌をペロリとめくる。
「カレとの初めての夜」という表題がついたページには、ハジメテに向けての準備やちょっとした心構えに紛れて「カレが手を出してくれない」と泣いたフリをする女性のピンショットが映る枠がある。いちいち本を開かなくても覚えてしまったその文章をなぞって深いため息を吐く。
カレが手を出してくれないってことは、あと一歩決め手が足りないのかも?
かわいい部屋着や花の匂いのシャンプー。普段とは違う雰囲気でカレを迎えてみよう!
これはあくまでの男女間の恋愛での話である。それは分かっている。分かっているのだが、ジュニアの部屋の、フェイスのいるスペースからは絶妙に見えない場所に、ひっそりと置かれているそれが購入されたのは仕方のない話なのだ。巷で女子に人気のピンクのボトルのシャンプーに、有名ブランドのふわふわした部屋着。馬鹿みたいだといっそ誰かに笑ってほしい。
こんなものを買ったって、結局アイツは今日も朝帰りで、俺には唇と唇を合わせただけのチープなキスだけ。空っぽのベッドを見ていると、なんだか無性にイライラして、ジュニアはシャンプーボトルを手に取るとシャワールームに駆け込んだ。
「わっ…スゲー匂い」
せっかく買ったのにもったいないという気持ちもあり、泡立てたそれで髪を洗う。普段使っている清涼感のあるすっきりとした匂いとは違い、花のようなふんわりとした香りがシャワールームに充満しているのは少しだけ恥ずかしさがある。でも、フェイスがいるときに使うのは期待しているみたいでもっと恥ずかしいから、いない夜のうちに使ってしまおう。
お湯で流してもふんわりと香るその匂いが元々する女の子だったら、袖を通したふわふわの部屋着が似合う子だったら、こんな気持ちにならなくて済んだのだろうか。フェイスのためにあつらえた身体なのに、今日もあいつはいない。どうせ朝まで帰ってこないならと、シャワールームを抜けていつもとは逆方向にあるベッドに潜り込む。ジュニアの布団よりもマットレスは固め。掛け布団の重さも違うのに、全部からフェイスの匂いがすると思うとそれだけで眠れてしまいそうなくらい安心した。自分から香る花の匂いと、腕にまとわりつくパステルカラーのモコモコが少し邪魔だけど、久しぶりに感じたフェイスの腕の中のような安心感に、ジュニアはそのまま意識を手放した。
フェイスが日付を跨ぐ前に部屋に帰り着いたのは、おおよそ三週間ぶりのことだった。誓って女遊びはしていない。兼業しているDJの仕事が忙しく、夜のうちになかなか帰れないでいたが、女の子からの誘いは極力きっぱり断るようにしていたし、この三週間の癒しは帰り着いた頃まだ夢の中にいる子どもみたいな寝顔にキスを一つ落とすことだった。触れた唇が離れるたびふにゃふにゃと何事か呟いているジュニアが可愛くて、睡眠時間を削って眺めていたこともある。おかげでしばらく目覚めているジュニアとは仕事以外の話をほとんど出来ていないが、そんな日々も今日で終いだ。
もうすっかりルーティンになっているジュニアのスペースへ顔を出すと、いつもなら健やかな顔で夢の世界へ旅立っているはずの膨らみが見当たらない。代わりにいつも取り巻きの女の子が纏っているような花の匂いがして、思わず顔をしかめた。いつもとは違う部屋。いなくなったジュニア。気配を感じて自分のスペースを振り返ると、朝は整っていたはずの掛け布団がこんもりと山になっていた。
誰かわからないけど、もしかしてカノジョに勝手に部屋に入られてる?面倒の予感を感じて、起こさないように自分の布団を捲ると、そこに眠っていたのは探していた幼い寝顔だった。
「おチビちゃん?」
「うーん…」
眩しかったのか布団に潜ろうとした小さな身体を追いかけると、先程から薄らと漂っていた花の匂いが強くなる。もしかしてこれ、この子の匂いかな。顔を寄せたフェイスに、寝返りをうったジュニアの身体が被さる。フェイスに触れたのは、ジュニアの着ているふわふわの部屋着だった。普段はTシャツハーフパンツで眠っているジュニアとはかけ離れた触り心地に、フェイスは大きく混乱していた。
とりあえずカノジョに不法侵入されたってことはなさそう?この匂いは女の子じゃなくてジュニアが纏っている匂いで、何故かかわいい部屋着まで身につけている。まとまらない頭の中でも、たった一つだけ理解できていることがある。
なにかの罠の可能性もあるが、これが俗に言う「据え膳」だということだ。しばらくジュニアに触れられていないフェイスにとって、これは夢のような状況だった。色恋になれないジュニアに合わせて亀かカタツムリか、くらいのスピードで進んできたが、もういいだろう。
「おチビちゃん、ねえ起きて」
「ん〜…」
そうと決まれば、起こさなければならない。眠っている子に手を出すのは、フェイスの流儀に反するからだ。夜に慣れていないオッドアイがぼんやりとフェイスを映す。口の端から溢れる涎すら美味しそうに見えて、それをペロリと舐めとった。突然の触れ合いに驚いたのか唇が開かれる瞬間を見逃さず、熱い舌を割り込ませる。小動物みたいに縮こまっているジュニアの舌を絡めとって、深いキスを交わした。
「ぷはっ」
鎖骨にキスを落として、ふわふわの部屋着をめくって薄い腹を撫でる。「や、やだ…」と涙を溜めた青と黒にも唇で触れると、花の匂いに紛れていつものジュニアの匂いがした。もっと欲しくて思いきり吸いこむと、くすぐったいのかびくんと身体が揺れる。熱情を秘めた視線が重なったことが嬉しくて、小さく笑った。
「もう、逃げられると思わないでね」
いまをときめくモデルがバッチリとポーズをとっているその雑誌がジュニアの部屋にあるのは、偶然というほかなかった。
パトロール中やけに仲睦まじいカップルが目についたのも、黄色い声を飛ばしてくる女の子たちにやけに腹が立ったのも、隣を歩くヘッドホン野郎がなかなか手を出してこないからだ。休憩に抜けたとき、本屋に並んでいた雑誌のとある文章がやけに目について、誰にもバレないようにひっそりをそれを買った。隣を歩く男は、相も変わらずヘラヘラした笑みを振りまいている。
ジュニアとその男…フェイスがいわゆるお付き合いを始めて二ヶ月が経った。その間の触れ合いといえば、付き合い始めて二週目に人目を忍んで手を繋ぎ、さらに一ヶ月が経った頃には唇が触れ合うだけのキスをした。これはおかしい。そう思ったのはその子どものようなキスが一週間続いた頃だ。
そもそも、手を繋ぐだけからキスに移るまでが異様に長いなとは思っていた。ジュニアだって思春期の男だから、経験がなくたってそれなりにそういうことに対するビジョンは持っている。童貞同士ならまだしも、イエローウエストの女なら名前を知らない者はいないフェイス・ビームスが相手ともなれば、もっと性急にことが進んでいくものだと思っていたのだ。まあ俺は男だからな。キスをするまでは心の準備が必要だったのかもしれないし、キスまで進めば、もうあとはあれだ、なし崩し的に展開していくのでは?と、思っていた時期が俺にもありました。誰に聞かせるわけでもないのに、ご丁寧にそう言い訳して雑誌をペロリとめくる。
「カレとの初めての夜」という表題がついたページには、ハジメテに向けての準備やちょっとした心構えに紛れて「カレが手を出してくれない」と泣いたフリをする女性のピンショットが映る枠がある。いちいち本を開かなくても覚えてしまったその文章をなぞって深いため息を吐く。
カレが手を出してくれないってことは、あと一歩決め手が足りないのかも?
かわいい部屋着や花の匂いのシャンプー。普段とは違う雰囲気でカレを迎えてみよう!
これはあくまでの男女間の恋愛での話である。それは分かっている。分かっているのだが、ジュニアの部屋の、フェイスのいるスペースからは絶妙に見えない場所に、ひっそりと置かれているそれが購入されたのは仕方のない話なのだ。巷で女子に人気のピンクのボトルのシャンプーに、有名ブランドのふわふわした部屋着。馬鹿みたいだといっそ誰かに笑ってほしい。
こんなものを買ったって、結局アイツは今日も朝帰りで、俺には唇と唇を合わせただけのチープなキスだけ。空っぽのベッドを見ていると、なんだか無性にイライラして、ジュニアはシャンプーボトルを手に取るとシャワールームに駆け込んだ。
「わっ…スゲー匂い」
せっかく買ったのにもったいないという気持ちもあり、泡立てたそれで髪を洗う。普段使っている清涼感のあるすっきりとした匂いとは違い、花のようなふんわりとした香りがシャワールームに充満しているのは少しだけ恥ずかしさがある。でも、フェイスがいるときに使うのは期待しているみたいでもっと恥ずかしいから、いない夜のうちに使ってしまおう。
お湯で流してもふんわりと香るその匂いが元々する女の子だったら、袖を通したふわふわの部屋着が似合う子だったら、こんな気持ちにならなくて済んだのだろうか。フェイスのためにあつらえた身体なのに、今日もあいつはいない。どうせ朝まで帰ってこないならと、シャワールームを抜けていつもとは逆方向にあるベッドに潜り込む。ジュニアの布団よりもマットレスは固め。掛け布団の重さも違うのに、全部からフェイスの匂いがすると思うとそれだけで眠れてしまいそうなくらい安心した。自分から香る花の匂いと、腕にまとわりつくパステルカラーのモコモコが少し邪魔だけど、久しぶりに感じたフェイスの腕の中のような安心感に、ジュニアはそのまま意識を手放した。
フェイスが日付を跨ぐ前に部屋に帰り着いたのは、おおよそ三週間ぶりのことだった。誓って女遊びはしていない。兼業しているDJの仕事が忙しく、夜のうちになかなか帰れないでいたが、女の子からの誘いは極力きっぱり断るようにしていたし、この三週間の癒しは帰り着いた頃まだ夢の中にいる子どもみたいな寝顔にキスを一つ落とすことだった。触れた唇が離れるたびふにゃふにゃと何事か呟いているジュニアが可愛くて、睡眠時間を削って眺めていたこともある。おかげでしばらく目覚めているジュニアとは仕事以外の話をほとんど出来ていないが、そんな日々も今日で終いだ。
もうすっかりルーティンになっているジュニアのスペースへ顔を出すと、いつもなら健やかな顔で夢の世界へ旅立っているはずの膨らみが見当たらない。代わりにいつも取り巻きの女の子が纏っているような花の匂いがして、思わず顔をしかめた。いつもとは違う部屋。いなくなったジュニア。気配を感じて自分のスペースを振り返ると、朝は整っていたはずの掛け布団がこんもりと山になっていた。
誰かわからないけど、もしかしてカノジョに勝手に部屋に入られてる?面倒の予感を感じて、起こさないように自分の布団を捲ると、そこに眠っていたのは探していた幼い寝顔だった。
「おチビちゃん?」
「うーん…」
眩しかったのか布団に潜ろうとした小さな身体を追いかけると、先程から薄らと漂っていた花の匂いが強くなる。もしかしてこれ、この子の匂いかな。顔を寄せたフェイスに、寝返りをうったジュニアの身体が被さる。フェイスに触れたのは、ジュニアの着ているふわふわの部屋着だった。普段はTシャツハーフパンツで眠っているジュニアとはかけ離れた触り心地に、フェイスは大きく混乱していた。
とりあえずカノジョに不法侵入されたってことはなさそう?この匂いは女の子じゃなくてジュニアが纏っている匂いで、何故かかわいい部屋着まで身につけている。まとまらない頭の中でも、たった一つだけ理解できていることがある。
なにかの罠の可能性もあるが、これが俗に言う「据え膳」だということだ。しばらくジュニアに触れられていないフェイスにとって、これは夢のような状況だった。色恋になれないジュニアに合わせて亀かカタツムリか、くらいのスピードで進んできたが、もういいだろう。
「おチビちゃん、ねえ起きて」
「ん〜…」
そうと決まれば、起こさなければならない。眠っている子に手を出すのは、フェイスの流儀に反するからだ。夜に慣れていないオッドアイがぼんやりとフェイスを映す。口の端から溢れる涎すら美味しそうに見えて、それをペロリと舐めとった。突然の触れ合いに驚いたのか唇が開かれる瞬間を見逃さず、熱い舌を割り込ませる。小動物みたいに縮こまっているジュニアの舌を絡めとって、深いキスを交わした。
「ぷはっ」
鎖骨にキスを落として、ふわふわの部屋着をめくって薄い腹を撫でる。「や、やだ…」と涙を溜めた青と黒にも唇で触れると、花の匂いに紛れていつものジュニアの匂いがした。もっと欲しくて思いきり吸いこむと、くすぐったいのかびくんと身体が揺れる。熱情を秘めた視線が重なったことが嬉しくて、小さく笑った。
「もう、逃げられると思わないでね」