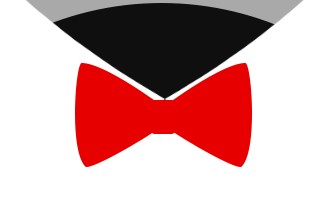フェイジュニ
【ウォータードロップウォート】
幸せになってください。俺の彼女にしては奥ゆかしい一節が書かれたこの手紙を受け取ったのは、パトロール中のことだった。いつもみたいに寄ってくる女の子たちも珍しくいなくて、今日はちょっといい日だななんて帰ろうとしたときに俺を呼び止めたのは、老女のしわがれた声だった。曰く、孫娘からの手紙を受け取ってほしいという。聞いてあげる必要もないんだけど、どこに感動したのかおチビちゃんが受け取ってやれってうるさいから、しぶしぶ手にした手紙は現在机の上に鎮座している。正直開けたくもないが、手紙と見つめ合う俺の後ろには監視の目を光らせるおチビちゃんがいて、どうにも逃げられない。早く読め、と急かされるような目線を投げかけられたのでしぶしぶ封を開けると、そこには前述の一節が書かれていたというわけだ。白い花の絵が描かれた便箋は、なんだか甘くて少しだけ苦手な匂いがする。
ラブレターというより詩のようなそれを読み進めるうちに、これは想いを伝えるだけの一方的なもので答えが求められていないこと、そして大きな間違いがあることに気がついた。俺は街を守るやる気になんて満ち溢れてないし、事なかれ主義なんだから女の子に優しいのなんていつものことだ。「そんなところが好きなんです」と馬鹿正直に書かれた丁寧な字は、いっそ苛立つほどに清廉な香りがした。
封を閉じて引き出しの奥深くに仕舞う。「ちゃんと読んだのかよ」と大きな青とグレーに見つめられる。
「ばっちり見てたでしょ。というか、どうしてそんなにこだわるの?」
「その子は誰かにお願いしてでも、お前に気持ちを伝えたかったんだろ」
「意外。おチビちゃんは直接伝えてくる子じゃないと嫌なのかと思ってた」
「…伝えようともしないでうじうじしてる奴より、百万倍マシだろ」
その言葉に、どくっと心臓が高鳴る。それ以上は興味ないようで、シャワールームに向かったおチビちゃんの背中を見送りながら、引き出しの中の一文の思い出す。「幸せになってください」俺がもしもこの子の立場だったら、同じことが言えるだろうか。
今日も今日とて治安がいいとは言いきれない街を、二人でパトロールする。始めこそ今日も朝から飲んだくれて使い物にならないキースに恨み言を吐いていたおチビちゃんだったが、いまは真面目に警戒の目を光らせている。毎度のことながら、飽きないことだ。俺はと言うと昨日とは打って変わって、山のように浴びせられる黄色い声を往なしながらおチビちゃんの数歩後ろを進む。「遊びに行かない?」だの「次に空いてる日はいつ?」だの、約束を取りつけるのに必死な彼女たちを見ていると、昨日の手紙を嫌でも思い出してしまう。
日の光に反射する柔らかな金糸から覗く横顔は、今日も眩しい。街を守ることを誇りに思う芯の強い両の眼も、たまにとんでもない暴言が飛び出すけど真っ直ぐで嘘のない薄い唇も、たくさんのものを背負っている小さな背中も、全てがキラキラしていている。伝えることができない劣情がチリっと胸の奥底を焦がして、途端に息苦しくなる。
「ねえ、ちょっと具合悪いんだけど」
「はぁ?」
「帰るね」
「お、おい。ちょっと!」
追いかけてくる足音は、聴こえない。真っ直ぐに俺とおチビちゃんの部屋に帰ると、そのままの勢いでガラッと引き出しを開けた。昨日の手紙は姿形が変わらないままそこにいて、それがまた悔しくてため息を吐いた。怒りのままに破り捨ててやろうか。それとも燃やしてやろうか。自分にこんな強い感情があったなんて驚きだ。手に取ると昨日嗅いだ白い花の匂いがぶり返して、また気分が悪くなる。強く握ると、便箋の端に皺が寄って、白い花の絵は茎からポッキリと折れてしまっている。そんなことにすら優越感を感じるのだから、恋とはままならないものだ。
「おい!」
聴き慣れた大きな声がして、封筒はもう一度引き出しの中に隠される。間一髪見られてはいなかったのか、珍しく心配そうに眉を下げたおチビちゃんと目が合った。陽だまりのような金色の髪の毛は汗で首筋に張りついていて、急いで追いかけてくれたのだということが分かる。
「急に帰るなよ!あんなに早く歩いて、もっと具合悪くなったらどうすんだよ」
「…」
どうやら、具合が悪いという俺のどうしようもない嘘を信じてくれているらしかった。とっさに抱きしめてしまいそうになるくらい愛おしいけど、またあの文言がぶり返して、思わず手を止めた。「幸せになってください」なんていう強い呪いの言葉は、雁字搦めの俺をどんどん臆病にする。俺はこの子といられれば幸せだけど、おチビちゃんはどうなのだろう。分からない。
俺の引き出しで眠っている白い花の手紙は、紛れもなくおチビちゃんに向けられたものだった。読み始めてすぐに気付いたが、どうしてもおチビちゃんには言い出せなかった。いかにも彼が好きそうな真っ直ぐな言葉たちが、そして奥ゆかしい呪いの言葉が、彼の心に巣食ってしまったらどうしようと恐ろしかったからだ。俺以外にも、おチビちゃんのことを好きな人がいる。そしてその人は、真っ直ぐに好意を伝えることができるくらい、そして自分のいない彼の人生の幸せを願えるくらい、強くて真っ直ぐな人なのだ。そんな勇気なんてこれっぽっちも持っていない自分と比べると、ひどく息苦しかった。触れてしまいたい、その唇に。握りしめたい、その手を。抱きしめてもいいかな、その小さな身体を。
この胸を巣食う呪いがいつか解けたら、おチビちゃんに言いたいことがあるんだ。手紙じゃなくて直接言うし、幸せになってなんて殊勝なことは口が裂けても言えないけれど、それでもいいかな。今日だけは、俺の嘘を信じてくれている彼の優しさに甘えて、柔らかな夢を見よう。そして夢から覚めても、白い花の君の呪いの言葉は俺だけが預かっておこう。君のおかげで「うじうじしてる奴」から卒業できそうだから、特別だよ。
幸せになってください。俺の彼女にしては奥ゆかしい一節が書かれたこの手紙を受け取ったのは、パトロール中のことだった。いつもみたいに寄ってくる女の子たちも珍しくいなくて、今日はちょっといい日だななんて帰ろうとしたときに俺を呼び止めたのは、老女のしわがれた声だった。曰く、孫娘からの手紙を受け取ってほしいという。聞いてあげる必要もないんだけど、どこに感動したのかおチビちゃんが受け取ってやれってうるさいから、しぶしぶ手にした手紙は現在机の上に鎮座している。正直開けたくもないが、手紙と見つめ合う俺の後ろには監視の目を光らせるおチビちゃんがいて、どうにも逃げられない。早く読め、と急かされるような目線を投げかけられたのでしぶしぶ封を開けると、そこには前述の一節が書かれていたというわけだ。白い花の絵が描かれた便箋は、なんだか甘くて少しだけ苦手な匂いがする。
ラブレターというより詩のようなそれを読み進めるうちに、これは想いを伝えるだけの一方的なもので答えが求められていないこと、そして大きな間違いがあることに気がついた。俺は街を守るやる気になんて満ち溢れてないし、事なかれ主義なんだから女の子に優しいのなんていつものことだ。「そんなところが好きなんです」と馬鹿正直に書かれた丁寧な字は、いっそ苛立つほどに清廉な香りがした。
封を閉じて引き出しの奥深くに仕舞う。「ちゃんと読んだのかよ」と大きな青とグレーに見つめられる。
「ばっちり見てたでしょ。というか、どうしてそんなにこだわるの?」
「その子は誰かにお願いしてでも、お前に気持ちを伝えたかったんだろ」
「意外。おチビちゃんは直接伝えてくる子じゃないと嫌なのかと思ってた」
「…伝えようともしないでうじうじしてる奴より、百万倍マシだろ」
その言葉に、どくっと心臓が高鳴る。それ以上は興味ないようで、シャワールームに向かったおチビちゃんの背中を見送りながら、引き出しの中の一文の思い出す。「幸せになってください」俺がもしもこの子の立場だったら、同じことが言えるだろうか。
今日も今日とて治安がいいとは言いきれない街を、二人でパトロールする。始めこそ今日も朝から飲んだくれて使い物にならないキースに恨み言を吐いていたおチビちゃんだったが、いまは真面目に警戒の目を光らせている。毎度のことながら、飽きないことだ。俺はと言うと昨日とは打って変わって、山のように浴びせられる黄色い声を往なしながらおチビちゃんの数歩後ろを進む。「遊びに行かない?」だの「次に空いてる日はいつ?」だの、約束を取りつけるのに必死な彼女たちを見ていると、昨日の手紙を嫌でも思い出してしまう。
日の光に反射する柔らかな金糸から覗く横顔は、今日も眩しい。街を守ることを誇りに思う芯の強い両の眼も、たまにとんでもない暴言が飛び出すけど真っ直ぐで嘘のない薄い唇も、たくさんのものを背負っている小さな背中も、全てがキラキラしていている。伝えることができない劣情がチリっと胸の奥底を焦がして、途端に息苦しくなる。
「ねえ、ちょっと具合悪いんだけど」
「はぁ?」
「帰るね」
「お、おい。ちょっと!」
追いかけてくる足音は、聴こえない。真っ直ぐに俺とおチビちゃんの部屋に帰ると、そのままの勢いでガラッと引き出しを開けた。昨日の手紙は姿形が変わらないままそこにいて、それがまた悔しくてため息を吐いた。怒りのままに破り捨ててやろうか。それとも燃やしてやろうか。自分にこんな強い感情があったなんて驚きだ。手に取ると昨日嗅いだ白い花の匂いがぶり返して、また気分が悪くなる。強く握ると、便箋の端に皺が寄って、白い花の絵は茎からポッキリと折れてしまっている。そんなことにすら優越感を感じるのだから、恋とはままならないものだ。
「おい!」
聴き慣れた大きな声がして、封筒はもう一度引き出しの中に隠される。間一髪見られてはいなかったのか、珍しく心配そうに眉を下げたおチビちゃんと目が合った。陽だまりのような金色の髪の毛は汗で首筋に張りついていて、急いで追いかけてくれたのだということが分かる。
「急に帰るなよ!あんなに早く歩いて、もっと具合悪くなったらどうすんだよ」
「…」
どうやら、具合が悪いという俺のどうしようもない嘘を信じてくれているらしかった。とっさに抱きしめてしまいそうになるくらい愛おしいけど、またあの文言がぶり返して、思わず手を止めた。「幸せになってください」なんていう強い呪いの言葉は、雁字搦めの俺をどんどん臆病にする。俺はこの子といられれば幸せだけど、おチビちゃんはどうなのだろう。分からない。
俺の引き出しで眠っている白い花の手紙は、紛れもなくおチビちゃんに向けられたものだった。読み始めてすぐに気付いたが、どうしてもおチビちゃんには言い出せなかった。いかにも彼が好きそうな真っ直ぐな言葉たちが、そして奥ゆかしい呪いの言葉が、彼の心に巣食ってしまったらどうしようと恐ろしかったからだ。俺以外にも、おチビちゃんのことを好きな人がいる。そしてその人は、真っ直ぐに好意を伝えることができるくらい、そして自分のいない彼の人生の幸せを願えるくらい、強くて真っ直ぐな人なのだ。そんな勇気なんてこれっぽっちも持っていない自分と比べると、ひどく息苦しかった。触れてしまいたい、その唇に。握りしめたい、その手を。抱きしめてもいいかな、その小さな身体を。
この胸を巣食う呪いがいつか解けたら、おチビちゃんに言いたいことがあるんだ。手紙じゃなくて直接言うし、幸せになってなんて殊勝なことは口が裂けても言えないけれど、それでもいいかな。今日だけは、俺の嘘を信じてくれている彼の優しさに甘えて、柔らかな夢を見よう。そして夢から覚めても、白い花の君の呪いの言葉は俺だけが預かっておこう。君のおかげで「うじうじしてる奴」から卒業できそうだから、特別だよ。