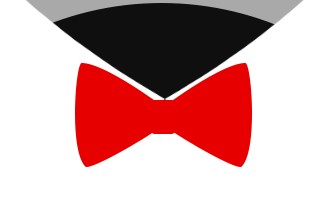フェイジュニ
【大嫌い、大好き】フェイジュニ
「おまえなんか、別に好きじゃない」
幼い頃から婚約者に浴びせられ続けてきたのは、そんな拒絶の言葉だった。所詮親同士が決めた結婚、物心ついた頃には「あなたたちは将来結婚するのよ」なんて煩わしく感じるほど聞かされ続け、自分自身感情が追いつく前に目の前の少年と自分はいつか結婚するんだなと事実として受け止めることしかできなかった。
だからそんなひどいことを言われても、正直な話「そうだろうな」としか思えなかった。とはいえ、親同士仲が良いこともあってよくお互いの家で遊んだし、三つ違いとはいえ同じくらいの年の子どもは周りにはお互いしかいなかったから、それなりの年齢になる頃には「おチビちゃんのこと、好きかも」なんて思うようになっていた。自分の気持ちが少しずつ変わっていったとはいえ、おチビちゃんは頑なに「おまえのことなんて好きじゃない!」という態度を貫いていたし、俺も俺で素直に好きアピールをするような性格でもないから、はいはいと受け流していた。それが俺たちの日常で、いつまでも続くと思っていた。
レオナルド・ライトの息子として一心に期待を受け、飛び級までして一気にヒーローとしての道を駆け上ったおチビちゃんは、俺と共にエリオスに入所した。相も変わらず婚約者とは思えないほど顔を合わせれば冷ややかな言葉を浴びせてくるおチビちゃんと、そんなおチビちゃんを子ども扱いする俺。そんな日常が変わったのは、いつも通りのある日のことだった。
「やっぱお子ちゃまだな〜」
「うるせえ! 一言余計なんだよっ!」
「どうしたの、アレ」
「あー、みんなで初恋はいつだったか、みたいな話になってね……」
なるほど。真面目なおチビちゃんはその質問に愚直にまだだと答えたんだろう。そしてそれを馬鹿にされて子どものように大騒ぎしている、と。まあ恋バナであることを除けばおおよそいつもの流れだ。珍しいことにルーキーたちが大集合して賑わっている談話室に立ち寄ったことをほんの少し後悔した。
「でもでも、稲妻ボーイって婚約者はいるんでしょ? その人とのエピソードとかはないの?」
「はぁ⁉︎ こいつに婚約者……」
厄介な流れになったな、なんて他人事のようにため息を吐く。実際は他人事どころか当事者中の当事者なんだけど。まあおチビちゃんがなんて答えるのかは気になるかな。なんて呑気に構えていたのが悪かったのか、頑として答えようとしないおチビちゃんをつつくのはやめたビリーが「そういえばDJにもいるんだよね、婚約者」と今度は俺に標準を合わせてきた。
「いるけど、こんなところで教えるようなことは何もないよ」
「お願い〜どんな人なのかだけで良いからぁ〜」
わざとらしく声を上げたビリーに、ここで必要以上に話を逸らすのはあまり良くないかなと思い至る。明言さえしなければ大丈夫でしょ。そう考えて、頭の中におチビちゃんの姿を思い浮かべた。
「いつもピィピィうるさいひよこみたいな子だよ。親が決めた相手だから恋バナってわけでもないでしょ。これでおしまい」
「えー、もうひと声!」
「なんかフェイスの婚約者って、ジュニアみたいなやつなんだな」
「え……」
まさかそれだけの情報で当てられるとは思わず言葉を無くしていると、おチビちゃんが勢いよく立ち上がって俺のことを指差した。怒っているのか顔が真っ赤で、嫌な予感がしたけどそれを止めるほどの余裕はなかった。
「お、おれだって好きでこんなやつの婚約者やってるんじゃねえし!」
「え?」
「うん……?」
「おチビちゃん……」
余計なことを言ってしまったとようやく気づいたのか百面相をするおチビちゃんと、ザワザワと騒がしくなる同期たち。こんなはずじゃなかったのになぁなんて独りごちていると「おれっ! もう部屋に戻る!」と全速力で談話室を出ていったおチビちゃんがジャックに咎められていた。いや、この雰囲気で俺だけ置いていくとかある?
あとで嫌味のひとつでも言ってやらないと。部屋に戻る気にもなれなくてこれからの行き先を脳内で探していると、ニヤニヤした顔のビリーが視界に入り込んできた。
「ヘイDJ、かわいい婚約者のこと追いかけなくてよかったの?」
「……怒るよ」
「まさかふたりがそう繋がるとはねぇ、初対面じゃないんだろうなとは思ってたけど」
「言ったでしょ、婚約者って言っても親が決めた結婚だから甘い空気とかそういうのはないんだよ」
「まああの稲妻ボーイだしね」
意味深に笑顔を浮かべるビリーから目を離して、意味もなくスマホの画面を見る。金になるから突いてはこないだろうが、俺の気持ちがどうかなんてとっくにお見通しなんだろう。本当に抜け目のないベスティだ。
一旦時間を置くとして、ご機嫌取りはちゃんとやらないと後々面倒なことになるだろうということが分かっている。なかなか良い案も浮かばずスマホの画面をつけたり消したり、手慰みにしているとビリーが「驚いた」と本当にそう思っているのかも微妙な声色で話しかけてきた。
「なにに」
「本当に好きなんだね」
「えっ」
その言葉に驚くと、ビリーが気まずそうに頭を掻く仕草を見せた。
「ごめん、カマかけてみただけなんだけど……」
「ちょっと」
もう怒る気にもなれず深く息を吐いて机に突っ伏す。気まずくなったのか俺たち以外の同期はいつの間にかいなくなっていて、今は閑散とした談話室に俺とビリーだけだ。
「DJは婚約者とか煩わしく思うタイプかと思ってたから、なんで婚約破棄とかしないんだろうって不思議だったけどそういうことだったんだね」
「皆まで言わなくていいから」
よりによって厄介な相手にバレてしまったことに肩を落とした。それからやけに脳内に残ったままの「婚約破棄」という文字が急に現実的なものになった気がする。いままでに全く考えたことがなかったわけではない。大人が時々提示してくるその言葉に頷かなかったのは俺自身で、生まれる前から決まっていた婚約に後ろめたさを感じ始めた大人たちに気持ちの逃げる隙を与えなかったのも俺だ。
何故って、俺はずっとおチビちゃんのことが好きだったからだ。どれだけ疎まれても、どれだけ好きじゃないと言われても、俺はおチビちゃんのことが好きだったから、どんな形であってもおチビちゃんと結婚したかった。
だけど、そろそろ潮時なのかもしれないとも思う。最初は照れ隠しだろうと気にしていなかったおチビちゃんからの「好きじゃない」も、こう何年も続くと流石に本心だということに気づくし、おチビちゃんの気持ちを捻じ曲げてまでする結婚ってなんだろうとも思う。嫌なことを無理やりするべきではないし、こんなにそばにいた俺のことをどうしても好きになれないというのなら手放してあげる方がおチビちゃんのためになるんじゃないか。それが紛いなりにもおチビちゃんよりも先に大人に差し掛かろうとしている俺にできる唯一のことなんじゃないかと気づき始めていた。
「……やっぱ柄じゃないことするのは向いてないのかもね」
返事がないことを期待した呟きのあとには予想通り静寂が訪れて、先ほどまでの騒々しい談話室とは別の空間にいるみたいだった。
◇◇◇
「おい、なに勝手なことしてんだよ」
「……何が?」
あの談話室での一件から十日経った。いままでであればおチビちゃんの機嫌を取って普段通りの生活に元通りって感じなんだけど、今回ばかりはそうもいかなかった。イライラを隠そうともしないおチビちゃんが、俺が座っていたベッドに乗り上げて胸ぐらを掴む。普段は希望いっぱいって感じで輝いているオッドアイが深い怒りに燃えていた。
「親父から聞いた。婚約破棄したって」
「ああそれね。そうだけど、それがどうかしたの?」
「……っ」
「この前おチビちゃんも言ってたじゃん。好きで婚約者やってるんじゃないって。実際その通りだし、お互い同じ気持ちならわざわざ古臭い婚約者なんていうしがらみに囚われなくてもいいんじゃないって思ってさ」
おチビちゃんも、こないだみたいに揶揄われるのもう嫌でしょ?
あくまでもおチビちゃんのためを思ってやりましたって姿勢を崩さずにそう言うと、癇に障ったのか俺を睨みつける視線が鋭くなった。このままもっと俺のことを嫌いになってくれ。そうしておチビちゃんの方からも俺と結婚はしないと宣言してくれれば、ようやく俺の恋心は静かな眠りにつくことができるのだから。
「大体、生まれる前からの親同士の口約束だなんて、おチビちゃんもずっと迷惑してたでしょ。俺も同期たちに揶揄われるのは嫌だし、ちょうどいいかなって。やっと殻のついたヒヨコちゃんから解放されるかと思うと清々するよ」
「おまえ、おれのことわざと怒らせようとしてるだろ」
「……なんでそう思ったの?」
「分からないわけねーだろ、ずっと一緒にいるんだから」
物心つく前からずっと一緒にいた。そこには大人たちの下心も多分に含まれていただろうけど、何よりおチビちゃんと過ごす時間が楽しくて、眩しかったからだ。大人になってからもずっと一緒にいられるのかと思うと嬉しくて、まだ意味も理解できていないうちから「婚約者っていいな」なんて思っていた。全く呑気なものだ。
一緒にいて、ずっと相手のことを見ているのは自分のほうだけだと思っていた。だけどさっきのおチビちゃんの言葉は、
「ずっと俺のことを見てたみたいな言い方するんだね」
そんな可愛げのない言葉しか出てこないのは、おチビちゃんよりも三年分早く大人になってしまったからだ。心の中でそう言い訳をすると、おチビちゃんが意味が分からないと言うように眉を顰めた。
「当たり前だろ、婚約者なんだから」
「好きでもないくせにね」
「それは……!」
何かを伝えようと大きく口を開いたおチビちゃんが声にならない声をあげて、それからまた口を閉じる。金魚みたいに何度も口をパクパクさせると、ようやく覚悟が決まったのかいつものおチビちゃんからは考えられないほど小さな声で話し始めた。
「好きじゃない、と思ってたんだよ」
「え?」
「おまえ見てると身体中が苦しくなって、口から心臓が出そうになって、好きじゃないからなんだと思ってた。だけど、兄ちゃんに聞いたら、それは好きってことだよって言われて……」
「そう、なんだ」
「でも、急にそんな、嫌いだと思ってたのに本当は好きって気づいたら、どうしていいか分からなくて」
顔を真っ赤にしてつっかえながらそう告げてくるおチビちゃんが嘘を言っているようには思えなかった。
「なんで、何度も好きじゃないって言ったの」
「だから、分からなかったんだよ。兄ちゃんに教えてもらってからは、好きじゃないとか言ってねーし……」
言われてみれば、ここ数年のおチビちゃんからの冷ややかな言葉はどれも「おまえなんか好きじゃない」ではなかった気がする。幼心にインパクトがあり傷ついていたのでずっと引きずっていただけなのかもしれない。とはいえ「いじわる」とか「クソDJ」とかも大概だとは思うが。
「じゃあ、おチビちゃんも俺のこと好きってこと?」
「だから、何度も言わせんな! ……って」
「俺もだから言い合いっこしようよ」
ようやく気づいたおチビちゃんに笑いが止まらなくなって、くすくすと漏れ出る笑い声はおチビちゃんの怒りのポイントに触れたようだった。いつものように「ふぁーっく!」と元気な声をあげたおチビちゃんは、きっと近いうちに婚約者でも幼馴染でもなく俺の恋人になるんだろう。その日が待ち遠しくて、だけどそれ以上にもっと、もう一度婚約者に戻る日が楽しみだなと思った。
「おまえなんか、別に好きじゃない」
幼い頃から婚約者に浴びせられ続けてきたのは、そんな拒絶の言葉だった。所詮親同士が決めた結婚、物心ついた頃には「あなたたちは将来結婚するのよ」なんて煩わしく感じるほど聞かされ続け、自分自身感情が追いつく前に目の前の少年と自分はいつか結婚するんだなと事実として受け止めることしかできなかった。
だからそんなひどいことを言われても、正直な話「そうだろうな」としか思えなかった。とはいえ、親同士仲が良いこともあってよくお互いの家で遊んだし、三つ違いとはいえ同じくらいの年の子どもは周りにはお互いしかいなかったから、それなりの年齢になる頃には「おチビちゃんのこと、好きかも」なんて思うようになっていた。自分の気持ちが少しずつ変わっていったとはいえ、おチビちゃんは頑なに「おまえのことなんて好きじゃない!」という態度を貫いていたし、俺も俺で素直に好きアピールをするような性格でもないから、はいはいと受け流していた。それが俺たちの日常で、いつまでも続くと思っていた。
レオナルド・ライトの息子として一心に期待を受け、飛び級までして一気にヒーローとしての道を駆け上ったおチビちゃんは、俺と共にエリオスに入所した。相も変わらず婚約者とは思えないほど顔を合わせれば冷ややかな言葉を浴びせてくるおチビちゃんと、そんなおチビちゃんを子ども扱いする俺。そんな日常が変わったのは、いつも通りのある日のことだった。
「やっぱお子ちゃまだな〜」
「うるせえ! 一言余計なんだよっ!」
「どうしたの、アレ」
「あー、みんなで初恋はいつだったか、みたいな話になってね……」
なるほど。真面目なおチビちゃんはその質問に愚直にまだだと答えたんだろう。そしてそれを馬鹿にされて子どものように大騒ぎしている、と。まあ恋バナであることを除けばおおよそいつもの流れだ。珍しいことにルーキーたちが大集合して賑わっている談話室に立ち寄ったことをほんの少し後悔した。
「でもでも、稲妻ボーイって婚約者はいるんでしょ? その人とのエピソードとかはないの?」
「はぁ⁉︎ こいつに婚約者……」
厄介な流れになったな、なんて他人事のようにため息を吐く。実際は他人事どころか当事者中の当事者なんだけど。まあおチビちゃんがなんて答えるのかは気になるかな。なんて呑気に構えていたのが悪かったのか、頑として答えようとしないおチビちゃんをつつくのはやめたビリーが「そういえばDJにもいるんだよね、婚約者」と今度は俺に標準を合わせてきた。
「いるけど、こんなところで教えるようなことは何もないよ」
「お願い〜どんな人なのかだけで良いからぁ〜」
わざとらしく声を上げたビリーに、ここで必要以上に話を逸らすのはあまり良くないかなと思い至る。明言さえしなければ大丈夫でしょ。そう考えて、頭の中におチビちゃんの姿を思い浮かべた。
「いつもピィピィうるさいひよこみたいな子だよ。親が決めた相手だから恋バナってわけでもないでしょ。これでおしまい」
「えー、もうひと声!」
「なんかフェイスの婚約者って、ジュニアみたいなやつなんだな」
「え……」
まさかそれだけの情報で当てられるとは思わず言葉を無くしていると、おチビちゃんが勢いよく立ち上がって俺のことを指差した。怒っているのか顔が真っ赤で、嫌な予感がしたけどそれを止めるほどの余裕はなかった。
「お、おれだって好きでこんなやつの婚約者やってるんじゃねえし!」
「え?」
「うん……?」
「おチビちゃん……」
余計なことを言ってしまったとようやく気づいたのか百面相をするおチビちゃんと、ザワザワと騒がしくなる同期たち。こんなはずじゃなかったのになぁなんて独りごちていると「おれっ! もう部屋に戻る!」と全速力で談話室を出ていったおチビちゃんがジャックに咎められていた。いや、この雰囲気で俺だけ置いていくとかある?
あとで嫌味のひとつでも言ってやらないと。部屋に戻る気にもなれなくてこれからの行き先を脳内で探していると、ニヤニヤした顔のビリーが視界に入り込んできた。
「ヘイDJ、かわいい婚約者のこと追いかけなくてよかったの?」
「……怒るよ」
「まさかふたりがそう繋がるとはねぇ、初対面じゃないんだろうなとは思ってたけど」
「言ったでしょ、婚約者って言っても親が決めた結婚だから甘い空気とかそういうのはないんだよ」
「まああの稲妻ボーイだしね」
意味深に笑顔を浮かべるビリーから目を離して、意味もなくスマホの画面を見る。金になるから突いてはこないだろうが、俺の気持ちがどうかなんてとっくにお見通しなんだろう。本当に抜け目のないベスティだ。
一旦時間を置くとして、ご機嫌取りはちゃんとやらないと後々面倒なことになるだろうということが分かっている。なかなか良い案も浮かばずスマホの画面をつけたり消したり、手慰みにしているとビリーが「驚いた」と本当にそう思っているのかも微妙な声色で話しかけてきた。
「なにに」
「本当に好きなんだね」
「えっ」
その言葉に驚くと、ビリーが気まずそうに頭を掻く仕草を見せた。
「ごめん、カマかけてみただけなんだけど……」
「ちょっと」
もう怒る気にもなれず深く息を吐いて机に突っ伏す。気まずくなったのか俺たち以外の同期はいつの間にかいなくなっていて、今は閑散とした談話室に俺とビリーだけだ。
「DJは婚約者とか煩わしく思うタイプかと思ってたから、なんで婚約破棄とかしないんだろうって不思議だったけどそういうことだったんだね」
「皆まで言わなくていいから」
よりによって厄介な相手にバレてしまったことに肩を落とした。それからやけに脳内に残ったままの「婚約破棄」という文字が急に現実的なものになった気がする。いままでに全く考えたことがなかったわけではない。大人が時々提示してくるその言葉に頷かなかったのは俺自身で、生まれる前から決まっていた婚約に後ろめたさを感じ始めた大人たちに気持ちの逃げる隙を与えなかったのも俺だ。
何故って、俺はずっとおチビちゃんのことが好きだったからだ。どれだけ疎まれても、どれだけ好きじゃないと言われても、俺はおチビちゃんのことが好きだったから、どんな形であってもおチビちゃんと結婚したかった。
だけど、そろそろ潮時なのかもしれないとも思う。最初は照れ隠しだろうと気にしていなかったおチビちゃんからの「好きじゃない」も、こう何年も続くと流石に本心だということに気づくし、おチビちゃんの気持ちを捻じ曲げてまでする結婚ってなんだろうとも思う。嫌なことを無理やりするべきではないし、こんなにそばにいた俺のことをどうしても好きになれないというのなら手放してあげる方がおチビちゃんのためになるんじゃないか。それが紛いなりにもおチビちゃんよりも先に大人に差し掛かろうとしている俺にできる唯一のことなんじゃないかと気づき始めていた。
「……やっぱ柄じゃないことするのは向いてないのかもね」
返事がないことを期待した呟きのあとには予想通り静寂が訪れて、先ほどまでの騒々しい談話室とは別の空間にいるみたいだった。
◇◇◇
「おい、なに勝手なことしてんだよ」
「……何が?」
あの談話室での一件から十日経った。いままでであればおチビちゃんの機嫌を取って普段通りの生活に元通りって感じなんだけど、今回ばかりはそうもいかなかった。イライラを隠そうともしないおチビちゃんが、俺が座っていたベッドに乗り上げて胸ぐらを掴む。普段は希望いっぱいって感じで輝いているオッドアイが深い怒りに燃えていた。
「親父から聞いた。婚約破棄したって」
「ああそれね。そうだけど、それがどうかしたの?」
「……っ」
「この前おチビちゃんも言ってたじゃん。好きで婚約者やってるんじゃないって。実際その通りだし、お互い同じ気持ちならわざわざ古臭い婚約者なんていうしがらみに囚われなくてもいいんじゃないって思ってさ」
おチビちゃんも、こないだみたいに揶揄われるのもう嫌でしょ?
あくまでもおチビちゃんのためを思ってやりましたって姿勢を崩さずにそう言うと、癇に障ったのか俺を睨みつける視線が鋭くなった。このままもっと俺のことを嫌いになってくれ。そうしておチビちゃんの方からも俺と結婚はしないと宣言してくれれば、ようやく俺の恋心は静かな眠りにつくことができるのだから。
「大体、生まれる前からの親同士の口約束だなんて、おチビちゃんもずっと迷惑してたでしょ。俺も同期たちに揶揄われるのは嫌だし、ちょうどいいかなって。やっと殻のついたヒヨコちゃんから解放されるかと思うと清々するよ」
「おまえ、おれのことわざと怒らせようとしてるだろ」
「……なんでそう思ったの?」
「分からないわけねーだろ、ずっと一緒にいるんだから」
物心つく前からずっと一緒にいた。そこには大人たちの下心も多分に含まれていただろうけど、何よりおチビちゃんと過ごす時間が楽しくて、眩しかったからだ。大人になってからもずっと一緒にいられるのかと思うと嬉しくて、まだ意味も理解できていないうちから「婚約者っていいな」なんて思っていた。全く呑気なものだ。
一緒にいて、ずっと相手のことを見ているのは自分のほうだけだと思っていた。だけどさっきのおチビちゃんの言葉は、
「ずっと俺のことを見てたみたいな言い方するんだね」
そんな可愛げのない言葉しか出てこないのは、おチビちゃんよりも三年分早く大人になってしまったからだ。心の中でそう言い訳をすると、おチビちゃんが意味が分からないと言うように眉を顰めた。
「当たり前だろ、婚約者なんだから」
「好きでもないくせにね」
「それは……!」
何かを伝えようと大きく口を開いたおチビちゃんが声にならない声をあげて、それからまた口を閉じる。金魚みたいに何度も口をパクパクさせると、ようやく覚悟が決まったのかいつものおチビちゃんからは考えられないほど小さな声で話し始めた。
「好きじゃない、と思ってたんだよ」
「え?」
「おまえ見てると身体中が苦しくなって、口から心臓が出そうになって、好きじゃないからなんだと思ってた。だけど、兄ちゃんに聞いたら、それは好きってことだよって言われて……」
「そう、なんだ」
「でも、急にそんな、嫌いだと思ってたのに本当は好きって気づいたら、どうしていいか分からなくて」
顔を真っ赤にしてつっかえながらそう告げてくるおチビちゃんが嘘を言っているようには思えなかった。
「なんで、何度も好きじゃないって言ったの」
「だから、分からなかったんだよ。兄ちゃんに教えてもらってからは、好きじゃないとか言ってねーし……」
言われてみれば、ここ数年のおチビちゃんからの冷ややかな言葉はどれも「おまえなんか好きじゃない」ではなかった気がする。幼心にインパクトがあり傷ついていたのでずっと引きずっていただけなのかもしれない。とはいえ「いじわる」とか「クソDJ」とかも大概だとは思うが。
「じゃあ、おチビちゃんも俺のこと好きってこと?」
「だから、何度も言わせんな! ……って」
「俺もだから言い合いっこしようよ」
ようやく気づいたおチビちゃんに笑いが止まらなくなって、くすくすと漏れ出る笑い声はおチビちゃんの怒りのポイントに触れたようだった。いつものように「ふぁーっく!」と元気な声をあげたおチビちゃんは、きっと近いうちに婚約者でも幼馴染でもなく俺の恋人になるんだろう。その日が待ち遠しくて、だけどそれ以上にもっと、もう一度婚約者に戻る日が楽しみだなと思った。
1/16ページ