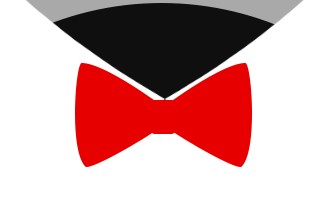フェイジュニ
退屈というのは誰にでも訪れるものであるし、齢十九になるフェイスにとっても初めてのことではなかった。ただ普段通りの退屈凌ぎに気が乗らなかっただけの話である。クラブに行く気分でもないし、だからと言ってひとりでレコードを回す気にもなれない。お気に入りのショコラは昨日切らしてしまっていて、シャワーを浴びるのも何か違うような気がする。
そんな折に部屋に帰ってきたのがレオナルド・ライト・ジュニアーーーフェイスの同室兼恋人の少年であった。恋人が退屈そうにベッドに転がっているというのに見向きもしないその態度に、フェイスの中の徒ら心が刺激された。そうだ、おチビちゃんのことを揶揄うのが一番いまの心持ちに沿っている気がする。そんなことを思いながら、あくまでも世間話の体を装って話しかける。
「おチビちゃんさぁ、こないだサウスが対応したサブスタンスのこと知ってる?」
「は? いきなり何だよ」
せっかく恋人が話しかけたというのにこの態度。まったくいつまでもお子ちゃまである。それでもいまのフェイスは大変機嫌が良いのだ。なんてったってお気に入りのおもちゃで遊ぼうとしているところなので。
フェイスが持ち込んだ話題は、先日サウスセクターが開いた交流会での話である。なんでも市民たちがサブスタンスの影響を受け、過度にときめきを求める「ロマンチック暴走症」なる状態に陥ってしまったのだとか。正直その部分が印象に残りすぎてどんな対応を取ったのかまではよく知らない。ブラッドに知られたら小言を言われそうではあるが、幸いなことにこの場に口うるさい兄の姿はなかった。
「ロマンチック暴走症ってやつ」
「ああ、アキラが言ってた……」
話に乗りかけたジュニアが怪訝そうな顔をしてはたと止まる。てっきりこのまま乗ってくるかと思ったのに、このお子ちゃまは勘が良くて存外侮れない。
「そうそう多分それ。すごいファンサさせられたらしいよ」
「……もうなんでもアリだな、サブスタンス」
「俺もファンサ欲しい」
「はぁ?」
「ファンサちょうだい。なるべくロマンチックなやつね」
金持ちの放蕩息子よろしく、いや実際にそうなのだが、普段よりもさらにその色を強めたフェイスがベッドに転がりながらファンサを求める図に、ジュニアは形の良い眉を吊り上げて睨むことしかできなかった。
フェイスとしてはファンサが欲しいというよりも、ジュニアの考えるロマンチックというものに興味がそそられた。ロマンチックのロの字も知らないようなお子ちゃまの考えるロマンチックなファンサは、きっとこの退屈な心を埋めるほど面白いに違いない。
大きな瞳がじろりとフェイスを睨んで、それから深いため息が部屋に落ちる。静寂すらも期待感を高める一助となってフェイスの鼓動を速める。空調の音、あるいは高所にあるタワーならではの強風に打ち消されるほどの小さな「……好きだ」という声は、おそらく聞き間違えではないだろう。フェイスは表情を弛緩させて薄ら笑いを浮かべた。
「それだけ?」
「だけってなんだ! だけって!」
「だってそんなのファンサでもロマンチックでもないじゃん」
ジュニアは日頃から愛の言葉を囁くようなタイプでもないので確かに一瞬驚いたものの、よく考えたらなんの捻りもない愛の言葉である。日頃のジュニアの言動の範疇を越えないという点で、フェイスの心を満足させるにはあと一歩刺激が足りない。
狙い通り会話ペースにはまって文句を垂れているジュニアに近づくため、フェイスはのそりと身体を起こした。久しぶりに縦に捉えた世界は、視界にジュニアがいるというだけでなんとなく面白い。
まだ発達途上な手を取って、ジュニアの部屋へと足を踏み入れる。不可侵領域であった過去はそう遠くないのに、いつの間にかなし崩し的に立ち入るようになったのは、フェイスとジュニアが恋人同士になったからに他ならない。
「わっ、わわっ……」
ベッドのへりにつんのめって慌てて体勢を戻そうとするジュニアの身体を軽くこずいて、シーツの海に倒れ込んだ恋人に覆い被さった。間近で見るオッドアイは遠くから見ている時よりもずっと繊細な色合いをしていて、フェイスは何度でもこの瞳に恋をしている。
まずは首筋。唇を這わせるとふるりと震える身体が逃げないようにするのは、案外難しいことではない。
それから手のひら。お互いのそこがくっつくように触れ合わせて、指をかき分けて握りしめる。いつまで経っても恋人繋ぎに慣れない両手にも、そろそろ握り返してほしい頃だ。
さいごに目と目を合わせると、静かな部屋にお互いの呼吸や鼓動の音まで聞こえてきて、フェイスはこの瞬間が大好きだった。キスをするために近づこうとすると、ジュニアはいつも力いっぱい目をつむる。今回はその習性を逆手に取って、キスをするふりをして近づいた。フェイスが心のままに動くと、ジュニアはいつも翻弄される。それはふたりが正反対であるからに他ならない。
「……いまだよ」
「え?」
「ロマンチックなこと、言ってみて」
恋人に押し倒されるこの状況でこの子はどんな言葉を口にするんだろうか。大きな瞳を何度も瞬かせてフリーズしてしまったジュニアの、次の言葉を待つ。
「……す、きだ」
「うん、合格」
同じ言葉だが状況が違うだけでこうも感じ方が違う。ロマンチックかと言われるとやはりその域には達していないが、まだ十六歳のお子ちゃまだ。これから少しずつ覚えていくだろう。
「ねえファンサービスってことはさ、俺以外の人にもこんなこと言うの?」
「ばかじゃねぇの」
ひねくれた返事しか返ってこなくても、フェイスにはそれが否であることは分かっている。それでもこんなときくらい素直に言わないよって言ってくれてもよくない? 呆れながら空気を吐くとその瞬間、ベッドに転がっていたジュニアがフェイスの首筋を引き寄せて強引にキスをした。
あまりにも突然なそれに勢いが止められず、歯同士はぶつかるし呼吸を止められてひどい息苦しさもある。それでも普段は受け身がちな舌先がフェイスの口内を探るようにそろりと這う様子は愛おしい。一刻も早く主導権を奪取したい欲求をどうにか鎮めて、フェイスはこの先の展開を待った。ジュニアがフェイスに翻弄されるように、フェイスもジュニアの何をしでかすか分からないところに強く惹かれているので。
「おまえ以外に、いるはずない」
「……アハッ」
どうやらこのお子ちゃまの中では、ロマンチックとは熱烈な愛の言葉であるらしい。だけどそれは本質的にはフェイスも同じだ。なぜならどんな美女に言い寄られた時よりも、夜景の綺麗な場所で告白されたときよりも、目の前にいる少年にまっすぐな愛を伝えられた時の方が間違いなく胸が高揚するのは事実なので。勘違いはいつか正してやるとして、いまは目の前のこの愛おしい恋人を味わい尽くしたい気分だ。
今度はフェイスの方からキスを交わすために近づくと、いつもの力いっぱい目をつむるジュニアはどこへやら。大きな瞳がじっとこちらを見てくる。このオッドアイに自分が映り込んでいる瞬間がたまらなく興奮するんだよな、と誰にも知られないように心の中でフェイスは反芻する。
いつの間にか退屈は跡形もなく消え去って、静かな部屋にはふたり分の呼吸と艶やかな口付けの音が聞こえていた。
そんな折に部屋に帰ってきたのがレオナルド・ライト・ジュニアーーーフェイスの同室兼恋人の少年であった。恋人が退屈そうにベッドに転がっているというのに見向きもしないその態度に、フェイスの中の徒ら心が刺激された。そうだ、おチビちゃんのことを揶揄うのが一番いまの心持ちに沿っている気がする。そんなことを思いながら、あくまでも世間話の体を装って話しかける。
「おチビちゃんさぁ、こないだサウスが対応したサブスタンスのこと知ってる?」
「は? いきなり何だよ」
せっかく恋人が話しかけたというのにこの態度。まったくいつまでもお子ちゃまである。それでもいまのフェイスは大変機嫌が良いのだ。なんてったってお気に入りのおもちゃで遊ぼうとしているところなので。
フェイスが持ち込んだ話題は、先日サウスセクターが開いた交流会での話である。なんでも市民たちがサブスタンスの影響を受け、過度にときめきを求める「ロマンチック暴走症」なる状態に陥ってしまったのだとか。正直その部分が印象に残りすぎてどんな対応を取ったのかまではよく知らない。ブラッドに知られたら小言を言われそうではあるが、幸いなことにこの場に口うるさい兄の姿はなかった。
「ロマンチック暴走症ってやつ」
「ああ、アキラが言ってた……」
話に乗りかけたジュニアが怪訝そうな顔をしてはたと止まる。てっきりこのまま乗ってくるかと思ったのに、このお子ちゃまは勘が良くて存外侮れない。
「そうそう多分それ。すごいファンサさせられたらしいよ」
「……もうなんでもアリだな、サブスタンス」
「俺もファンサ欲しい」
「はぁ?」
「ファンサちょうだい。なるべくロマンチックなやつね」
金持ちの放蕩息子よろしく、いや実際にそうなのだが、普段よりもさらにその色を強めたフェイスがベッドに転がりながらファンサを求める図に、ジュニアは形の良い眉を吊り上げて睨むことしかできなかった。
フェイスとしてはファンサが欲しいというよりも、ジュニアの考えるロマンチックというものに興味がそそられた。ロマンチックのロの字も知らないようなお子ちゃまの考えるロマンチックなファンサは、きっとこの退屈な心を埋めるほど面白いに違いない。
大きな瞳がじろりとフェイスを睨んで、それから深いため息が部屋に落ちる。静寂すらも期待感を高める一助となってフェイスの鼓動を速める。空調の音、あるいは高所にあるタワーならではの強風に打ち消されるほどの小さな「……好きだ」という声は、おそらく聞き間違えではないだろう。フェイスは表情を弛緩させて薄ら笑いを浮かべた。
「それだけ?」
「だけってなんだ! だけって!」
「だってそんなのファンサでもロマンチックでもないじゃん」
ジュニアは日頃から愛の言葉を囁くようなタイプでもないので確かに一瞬驚いたものの、よく考えたらなんの捻りもない愛の言葉である。日頃のジュニアの言動の範疇を越えないという点で、フェイスの心を満足させるにはあと一歩刺激が足りない。
狙い通り会話ペースにはまって文句を垂れているジュニアに近づくため、フェイスはのそりと身体を起こした。久しぶりに縦に捉えた世界は、視界にジュニアがいるというだけでなんとなく面白い。
まだ発達途上な手を取って、ジュニアの部屋へと足を踏み入れる。不可侵領域であった過去はそう遠くないのに、いつの間にかなし崩し的に立ち入るようになったのは、フェイスとジュニアが恋人同士になったからに他ならない。
「わっ、わわっ……」
ベッドのへりにつんのめって慌てて体勢を戻そうとするジュニアの身体を軽くこずいて、シーツの海に倒れ込んだ恋人に覆い被さった。間近で見るオッドアイは遠くから見ている時よりもずっと繊細な色合いをしていて、フェイスは何度でもこの瞳に恋をしている。
まずは首筋。唇を這わせるとふるりと震える身体が逃げないようにするのは、案外難しいことではない。
それから手のひら。お互いのそこがくっつくように触れ合わせて、指をかき分けて握りしめる。いつまで経っても恋人繋ぎに慣れない両手にも、そろそろ握り返してほしい頃だ。
さいごに目と目を合わせると、静かな部屋にお互いの呼吸や鼓動の音まで聞こえてきて、フェイスはこの瞬間が大好きだった。キスをするために近づこうとすると、ジュニアはいつも力いっぱい目をつむる。今回はその習性を逆手に取って、キスをするふりをして近づいた。フェイスが心のままに動くと、ジュニアはいつも翻弄される。それはふたりが正反対であるからに他ならない。
「……いまだよ」
「え?」
「ロマンチックなこと、言ってみて」
恋人に押し倒されるこの状況でこの子はどんな言葉を口にするんだろうか。大きな瞳を何度も瞬かせてフリーズしてしまったジュニアの、次の言葉を待つ。
「……す、きだ」
「うん、合格」
同じ言葉だが状況が違うだけでこうも感じ方が違う。ロマンチックかと言われるとやはりその域には達していないが、まだ十六歳のお子ちゃまだ。これから少しずつ覚えていくだろう。
「ねえファンサービスってことはさ、俺以外の人にもこんなこと言うの?」
「ばかじゃねぇの」
ひねくれた返事しか返ってこなくても、フェイスにはそれが否であることは分かっている。それでもこんなときくらい素直に言わないよって言ってくれてもよくない? 呆れながら空気を吐くとその瞬間、ベッドに転がっていたジュニアがフェイスの首筋を引き寄せて強引にキスをした。
あまりにも突然なそれに勢いが止められず、歯同士はぶつかるし呼吸を止められてひどい息苦しさもある。それでも普段は受け身がちな舌先がフェイスの口内を探るようにそろりと這う様子は愛おしい。一刻も早く主導権を奪取したい欲求をどうにか鎮めて、フェイスはこの先の展開を待った。ジュニアがフェイスに翻弄されるように、フェイスもジュニアの何をしでかすか分からないところに強く惹かれているので。
「おまえ以外に、いるはずない」
「……アハッ」
どうやらこのお子ちゃまの中では、ロマンチックとは熱烈な愛の言葉であるらしい。だけどそれは本質的にはフェイスも同じだ。なぜならどんな美女に言い寄られた時よりも、夜景の綺麗な場所で告白されたときよりも、目の前にいる少年にまっすぐな愛を伝えられた時の方が間違いなく胸が高揚するのは事実なので。勘違いはいつか正してやるとして、いまは目の前のこの愛おしい恋人を味わい尽くしたい気分だ。
今度はフェイスの方からキスを交わすために近づくと、いつもの力いっぱい目をつむるジュニアはどこへやら。大きな瞳がじっとこちらを見てくる。このオッドアイに自分が映り込んでいる瞬間がたまらなく興奮するんだよな、と誰にも知られないように心の中でフェイスは反芻する。
いつの間にか退屈は跡形もなく消え去って、静かな部屋にはふたり分の呼吸と艶やかな口付けの音が聞こえていた。