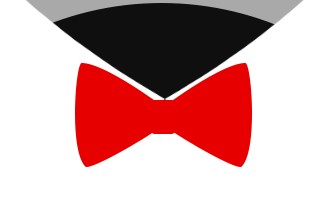フェイジュニ
クリスマスにもらって嬉しいもの、焼きたてのクッキー、お菓子がたくさん入ったブーツ、そして何と言っても一番はプレゼントボックスだろう。
何が出てくるのか分からないワクワク。箱を開ける時の高揚感。そして一番欲しかったものが出てきた時のよろこび。いくつになってもプレゼントを開くのは“うれしいこと”の象徴だった。
雪が降る季節になると心が躍るのは、きっと小さい頃のそんな記憶が思い出されるからだろう。それと、今年の冬がワクワクするのは隣にいるこの子のせいでもある。
「さみー」
「今年はいつもより雪が降るらしいよ」
「げー、マジか……」
真っ赤なマフラーに鼻まで埋めて隣を歩いているのはレオナルド・ライト・ジュニア、俺の恋人だ。あたたかい時期よりもその足取りは心なしか重い。ただでさえ成長途中なのに縮こまってさらに小さく見えて、言葉通り「おチビちゃん」である。
ぷっと吹き出すと、自分のことだと気付いたのかギロリとこちらを睨んでお決まりの「ふぁっく!」という随分な挨拶が飛んできた。
「おい、なに笑ってやがる」
「別にー」
「いまおれのこと笑ってただろ、おい!」
寒くて縮こまっていたというのに威勢のいいことだ。すっかり元通りくらいの大きさには戻った恋人とは、それでも目線が合わない。
クリスマス直前の道路は賑やかだ。華やかな電飾に、並んで歩くカップルや親子。その誰もが俺たちのことなんてまるで気にしていない。普段は街を守るヒーローとして注目されたりファンサービスをしたりする存在ではあるけれど、いまおチビちゃんのことを見ているのは俺だけだ。胸が躍るのは優越感に他ならない。
ほんの少しだけずれ上がったマフラーの隙間から指を差し込むと、おチビちゃんの身体がぷるりと震えた。冷たい指とほんのりあたたかい頬。指の腹ですり……となぞるとくすぐったいのか形のいい眉が寄った。ほんの少しとがった唇にキスを落とすと不服そうな表情で訴えかけてくる。
「つめたい……」
「アハ、ごめん」
「つーか、外ですんな!」
小さく首を振って周囲を見回すあたり、やっぱりおチビちゃんって真面目だ。もう一度、マフラーから溢れたふっくらとした頬に触れる。いくら大人ぶってみたところで、やっぱり俺から見たら「おチビちゃん」であることに変わりはない。
「赤ちゃんのほっぺもこんな感じ?」
「おい」
「触り心地いいね」
誰かに触れたいと思うこと、自分でない他人に触れて心が穏やかになったり、ワクワクしたりすること。そのどれもが、この子が恋人になって俺に教えてくれたことだ。
誰に触っても満たされなかった。だから恋人がたくさんいた。いま考えるとサイテーなやつだ。そんな俺のいいところを俺自身にたくさん教えてくれたのも、おチビちゃんだ。
「わっ」
おチビちゃんが突然俺の手を鷲掴んで、自分の頬に押し当てた。ほんのりあたたかかったはずのそこは、俺の手のひらによって少しずつ冷たくなっていく。
「なに……?」
「いまのうちに、思う存分触っとけ」
「は?」
「来年はもっと大人になってるんだからな!」
ふふんと満足げに俺の手を握っているおチビちゃんは、鼻の頭を真っ赤にしてまだまだお子様って感じ。言ってることもなんだか子どもみたいだし、自分には思いつかないようなまっすぐな言葉が飛び出てくる飽きない子。時々呆れることもあるけど、この子はそう、例えるならばプレゼントボックスに似ている。
スーパーヒーローの息子、飛び級、オッドアイ、最年少ルーキー。そんなキラキラのラッピングの中に、それを超えるような驚きとよろこびが詰まっている人。
きっと来年ではないだろうけど、おチビちゃんが言う通りすっかり大人になって、この柔らかくてあたたかい頬が俺と同じような大人と同じ輪郭を持つとき、それでもこの子は俺のことを離さないでいてくれるんだろう。
いまでも心の中に大切にしまわれたままのかつてのプレゼントたちみたいに、離れても、仮に別れたとしても、この子のことを思い出すたびに喜びだとか嬉しさだとか、そんなポジティブな感情も一緒に思い出すんだろう。
「帰ろっか」
「ん」
「手、繋いでもいい?」
「……別に、聞かなくてもいい」
差し出された手を繋ぐと、真っ赤な鼻と冷えた頬はまたマフラーの中にしまわれて、見ることも触れることもできなくなる。だけど俺はいつだってこのプレゼントを開けて冬のよろこびに触れることができるし、来年の冬も同じようにドキドキしながらおチビちゃんの頬を揉むんだろう。
もちろん冬だけじゃなくて、これから来る春も夏も秋も、全部の季節をおチビちゃんと一緒に過ごしていく。だけど俺にとってやっぱりおチビちゃんに感じるドキドキは、プレゼントを開く時のそれに似ているから、きっと来年も冬になったらより一層おチビちゃんのことが愛おしくなるんだろう。
周囲の誰もが俺たちのことを見ていないことにおチビちゃんも気がついたんだろう。先ほどまでとは打って変わって手を繋ぐことが許されて、ふたつの影はひとつになって華やかなイルミネーションに照らされている。
「帰ったらもう一回してもいい?」
「なっ! にを……」
「アハ、なんだと思う?」
さっきまであんなに大それたことをさせていたというのに、こんな言葉ひとつで目に見えるくらい緊張しちゃって。やっぱりおチビちゃんといると飽きないな。
マフラーを解いて、柔らかい頬に触れて、キスをして。誰にも邪魔されない場所でプレゼントボックスを開くのは、きっと格別の気分だろう。おチビちゃんが許してくれれば、もっと他のことをしたっていい。
あたたかい部屋で幸福と高揚感に包まれる時間を待ち遠しく思いながら、ひとつになった影が足早に街を抜けていく。口から漏れる白い息だけが、恋人たちが確かにここにいたことを証明していた。