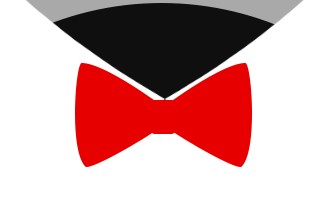フェイジュニ
赤いリップに、折れそうなほど細いヒール。あいつの周りにいる女の子は、流行りの服装を着こなしていて、みんなかわいい。そしてそんな彼女たちから求められると、あいつは躊躇もせず「かわいい」と言う。そんな姿にモヤモヤするようになったのはいつのことだったっけ。
「ジュニアまた珍しい格好してるのか〜」
「かわいい!似合ってるね」
「…おう、ありがとう」
珍しい格好、と評されたフレアなミニスカートは、おれの普段着にも似合うものを選んでもらった。そよそよと風が吹くたびに揺れるその感覚には未だに慣れないが、そのうち気にならなくなるのだろう。
服装に触れてきたメンター組に対して、唯一の同僚は冷ややかな目線だ。こいつはおれがオシャレした日はいつもこうだ。ちやほやしてくる女の子たちからすると見劣りするのか、上から下まで見回すと、ふいっと目を逸らしてしまう。
「…なんか言えよ」
「そんな格好して、急に仕事入ったらどうするの?もう少しヒーローとしての自覚を持った方がいいんじゃない?」
「……」
こんな調子だ。普段はヒーローのヒの字すら意識している様子のないやる気のなさなのに、おれがちょっとオシャレをしただけで突っかかってくる。
「まあまあジュニア、フェイスは照れてるだけだからさ」
「ちょっとディノ、変なこと言わないでくれる?」
言われる理由は十分に理解している。普段あれだけヒーローの自覚が足りない、とかおれに言われているから、フェイスは納得がいかないのだ。
今日こそは言ってもらえるかも、と期待した心には見ないふりをして、小さく「行ってきます」とだけ呟く。背負い慣れているギターケースがやけに重く感じて、折角天気の良いオフの日だというのに憂鬱だった。
「ま〜た振られちまったのか!元気出せよジュニア!」
「振られてねえし!てか何で知ってんだよ!」
「兄貴から聞いたぜ」
「兄ちゃん…!」
対バン相手との打ち合わせ中な兄ちゃんは、食えない笑顔でニコッとこちらを見た。その姿が最近ずっと脳内を占拠しているクソ野郎と重なって、無性に腹が立った。
感情に任せてギターを弾くと、呼応するようにバンドのメンバーたちが盛り上がっていく。お客さんの前で披露するときの感覚も好きだが、開場前の高揚感はなにものにも変え難い。夢中でギターをかき鳴らすと、心のモヤモヤが少しだけ晴れたような気がした。
「いや〜今日は一段と盛り上がったな!」
「サイコーだったぜジュニア!」
俺たちの盛り上がりが伝わったのか、客の反応もよく、ライブは大成功だった。着てきた私服に着替え、帰り支度をしていると、近寄ってきたのは対バン相手の一人だった。特にノリが良くて陽気なヤツだ。
「おう、おつかれジュニア。今日この後ヒマか?」
「特に用事はないけど…」
気のいいヤツだが、からみ酒が厄介なんだと以前兄ちゃんが言っていたこともあり、警戒が顔に出てしまったのだろう。そいつが慌てた様子で言葉を継ぐ。
「いやあ、コイツがさ!一緒に飯でも行かねえかって」
呼び出されたのは、メンバーの中でも若く新参者の男だった。今日の準備やライブ中にもさりげなく話しかけてきてくれていたのを思い出す。申し訳なさそうなその表情に、この男も多分推しの強いメンバーに逆らえなかったのだろうと当たりをつける。時間は19時30分。小腹も空いているし、軽く食べて帰るくらいなら問題ないだろう。
了承すると「ホテルは二回目以降にしろよ」と汚いヤジが飛ぶ。兄ちゃんに目配せをすると「何かあったら電話しろ」とハンドサインが飛んできた。この気弱そうな男が手を出してくるなんてあり得ないと分かっているくせに、どいつもこいつも勝手な想像をするものだ。
案の定和やかな雰囲気のまま終わった「お食事会」だったが、意外と音楽に対する価値観が合うという事が分かり、そのうち一緒に好きなバンドのライブに行くことになった。次のライブの予定を嬉々として語る姿が兄ちゃんに似ていて、微笑ましく感じた。
「普段とは違うけど、その服装もかわいい」と言及されたスカートだけが少しだけ居心地を悪くした。欲しい言葉なのに、相手が違うだけでこんなにも満たされないものなんだという事実がおれの心を暗くする。
どれだけ願っても無駄なのに、それでもフェイスからの一言を求めてしまう浅ましさが嫌になる。
こんな惨めな初恋なんて捨ててしまって、おれの隣で穏やかに笑ってくれるこの男と幸せになれればいいのに。そんな気持ちを知ってか知らずか、店を出た途端に降り出した雨がおれたちを濡らす。
「降り出したな、じゃあ…」
「あ、あの…傘、あるんだけど」
急いで帰ろうとすると、鞄から出したのか大きめの折り畳み傘を手渡される。
「でも、これじゃアンタが濡れるだろ」
「じゃ、じゃあ、送って行かせてよ!女の子をそのまま帰すなんてできないよ」
広げられた傘は、確かにおれと二人で入っても十分なサイズ感だ。お言葉に甘えて横に並ぶと、男は耳まで真っ赤になっていた。この距離感は確かに、少し照れくさいかも。
会話だけは途切れることなく、降り続く雨の中をタワーまで並んで歩いた。
帰り着くと、こんな時間だというのにタワーの入り口には人だかりが出来ていた。しかも女だらけ。嫌な予感がして、隣の男に礼だけ言って足早に通り過ぎようとすると、人だかりの中心から聞きなれた声がかけられた。
「アハ、おチビちゃんも男連れで帰ってくるようになったんだね。やるじゃん」
「クソDJ…」
「こんな時間までどこに行ってたの?」
「…べつに、ライブだよ」
「ライブはもっと早く終わったでしょ」
おれの一挙一動が気に食わないなら、声をかけなければいいのに。自分のことは隠したがるくせに、こういうときばかり食い下がってくるクソ野郎に思わず声を荒げてしまう。
「だったら何だってんだよ!お前だって女と飯行ってんだろ!」
「ふーん、ご飯行ったんだ。それって二人で?今日はお兄さんたちも一緒だったんだよね」
「だとしても、お前に関係ねえだろ!いつもいつも突っかかってきて、ウゼーんだよ!」
ギャラリー有りの口喧嘩に、タワー内からも人が出てくる。売り言葉に買い言葉、止まれなくなったおれたちは、その後キースとディノの手によって部屋に回収されるまで、口争いを続けるのだった。
やっちまった。そう気付いたのは次の日の朝。起きた瞬間から感じる身体の気怠さと火照り。冷たい雨の中履き慣れないスカートを履き続けた上、帰ってきてからはフェイスとのくだらない諍いからの説教コースだったので、すっかり身体を冷やしてしまったのだろう。
やっぱりおれみたいな男女が「かわいい」と思われようとしたのが間違いだったのだ。
ポーチから解熱剤を取り出して、用法通りに飲む。どれくらい効くかは分からないが、嚥下した水の冷たさが火照った身体にちょうど良かった。
「ねぇ…」
どうせ起きてないだろうと高を括っていた同室の男が、じっとこちらを見ている。別に悪いことはしていないのに、見られていたのが気まずくて、声をかけられたのもお構いなしに部屋を出た。
共有スペースではディノと、今日も叩き起こされたのであろうキースが欠伸をしながら食事を準備している。熱のせいか普段は美味しく感じるチーズやベーコンの匂いが気持ち悪くて早めに部屋を出た。
外はまだ冬の寒さだが、雨もなくしっかりと着込んでいる分昨日よりは随分とマシに思える。
「ねえ、待ってよ」
「…追いかけてくんな」
「話がしたいんだけど」
「話すことなんて何もねえよ」
足早に去ろうとすると、リーチの差で軽々と追いついてくる。肩に触れた手が、昨夜見た光景と重なって反射的に振り解いた。
「おれは…!」
何が言いたかったんだっけ。こいつになんて言ってもらいたかったんだっけ。クラクラする頭の中で「かわいい」と女の子たちに言葉を振りまくフェイスの姿が回っていた。
目が覚めると、見慣れた天井に肌触り。まごうことなき自分の部屋のベッドだ。身体を起こそうとすると、何かの重みに邪魔されていることに気づく。空いている手で探ると、触り心地の良い髪にたどり着いた。艶やかな黒は、ここしばらく焦がれている男のものだ。
おれの体温が高いのか、それともこいつの体が冷たいのか、ひんやりとした手のひらにそっと触れた。
ここまで運んできてくれたのかな。憎たらしいこともあるが、実は優しいことも知っているし、そういうところが好きなんだ。まあ、こいつのことだから、ついでにサボれてラッキーってところだろう。おれよりも深く眠っているその横顔が大嫌いで、でも大好きなことに気づいてしまったから、この勝負はどう足掻いてもおれの負けなのだ。
せめて「かわいい」の一言くらいは欲しかったけど、こいつが意地でも言わないというのなら、この気持ちはすっぱりと諦めてしまおう。
惨めなまま心の一番奥深くにしまって、墓場まで持っていくのだ。
重ねたままの手のひらをそのままにしていると、くすぐったかったのかフェイスが「うーん」と伸びをした。手を離して、なんでもないような顔をして、そっぽを向く。
「おチビちゃん、目が覚めたんだね」
「…おう」
寝起きだからか、甘ったるい声を向けられて涙が出そうになった。それはずっと自分にも向けて欲しいと思っていたもので、ついでに「かわいい」って思って欲しくて。つい今しがた墓場まで連れて行こうと思っていた暴れ馬のような恋心がまた目を覚ました。
「あのさ」
口を開いたのはフェイスだった。必死で締め付けようとしている心を、いとも簡単にこじ開けようとしてくる柔らかな声色。じんわりと涙が滲んだので、バレないように下を向いた。
「昨日は、みっともないことしてごめん」
みっともないこと。すぐに思い浮かばなくて、記憶を巡らせる。帰りのタワーでのことだろうか。でも、おれたちの間ではあんな口喧嘩なんて「よくあること」だ。
離したはずの手のひらが触れる。今度はフェイスから近寄ってきたのだ。おれの、到底女の子らしくはないカサカサの手の甲を、大事なもののように撫でるその動きがくすぐったい。
分からない、という表情を読まれたのか、フェイスは「昨日の、朝も夜も」と続ける。
「ディノにかわいいって言われて照れてる姿に嫉妬してたんだ。夜は知らない男と夜遅くに帰ってくるし、つい嫌なこと言っちゃった。ごめんね」
「こっちこそ、ごめん…」
言いすぎてしまったことを謝るなんて、こいつにしては殊勝な態度だ。
「心配しちゃうから、あんな短いスカートで夜に出歩くのはもうやめてね」
「…やっぱり、似合ってなかったか?」
言及されたスカートは、やっぱり「かわいい」とは言ってもらえなくて。そんな面倒くさい女みたいなことを聞くと、案の定深いため息が返ってきた。
「ごめん、変なこと聞いた」
「似合ってるよ、すごく可愛い。だから心配って、分かる?」
頬にそっと触れられた手は、優しいながら強引に上を向かせる。溢れた涙でぼんやりとしたフェイスの輪郭と、印象的なマゼンタの瞳が真っ直ぐにこちらを見ている。
「好きだよ、おチビちゃん。信じてもらえないかもしれないけど、ずっと好きだった」
「なっ…」
何か言いたいのに、どれも言葉にならずに嗚咽として溢れていく。一緒にあふれた涙を掬ったのは、フェイスの指先だった。
「ゆっくりでいいから、おチビちゃんの気持ちも教えてほしいな」
「お、おれ」
どれくらい伝えられたかは分からないが、一つひとつ言葉にした。おれもフェイスが好きってこと、周りの女の子たちが羨ましくて、自分も「かわいい」って思われたかったこと。
「クソDJのことが、すきだ」
「嬉しい…」
抱きしめられたと気付いたのは、フェイスの匂いに包まれたからだ。耳元で聴こえる鼓動がおれよりも早くて、らしくもなく緊張していたことを知った。
「ジュニアまた珍しい格好してるのか〜」
「かわいい!似合ってるね」
「…おう、ありがとう」
珍しいと称されたプリーツスカートはおれのお気に入りだ。そよそよと風が吹くたびに控えめに揺れる足元の春色が気分を高める。
「なんだ、先に出てたのか」
「準備遅え」
「フェイスと出かけるのか!それなら安心だな」
「遅くならないうちに帰ってこいよ〜」
それぞれらしいことを言って送り出してくれたメンターズに別れを告げて、春の街を歩き出す。
「おチビちゃん」
「ん…」
見上げると、不意に短いキスが落ちてくる。まだ朝とはいえ往来での突然の行動に怒ると、おれに負けず劣らず赤く染まった頬の男が一言呟いた。
「ジュニアまた珍しい格好してるのか〜」
「かわいい!似合ってるね」
「…おう、ありがとう」
珍しい格好、と評されたフレアなミニスカートは、おれの普段着にも似合うものを選んでもらった。そよそよと風が吹くたびに揺れるその感覚には未だに慣れないが、そのうち気にならなくなるのだろう。
服装に触れてきたメンター組に対して、唯一の同僚は冷ややかな目線だ。こいつはおれがオシャレした日はいつもこうだ。ちやほやしてくる女の子たちからすると見劣りするのか、上から下まで見回すと、ふいっと目を逸らしてしまう。
「…なんか言えよ」
「そんな格好して、急に仕事入ったらどうするの?もう少しヒーローとしての自覚を持った方がいいんじゃない?」
「……」
こんな調子だ。普段はヒーローのヒの字すら意識している様子のないやる気のなさなのに、おれがちょっとオシャレをしただけで突っかかってくる。
「まあまあジュニア、フェイスは照れてるだけだからさ」
「ちょっとディノ、変なこと言わないでくれる?」
言われる理由は十分に理解している。普段あれだけヒーローの自覚が足りない、とかおれに言われているから、フェイスは納得がいかないのだ。
今日こそは言ってもらえるかも、と期待した心には見ないふりをして、小さく「行ってきます」とだけ呟く。背負い慣れているギターケースがやけに重く感じて、折角天気の良いオフの日だというのに憂鬱だった。
「ま〜た振られちまったのか!元気出せよジュニア!」
「振られてねえし!てか何で知ってんだよ!」
「兄貴から聞いたぜ」
「兄ちゃん…!」
対バン相手との打ち合わせ中な兄ちゃんは、食えない笑顔でニコッとこちらを見た。その姿が最近ずっと脳内を占拠しているクソ野郎と重なって、無性に腹が立った。
感情に任せてギターを弾くと、呼応するようにバンドのメンバーたちが盛り上がっていく。お客さんの前で披露するときの感覚も好きだが、開場前の高揚感はなにものにも変え難い。夢中でギターをかき鳴らすと、心のモヤモヤが少しだけ晴れたような気がした。
「いや〜今日は一段と盛り上がったな!」
「サイコーだったぜジュニア!」
俺たちの盛り上がりが伝わったのか、客の反応もよく、ライブは大成功だった。着てきた私服に着替え、帰り支度をしていると、近寄ってきたのは対バン相手の一人だった。特にノリが良くて陽気なヤツだ。
「おう、おつかれジュニア。今日この後ヒマか?」
「特に用事はないけど…」
気のいいヤツだが、からみ酒が厄介なんだと以前兄ちゃんが言っていたこともあり、警戒が顔に出てしまったのだろう。そいつが慌てた様子で言葉を継ぐ。
「いやあ、コイツがさ!一緒に飯でも行かねえかって」
呼び出されたのは、メンバーの中でも若く新参者の男だった。今日の準備やライブ中にもさりげなく話しかけてきてくれていたのを思い出す。申し訳なさそうなその表情に、この男も多分推しの強いメンバーに逆らえなかったのだろうと当たりをつける。時間は19時30分。小腹も空いているし、軽く食べて帰るくらいなら問題ないだろう。
了承すると「ホテルは二回目以降にしろよ」と汚いヤジが飛ぶ。兄ちゃんに目配せをすると「何かあったら電話しろ」とハンドサインが飛んできた。この気弱そうな男が手を出してくるなんてあり得ないと分かっているくせに、どいつもこいつも勝手な想像をするものだ。
案の定和やかな雰囲気のまま終わった「お食事会」だったが、意外と音楽に対する価値観が合うという事が分かり、そのうち一緒に好きなバンドのライブに行くことになった。次のライブの予定を嬉々として語る姿が兄ちゃんに似ていて、微笑ましく感じた。
「普段とは違うけど、その服装もかわいい」と言及されたスカートだけが少しだけ居心地を悪くした。欲しい言葉なのに、相手が違うだけでこんなにも満たされないものなんだという事実がおれの心を暗くする。
どれだけ願っても無駄なのに、それでもフェイスからの一言を求めてしまう浅ましさが嫌になる。
こんな惨めな初恋なんて捨ててしまって、おれの隣で穏やかに笑ってくれるこの男と幸せになれればいいのに。そんな気持ちを知ってか知らずか、店を出た途端に降り出した雨がおれたちを濡らす。
「降り出したな、じゃあ…」
「あ、あの…傘、あるんだけど」
急いで帰ろうとすると、鞄から出したのか大きめの折り畳み傘を手渡される。
「でも、これじゃアンタが濡れるだろ」
「じゃ、じゃあ、送って行かせてよ!女の子をそのまま帰すなんてできないよ」
広げられた傘は、確かにおれと二人で入っても十分なサイズ感だ。お言葉に甘えて横に並ぶと、男は耳まで真っ赤になっていた。この距離感は確かに、少し照れくさいかも。
会話だけは途切れることなく、降り続く雨の中をタワーまで並んで歩いた。
帰り着くと、こんな時間だというのにタワーの入り口には人だかりが出来ていた。しかも女だらけ。嫌な予感がして、隣の男に礼だけ言って足早に通り過ぎようとすると、人だかりの中心から聞きなれた声がかけられた。
「アハ、おチビちゃんも男連れで帰ってくるようになったんだね。やるじゃん」
「クソDJ…」
「こんな時間までどこに行ってたの?」
「…べつに、ライブだよ」
「ライブはもっと早く終わったでしょ」
おれの一挙一動が気に食わないなら、声をかけなければいいのに。自分のことは隠したがるくせに、こういうときばかり食い下がってくるクソ野郎に思わず声を荒げてしまう。
「だったら何だってんだよ!お前だって女と飯行ってんだろ!」
「ふーん、ご飯行ったんだ。それって二人で?今日はお兄さんたちも一緒だったんだよね」
「だとしても、お前に関係ねえだろ!いつもいつも突っかかってきて、ウゼーんだよ!」
ギャラリー有りの口喧嘩に、タワー内からも人が出てくる。売り言葉に買い言葉、止まれなくなったおれたちは、その後キースとディノの手によって部屋に回収されるまで、口争いを続けるのだった。
やっちまった。そう気付いたのは次の日の朝。起きた瞬間から感じる身体の気怠さと火照り。冷たい雨の中履き慣れないスカートを履き続けた上、帰ってきてからはフェイスとのくだらない諍いからの説教コースだったので、すっかり身体を冷やしてしまったのだろう。
やっぱりおれみたいな男女が「かわいい」と思われようとしたのが間違いだったのだ。
ポーチから解熱剤を取り出して、用法通りに飲む。どれくらい効くかは分からないが、嚥下した水の冷たさが火照った身体にちょうど良かった。
「ねぇ…」
どうせ起きてないだろうと高を括っていた同室の男が、じっとこちらを見ている。別に悪いことはしていないのに、見られていたのが気まずくて、声をかけられたのもお構いなしに部屋を出た。
共有スペースではディノと、今日も叩き起こされたのであろうキースが欠伸をしながら食事を準備している。熱のせいか普段は美味しく感じるチーズやベーコンの匂いが気持ち悪くて早めに部屋を出た。
外はまだ冬の寒さだが、雨もなくしっかりと着込んでいる分昨日よりは随分とマシに思える。
「ねえ、待ってよ」
「…追いかけてくんな」
「話がしたいんだけど」
「話すことなんて何もねえよ」
足早に去ろうとすると、リーチの差で軽々と追いついてくる。肩に触れた手が、昨夜見た光景と重なって反射的に振り解いた。
「おれは…!」
何が言いたかったんだっけ。こいつになんて言ってもらいたかったんだっけ。クラクラする頭の中で「かわいい」と女の子たちに言葉を振りまくフェイスの姿が回っていた。
目が覚めると、見慣れた天井に肌触り。まごうことなき自分の部屋のベッドだ。身体を起こそうとすると、何かの重みに邪魔されていることに気づく。空いている手で探ると、触り心地の良い髪にたどり着いた。艶やかな黒は、ここしばらく焦がれている男のものだ。
おれの体温が高いのか、それともこいつの体が冷たいのか、ひんやりとした手のひらにそっと触れた。
ここまで運んできてくれたのかな。憎たらしいこともあるが、実は優しいことも知っているし、そういうところが好きなんだ。まあ、こいつのことだから、ついでにサボれてラッキーってところだろう。おれよりも深く眠っているその横顔が大嫌いで、でも大好きなことに気づいてしまったから、この勝負はどう足掻いてもおれの負けなのだ。
せめて「かわいい」の一言くらいは欲しかったけど、こいつが意地でも言わないというのなら、この気持ちはすっぱりと諦めてしまおう。
惨めなまま心の一番奥深くにしまって、墓場まで持っていくのだ。
重ねたままの手のひらをそのままにしていると、くすぐったかったのかフェイスが「うーん」と伸びをした。手を離して、なんでもないような顔をして、そっぽを向く。
「おチビちゃん、目が覚めたんだね」
「…おう」
寝起きだからか、甘ったるい声を向けられて涙が出そうになった。それはずっと自分にも向けて欲しいと思っていたもので、ついでに「かわいい」って思って欲しくて。つい今しがた墓場まで連れて行こうと思っていた暴れ馬のような恋心がまた目を覚ました。
「あのさ」
口を開いたのはフェイスだった。必死で締め付けようとしている心を、いとも簡単にこじ開けようとしてくる柔らかな声色。じんわりと涙が滲んだので、バレないように下を向いた。
「昨日は、みっともないことしてごめん」
みっともないこと。すぐに思い浮かばなくて、記憶を巡らせる。帰りのタワーでのことだろうか。でも、おれたちの間ではあんな口喧嘩なんて「よくあること」だ。
離したはずの手のひらが触れる。今度はフェイスから近寄ってきたのだ。おれの、到底女の子らしくはないカサカサの手の甲を、大事なもののように撫でるその動きがくすぐったい。
分からない、という表情を読まれたのか、フェイスは「昨日の、朝も夜も」と続ける。
「ディノにかわいいって言われて照れてる姿に嫉妬してたんだ。夜は知らない男と夜遅くに帰ってくるし、つい嫌なこと言っちゃった。ごめんね」
「こっちこそ、ごめん…」
言いすぎてしまったことを謝るなんて、こいつにしては殊勝な態度だ。
「心配しちゃうから、あんな短いスカートで夜に出歩くのはもうやめてね」
「…やっぱり、似合ってなかったか?」
言及されたスカートは、やっぱり「かわいい」とは言ってもらえなくて。そんな面倒くさい女みたいなことを聞くと、案の定深いため息が返ってきた。
「ごめん、変なこと聞いた」
「似合ってるよ、すごく可愛い。だから心配って、分かる?」
頬にそっと触れられた手は、優しいながら強引に上を向かせる。溢れた涙でぼんやりとしたフェイスの輪郭と、印象的なマゼンタの瞳が真っ直ぐにこちらを見ている。
「好きだよ、おチビちゃん。信じてもらえないかもしれないけど、ずっと好きだった」
「なっ…」
何か言いたいのに、どれも言葉にならずに嗚咽として溢れていく。一緒にあふれた涙を掬ったのは、フェイスの指先だった。
「ゆっくりでいいから、おチビちゃんの気持ちも教えてほしいな」
「お、おれ」
どれくらい伝えられたかは分からないが、一つひとつ言葉にした。おれもフェイスが好きってこと、周りの女の子たちが羨ましくて、自分も「かわいい」って思われたかったこと。
「クソDJのことが、すきだ」
「嬉しい…」
抱きしめられたと気付いたのは、フェイスの匂いに包まれたからだ。耳元で聴こえる鼓動がおれよりも早くて、らしくもなく緊張していたことを知った。
「ジュニアまた珍しい格好してるのか〜」
「かわいい!似合ってるね」
「…おう、ありがとう」
珍しいと称されたプリーツスカートはおれのお気に入りだ。そよそよと風が吹くたびに控えめに揺れる足元の春色が気分を高める。
「なんだ、先に出てたのか」
「準備遅え」
「フェイスと出かけるのか!それなら安心だな」
「遅くならないうちに帰ってこいよ〜」
それぞれらしいことを言って送り出してくれたメンターズに別れを告げて、春の街を歩き出す。
「おチビちゃん」
「ん…」
見上げると、不意に短いキスが落ちてくる。まだ朝とはいえ往来での突然の行動に怒ると、おれに負けず劣らず赤く染まった頬の男が一言呟いた。