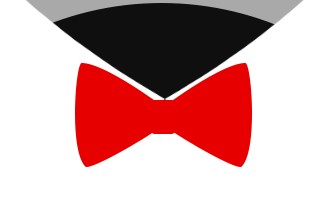フェイジュニ
【嘘つきは恋人のはじまり】女体化
恋とはもっと、甘やかなものだと思っていた。
先人たちの歌にはそう綴られていたし、身近なものたちは恋しい相手の話をするたびに甘いものでも頬張っているような蕩けた顔をする。だから、自分もそうなるものだと思っていた。
恋とは一律に甘くて、美しくて、煌びやかなもの。そんな幻想を打ち砕いたのは、おれが恋をした相手だった。
「諸事情あってさ、恋人が必要なんだよね」
だから付き合ってよ。
いとも軽々しく伝えられた言葉に、心が冷えていく。
これは取引でもなんでもなく、おれの答えが分かった上で与えられたひとときの夢。一方的で強引なこの夢から覚めた後の冷たい世界は想像に容易いけれど、それでもおれは首を縦に振るしかないのだ。
「分かった。お前と…付き合う」
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアと目の前のこの男、フェイス・ビームスは恋人同士となったのだった。
◇◇◇
【はじめての恋人】
「恋人同士ってさ、何すんの」
「はぁ?」
恒例になりつつあるA班のゲーム集会中にぽろりと漏れたおれの言葉に真っ先に反応したのは、他でもないアキラだった。
あとの二人…グレイとガストは顔を赤くしたり、ポリポリと頭を掻いたり…それぞれらしい反応で固まっている。
「それは恋人同士なんだし?手繋いだりとか、キスしたりとか…」
「ガキの恋愛ごっこかよ。そりゃセッ…」
「アキラ、ストップ。ジュニアは女の子だぞ。あー、一緒に映画観るとか、カフェに行くとかいいんじゃねえか?」
好き勝手に騒ぎ立てる言葉から、心当たりのあるものだけをチョイスする。
手を繋ぐ、キスをする、映画を観る、カフェに行く、それから……
ボンっという効果音でも付きそうなほど真っ赤になった顔を扇いでいると、ニヤついた顔のアキラが身を乗り出す。
「はっはーん、さてはお前、コイビトが出来たな」
「う、うるせえな、そうじゃねぇと聞かねーだろ」
「誰だよ、教えろよ〜」
「うるせー!しらねー!」
アキラと二人で取っ組み合いをしているとドアが開いて、間抜けな顔をしたフェイス…もといクソDJが入ってきた。誰もいないからとウエストの共有スペースでゲーム会を開いていたのだが、予定が早く終わったのだろうか。どことなく機嫌の悪いフェイスは、こちらをチラッと見ただけで一言も発することなくへ自室へ戻っていった。
「も、もしかしてフェイスくん…怒ってた?」
「勝手にココ使ったからか?」
「いや、いちおー使う前にみんなに一声かけておいたからそれはないんじゃね」
「てかおい、喋ってねーで降りろチビっこ」
「うるせー、誰がチビだ!」
鳩尾に手を置いて、乗り上げていたアキラから降りる。ぐっと力が入った瞬間「ぐえっ」と聞こえてきて何度も咳き込む姿が見えたが、こちらは髪を引っ張られたり馬鹿力で押さられたりしているのだ。お互い様というやつだろう。
理由は分からないが、クソDJが機嫌最悪マックスで帰ってきたので、今日のゲーム会はお開きの流れになった。おれとしても、冷やかされる一歩手前の空気感に耐えかねていたところだったのでありがたい。
「あー、さっきの話だけどさ」
最後に余ったお菓子とゲーム機を持ったガストが小さい声で耳打ちをする。
「フェイスに聞いてみるのがいいと思うぜ」
「フェイスに…」
一体何の話だろう。首を傾げながら見送ると、背後に気配があることに気がついた。
斜め上を見上げると、やはり機嫌の悪いフェイスが、今しがた三人の出て行った扉を冷ややかな目で見ている。
「仲良いんだね、A班って」
「仲良いって…B班もたまに集まってんじゃねーのかよ」
「俺らはお茶するとか談笑するとかその程度。ボディタッチしたり顔近づけて内緒話するほど仲良くはないよ」
「はぁ?何だよそれ…」
わざわざ棘のある言い方をしてくるクソDJに、瞬間的に怒りが湧く。
「何があったか知らねーけどよ、関係ないおれたちにまでそーいう態度取って…」
「…なくない」
「え?」
ドン、と壁に押さえつけられたのはその瞬間のことだった。呼吸のひとつ、鼓動のひとつですら手にとるような位置にいるのは初めてのことだ。美術品のように整った顔が近寄ってくる。おれの顔を目掛けてフッと息を吐いてきたので、息が苦しくなってそのままゲホゲホと咳き込んだ。
「関係なくないよ」
「は……」
聞きたかった言葉たちは、少しだけかさついた唇に飲み込まれていく。唇が触れ合うだけでは終わらない深いキスに、脳内に浮かんでいたバラバラの単語も真っ白く塗り潰されて、あとには荒い息を吐くおれたちだけが残されてしまった。
なんで、どうして、いまのは何?
やっと回り始めた脳内に浮かぶのはそんな要領を得ない質問ばかりで、浮かんでいた涙が一粒だけぽろりと落ちる。
「俺が機嫌悪い理由が知りたかったんでしょ。おチビちゃんとアイツら…A班の人たち、関係ないどころか俺が機嫌悪い原因そのものだよ」
「なんで…だってお前、帰ってきたばっかりで…」
「そう、帰ってきたばっかり。それで自分の彼女が他の男とボディタッチして、挙句キスされそうなくらいの距離で内緒話してるの見た時の気分、おチビちゃんには分からないか」
「そんな、の…」
コイツは事情があって仕方なくおれを恋人にしただけのどうしようもない奴だ。なのに何でここんなに怒ってるんだろう。分かるわけないだろ、と直接言えない分、心の中で悪態を吐く。
「俺の彼女になったからには、もう二度と他の男とあんなことしちゃダメ。分かった?」
小さく頷くと、大きな手が「いいこ」とおれの頭を撫でる。
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスから、理解不能な強烈な束縛を受けることになったのだった。
◇◇◇
【はじめての手を繋ぐ】
クソ寒い日のパトロール休憩に入ったのは、おれでも入りやすいような若者向けのカフェだった。選んだのはもちろんクソDJで、ボックス席の向かいに腰掛けて機嫌良さそうな笑みを浮かべている。
「ご注文お伺いします」
「コーヒーとオレンジジュース一つずつ」
「少々お待ちください」
店員が厨房に戻っていくのを見計らってプッと噴き出す音が聞こえてくる。小刻みに肩を揺らしているのは目の前に座るソイツしかいない。
「…なんだよ」
「カフェに来てオレンジジュースって…ふふっ」
「飲めないもの残すよりいいだろ」
「まぁそれもそうだけど…アハっ、やっぱりおチビちゃんだね」
「ふぁーっく!だれがガキだコラ!」
店内だから小さな声で。お互いに届く程度の小競り合いを続けていると、オレンジジュースとコーヒーを持った店員が戻ってきた。クソDJの前には湯気立つコーヒーを置いて、おれにはオレンジジュースを手渡してくる。溢さないようにと受け取ると、指先がほんの少しだけ触れたのが分かった。その瞬間、いかにも女にモテそうな店員がこちらにニッコリと微笑みかける。
訳も分からず首を傾げると、先程のクソDJと同じような噴き出す寸前のような笑みを浮かべて「ごゆっくり」と去っていった。まあいいか、とストロー越しのオレンジジュースに口をつけると、じっとりと張りつくような目線を送ってきているクソDJと目が合った。
「な、なんだよ…」
「別に…」
さっきまで機嫌良く笑っていたはずなのに、変なやつだ。ふいっと窓の方を向いてしまって、もはや目も合わなくなってしまった。
気まずい空気をどうしたらいいか分からず、オレンジジュースをちびちびと飲んでいると、コースターに置く瞬間を見計らって、コップごとおれの手を握ってくる大きな手があった。目の前に座っているクソDJの手だ。
驚いて逃げようとするおれの右手を逃さないように、指を絡ませてくる。優しく握ったり、揉んだり、手の大きさと力強さの違いに改めて男女の違いを実感する。少しだけ強い力で手を握られるのがむず痒くて、今度はおれが窓の方を見る番だった。
おれの手で遊び飽きたのか、パッと解放される。それはどれくらい長い時間だったのか分からないが、外の寒さとオレンジジュースで冷え切ったおれの手を温めるのに十分な長さだったことは確かだ。
また遊ばれないうちにと慌ててコップを掴み、オレンジジュースを飲み干す。カランと氷の揺れる音がやけに耳に残った。
「そろそろ出よっか」
「そ、そうだな」
口を拭いて、アウターを着て、荷物を準備して、とバタバタしている間にボックス席の出口は塞がれていた。さっきも触れたおれよりひと回りは大きな手が差し伸べられている。
「なんか欲しいのか?」
「おチビちゃんの右手」
「は?」
「手、繋ごうよ」
拒否権もないまま繋がれた右手を引っ張って連れてこられたのは会計をする場所だ。さっきオレンジジュースとコーヒーを届けてくれた店員が前の客の接客をしている。
「ごちそうさま」
「お会計こちらになります」
レジスターに表示された金額をクソDJが払い、店員がお釣りの硬貨を探す。その様子をぼーっと眺めていたが、自分の分は出さなきゃと思い、空いている左手でバッグを漁る。
「待って、オレンジジュース代出すから」
「いいよ、今日は俺の奢り」
「そんな訳には…」
「いいの、だって俺たち恋人同士でしょ」
わざと“恋人同士”という一言を強調するような物言いに、カーッと頬に熱が集まるのが分かった。クソDJは何が嬉しいのかニコニコと満面の笑みを浮かべている。
「バカ、こんな、聞こえるようなとこでっ」
「別に隠すようなことじゃないでしょ。ね、店員さん可愛いでしょ、俺のカノジョ♪」
「…そうですね」
俗に言うイケメンと呼ばれる男が二人笑顔を飛ばし合っている光景なのに、何故だか肝が冷える。クソDJを繋がれた手ごと店から引っ張り出して、やっと深いため息が出た。
「おまえ、何がしたいんだよ…」
「柄にもなく、売られたケンカを買っちゃった。ゴメンね」
「ケンカ?知り合いなのか?」
「ぜ〜んぜん、知らない人」
そのケンカとやらに勝ったのか、機嫌良く隣を歩くクソDJに疑問符が飛ぶが、どうせ聞いたところで教えてはくれないのだろう。クスクスと微笑ましいものを見るかのような街の人からの視線に、思考が現実に引き戻される。
「ていうか、手!離せよ!恥ずかしいだろっ」
「えー?」
男女差ありの到底覆せない力でギュッと握られた手は、離れる気配がない。離れようともがけばもがくほど、ブンブンと仲良く手を振って歩いているようで恥ずかしい。大人しく動きを止めると、満足したのかクソDJが微笑んだ。
「しばらくこのままで」
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスと一歩ずつ恋人としての階段を上っていくことになったのである。
◇◇◇
【はじめての生理】
よくある朝だった。だからそんなことになるなんて思ってもいなくて、いつも通りパトロールに出かけて、指令通りキースと一緒に与えられた場所の探索を行った。
いつもと違うことといえば、途中でキースに上着を借りるはめになったこと、そしてその場面をクソDJに見られたことだ。ディノと一緒に隣の地区をパトロールしていたはずのフェイスが、おれを見るなり早足で歩いてきて、腰に巻いていたキースの上着を勢いよく剥がした。
「ちょっ、待てそれ取ると…っ」
「キースの上着を脱ぐと、なにか不都合なことでもあるわけ?」
「いや、あの…」
「今日そんなに寒くないからおチビちゃんの上着だけあれば平気だよね?寒くて無理なら俺のを貸すからキースのは着ないで、分かった?」
ひとくちで捲し立てるようにそう言ったフェイスと困り果てたおれを見ながら、キースが苦笑いをひとつ溢した。一緒に吐き出された紫煙が寒空に広がっていく。
この際上着はもういいから、どうか気付いてくれるな。そんなおれの願いも虚しく、キースの上着をまじまじと見たフェイスが小さな違和感を見つけた。
「キースじゃない匂いもする…ってこれ、血?」
「大丈夫かジュニア、怪我したのか?」
ちょうど腰に当てていた辺りにベッタリと付いた血にしっかり気づいた二人が、口ぐちに心配の言葉をかけてくる。だけどおれは、別に怪我をしたわけではない。公衆の面前で血の出どころを剥かれて心配されるのは、正直恥ずかしくて仕方なかった。
「あぅ…そ、その、別に、身体はへ、へいき…だしっ」
「でも、ああほら見て?スカートにも、こんなにベッタリ、血、が……」
そこまで言ってはたと思い至ったのか、二の句を告げなくなったフェイスをキッと睨みつける。
「待てって、言ったのに…っ」
「……」
黙ったままキースの上着をおれに押し付けてきたクソDJは、即座に自分の上着を脱いでおれの腰に巻いた。さっきおれが結んだキースの上着より強く結ばれていて少しキツいけど、腹痛もあるからしっかり締められてるのはちょうど良かった。
「パトロールの時間、もう終わりだよね?」
「ああ、そうだな」
「俺とおチビちゃんはもう帰るから。あと、キースの上着は洗って返すね。じゃ、お先に」
「お、おいクソDJ!おい待てって!」
「…キースが馬に蹴られたらどうしよう」
「縁起でもないこと言うなよ…」
◇◇◇
おれの手をしっかり握ったクソDJに手を引かれて、タワーまでの道を歩く。二人から離れる時は足早だったが、見えなくなるとおれのペースに合わせてゆっくり歩いてくれた。
暮れかけていた日がどこかの海辺に隠れた頃、ようやく帰宅できた。おれの冷えた指先を健気に温めてくれていた手が離れたことだけが少し残念だった。
部屋にたどり着くと「シャワー浴びてきなよ」と浴室に入れられ、すっかり汚れを落として綺麗になって部屋に戻ると、フェイスの机には鎮痛剤やゼリーなど、生理のときに欲しいものが山ほど並べられていた。
「甘やかすんじゃねえよ…は、恥ずかしいだろ」
「甘やかして何が悪いの?彼女が生理で困ってるんだからさ、これくらいカッコつけさせてよ」
「べ、別に困ってねーし!今日はたまたま!血が、おおく、て…」
声を張り上げると、ドボッと大量に血が出たのが分かって思わずうずくまった。部屋に戻ってきて安心したからか、痛みもどんどん増している気がする。
「とりあえず横になって。鎮痛剤はこれでも大丈夫?飲んだらそのまま寝ちゃっていいから」
「で、でもお前のベッド、よごれる…」
「バスタオル敷いてるから大丈夫。はい、お水」
至れり尽せりな状況に困惑しているが、意地になって自分で何でもかんでもやる気力も体力も残っていない。薬を飲んでクソDJのベッドに横になると、暖かさと落ち着く匂いに、意識が微睡んでいく。
布団の上から優しく腹の上を撫でる手が、少しだけむずがゆくて、でもそれ以上に嬉しかった。そんなはずもないのに、分厚い布団越しにじんわり温かくなってきているような気さえして、痛みで一日中刻まれていた眉間の皺が少しずつ解れていくのを感じた。
「…寝る前にさ、ひとつだけ約束してくれる?」
「ん…」
「困ってる時はさ、他の誰でもなくて…俺を頼ってほしい。できる?」
「う、ん…」
「いいお返事。それじゃあ、ゆっくりおやすみ。おチビちゃん」
すっかり眠りこけてしまったおれには、そのあとクソDJがなんて言っていたのかは分からない。だけど、この空間が、安心して休める場所だってことはなんとなく分かった。
「いつかおチビちゃんが、同情でもなく俺のことを選んでくれて、本物の恋人同士になれたらさ、その時は……」
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスにたくさん甘やかされて、幸せな夢を見ているのだった。
◇◇◇
【はじめての名前呼び】
生理痛でフェイスのベッドに寝かせてもらってから、夜に一緒に眠ることが増えた。といっても、おれからねだることはない。特別寒い夜にクソDJに「おいで」と言われて、そのまま二人で抱き合って眠る。ただそれだけのことだ。
それでも、二人で眠る布団の暖かさや、クソDJの匂いが間近でする心地よさに気が付いてしまえば、次はいつ誘われるかと心待ちにしてしまうのは仕方のないことだった。
毎日何度も天気予報を確認して、気温の高い予報の時には「寒くなれ」なんて信じてもいない神頼みをする。今日はそんな都合の良い神頼みが伝わったのか、一日中晴れで高い気温を保つ予定が外れ、午後から積もらない程度の雪が降る予報に変わっていた。
「た、ただいま…」
そわそわとした気持ちを抑えきれないまま、一旦シャワーを浴びて自室に戻ると、まだ夕日が沈んだばかりだというのに電気を消して布団に潜り込んでいる姿が見えた。珍しい、と思い静かに部屋に入って荷物を置くと、暗闇が動いて小さな声が聞こえた。
「おチビ、ちゃん…」
「く、クソDJ…?」
「アハ、パトロール、お疲れさま…」
声から伝わる覇気のなさが気になって電気をつけると、真っ赤な顔でベッドサイドに身体を起こしているクソDJの姿が見えた。肩が大きく揺れるくらい荒い呼吸をしている。
「風邪か?もしかしてずっと寝てたのか?」
「朝は、ちょっと頭痛いかなって…くらいだったんだけど」
「ちょっとって…熱あるだろ、これ…」
慌ててもう一度ベッドに横にして、この間世話を焼いてもらった時の薬やゼリーの残りをかき集める。体温計は38.5℃を表示していて、代わってやれなくても辛いことが伺えた。
「ごめん、寝てれば治るから…」
「でも寝てても治ってないんだろ?医務室行ってく…」
「やだ」
引き止めてきた左手が、普段冷え性な男のものだとは思えないくらい熱くて困惑する。
「やだって…」
「そばにいてよ、おチビちゃん」
「なっ」
「お医者さんじゃなくて、おチビちゃんがいい」
そう言うと体力の限界を迎えたのか、静かに眠りについてしまった。熱を持った手はもちろん繋がれたままだ。抜け出ようかとも思ったが、眠っているとは思えないほどの力で握り締められていてうまくいかない。
諦めてそのままベッドサイドに寄りかかると、寒気の気配が足先から身体を襲い始めた。暖房が効いているとはいえ床に直で座るのは、今度はおれが風邪をひいてしまう番だ。
クソDJを起こさないようにそーっと布団の中に潜り込む。体温の上がったクソDJが寝ていたこともあっていつもより暖かいそこは、今日みたいに雪が降る日にはちょうど良いかもしれない。
パジャマ越しに伝わる熱に身体を預けて、おれも深い眠りの底に落ちていった。
◇◇◇
目が覚めたのは、まだ夜が明けきっていない頃だった。おれの手を握ったり揉んだりしている気配を感じてゆっくりと目を開けると、穏やかに微笑むクソDJの顔が真正面にあった。
「ごめん、起こしちゃった?」
「へーき…熱は?」
「この通り、下がったよ」
握った手をそのままつるりとした額に当てられる。眠る前のようにいやな熱さはない。ほぼ平熱だろう。起きたついでにトイレに行こうと、ベッドから降りようとすると、繋いだままの手をぐっと引っ張られる。
「ちょっと、トイレ…」
「やだ」
「は、はぁ?」
「離れたくない」
ぬくい布団の中で離れたいおれと離れたくないクソDJの攻防が始まった。身体ごとすっかりホールドされているおれに勝ち目などない。サボってばかりのくせにしっかりと筋肉のついた胸元や、ちょっとやそっとじゃ敵わない腕力の違いに、おれとこいつが違う生き物であることを改めて実感する。
離れたくない、なんてキザな台詞もきっとヒットナンバーみたいに口ずさみ慣れていて、いままで何人もの女の子に同じことを呟いてきたんだろう。
いまだけは、こいつの全部がおれのものだけど、またいつか…クソDJが飽きたり、“諸事情”とやらが解決すれば、ただの同僚に戻るんだろう。それが心の底から残念だった。
「トイレくらい、行かせろよ」
そうやって目を逸らすおれは、きっとどうしようもなく可愛げのない女に見えたことだろう。二人の間に静寂が流れて、そのままクソDJの力が緩んだときにベッドから離れる…つもりだった。
「やだ」
「なっ…」
「寒いし、一人で寝るのはいや。離したくない」
「おまえっワガママ言うな!」
「風邪ひいてる時くらい優しくしてよ」
「もう治ってるだろ!」
しょうもない言い合いを続けていると、ふいに抱きしめる力がくぐっと強くなる。離れ離れの足先だけがやけに冷たいな、なんてそんなことが脳裏を過ぎった。
「おチビちゃんが、名前呼んでくれたらトイレ行かせてあげる」
「は、はぁ…?」
「ほら、行きたいんでしょ?名前呼んでみてよ」
意地悪を言っているようで、そのマゼンタの瞳は静かに凪いでいる。目覚めたからついでに行きたかっただけで、実はそんなにトイレに行きたいわけではないんだけど。期待の籠った両目をどうしても無視できなくて、小さな一言だけを呟いた。
「ふぇ、いす……」
「よくできました」
力が緩んだ瞬間を見計らって、言葉通り脱兎のように布団を抜け出す。何故か抱きしめられていたわけでもない顔中が熱くて、鏡で確認すると真っ赤に染まっていた。クソDJに抱きしめられていたのが、真っ暗な布団の中で良かったと心底思った。
おれを彼女にした理由も、付き合い始めてから妙に優しい理由も、何も分からないけど。いつか離れるって事実だけが明確にそばにあるのに、こんなにも期待してしまっている自分がいる。
「どんな顔して戻ればいいんだよ……」
おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスと本当の恋人同士になれたらいいと思っている。
◇◇◇
【はじめての疑惑】
クソDJと、本当の恋人同士になりたい。
だけどいままでロクに付き合った経験もなければ、興味もなかったおれには、どうしたらクソDJが好きになってくれるのかなんて分からない。そもそもおれを偽物の恋人にした理由も分からないのだ。
あたたかい布団の中で抱きしめられながらアレコレ考えるが、恋愛上級者ともいえるクソDJ相手に太刀打ちできる案なんて思い浮かぶはずもない。
こうやって同じ布団で眠りについて、目が覚めた時にはキスを交わす。それって、いまのおれたちじゃそもそも出来ないことなんだろうか。
「……」
眠っているクソDJの嫌味みたいに整った顔に唇を寄せる。あともう少しで触れそう。穏やかな寝息が当たるくらい近づいて…止まった。
眠っている相手に勝手にキスをするのはなんだか卑怯な気がしたからだ。キスとか抱き合うとか、そもそも好き同士の本当の恋人がするものだ。正々堂々振り向いてもらって、クソDJと同じ気持ちでやらなきゃ意味がない。
布団の中にズボっと潜り込むと、ほどよいあたたかさに瞼が下りていく。明日も寒ければいいなと思った。
◇◇◇
「好きな人に、好きになってもらう方法?」
「こ、声がデケーよっ」
「うーん、それって…」
今回A班で集まったのはグレイの部屋だ。持ち運ばなくてもゲームがたくさん置いてある、いわゆる集まり慣れた部屋だ。ゴーグルも不在なので、小さい声ではあるがこの間の話の続きをする。
「というかガキンチョ、この間恋人ができたとか言ってなかったか?」
「そ、それはっ…あれは、ナシだ。忘れろ」
「はぁ?なんだよそれ…」
アキラはともかく、グレイとガストが意味深に微笑んでいるのが気になるが、こいつら以外に相談できる相手も思い浮かばない。ゴーグルに聞かれた日には弱みとして握られる可能性だってある。不在で心底良かったと思った。
「このメンバー、あんまりそういう話には詳しくないと思うんだけど…」
「ガストとかほら、モテるしなんかねーのかよ」
「おう、俺か…あー、相手の好きそうな服を着てみる、とかか?ジュニアたちの場合、趣味真反対になりそうだけど…」
「確かに。自分の好きな服を着てくれたら嬉しいかも…」
「服、か…」
「……めだ」
ガストたちの真っ当な意見に耳を傾けていると、それまで黙っていたアキラが口を開く。ビシッと効果音のつきそうなほど眼前に突き立てられた人差し指を避けると、自信満々の声が響いた。
「ぜんっぜんダメだ!そんなんじゃ!」
「はぁ…?」
「あ、アキラはどんなのがいいと思うんだ?」
「そりゃイロジカケしかねーだろ」
◇◇◇
放心したりドン引きしたり諌めたり…etc
三者三様の反応をアキラは不服そうにしていたが、その後ゲームが始まると興味も失ったのか、それ以上言及してくることはなかった。
イロジカケ…もとい、色仕掛け。自分の凹凸のない身体を見下ろす。身体にフィットするサイズの制服を着ているというのに、悲しいほどに色気がない。パトロールの際に兄ちゃんと間違えて「レオナルド・ライトの息子」に話しかけてくる市民までいるレベルだ。
服にだってあまり興味がない。それなりのものを着られさえすればそれでいいし、ショッピングやカフェに屯している女子と比べて圧倒的に欠けているもの。どう考えたって一番顕著なのが「色気」だ。
しかし、アドバイスを貰ったからには「興味ない」で終わらせるわけにもいかない。市民の安全にはもちろん目を光らせつつ、道ゆく少女たちのファッションも眺める。
「今日も平和そうだな〜」
「ヒーローが歩きタバコすんじゃねー!」
堂々と一服し始めたキースを喫煙所に押し込んで、少し離れたところで待つ。薄っすらと漂うタバコの匂いは、おれが未成年だからなのか頭をぼんやりとさせた。
紫煙を振り切るように目線をずらすと、見慣れた黒髪の男が雑踏の奥に見えた。オフのはずのクソDJだ。最近は外に繰り出すよりも部屋で音楽を聴いているほうが気に入っているようだったから、まさかこんな街中で会うとは思わずどきりと心臓が跳ねる。
「ふぇ、」
名前を全部呼ぶことはできなかった。人混みの向こうに、クソDJともう一人の人影が見えたからだ。一秒前までとは違う意味で、いやになるくらいの鼓動が聞こえる。
腕を組んで歩いている。知らない女と、アイツが。自分のものだと思えないくらい呼吸が乱れて、それ以外の音が聞こえなくなる。容姿もお似合いで、色気もおれより何万倍もある綺麗な人だ。長く伸ばした髪は手入れが行き届いていて、間違っても男と勘違いされることはないだろう。
キースに声をかけられるまで放心していたようで、遠くに見えていたクソDJと知らない女の人はどこかに消えていた。心がズキズキと傷むような感覚も一緒にどっかにいってくれれば良かったのに、と思った。
キースとのパトロールを終えて、帰路に着く。案の定部屋は真っ暗で、人の気配が感じられない冷たさを放っている。
どうしておれに声をかけたんだろう。誰でもいいのなら、どうしておれだったんだろう。「恋人になって」なんて言われなければ、この好意の芽を大事に育てることなんてしなかった。知らない誰かと抱き合って、キスをして、愛を囁くのも我慢できた。
だけど一度手に入ってしまったから、離れたくないと、お前にも好きになってほしいと浅ましく願う自分がいる。全部全部、クソDJのせいなのに。
「あほ、ばか……クソDJ、」
誰もいない部屋は、かじかんだ手を虐めているみたいだ。抜け出たままのベッドがひどく滑稽に映って、よろよろとシャワールームを目指す。
耳につく鼓動も、勝手に流れる涙も、いまはぬるいシャワーの音で誤魔化してしまうしかなかった。
◇◇◇
【二度目の恋人】
「諸事情あってさ、恋人が必要なんだよね」
おれたちの関係をはじめたのは、クソDJの一言だ。
だけど終わりの一言を待てるほど、おれには余裕も何もなくて。しばらく避けて、避けまくっておれが出した結論は、自分から別れを告げることだった。
好きになって欲しかったのは本当だ。本物の恋人同士になりたかったのも本当。だけどその見込みが限りなく少ないのに、これ以上この気持ちを大事に大事に抱えられるほどおれは出来た人間じゃない。
呼び出した屋上は真冬の夜らしく冷たい風が吹いていて、この恋を儚く散らすのにはちょうど良い場所だと思えた。
来ないかもと思っていたソイツはおれよりも先に着いていたようで、姿を見るなりゆっくりとこちらに歩き出した。買い物帰りなのか大きな紙袋を持っている。前に見た女の人との時間を邪魔していたら申し訳ないとも思ったが、終わりくらいちゃんとしたい。
「悪い、待たせた」
「俺もいま来たところだから気にしないで。おチビちゃんから話があるって聞いたら嬉しくて少し早く着いちゃって」
「ふふっ、なんだそれ…」
別に好きでもなんでもない相手にまで、気を遣わせないように優しい嘘を吐いてくれる。それを軽薄だと思うやつもいるだろうが、おれはそういうところもクソDJの美点だと思っている。
おれの好きになったところのひとつだ。
「パトロール、寒かったでしょ」
「まあぼちぼち」
「うそ、鼻の頭真っ赤になってるよ」
男らしい節くれだった指がおれの鼻にそっと触れる。見つめたら吸い込まれそうなマゼンタが少しずつ近づいてきて、キスでもしそうな距離に、クソDJが、いる。
唇の代わりに鼻先だけが掠って、端正な顔が離れていく。最後の最後にも、キスだけはしてくれない。おれとクソDJは、偽物の恋人だからだ。
「あのさ、それで…話なんだけど」
「うん」
冬の夜で良かった。泣きそうになって声が小さくなっても、この静けさならクソDJの耳までちゃんと届くだろうから。
本当は言いたかった。鼻が赤いのは、寒いからだけじゃなくて、ここにくる途中ずっとお前と別れるための言葉を用意してたからだって。
「おまえと恋人になってから、毎日悪くなかったよ」
「…嬉しいな」
「おまえは優しくて、たくさん甘やかしてくれて…頼ってほしいって言われたときは、おれのこと女の子扱いしてくれるんだって、それも嬉しかった」
「そんなの当たり前でしょ」
「どんどんおまえと離れたくなくなって、気持ちが膨らんで…自分がどんどんダメになっていくのが分かった」
「え…」
「もう誰かのことを憎らしく思いたくないし、お前のことをこれ以上好きにもなりたくない。だから…」
別れてほしい。
視界がぼやけてよく見えないけど、クソDJがおれのことをじっと見ていることは分かった。偽物の恋人なのに、少し優しくしてやっただけなのに、面倒なやつに声をかけてしまったと思うだろうか。
それでもいい。もう二度と、おれを自分の都合に巻き込まないでいてくれるならそれで。
「俺のこと、嫌いになった?」
クソDJが聞いてきたのは、その一言だった。泣いてしまったせいか、クソDJの声まで震えて聞こえる。冷たい風が頬を突き刺すように去っていった。
「もうわかんねー」
「そっか」
これ以上好きになりたくないと言ったり、分からないと言ったり。だけどどちらも本当のことだった。頭の中はぐちゃぐちゃで、もう自分の気持ちすらよく分からない。頭の中に浮かぶのは、クソDJと過ごした毎日のこと。本当の恋人みたいに優しくしてくれたひとりの男の顔だけだった。
突然なにかに遮られたみたいに風が止んで、身体がきつく抱きしめられる。クソDJに抱きしめられていると分かったのは少し経ってからのことだった。
「…おまえ、いまの話聞いてたか?はなせよ」
「俺前に言ったよね。困ってるときは一番に俺を頼ってほしいって」
「言ったけど、それがなんだよ…」
忘れるわけがない。とはいえ困っていると頼りに行く前にあれこれ世話を焼いてくれていたから、実際に相談したことはほとんどなかった気がするが。それも別れたらおしまいだろう。ただの同僚の悩みを解決する義理はないはずだ。
「俺にはさ、いまのおチビちゃんの話、助けてって言ってるように聞こえたんだけど」
「……え」
「やっと頼ってくれたね」
身体が浮くくらい強い力で抱きしめられて、すこし痛いくらいだ。だけど寒い日に布団の中でいつも大事にあたためてくれていた腕と同じ力加減で、同じ匂いがすることがどうしても嬉しかった。
助けてなんて言ってない。離れたいって言ったんだ。
そんな強がりを吹き飛ばすくらいわがままな抱擁に、膜を張っていた涙が粒となって溢れ出る。大きな手が頭を撫でてくれるのが心地よかった。
少し経って離れると、涙も落ち着いた。改めて言えるはずだ。
「やっぱりおまえとは別れたい。好きな気持ちを抱えたまま、偽物の恋人は続けられないから」
「……おチビちゃんが真面目で超頑固なの、忘れてた」
「うるせー」
「気持ちが分かった後でこんなことするの、ちょっとズルい気もするけど…」
アハ、と聞き慣れた声で笑みをひとつこぼしたクソDJは、持ってきていた紙袋から小さなギフト用のジュエリーボックスを取り出した。そっと開かれた中にはリングの付いたペンダントが大事そうに仕舞われている。
「おチビちゃん、おれと本当の恋人になってください」
「…え」
「もしかして、ダメ?さっきの言い方だと、本当の恋人同士になら、なってくれるかなと思ったんだけど」
「そうだけど、それが出来ないから、別れようって…」
「そもそも俺、一言もおチビちゃんのこと好きじゃないなんて言ってないよ」
え、と驚いてムカつくほど整った顔を見上げると、悪戯な言葉とは裏腹に穏やかな表情をしていた。愛おしいと心の底から伝えてくるようなその目を、コイツは一体いつからおれに向けていたんだろう。
「これ、つけてもいい?」
「うん、いいけど…」
ペンダントを器用におれの首元に飾ったクソDJは、やっぱり似合うだなんだと穏やかな声で褒めるから、聞いているこっちが恥ずかしくなってくる。
本当の恋人になるかどうか、迷うはずもない返事を保留にしているのがモヤモヤした。
だけどどうしても聞かなければならないことがあるのだ。
「じゃあ、あの女の人は誰なんだよ…」
いまおれの胸元に光っているペンダントと、あの日クソDJたちが消えていった方向にあるジュエリーショップは同じはずだ。
「もしかして、見てたの?」
それだけ呟いたクソDJは、甘えるようにおれの身体を抱きしめてのしかかってきた。
「ダサいな、俺…いや、女の子といたこともだけど、買うとこ見られてたとか…」
「ごまかすんじゃねーぞ」
「ごまかすも何も、名前覚えてないくらい前のカノジョ。多分俺がジュエリーショップ入るとこ見て、あわよくば何か買ってもらおうと思ってたんじゃないの」
確かにあのとき、抱きついていたのは女の人だけだった。向こうに歩いていく姿しか見ていないから、クソDJがどんな表情をしていたのかは見えなかったけど、よくよく思い返してみるとデートって雰囲気ではなかったのかもしれない。
「じゃあ待ち合わせしてたわけじゃ…」
「そんな訳ないでしょ。おチビちゃんのためのペンダント買いに行ったんだよ」
クソDJが、おれのことだけを思って選んでくれたプレゼント。
それだけで胸を覆っていたいやな感情が全部無くなってしまうくらいに嬉しかった。
「…そっか」
クソDJが選んでくれたそれをそっと手で触る。可愛らしいけれどシンプルなデザインは、おれが付けていても違和感がないだろう。色仕掛けだなんだと考えていたあの日の自分がバカらしく思える。クソDJはもうずっとおれのことを見ててくれていたというのに。
「なあ、さっきの返事してもいい?」
「うん、聞かせてほしいな」
「その前に、もういっこ聞きたいんだ」
なんで、偽物の恋人が必要だったんだ?
そう聞くと、クソDJは目を丸くさせて、それから気まずそうに笑った。いまの破顔は、周りに人がいたらさぞ女の子たちをメロメロにしたことだろう。寒さで鼻が真っ赤になっていなければの話だが。
「偽物の恋人が必要だった訳じゃなくて、おチビちゃんにお試しでもいいから付き合ってほしかったんだよね」
「おれに…お試しで?」
クソDJいわく、おれが恋をしている顔をしていたらしい。誰のことを考えているのか分からなくてモヤモヤしていたから、自分を意識してもらおうと嘘をついて偽物の恋人になったのだとか。
「そんなのアリかよ…」
「だってさ、あの時のおチビちゃん、甘いものでも食べてるんじゃないかってくらい幸せそうな顔してて…」
誰にも渡したくなかったんだ。
恋をしている顔だった。いつから、なんて野暮だ。こいつはずっと、おれに恋をしていたんだから。いままで一緒に過ごした時間を思い出すと、頬に熱が集まったのが分かった。
「冷えちゃったね、帰ろっか」
お互いに冷えきった手を繋いで、部屋までの道を歩く。こんなふわふわとした気持ちでこいつとここを歩くことになるなんて思ってもみなくて、我慢しようとすればするほど口角が上がってしまうのが分かった。
寝る支度を済ませてちらりとクソDJのベッドを見ると、まるで当然とでもいうように布団の半分のスペースが空けられていた。おそるおそる自分から入ると、すでに人肌でじんわりとあたたかい。
いつものように回された腕を邪魔しないように、今日はおれも抱きしめ返す。
「あったかいね」
「そうだな」
「外してきちゃったの?」
さらりと首筋を撫でられて、思わず身震いする。一緒に寝ることはあっても、抱きしめたり手を握ったりする以外の接触は思えば初めてだった。
「無くしたらかなしいだろ…」
「アハ、そうだね」
「…どうして急に、ペンダントなんだよ」
屋上にいる時から思っていたことがポロリと口から漏れた。「なぜ」や「なんで」が浮かびすぎて出す機会を無くしていたが、聞かないままなのはなんとなくモヤモヤする。
「急に…やっぱり分かんないか」
「やっぱり、ってなんだよ」
「俺とおチビちゃんが付き合い始めて…といっても偽物の恋人になって、だけど…あれから一ヶ月めなんだよ、今日」
「もうそんなに経つのか…」
「だからケジメを付けたかったというか何というか…まあ俺にだってさ、カッコつけたいことはあるんだよ」
好きな子の前ならね。
そんな言葉にもどうしようもなくときめいて、恋をしてしまうから。早鐘のようになっている鼓動だけは回された手のひらごしに伝わってしまわないように、ぎゅっと両手を握る。
あたたかくなった布団の中で端正な顔を見上げると、愛おしさを煮詰めたようなマゼンタの瞳が今度こそくっつくほど近くにいたから、目を瞑ってはじめてのキスを受け入れた。
恋とはもっと、甘やかなものだと思っていた。
先人たちの歌にはそう綴られていたし、身近なものたちは恋しい相手の話をするたびに甘いものでも頬張っているような蕩けた顔をする。だから、自分もそうなるものだと思っていた。
恋とは一律に甘くて、美しくて、煌びやかなもの。そんな幻想を打ち砕いたのは、おれが恋をした相手だった。
「諸事情あってさ、恋人が必要なんだよね」
だから付き合ってよ。
いとも軽々しく伝えられた言葉に、心が冷えていく。
これは取引でもなんでもなく、おれの答えが分かった上で与えられたひとときの夢。一方的で強引なこの夢から覚めた後の冷たい世界は想像に容易いけれど、それでもおれは首を縦に振るしかないのだ。
「分かった。お前と…付き合う」
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアと目の前のこの男、フェイス・ビームスは恋人同士となったのだった。
◇◇◇
【はじめての恋人】
「恋人同士ってさ、何すんの」
「はぁ?」
恒例になりつつあるA班のゲーム集会中にぽろりと漏れたおれの言葉に真っ先に反応したのは、他でもないアキラだった。
あとの二人…グレイとガストは顔を赤くしたり、ポリポリと頭を掻いたり…それぞれらしい反応で固まっている。
「それは恋人同士なんだし?手繋いだりとか、キスしたりとか…」
「ガキの恋愛ごっこかよ。そりゃセッ…」
「アキラ、ストップ。ジュニアは女の子だぞ。あー、一緒に映画観るとか、カフェに行くとかいいんじゃねえか?」
好き勝手に騒ぎ立てる言葉から、心当たりのあるものだけをチョイスする。
手を繋ぐ、キスをする、映画を観る、カフェに行く、それから……
ボンっという効果音でも付きそうなほど真っ赤になった顔を扇いでいると、ニヤついた顔のアキラが身を乗り出す。
「はっはーん、さてはお前、コイビトが出来たな」
「う、うるせえな、そうじゃねぇと聞かねーだろ」
「誰だよ、教えろよ〜」
「うるせー!しらねー!」
アキラと二人で取っ組み合いをしているとドアが開いて、間抜けな顔をしたフェイス…もといクソDJが入ってきた。誰もいないからとウエストの共有スペースでゲーム会を開いていたのだが、予定が早く終わったのだろうか。どことなく機嫌の悪いフェイスは、こちらをチラッと見ただけで一言も発することなくへ自室へ戻っていった。
「も、もしかしてフェイスくん…怒ってた?」
「勝手にココ使ったからか?」
「いや、いちおー使う前にみんなに一声かけておいたからそれはないんじゃね」
「てかおい、喋ってねーで降りろチビっこ」
「うるせー、誰がチビだ!」
鳩尾に手を置いて、乗り上げていたアキラから降りる。ぐっと力が入った瞬間「ぐえっ」と聞こえてきて何度も咳き込む姿が見えたが、こちらは髪を引っ張られたり馬鹿力で押さられたりしているのだ。お互い様というやつだろう。
理由は分からないが、クソDJが機嫌最悪マックスで帰ってきたので、今日のゲーム会はお開きの流れになった。おれとしても、冷やかされる一歩手前の空気感に耐えかねていたところだったのでありがたい。
「あー、さっきの話だけどさ」
最後に余ったお菓子とゲーム機を持ったガストが小さい声で耳打ちをする。
「フェイスに聞いてみるのがいいと思うぜ」
「フェイスに…」
一体何の話だろう。首を傾げながら見送ると、背後に気配があることに気がついた。
斜め上を見上げると、やはり機嫌の悪いフェイスが、今しがた三人の出て行った扉を冷ややかな目で見ている。
「仲良いんだね、A班って」
「仲良いって…B班もたまに集まってんじゃねーのかよ」
「俺らはお茶するとか談笑するとかその程度。ボディタッチしたり顔近づけて内緒話するほど仲良くはないよ」
「はぁ?何だよそれ…」
わざわざ棘のある言い方をしてくるクソDJに、瞬間的に怒りが湧く。
「何があったか知らねーけどよ、関係ないおれたちにまでそーいう態度取って…」
「…なくない」
「え?」
ドン、と壁に押さえつけられたのはその瞬間のことだった。呼吸のひとつ、鼓動のひとつですら手にとるような位置にいるのは初めてのことだ。美術品のように整った顔が近寄ってくる。おれの顔を目掛けてフッと息を吐いてきたので、息が苦しくなってそのままゲホゲホと咳き込んだ。
「関係なくないよ」
「は……」
聞きたかった言葉たちは、少しだけかさついた唇に飲み込まれていく。唇が触れ合うだけでは終わらない深いキスに、脳内に浮かんでいたバラバラの単語も真っ白く塗り潰されて、あとには荒い息を吐くおれたちだけが残されてしまった。
なんで、どうして、いまのは何?
やっと回り始めた脳内に浮かぶのはそんな要領を得ない質問ばかりで、浮かんでいた涙が一粒だけぽろりと落ちる。
「俺が機嫌悪い理由が知りたかったんでしょ。おチビちゃんとアイツら…A班の人たち、関係ないどころか俺が機嫌悪い原因そのものだよ」
「なんで…だってお前、帰ってきたばっかりで…」
「そう、帰ってきたばっかり。それで自分の彼女が他の男とボディタッチして、挙句キスされそうなくらいの距離で内緒話してるの見た時の気分、おチビちゃんには分からないか」
「そんな、の…」
コイツは事情があって仕方なくおれを恋人にしただけのどうしようもない奴だ。なのに何でここんなに怒ってるんだろう。分かるわけないだろ、と直接言えない分、心の中で悪態を吐く。
「俺の彼女になったからには、もう二度と他の男とあんなことしちゃダメ。分かった?」
小さく頷くと、大きな手が「いいこ」とおれの頭を撫でる。
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスから、理解不能な強烈な束縛を受けることになったのだった。
◇◇◇
【はじめての手を繋ぐ】
クソ寒い日のパトロール休憩に入ったのは、おれでも入りやすいような若者向けのカフェだった。選んだのはもちろんクソDJで、ボックス席の向かいに腰掛けて機嫌良さそうな笑みを浮かべている。
「ご注文お伺いします」
「コーヒーとオレンジジュース一つずつ」
「少々お待ちください」
店員が厨房に戻っていくのを見計らってプッと噴き出す音が聞こえてくる。小刻みに肩を揺らしているのは目の前に座るソイツしかいない。
「…なんだよ」
「カフェに来てオレンジジュースって…ふふっ」
「飲めないもの残すよりいいだろ」
「まぁそれもそうだけど…アハっ、やっぱりおチビちゃんだね」
「ふぁーっく!だれがガキだコラ!」
店内だから小さな声で。お互いに届く程度の小競り合いを続けていると、オレンジジュースとコーヒーを持った店員が戻ってきた。クソDJの前には湯気立つコーヒーを置いて、おれにはオレンジジュースを手渡してくる。溢さないようにと受け取ると、指先がほんの少しだけ触れたのが分かった。その瞬間、いかにも女にモテそうな店員がこちらにニッコリと微笑みかける。
訳も分からず首を傾げると、先程のクソDJと同じような噴き出す寸前のような笑みを浮かべて「ごゆっくり」と去っていった。まあいいか、とストロー越しのオレンジジュースに口をつけると、じっとりと張りつくような目線を送ってきているクソDJと目が合った。
「な、なんだよ…」
「別に…」
さっきまで機嫌良く笑っていたはずなのに、変なやつだ。ふいっと窓の方を向いてしまって、もはや目も合わなくなってしまった。
気まずい空気をどうしたらいいか分からず、オレンジジュースをちびちびと飲んでいると、コースターに置く瞬間を見計らって、コップごとおれの手を握ってくる大きな手があった。目の前に座っているクソDJの手だ。
驚いて逃げようとするおれの右手を逃さないように、指を絡ませてくる。優しく握ったり、揉んだり、手の大きさと力強さの違いに改めて男女の違いを実感する。少しだけ強い力で手を握られるのがむず痒くて、今度はおれが窓の方を見る番だった。
おれの手で遊び飽きたのか、パッと解放される。それはどれくらい長い時間だったのか分からないが、外の寒さとオレンジジュースで冷え切ったおれの手を温めるのに十分な長さだったことは確かだ。
また遊ばれないうちにと慌ててコップを掴み、オレンジジュースを飲み干す。カランと氷の揺れる音がやけに耳に残った。
「そろそろ出よっか」
「そ、そうだな」
口を拭いて、アウターを着て、荷物を準備して、とバタバタしている間にボックス席の出口は塞がれていた。さっきも触れたおれよりひと回りは大きな手が差し伸べられている。
「なんか欲しいのか?」
「おチビちゃんの右手」
「は?」
「手、繋ごうよ」
拒否権もないまま繋がれた右手を引っ張って連れてこられたのは会計をする場所だ。さっきオレンジジュースとコーヒーを届けてくれた店員が前の客の接客をしている。
「ごちそうさま」
「お会計こちらになります」
レジスターに表示された金額をクソDJが払い、店員がお釣りの硬貨を探す。その様子をぼーっと眺めていたが、自分の分は出さなきゃと思い、空いている左手でバッグを漁る。
「待って、オレンジジュース代出すから」
「いいよ、今日は俺の奢り」
「そんな訳には…」
「いいの、だって俺たち恋人同士でしょ」
わざと“恋人同士”という一言を強調するような物言いに、カーッと頬に熱が集まるのが分かった。クソDJは何が嬉しいのかニコニコと満面の笑みを浮かべている。
「バカ、こんな、聞こえるようなとこでっ」
「別に隠すようなことじゃないでしょ。ね、店員さん可愛いでしょ、俺のカノジョ♪」
「…そうですね」
俗に言うイケメンと呼ばれる男が二人笑顔を飛ばし合っている光景なのに、何故だか肝が冷える。クソDJを繋がれた手ごと店から引っ張り出して、やっと深いため息が出た。
「おまえ、何がしたいんだよ…」
「柄にもなく、売られたケンカを買っちゃった。ゴメンね」
「ケンカ?知り合いなのか?」
「ぜ〜んぜん、知らない人」
そのケンカとやらに勝ったのか、機嫌良く隣を歩くクソDJに疑問符が飛ぶが、どうせ聞いたところで教えてはくれないのだろう。クスクスと微笑ましいものを見るかのような街の人からの視線に、思考が現実に引き戻される。
「ていうか、手!離せよ!恥ずかしいだろっ」
「えー?」
男女差ありの到底覆せない力でギュッと握られた手は、離れる気配がない。離れようともがけばもがくほど、ブンブンと仲良く手を振って歩いているようで恥ずかしい。大人しく動きを止めると、満足したのかクソDJが微笑んだ。
「しばらくこのままで」
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスと一歩ずつ恋人としての階段を上っていくことになったのである。
◇◇◇
【はじめての生理】
よくある朝だった。だからそんなことになるなんて思ってもいなくて、いつも通りパトロールに出かけて、指令通りキースと一緒に与えられた場所の探索を行った。
いつもと違うことといえば、途中でキースに上着を借りるはめになったこと、そしてその場面をクソDJに見られたことだ。ディノと一緒に隣の地区をパトロールしていたはずのフェイスが、おれを見るなり早足で歩いてきて、腰に巻いていたキースの上着を勢いよく剥がした。
「ちょっ、待てそれ取ると…っ」
「キースの上着を脱ぐと、なにか不都合なことでもあるわけ?」
「いや、あの…」
「今日そんなに寒くないからおチビちゃんの上着だけあれば平気だよね?寒くて無理なら俺のを貸すからキースのは着ないで、分かった?」
ひとくちで捲し立てるようにそう言ったフェイスと困り果てたおれを見ながら、キースが苦笑いをひとつ溢した。一緒に吐き出された紫煙が寒空に広がっていく。
この際上着はもういいから、どうか気付いてくれるな。そんなおれの願いも虚しく、キースの上着をまじまじと見たフェイスが小さな違和感を見つけた。
「キースじゃない匂いもする…ってこれ、血?」
「大丈夫かジュニア、怪我したのか?」
ちょうど腰に当てていた辺りにベッタリと付いた血にしっかり気づいた二人が、口ぐちに心配の言葉をかけてくる。だけどおれは、別に怪我をしたわけではない。公衆の面前で血の出どころを剥かれて心配されるのは、正直恥ずかしくて仕方なかった。
「あぅ…そ、その、別に、身体はへ、へいき…だしっ」
「でも、ああほら見て?スカートにも、こんなにベッタリ、血、が……」
そこまで言ってはたと思い至ったのか、二の句を告げなくなったフェイスをキッと睨みつける。
「待てって、言ったのに…っ」
「……」
黙ったままキースの上着をおれに押し付けてきたクソDJは、即座に自分の上着を脱いでおれの腰に巻いた。さっきおれが結んだキースの上着より強く結ばれていて少しキツいけど、腹痛もあるからしっかり締められてるのはちょうど良かった。
「パトロールの時間、もう終わりだよね?」
「ああ、そうだな」
「俺とおチビちゃんはもう帰るから。あと、キースの上着は洗って返すね。じゃ、お先に」
「お、おいクソDJ!おい待てって!」
「…キースが馬に蹴られたらどうしよう」
「縁起でもないこと言うなよ…」
◇◇◇
おれの手をしっかり握ったクソDJに手を引かれて、タワーまでの道を歩く。二人から離れる時は足早だったが、見えなくなるとおれのペースに合わせてゆっくり歩いてくれた。
暮れかけていた日がどこかの海辺に隠れた頃、ようやく帰宅できた。おれの冷えた指先を健気に温めてくれていた手が離れたことだけが少し残念だった。
部屋にたどり着くと「シャワー浴びてきなよ」と浴室に入れられ、すっかり汚れを落として綺麗になって部屋に戻ると、フェイスの机には鎮痛剤やゼリーなど、生理のときに欲しいものが山ほど並べられていた。
「甘やかすんじゃねえよ…は、恥ずかしいだろ」
「甘やかして何が悪いの?彼女が生理で困ってるんだからさ、これくらいカッコつけさせてよ」
「べ、別に困ってねーし!今日はたまたま!血が、おおく、て…」
声を張り上げると、ドボッと大量に血が出たのが分かって思わずうずくまった。部屋に戻ってきて安心したからか、痛みもどんどん増している気がする。
「とりあえず横になって。鎮痛剤はこれでも大丈夫?飲んだらそのまま寝ちゃっていいから」
「で、でもお前のベッド、よごれる…」
「バスタオル敷いてるから大丈夫。はい、お水」
至れり尽せりな状況に困惑しているが、意地になって自分で何でもかんでもやる気力も体力も残っていない。薬を飲んでクソDJのベッドに横になると、暖かさと落ち着く匂いに、意識が微睡んでいく。
布団の上から優しく腹の上を撫でる手が、少しだけむずがゆくて、でもそれ以上に嬉しかった。そんなはずもないのに、分厚い布団越しにじんわり温かくなってきているような気さえして、痛みで一日中刻まれていた眉間の皺が少しずつ解れていくのを感じた。
「…寝る前にさ、ひとつだけ約束してくれる?」
「ん…」
「困ってる時はさ、他の誰でもなくて…俺を頼ってほしい。できる?」
「う、ん…」
「いいお返事。それじゃあ、ゆっくりおやすみ。おチビちゃん」
すっかり眠りこけてしまったおれには、そのあとクソDJがなんて言っていたのかは分からない。だけど、この空間が、安心して休める場所だってことはなんとなく分かった。
「いつかおチビちゃんが、同情でもなく俺のことを選んでくれて、本物の恋人同士になれたらさ、その時は……」
こうして、おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスにたくさん甘やかされて、幸せな夢を見ているのだった。
◇◇◇
【はじめての名前呼び】
生理痛でフェイスのベッドに寝かせてもらってから、夜に一緒に眠ることが増えた。といっても、おれからねだることはない。特別寒い夜にクソDJに「おいで」と言われて、そのまま二人で抱き合って眠る。ただそれだけのことだ。
それでも、二人で眠る布団の暖かさや、クソDJの匂いが間近でする心地よさに気が付いてしまえば、次はいつ誘われるかと心待ちにしてしまうのは仕方のないことだった。
毎日何度も天気予報を確認して、気温の高い予報の時には「寒くなれ」なんて信じてもいない神頼みをする。今日はそんな都合の良い神頼みが伝わったのか、一日中晴れで高い気温を保つ予定が外れ、午後から積もらない程度の雪が降る予報に変わっていた。
「た、ただいま…」
そわそわとした気持ちを抑えきれないまま、一旦シャワーを浴びて自室に戻ると、まだ夕日が沈んだばかりだというのに電気を消して布団に潜り込んでいる姿が見えた。珍しい、と思い静かに部屋に入って荷物を置くと、暗闇が動いて小さな声が聞こえた。
「おチビ、ちゃん…」
「く、クソDJ…?」
「アハ、パトロール、お疲れさま…」
声から伝わる覇気のなさが気になって電気をつけると、真っ赤な顔でベッドサイドに身体を起こしているクソDJの姿が見えた。肩が大きく揺れるくらい荒い呼吸をしている。
「風邪か?もしかしてずっと寝てたのか?」
「朝は、ちょっと頭痛いかなって…くらいだったんだけど」
「ちょっとって…熱あるだろ、これ…」
慌ててもう一度ベッドに横にして、この間世話を焼いてもらった時の薬やゼリーの残りをかき集める。体温計は38.5℃を表示していて、代わってやれなくても辛いことが伺えた。
「ごめん、寝てれば治るから…」
「でも寝てても治ってないんだろ?医務室行ってく…」
「やだ」
引き止めてきた左手が、普段冷え性な男のものだとは思えないくらい熱くて困惑する。
「やだって…」
「そばにいてよ、おチビちゃん」
「なっ」
「お医者さんじゃなくて、おチビちゃんがいい」
そう言うと体力の限界を迎えたのか、静かに眠りについてしまった。熱を持った手はもちろん繋がれたままだ。抜け出ようかとも思ったが、眠っているとは思えないほどの力で握り締められていてうまくいかない。
諦めてそのままベッドサイドに寄りかかると、寒気の気配が足先から身体を襲い始めた。暖房が効いているとはいえ床に直で座るのは、今度はおれが風邪をひいてしまう番だ。
クソDJを起こさないようにそーっと布団の中に潜り込む。体温の上がったクソDJが寝ていたこともあっていつもより暖かいそこは、今日みたいに雪が降る日にはちょうど良いかもしれない。
パジャマ越しに伝わる熱に身体を預けて、おれも深い眠りの底に落ちていった。
◇◇◇
目が覚めたのは、まだ夜が明けきっていない頃だった。おれの手を握ったり揉んだりしている気配を感じてゆっくりと目を開けると、穏やかに微笑むクソDJの顔が真正面にあった。
「ごめん、起こしちゃった?」
「へーき…熱は?」
「この通り、下がったよ」
握った手をそのままつるりとした額に当てられる。眠る前のようにいやな熱さはない。ほぼ平熱だろう。起きたついでにトイレに行こうと、ベッドから降りようとすると、繋いだままの手をぐっと引っ張られる。
「ちょっと、トイレ…」
「やだ」
「は、はぁ?」
「離れたくない」
ぬくい布団の中で離れたいおれと離れたくないクソDJの攻防が始まった。身体ごとすっかりホールドされているおれに勝ち目などない。サボってばかりのくせにしっかりと筋肉のついた胸元や、ちょっとやそっとじゃ敵わない腕力の違いに、おれとこいつが違う生き物であることを改めて実感する。
離れたくない、なんてキザな台詞もきっとヒットナンバーみたいに口ずさみ慣れていて、いままで何人もの女の子に同じことを呟いてきたんだろう。
いまだけは、こいつの全部がおれのものだけど、またいつか…クソDJが飽きたり、“諸事情”とやらが解決すれば、ただの同僚に戻るんだろう。それが心の底から残念だった。
「トイレくらい、行かせろよ」
そうやって目を逸らすおれは、きっとどうしようもなく可愛げのない女に見えたことだろう。二人の間に静寂が流れて、そのままクソDJの力が緩んだときにベッドから離れる…つもりだった。
「やだ」
「なっ…」
「寒いし、一人で寝るのはいや。離したくない」
「おまえっワガママ言うな!」
「風邪ひいてる時くらい優しくしてよ」
「もう治ってるだろ!」
しょうもない言い合いを続けていると、ふいに抱きしめる力がくぐっと強くなる。離れ離れの足先だけがやけに冷たいな、なんてそんなことが脳裏を過ぎった。
「おチビちゃんが、名前呼んでくれたらトイレ行かせてあげる」
「は、はぁ…?」
「ほら、行きたいんでしょ?名前呼んでみてよ」
意地悪を言っているようで、そのマゼンタの瞳は静かに凪いでいる。目覚めたからついでに行きたかっただけで、実はそんなにトイレに行きたいわけではないんだけど。期待の籠った両目をどうしても無視できなくて、小さな一言だけを呟いた。
「ふぇ、いす……」
「よくできました」
力が緩んだ瞬間を見計らって、言葉通り脱兎のように布団を抜け出す。何故か抱きしめられていたわけでもない顔中が熱くて、鏡で確認すると真っ赤に染まっていた。クソDJに抱きしめられていたのが、真っ暗な布団の中で良かったと心底思った。
おれを彼女にした理由も、付き合い始めてから妙に優しい理由も、何も分からないけど。いつか離れるって事実だけが明確にそばにあるのに、こんなにも期待してしまっている自分がいる。
「どんな顔して戻ればいいんだよ……」
おれレオナルド・ライト・ジュニアは、恋人契約を結んだフェイス・ビームスと本当の恋人同士になれたらいいと思っている。
◇◇◇
【はじめての疑惑】
クソDJと、本当の恋人同士になりたい。
だけどいままでロクに付き合った経験もなければ、興味もなかったおれには、どうしたらクソDJが好きになってくれるのかなんて分からない。そもそもおれを偽物の恋人にした理由も分からないのだ。
あたたかい布団の中で抱きしめられながらアレコレ考えるが、恋愛上級者ともいえるクソDJ相手に太刀打ちできる案なんて思い浮かぶはずもない。
こうやって同じ布団で眠りについて、目が覚めた時にはキスを交わす。それって、いまのおれたちじゃそもそも出来ないことなんだろうか。
「……」
眠っているクソDJの嫌味みたいに整った顔に唇を寄せる。あともう少しで触れそう。穏やかな寝息が当たるくらい近づいて…止まった。
眠っている相手に勝手にキスをするのはなんだか卑怯な気がしたからだ。キスとか抱き合うとか、そもそも好き同士の本当の恋人がするものだ。正々堂々振り向いてもらって、クソDJと同じ気持ちでやらなきゃ意味がない。
布団の中にズボっと潜り込むと、ほどよいあたたかさに瞼が下りていく。明日も寒ければいいなと思った。
◇◇◇
「好きな人に、好きになってもらう方法?」
「こ、声がデケーよっ」
「うーん、それって…」
今回A班で集まったのはグレイの部屋だ。持ち運ばなくてもゲームがたくさん置いてある、いわゆる集まり慣れた部屋だ。ゴーグルも不在なので、小さい声ではあるがこの間の話の続きをする。
「というかガキンチョ、この間恋人ができたとか言ってなかったか?」
「そ、それはっ…あれは、ナシだ。忘れろ」
「はぁ?なんだよそれ…」
アキラはともかく、グレイとガストが意味深に微笑んでいるのが気になるが、こいつら以外に相談できる相手も思い浮かばない。ゴーグルに聞かれた日には弱みとして握られる可能性だってある。不在で心底良かったと思った。
「このメンバー、あんまりそういう話には詳しくないと思うんだけど…」
「ガストとかほら、モテるしなんかねーのかよ」
「おう、俺か…あー、相手の好きそうな服を着てみる、とかか?ジュニアたちの場合、趣味真反対になりそうだけど…」
「確かに。自分の好きな服を着てくれたら嬉しいかも…」
「服、か…」
「……めだ」
ガストたちの真っ当な意見に耳を傾けていると、それまで黙っていたアキラが口を開く。ビシッと効果音のつきそうなほど眼前に突き立てられた人差し指を避けると、自信満々の声が響いた。
「ぜんっぜんダメだ!そんなんじゃ!」
「はぁ…?」
「あ、アキラはどんなのがいいと思うんだ?」
「そりゃイロジカケしかねーだろ」
◇◇◇
放心したりドン引きしたり諌めたり…etc
三者三様の反応をアキラは不服そうにしていたが、その後ゲームが始まると興味も失ったのか、それ以上言及してくることはなかった。
イロジカケ…もとい、色仕掛け。自分の凹凸のない身体を見下ろす。身体にフィットするサイズの制服を着ているというのに、悲しいほどに色気がない。パトロールの際に兄ちゃんと間違えて「レオナルド・ライトの息子」に話しかけてくる市民までいるレベルだ。
服にだってあまり興味がない。それなりのものを着られさえすればそれでいいし、ショッピングやカフェに屯している女子と比べて圧倒的に欠けているもの。どう考えたって一番顕著なのが「色気」だ。
しかし、アドバイスを貰ったからには「興味ない」で終わらせるわけにもいかない。市民の安全にはもちろん目を光らせつつ、道ゆく少女たちのファッションも眺める。
「今日も平和そうだな〜」
「ヒーローが歩きタバコすんじゃねー!」
堂々と一服し始めたキースを喫煙所に押し込んで、少し離れたところで待つ。薄っすらと漂うタバコの匂いは、おれが未成年だからなのか頭をぼんやりとさせた。
紫煙を振り切るように目線をずらすと、見慣れた黒髪の男が雑踏の奥に見えた。オフのはずのクソDJだ。最近は外に繰り出すよりも部屋で音楽を聴いているほうが気に入っているようだったから、まさかこんな街中で会うとは思わずどきりと心臓が跳ねる。
「ふぇ、」
名前を全部呼ぶことはできなかった。人混みの向こうに、クソDJともう一人の人影が見えたからだ。一秒前までとは違う意味で、いやになるくらいの鼓動が聞こえる。
腕を組んで歩いている。知らない女と、アイツが。自分のものだと思えないくらい呼吸が乱れて、それ以外の音が聞こえなくなる。容姿もお似合いで、色気もおれより何万倍もある綺麗な人だ。長く伸ばした髪は手入れが行き届いていて、間違っても男と勘違いされることはないだろう。
キースに声をかけられるまで放心していたようで、遠くに見えていたクソDJと知らない女の人はどこかに消えていた。心がズキズキと傷むような感覚も一緒にどっかにいってくれれば良かったのに、と思った。
キースとのパトロールを終えて、帰路に着く。案の定部屋は真っ暗で、人の気配が感じられない冷たさを放っている。
どうしておれに声をかけたんだろう。誰でもいいのなら、どうしておれだったんだろう。「恋人になって」なんて言われなければ、この好意の芽を大事に育てることなんてしなかった。知らない誰かと抱き合って、キスをして、愛を囁くのも我慢できた。
だけど一度手に入ってしまったから、離れたくないと、お前にも好きになってほしいと浅ましく願う自分がいる。全部全部、クソDJのせいなのに。
「あほ、ばか……クソDJ、」
誰もいない部屋は、かじかんだ手を虐めているみたいだ。抜け出たままのベッドがひどく滑稽に映って、よろよろとシャワールームを目指す。
耳につく鼓動も、勝手に流れる涙も、いまはぬるいシャワーの音で誤魔化してしまうしかなかった。
◇◇◇
【二度目の恋人】
「諸事情あってさ、恋人が必要なんだよね」
おれたちの関係をはじめたのは、クソDJの一言だ。
だけど終わりの一言を待てるほど、おれには余裕も何もなくて。しばらく避けて、避けまくっておれが出した結論は、自分から別れを告げることだった。
好きになって欲しかったのは本当だ。本物の恋人同士になりたかったのも本当。だけどその見込みが限りなく少ないのに、これ以上この気持ちを大事に大事に抱えられるほどおれは出来た人間じゃない。
呼び出した屋上は真冬の夜らしく冷たい風が吹いていて、この恋を儚く散らすのにはちょうど良い場所だと思えた。
来ないかもと思っていたソイツはおれよりも先に着いていたようで、姿を見るなりゆっくりとこちらに歩き出した。買い物帰りなのか大きな紙袋を持っている。前に見た女の人との時間を邪魔していたら申し訳ないとも思ったが、終わりくらいちゃんとしたい。
「悪い、待たせた」
「俺もいま来たところだから気にしないで。おチビちゃんから話があるって聞いたら嬉しくて少し早く着いちゃって」
「ふふっ、なんだそれ…」
別に好きでもなんでもない相手にまで、気を遣わせないように優しい嘘を吐いてくれる。それを軽薄だと思うやつもいるだろうが、おれはそういうところもクソDJの美点だと思っている。
おれの好きになったところのひとつだ。
「パトロール、寒かったでしょ」
「まあぼちぼち」
「うそ、鼻の頭真っ赤になってるよ」
男らしい節くれだった指がおれの鼻にそっと触れる。見つめたら吸い込まれそうなマゼンタが少しずつ近づいてきて、キスでもしそうな距離に、クソDJが、いる。
唇の代わりに鼻先だけが掠って、端正な顔が離れていく。最後の最後にも、キスだけはしてくれない。おれとクソDJは、偽物の恋人だからだ。
「あのさ、それで…話なんだけど」
「うん」
冬の夜で良かった。泣きそうになって声が小さくなっても、この静けさならクソDJの耳までちゃんと届くだろうから。
本当は言いたかった。鼻が赤いのは、寒いからだけじゃなくて、ここにくる途中ずっとお前と別れるための言葉を用意してたからだって。
「おまえと恋人になってから、毎日悪くなかったよ」
「…嬉しいな」
「おまえは優しくて、たくさん甘やかしてくれて…頼ってほしいって言われたときは、おれのこと女の子扱いしてくれるんだって、それも嬉しかった」
「そんなの当たり前でしょ」
「どんどんおまえと離れたくなくなって、気持ちが膨らんで…自分がどんどんダメになっていくのが分かった」
「え…」
「もう誰かのことを憎らしく思いたくないし、お前のことをこれ以上好きにもなりたくない。だから…」
別れてほしい。
視界がぼやけてよく見えないけど、クソDJがおれのことをじっと見ていることは分かった。偽物の恋人なのに、少し優しくしてやっただけなのに、面倒なやつに声をかけてしまったと思うだろうか。
それでもいい。もう二度と、おれを自分の都合に巻き込まないでいてくれるならそれで。
「俺のこと、嫌いになった?」
クソDJが聞いてきたのは、その一言だった。泣いてしまったせいか、クソDJの声まで震えて聞こえる。冷たい風が頬を突き刺すように去っていった。
「もうわかんねー」
「そっか」
これ以上好きになりたくないと言ったり、分からないと言ったり。だけどどちらも本当のことだった。頭の中はぐちゃぐちゃで、もう自分の気持ちすらよく分からない。頭の中に浮かぶのは、クソDJと過ごした毎日のこと。本当の恋人みたいに優しくしてくれたひとりの男の顔だけだった。
突然なにかに遮られたみたいに風が止んで、身体がきつく抱きしめられる。クソDJに抱きしめられていると分かったのは少し経ってからのことだった。
「…おまえ、いまの話聞いてたか?はなせよ」
「俺前に言ったよね。困ってるときは一番に俺を頼ってほしいって」
「言ったけど、それがなんだよ…」
忘れるわけがない。とはいえ困っていると頼りに行く前にあれこれ世話を焼いてくれていたから、実際に相談したことはほとんどなかった気がするが。それも別れたらおしまいだろう。ただの同僚の悩みを解決する義理はないはずだ。
「俺にはさ、いまのおチビちゃんの話、助けてって言ってるように聞こえたんだけど」
「……え」
「やっと頼ってくれたね」
身体が浮くくらい強い力で抱きしめられて、すこし痛いくらいだ。だけど寒い日に布団の中でいつも大事にあたためてくれていた腕と同じ力加減で、同じ匂いがすることがどうしても嬉しかった。
助けてなんて言ってない。離れたいって言ったんだ。
そんな強がりを吹き飛ばすくらいわがままな抱擁に、膜を張っていた涙が粒となって溢れ出る。大きな手が頭を撫でてくれるのが心地よかった。
少し経って離れると、涙も落ち着いた。改めて言えるはずだ。
「やっぱりおまえとは別れたい。好きな気持ちを抱えたまま、偽物の恋人は続けられないから」
「……おチビちゃんが真面目で超頑固なの、忘れてた」
「うるせー」
「気持ちが分かった後でこんなことするの、ちょっとズルい気もするけど…」
アハ、と聞き慣れた声で笑みをひとつこぼしたクソDJは、持ってきていた紙袋から小さなギフト用のジュエリーボックスを取り出した。そっと開かれた中にはリングの付いたペンダントが大事そうに仕舞われている。
「おチビちゃん、おれと本当の恋人になってください」
「…え」
「もしかして、ダメ?さっきの言い方だと、本当の恋人同士になら、なってくれるかなと思ったんだけど」
「そうだけど、それが出来ないから、別れようって…」
「そもそも俺、一言もおチビちゃんのこと好きじゃないなんて言ってないよ」
え、と驚いてムカつくほど整った顔を見上げると、悪戯な言葉とは裏腹に穏やかな表情をしていた。愛おしいと心の底から伝えてくるようなその目を、コイツは一体いつからおれに向けていたんだろう。
「これ、つけてもいい?」
「うん、いいけど…」
ペンダントを器用におれの首元に飾ったクソDJは、やっぱり似合うだなんだと穏やかな声で褒めるから、聞いているこっちが恥ずかしくなってくる。
本当の恋人になるかどうか、迷うはずもない返事を保留にしているのがモヤモヤした。
だけどどうしても聞かなければならないことがあるのだ。
「じゃあ、あの女の人は誰なんだよ…」
いまおれの胸元に光っているペンダントと、あの日クソDJたちが消えていった方向にあるジュエリーショップは同じはずだ。
「もしかして、見てたの?」
それだけ呟いたクソDJは、甘えるようにおれの身体を抱きしめてのしかかってきた。
「ダサいな、俺…いや、女の子といたこともだけど、買うとこ見られてたとか…」
「ごまかすんじゃねーぞ」
「ごまかすも何も、名前覚えてないくらい前のカノジョ。多分俺がジュエリーショップ入るとこ見て、あわよくば何か買ってもらおうと思ってたんじゃないの」
確かにあのとき、抱きついていたのは女の人だけだった。向こうに歩いていく姿しか見ていないから、クソDJがどんな表情をしていたのかは見えなかったけど、よくよく思い返してみるとデートって雰囲気ではなかったのかもしれない。
「じゃあ待ち合わせしてたわけじゃ…」
「そんな訳ないでしょ。おチビちゃんのためのペンダント買いに行ったんだよ」
クソDJが、おれのことだけを思って選んでくれたプレゼント。
それだけで胸を覆っていたいやな感情が全部無くなってしまうくらいに嬉しかった。
「…そっか」
クソDJが選んでくれたそれをそっと手で触る。可愛らしいけれどシンプルなデザインは、おれが付けていても違和感がないだろう。色仕掛けだなんだと考えていたあの日の自分がバカらしく思える。クソDJはもうずっとおれのことを見ててくれていたというのに。
「なあ、さっきの返事してもいい?」
「うん、聞かせてほしいな」
「その前に、もういっこ聞きたいんだ」
なんで、偽物の恋人が必要だったんだ?
そう聞くと、クソDJは目を丸くさせて、それから気まずそうに笑った。いまの破顔は、周りに人がいたらさぞ女の子たちをメロメロにしたことだろう。寒さで鼻が真っ赤になっていなければの話だが。
「偽物の恋人が必要だった訳じゃなくて、おチビちゃんにお試しでもいいから付き合ってほしかったんだよね」
「おれに…お試しで?」
クソDJいわく、おれが恋をしている顔をしていたらしい。誰のことを考えているのか分からなくてモヤモヤしていたから、自分を意識してもらおうと嘘をついて偽物の恋人になったのだとか。
「そんなのアリかよ…」
「だってさ、あの時のおチビちゃん、甘いものでも食べてるんじゃないかってくらい幸せそうな顔してて…」
誰にも渡したくなかったんだ。
恋をしている顔だった。いつから、なんて野暮だ。こいつはずっと、おれに恋をしていたんだから。いままで一緒に過ごした時間を思い出すと、頬に熱が集まったのが分かった。
「冷えちゃったね、帰ろっか」
お互いに冷えきった手を繋いで、部屋までの道を歩く。こんなふわふわとした気持ちでこいつとここを歩くことになるなんて思ってもみなくて、我慢しようとすればするほど口角が上がってしまうのが分かった。
寝る支度を済ませてちらりとクソDJのベッドを見ると、まるで当然とでもいうように布団の半分のスペースが空けられていた。おそるおそる自分から入ると、すでに人肌でじんわりとあたたかい。
いつものように回された腕を邪魔しないように、今日はおれも抱きしめ返す。
「あったかいね」
「そうだな」
「外してきちゃったの?」
さらりと首筋を撫でられて、思わず身震いする。一緒に寝ることはあっても、抱きしめたり手を握ったりする以外の接触は思えば初めてだった。
「無くしたらかなしいだろ…」
「アハ、そうだね」
「…どうして急に、ペンダントなんだよ」
屋上にいる時から思っていたことがポロリと口から漏れた。「なぜ」や「なんで」が浮かびすぎて出す機会を無くしていたが、聞かないままなのはなんとなくモヤモヤする。
「急に…やっぱり分かんないか」
「やっぱり、ってなんだよ」
「俺とおチビちゃんが付き合い始めて…といっても偽物の恋人になって、だけど…あれから一ヶ月めなんだよ、今日」
「もうそんなに経つのか…」
「だからケジメを付けたかったというか何というか…まあ俺にだってさ、カッコつけたいことはあるんだよ」
好きな子の前ならね。
そんな言葉にもどうしようもなくときめいて、恋をしてしまうから。早鐘のようになっている鼓動だけは回された手のひらごしに伝わってしまわないように、ぎゅっと両手を握る。
あたたかくなった布団の中で端正な顔を見上げると、愛おしさを煮詰めたようなマゼンタの瞳が今度こそくっつくほど近くにいたから、目を瞑ってはじめてのキスを受け入れた。