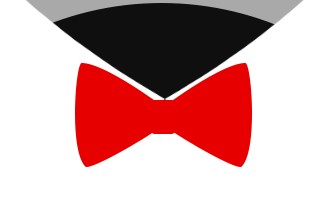フェイジュニ
【ティンカーベルはいない】
大人にならないでいるっていうのは、本当に幸せなことなのだろうか。おれにはそれが分からない。いまおれは、子どもだからこそ許される恋をしている。
結婚式の招待状が届いたのは、新しいセクターに移って二年目の冬。らしくない絢爛な封筒で届いたそれは、羨ましくなるくらい幸せに満ち溢れていた。素っ裸のままそれをぼうっと眺めていると、同じく素っ裸のフェイスが布団から顔を出す。
「行くの?」
「行くだろ。特に用事もないし」
「ふーん」
特にそれ以上の話はないのか、フェイスは再び布団の中に潜り込む。まだ明け方で、室内は薄暗いというのにその手紙だけはくすむことなく煌びやかに見えた。将来を誓い合った二人の、未来への切符だ。まるで幸せの象徴。おれが手にすることのできないもの。
ルーキーの頃には切磋琢磨して、同じくらいに見えていたアイツが大人になったのを感じる。アイツだけじゃない、あの頃そばにいた人たちはやっぱりおれよりも随分と大人で、追いつけることなんてないまま先に進んでいく。ずるいと思っていた。追いつきたいと思っていた。
それがどうだろう。腹立たしいほど綺麗な顔で眠る隣の男に恋をしてから、そんな気持ちはとうになりを潜めてしまった。ずっと子どものままでいたい。この恋を許されたい。ずっとコイツの隣で、同じ景色を見ていたい。
幸か不幸か、フェイスはおれを選んでくれた。でもそれは恋人としてではなく、身体だけを重ねるオトモダチとしてだ。それでも期待してしまう。おれとこうなってから、彼女全員と縁を切ったこと。たまにデートに連れ出してくれること。だけど現実はどこまでも残酷で、おとぎ話のように一晩限りの夢さえも見させてはくれない。
キスをして抱き合って、セックスをして、ふわふわした頭のまま眠りにつくと、次の日の朝にはフェイスはいない。冷たくなったベッドとおれの身体だけが熱を忘れてしまうのだ。初めの頃は、朝目覚めて隣にいてさえくれないフェイスに怒りも湧いたものだが、いまとなってはそんな中途半端なことをしなかったことに感謝の念さえ抱いている。だってそれは、おれたちに許される朝じゃない。
おれのヒーロー人生の中には、ずっとフェイスがいた。同僚として、仲間として、相棒として、そしてーーー。これからも、そういう風に隣にいてくれるだろうか。セフレのままでいいから、おれを隣に置いてくれるだろうか。そんな亡霊のような不安に、長いあいだ取り憑かれている。
◇◇◇
結婚式は盛況のうちに終わった。勿体無いくらい綺麗な奥さんと、白いタキシードを着てはにかむアイツ。なんだかとってもお似合いで、頭から離れない。
フェイスと一緒に式場を出ると、自分たちが周りからどう見えているのかが無性に気になった。仲の良い同僚に見えているだろうか。それとも腐れ縁のようだろうか。アイツらのように、お似合いの、
「…ダメだ」
「え?」
「ごめん、でも、このままじゃ…ダメだろ」
「何が?急にどうしたの」
「分からない。でも、急じゃないんだよ」
お前とは、もう一緒にいられない。
この時のこの言葉は、アイツの耳に、心に、どんな響きで聴こえていたのだろう。
ずっとずっと逃げ出したかったのだ。おれの気持ちや、身体と情を交わした夜から毎回いなくなるアイツみたいに、おれだって駆け出して、大声で泣きたかった。そう気付いたのは、逃げ出した後のことだった。だから知らなくていいのだ。おれがどんな思いでフェイスと一緒にいたのか、なんて。
◇◇◇
あの逃げ出した結婚式の帰り道から、一ヶ月が経っていた。
フェイスは追いかけても来なかったし、その後顔を合わせることもなかった。セクターが分かれたんだから、会おうとしなければそう頻繁に会うことなんてない。当然と言えば当然の話だ。
机の上に放置された引き出物のバームクーヘンが、当たり前に上手くいかなかったおれたちの関係性を嘲笑っているようで悲しさやら虚しさやらが綯い交ぜになった感情に襲われる。そうだ、おれたちは元々祝福されるような関係じゃなかった。みんなみたいに、大人にならなきゃ。無理矢理そう思い込もうとするたび、涙がぽろりと落ちて幼いおれが問いを投げかける。
どうして、好きな人と一緒にいられないの。どうして、大人にならなきゃいけないの。どうして、アイツとおれじゃ幸せになれないの。どうして、あの時逃げ出したの。どうして、どうして…
目が覚めると、いつも通りの朝だった。冷たいシーツにおれ一人の身体。身支度を整えて、朝食を食べる。何をしてもしなくても、お腹が空く。相変わらずバームクーヘンは放置されたまま、中がどうなっているのかなんておれには分からない。
最後に一度だけ会って話したかったから、ダメ元でメールを送った。フェイスはいつもふらりと現れて勝手におれのそばにいたから、おれから連絡を取るのはほとんど初めてに近いことだった。
「最後、か…」
どんな話をすればいいんだろう。勝手に縁を切ろうとして怒られるだろうか、重い話をしてめんどくさがられるだろうか。そもそも来てくれるだろうか。不安ばかり感じる一日が少しずつ過ぎていった。
◇◇◇
身体を重ねるのは、いつも決まっておれの家だ。
研修チームが解散して新しいセクターに異動になったのを機に借りた部屋で、一人暮らしにしては広いその部屋をおれはとても気に入っていたし、フェイスも気に入ったのか頻繁に泊まりに来てはおれを抱いて、気まぐれに帰っていった。初めてセックスをしたのもこの部屋だ。引っ越しの祝いに来て、酒の入ったまま身体を重ねた。おれはとっくにフェイスのことが好きだったから、コイツもおれのことが好きなのかなってドキドキしたのを覚えている。
そんなこの部屋で、おれは全てを終わらせたい。
コンコンコンとノックは三回。アイツが部屋を訪ねてくる時の合図だ。とうに来てくれたことを無邪気に喜べる心持ちではなくなってしまっている。玄関までの道のりがやけに長く感じた。扉を開けると、少し機嫌のいいフェイスが立っていた。最後の思い出が怒り顔や悲しい顔になるよりは、よっぽどマシだと思った。
「珍しいね、おチビちゃんが呼んでくれるなんて」
「初めてかもな」
そして、きっと最後だろう。部屋に向かおうとフェイスに背を向けると、やけに熱い吐息が耳にかかったのを感じた。ぐっと引き寄せられた身体は密着していて、触れたところからフェイスの熱が伝わってくる。
「ねえ、これってどっち?」
「…?」
突然の行動に、意味の分からない言葉をかけられて頭が混乱する。さっきまで見えていたフェイスの顔は笑っていたはずなのに、声は泣きそうに震えているように感じた。
「別れ話?それともヨリを戻そうってやつ?…どっちもやだな」
自嘲したように吐き出された息に、ガンと頭を殴られたような気分になった。コイツはおれとこれ以上の関係になりたいと望むことも、きっぱり離れようという気もないのか。結局のところ体の良いセフレでしかなかったということだ。
なんでお前がそんな声を出すんだ。おれの悲しみも、苦しみも、何ひとつ知らないくせして。
力いっぱいフェイスの身体を押しのけて距離を取る。顔も見られないまま、止まらない涙が足元をじっとりと濡らしていく。
「別れ話なんて、そんな大層なものじゃないだろ」
大人にならないでいるっていうのは、本当に幸せなことなのだろうか。おれにはそれが分からない。いまおれは、子どもだからこそ許される恋をしている。
結婚式の招待状が届いたのは、新しいセクターに移って二年目の冬。らしくない絢爛な封筒で届いたそれは、羨ましくなるくらい幸せに満ち溢れていた。素っ裸のままそれをぼうっと眺めていると、同じく素っ裸のフェイスが布団から顔を出す。
「行くの?」
「行くだろ。特に用事もないし」
「ふーん」
特にそれ以上の話はないのか、フェイスは再び布団の中に潜り込む。まだ明け方で、室内は薄暗いというのにその手紙だけはくすむことなく煌びやかに見えた。将来を誓い合った二人の、未来への切符だ。まるで幸せの象徴。おれが手にすることのできないもの。
ルーキーの頃には切磋琢磨して、同じくらいに見えていたアイツが大人になったのを感じる。アイツだけじゃない、あの頃そばにいた人たちはやっぱりおれよりも随分と大人で、追いつけることなんてないまま先に進んでいく。ずるいと思っていた。追いつきたいと思っていた。
それがどうだろう。腹立たしいほど綺麗な顔で眠る隣の男に恋をしてから、そんな気持ちはとうになりを潜めてしまった。ずっと子どものままでいたい。この恋を許されたい。ずっとコイツの隣で、同じ景色を見ていたい。
幸か不幸か、フェイスはおれを選んでくれた。でもそれは恋人としてではなく、身体だけを重ねるオトモダチとしてだ。それでも期待してしまう。おれとこうなってから、彼女全員と縁を切ったこと。たまにデートに連れ出してくれること。だけど現実はどこまでも残酷で、おとぎ話のように一晩限りの夢さえも見させてはくれない。
キスをして抱き合って、セックスをして、ふわふわした頭のまま眠りにつくと、次の日の朝にはフェイスはいない。冷たくなったベッドとおれの身体だけが熱を忘れてしまうのだ。初めの頃は、朝目覚めて隣にいてさえくれないフェイスに怒りも湧いたものだが、いまとなってはそんな中途半端なことをしなかったことに感謝の念さえ抱いている。だってそれは、おれたちに許される朝じゃない。
おれのヒーロー人生の中には、ずっとフェイスがいた。同僚として、仲間として、相棒として、そしてーーー。これからも、そういう風に隣にいてくれるだろうか。セフレのままでいいから、おれを隣に置いてくれるだろうか。そんな亡霊のような不安に、長いあいだ取り憑かれている。
◇◇◇
結婚式は盛況のうちに終わった。勿体無いくらい綺麗な奥さんと、白いタキシードを着てはにかむアイツ。なんだかとってもお似合いで、頭から離れない。
フェイスと一緒に式場を出ると、自分たちが周りからどう見えているのかが無性に気になった。仲の良い同僚に見えているだろうか。それとも腐れ縁のようだろうか。アイツらのように、お似合いの、
「…ダメだ」
「え?」
「ごめん、でも、このままじゃ…ダメだろ」
「何が?急にどうしたの」
「分からない。でも、急じゃないんだよ」
お前とは、もう一緒にいられない。
この時のこの言葉は、アイツの耳に、心に、どんな響きで聴こえていたのだろう。
ずっとずっと逃げ出したかったのだ。おれの気持ちや、身体と情を交わした夜から毎回いなくなるアイツみたいに、おれだって駆け出して、大声で泣きたかった。そう気付いたのは、逃げ出した後のことだった。だから知らなくていいのだ。おれがどんな思いでフェイスと一緒にいたのか、なんて。
◇◇◇
あの逃げ出した結婚式の帰り道から、一ヶ月が経っていた。
フェイスは追いかけても来なかったし、その後顔を合わせることもなかった。セクターが分かれたんだから、会おうとしなければそう頻繁に会うことなんてない。当然と言えば当然の話だ。
机の上に放置された引き出物のバームクーヘンが、当たり前に上手くいかなかったおれたちの関係性を嘲笑っているようで悲しさやら虚しさやらが綯い交ぜになった感情に襲われる。そうだ、おれたちは元々祝福されるような関係じゃなかった。みんなみたいに、大人にならなきゃ。無理矢理そう思い込もうとするたび、涙がぽろりと落ちて幼いおれが問いを投げかける。
どうして、好きな人と一緒にいられないの。どうして、大人にならなきゃいけないの。どうして、アイツとおれじゃ幸せになれないの。どうして、あの時逃げ出したの。どうして、どうして…
目が覚めると、いつも通りの朝だった。冷たいシーツにおれ一人の身体。身支度を整えて、朝食を食べる。何をしてもしなくても、お腹が空く。相変わらずバームクーヘンは放置されたまま、中がどうなっているのかなんておれには分からない。
最後に一度だけ会って話したかったから、ダメ元でメールを送った。フェイスはいつもふらりと現れて勝手におれのそばにいたから、おれから連絡を取るのはほとんど初めてに近いことだった。
「最後、か…」
どんな話をすればいいんだろう。勝手に縁を切ろうとして怒られるだろうか、重い話をしてめんどくさがられるだろうか。そもそも来てくれるだろうか。不安ばかり感じる一日が少しずつ過ぎていった。
◇◇◇
身体を重ねるのは、いつも決まっておれの家だ。
研修チームが解散して新しいセクターに異動になったのを機に借りた部屋で、一人暮らしにしては広いその部屋をおれはとても気に入っていたし、フェイスも気に入ったのか頻繁に泊まりに来てはおれを抱いて、気まぐれに帰っていった。初めてセックスをしたのもこの部屋だ。引っ越しの祝いに来て、酒の入ったまま身体を重ねた。おれはとっくにフェイスのことが好きだったから、コイツもおれのことが好きなのかなってドキドキしたのを覚えている。
そんなこの部屋で、おれは全てを終わらせたい。
コンコンコンとノックは三回。アイツが部屋を訪ねてくる時の合図だ。とうに来てくれたことを無邪気に喜べる心持ちではなくなってしまっている。玄関までの道のりがやけに長く感じた。扉を開けると、少し機嫌のいいフェイスが立っていた。最後の思い出が怒り顔や悲しい顔になるよりは、よっぽどマシだと思った。
「珍しいね、おチビちゃんが呼んでくれるなんて」
「初めてかもな」
そして、きっと最後だろう。部屋に向かおうとフェイスに背を向けると、やけに熱い吐息が耳にかかったのを感じた。ぐっと引き寄せられた身体は密着していて、触れたところからフェイスの熱が伝わってくる。
「ねえ、これってどっち?」
「…?」
突然の行動に、意味の分からない言葉をかけられて頭が混乱する。さっきまで見えていたフェイスの顔は笑っていたはずなのに、声は泣きそうに震えているように感じた。
「別れ話?それともヨリを戻そうってやつ?…どっちもやだな」
自嘲したように吐き出された息に、ガンと頭を殴られたような気分になった。コイツはおれとこれ以上の関係になりたいと望むことも、きっぱり離れようという気もないのか。結局のところ体の良いセフレでしかなかったということだ。
なんでお前がそんな声を出すんだ。おれの悲しみも、苦しみも、何ひとつ知らないくせして。
力いっぱいフェイスの身体を押しのけて距離を取る。顔も見られないまま、止まらない涙が足元をじっとりと濡らしていく。
「別れ話なんて、そんな大層なものじゃないだろ」