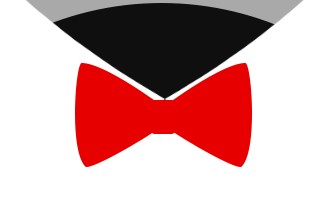フェイジュニ
【茨の猛毒】
付き合ってるってなんだっけ。恋人ってなんだっけ。
おれにとっては、愛を交わす相手も、熱を交わす相手もたったひとりだけ。でもそれは、アイツの世界では普通のことじゃなかったみたいだ。
見かけるのは決まって路地裏のモーテル。仲睦まじく歩いていくさまは、おれとアイツよりよっぽど恋人のようだ。「好き」と言われた。「愛してる」と言われた。キスもした。だけどたったひとつ、アイツはおれを抱かない。そんな事実にどうしようもなく打ちのめされて、天気予報とは裏腹な大粒の雨が降り出すまで、おれは動くことができないでいた。
おれとクソDJがこんな関係になったきっかけは、アイツの誕生日。メンティーのアルコール解禁に舞い上がったキースとディノにたらふく酒を飲まされたクソDJが、おれに告白してきたところから始まった。
正気かどうかも分からない熱に浮かされた瞳で「好きだよ」と言われて、キスをした。ファーストキスは美味しくもない酒の味だったけど、その時おれは案外悪くないなと思った自分に気がついたのだ。
抵抗する手を緩めると、アイツの手はおれの腹の辺りを弄ってきた。あれよあれよと服を脱がされたおれの、一番恥ずかしいところ。その場所に熱い手が触れた時、おれは「待ってくれ」と言った。こんな風に、正気かどうかも分からない相手に流されるのは嫌だった。
アイツは眠気もあったようで、断られるとおれを抱え込んだまま眠ってしまった。その体勢のままスマホで調べると、男同士のセックスには大変な準備が要ることを知った。
次の日から、おれの努力の日々が始まった。完全に酔っていたくせに告白をした時の記憶はあるようで、晴れて恋人同士になったおれに無遠慮に触れようとする手のひらを避けながら、一人の時間に身体を綺麗にして奥を拓いていく。痛くて怖くて、初めて繋がった時には好き勝手に動き回る熱の塊に文句の一つでも言ってやりたくなったが、甘い声で「好きだよ」と言ってキスを落とすその男の蕩けるような表情を見たらどうでも良くなった。さすがのコイツも男は初めてなのだろう。慣れない粗雑な動きが少し嬉しくもあった。告白はフェイスからだったが、この時にはすでにおれもコイツのことが大好きだったんだ。
だから、初めてそこでクソDJを見た時は信じられない気持ちだった。奈落にでも落ちるような心地で、フェイスと知らない女が連れ立って歩くのを見ていた。
「ねえ、本命くんとは上手くいってるの?」
「んー、まぁまぁ?」
「やだ、なによぉそれ」
媚を売るような猫撫で声が、裏路地の雑踏に紛れて聞こえてくる。
「なんか拒否されることも多いし、しばらくはあの子とセックスしなくていいかな〜って感じ」
「だからって私たちで発散してるの?本当にやな男」
まだホテルの外だというのに、女は豊満な胸をフェイスに押しつける。皮肉を言いながらも、これからの時間に期待をしているのだろう。手を絡めて、つま先を伸ばして、唇を寄せようとする。
ふるりとした女性らしい唇を空いている掌で止めると、クソDJは女に向かって心底軽蔑したような表情を向けた。
「ねえ、キスはしないって。そういう約束でしょ」
「んー、つれないわァ。いいじゃないの一回くらい」
「俺の唇はおチビちゃんだけのものなの」
「セックスは面倒がるくせに」
アハハ、と嘲笑するような女の笑い声を最後に二人はホテルに消えていった。それからどうやってタワーまで帰ったかは覚えていない。
結局のところ、クソDJの中の「好き」とおれの「好き」には深い溝があったという話だ。毎日は繋がれなくても、好きと言い合うだけで、キスを交わすだけで満たされた心地になっていたおれがバカだった。ちょっとの時間だけでも深いところで繋がるために身体を用意していた時間は、アイツにとって無駄なことだったのだろう。それに気づかず、拒否されたと思われて、挙げ句の果てには浮気されて、大真面目に付き合っていると思っているおれのことを嘲笑っていたのだろうと考えると、やりきれなかった。
キスはしてないから浮気にならないなんて予防線を張っていたのもサイテーだ。いつか女に刺されそうなやつだとは思っていたが、自分が刺す側に回りそうな日が来るとは思ってもいなかった。帰ってきてそこそこにベッドに倒れ込み、自分の薄い唇をなぞる。クソDJいわく、おれとアイツが恋人である唯一の証だ。宝物みたいに、慈しむようにアイツに抱かれることはこれからもないのだと悟り、溢れた涙がひとすじ頬を伝った。
付き合ってるってなんだっけ。恋人ってなんだっけ。
おれにとっては、愛を交わす相手も、熱を交わす相手もたったひとりだけ。でもそれは、アイツの世界では普通のことじゃなかったみたいだ。
見かけるのは決まって路地裏のモーテル。仲睦まじく歩いていくさまは、おれとアイツよりよっぽど恋人のようだ。「好き」と言われた。「愛してる」と言われた。キスもした。だけどたったひとつ、アイツはおれを抱かない。そんな事実にどうしようもなく打ちのめされて、天気予報とは裏腹な大粒の雨が降り出すまで、おれは動くことができないでいた。
おれとクソDJがこんな関係になったきっかけは、アイツの誕生日。メンティーのアルコール解禁に舞い上がったキースとディノにたらふく酒を飲まされたクソDJが、おれに告白してきたところから始まった。
正気かどうかも分からない熱に浮かされた瞳で「好きだよ」と言われて、キスをした。ファーストキスは美味しくもない酒の味だったけど、その時おれは案外悪くないなと思った自分に気がついたのだ。
抵抗する手を緩めると、アイツの手はおれの腹の辺りを弄ってきた。あれよあれよと服を脱がされたおれの、一番恥ずかしいところ。その場所に熱い手が触れた時、おれは「待ってくれ」と言った。こんな風に、正気かどうかも分からない相手に流されるのは嫌だった。
アイツは眠気もあったようで、断られるとおれを抱え込んだまま眠ってしまった。その体勢のままスマホで調べると、男同士のセックスには大変な準備が要ることを知った。
次の日から、おれの努力の日々が始まった。完全に酔っていたくせに告白をした時の記憶はあるようで、晴れて恋人同士になったおれに無遠慮に触れようとする手のひらを避けながら、一人の時間に身体を綺麗にして奥を拓いていく。痛くて怖くて、初めて繋がった時には好き勝手に動き回る熱の塊に文句の一つでも言ってやりたくなったが、甘い声で「好きだよ」と言ってキスを落とすその男の蕩けるような表情を見たらどうでも良くなった。さすがのコイツも男は初めてなのだろう。慣れない粗雑な動きが少し嬉しくもあった。告白はフェイスからだったが、この時にはすでにおれもコイツのことが大好きだったんだ。
だから、初めてそこでクソDJを見た時は信じられない気持ちだった。奈落にでも落ちるような心地で、フェイスと知らない女が連れ立って歩くのを見ていた。
「ねえ、本命くんとは上手くいってるの?」
「んー、まぁまぁ?」
「やだ、なによぉそれ」
媚を売るような猫撫で声が、裏路地の雑踏に紛れて聞こえてくる。
「なんか拒否されることも多いし、しばらくはあの子とセックスしなくていいかな〜って感じ」
「だからって私たちで発散してるの?本当にやな男」
まだホテルの外だというのに、女は豊満な胸をフェイスに押しつける。皮肉を言いながらも、これからの時間に期待をしているのだろう。手を絡めて、つま先を伸ばして、唇を寄せようとする。
ふるりとした女性らしい唇を空いている掌で止めると、クソDJは女に向かって心底軽蔑したような表情を向けた。
「ねえ、キスはしないって。そういう約束でしょ」
「んー、つれないわァ。いいじゃないの一回くらい」
「俺の唇はおチビちゃんだけのものなの」
「セックスは面倒がるくせに」
アハハ、と嘲笑するような女の笑い声を最後に二人はホテルに消えていった。それからどうやってタワーまで帰ったかは覚えていない。
結局のところ、クソDJの中の「好き」とおれの「好き」には深い溝があったという話だ。毎日は繋がれなくても、好きと言い合うだけで、キスを交わすだけで満たされた心地になっていたおれがバカだった。ちょっとの時間だけでも深いところで繋がるために身体を用意していた時間は、アイツにとって無駄なことだったのだろう。それに気づかず、拒否されたと思われて、挙げ句の果てには浮気されて、大真面目に付き合っていると思っているおれのことを嘲笑っていたのだろうと考えると、やりきれなかった。
キスはしてないから浮気にならないなんて予防線を張っていたのもサイテーだ。いつか女に刺されそうなやつだとは思っていたが、自分が刺す側に回りそうな日が来るとは思ってもいなかった。帰ってきてそこそこにベッドに倒れ込み、自分の薄い唇をなぞる。クソDJいわく、おれとアイツが恋人である唯一の証だ。宝物みたいに、慈しむようにアイツに抱かれることはこれからもないのだと悟り、溢れた涙がひとすじ頬を伝った。