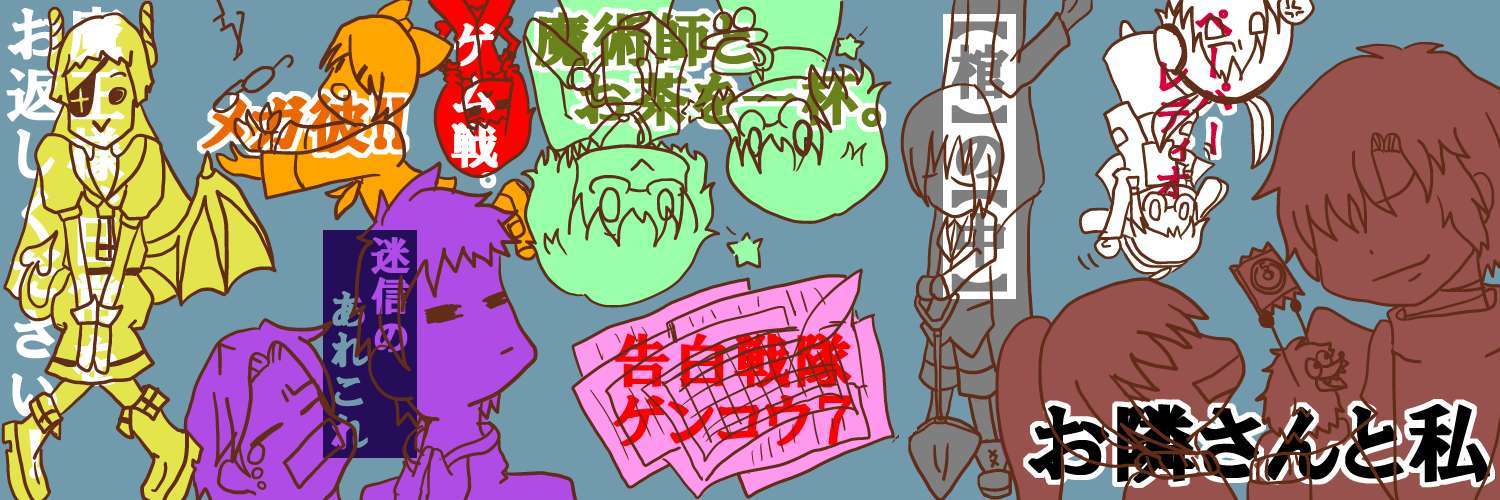七月の季節
【深夜営業の花屋に薔薇はあるか】
灯りが普及した現代、深夜営業は珍しくない。土地によっては当たり前なくらいだ。でも、どこでもそれが当たり前ではない――。
「うっ、気持ち悪い……」
時刻は深夜零時を回っている。店長の横暴さにブちぎれてしまった俺は後先考えずに店をやめてしまった。そして自暴自棄になってヤケ酒をあおって終電で自宅のある街に戻った。
家賃の安さから選んだ家は電車で街中に出るにはそんなに困らないが、駅からは離れている。
それに明るいうちでも少し不気味な雰囲気が漂うシャッター街を通り抜けなければいけない。昔は地元の人に愛されていた商店街なのかもしれないが、放置された店の数々は得体のしれない不気味さを醸し出しているわけで、俺は苦手だ。
住宅地にポツリと出現しているそのシャッター街は、あくまでも商店街だということを主張するように屋根が付けられており、所々に濁った色の裸電球がぶら下がって今でも夜になると転倒する。
ホラー映画のCMを地上波で流すこと反対派の俺は競歩選手になったつもりでシャッター街にを通り抜ける。そんなに広くはないはずなのに、この中は何処か迷路のようで十字路やT字路になっている部分もあって、通ったことのない道も多い。
けれどそんなことはどうでもいい。どうせ開いている店などないし、開いていても不気味なことこの上ないはずだ。
そんなことを考えていたのに自分で自分が相当に酔っていることを忘れていた。急に目の前がひっくり返り、ガシャンという薄い鉄と重たいものがぶつかった音が響く。
簡単にいえば転んだ。けれどそれで少し酔いがさめた気もした。
「大丈夫です??」
突然かけられた声にさらに酔いがさめる。
「ちょっと、足がもつれて……」
言い訳をしながら顔をあげるとそこには、綺麗な中性的な顔立ちに、長い黒髪を輪を一つ作りしばっている人物がいた。
赤いカッターシャツに黒いズボン。そして、黒いエプロンというどこかのお店の制服のような服装。やはり男性なのか女性なのかわからない。
「あらあら。血が出てますよ」
その人はそう言いながら自分のおでこを指さす。
「服に血が付いたら大変ですから、絆創膏だけでも貼った方がいいですよ」
どこかの貴族かというような振る舞いで俺を立たせると、一番近くの曲がり角を曲がった。そこも裸電球がぶら下がるシャッター街だったが、場違いのように一ヶ所だけ灯りがを放っている場所がある。
近付くとそこが花屋であることは容易にわかった。お洒落な街中にでもありそうな、白をベースにした現代的な作りのお店で、LEDライトの眩しさは尋常ではない。
店の奥の方まで案内され、気が付けばパイプ椅子に座らされていた。
奥といっても広さはない。外を見なければ植物園の温室を思い出す。全ての花が今摘んできたかのように生き生きとしている。
明日の朝から営業する予定なら時間的に鮮度が失われてしまう気がしたが、まずこの量がここで売れるのかという疑問の方が大きかった。
ぼーっと店内を眺めてるうちに「ちょっとしみますよ」と着々と俺の額は修理されていく。
「このお店っていつもこの時間に空けてるんですか??」
世間話のように訊ねてみると「えぇ。ずっと昔から開店時間は午前零時からですよ」と笑顔で返された。
「よく潰れませんね」と口を滑らせた俺に「この店の花を必要としている人がいる限りは」とまた笑顔で返される。
「この店の花は不思議な花ばかりで、役目を果たすまで決して枯れないんですよ」
ちょっとこの人は頭がおかしいのかと思い始めた。
「あるべき場所へ。それを必要な人に渡すのが仕事なんですよ」
やっぱり頭がおかしい人だ。
心の中でそんな感想を述べていると、一本のチューリップを差し出された。
「今日の不幸は明日の幸せのための対価」
「花言葉ですか??」
「いいえ。貴方への言葉ですよ」
すべて知っていると言いたげに笑う店主は「お代は結構ですよ」といい強引にチューリップを持たされる。
ホラーとは違うが色んな意味で不気味だったので逃げるように店から離れた。
シャッター街を通り抜けるとさっきの出来事がどこか夢だったのではないかという気分に襲われる。それこそ狐にでも化かされたような感覚だ。そんな経験はないけど。
それでも自分の手には綺麗なチューリップが一輪あり、額には絆創膏が張られている。
気が付けば、いつの間にか酔いも嫌な気持ちも不安も消えていた。明日の朝一で店長に謝るか……そんなことを考えながら歩いていた俺の前に、今度は男性が転がり飛んできた。
「最低!!」という罵声と共に、一軒家の扉が大きな音を立てて締まる。男性は涙目で地面と一体化しようとしていたので、なんだかいたたまれなくなり声をかける。
なんでも結婚記念日には毎年一本の花を贈るという約束をしていたのに、従業員が辞めて仕事が忙しくうっかり忘れたそうだ。
「よければこれを」
さっきの『あるべき場所へ。それを必要な人に渡すのが仕事』という言葉が蘇り、俺は半ば強引に花を男性に手渡して、家に帰った。
翌日からその男性が新たな雇い主になるなんて、一切想像することさえなく……。
灯りが普及した現代、深夜営業は珍しくない。土地によっては当たり前なくらいだ。でも、どこでもそれが当たり前ではない――。
「うっ、気持ち悪い……」
時刻は深夜零時を回っている。店長の横暴さにブちぎれてしまった俺は後先考えずに店をやめてしまった。そして自暴自棄になってヤケ酒をあおって終電で自宅のある街に戻った。
家賃の安さから選んだ家は電車で街中に出るにはそんなに困らないが、駅からは離れている。
それに明るいうちでも少し不気味な雰囲気が漂うシャッター街を通り抜けなければいけない。昔は地元の人に愛されていた商店街なのかもしれないが、放置された店の数々は得体のしれない不気味さを醸し出しているわけで、俺は苦手だ。
住宅地にポツリと出現しているそのシャッター街は、あくまでも商店街だということを主張するように屋根が付けられており、所々に濁った色の裸電球がぶら下がって今でも夜になると転倒する。
ホラー映画のCMを地上波で流すこと反対派の俺は競歩選手になったつもりでシャッター街にを通り抜ける。そんなに広くはないはずなのに、この中は何処か迷路のようで十字路やT字路になっている部分もあって、通ったことのない道も多い。
けれどそんなことはどうでもいい。どうせ開いている店などないし、開いていても不気味なことこの上ないはずだ。
そんなことを考えていたのに自分で自分が相当に酔っていることを忘れていた。急に目の前がひっくり返り、ガシャンという薄い鉄と重たいものがぶつかった音が響く。
簡単にいえば転んだ。けれどそれで少し酔いがさめた気もした。
「大丈夫です??」
突然かけられた声にさらに酔いがさめる。
「ちょっと、足がもつれて……」
言い訳をしながら顔をあげるとそこには、綺麗な中性的な顔立ちに、長い黒髪を輪を一つ作りしばっている人物がいた。
赤いカッターシャツに黒いズボン。そして、黒いエプロンというどこかのお店の制服のような服装。やはり男性なのか女性なのかわからない。
「あらあら。血が出てますよ」
その人はそう言いながら自分のおでこを指さす。
「服に血が付いたら大変ですから、絆創膏だけでも貼った方がいいですよ」
どこかの貴族かというような振る舞いで俺を立たせると、一番近くの曲がり角を曲がった。そこも裸電球がぶら下がるシャッター街だったが、場違いのように一ヶ所だけ灯りがを放っている場所がある。
近付くとそこが花屋であることは容易にわかった。お洒落な街中にでもありそうな、白をベースにした現代的な作りのお店で、LEDライトの眩しさは尋常ではない。
店の奥の方まで案内され、気が付けばパイプ椅子に座らされていた。
奥といっても広さはない。外を見なければ植物園の温室を思い出す。全ての花が今摘んできたかのように生き生きとしている。
明日の朝から営業する予定なら時間的に鮮度が失われてしまう気がしたが、まずこの量がここで売れるのかという疑問の方が大きかった。
ぼーっと店内を眺めてるうちに「ちょっとしみますよ」と着々と俺の額は修理されていく。
「このお店っていつもこの時間に空けてるんですか??」
世間話のように訊ねてみると「えぇ。ずっと昔から開店時間は午前零時からですよ」と笑顔で返された。
「よく潰れませんね」と口を滑らせた俺に「この店の花を必要としている人がいる限りは」とまた笑顔で返される。
「この店の花は不思議な花ばかりで、役目を果たすまで決して枯れないんですよ」
ちょっとこの人は頭がおかしいのかと思い始めた。
「あるべき場所へ。それを必要な人に渡すのが仕事なんですよ」
やっぱり頭がおかしい人だ。
心の中でそんな感想を述べていると、一本のチューリップを差し出された。
「今日の不幸は明日の幸せのための対価」
「花言葉ですか??」
「いいえ。貴方への言葉ですよ」
すべて知っていると言いたげに笑う店主は「お代は結構ですよ」といい強引にチューリップを持たされる。
ホラーとは違うが色んな意味で不気味だったので逃げるように店から離れた。
シャッター街を通り抜けるとさっきの出来事がどこか夢だったのではないかという気分に襲われる。それこそ狐にでも化かされたような感覚だ。そんな経験はないけど。
それでも自分の手には綺麗なチューリップが一輪あり、額には絆創膏が張られている。
気が付けば、いつの間にか酔いも嫌な気持ちも不安も消えていた。明日の朝一で店長に謝るか……そんなことを考えながら歩いていた俺の前に、今度は男性が転がり飛んできた。
「最低!!」という罵声と共に、一軒家の扉が大きな音を立てて締まる。男性は涙目で地面と一体化しようとしていたので、なんだかいたたまれなくなり声をかける。
なんでも結婚記念日には毎年一本の花を贈るという約束をしていたのに、従業員が辞めて仕事が忙しくうっかり忘れたそうだ。
「よければこれを」
さっきの『あるべき場所へ。それを必要な人に渡すのが仕事』という言葉が蘇り、俺は半ば強引に花を男性に手渡して、家に帰った。
翌日からその男性が新たな雇い主になるなんて、一切想像することさえなく……。