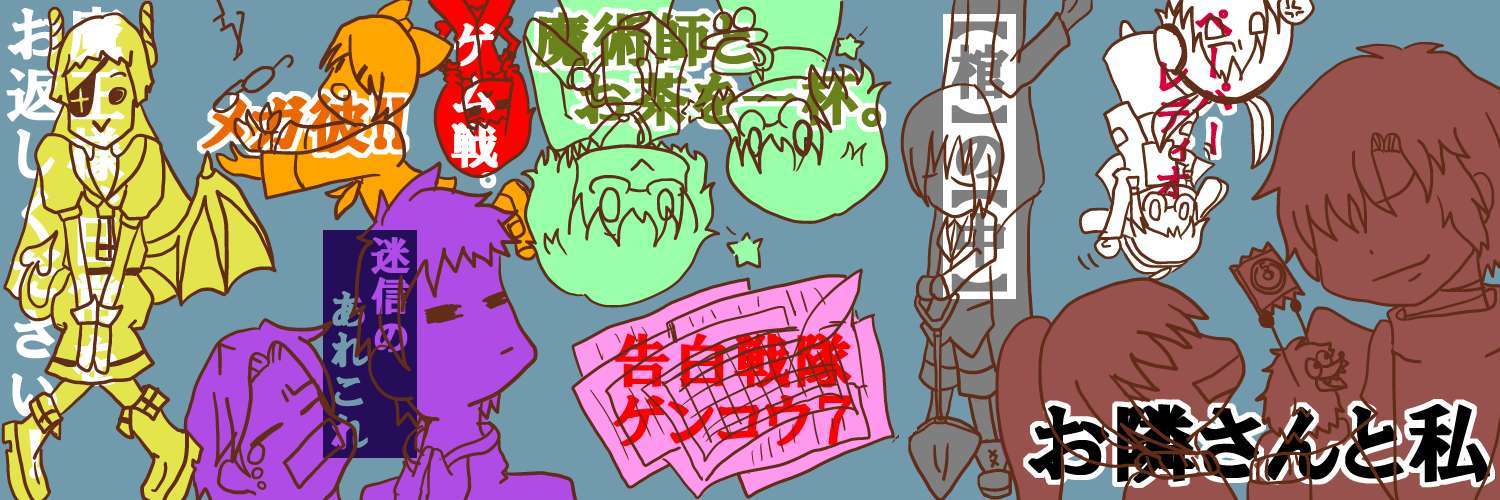七月の季節
【たった一度の願い】
「お前で最後にするって決めたんだ」と言ったアナタは本当に残酷な人だった――。
ありふれた台詞で『人生でたった一度でいい』というものがある。でも、快楽なんてものは一度知ってしまえばどんなものであれ過激になるばかりだ。
当時の私には好きな人がいた。誰もが呆れる程に愛してしまった。
その人もわたしのことを愛してくれているのか、とても大切にしてくれて、他人に傷付けられないようにいつも守ってくれたし、沢山の話をしてくれて自分の一部のように扱ってくれた。けど……
……同時にとても残酷だった。というのはワガママだろうか。
わたしが愛を伝える前から「お前を一番に選ぶことはできない」って抱きしめながら言っていたのだから。
それでも大切だからといっていつだって抱きしめてくれた。どんな感情の日でもわたしに触れ、抱きしめる。
わたしからはそんなことさせてくれないのに、硬い手でわたしを撫でるのだ。そうされると自分が酷く汚れていくのがわかったけれど、拒絶することなんてできなかった。
「来年には結婚すると思う」
口調と表情からわたしは自分でもうこの部屋に居られないのだと悟ったのは夏の始まり。祭り好きのアナタが一番好きな季節。
わたしはたった一度でいいからと、あとはなんでも言うことをきくからと、初めて願い事を口にした。
アナタがよく理想として語っていた浴衣デートというものをしたくて、お土産じゃなくてリンゴ飴と綿菓子を食べてみたくて、夜空に咲く本物の花火を見てみたかったのだ。
悩んだ挙句にアナタはわたしに浴衣を買ってくれて、でも自分はTシャツで、隣の県の夏祭りに行こうと言った事情は黙っておくことにした。
だって、わたしと一緒に祭りを楽しむ姿を知り合いに見られるわけにはいけないということくらいはどんなに馬鹿なわたしでもわかる。
なんでも器用にこなす人だったから浴衣の着付けも私なんかよりも何倍も上手くて、髪を結って、浴衣と一緒に買ったらしいお面をわたしにかぶせるととても嬉しそうに笑っていた。その笑顔が今でも忘れられない。
暗闇の小さな穴から見たその笑顔は、初めて出会った日を思い出した。
そしてアナタはあの日のようにわたしの手を引くと、夕立で他人の視界を遮るようにしてわたしを連れ出す。
外はこの家の玄関をくぐってからは初めてでとても怖かったけど、アナタの手の熱が大丈夫だと言い聞かせるようだと思った。
浴衣が汚れるから本当は嫌だったけれど、後部座席に隠れておくようにといわれ、上からかけられた毛布はこの季節にはあまりにも暑かったのをよく覚えてる。
高速に乗り、パーキングエリアでやっと助手席に座らせてくれた。ここに座るのもあの日以来でとても懐かしくなった。長かったような、短かったようなそんな年月。
自分の手を見て、随分汚れたものだと思ったけれど、嫌ではない。
次第に外が暗くなっていく。途中で道を何度か間違えたせいと、祭り会場は予想以上に混んでいたので、車を降りる頃には花火は始まっていた。
骨に響くような爆音が頭上からする。生まれて初めての本物の花火。
上を見て歩くものだから、アナタは自分の服のすそでも掴んでおけと手を引いたけど、繋いでくれなかったのは恋人を裏切りたくないという純粋さなのだろう。
一体どのくらいの時間花火を見ていたかわからない。すべてがあまりにもわたしには新鮮で、これ以上幸せな時間はもうないのではないかと思った。でも、同時に一度でいいと言ったことに後悔したのだ。
世界は素敵なものであふれているのではないかと――。
かき氷と箸巻きとリンゴ飴を買って二人で食べた。綿菓子だけは見つからなくてアナタは「残念だったな」とわたしの頭を撫でる。
わたしと同い年くらいの子が綿菓子を持って、両親に手を引かれているのをみて、自分の中でプツリと何かが音を立てて切れた気がした。
唐突に現実に引き戻される感覚。他の子みたいになりたくなかった。この人がいなくなったらどう生きれば良いのかわからない。それでも殺されたくなくなって、アナタを突き飛ばす。
涙が止まらなかったのは本当に好きだったし、家には帰りたくはなかったから。
たった一度でいい。死にたくなかった。イタイのはもう嫌だった。両親から付けられた傷がうずく。助けて欲しいと願った。生きたかった。
制服の警官を見つけてわたしは抱き着くように助けを求める。背後からはアナタが追ってきているのがわかったが、警官はしゃがんでわたしに身長をあわせ優しい顔でこういったのだ。
「その願いはもう使用されました」
アナタは放心するわたしを抱きかかえると、車に戻りトランクに投げ込む。抵抗する気なんて起きなかった。車の中で熱せられ続けていたシャベルの感覚はどこかアイロンに似ていて……締まる直前にアナタの後ろをホタルが舞ったのはこんなわたしへのせめてもの供養だったのだろうか。
「お前で最後にするって決めたんだ」と言ったアナタは本当に残酷な人だった――。
ありふれた台詞で『人生でたった一度でいい』というものがある。でも、快楽なんてものは一度知ってしまえばどんなものであれ過激になるばかりだ。
当時の私には好きな人がいた。誰もが呆れる程に愛してしまった。
その人もわたしのことを愛してくれているのか、とても大切にしてくれて、他人に傷付けられないようにいつも守ってくれたし、沢山の話をしてくれて自分の一部のように扱ってくれた。けど……
……同時にとても残酷だった。というのはワガママだろうか。
わたしが愛を伝える前から「お前を一番に選ぶことはできない」って抱きしめながら言っていたのだから。
それでも大切だからといっていつだって抱きしめてくれた。どんな感情の日でもわたしに触れ、抱きしめる。
わたしからはそんなことさせてくれないのに、硬い手でわたしを撫でるのだ。そうされると自分が酷く汚れていくのがわかったけれど、拒絶することなんてできなかった。
「来年には結婚すると思う」
口調と表情からわたしは自分でもうこの部屋に居られないのだと悟ったのは夏の始まり。祭り好きのアナタが一番好きな季節。
わたしはたった一度でいいからと、あとはなんでも言うことをきくからと、初めて願い事を口にした。
アナタがよく理想として語っていた浴衣デートというものをしたくて、お土産じゃなくてリンゴ飴と綿菓子を食べてみたくて、夜空に咲く本物の花火を見てみたかったのだ。
悩んだ挙句にアナタはわたしに浴衣を買ってくれて、でも自分はTシャツで、隣の県の夏祭りに行こうと言った事情は黙っておくことにした。
だって、わたしと一緒に祭りを楽しむ姿を知り合いに見られるわけにはいけないということくらいはどんなに馬鹿なわたしでもわかる。
なんでも器用にこなす人だったから浴衣の着付けも私なんかよりも何倍も上手くて、髪を結って、浴衣と一緒に買ったらしいお面をわたしにかぶせるととても嬉しそうに笑っていた。その笑顔が今でも忘れられない。
暗闇の小さな穴から見たその笑顔は、初めて出会った日を思い出した。
そしてアナタはあの日のようにわたしの手を引くと、夕立で他人の視界を遮るようにしてわたしを連れ出す。
外はこの家の玄関をくぐってからは初めてでとても怖かったけど、アナタの手の熱が大丈夫だと言い聞かせるようだと思った。
浴衣が汚れるから本当は嫌だったけれど、後部座席に隠れておくようにといわれ、上からかけられた毛布はこの季節にはあまりにも暑かったのをよく覚えてる。
高速に乗り、パーキングエリアでやっと助手席に座らせてくれた。ここに座るのもあの日以来でとても懐かしくなった。長かったような、短かったようなそんな年月。
自分の手を見て、随分汚れたものだと思ったけれど、嫌ではない。
次第に外が暗くなっていく。途中で道を何度か間違えたせいと、祭り会場は予想以上に混んでいたので、車を降りる頃には花火は始まっていた。
骨に響くような爆音が頭上からする。生まれて初めての本物の花火。
上を見て歩くものだから、アナタは自分の服のすそでも掴んでおけと手を引いたけど、繋いでくれなかったのは恋人を裏切りたくないという純粋さなのだろう。
一体どのくらいの時間花火を見ていたかわからない。すべてがあまりにもわたしには新鮮で、これ以上幸せな時間はもうないのではないかと思った。でも、同時に一度でいいと言ったことに後悔したのだ。
世界は素敵なものであふれているのではないかと――。
かき氷と箸巻きとリンゴ飴を買って二人で食べた。綿菓子だけは見つからなくてアナタは「残念だったな」とわたしの頭を撫でる。
わたしと同い年くらいの子が綿菓子を持って、両親に手を引かれているのをみて、自分の中でプツリと何かが音を立てて切れた気がした。
唐突に現実に引き戻される感覚。他の子みたいになりたくなかった。この人がいなくなったらどう生きれば良いのかわからない。それでも殺されたくなくなって、アナタを突き飛ばす。
涙が止まらなかったのは本当に好きだったし、家には帰りたくはなかったから。
たった一度でいい。死にたくなかった。イタイのはもう嫌だった。両親から付けられた傷がうずく。助けて欲しいと願った。生きたかった。
制服の警官を見つけてわたしは抱き着くように助けを求める。背後からはアナタが追ってきているのがわかったが、警官はしゃがんでわたしに身長をあわせ優しい顔でこういったのだ。
「その願いはもう使用されました」
アナタは放心するわたしを抱きかかえると、車に戻りトランクに投げ込む。抵抗する気なんて起きなかった。車の中で熱せられ続けていたシャベルの感覚はどこかアイロンに似ていて……締まる直前にアナタの後ろをホタルが舞ったのはこんなわたしへのせめてもの供養だったのだろうか。