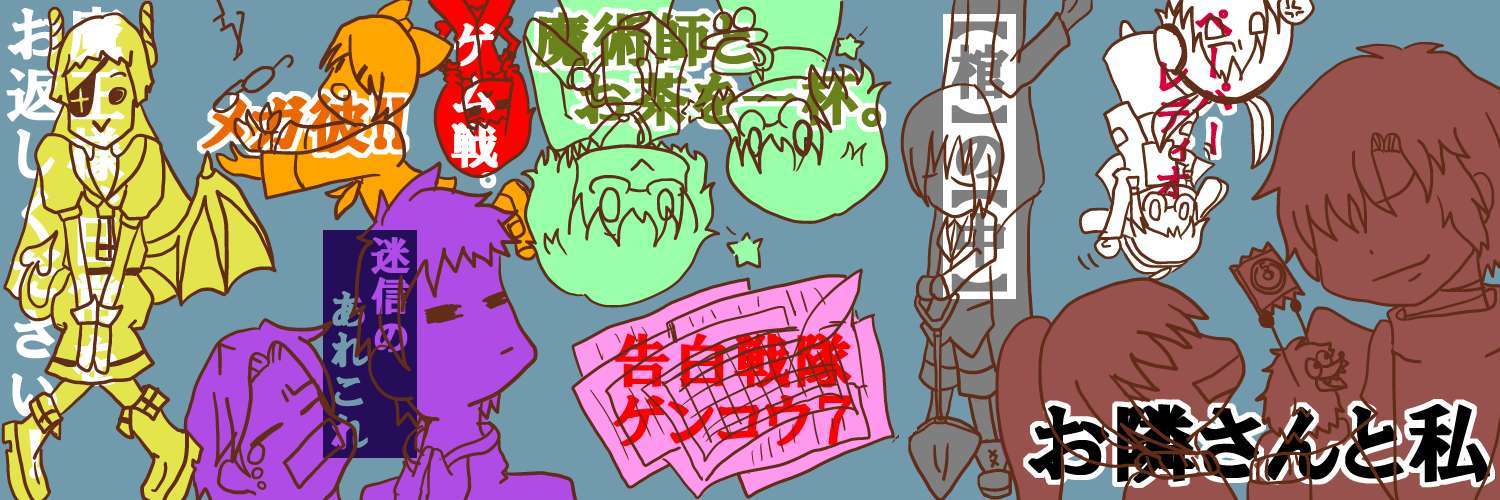七月の季節
【猫の瞳は何処へ往く】
家の近くに一匹の猫がいる。赤い首輪をつけた尻尾の長い、灰色の猫。いつも片目だけでぼくを見下ろす。
ぼくは勝手にその猫を「ミケ」という名前で呼んでいる。あまりにも小さい頃からそう呼んでいるので、何故ミケなのかは覚えていない。
ミケはぼくにさわられるのは嫌いらしく、他の人にはその艶やかな毛並みを触らせていてもぼくが近づけば手の届かない高いところへ上り、「みゃっ」と鳴いては片目で見下ろしてくる。
そんな訳で今日もぼくはミケにあしらわれながらも尻尾の先にでも触れられないかとブロック塀の前でジャンプを繰り返す。
「ミケー遊んでよー。暇なんだよー」
「みゃみゃっ」
安易に返事をするミケはちゃんと人間の言葉をわかっているらしい。
「ねぇー。煮干しあげるからさー」
もちろん、煮干しなんて持っていない。カバンを探る仕草をしてもぷいっと向こうを向く。言葉だけではなく嘘もわかるらしい。
「ミケー。ミケさーん。遊ぼうよー」
ジャンプするたびに制服のスカートがふわりと広がる。その裾をミケはチラリと片目で眺め「みゃー」と鳴く。
そういえば小さな頃からミケはずっと片目を閉じている。この辺りの猫はみんなミケには一目置いているようだけれど、やはりどこかで怪我をしたのか、産まれ付き悪いのかもしれない。
ミケがだらりと尻尾をおろしそっぽを向くので、立ち去る振りをして、走って戻りその尻尾の先に触れた瞬間だった。
驚き、振り向いたミケの両目は見開かれていて、昔も一度この目をぼくは見たことがある気がすると考えたいたのだが……暗転。
周囲が突然暗くなり、妙に体が軽い。男に間違われるほど短くカットしている髪は心なしか宙を舞い、地に足がついていないというような感じ。
目の前には、いつかテレビでいや、結構日常的に見ている青くきらめく星が浮かんでいた。力が抜け、座り込んだその砂地も見覚えがある。
ぼくは月面に座り込み地球を眺めていた。
言葉は失ったが、息はできているようで茫然と地球を眺めていると近くから「みゃっ」とこの状態には不釣り合いな鳴き声が響く。
振り返ったそこではミケが二本足で立ち、腕組みをしていた。余計に混乱して口を魚のようにパクパクさせることしかできなかったぼくにミケは鼻で笑うと低い声で一言こういった。
『暇だったんだろ??』
家の近くに一匹の猫がいる。赤い首輪をつけた尻尾の長い、灰色の猫。いつも片目だけでぼくを見下ろす。
ぼくは勝手にその猫を「ミケ」という名前で呼んでいる。あまりにも小さい頃からそう呼んでいるので、何故ミケなのかは覚えていない。
ミケはぼくにさわられるのは嫌いらしく、他の人にはその艶やかな毛並みを触らせていてもぼくが近づけば手の届かない高いところへ上り、「みゃっ」と鳴いては片目で見下ろしてくる。
そんな訳で今日もぼくはミケにあしらわれながらも尻尾の先にでも触れられないかとブロック塀の前でジャンプを繰り返す。
「ミケー遊んでよー。暇なんだよー」
「みゃみゃっ」
安易に返事をするミケはちゃんと人間の言葉をわかっているらしい。
「ねぇー。煮干しあげるからさー」
もちろん、煮干しなんて持っていない。カバンを探る仕草をしてもぷいっと向こうを向く。言葉だけではなく嘘もわかるらしい。
「ミケー。ミケさーん。遊ぼうよー」
ジャンプするたびに制服のスカートがふわりと広がる。その裾をミケはチラリと片目で眺め「みゃー」と鳴く。
そういえば小さな頃からミケはずっと片目を閉じている。この辺りの猫はみんなミケには一目置いているようだけれど、やはりどこかで怪我をしたのか、産まれ付き悪いのかもしれない。
ミケがだらりと尻尾をおろしそっぽを向くので、立ち去る振りをして、走って戻りその尻尾の先に触れた瞬間だった。
驚き、振り向いたミケの両目は見開かれていて、昔も一度この目をぼくは見たことがある気がすると考えたいたのだが……暗転。
周囲が突然暗くなり、妙に体が軽い。男に間違われるほど短くカットしている髪は心なしか宙を舞い、地に足がついていないというような感じ。
目の前には、いつかテレビでいや、結構日常的に見ている青くきらめく星が浮かんでいた。力が抜け、座り込んだその砂地も見覚えがある。
ぼくは月面に座り込み地球を眺めていた。
言葉は失ったが、息はできているようで茫然と地球を眺めていると近くから「みゃっ」とこの状態には不釣り合いな鳴き声が響く。
振り返ったそこではミケが二本足で立ち、腕組みをしていた。余計に混乱して口を魚のようにパクパクさせることしかできなかったぼくにミケは鼻で笑うと低い声で一言こういった。
『暇だったんだろ??』