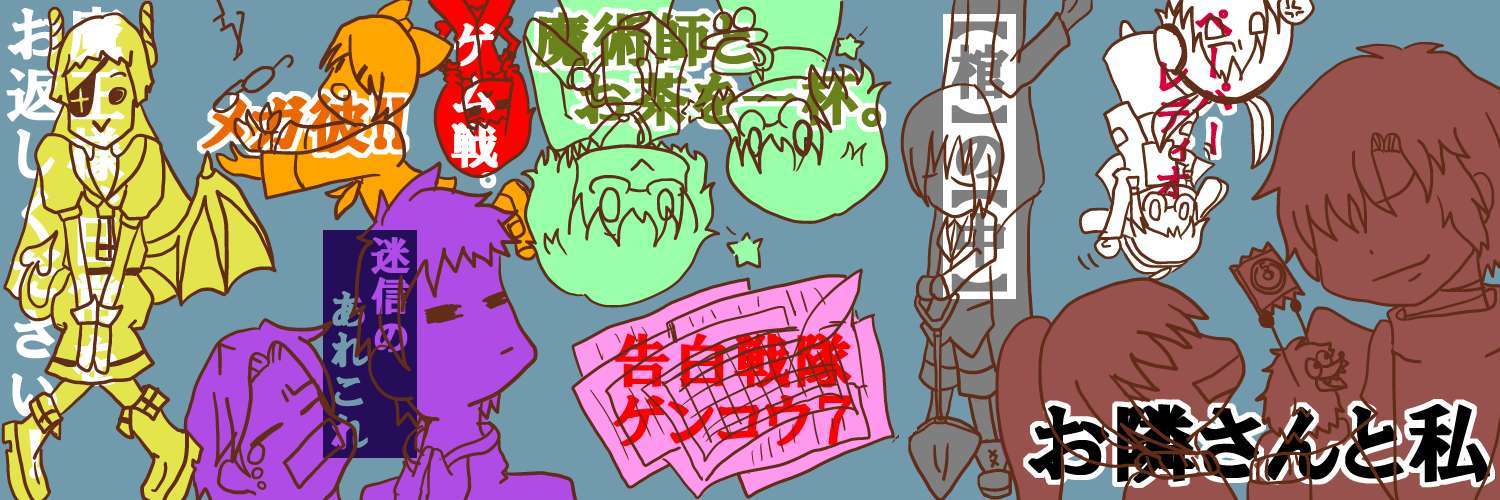七月の季節
【それは日常】
そう、それは誰かにとっては日常のただの地下鉄。でも初めてそこを訪れた私にとって迷宮と呼べるような異次元なのだ。
暗い線路のどこかには魔物が潜んでいて、人知れずに誰かを喰らっている。
他人に無関心なこの街だ。静かに誰かが消えたところで気付きもしない。
だって、ほら。一瞬電気が消えたうちに空席が出来てる。だけど、すぐに他の人がその席を埋めた。
そこに汚れがついていようと、誰も気にしない。何故そこが空席になったのかなど……。
暗い中で見るとわかる。車内のあちらこちらに異様な汚れが見られ、異臭も激しい。
それでも気にしないのはこれがこの人達にとっての日常だからなのだろう。
「私も毎日ここへ来るようになったら何も感じなくなってしまうのだろうか」
心の中でそんなことを呟きながら、吐き出されるように、押し出されるように革靴で歪なホームに踏み出す。
案内板を探している間にも、警笛が鳴り、次から次へと電車は発射してまた、滑り込んでくる。電車から吐き出される人達は私など見えていないかのようにぶつかってはどこかへ流されていった。
見えていないのはきっと私が異物だからなのだ。早くここを立ち去らねば。そう考えつつも、不意な好奇心が生温かい風と共に心に流れ込む。
一度、ベンチに腰掛け地下というには高すぎる天上を眺めながら私は願う。このまま私を非日常へといざなってくれる人物を。
立ち上がろうと手をかけたベンチの背にはベタリとした生温かいものが付着していて、私はその赤をジッと見つめた。
「気付いてしまったんだね、お嬢さん」
横に座っていたスーツの男が何かを言ったが、その言葉は滑り込む電車の音とイヤホンから流れる音楽でかき消される。
立ち上がった瞬間、生温かいものが鎖骨へと伝い落ちた。
私は自分の手に付着した赤色を都合よく手に入った布切れで拭くとゴミ箱に捨てる。
「その日常は知ってるんだ。連れ出してくれるならもっと強引でなければ」
イヤホンを外し、珍しくワックスで固めた髪を整え、一歩踏み出すと生温かい風と共に私のすぐ横を非日常が通過して行った。
そう、それは誰かにとっては日常のただの地下鉄。でも初めてそこを訪れた私にとって迷宮と呼べるような異次元なのだ。
暗い線路のどこかには魔物が潜んでいて、人知れずに誰かを喰らっている。
他人に無関心なこの街だ。静かに誰かが消えたところで気付きもしない。
だって、ほら。一瞬電気が消えたうちに空席が出来てる。だけど、すぐに他の人がその席を埋めた。
そこに汚れがついていようと、誰も気にしない。何故そこが空席になったのかなど……。
暗い中で見るとわかる。車内のあちらこちらに異様な汚れが見られ、異臭も激しい。
それでも気にしないのはこれがこの人達にとっての日常だからなのだろう。
「私も毎日ここへ来るようになったら何も感じなくなってしまうのだろうか」
心の中でそんなことを呟きながら、吐き出されるように、押し出されるように革靴で歪なホームに踏み出す。
案内板を探している間にも、警笛が鳴り、次から次へと電車は発射してまた、滑り込んでくる。電車から吐き出される人達は私など見えていないかのようにぶつかってはどこかへ流されていった。
見えていないのはきっと私が異物だからなのだ。早くここを立ち去らねば。そう考えつつも、不意な好奇心が生温かい風と共に心に流れ込む。
一度、ベンチに腰掛け地下というには高すぎる天上を眺めながら私は願う。このまま私を非日常へといざなってくれる人物を。
立ち上がろうと手をかけたベンチの背にはベタリとした生温かいものが付着していて、私はその赤をジッと見つめた。
「気付いてしまったんだね、お嬢さん」
横に座っていたスーツの男が何かを言ったが、その言葉は滑り込む電車の音とイヤホンから流れる音楽でかき消される。
立ち上がった瞬間、生温かいものが鎖骨へと伝い落ちた。
私は自分の手に付着した赤色を都合よく手に入った布切れで拭くとゴミ箱に捨てる。
「その日常は知ってるんだ。連れ出してくれるならもっと強引でなければ」
イヤホンを外し、珍しくワックスで固めた髪を整え、一歩踏み出すと生温かい風と共に私のすぐ横を非日常が通過して行った。