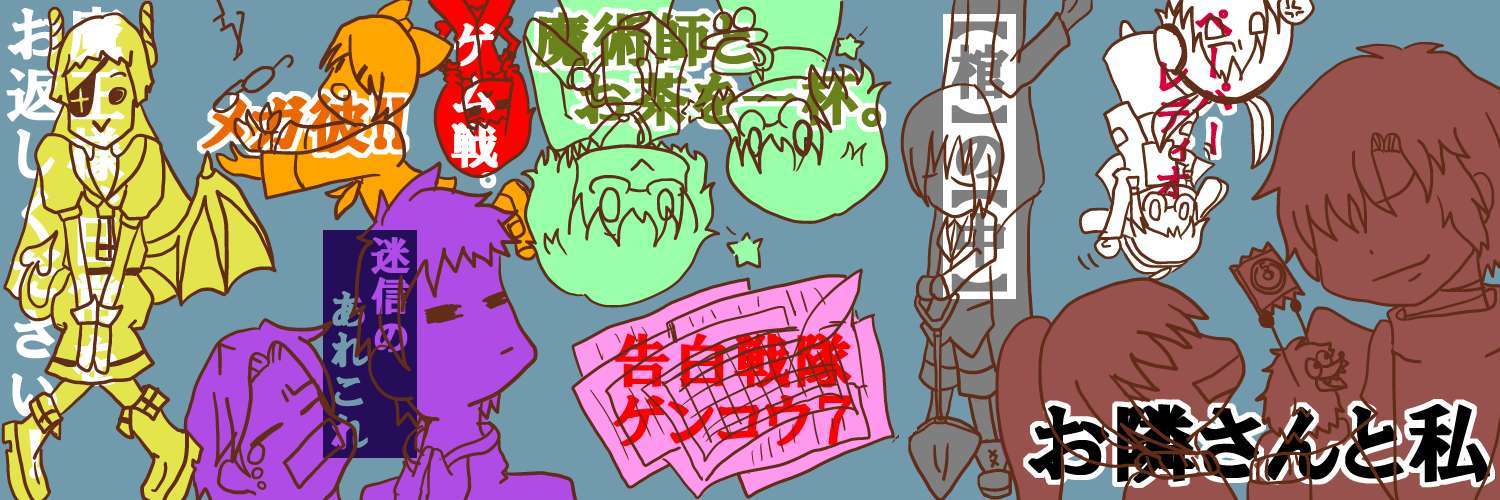七月の季節
【忘れられない思い出】
これはまだ俺が一人称を僕と言っていた頃の思い出。街に街頭は少なく、夜は真っ暗で祖父もまだ若く、黒い髪が残っていた。
当時、祖父の家に行くときは高速を使い、祖父が迎えに来てくれたのは嬉しくて、後部座席で舌を出したキツネのヌイグルミを膝にのせて暗くなっていく外を見るのだ。
そしてあれは冬だったと思う。嫌だというのに母に無理矢理、毛糸のセーターを着せられたから。
車の暖房が壊れたという理由だったか、普段は立ち寄らないサービスエリアに立ち寄ったのが思い出の始まり。
サービスエリアは当時でも明るめだったけれど、そこには小高い丘があり、近くの街を一望できるようだった。
祖父は夜景を見せてやろうといい、俺の手を引き丘を登っていく。暗闇が広がっていたが、数人の話声、特に子供の声が聞こえてくる。
思い出のキーパーソンはその丘で望遠鏡を調節していた。とても立派な望遠鏡。
真っ白な髪の祖父よりも歳をとっていたその老人は「あったあった」と笑うと、周りの子供達に「動かしちゃいかんぞ」と言い望遠鏡を覗かしていた。
「何が見えるんですか??」
先に声をかけたのは祖父。俺は隠れるようにその老人と見慣れない望遠鏡というものを見つめる。
「土星ですよ。輪まで綺麗にみえるんです。見てみますか??」
会話をしている間にも子供達は大喜びで、奪い合うように望遠鏡を覗きこんでいた。
「ほら、坊やも覗いてごらん」
老人にうなされ、そっと望遠鏡を覗くと肉眼で空を見上げても何もないのに図鑑で見たのとそっくりな土星がそこには映し出されていたのだ。
それまで感じたことのない感動というような感情がこみ上げ、俺はその年のクリスマスに望遠鏡をお願いした。
筒を覗くと、肉眼ではとらえられない様々なものが見えるその感動は何度繰り返しても忘れられなく、双眼鏡に顕微鏡と俺の部屋はそういった筒であふれることになる。
中毒と呼べるほどに筒を通して見える世界にハマった俺はできるだけ長く、その世界が見える職業につきたいと願い、叶えた。そんな俺の職業は狙撃手。
世界でも指折りと言われる腕前だ。スコープを覗くと今でも時折思い出す。あの日見た、打ち抜いたように見事な土星の姿を。
あの老人は今でも夜になれば空を覗き込んでいるのだろうか……。
……小さな少女が親の手を振りほどきパーキングエリアの中の丘を昇る。雲一つない青空に少女の笑顔がきらめく。
「おっきなぼうえんきょう!!」
少女は丘の上で昼間だというのに望遠鏡を調節する白髪の老人を見て声をあげる。
「お嬢ちゃん、覗いてみるかい??」
老人の言葉に少女は望遠鏡に駆け寄り、その筒を覗いた。
「うわぁー!! あたしこれ知ってる!! 土星でしょ!?」
これはまだ俺が一人称を僕と言っていた頃の思い出。街に街頭は少なく、夜は真っ暗で祖父もまだ若く、黒い髪が残っていた。
当時、祖父の家に行くときは高速を使い、祖父が迎えに来てくれたのは嬉しくて、後部座席で舌を出したキツネのヌイグルミを膝にのせて暗くなっていく外を見るのだ。
そしてあれは冬だったと思う。嫌だというのに母に無理矢理、毛糸のセーターを着せられたから。
車の暖房が壊れたという理由だったか、普段は立ち寄らないサービスエリアに立ち寄ったのが思い出の始まり。
サービスエリアは当時でも明るめだったけれど、そこには小高い丘があり、近くの街を一望できるようだった。
祖父は夜景を見せてやろうといい、俺の手を引き丘を登っていく。暗闇が広がっていたが、数人の話声、特に子供の声が聞こえてくる。
思い出のキーパーソンはその丘で望遠鏡を調節していた。とても立派な望遠鏡。
真っ白な髪の祖父よりも歳をとっていたその老人は「あったあった」と笑うと、周りの子供達に「動かしちゃいかんぞ」と言い望遠鏡を覗かしていた。
「何が見えるんですか??」
先に声をかけたのは祖父。俺は隠れるようにその老人と見慣れない望遠鏡というものを見つめる。
「土星ですよ。輪まで綺麗にみえるんです。見てみますか??」
会話をしている間にも子供達は大喜びで、奪い合うように望遠鏡を覗きこんでいた。
「ほら、坊やも覗いてごらん」
老人にうなされ、そっと望遠鏡を覗くと肉眼で空を見上げても何もないのに図鑑で見たのとそっくりな土星がそこには映し出されていたのだ。
それまで感じたことのない感動というような感情がこみ上げ、俺はその年のクリスマスに望遠鏡をお願いした。
筒を覗くと、肉眼ではとらえられない様々なものが見えるその感動は何度繰り返しても忘れられなく、双眼鏡に顕微鏡と俺の部屋はそういった筒であふれることになる。
中毒と呼べるほどに筒を通して見える世界にハマった俺はできるだけ長く、その世界が見える職業につきたいと願い、叶えた。そんな俺の職業は狙撃手。
世界でも指折りと言われる腕前だ。スコープを覗くと今でも時折思い出す。あの日見た、打ち抜いたように見事な土星の姿を。
あの老人は今でも夜になれば空を覗き込んでいるのだろうか……。
……小さな少女が親の手を振りほどきパーキングエリアの中の丘を昇る。雲一つない青空に少女の笑顔がきらめく。
「おっきなぼうえんきょう!!」
少女は丘の上で昼間だというのに望遠鏡を調節する白髪の老人を見て声をあげる。
「お嬢ちゃん、覗いてみるかい??」
老人の言葉に少女は望遠鏡に駆け寄り、その筒を覗いた。
「うわぁー!! あたしこれ知ってる!! 土星でしょ!?」