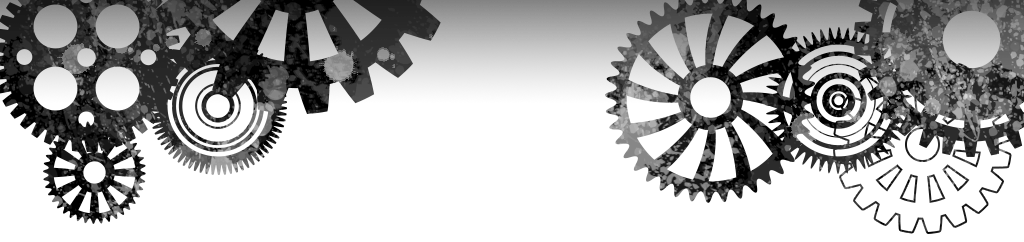傭兵
名前
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
暗い割にかつて人のいた形跡がそこここに残る寂れ村は、捕えられた時の恐怖や不気味さもまた格別だった。
特に邪悪な笑みを浮かべた道化師が、その武器でロケットチェアを小突いてくる時は。
仲間のうち2人は既に脱出済み、もう1人もゲート傍に居たから直に脱出するだろう。
ナワーブは身動ぎもせず、これ以上苦しまずに早く荘園に戻れることだけを願っていた。
「先陣切ってチェイスしていた割に捕まった感想はどうだよ、緑の子猫ちゃん?」
「最高にハイ!ってやつだぜ、クソピエロ」
忌々しさを隠そうともせず、精一杯の憎まれ口を返す。
それにしてもおかしい。
通常他サバイバーがいなくなれば拘束された者は即座に打ち上がるはずだが、その様子はない。
答えはハンターの背後から走ってきた。
「こっち向けジョーカァァァ!!」
「ーっ痛ってぇぇぇぇぇぇぇぇ!!」
残っていた最後の一人、オルガレーノが投げつけた特殊警棒が振り向きざまに膝を直撃し、叫びながら屈み込むピエロ。
「馬鹿野郎ッ!!」
なんで逃げなかった、という言葉より早く拘束を解き終えた手に引かれ、そのままゲートへ走り出す。
言わずともナワーブの意思は伝わっていたようで、オルガレーノは答えた。
「分かってるよ!でも置いていけなかった…
表には、出さないだろうけど…きっと怖くて苦しいのは、一緒だと思ったから!」
息切れしながら、それでもオルガレーノは律儀に応える。
守る者でいるには、守られる者からの全幅の信頼が必須だ。
本当にこの者に頼っていいか?
寄りかかっても折れずいてくれるか?
その期待に応えられなければならない。
この殺伐とした状況下で、ナワーブの傭兵という役職は信頼を得るには充分過ぎた。
銃弾と剣戟の降り注ぐ死線から離れる為に傭兵を辞めたはずなのに、結局また最前線で体を張っている。
本来気が優しい性分の彼にとって、それは守れることへの矜恃と共に、戦うことへの恐怖を抱えることでもあった。
「ナワーブが抱えてきたプレッシャーを、簡単にわかるなんて言えない。
それでも分かりたいとは思っているよ。
だから…あなたが抱えているもの、私にも分けて欲しい」
葛藤を表に出せなかったナワーブに、この言葉がどれほど救いになったか、彼自身にも計り知れなかった。
客観的に見ればお互い負傷して、ゲートまでたどり着けるかギリギリの状態。
なのに何故か口角が上がるのを抑えられない。
隣に誰かがいてくれるのは、こんなにも温かくて勇気の出ることだったのか。
ナワーブは救助された後からずっとオルガレーノと手を繋いだままでいたのを思い出した。
思い出して、この温かい手が離しがたくて、一層強く握り直して出口を走り抜けた。
* * *
二人とも息が上がってしまい、しばらく地面に座り込んでいた。
ゼェゼェ息切れしながら胡座をかいた足に自身の手を置いて上半身を支えるオルガレーノ。
「レノ」
不意に名前を呼ばれ、何事かと振り向く…前にぐいっと引き寄せられた。
肩甲骨の辺りでドクドクと波打つ鼓動と、肩越しにまわされた腕。
オルガレーノが後ろから抱きしめられたのだと気づくのに数秒要した。
「少しだけ…このままいさせてくれ」
左肩に顎を預けながら呟かれた声は静かで、それでいて懇願するような切実さがあった。
オルガレーノはといえば、彼のただならぬ様子に言葉を返せずにいる。
言葉の代わりに、回された腕にそっと手を添えた。
ナワーブはどちらかと言えばさほど口数の多くない方だ。
話しかけられた、もしくは何か用件があれば普通に会話もするが、さり気なく周りに壁をつくる、そんなタイプ。
そんな彼が近しい距離に寄ってくるに留まらず、こんな大胆に接触してきたことに少なからず困惑した。
かといって無下にもできず、なにより回された腕の熱が不思議と心地よかった。
「さっき…ありがとうな」
どれくらいそうしていただろうか、沈黙を破ったのはナワーブの方だった。
先程より幾分か落ち着いた声。
「嬉しかったよ、まさか俺が人に守られるなんて思わなかった」
そこで一旦言葉を区切る。小さくすぅっ、と息を吸い込む音がする。
「お前に何かあった時は…必ず俺が助けに行く」
耳に吐息がかかるほど近距離で囁くものだから、落ち着きかけていた脈拍がまた急上昇した。
顔面に全身の血が集まっているんじゃなかろうか。
抱きしめられた時とは別の理由で言葉を返さずにいると、耳元でふっ、と笑う声がした。
「…照れてるのか?」
「っからかったな!!」
図星を刺されたのが恥ずかしさに拍車をかけ、怒りながらナワーブの方を振り返れば彼も熟れた林檎のように赤い顔をしていた。
「ナワーブ、顔真っ赤」
「…人の事言えた面かよ」
一瞬おいて響く二人分の笑い声。
ナワーブがこんなふうに笑うのを初めて見たような気がする。
一頻り笑うと、よっこらせっと掛け声を掛けてナワーブが立ち上がる。
「ん」
差し伸べられた手を、続けて差し伸べた本人の顔を見上げる。
その手を取ってオルガレーノも立ち上がった。
ゲームで脱出してきた時と同じように、しかし今度は互いの明確な意思で手を繋いだまま、荘園への帰途へ着いた。
特に邪悪な笑みを浮かべた道化師が、その武器でロケットチェアを小突いてくる時は。
仲間のうち2人は既に脱出済み、もう1人もゲート傍に居たから直に脱出するだろう。
ナワーブは身動ぎもせず、これ以上苦しまずに早く荘園に戻れることだけを願っていた。
「先陣切ってチェイスしていた割に捕まった感想はどうだよ、緑の子猫ちゃん?」
「最高にハイ!ってやつだぜ、クソピエロ」
忌々しさを隠そうともせず、精一杯の憎まれ口を返す。
それにしてもおかしい。
通常他サバイバーがいなくなれば拘束された者は即座に打ち上がるはずだが、その様子はない。
答えはハンターの背後から走ってきた。
「こっち向けジョーカァァァ!!」
「ーっ痛ってぇぇぇぇぇぇぇぇ!!」
残っていた最後の一人、オルガレーノが投げつけた特殊警棒が振り向きざまに膝を直撃し、叫びながら屈み込むピエロ。
「馬鹿野郎ッ!!」
なんで逃げなかった、という言葉より早く拘束を解き終えた手に引かれ、そのままゲートへ走り出す。
言わずともナワーブの意思は伝わっていたようで、オルガレーノは答えた。
「分かってるよ!でも置いていけなかった…
表には、出さないだろうけど…きっと怖くて苦しいのは、一緒だと思ったから!」
息切れしながら、それでもオルガレーノは律儀に応える。
守る者でいるには、守られる者からの全幅の信頼が必須だ。
本当にこの者に頼っていいか?
寄りかかっても折れずいてくれるか?
その期待に応えられなければならない。
この殺伐とした状況下で、ナワーブの傭兵という役職は信頼を得るには充分過ぎた。
銃弾と剣戟の降り注ぐ死線から離れる為に傭兵を辞めたはずなのに、結局また最前線で体を張っている。
本来気が優しい性分の彼にとって、それは守れることへの矜恃と共に、戦うことへの恐怖を抱えることでもあった。
「ナワーブが抱えてきたプレッシャーを、簡単にわかるなんて言えない。
それでも分かりたいとは思っているよ。
だから…あなたが抱えているもの、私にも分けて欲しい」
葛藤を表に出せなかったナワーブに、この言葉がどれほど救いになったか、彼自身にも計り知れなかった。
客観的に見ればお互い負傷して、ゲートまでたどり着けるかギリギリの状態。
なのに何故か口角が上がるのを抑えられない。
隣に誰かがいてくれるのは、こんなにも温かくて勇気の出ることだったのか。
ナワーブは救助された後からずっとオルガレーノと手を繋いだままでいたのを思い出した。
思い出して、この温かい手が離しがたくて、一層強く握り直して出口を走り抜けた。
* * *
二人とも息が上がってしまい、しばらく地面に座り込んでいた。
ゼェゼェ息切れしながら胡座をかいた足に自身の手を置いて上半身を支えるオルガレーノ。
「レノ」
不意に名前を呼ばれ、何事かと振り向く…前にぐいっと引き寄せられた。
肩甲骨の辺りでドクドクと波打つ鼓動と、肩越しにまわされた腕。
オルガレーノが後ろから抱きしめられたのだと気づくのに数秒要した。
「少しだけ…このままいさせてくれ」
左肩に顎を預けながら呟かれた声は静かで、それでいて懇願するような切実さがあった。
オルガレーノはといえば、彼のただならぬ様子に言葉を返せずにいる。
言葉の代わりに、回された腕にそっと手を添えた。
ナワーブはどちらかと言えばさほど口数の多くない方だ。
話しかけられた、もしくは何か用件があれば普通に会話もするが、さり気なく周りに壁をつくる、そんなタイプ。
そんな彼が近しい距離に寄ってくるに留まらず、こんな大胆に接触してきたことに少なからず困惑した。
かといって無下にもできず、なにより回された腕の熱が不思議と心地よかった。
「さっき…ありがとうな」
どれくらいそうしていただろうか、沈黙を破ったのはナワーブの方だった。
先程より幾分か落ち着いた声。
「嬉しかったよ、まさか俺が人に守られるなんて思わなかった」
そこで一旦言葉を区切る。小さくすぅっ、と息を吸い込む音がする。
「お前に何かあった時は…必ず俺が助けに行く」
耳に吐息がかかるほど近距離で囁くものだから、落ち着きかけていた脈拍がまた急上昇した。
顔面に全身の血が集まっているんじゃなかろうか。
抱きしめられた時とは別の理由で言葉を返さずにいると、耳元でふっ、と笑う声がした。
「…照れてるのか?」
「っからかったな!!」
図星を刺されたのが恥ずかしさに拍車をかけ、怒りながらナワーブの方を振り返れば彼も熟れた林檎のように赤い顔をしていた。
「ナワーブ、顔真っ赤」
「…人の事言えた面かよ」
一瞬おいて響く二人分の笑い声。
ナワーブがこんなふうに笑うのを初めて見たような気がする。
一頻り笑うと、よっこらせっと掛け声を掛けてナワーブが立ち上がる。
「ん」
差し伸べられた手を、続けて差し伸べた本人の顔を見上げる。
その手を取ってオルガレーノも立ち上がった。
ゲームで脱出してきた時と同じように、しかし今度は互いの明確な意思で手を繋いだまま、荘園への帰途へ着いた。
2/2ページ