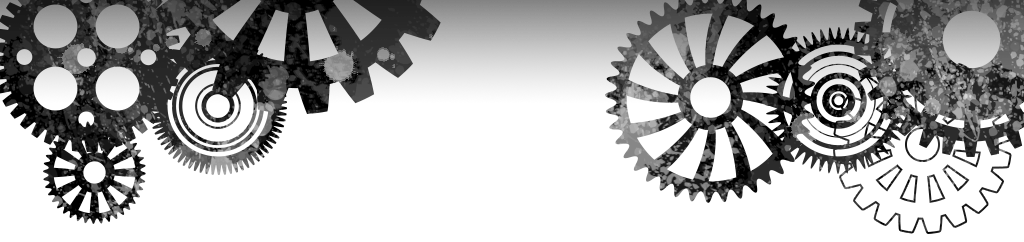納棺師
名前
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「貴女はいつもボロボロですね」
「ははっ、返す言葉もない…」
左脛から膝にかけて、背中、右前頭部の打撲、右肩から右腕の擦過傷…オルガレーノが本日のゲームで負った怪我のお品書きだ。
エミリーの治療の後、納棺救助してくれたイソップにお礼がてら雑談しに彼の部屋を訪れていた。
雑談と言ってもオルガレーノが話しかけて、それに黙々と道具のメンテナンスに勤しみながらイソップが答える、という流れが常だ。
イソップは用件がない限り、自発的に話しかけてこない。
「カールさんは、死者に向き合う時、死者に対してどんなことを思っているの?」
「労い…でしょうか。どんな形であれ、命を全うしたのだから、せめて穏やかに送り出したいです。」
嘆きや悲しみではなく、労り。
なぜとは言い難いが、なんとなく彼らしい考え方だなと思った。
「なら…もしも私が死んだら、労ってくれる?」
「さぁ…想像がつかないのでなんとも」
「そうなの?それは意外」
常に死に向き合い続けてきた彼のことだ、仲間が死んだ時のことくらい常に想定しているのかと思っていただけに、この回答は予想外だった。
「死なせませんから」
彼の能力、死者蘇生。その能力で救ってみせるということか。
彼にしては力強く言い切ったことに意外さを感じたが、それなら納得がいく。
「気持ちは嬉しいよ…でもこんな環境じゃ、いつ死んだって「分かってます、そんなのっ!」
いつ死んだっておかしくない。そう言い切ることは叶わなかった。
これまで淀みなく流れていた手を止め、激昂したイソップに遮られたのだ。
そしてオルガレーノの方を向くや否や、ツカツカと詰め寄り両肩を掴んで押さえつける。
咄嗟に避けも止めもできず、オルガレーノはイソップ諸共ベッドに倒れ込んだ。
静かになった部屋に、古いスプリングの軋む音が響く。
「分かってますよ…それでも、貴女の口から、そんなこと聞きたくないっ」
突然のことに呆気に取られているオルガレーノを他所に、イソップは続ける。
「…どんなにみっともなくても、とにかく生きてっ…貴女がもし死にそうになったら…僕は、何度でも、貴女を連れ戻します。だから、死ぬなんて…考えないでっ…」
息を切らして鬼気迫る表情で押し倒したのに、イソップは今にも泣き崩れそうに顔をしていた。
「…ごめんね、もう二度とこんなこと言わないよ」
イソップは感情表現や言葉選びが独特な部分がある。
顔色一つ使えずにサラリととんでもないことを言ったかと思えば、こんな風に突然感情を剥き出しにする。
死に向き合い続けてきたからこそ、安易な死への「たられば」を受け入れられない彼の苦しみに触れてしまったのだろう。
どうすれば彼の昂った感情を抑えられるかと、イソップの背中に手を添えてポンポンと撫でて宥めてみる。
すると彼はマスクをずらしてオルガレーノの頬に自分の頬を当て、擦り寄せてきた。
「グラウカさん…温かい」
意外と体温の高い、スベスベした頬が柔らかくて気持ちいい。
今度はゆっくり頬を離し、オルガレーノを鼻と鼻が付きそうな距離で見つめ…そのまま口付けた。
「んっ…」
やや強めに押し付けるように唇を合わせられれば、その薄さと柔らかさを意識してしまう。
イソップが若干頭を引くと、今度は間髪入れず下唇を啄まれる。
湿り気のある弾力に挟まれて、我に返ったオルガレーノが止めようとする前に、イソップの方が先に身を起こした。
「ちょっと、ちゃっかり何してるのさ…」
「生きているうちじゃなきゃ、出来ませんから」
「…物は言いようだね」
真顔でサラリと恥ずかしいことを言ってのける、いつものイソップに戻っている。
傷は痛むが、上に乗るこの体温は不思議と心地いい。
イソップのことは猫のようだと思っていたが、実は犬の方が合っているのかもしれない。
彼は命を見張る番犬で、役割を終えた命を穏やかに送り出し、まだ役割を残す命を連れ戻す。
(この温もりが続くのなら、苦しくても、みっともなくても、もがき続けてみようかな)
未だに怪我人の身体に乗り続ける、不器用な白い番犬の頭をそっと撫でて、今度はオルガレーノから触れるだけのキスを返した。
「ははっ、返す言葉もない…」
左脛から膝にかけて、背中、右前頭部の打撲、右肩から右腕の擦過傷…オルガレーノが本日のゲームで負った怪我のお品書きだ。
エミリーの治療の後、納棺救助してくれたイソップにお礼がてら雑談しに彼の部屋を訪れていた。
雑談と言ってもオルガレーノが話しかけて、それに黙々と道具のメンテナンスに勤しみながらイソップが答える、という流れが常だ。
イソップは用件がない限り、自発的に話しかけてこない。
「カールさんは、死者に向き合う時、死者に対してどんなことを思っているの?」
「労い…でしょうか。どんな形であれ、命を全うしたのだから、せめて穏やかに送り出したいです。」
嘆きや悲しみではなく、労り。
なぜとは言い難いが、なんとなく彼らしい考え方だなと思った。
「なら…もしも私が死んだら、労ってくれる?」
「さぁ…想像がつかないのでなんとも」
「そうなの?それは意外」
常に死に向き合い続けてきた彼のことだ、仲間が死んだ時のことくらい常に想定しているのかと思っていただけに、この回答は予想外だった。
「死なせませんから」
彼の能力、死者蘇生。その能力で救ってみせるということか。
彼にしては力強く言い切ったことに意外さを感じたが、それなら納得がいく。
「気持ちは嬉しいよ…でもこんな環境じゃ、いつ死んだって「分かってます、そんなのっ!」
いつ死んだっておかしくない。そう言い切ることは叶わなかった。
これまで淀みなく流れていた手を止め、激昂したイソップに遮られたのだ。
そしてオルガレーノの方を向くや否や、ツカツカと詰め寄り両肩を掴んで押さえつける。
咄嗟に避けも止めもできず、オルガレーノはイソップ諸共ベッドに倒れ込んだ。
静かになった部屋に、古いスプリングの軋む音が響く。
「分かってますよ…それでも、貴女の口から、そんなこと聞きたくないっ」
突然のことに呆気に取られているオルガレーノを他所に、イソップは続ける。
「…どんなにみっともなくても、とにかく生きてっ…貴女がもし死にそうになったら…僕は、何度でも、貴女を連れ戻します。だから、死ぬなんて…考えないでっ…」
息を切らして鬼気迫る表情で押し倒したのに、イソップは今にも泣き崩れそうに顔をしていた。
「…ごめんね、もう二度とこんなこと言わないよ」
イソップは感情表現や言葉選びが独特な部分がある。
顔色一つ使えずにサラリととんでもないことを言ったかと思えば、こんな風に突然感情を剥き出しにする。
死に向き合い続けてきたからこそ、安易な死への「たられば」を受け入れられない彼の苦しみに触れてしまったのだろう。
どうすれば彼の昂った感情を抑えられるかと、イソップの背中に手を添えてポンポンと撫でて宥めてみる。
すると彼はマスクをずらしてオルガレーノの頬に自分の頬を当て、擦り寄せてきた。
「グラウカさん…温かい」
意外と体温の高い、スベスベした頬が柔らかくて気持ちいい。
今度はゆっくり頬を離し、オルガレーノを鼻と鼻が付きそうな距離で見つめ…そのまま口付けた。
「んっ…」
やや強めに押し付けるように唇を合わせられれば、その薄さと柔らかさを意識してしまう。
イソップが若干頭を引くと、今度は間髪入れず下唇を啄まれる。
湿り気のある弾力に挟まれて、我に返ったオルガレーノが止めようとする前に、イソップの方が先に身を起こした。
「ちょっと、ちゃっかり何してるのさ…」
「生きているうちじゃなきゃ、出来ませんから」
「…物は言いようだね」
真顔でサラリと恥ずかしいことを言ってのける、いつものイソップに戻っている。
傷は痛むが、上に乗るこの体温は不思議と心地いい。
イソップのことは猫のようだと思っていたが、実は犬の方が合っているのかもしれない。
彼は命を見張る番犬で、役割を終えた命を穏やかに送り出し、まだ役割を残す命を連れ戻す。
(この温もりが続くのなら、苦しくても、みっともなくても、もがき続けてみようかな)
未だに怪我人の身体に乗り続ける、不器用な白い番犬の頭をそっと撫でて、今度はオルガレーノから触れるだけのキスを返した。
1/2ページ