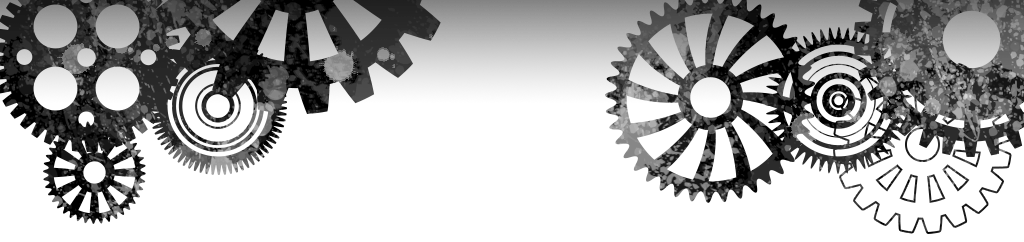障子
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「玖珠理は、どんなタイプが好きとか、
好きな人とか……そういうのはあるのか」
「はい?」
あまりにも唐突で、しかもおよそこの手の話題に積極的に踏み入らなさそうな相手から振られたものだから思わず聞き返してしまった。まさかこんな流れで「あなたが好きです」と言える訳もなく。何とか話題を逸らせないものか……
「また随分藪から棒に……障子もそういうの興味あるんだね」
「最近女子がよくその手の話をしているのを耳にして、玖珠理はどうなのかと思ってな」
確かに芦戸や葉隠あたりは恋バナが大好きだ。よくその手の話題──主に障子絡みのこと──をつつかれるし、私は私でのらりくらりとそれを躱している。
「で、どうなんだ?」とご丁寧に複製腕で目を増やして覗き込まれると、言い逃れるのも苦しい。
「うーん……まぁ、話しやすくて、一緒にいて落ち着く人かな」
「……そうか」
核心には触れず、でも嘘はついていない。お願いだからこれで引き下がって欲しい。
「そういう障子はどうなの?」
「俺は……」
先程追求してきた勢いはどこへやら、急に口篭る。複製腕も引っ込んだ。まさか聞き返されるとは思ってなかったんだろうか?
まぁこちらも社交辞令で聞き返しただけなので流してくれて構わないんだけど。むしろそうして欲しい、聞くのが怖い。
寡黙だがはっきりものを言う障子には珍しく目線を泳がせている。こんなの「好きな人がいる」と言っているようなものだ。
「……この人だ」
そういって差し出されたのは彼のスマホ。まさか写真出してくる気?いよいよ残酷過ぎない?そして相手のこと好き過ぎんか??
もの凄く気になるけどもの凄く見たくない、でもここで自然に断る口実もない。
スマホを受け取るまでの数秒。腹を括って、リアクションのシミュレーションまでして、半ばやけくそで液晶画面を覗き込む。
「あーわかる。確かに可愛いもんね」
「えっ意外!あんまり接点ないイメージ……さては障子、本命には奥手なタイプ?」
さてどのパターンを引き出すかと意気込んだ結果、そのどれも不発で終わってしまった。
そこにいたのは眉間に皺を寄せ、なんとも言えない表情の見慣れた顔───インカメに写った自分だったからだ。
「なっ、なーんだもうびっくりした!!障子もこういうイタズラするんだね!!」
人の覚悟を返してくれ!!と叫びたい気持ちを必死に押し込めて、作り笑いしながらスマホを返す。
しかし当の持ち主はそれを受け取ろうとせず、ただ真っ直ぐ私の目を見つめていた。
「しょ、うじ?」
「そういう、ことだ」
そういうことってどういうこと?いやたぶん、意味はわかったんだけど。
障子なりのボケだったりしない?私のイタい勘違いだったりしない?───そんなこと聞き返せないくらい、障子の目は真剣で。
いやいやいや、待ってよ。待ってってば。
「そ、れって……」
ダメだ心臓がバクバクして苦しくなってきた。顔に熱が籠って考えがまとまらない。
こちらのキャパオーバーを知ってか知らずか、フーっと息を吐き出してから障子が口を開いた。
「すまない、つい回りくどい言い方をしてしまった。……玖珠理が好きだ」
障子とはクラスの中でもそこそこ付き合いがある方だと自負しているが、私から見ても彼はいつも冷静で、動揺は愚か声を上げて笑うところすらほぼ見た事がない。ましてやそんな彼が自分のためにこんな真っ赤な顔をするなんて、予想外にも程がある。
「叶うなら交際したい。もし玖珠理にその気がないなら……出来れば、今後恋愛対象になれるよう努力する機会をくれないか」
返事は急がなくていい。
どうやら障子はもう話を切り上げるつもりらしい。不意打ちでこれだけ人の心をかき乱して置いて一方的に言い逃げなんてずるいじゃないか。そう思った時にはもう声が出ていた。
「私もっ、障子が好きだよ!さっきは……その、誤魔化しちゃったけど、ずっと好きだった」
好きって言葉はたった二文字なのにどうしてこうも扱いにくいんだろう。言われたら嬉しいけど気恥ずかしいし、自分で言うともっと恥ずかしくてもう心臓が痛い。
「障子?」
返事がないどころか全身固まってしまった障子に声をかけたら、先程の比じゃないくらい顔が真っ赤になっていた。
「……あまり見ないでくれ」
恥ずかしそうに顔を逸らす、障子のこんな反応はだいぶレアだ。緊張したのは私だけじゃなかったんだなって安心感と共に、ふつふつと悪戯心が湧いてくる。
「ふふっ、茹でダコみたい」
「見るなっ」
「だって障子のこんな顔珍し──いっ!?」
この機会に照れ顔をしっかり焼き付けておこうとしたのに、身体が傾いて視界が迷彩柄で埋め尽くされた。そして後ろから温かいものに包み込まれる抱擁感。やっぱり障子はずるい。こんなことをされてはからかう余裕なんて無くなってしまう。
「言っておくが」
ダメ押しとばかりに、耳元で障子が落ち着いた声で囁く。
「お前も人のこと言えないくらい真っ赤だ。……ありがとう」
ああもう本当、障子には敵わないな。
───────
クラスで玖珠理が恋バナを振られているのを耳にする度に内心気が気じゃなかった障子。どうやったら彼女の好きな人を知れるか、自分の思いを伝えられるか、考えすぎた結果こうなった。
好きな人とか……そういうのはあるのか」
「はい?」
あまりにも唐突で、しかもおよそこの手の話題に積極的に踏み入らなさそうな相手から振られたものだから思わず聞き返してしまった。まさかこんな流れで「あなたが好きです」と言える訳もなく。何とか話題を逸らせないものか……
「また随分藪から棒に……障子もそういうの興味あるんだね」
「最近女子がよくその手の話をしているのを耳にして、玖珠理はどうなのかと思ってな」
確かに芦戸や葉隠あたりは恋バナが大好きだ。よくその手の話題──主に障子絡みのこと──をつつかれるし、私は私でのらりくらりとそれを躱している。
「で、どうなんだ?」とご丁寧に複製腕で目を増やして覗き込まれると、言い逃れるのも苦しい。
「うーん……まぁ、話しやすくて、一緒にいて落ち着く人かな」
「……そうか」
核心には触れず、でも嘘はついていない。お願いだからこれで引き下がって欲しい。
「そういう障子はどうなの?」
「俺は……」
先程追求してきた勢いはどこへやら、急に口篭る。複製腕も引っ込んだ。まさか聞き返されるとは思ってなかったんだろうか?
まぁこちらも社交辞令で聞き返しただけなので流してくれて構わないんだけど。むしろそうして欲しい、聞くのが怖い。
寡黙だがはっきりものを言う障子には珍しく目線を泳がせている。こんなの「好きな人がいる」と言っているようなものだ。
「……この人だ」
そういって差し出されたのは彼のスマホ。まさか写真出してくる気?いよいよ残酷過ぎない?そして相手のこと好き過ぎんか??
もの凄く気になるけどもの凄く見たくない、でもここで自然に断る口実もない。
スマホを受け取るまでの数秒。腹を括って、リアクションのシミュレーションまでして、半ばやけくそで液晶画面を覗き込む。
「あーわかる。確かに可愛いもんね」
「えっ意外!あんまり接点ないイメージ……さては障子、本命には奥手なタイプ?」
さてどのパターンを引き出すかと意気込んだ結果、そのどれも不発で終わってしまった。
そこにいたのは眉間に皺を寄せ、なんとも言えない表情の見慣れた顔───インカメに写った自分だったからだ。
「なっ、なーんだもうびっくりした!!障子もこういうイタズラするんだね!!」
人の覚悟を返してくれ!!と叫びたい気持ちを必死に押し込めて、作り笑いしながらスマホを返す。
しかし当の持ち主はそれを受け取ろうとせず、ただ真っ直ぐ私の目を見つめていた。
「しょ、うじ?」
「そういう、ことだ」
そういうことってどういうこと?いやたぶん、意味はわかったんだけど。
障子なりのボケだったりしない?私のイタい勘違いだったりしない?───そんなこと聞き返せないくらい、障子の目は真剣で。
いやいやいや、待ってよ。待ってってば。
「そ、れって……」
ダメだ心臓がバクバクして苦しくなってきた。顔に熱が籠って考えがまとまらない。
こちらのキャパオーバーを知ってか知らずか、フーっと息を吐き出してから障子が口を開いた。
「すまない、つい回りくどい言い方をしてしまった。……玖珠理が好きだ」
障子とはクラスの中でもそこそこ付き合いがある方だと自負しているが、私から見ても彼はいつも冷静で、動揺は愚か声を上げて笑うところすらほぼ見た事がない。ましてやそんな彼が自分のためにこんな真っ赤な顔をするなんて、予想外にも程がある。
「叶うなら交際したい。もし玖珠理にその気がないなら……出来れば、今後恋愛対象になれるよう努力する機会をくれないか」
返事は急がなくていい。
どうやら障子はもう話を切り上げるつもりらしい。不意打ちでこれだけ人の心をかき乱して置いて一方的に言い逃げなんてずるいじゃないか。そう思った時にはもう声が出ていた。
「私もっ、障子が好きだよ!さっきは……その、誤魔化しちゃったけど、ずっと好きだった」
好きって言葉はたった二文字なのにどうしてこうも扱いにくいんだろう。言われたら嬉しいけど気恥ずかしいし、自分で言うともっと恥ずかしくてもう心臓が痛い。
「障子?」
返事がないどころか全身固まってしまった障子に声をかけたら、先程の比じゃないくらい顔が真っ赤になっていた。
「……あまり見ないでくれ」
恥ずかしそうに顔を逸らす、障子のこんな反応はだいぶレアだ。緊張したのは私だけじゃなかったんだなって安心感と共に、ふつふつと悪戯心が湧いてくる。
「ふふっ、茹でダコみたい」
「見るなっ」
「だって障子のこんな顔珍し──いっ!?」
この機会に照れ顔をしっかり焼き付けておこうとしたのに、身体が傾いて視界が迷彩柄で埋め尽くされた。そして後ろから温かいものに包み込まれる抱擁感。やっぱり障子はずるい。こんなことをされてはからかう余裕なんて無くなってしまう。
「言っておくが」
ダメ押しとばかりに、耳元で障子が落ち着いた声で囁く。
「お前も人のこと言えないくらい真っ赤だ。……ありがとう」
ああもう本当、障子には敵わないな。
───────
クラスで玖珠理が恋バナを振られているのを耳にする度に内心気が気じゃなかった障子。どうやったら彼女の好きな人を知れるか、自分の思いを伝えられるか、考えすぎた結果こうなった。
1/1ページ