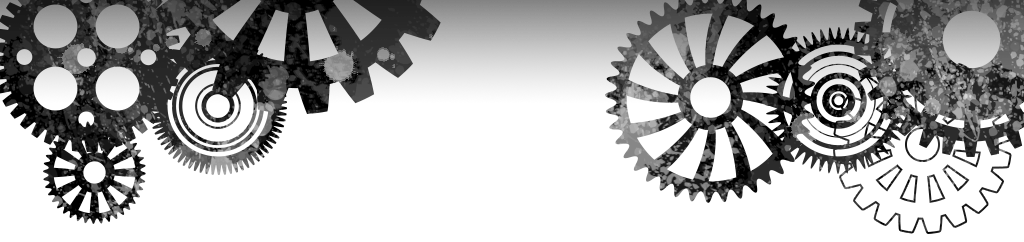カウボーイ
名前
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
「よう、レノ」
「あ、カヴィン」
荘園の一角にある小さな共有スペースで、オルガレーノが日記を書いていた時のこと。
同じ体勢をし続けて凝り固まった身体を伸ばして深呼吸すると、カウボーイのカヴィンがやってきた。
テンガロンハットに西陽を浴びながら歩み寄る姿は、絵の如く様になる。
「油売りに来ただけなんだけどな、今忙しいか?」
「いや、ちょうど一息ついた所だよ」
なら良かった、と呟いて横並びの隣席を引いて座った。
カヴィンは一緒にゲームをした後、決まってこの図書スペースにくる。
その日ゲームでむしゃくしゃしたり落ち込んだりしても晴れやかな気持ちになれるこの時間を、オルガレーノは密かに楽しみにしていた。
「しっかし、ラグビーボール持って爆走してくるレノ、面白かったなぁ……くくっ」
「なっ!?なにも笑うことないだろ!たまたま近くにあった箱の中身があれだったんだから……」
あの時は無我夢中だったが、他人から改めて言われると恥ずかしい。
だが心底可笑しそうに笑う彼の表情を見て嫌な気はしないから不思議だ。
「それだけ必死に助けに来てくれたんだろ、ありがとな。……惚れ直したよ」
テーブルに肘を付いて彼女に身体を向けながら、彼お得意の甘い言葉を吐くカヴィンに
「はいはい、相変わらずお上手で」
と慣れた調子で軽く返すオルガレーノ。
いつもならここで「つれねぇなぁ!」なんて笑い声が返ってくるのに、今日の彼は妙に静かだ。
「?カヴィ「……なら、真面目に言ったら逃げずに聞いてくれるか?」
カヴィンの顔を覗き込もうとしたら、先に彼の方が動いた。
オルガレーノの座っている椅子の背もたれを掴んで覗き込んでくる。
距離の近さと背後に回された腕の位置。
「〜〜〜っ!?」
それを意識した途端、彼に抱かれているような感覚に陥って一気に顔が熱を持つ。
近過ぎる距離を離したいのに、隅席のため後ろに下がることも出来ず壁に背を預けた。
「で、でもっ、カヴィンは他の女性にも……色々言ってるし」
「まあ確かにそれはあるけどな。……ただ、今のこれは女だから言ってるんじゃない。レノだから、レノにだけ、言ってるんだぜ?」
彼のことは憎からず思っていた。
思ってはいたが、あまりにもこれは急展開過ぎる。
こんな時に小洒落たセリフの一つも囁き返すのが大人の女なのだろうが、生憎そんなノウハウも経験も持ち合わせていなかった。
カヴィンの左手がそっとオルガレーノの頬に触れる。
彼愛用のメンソールシガーの香りが鼻先を掠めた。
「……そんな歯の浮くようなセリフ、よく言えるね」
「俺だって正直恥ずかしいけどな。……でもちゃんと伝えなきゃ、オルガレーノには伝わらないだろ?」
照れ隠しに呟けばそれすらも真っ直ぐに包まれてしまう。
直視することもあからさまに逸らすことも出来ず、視線のやり場に困っていると、彼の顔がゆっくりと近付いてきた。
「逃げる」「手で遮る」、そんな選択肢が浮かんだ中で「腹を括る」を選んだオルガレーノは目を瞑り、柔らかくて温かな感触を受け止めた。
……ただし受け止めた先は、唇ではなく額だったが。
「えっ……」
顔を上げれば、距離をとったカヴィンが、目を細めて笑っていた。
「なんだ、唇の方が良かった?」
言いながら、親指がそっとオルガレーノの唇をなぞる。
「っそ、それは……」
正直ほんの少しだけだけがっかりしたが、したとは言えず。
言い返せない時点で答えたようなものだが、
不器用なオルガレーノは言葉に詰まった。
「まっ、今回はお預けだけどな」
「えっ……あ、またからかって!」
「ははっ、バーカ」
次は唇にするから覚悟してって意味だよ。
そう言い残して不敵に笑うと、テンガロンハットをポスリとオルガレーノに被せて去っていった。
オルガレーノの頭に残されたメンソールシガーの香りが、カヴィンが去った後も心を掻き乱し続けた。
* * *
「っはぁーーーっ」
カヴィンは自室の扉を閉めた後、風船の空気が抜けるような溜息を吐きながらしゃがみ込んだ。
その顔は夕陽に照らされていても分かる程赤面している。
「あれは、ズルすぎるだろ……」
これまで女性との交際や、更に先へ踏み込んだ経験はある。
だがオルガレーノに抱く感情は、これまでの女性に向けてきたそれとは比べ物にならないほどむず痒くて抑え難くて、そして繊細なものだ。
(どれだけ殺し文句を言っても響かない癖に、思わぬ所でウブな顔するなんてなぁ……)
ハンターに追われても眉一つ動かさぬ凛々しさが、不意に崩れた時の愛おしさを知ってから、もう目を離せなくなってしまった。
先程キスしても良かったのか、と聞いた時、彼女の目が自分の唇を見つめ返していたのが忘れられない。
「あんな状態でキスなんかしたら、我慢できねぇって……!」
もとより逃がす気も誰かに譲る気も毛頭ない。
しかし彼女の気持ちを彼女から示してくれるようになって、同じ気持ちになってから求め合いたい。
だからこそ、抑えの効かない状態で決定打を出すことは気が引けるのだ。
言葉になるほどオルガレーノの心を解くのにはまだまだ時間がかかるだろうがそれでも。
「唇にキスしても良かったのか」と聞いたら、彼女が「唇がいい」と答えられるようになるまで待とう。
そしてその時が来たら今度こそは、遠慮なく。
「あ、カヴィン」
荘園の一角にある小さな共有スペースで、オルガレーノが日記を書いていた時のこと。
同じ体勢をし続けて凝り固まった身体を伸ばして深呼吸すると、カウボーイのカヴィンがやってきた。
テンガロンハットに西陽を浴びながら歩み寄る姿は、絵の如く様になる。
「油売りに来ただけなんだけどな、今忙しいか?」
「いや、ちょうど一息ついた所だよ」
なら良かった、と呟いて横並びの隣席を引いて座った。
カヴィンは一緒にゲームをした後、決まってこの図書スペースにくる。
その日ゲームでむしゃくしゃしたり落ち込んだりしても晴れやかな気持ちになれるこの時間を、オルガレーノは密かに楽しみにしていた。
「しっかし、ラグビーボール持って爆走してくるレノ、面白かったなぁ……くくっ」
「なっ!?なにも笑うことないだろ!たまたま近くにあった箱の中身があれだったんだから……」
あの時は無我夢中だったが、他人から改めて言われると恥ずかしい。
だが心底可笑しそうに笑う彼の表情を見て嫌な気はしないから不思議だ。
「それだけ必死に助けに来てくれたんだろ、ありがとな。……惚れ直したよ」
テーブルに肘を付いて彼女に身体を向けながら、彼お得意の甘い言葉を吐くカヴィンに
「はいはい、相変わらずお上手で」
と慣れた調子で軽く返すオルガレーノ。
いつもならここで「つれねぇなぁ!」なんて笑い声が返ってくるのに、今日の彼は妙に静かだ。
「?カヴィ「……なら、真面目に言ったら逃げずに聞いてくれるか?」
カヴィンの顔を覗き込もうとしたら、先に彼の方が動いた。
オルガレーノの座っている椅子の背もたれを掴んで覗き込んでくる。
距離の近さと背後に回された腕の位置。
「〜〜〜っ!?」
それを意識した途端、彼に抱かれているような感覚に陥って一気に顔が熱を持つ。
近過ぎる距離を離したいのに、隅席のため後ろに下がることも出来ず壁に背を預けた。
「で、でもっ、カヴィンは他の女性にも……色々言ってるし」
「まあ確かにそれはあるけどな。……ただ、今のこれは女だから言ってるんじゃない。レノだから、レノにだけ、言ってるんだぜ?」
彼のことは憎からず思っていた。
思ってはいたが、あまりにもこれは急展開過ぎる。
こんな時に小洒落たセリフの一つも囁き返すのが大人の女なのだろうが、生憎そんなノウハウも経験も持ち合わせていなかった。
カヴィンの左手がそっとオルガレーノの頬に触れる。
彼愛用のメンソールシガーの香りが鼻先を掠めた。
「……そんな歯の浮くようなセリフ、よく言えるね」
「俺だって正直恥ずかしいけどな。……でもちゃんと伝えなきゃ、オルガレーノには伝わらないだろ?」
照れ隠しに呟けばそれすらも真っ直ぐに包まれてしまう。
直視することもあからさまに逸らすことも出来ず、視線のやり場に困っていると、彼の顔がゆっくりと近付いてきた。
「逃げる」「手で遮る」、そんな選択肢が浮かんだ中で「腹を括る」を選んだオルガレーノは目を瞑り、柔らかくて温かな感触を受け止めた。
……ただし受け止めた先は、唇ではなく額だったが。
「えっ……」
顔を上げれば、距離をとったカヴィンが、目を細めて笑っていた。
「なんだ、唇の方が良かった?」
言いながら、親指がそっとオルガレーノの唇をなぞる。
「っそ、それは……」
正直ほんの少しだけだけがっかりしたが、したとは言えず。
言い返せない時点で答えたようなものだが、
不器用なオルガレーノは言葉に詰まった。
「まっ、今回はお預けだけどな」
「えっ……あ、またからかって!」
「ははっ、バーカ」
次は唇にするから覚悟してって意味だよ。
そう言い残して不敵に笑うと、テンガロンハットをポスリとオルガレーノに被せて去っていった。
オルガレーノの頭に残されたメンソールシガーの香りが、カヴィンが去った後も心を掻き乱し続けた。
* * *
「っはぁーーーっ」
カヴィンは自室の扉を閉めた後、風船の空気が抜けるような溜息を吐きながらしゃがみ込んだ。
その顔は夕陽に照らされていても分かる程赤面している。
「あれは、ズルすぎるだろ……」
これまで女性との交際や、更に先へ踏み込んだ経験はある。
だがオルガレーノに抱く感情は、これまでの女性に向けてきたそれとは比べ物にならないほどむず痒くて抑え難くて、そして繊細なものだ。
(どれだけ殺し文句を言っても響かない癖に、思わぬ所でウブな顔するなんてなぁ……)
ハンターに追われても眉一つ動かさぬ凛々しさが、不意に崩れた時の愛おしさを知ってから、もう目を離せなくなってしまった。
先程キスしても良かったのか、と聞いた時、彼女の目が自分の唇を見つめ返していたのが忘れられない。
「あんな状態でキスなんかしたら、我慢できねぇって……!」
もとより逃がす気も誰かに譲る気も毛頭ない。
しかし彼女の気持ちを彼女から示してくれるようになって、同じ気持ちになってから求め合いたい。
だからこそ、抑えの効かない状態で決定打を出すことは気が引けるのだ。
言葉になるほどオルガレーノの心を解くのにはまだまだ時間がかかるだろうがそれでも。
「唇にキスしても良かったのか」と聞いたら、彼女が「唇がいい」と答えられるようになるまで待とう。
そしてその時が来たら今度こそは、遠慮なく。
1/1ページ