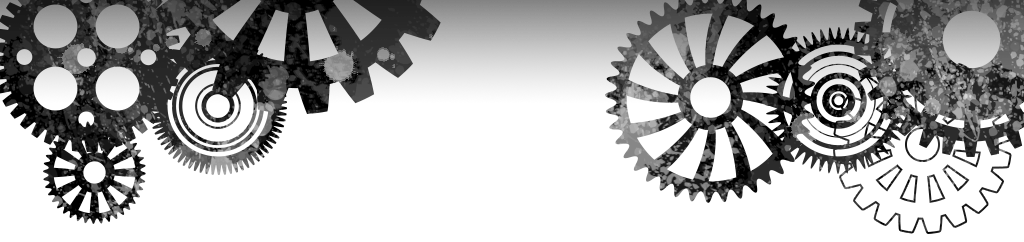泥棒
名前
「っぐしっ!!」
オルガレーノの部屋になんとも情けないくしゃみの音が谺響する。
「あー…つらっ」
オルガレーノは昨日レオの思い出で復讐者レオ相手にゲームをした際、引き分けか敗北の瀬戸際となる局面で最後のサバイバーとなった。
そして数時間に及ぶチェイスを繰り広げた末の粘り勝ちを収めた代償に、熱を出して寝込む羽目になったのだ。
(久しぶりに熱を出すとなかなか辛いな…お腹空いた…でも動ける気がしない)
熱が篭もって鈍った頭でぼんやり考えるとコンコン、とノックの音がする。
自室のドアノブが周り、控えめに開けられた隙間からキャスケット帽と髭面のクリーチャー・ピアソンが覗いた。
「レノ、お、起きてるか?」
「起きてるよ。どうし…あれ?」
何をしに来たのか、と問う前に何か香しい匂いが漂ってくるのに気が付いた。
見れば彼は手に皿の乗ったトレーを持っている。
サイドデスクの上に置かれたトレーを見ると、一口サイズに切られた野菜がたっぷり入ったリゾットがスープ皿に盛られていた。
少し迷った素振りを見せた後、近くの椅子を寄せてピアソンはベッド脇に座る。
「お、お腹、空いてるかと思って」
「ありがとう、いい匂い…これ、ピアソンが?」
「あ、ああ。……嫌、だったか?」
「いや、ちょうどお腹が空いてたから嬉しいよ」
食事をするべく、まだ気怠い身体をどうにか起こす。
匙を手に取ろうとしたがトレーに乗っておらず、ピアソンの方を見れば目的のものは彼の手に握られていた。
ピアソンは匙にリゾットを掬ってふーふーと息をかけて冷まし、オルガレーノに差し出した。
俗に言う「あーん」の状態である。
しかし彼は自分が何をしたのか思い出したか、はっとして、続いて頬を赤く染めて謝罪した。
「あっ…す、す、すまんっ!つい」
「えっ、いやいや、あ、ありがとっ!ねぇピアソン、そ…そのまま食べさせてよ」
「うっ、え…?」
大いに恥ずかしい。が、これはチャンスだ。
そう思ったオルガレーノは、ピアソンが手を引っ込めてしまうのを予期して先手を打った。
結果、頬のみならず顔全体を真っ赤にしたピアソンが呻くようななんとも言えない声を上げて固まり、俯いた。
やがてガバッと顔を上げると、手に持っていた匙を再びオルガレーノの口元に差し出した。
「ん」
「ふふっ、ありがとう」
礼を言いつつ、リゾットを頬張った。
「…美味しい!」
適温に冷めたそれは、具材に程よくコンソメが染み込んだ優しい味付けで、消化力の落ちた胃に優しく染み渡る。
ホロホロになった玉ねぎとセロリの持つ旨みが口に広がり、疲労が和らぐような心地がした。
(ピアソンが料理上手ってちょっと意外だな…そういえば孤児院運営してたんだっけ)
ふっと彼の経歴を思い出したら納得がいった。
子供の世話をみていれば、当然病人の看病をする機会もあるだろう。
最初こそ赤ら顔でぎこちないピアソンだったが、オルガレーノの嚥下ペースに合わせて上手く差し出してくれるので、何不自由無く食事を終えられた。
「美味しかった!ご馳走様でした」
「ど、どういたしまして」
「でも、どうしてピアソンが?エミリーが来るかと思ってた」
「ああ、彼女はゲーム中だから…そ、それに…昨日、助けてくれたせいだろ?その風邪…」
「昨日?」
昨日と言われ、昨日のゲームのことを思い返す。
心眼ヘレナ、調香師ウィラ、そして泥棒ピアソンと護衛オルガレーノの4人が参加した。
ヘレナとウィラが飛ばされ、ピアソンも拘束されたところをオルガレーノが救助・肉盾して逃がした、その事だろうか。
確かに昨日のゲームが長引いたのは、自分の完全勝利だと思った試合を引き分けに持ち込まれたレオが怒り狂ってオルガレーノを追いかけ回したから、ではある。
しかしそれは決してピアソンのせいではないし、味方の救助に行くのは当然のことだ。
「そんな、気にすることじゃないのに…」
「い、いいんだ」
そう言っておどおどしながらピアソンが笑う。
傍目から見ると常に挙動不審気味な彼の笑顔は引き攣って不自然に映る。
だがこれが彼なのだ、と思うようになってからは、寧ろ愛嬌すら感じるから不思議だ。
「そ、そうだ!熱…」
ピアソンは思い出したように言うと、掌が添えられた。
「…掌、気持ちいい」
普段グローブで覆われてる手は少し冷たくてカサついていて、熱を帯びて汗ばんだ肌にちょうど気持ちいい。
「…そ、そうか」
戸惑ったようにオルガレーノの額のタオルを取り去り、交換したタオルを乗せてくれる。
ピアソンの掌を名残惜しく思いつつもさすがにこれ以上手間をかけさせる訳にもいかず、黙って作業中のピアソンを見守っていた。
すると視線に気づいたのか、視線を頻りに行ったり来たりさせ、オルガレーノを数秒見つめた後、おずおずと手をオルガレーノの頭に添えてそっと撫でた。
「あっ…ありがとう」
言葉にせずとも自分の気持ちを汲んでくれたのが照れくさいけど嬉しくて、オルガレーノはむず痒さを覚えた。
「きょ、今日くらい…ゆっくり、休んだらいい」
言われてみれば最近ゲーム続きで身体が休まる暇がなかったような気がする。
それを自覚した途端、安心したのもあるのか抗いがたい眠気に襲われた。
そんな様子を察したのか、ピアソンが小さく笑う。
「お、おやすみ…オルガレーノ」
(ああ、彼はこんな笑い方もできるんだ…)
先程の引き攣った笑顔とは違い、自然に頬が緩んだような、初めて見る穏やかな笑顔。
この笑顔を、いつか独り占めしたい…そんなことを考えながら額にピアソンの体温を感じ、オルガレーノは再び微睡みに落ちていった。
オルガレーノの部屋になんとも情けないくしゃみの音が谺響する。
「あー…つらっ」
オルガレーノは昨日レオの思い出で復讐者レオ相手にゲームをした際、引き分けか敗北の瀬戸際となる局面で最後のサバイバーとなった。
そして数時間に及ぶチェイスを繰り広げた末の粘り勝ちを収めた代償に、熱を出して寝込む羽目になったのだ。
(久しぶりに熱を出すとなかなか辛いな…お腹空いた…でも動ける気がしない)
熱が篭もって鈍った頭でぼんやり考えるとコンコン、とノックの音がする。
自室のドアノブが周り、控えめに開けられた隙間からキャスケット帽と髭面のクリーチャー・ピアソンが覗いた。
「レノ、お、起きてるか?」
「起きてるよ。どうし…あれ?」
何をしに来たのか、と問う前に何か香しい匂いが漂ってくるのに気が付いた。
見れば彼は手に皿の乗ったトレーを持っている。
サイドデスクの上に置かれたトレーを見ると、一口サイズに切られた野菜がたっぷり入ったリゾットがスープ皿に盛られていた。
少し迷った素振りを見せた後、近くの椅子を寄せてピアソンはベッド脇に座る。
「お、お腹、空いてるかと思って」
「ありがとう、いい匂い…これ、ピアソンが?」
「あ、ああ。……嫌、だったか?」
「いや、ちょうどお腹が空いてたから嬉しいよ」
食事をするべく、まだ気怠い身体をどうにか起こす。
匙を手に取ろうとしたがトレーに乗っておらず、ピアソンの方を見れば目的のものは彼の手に握られていた。
ピアソンは匙にリゾットを掬ってふーふーと息をかけて冷まし、オルガレーノに差し出した。
俗に言う「あーん」の状態である。
しかし彼は自分が何をしたのか思い出したか、はっとして、続いて頬を赤く染めて謝罪した。
「あっ…す、す、すまんっ!つい」
「えっ、いやいや、あ、ありがとっ!ねぇピアソン、そ…そのまま食べさせてよ」
「うっ、え…?」
大いに恥ずかしい。が、これはチャンスだ。
そう思ったオルガレーノは、ピアソンが手を引っ込めてしまうのを予期して先手を打った。
結果、頬のみならず顔全体を真っ赤にしたピアソンが呻くようななんとも言えない声を上げて固まり、俯いた。
やがてガバッと顔を上げると、手に持っていた匙を再びオルガレーノの口元に差し出した。
「ん」
「ふふっ、ありがとう」
礼を言いつつ、リゾットを頬張った。
「…美味しい!」
適温に冷めたそれは、具材に程よくコンソメが染み込んだ優しい味付けで、消化力の落ちた胃に優しく染み渡る。
ホロホロになった玉ねぎとセロリの持つ旨みが口に広がり、疲労が和らぐような心地がした。
(ピアソンが料理上手ってちょっと意外だな…そういえば孤児院運営してたんだっけ)
ふっと彼の経歴を思い出したら納得がいった。
子供の世話をみていれば、当然病人の看病をする機会もあるだろう。
最初こそ赤ら顔でぎこちないピアソンだったが、オルガレーノの嚥下ペースに合わせて上手く差し出してくれるので、何不自由無く食事を終えられた。
「美味しかった!ご馳走様でした」
「ど、どういたしまして」
「でも、どうしてピアソンが?エミリーが来るかと思ってた」
「ああ、彼女はゲーム中だから…そ、それに…昨日、助けてくれたせいだろ?その風邪…」
「昨日?」
昨日と言われ、昨日のゲームのことを思い返す。
心眼ヘレナ、調香師ウィラ、そして泥棒ピアソンと護衛オルガレーノの4人が参加した。
ヘレナとウィラが飛ばされ、ピアソンも拘束されたところをオルガレーノが救助・肉盾して逃がした、その事だろうか。
確かに昨日のゲームが長引いたのは、自分の完全勝利だと思った試合を引き分けに持ち込まれたレオが怒り狂ってオルガレーノを追いかけ回したから、ではある。
しかしそれは決してピアソンのせいではないし、味方の救助に行くのは当然のことだ。
「そんな、気にすることじゃないのに…」
「い、いいんだ」
そう言っておどおどしながらピアソンが笑う。
傍目から見ると常に挙動不審気味な彼の笑顔は引き攣って不自然に映る。
だがこれが彼なのだ、と思うようになってからは、寧ろ愛嬌すら感じるから不思議だ。
「そ、そうだ!熱…」
ピアソンは思い出したように言うと、掌が添えられた。
「…掌、気持ちいい」
普段グローブで覆われてる手は少し冷たくてカサついていて、熱を帯びて汗ばんだ肌にちょうど気持ちいい。
「…そ、そうか」
戸惑ったようにオルガレーノの額のタオルを取り去り、交換したタオルを乗せてくれる。
ピアソンの掌を名残惜しく思いつつもさすがにこれ以上手間をかけさせる訳にもいかず、黙って作業中のピアソンを見守っていた。
すると視線に気づいたのか、視線を頻りに行ったり来たりさせ、オルガレーノを数秒見つめた後、おずおずと手をオルガレーノの頭に添えてそっと撫でた。
「あっ…ありがとう」
言葉にせずとも自分の気持ちを汲んでくれたのが照れくさいけど嬉しくて、オルガレーノはむず痒さを覚えた。
「きょ、今日くらい…ゆっくり、休んだらいい」
言われてみれば最近ゲーム続きで身体が休まる暇がなかったような気がする。
それを自覚した途端、安心したのもあるのか抗いがたい眠気に襲われた。
そんな様子を察したのか、ピアソンが小さく笑う。
「お、おやすみ…オルガレーノ」
(ああ、彼はこんな笑い方もできるんだ…)
先程の引き攣った笑顔とは違い、自然に頬が緩んだような、初めて見る穏やかな笑顔。
この笑顔を、いつか独り占めしたい…そんなことを考えながら額にピアソンの体温を感じ、オルガレーノは再び微睡みに落ちていった。
1/1ページ