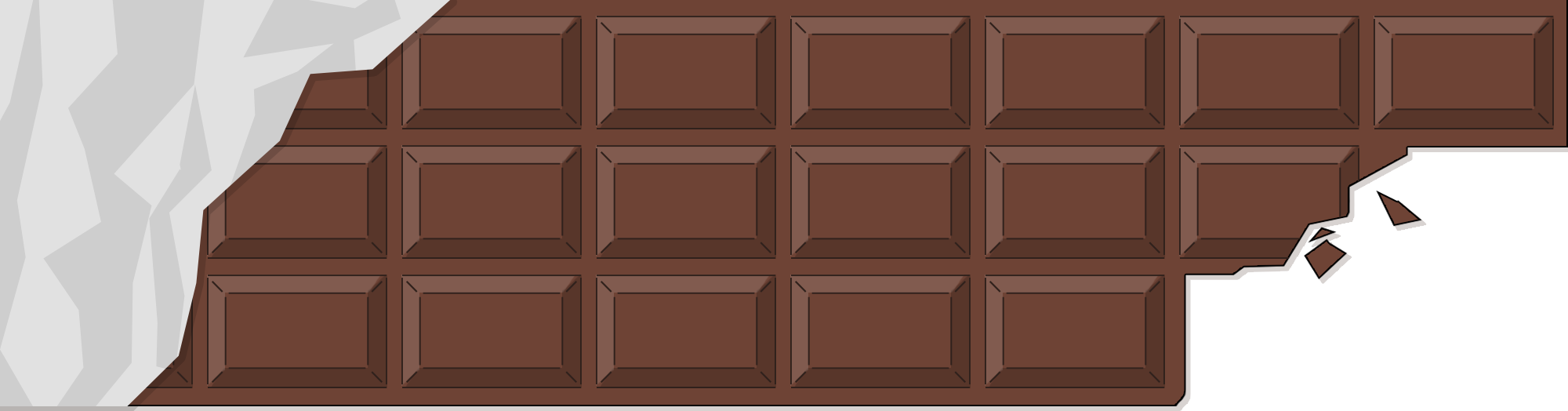第一章
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
天地が去った後、鈴蘭高校では派閥同士の小競り合いで乱闘が起こっていた。
そんな中で花が一年戦争の覇者という事もあって神戸に呼び出しを受けていた頃、夢野は1階にあるトイレに来ていた。
本来なら教室に近い同じ階のトイレを使えば良いのだが女性だとバレる危険性が高いので、こうして教室から離れたトイレを使っているのだ。
それに何やら迫田達が集まって話しているのが聞こえたというのもある。
ついでに自販機に寄ってから教室に戻ろうとしたら、寅之助と教室に居るはずの花とすれ違った。
「あれ?どっか行くの?」
「今、ブーさんに挨拶したから他の先輩方への挨拶だよ!」
「へぇ、どういう所に回るの?」
「美術室とか図書室だな。あ、屋上にも行くぞ!」
先輩達への挨拶回りは遠慮したいところだが、図書室と聞いた夢野はピクリと反応した。
「葵も行く?」
「図書室は行きたいけど……」
「なら、決まりだな!!」
「えっ!? ちょっと!!」
抵抗するも力では敵わず、夢野はずるずると引きずられていった。
初めは美術室に連れていかれた。
一緒に挨拶するかと聞かれたが夢野はそれを断り、美術室の前にひっそり立って待っていた。
しかし、それはすぐに後悔へと変わった。
あの一年戦争の覇者が挨拶に来ていると人が集まっていたからだ。
明らかに睨まれていると察した夢野はなるべく目を合わせないようにと俯いた。
――早く戻ってきて!
そう願っているとポケットに入れていた携帯電話が鳴った。
携帯電話を開き、確認すると寅之助からだった。
「もしもし?」
『葵ちゃん! 今どこに居るの!? 実は花ちゃんが――』
「あ、一緒に居るよ」
『え!?』
「図書室にも行くって言うし、無理矢理引っ張るもんだから……」
『それで、ついていっちゃったと』
ごにょごにょと伝えれば向こうから溜息が聞こえた。
――溜息をつきたいのはこっちもだ。
とりあえず、今のところは大丈夫だと伝えれば寅之助は蓮次達を探してくるとだけ言い残し、電話を切られた。
「どうしたんだ?」
いつの間にか挨拶を済ませてきた花が後ろに立っていた。
「寅くんから。ねぇ、どうだった? イワシロ先輩とハラダ先輩だっけ」
「良い先輩だったぞ! いつでも相談に乗るってさ」
「へぇ、優しい先輩達だね。じゃあ、オレはそろそろ――」
「じゃ、次は図書室だな!」
「ですよね〜」
逃げようかと考えていたのがバレていたのか、ガッチリと掴まれて引きずられていく。
図書室も同じ様に夢野は待っている事にした。
どんな先輩達なのか花に聞いてから図書室への出入り許可を尋ねようと考えていたからだ。
恐そうなら諦めようと最初から決めていた。
ここでも視線は痛かったが、睨まれるだけで何もしてこないと解れば問題はなかった。
花もすぐに挨拶を終えて出てきた。
「おかえり。どう? 恐そう?」
「待ってくれてるぞ」
「……え?」
「もう一人話があるからって言っといた! オレは先に屋上行ってくるよ!」
「あ、うん。アリガトウ……」
今だけは花の優しさが憎かった。
いっそのこと、帰ろうかとも思ったが待たせたくせに来なかったと怒らせてしまうのも恐かったので意を決して図書室への扉をくぐった。
「……す、すみません」
「おーなんか話があるって?」
金髪で眉にはピアス。そして、奥にはスラッとした黒髪のオールバック。
やはり辞めておけばよかったと本日最大の後悔をした。あまりにも恐かったのだ。
もう出入りの許可なんていらないから早く済ませようと夢野は口を開いた。
「オレは1年の夢野葵って言います。本が借りたくて図書室への出入りを許して欲しかったんですけど、もう大丈夫です! お時間取らせてすみませんでした! 失礼します!」
頭を下げ、後は逃げるだけだと夢野は急いで図書室を出ようと背中を向けた。
「おいおい、逃げるなって」
「ぎゃっ!!」
後ろ襟を掴まれ、情けない悲鳴を上げる。
「ハハハッ! お前、なんつー声出してんだよ」
首をなんとか傾げて、見上げれば後ろ襟を掴んでいるのは金髪の先輩だった。
「お前、ゼットンと屋上に行った奴だろ」
「え、なんで知って――」
「コメから聞いた。ちっせーのを引き連れて屋上に来たって」
「ああ、なるほど。……ところで、放してもらえませんかね」
「ぜってー逃げるなよ」
「逃げません!」
何度も首を縦に振れば解放された。
2人に向き合い、もう一度自己紹介をして会釈をする。
「改めてよろしくお願いします」
「オレは小林政成。で、あっちは加東秀吉」
「小林先輩と加東先輩ですね」
窓際に立ち、何かを見定めるように黙ったまま秀吉が見つめてくる。
どうしたらいいのか助けを求めようと政成を見れば面倒臭そうに溜息をついた。
「……なんで出入りなんかしたいんだよ」
「いや、図書室なんだから本を借りる以外ないかと思いますけど」
「はぁ?この学校で好き好んで本を読む奴なんていねぇよ」
確かに居なさそうではあった。
それでも一人くらいは居るだろうと思っていたのだが、読みは完全に外れていたらしい。
「なら、諦めます。失礼します」
「だから、すぐ逃げんなって」
「ぐうっ!」
また後ろ襟を引っ張られ首が絞まる。
「どーするよ秀吉」
「……勝手にしろ」
「だとよ」
「え、良いんですか!」
まさか許可が出るとは思っていなかった。
案外、話のわかる人なのかもしれない。
「めちゃくちゃ来ますよ?」
「遠慮なしかよ」
「いたっ!」
政成に脳天をチョップされた。
この人苦手かもしれないと睨めば、お返しに睨み返されたので慌てて目を逸らした。
そろそろ、お暇した方が良いかもしれない。
「とりあえず、許可はありがとうございます! 今日のところは失礼します!」
今度こそ捕まらないように廊下へと飛び出した。
後ろで政成が何か叫んでいたが、もちろん聞こえないフリをした。
さっさと教室に帰ろうとすると花と階段ですれ違った。
随分と怒っているようで、こちらに気付く様子はなく下に降りていってしまった。
「……どうしたんだろ」
間違いなく屋上で何かあったのだろう。
屋上ならばゼットンと米崎が居るので話を聞きに階段を上がった。
「失礼します」
「おー夢野どうした?」
屋上を覗いて見ると、やはりゼットンと米崎が居た。
そして一年戦争で見物料を徴収していた亜久津も居た。
手短に亜久津との挨拶を済ませて何があったのか聞いてみる。
「今、階段で花くんとすれ違ったんですけど、かなり怒ってたから何かあったのかなって」
「避けては通れねー男のところに行ってもらうために、ちょっとな」
ゼットンは何かを企んでいるらしく楽しそうだ。
「避けては通れない男……」
「夢野は気を付けた方が良いかもな」
「どういうことですか米崎先輩」
「無類の女好きだから」
夢野は盛大に噎せた。
「九里虎も流石に男には手を出さないと思うんスけど」
亜久津がすかさずツッコミを入れる。
「わかんねーぜ?こいつの顔だけ見りゃ間違えそうだろ」
「まぁ……確かに?」
「勘弁してください!」
亜久津に顔を覗きこまれ、慌てて距離をとる。
それにしても米崎は恐ろしい発言をしたものだ。
顔だけはどうしようもないと覚悟はしていたが、いざ言われてみると心臓に悪かった。
「夢野」
「な、なんですかゼットン先輩」
「もし九里虎のヤローに触られたら股間蹴り上げてやれ!!」
両肩を掴まれゼットンに迫られる。
物凄い顔で物凄い事を言っている。
「というか、凄い名前ですね……」
「花木九里虎だ。覚えとけよ」
「はぁ」
やけに米崎は念を押すが、忘れたくても忘れられない名前である。
「さてと、腹も減ったし飯でも行くか」
「いいっスね」
「夢野はどうする?」
「オレは教室に戻ります」
「じゃーな」
ぞろぞろと出ていく3人に続き夢野も屋上を後にした。
あれから花は怪我をして帰ってきた。
九里虎と喧嘩をしてきたらしい。
一年戦争で花の強さを目の当たりにしているからこそ、九里虎とは一体どんな男なのか謎が深まるばかりだ。
しかし、その九里虎と出会うのは意外にもすぐだった――。
晴れ渡る空の下、体育の授業はサッカー。
真面目にやる者など居らず、ルールも解らないのでお世辞にもサッカーと呼べるものではなかった。
夢野も早々に離脱し、ゆるゆるとボールを蹴ってみたり、リフティングの真似事をしていた。
やってみれば意外と楽しいものである。
「葵ちゃん上手いね」
「そう?」
「オレなんか全然だよ」
寅之助が1回、2回とボールを蹴ればすぐ飛んでいってしまう。
「どうやってんだ?」
花も寅之助よりかは出来ていたが、そこまで長く出来ていなかった。
「足首が固いのかも。力を吸収するイメージで受け止める感じ、ほら」
ポンポンッとリズム良くリフティングをもう一度見せてやる。
「なんかやってたのか?」
「え?」
「体の使い方が上手いって事だろ」
「あ〜それは――」
花の鋭い質問にどう答えようかと悩んでいると、迫田達がこちらに向かってきているのが見えた。
「おい、あの花木九里虎が来てるらしいぞ」
「なに!? 九里虎はんが学校に来てるって!? どこよ!?」
「知るかよ」
「でもオレ朝見たぜ」
八板がそう答えた瞬間に花が走り出した。
「ちょっと行ってくる」
「どこ行くんだよ」
「だってよー誤解とはいえオレはあの人に一方的にケンカ売っちまったんだぜ。あの人にもクロサーさんにもやっぱ一応謝っとこーと思ってよ」
「負けたのにか……」
迫田の一言に花がそれもそうかと固まった。
「それとこれは別問題だろーが! やっぱちょっと行ってくる!」
花にとって行かない理由にはならないらしく再び走り出した。
ちょうどチャイムも鳴り、片付けを終えれば皆ぞろぞろと教室に戻っていく。
夢野は授業前も運良く誰も居なかった保健室で着替えてきたので、また保健室に行かなければならない。
「葵ちゃんどうしたの?」
「えーと靴ずれしたみたいだから保健室に行ってくる」
あまり嘘をつくのは嫌だが、こればかりは仕方ない。
また保健室には誰も居なかったので、ベッドカーテンを閉めて着替えを済ませた。
早く教室に戻ろうと保健室から出ると廊下で誰かとぶつかった。
「うあっ!」
思い切り尻もちをついた。
まるで壁にぶつかったみたいだった。
「あぶなかとね」
聞き馴染みのない方言に顔を上げる。
「……もじゃもじゃ」
率直な感想が口から出た。
派手な柄シャツにもじゃもじゃ頭の男が立っていたのだ。
その男は静かにしゃがみ、目線が合う。
「……ニシャ」
「す、すみません!! ワザとじゃないんです!!」
「なーんでこげん所に女の子がおるったい? あいらしかね〜名前はなんていうと?」
にこにこと喋りながら、そっと手を握られる。
あまり触られたくないが、ガッチリと握りこまれてしまった。
「夢野葵です。あと、男です」
とりあえず訂正だけはさせてもらう。
「うんうん、葵ちゃんっていうんやね。これまたあいらしか名前ばい!」
「ありがとうございます。でも、男です」
「冗談が上手かね〜」
――どうしたものか。
何を言っても通じなさそうである。
しかし、だからといって認めるわけにもいかない。
「おい、なにやってんだ」
奥からバンダナをした男がやってきた。
「ん〜?こげん所に女の子がおったと」
ほれ、と指差されたが必死に首を振った。
「違います!」
「……鈴蘭に居る時点で男だろ」
「そうですよ! ええと――」
「オレは黒澤和光だ」
「あ、オレは夢野葵です。黒澤先輩もっと言ってください」
目の前で今も手を握っている男には話を聞いてもらえなさそうだが、黒澤なら話が通じそうだ。
「早く放してやれよ、グリコ」
「え、九里虎?」
この人がそうだったのか。
確かに女性好きなのだろう。スキンシップをしてくる。
「名前知っとったんやね。嬉しかね〜」
「米崎先輩に気を付けろって言われたのとゼットン先輩には股間を蹴り上げてやれと言われました」
「おー蹴ってやれ」
「解りました」
尻もちをついたままだったが蹴れないことはない。
「そりゃ勘弁して欲しか!」
狙いを定めた瞬間に九里虎は慌てて立ち上がり、やっとの事で解放された。
夢野は立ち上がり、ズボンについた埃を払った。
「うーん、やっぱり腰つきが女の子や」
「細いだけです!!」
腰にまで手を伸ばされそうになり飛び退くと、触れなかった分なのかジーッと観察される。
その視線から逃れるために黒澤の後ろに隠れた。
「おい」
「すみません黒澤先輩。壁になってください」
「クロサーより優しゅうするばい!」
「意味がわかりません! 失礼します!」
「あっ!! 待たんね!!」
捕まる前に夢野は全速力で階段を駆け上がった。
米崎の言った通り要注意人物である。
なんだか先輩からは逃げ出してばかりだなと情けなく笑うのだった。
――その日の放課後、夢野は図書室の前まで来ていた。
祖父の所に向かう前に折角なら本を借りてみようと思ったのだ。
いざ来てみると緊張はするが、2人とも居ない事を祈りながら意を決して扉を開いた。
「失礼します」
恐る恐る声を掛けたが返事はない。
もしかしたら誰も居ないかもしれないと思い、奥に進むと秀吉が居た。
驚き飛び上がるも反応はなく、どうやら寝ているらしい。
これはチャンスだと急いで本を物色する。
あまり近くに寄ると起こしてしまう可能性があったので、今回は手前の本棚だけにしておく。
「……これとこれにしておこうかな」
「わっ!!」
「おああああっ!?!?」
耳元で叫ばれ、驚きのあまり夢野は横に倒れ込んだ。
さらに小説も投げ飛ばしてしまった。
「ワッハッハッ! 吹っ飛んだなぁ」
「こ、小林先輩……!!」
「いや〜傑作、傑作」
「心臓止まるかと思いました」
バクバクと高鳴る胸を押さえながら、夢野が項垂れると政成は腹を抱えて笑っていた。
「折角、静かにしてたのに」
「ん? なんでだよ」
「いや、加東先輩寝てたんで」
そう伝えると、また政成が笑った。
「アイツ起きてるぞ」
「えっ!?」
立ち上がり本棚から顔を覗かせて秀吉を見ると確かに起きていた。
意地の悪い顔で笑っていたので恐らく入ってきた時から起きていたのだろう。
「……もしかしなくても加東先輩って嫌な人ですか?」
「殴られるぞ、お前」
「まぁ、驚かしてきた小林先輩も嫌な人でしょうけど」
「泣かす」
「ぐええ!」
政成にヘッドロックをされ変な声が出る。
苦しいのもあるが、あまり密着されるのも困るので必死に腕をタップした。
力加減はそこまで強めてないだろうが、身長差も相まって完全に締め上げられていた。
「先輩は敬うよーに!」
やっとのことで解放され、息を吸えた。
ゲホゲホと咳込み、あまりの苦しさに出てきた涙を拭いていると背中を撫でられた。一応、罪悪感はあったらしい。
「お、おいっ大丈夫かよ」
「しぬかと、おもいました……」
「そんなんじゃ、やってけねーぞ」
秀吉が投げ飛ばしてしまった小説を拾うと、差し出してくれたので受け取る。
「喧嘩しない分、発言には気を付けます」
「ちっせぇと絡まれやすいしな」
ぐりぐりと政成に頭を撫で回される。普通に痛かった。
「確かにそうかもしれないのです。九里虎先輩にも会いましたけど……」
「へーアイツにか」
「なんか――」
夢野は慌てて口を閉じた。
女性に間違われたなんて言えば、変に疑いの目を向けられるかもしれないからだ。
「なんだよ」
「いえ、何でもないです。じゃあ、オレはこの後予定があるんで帰りますね」
「もう行くのかよ」
「祖父の所に御見舞に行くんですよ」
そう伝えると政成の顔が少し歪んだ。
「……体でもわりぃのか?」
「命に関わるものじゃないって言ってたんで、そんなに気にして貰わなくても大丈夫ですよ」
「ふーん、なら良いけどよ。……そうだ、ここの本持ってってやれよ」
「いやいや流石に学校の本を家族に貸し出すのは」
「平気だろ。なぁ、秀吉」
「管理なんかされてねぇしな」
何とまぁ適当なのだろうか。
しかし、秀吉が言う通り司書が居そうにもない。
「……良いのありますかね」
「お、悪事に手を染めるぞコイツ」
「ちょっと小林先輩!」
「つーかさ、その小林ってのやめろよ。マサで良いって。なんか気持ちわりぃんだよな」
「はぁ……じゃあマサ先輩で」
素直にそう呼べば満足したのか、また乱雑に頭を撫でられた。
きっと髪はぐしゃぐしゃになっているだろう。
「ところで、何かオススメあります?」
「オレに聞くなよ。秀吉、なんかねぇの?」
「わかるかよ」
「加東先輩もあんまり読まないんですか」
「そりゃあな」
そう言いながらも秀吉は本棚を眺めているあたり、探してくれているみたいだ。
「なんかよー時代劇みたいな本なかったっけ」
「……歴史小説ですか?」
「おう、それそれ」
「歴史ならこっちだな」
秀吉が反対側の本棚を指差す。
読まないとは言っていたが、全く知らないわけではないらしい。
「これにしろよ」
政成が渡してきた小説の表紙には『豊臣秀吉』と書かれていた。
何とも反応に困るチョイスだ。
「これは試されてます?」
「有名だろ」
「……まぁ、そうですけど」
ちらりと秀吉の様子を確認すると案の定、顔を歪ませていた。
なんて恐れ知らずの人なのだろうか。
「今回はこっちにしておきます」
別の小説を引き抜いた。
こちらも同じく戦国武将である『石田三成』だ。
「豊臣秀吉でも良いじゃねぇか」
「いや、恐いですし」
「なにが」
「秀吉先輩……じゃなくて、加東先輩」
秀吉、秀吉と聞きすぎて引っ張られてしまった。
「別に呼んでもいいよな」
何故か政成が勝手に答えていたが、秀吉も特に気にしていない様子だった。
「じゃあ、そう呼びます。さてと、そろそろオレは行きますね! ありがとうございました!」
「おう、じゃあな!」
2人に別れを告げ、夢野は浮足立ちながら病院へと向かった。
祖父が転院した病院に初めて来たが、大きな病院だった。
4人部屋の病室に入り、1番奥に祖父は居た。
「ジィちゃん、来たよ」
「よく来たな」
「体調は?」
「ぼちぼちってところだな。葵はどうだ?見舞いに来たって事は友達が出来たんだろう?」
「うん!先輩とも知り合ったし」
一人だけ苦手な先輩は出来たが、花達とは友達になれたと思っている。
「あ、そうそう! 先輩がジィちゃんに小説持ってってやれって借りてきたの」
「おお、これはこれは」
小説を渡せば喜んでくれた。
借りてきて正解だったかもしれない。政成には感謝だ。
「また読み終わったら違うの借りてくるから、ゆっくり読んでよ」
「これなら暇せんで良い。さ、学校の話も聞かせてくれ」
「うん、あのね――」
それから、一年戦争というものがあった、授業はついていけてる、ひとり暮らしも今のところは辛くないと話した。
祖父は最後まで頬を緩ませながら聞いてくれた。
久しぶりに会えたのが楽しく、会話は止まらなかった――。
「お夕食ですよ〜」
「あ、もうそんな時間か」
看護師が食事の配膳にやってきた。いい匂いがする。
時刻はもう18時を過ぎた頃だった。
「そろそろ帰るよ」
「おう、気を付けてな」
「またすぐ来るからね」
祖父に手を振り、看護師に会釈をして病室を後にした。
「今のが話してくれたお孫さんですか?」
「ああ、可愛いだろう」
「本当! いい子そうだし。……でも、お話できてないんでしょう体のこと」
「そのうち話すさなきゃとは思ってるんだけどなぁ」
夢野が帰った後、そんな話がされていたとは知らずに夢野は借りた小説も早く読みたいと足早に帰宅したのだった。