六畳一間の魔王さまの日本侵略日記
魔王の食事が終わるのを待っていたかのように、赤ちゃんが泣き出しました。
理由がわからずオロオロする魔王。泣く子も黙る巨大なドラゴンと呼ばれていたのに、形無しです。
対するトメさんは落ち着いたもの。子どもを一人立派に育て上げた女性なので場数が違います。
「この泣き方。お腹が空いたようだね」
「わかるのか。すごいのう」
「もう五十年は前だが、おれは子育てをしとったんだ。わかるに決まっている。ご近所で粉ミルクをもらってきたから作ろうかい。哺乳びんも、向井さんからもらったんだ」
「うむ。なにからなにまで助かるのう、トメ」
トメさんが電気ポットの蓋を押すとお湯が出てきたので、魔王は驚きます。
「うぬぅ。このような鉄の筒に湯が保存されておるのか? このような技術があるとは、人間はあなどれんの」
「かっかっか。電気ポットがスゴイなら、もうテレビでも炊飯器でも、なんでも目新しかろうなぁ」
この世界に魔法はないけれど、魔法に匹敵するような技術がありました。
いま室内を照らしている電気というものしかり。
トメさんが電気をつけたら、夜なのに昼のような明るさになったのです。
だいたいどの家にも当たり前にあるものだと言われて、魔王は度肝を抜かれました。
とにかく赤ちゃんのため、言われるまま湯の温度調節して、粉ミルクをよく溶かします。
赤ちゃんを抱っこして、哺乳びんの吸いくちを赤ちゃんの口元に持っていきます。
赤ちゃんは誰に教わるでもなく、本能でそれがミルクだとわかるようです。いっぱい飲んできゃっきゃと笑います。
「おお、うまいか。儂が作ったのだから心して飲むが良いぞ」
楽しげに赤ちゃんの世話をする魔王を見てトメさんはつぶやきます。
「しかし登呂さんも奇特な人じゃな。見ず知らずの子を、よう川に飛び込んで助けようと思ったのう」
「ぬう。お主も今、食べ物を作ったり服をくれたり、儂を助けてくれておるだろう。助けるのに理由が必要なのか? 人とは不思議な生き物よ」
魔王の言葉に、トメさんはハッとしました。
トメさんも、ただただ、「登呂さんは記憶をなくして何かと大変だろう」と思い、見返りがほしいわけでもなく手助けしていました。
それと同じこと。打算や理屈なんてないのでしょう。
どこかトンチンカンなこの人のことを、トメさんはこの半日でとても気に入りました。
記憶をなくす前からこういう風に、朗らかで大きな心を持つひとだったのだと思えます。
ミルクをあげてから一時間も経たないうちに赤ちゃんが泣きだしてしまいました。
どうやらウンチのようです。
トメさんに教えられるまま、たどたどしい手つきでオムツをとりかえますが、それでも泣き止んでくれません。
「ふぬおおお、どうしろというのだ。お腹いっぱいだろ、オムツもかえた。なのになぜまだ泣くのだっ!?」
「落ち着きなさいな、登呂さん。アンタが落ち着かんとその子も落ち着かんよ。ちょっとこの子をおんぶして、外の空気を吸ってきなさいな」
赤ちゃんが背中から落ちないよう、おんぶ紐でしっかり固定して、寒くないようにとその上から袢纏 をはおります。
そのまま魔王は夜風に吹かれながら、近所を歩きます。見上げた月は遠く。
元の世界の月は双子月といって、二つ並んでいましたがここでは一つしかない。
違う世界に来たんだなと月を眺めながら改めて思います。
「ほうれ。早く眠るのだ。あーと、名前がないと呼びにくいのう。うん、リュウと呼ぼう。この国でドラゴンを指す言葉だと本に書いてあった。儂の幹部なのだからそうとわかる名にせんとな」
魔王の背中が温かいのか、それとも歩調が心地いいのか。いつの間にかリュウは安らかな寝息をたてていました。
「よいかリュウ。たくさん寝るのだ。寝る子は育つとトメが言っていた。早く大きくなって、この国を統べるがよい」
リュウを起こさないようゆっくり歩きながら、魔王はのどか荘への帰路につきました。

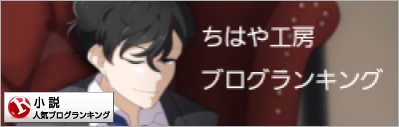
理由がわからずオロオロする魔王。泣く子も黙る巨大なドラゴンと呼ばれていたのに、形無しです。
対するトメさんは落ち着いたもの。子どもを一人立派に育て上げた女性なので場数が違います。
「この泣き方。お腹が空いたようだね」
「わかるのか。すごいのう」
「もう五十年は前だが、おれは子育てをしとったんだ。わかるに決まっている。ご近所で粉ミルクをもらってきたから作ろうかい。哺乳びんも、向井さんからもらったんだ」
「うむ。なにからなにまで助かるのう、トメ」
トメさんが電気ポットの蓋を押すとお湯が出てきたので、魔王は驚きます。
「うぬぅ。このような鉄の筒に湯が保存されておるのか? このような技術があるとは、人間はあなどれんの」
「かっかっか。電気ポットがスゴイなら、もうテレビでも炊飯器でも、なんでも目新しかろうなぁ」
この世界に魔法はないけれど、魔法に匹敵するような技術がありました。
いま室内を照らしている電気というものしかり。
トメさんが電気をつけたら、夜なのに昼のような明るさになったのです。
だいたいどの家にも当たり前にあるものだと言われて、魔王は度肝を抜かれました。
とにかく赤ちゃんのため、言われるまま湯の温度調節して、粉ミルクをよく溶かします。
赤ちゃんを抱っこして、哺乳びんの吸いくちを赤ちゃんの口元に持っていきます。
赤ちゃんは誰に教わるでもなく、本能でそれがミルクだとわかるようです。いっぱい飲んできゃっきゃと笑います。
「おお、うまいか。儂が作ったのだから心して飲むが良いぞ」
楽しげに赤ちゃんの世話をする魔王を見てトメさんはつぶやきます。
「しかし登呂さんも奇特な人じゃな。見ず知らずの子を、よう川に飛び込んで助けようと思ったのう」
「ぬう。お主も今、食べ物を作ったり服をくれたり、儂を助けてくれておるだろう。助けるのに理由が必要なのか? 人とは不思議な生き物よ」
魔王の言葉に、トメさんはハッとしました。
トメさんも、ただただ、「登呂さんは記憶をなくして何かと大変だろう」と思い、見返りがほしいわけでもなく手助けしていました。
それと同じこと。打算や理屈なんてないのでしょう。
どこかトンチンカンなこの人のことを、トメさんはこの半日でとても気に入りました。
記憶をなくす前からこういう風に、朗らかで大きな心を持つひとだったのだと思えます。
ミルクをあげてから一時間も経たないうちに赤ちゃんが泣きだしてしまいました。
どうやらウンチのようです。
トメさんに教えられるまま、たどたどしい手つきでオムツをとりかえますが、それでも泣き止んでくれません。
「ふぬおおお、どうしろというのだ。お腹いっぱいだろ、オムツもかえた。なのになぜまだ泣くのだっ!?」
「落ち着きなさいな、登呂さん。アンタが落ち着かんとその子も落ち着かんよ。ちょっとこの子をおんぶして、外の空気を吸ってきなさいな」
赤ちゃんが背中から落ちないよう、おんぶ紐でしっかり固定して、寒くないようにとその上から
そのまま魔王は夜風に吹かれながら、近所を歩きます。見上げた月は遠く。
元の世界の月は双子月といって、二つ並んでいましたがここでは一つしかない。
違う世界に来たんだなと月を眺めながら改めて思います。
「ほうれ。早く眠るのだ。あーと、名前がないと呼びにくいのう。うん、リュウと呼ぼう。この国でドラゴンを指す言葉だと本に書いてあった。儂の幹部なのだからそうとわかる名にせんとな」
魔王の背中が温かいのか、それとも歩調が心地いいのか。いつの間にかリュウは安らかな寝息をたてていました。
「よいかリュウ。たくさん寝るのだ。寝る子は育つとトメが言っていた。早く大きくなって、この国を統べるがよい」
リュウを起こさないようゆっくり歩きながら、魔王はのどか荘への帰路につきました。
