ユーメシ! 〜ゲーム実況ユーチューバーの異世界メシテロ〜
スライムを食べたあとは家の裏手に出た。
雑草だらけのこじんまりした畑を前にして、ミミから古びたクワを渡された。
木製の柄の先端に平たい鉄板、まごうことなきクワ。
「これは」
「のうぐ、しらない?」
「知ってるよ。触ったことないけど、日本にもこういう農具はあった。この世界にもあるんだなって思っただけ」
「しってるなら、はなしはやい。はたけをたがやす、たねをまく。みずやり。やさいは、じぶんでそだてる」
「よっし! 任しときな! 働かざるもの食うべからずって言うからな。食った分働くぜ」
ミミのようなちびっこじゃ農作業はきついだろうし。力仕事はオレがやろう。
雑草を引っこ抜いて土が柔らかくなるよう耕す、種まきと水やり。楽ショーだぜ! 1時間もいらねー。
──と思っていた30分前の自分を殴りてぇ。
しゃがむ姿勢なんて普段あまりしないから、膝の裏とふくらはぎが痛い。足の筋肉全体が悲鳴を上げている。
くそう。ゲームで見てるときはAボタンやXボタン押すだけだったのに。
そうだよな。これはゲームじゃなくて現実なんだよ。
まくりあげた袖の形にそって、腕が日焼けしている。日差しも強えな。服に汗がしみて肌に張り付く。
うん、金を稼げるようになったら肌着を買おうか。
「キムラン、おつかれさま」
「ありがとな、ミミ!」
ミミがうすく紅色のついた水をコップに入れて手渡してくれた。
飲んでみると、舌先にほんのり岩塩に似た塩味を感じる。汗で失われた塩分が戻ってくる。異世界版スポーツドリンクか。
「いどみずに、ハルルのみつと、しおいれた。つかれたときにいい」
「そっか。美味いなこれ」
スポドリを飲み干して、次は土を耕そう。
「クワってどう持って振るのが正しいんだ?」
とりあえず牧場ゲームで見たみたいに高く振り上げて振り下ろしてみるけど、目当てのところじゃない方向に刺さってしまってうまくいかない。
農家の皆さん、農業を侮っていてごめんなさい。これからはもっと生産者に感謝して食べます……。
いつまでも耕すのが進まない。みかねたらしい隣の住人が出てきた。
10才そこそこで小柄な、金髪の少年だ。
「お兄さん。こうやって持って、斜め上から土に刺して、土を手前に持ち上げるようにしてください。あんまり大きく振り上げると手元が狂うので、この高さで」
「そうなのか。知らなかったよ。ありがとう。助かる!」
年齢にそぐわぬ穏やかな口調の少年にレクチャーされ、初心者のオレでも、ある程度土を耕すことができた。
ここまでくれば残るは種まきと水やりだな。あとは自分でがんばろう。
ひと通り教えてくれたあと、少年が言う。
「自己紹介がまだでしたね。ぼくはナルシェ。隣の家で従姉のオリビア姉さんと暮らしています。
貴方のことは、村長さんから聞きました。貴方がミミちゃんの保護者になってくれるって。みんなミミちゃんの今後を心配していたので、助かります」
本当はミミが「わたしがキムランをやしなう」って言ったんだけど、ゴルドさんはオレの世間体を気にして“オレが保護者役になると言い出した”ということにしてくれたらしい。
「そういうことになってるのか………」
「へ?」
「あ、いや、こっちの話。オレはキムラン。この世界について知らないことも多いから、また何かあったら頼ると思う。よろしくな」
「はい。よろしくお願いします」
うう、なんて礼儀正しい子だ。お兄さん感動しちゃったよ。実家の弟なんて反抗期でクソ兄だの邪魔だの言ってたのに。泣けるわー。
話し込んでいると、ナルシェの家から女性の間延びした声が聞こえてきた。
「ナルシェくーん、お肉入れたらスープが変な色になったの〜」
「うわあああああ!! 駄目! 頼むから姉さんは鍋に触らないで!!」
ナルシェが真っ青になって家にかけ戻る。
入れ替わるようにして、20歳そこそこの女性が出てきた。
背中まである緩やかな銀髪に水色の瞳、おっとりした雰囲気の人だ。日本にいたら超モテるね。
「あら、ちょうどいいところに! ミミちゃんの親戚のキムランさんですよね。お引越し祝いにスープを作ったんです。ミミちゃんと食べてくださいな」
女性が自信満々にフタを開けた鍋の中身は…………………。
え、なにこれドブ川の水?
焦げて黒ずんだ液体に、ドロドロに溶けた何かが浮いている。鍋からは、腐った生ゴミみたいなエグい臭いも漂ってくる。
オレの本能が『これはゲテモノだ。食うな』と警鐘を鳴らしている。
「ええと、これはいったい」
もしかしたらこの世界の一般的な料理かもしれないから、念の為聞いてみる。
「オリビア姉さん、頼むから料理作るのやめてって言ったでしょう!!」
「えぇ〜。ナルシェくんひどい! わたしは純粋にお隣さんが増えたお祝いを」
「頼むから! 祝う気があるなら洗濯と掃除以外何もしないで。一生のお願い!!」
ぷぅ、とほほをふくらませてスネるオリビアさんに、ナルシェが懇願した。
1時間ほどして、ナルシェがまともなスープを持ってきてくれた。多分あのゲテモノスープの製作者は………。心労を察するぞ、少年。
使った肉は、森に出る鳥型モンスターのものだという。
さっきのスライムといい、この世界では普通にモンスターを料理するんだな。
透明度の高い黄金色のスープに、一口大に切られた肉が沈んでいる。スプーンですくい上げていただく。
「おおお……肉の歯ごたえはぷりぷり。弾力があるが軽くかみちぎれる。きちんと下処理もしているからこそか。このいい香りの野菜はなんだろう」
「しろいホクホクのはマルイモ。あかいのはニンジャ。においけしのやさい」
ミミ先生の解説が光る。ニンジャは忍法の忍者じゃないわね。
「なるほどこいつは香味野菜なんだな。ふふふ。野菜が肉の臭みを打ち消して相乗効果を発揮し、えーと、つまりなんていうか、この料理めっちゃうまい!! 少年を嫁にほしい!」
はっはっは。異世界メシについてかっこいいこと言おうと思ったが、オレにはグルメ番組のリポーターみたいなのは無理だった。
まあ、とにかくこのスープは美味い。
ミミがスプーンをくわえてジト目になる。
「……キムランは、だまってたべられないのか」
「あ、それオレがウルサイって言ってる?」
「おお、わかるか」
ウルサイと言いつつも、ミミは笑顔だ。
長らく独り暮らししていたから、こうしてごはんをともにする相手がいるっていうのも久しぶりだ。
やっぱり、誰かと一緒にごはんを食べるのは楽しいんだな。
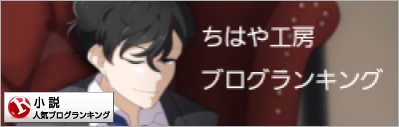
雑草だらけのこじんまりした畑を前にして、ミミから古びたクワを渡された。
木製の柄の先端に平たい鉄板、まごうことなきクワ。
「これは」
「のうぐ、しらない?」
「知ってるよ。触ったことないけど、日本にもこういう農具はあった。この世界にもあるんだなって思っただけ」
「しってるなら、はなしはやい。はたけをたがやす、たねをまく。みずやり。やさいは、じぶんでそだてる」
「よっし! 任しときな! 働かざるもの食うべからずって言うからな。食った分働くぜ」
ミミのようなちびっこじゃ農作業はきついだろうし。力仕事はオレがやろう。
雑草を引っこ抜いて土が柔らかくなるよう耕す、種まきと水やり。楽ショーだぜ! 1時間もいらねー。
──と思っていた30分前の自分を殴りてぇ。
しゃがむ姿勢なんて普段あまりしないから、膝の裏とふくらはぎが痛い。足の筋肉全体が悲鳴を上げている。
くそう。ゲームで見てるときはAボタンやXボタン押すだけだったのに。
そうだよな。これはゲームじゃなくて現実なんだよ。
まくりあげた袖の形にそって、腕が日焼けしている。日差しも強えな。服に汗がしみて肌に張り付く。
うん、金を稼げるようになったら肌着を買おうか。
「キムラン、おつかれさま」
「ありがとな、ミミ!」
ミミがうすく紅色のついた水をコップに入れて手渡してくれた。
飲んでみると、舌先にほんのり岩塩に似た塩味を感じる。汗で失われた塩分が戻ってくる。異世界版スポーツドリンクか。
「いどみずに、ハルルのみつと、しおいれた。つかれたときにいい」
「そっか。美味いなこれ」
スポドリを飲み干して、次は土を耕そう。
「クワってどう持って振るのが正しいんだ?」
とりあえず牧場ゲームで見たみたいに高く振り上げて振り下ろしてみるけど、目当てのところじゃない方向に刺さってしまってうまくいかない。
農家の皆さん、農業を侮っていてごめんなさい。これからはもっと生産者に感謝して食べます……。
いつまでも耕すのが進まない。みかねたらしい隣の住人が出てきた。
10才そこそこで小柄な、金髪の少年だ。
「お兄さん。こうやって持って、斜め上から土に刺して、土を手前に持ち上げるようにしてください。あんまり大きく振り上げると手元が狂うので、この高さで」
「そうなのか。知らなかったよ。ありがとう。助かる!」
年齢にそぐわぬ穏やかな口調の少年にレクチャーされ、初心者のオレでも、ある程度土を耕すことができた。
ここまでくれば残るは種まきと水やりだな。あとは自分でがんばろう。
ひと通り教えてくれたあと、少年が言う。
「自己紹介がまだでしたね。ぼくはナルシェ。隣の家で従姉のオリビア姉さんと暮らしています。
貴方のことは、村長さんから聞きました。貴方がミミちゃんの保護者になってくれるって。みんなミミちゃんの今後を心配していたので、助かります」
本当はミミが「わたしがキムランをやしなう」って言ったんだけど、ゴルドさんはオレの世間体を気にして“オレが保護者役になると言い出した”ということにしてくれたらしい。
「そういうことになってるのか………」
「へ?」
「あ、いや、こっちの話。オレはキムラン。この世界について知らないことも多いから、また何かあったら頼ると思う。よろしくな」
「はい。よろしくお願いします」
うう、なんて礼儀正しい子だ。お兄さん感動しちゃったよ。実家の弟なんて反抗期でクソ兄だの邪魔だの言ってたのに。泣けるわー。
話し込んでいると、ナルシェの家から女性の間延びした声が聞こえてきた。
「ナルシェくーん、お肉入れたらスープが変な色になったの〜」
「うわあああああ!! 駄目! 頼むから姉さんは鍋に触らないで!!」
ナルシェが真っ青になって家にかけ戻る。
入れ替わるようにして、20歳そこそこの女性が出てきた。
背中まである緩やかな銀髪に水色の瞳、おっとりした雰囲気の人だ。日本にいたら超モテるね。
「あら、ちょうどいいところに! ミミちゃんの親戚のキムランさんですよね。お引越し祝いにスープを作ったんです。ミミちゃんと食べてくださいな」
女性が自信満々にフタを開けた鍋の中身は…………………。
え、なにこれドブ川の水?
焦げて黒ずんだ液体に、ドロドロに溶けた何かが浮いている。鍋からは、腐った生ゴミみたいなエグい臭いも漂ってくる。
オレの本能が『これはゲテモノだ。食うな』と警鐘を鳴らしている。
「ええと、これはいったい」
もしかしたらこの世界の一般的な料理かもしれないから、念の為聞いてみる。
「オリビア姉さん、頼むから料理作るのやめてって言ったでしょう!!」
「えぇ〜。ナルシェくんひどい! わたしは純粋にお隣さんが増えたお祝いを」
「頼むから! 祝う気があるなら洗濯と掃除以外何もしないで。一生のお願い!!」
ぷぅ、とほほをふくらませてスネるオリビアさんに、ナルシェが懇願した。
1時間ほどして、ナルシェがまともなスープを持ってきてくれた。多分あのゲテモノスープの製作者は………。心労を察するぞ、少年。
使った肉は、森に出る鳥型モンスターのものだという。
さっきのスライムといい、この世界では普通にモンスターを料理するんだな。
透明度の高い黄金色のスープに、一口大に切られた肉が沈んでいる。スプーンですくい上げていただく。
「おおお……肉の歯ごたえはぷりぷり。弾力があるが軽くかみちぎれる。きちんと下処理もしているからこそか。このいい香りの野菜はなんだろう」
「しろいホクホクのはマルイモ。あかいのはニンジャ。においけしのやさい」
ミミ先生の解説が光る。ニンジャは忍法の忍者じゃないわね。
「なるほどこいつは香味野菜なんだな。ふふふ。野菜が肉の臭みを打ち消して相乗効果を発揮し、えーと、つまりなんていうか、この料理めっちゃうまい!! 少年を嫁にほしい!」
はっはっは。異世界メシについてかっこいいこと言おうと思ったが、オレにはグルメ番組のリポーターみたいなのは無理だった。
まあ、とにかくこのスープは美味い。
ミミがスプーンをくわえてジト目になる。
「……キムランは、だまってたべられないのか」
「あ、それオレがウルサイって言ってる?」
「おお、わかるか」
ウルサイと言いつつも、ミミは笑顔だ。
長らく独り暮らししていたから、こうしてごはんをともにする相手がいるっていうのも久しぶりだ。
やっぱり、誰かと一緒にごはんを食べるのは楽しいんだな。
