ユーメシ! 〜ゲーム実況ユーチューバーの異世界メシテロ〜
「ここ、わたしのいえ」
ミミに連れられて、ゴルドさんちの二軒となりの家に入った。
「すきにつかえ、キムラン」
「あー、あのさ。行くあてもなかったし、オレとしては住まわせてもらえるのは嬉しいけど、勝手に決めちゃっていいの? ミミの親御さんに相談しなくていいのか?」
「おや、せんげつしんだ。わたししか、いない」
ミミは顔色を変えずにとんでもないことを言う。
「あ……ごめん。………ミミ、一人なのか」
五才かそこらの幼子が、たった一人で生きる。日本じゃ考えられない。
なんて言っていいのかわからない気持ちが、胸の中でぐるぐるまわる。元の世界に帰る方法を探したい、という気持ちはあるけれど、それよりもミミをひとりぼっちにしておきたくない、という気持ちのほうが勝った。
「ひとり、ちがう。きょうから、ふたり。キムランいる」
「そうだな。オレがいるから二人暮らしだな」
不安にさせないよう、ミミの言葉を肯定する。オレはうまく笑えているだろうか。
ミミは棚をゴソゴソとさぐり、なにかを取り出した。
フライパン? うん。まごうことなきフライパンだ。
背が低くて調理台に届かないからか、踏み台を持ってきてそれに乗る。そしてフライパンを赤い石の上に置くと、ジュ、と鉄の焼ける音がした。
「これ、まほうぐ。あつい」
「へ〜。この世界のコンロってわけか。すっげーーー! オレ、生の魔法を見たのは初めてだ」
「なまのまほう、ちがう。これ、ひのまほう」
「火の魔法な、わかった」
フライパンがあたたまったところで、ミミが1メートル四方くらいの石の箱を開けた。同時に、中から白い冷気が漂ってくる。
魔法のコンロがあるなら、こっちは魔法の冷蔵庫か。
「そんちょがくれた、すらいむのにくがある」
「スライムの肉……」
「ぷるぷる、おなかにやさしいヨ」
溶解液で地面溶けてたけど……食えるのかあいつら。食ったら口の中溶けたりしないよな。
オレの不安をよそに、ミミは半透明のぷるぷるを一センチほどの厚さに切り分ける。大きな木の葉にスライム肉を置いて、ピンクの顆粒をふりかける。調味料だな。
調味料を振ったスライム肉を麺棒でペンペン叩く。
熱々になったフライパンに油(たぶん)をしいて、よく叩いたスライム肉を投入する。 ジュワ! しぶきがあがってスライムの水分が飛ぶ。
半透明だったスライム肉は、火が通るにつれて白身魚のような、品のある白い色へと変わった。
香りもバターソテーのよう。やべぇ、よだれが。
木べらで器用にひっくり返して、きつね色に焼けた面が上に来る。両面よく焼けたら木皿に盛り付けて、完成。
ミミはオレの反応をじっと見て、ドヤ顔になる。
「たべろ。あつあつが、うまい」
「ありがとうミミ。いただきまーす!」
「キムラン。いただきます、とは?」
「いただきますっていうのはだな、オレの世界でごはんを食べるときのあいさつだ」
木を粗く削って作られたフォークをさす。ふわりとほぐれる白身。戦ったときのエゲツない弾力がうそのようだ。
「おおおお、口に広がるうすしお味。口当たりなめらか。腹が痛かったから、素朴な甘じょっぱいたべものは口にもやさしいな。口の中が幸せにみちあふれているぜ!!」
オレの中のユーチューバーの魂が、このスライムの旨さを讃えろと叫んでいる。この世界にビデオカメラがあるなら、高画質録画して永久保存版にする。
ミミはハルルのみつをコップに注いで、オレの前においてくれる。
「ごっごっごっ。プハー! スライム肉はハルルのみつとの相性も抜群だな!」
「キムラン、うるさい」
「わりーわりー。あまりのうまさに叫んじまった!」
「……そうか、うまいか」
ミミは自分の分をオレの向かいに用意して、椅子に腰掛ける。それから目を閉じて、両手の平を胸に乗せて交差させる。
「きょうも、アマツカミのめぐみにかんしゃします」
「へー。じゃあオレも郷に入っては郷に従えってことで。今日もアマツカミの恵みに感謝します」
ミミが作ってくれた歓迎のスライムステーキはとても美味しくて、2回もおかわりしてしまった。
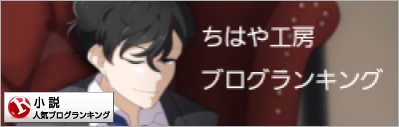

ミミに連れられて、ゴルドさんちの二軒となりの家に入った。
「すきにつかえ、キムラン」
「あー、あのさ。行くあてもなかったし、オレとしては住まわせてもらえるのは嬉しいけど、勝手に決めちゃっていいの? ミミの親御さんに相談しなくていいのか?」
「おや、せんげつしんだ。わたししか、いない」
ミミは顔色を変えずにとんでもないことを言う。
「あ……ごめん。………ミミ、一人なのか」
五才かそこらの幼子が、たった一人で生きる。日本じゃ考えられない。
なんて言っていいのかわからない気持ちが、胸の中でぐるぐるまわる。元の世界に帰る方法を探したい、という気持ちはあるけれど、それよりもミミをひとりぼっちにしておきたくない、という気持ちのほうが勝った。
「ひとり、ちがう。きょうから、ふたり。キムランいる」
「そうだな。オレがいるから二人暮らしだな」
不安にさせないよう、ミミの言葉を肯定する。オレはうまく笑えているだろうか。
ミミは棚をゴソゴソとさぐり、なにかを取り出した。
フライパン? うん。まごうことなきフライパンだ。
背が低くて調理台に届かないからか、踏み台を持ってきてそれに乗る。そしてフライパンを赤い石の上に置くと、ジュ、と鉄の焼ける音がした。
「これ、まほうぐ。あつい」
「へ〜。この世界のコンロってわけか。すっげーーー! オレ、生の魔法を見たのは初めてだ」
「なまのまほう、ちがう。これ、ひのまほう」
「火の魔法な、わかった」
フライパンがあたたまったところで、ミミが1メートル四方くらいの石の箱を開けた。同時に、中から白い冷気が漂ってくる。
魔法のコンロがあるなら、こっちは魔法の冷蔵庫か。
「そんちょがくれた、すらいむのにくがある」
「スライムの肉……」
「ぷるぷる、おなかにやさしいヨ」
溶解液で地面溶けてたけど……食えるのかあいつら。食ったら口の中溶けたりしないよな。
オレの不安をよそに、ミミは半透明のぷるぷるを一センチほどの厚さに切り分ける。大きな木の葉にスライム肉を置いて、ピンクの顆粒をふりかける。調味料だな。
調味料を振ったスライム肉を麺棒でペンペン叩く。
熱々になったフライパンに油(たぶん)をしいて、よく叩いたスライム肉を投入する。 ジュワ! しぶきがあがってスライムの水分が飛ぶ。
半透明だったスライム肉は、火が通るにつれて白身魚のような、品のある白い色へと変わった。
香りもバターソテーのよう。やべぇ、よだれが。
木べらで器用にひっくり返して、きつね色に焼けた面が上に来る。両面よく焼けたら木皿に盛り付けて、完成。
ミミはオレの反応をじっと見て、ドヤ顔になる。
「たべろ。あつあつが、うまい」
「ありがとうミミ。いただきまーす!」
「キムラン。いただきます、とは?」
「いただきますっていうのはだな、オレの世界でごはんを食べるときのあいさつだ」
木を粗く削って作られたフォークをさす。ふわりとほぐれる白身。戦ったときのエゲツない弾力がうそのようだ。
「おおおお、口に広がるうすしお味。口当たりなめらか。腹が痛かったから、素朴な甘じょっぱいたべものは口にもやさしいな。口の中が幸せにみちあふれているぜ!!」
オレの中のユーチューバーの魂が、このスライムの旨さを讃えろと叫んでいる。この世界にビデオカメラがあるなら、高画質録画して永久保存版にする。
ミミはハルルのみつをコップに注いで、オレの前においてくれる。
「ごっごっごっ。プハー! スライム肉はハルルのみつとの相性も抜群だな!」
「キムラン、うるさい」
「わりーわりー。あまりのうまさに叫んじまった!」
「……そうか、うまいか」
ミミは自分の分をオレの向かいに用意して、椅子に腰掛ける。それから目を閉じて、両手の平を胸に乗せて交差させる。
「きょうも、アマツカミのめぐみにかんしゃします」
「へー。じゃあオレも郷に入っては郷に従えってことで。今日もアマツカミの恵みに感謝します」
ミミが作ってくれた歓迎のスライムステーキはとても美味しくて、2回もおかわりしてしまった。
