一章 セツカと時の鎖
「助けてくださってありがとうございます」
俺とリーンは揃ってフェンさんに頭を下げる。
この人は貴族の中でもそれなりに発言力がある人だろう。
あれだけ上から目線だった令息たちが、フェンさんの顔を見た途端逃げ出すんだから。
フェンさんは手を横に振って、大したことしてないと笑う。
「君、勇気があるね。未成年とはいえ、彼は炎魔法士。下手すると焼き殺されるよ。適当に謝って場を丸くおさめようって思わなかったのかい」
「リーンは何も悪くないのに、謝るのはおかしいでしょう」
理不尽な言いがかりで絡まれていたのだから、こちらが謝る理由は何もない。
「危なっかしいねぇ。でも、嫌いじゃないよ、そういうの」
口元に手を当てて笑うフェンさん。光魔法の残滓で手のひらがほのかに光っている。
「失礼かもしれませんが、あなたは魔法士なのに、名前が花じゃないんですか」
魔法を使える人間は生まれながらに髪か瞳、あるいは両方に黒が発現する。貴族は魔法を持って生まれた子どもには花か樹木の名前をつける。
俺の知る限り、フェンという名の花はない。
「フェンはあだ名だよ。そもそも、ボクは貴族の風習、嫌いなんだ。髪か瞳が黒なら花の名前をつけるってやつ。さっきの子たち、心根は貴 くないじゃない」
「そうですね」
アーノルドさんの知人なだけあって、フェンさんは色で人を判断するタイプじゃないみたいだ。
「あなたの探しているマーズ家は、俺が働いているところです。この子はアーノルドさんの娘のアイリーン。屋敷までご案内します」
「助かるよ、セツカくん」
フェンさんを屋敷まで案内してから、すぐに着替える。濡れた服を絞って、部屋の窓際に吊るす。
アーノルドさんに頼まれていた買い物がまだ残っているから、済ませておかないと。
傘をさして再び西地区に向かうと、ブーツが雨を弾く音が追ってきた。
「セツカ、待って!」
リーンだ。傘を振り上げて水たまりを飛び越え、肩で息をしながら俺を見上げる。
「どうしたんだ」
「お礼、ちゃんと言えてなかったから。さっきは助けに来てくれてありがとう」
「俺は何もできていない。助けたのは俺じゃなくてフェンさんだろ」
むしろ俺が余計なことをしたから、あいつらを逆上させた。危険に晒してしまって申し訳ない気持ちでいっぱいだ。
「ううん。私を守ろうとしてくれて、庇ってくれて、すごく、嬉しかったの。だから、ありがとう、セツカ」
リーンは目を細めてふんわり笑う。
「お仕事、終わったんじゃないの? まだ用事がある?」
「アーノルドさんに買い物を頼まれてる。リーンに、感謝祭の贈り物をしたいから選んでくれって」
「じゃあ私も行く! いいでしょ? ね?」
「……君ってひとは、まったく。俺といたのがジーナさんにバレたら怒られるよ?」
執事長たちにバレたら大目玉を食らうのは確実。
けど、説得して追い返したところでついてくるのがリーンだ。
二人でアクセサリー屋に入ったら、店員に「恋人への贈り物ですか?」なんて勘違いされてしまったから、やっぱり追い返したほうがよかったかもしれない。
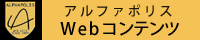


俺とリーンは揃ってフェンさんに頭を下げる。
この人は貴族の中でもそれなりに発言力がある人だろう。
あれだけ上から目線だった令息たちが、フェンさんの顔を見た途端逃げ出すんだから。
フェンさんは手を横に振って、大したことしてないと笑う。
「君、勇気があるね。未成年とはいえ、彼は炎魔法士。下手すると焼き殺されるよ。適当に謝って場を丸くおさめようって思わなかったのかい」
「リーンは何も悪くないのに、謝るのはおかしいでしょう」
理不尽な言いがかりで絡まれていたのだから、こちらが謝る理由は何もない。
「危なっかしいねぇ。でも、嫌いじゃないよ、そういうの」
口元に手を当てて笑うフェンさん。光魔法の残滓で手のひらがほのかに光っている。
「失礼かもしれませんが、あなたは魔法士なのに、名前が花じゃないんですか」
魔法を使える人間は生まれながらに髪か瞳、あるいは両方に黒が発現する。貴族は魔法を持って生まれた子どもには花か樹木の名前をつける。
俺の知る限り、フェンという名の花はない。
「フェンはあだ名だよ。そもそも、ボクは貴族の風習、嫌いなんだ。髪か瞳が黒なら花の名前をつけるってやつ。さっきの子たち、心根は
「そうですね」
アーノルドさんの知人なだけあって、フェンさんは色で人を判断するタイプじゃないみたいだ。
「あなたの探しているマーズ家は、俺が働いているところです。この子はアーノルドさんの娘のアイリーン。屋敷までご案内します」
「助かるよ、セツカくん」
フェンさんを屋敷まで案内してから、すぐに着替える。濡れた服を絞って、部屋の窓際に吊るす。
アーノルドさんに頼まれていた買い物がまだ残っているから、済ませておかないと。
傘をさして再び西地区に向かうと、ブーツが雨を弾く音が追ってきた。
「セツカ、待って!」
リーンだ。傘を振り上げて水たまりを飛び越え、肩で息をしながら俺を見上げる。
「どうしたんだ」
「お礼、ちゃんと言えてなかったから。さっきは助けに来てくれてありがとう」
「俺は何もできていない。助けたのは俺じゃなくてフェンさんだろ」
むしろ俺が余計なことをしたから、あいつらを逆上させた。危険に晒してしまって申し訳ない気持ちでいっぱいだ。
「ううん。私を守ろうとしてくれて、庇ってくれて、すごく、嬉しかったの。だから、ありがとう、セツカ」
リーンは目を細めてふんわり笑う。
「お仕事、終わったんじゃないの? まだ用事がある?」
「アーノルドさんに買い物を頼まれてる。リーンに、感謝祭の贈り物をしたいから選んでくれって」
「じゃあ私も行く! いいでしょ? ね?」
「……君ってひとは、まったく。俺といたのがジーナさんにバレたら怒られるよ?」
執事長たちにバレたら大目玉を食らうのは確実。
けど、説得して追い返したところでついてくるのがリーンだ。
二人でアクセサリー屋に入ったら、店員に「恋人への贈り物ですか?」なんて勘違いされてしまったから、やっぱり追い返したほうがよかったかもしれない。
