二章 アイセと声無き少女
翌朝。
せっちゃんの私室に行くと、せっちゃんは本を読んでいた。
こちらに見える背表紙はサウザン文字のもの。ボクにはなにが書かれているかわからない。
「おはよ。相変わらず朝が早いね」
「庭師だったころの癖が抜けないんだ」
「日の出より早く起きるんだっけ。おじいちゃんみたい」
一言多いよ、と心の突っ込みを食らった。
怒らせるつもりで言ったわけじゃないのにな。
「素直なのは悪いことではないけれど、雄弁は銀、寡黙は金という言葉がある」
「マリアにもよく言われるよ。その口を塞いどけって」
「…………そうだろうな」
あきれた目をされた。
「愛の神子様もお目覚めでしたか。おはようございます」
「どうも」
男性神官の、なんだっけ。ヤマトか。ヤマトが入ってきてお辞儀をする。
「愛の神子様。マーガレットが起きたら確かめていただきたいことがあるのです」
「なに?」
「食べられないものがあったら知りたいです。ここに来たばかりの数日は、口をつけてくれないものばかりで。会話ができないし文字の読み書きもできないから、確認しようがなくて」
「あー、なるほど」
昨日の夕食の風景を見ているかぎりだと、あんまお行儀よくなかったんだよな。
一応貴族令嬢のお嬢ちゃんと並んで食べていたから、違いがよくわかった。
ミートパイを手づかみで食べようとするし、スプーンの持ち方がおかしいし。
貴族として育っていないような気がした。
「ヤマト。マーガレットは鳥肉が嫌いみたいだ。こう、巧みに皮のカケラを除けて食べようとする姿が誰かさんと同じだったから。栄養素が近い別のものを代用した方がよさそうだよ」
せっちゃんが本から顔を上げてポツリとつぶやく。
「誰かさんって誰さ。お嬢ちゃんは美味しいって言って完食してたから違うよね」
「……え?」
自分で言っておいてよく分かっていないのか、せっちゃんは首をかしげる。
「僕、そんなこと言った?」
「たった今自分で言ったのに覚えてないの? やっぱおじいちゃんなんじゃ」
睨まれたから口を閉じることにした。
マーガレットとお嬢ちゃんも起きてきて、神官のみんなが朝食の準備にとりかかる。
マーガレットはせっちゃん指導の下、白い紙に羽ペンでなにか書こうとやっきになっている。絵、ではなさそうだ。
「なにをしているところ?」
「文字を教えているんだ。アイセもずっとここにいられるわけじゃないだろう。筆談できるようになればアイセの負担が減る」
「それはどうも」
これまで文字を書いたこともないらしい。
せっちゃんが書いたマーガレットの名前を手本にして、自分の手元と手本を何度も見比べているが、インクがべちゃべちゃになって手が真っ黒だ。
「慣れるまでこれ使う?」
お嬢ちゃんがパンパンに膨らんだ鞄をひっくり返した。飛び散った荷物の中から、クレヨンセットを引っ張り出す。
相変わらず豪快だな……と、せっちゃんは思っても口にしない。
散ったあれこれを回収してそっと鞄に押し込む。
黙っていた方がいいってのはこういう場面ね。察した。
『リーンさん、ありがと』
口パクでも、お嬢ちゃんには伝わった。お嬢ちゃんは笑顔でマーガレットの頭をなでる。
気を取り直して、マーガレットはクレヨンで文字の練習を再開した。
朝食のあと、お嬢ちゃんが帰るのをマーガレットは泣いて惜しんだ。ボクへのあたりが強かったのに、お嬢ちゃんには懐くの早すぎない?
それから一時間もしないうちに、普段使わない頭をたくさん使って疲れたのか、クレヨンを持ったまま寝落ちした。
神官のソレイユが毛糸のブランケットをマーガレットの背中にかける。
「疲れて昼寝とか、完全にオコチャマだよねぇ……」
「そう言うなよアイセ。家族を亡くしたばかりで、知り合いが一人もいない生活をすることになったんだから、精神的にも疲れるのは仕方ないさ」
今の環境に慣れようと、マーガレットは必死になっている。また犯人がくるんじゃないかという恐怖と戦い、明日どこに身を置くことになるかもわからない。
「一応聞くけどさ。犯人が捕まったとして、この子そのあとどこに行くことになるの? 養子にほしいって貴族が出ない限りは孤児院? 貴族の子が孤児院行きになるパターン、ある?」
「珍しいみたいに言うけれど、君もすでに会ったことがあるだろう?」
「誰それ」
孤児院育ちの貴族に会ったことがある? ボクが?
「貴族は魔法のない子を殺すか捨てる。この捨てるっていうのは、孤児院に置いていくのも含む」
孤児院に捨てられた、魔法を持たない貴族?
なんだかこれ以上聞いちゃいけない気がして、ボクは口を閉ざす。
マーガレットがみじろぎして、ブランケットがずり落ちそうになる。
うなされている。まゆをひそめて、苦しそうだ。
『あかい、目、ひのまほう、こわい、きぞくのほう、が、つごうが、いい? だめ、にいちゃんを、たすけて、ゆうしゃ、さま』
ブランケットに手を伸ばそうとして、聞こえてきた単語に耳を疑った。
調査報告書では、村人たちは刺殺されている。火傷を負った人間はいない。
犯人は金髪だというのが、マーガレットからの情報だ。
そして今の寝言。
赤い瞳。
金髪で赤い瞳を持つ魔法士は、この広い世界に一人しか存在しない。
サウザンを守護する、命の神子。
サウザンの首都で暮らす神子の顔を、ノーゼンハイムの寒村にいるマーガレットが知るチャンスなんて、あるわけがない。
だからマーガレットは、対峙したソレが命の神子だと知らずに言っている。
村を滅ぼした犯人は……命の神子、なのか。
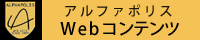


せっちゃんの私室に行くと、せっちゃんは本を読んでいた。
こちらに見える背表紙はサウザン文字のもの。ボクにはなにが書かれているかわからない。
「おはよ。相変わらず朝が早いね」
「庭師だったころの癖が抜けないんだ」
「日の出より早く起きるんだっけ。おじいちゃんみたい」
一言多いよ、と心の突っ込みを食らった。
怒らせるつもりで言ったわけじゃないのにな。
「素直なのは悪いことではないけれど、雄弁は銀、寡黙は金という言葉がある」
「マリアにもよく言われるよ。その口を塞いどけって」
「…………そうだろうな」
あきれた目をされた。
「愛の神子様もお目覚めでしたか。おはようございます」
「どうも」
男性神官の、なんだっけ。ヤマトか。ヤマトが入ってきてお辞儀をする。
「愛の神子様。マーガレットが起きたら確かめていただきたいことがあるのです」
「なに?」
「食べられないものがあったら知りたいです。ここに来たばかりの数日は、口をつけてくれないものばかりで。会話ができないし文字の読み書きもできないから、確認しようがなくて」
「あー、なるほど」
昨日の夕食の風景を見ているかぎりだと、あんまお行儀よくなかったんだよな。
一応貴族令嬢のお嬢ちゃんと並んで食べていたから、違いがよくわかった。
ミートパイを手づかみで食べようとするし、スプーンの持ち方がおかしいし。
貴族として育っていないような気がした。
「ヤマト。マーガレットは鳥肉が嫌いみたいだ。こう、巧みに皮のカケラを除けて食べようとする姿が誰かさんと同じだったから。栄養素が近い別のものを代用した方がよさそうだよ」
せっちゃんが本から顔を上げてポツリとつぶやく。
「誰かさんって誰さ。お嬢ちゃんは美味しいって言って完食してたから違うよね」
「……え?」
自分で言っておいてよく分かっていないのか、せっちゃんは首をかしげる。
「僕、そんなこと言った?」
「たった今自分で言ったのに覚えてないの? やっぱおじいちゃんなんじゃ」
睨まれたから口を閉じることにした。
マーガレットとお嬢ちゃんも起きてきて、神官のみんなが朝食の準備にとりかかる。
マーガレットはせっちゃん指導の下、白い紙に羽ペンでなにか書こうとやっきになっている。絵、ではなさそうだ。
「なにをしているところ?」
「文字を教えているんだ。アイセもずっとここにいられるわけじゃないだろう。筆談できるようになればアイセの負担が減る」
「それはどうも」
これまで文字を書いたこともないらしい。
せっちゃんが書いたマーガレットの名前を手本にして、自分の手元と手本を何度も見比べているが、インクがべちゃべちゃになって手が真っ黒だ。
「慣れるまでこれ使う?」
お嬢ちゃんがパンパンに膨らんだ鞄をひっくり返した。飛び散った荷物の中から、クレヨンセットを引っ張り出す。
相変わらず豪快だな……と、せっちゃんは思っても口にしない。
散ったあれこれを回収してそっと鞄に押し込む。
黙っていた方がいいってのはこういう場面ね。察した。
『リーンさん、ありがと』
口パクでも、お嬢ちゃんには伝わった。お嬢ちゃんは笑顔でマーガレットの頭をなでる。
気を取り直して、マーガレットはクレヨンで文字の練習を再開した。
朝食のあと、お嬢ちゃんが帰るのをマーガレットは泣いて惜しんだ。ボクへのあたりが強かったのに、お嬢ちゃんには懐くの早すぎない?
それから一時間もしないうちに、普段使わない頭をたくさん使って疲れたのか、クレヨンを持ったまま寝落ちした。
神官のソレイユが毛糸のブランケットをマーガレットの背中にかける。
「疲れて昼寝とか、完全にオコチャマだよねぇ……」
「そう言うなよアイセ。家族を亡くしたばかりで、知り合いが一人もいない生活をすることになったんだから、精神的にも疲れるのは仕方ないさ」
今の環境に慣れようと、マーガレットは必死になっている。また犯人がくるんじゃないかという恐怖と戦い、明日どこに身を置くことになるかもわからない。
「一応聞くけどさ。犯人が捕まったとして、この子そのあとどこに行くことになるの? 養子にほしいって貴族が出ない限りは孤児院? 貴族の子が孤児院行きになるパターン、ある?」
「珍しいみたいに言うけれど、君もすでに会ったことがあるだろう?」
「誰それ」
孤児院育ちの貴族に会ったことがある? ボクが?
「貴族は魔法のない子を殺すか捨てる。この捨てるっていうのは、孤児院に置いていくのも含む」
孤児院に捨てられた、魔法を持たない貴族?
なんだかこれ以上聞いちゃいけない気がして、ボクは口を閉ざす。
マーガレットがみじろぎして、ブランケットがずり落ちそうになる。
うなされている。まゆをひそめて、苦しそうだ。
『あかい、目、ひのまほう、こわい、きぞくのほう、が、つごうが、いい? だめ、にいちゃんを、たすけて、ゆうしゃ、さま』
ブランケットに手を伸ばそうとして、聞こえてきた単語に耳を疑った。
調査報告書では、村人たちは刺殺されている。火傷を負った人間はいない。
犯人は金髪だというのが、マーガレットからの情報だ。
そして今の寝言。
赤い瞳。
金髪で赤い瞳を持つ魔法士は、この広い世界に一人しか存在しない。
サウザンを守護する、命の神子。
サウザンの首都で暮らす神子の顔を、ノーゼンハイムの寒村にいるマーガレットが知るチャンスなんて、あるわけがない。
だからマーガレットは、対峙したソレが命の神子だと知らずに言っている。
村を滅ぼした犯人は……命の神子、なのか。
