一章 セツカと時の鎖
祈願祭のあとリーンと再会した僕は、マーズの庭園にある東屋で、これまで時の森でどう過ごしていたのかを話した。
神官のみんなにサポートされながら魔法の訓練をして、最低限日常生活に支障がない程度にはなってきたこと。
リーンは僕の隣にピッタリくっついて、勉強を頑張ったとか、進級してからのこととかとりとめなく話してくれる。
肩によりかかってきて、指を絡めて、触れ合う手からぬくもりが伝わってくる。
十五年幼馴染みとして育ち、離れたのは一年に満たない期間だ。
離れていた時間を埋めるように、リーンは僕に触れ、存在を確認する。
「ずっと、会いたかったよ」
「……ごめんな、リーン。このあと平和祈願祭の夜会がある。それが終わったら、また時の森に帰って修行しないといけないんだ。森の管理は神子の役目でもあるし。でも、手紙を書くよ」
「うん。私も、手紙書く」
本当はそばにいたいし、一緒に連れていきたいくらいだ。
けれどリーンはまだ学生。
学ばないといけないことがたくさんある。私情を優先させてはいけない。
「私、頑張るから。頑張って卒業したら、セツカの役に立てるような仕事に就く。神官でなくても、セツカを支えられる仕事はあるでしょう?」
「僕がどうこうでなく、リーンがしたい仕事を選びな」
「セツカの支えになることが、私のしたいことなの。港町の教会にするつもり。ツヴォルフの教会では父様やウルさんみたいな、孤児を引取って育てているって聞いたの」
「たしかに、そこも僕の管轄だ」
神子の仕事は国をあげての行事だけでなく、神子の管轄下にある地域の運営、結婚式の神父や葬儀など多岐にわたる。
リーンなら教会の子どもたちに大人気になるだろう。今だって、首都の中にある公園で小さい子の遊び相手をしているくらいだ。
誰に言われるでもなく、自分の意志で僕のところにつながる道を進もうとしている。
こんなに嬉しいことはない。
「夏休みになったら、私の方から会いに行くから。だめって言わないでね?」
「言わないよ」
神子になって背負うことになった重たいものは多い。
けど、辛いことばかりでもない。
神子としてこの時代に生まれたからこそ、こうして、リーンの隣にいることができるのだから。
「リーン」
リーンを抱きしめて、ふわふわの栗毛に顔を埋めて囁く。
昔から繰り返し見る夢がある。
夢の中の幼い僕は吟遊詩人の少女に恋をして、告白する。
“僕のお嫁さんになって”
どことなくリーンに似ている少女はふわりと笑って、小指を差し出す。
“私たちが生まれ変わって、また貴方と巡り会えたら。そのときはお嫁さんになるわ”
きっと僕たちは前世で、今と違う形で出会った。
時をこえて生まれ変わり、魂が呼び合って、僕たちはめぐり逢った。
そんな気がする。
夢の中で口にしたのと同じ言葉を声にする。
「僕のお嫁さんになって」
「もちろんよ!」
一瞬の迷いもなく、リーンは太陽みたいにキラキラした笑顔をみせてくれた。
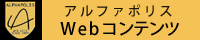

神官のみんなにサポートされながら魔法の訓練をして、最低限日常生活に支障がない程度にはなってきたこと。
リーンは僕の隣にピッタリくっついて、勉強を頑張ったとか、進級してからのこととかとりとめなく話してくれる。
肩によりかかってきて、指を絡めて、触れ合う手からぬくもりが伝わってくる。
十五年幼馴染みとして育ち、離れたのは一年に満たない期間だ。
離れていた時間を埋めるように、リーンは僕に触れ、存在を確認する。
「ずっと、会いたかったよ」
「……ごめんな、リーン。このあと平和祈願祭の夜会がある。それが終わったら、また時の森に帰って修行しないといけないんだ。森の管理は神子の役目でもあるし。でも、手紙を書くよ」
「うん。私も、手紙書く」
本当はそばにいたいし、一緒に連れていきたいくらいだ。
けれどリーンはまだ学生。
学ばないといけないことがたくさんある。私情を優先させてはいけない。
「私、頑張るから。頑張って卒業したら、セツカの役に立てるような仕事に就く。神官でなくても、セツカを支えられる仕事はあるでしょう?」
「僕がどうこうでなく、リーンがしたい仕事を選びな」
「セツカの支えになることが、私のしたいことなの。港町の教会にするつもり。ツヴォルフの教会では父様やウルさんみたいな、孤児を引取って育てているって聞いたの」
「たしかに、そこも僕の管轄だ」
神子の仕事は国をあげての行事だけでなく、神子の管轄下にある地域の運営、結婚式の神父や葬儀など多岐にわたる。
リーンなら教会の子どもたちに大人気になるだろう。今だって、首都の中にある公園で小さい子の遊び相手をしているくらいだ。
誰に言われるでもなく、自分の意志で僕のところにつながる道を進もうとしている。
こんなに嬉しいことはない。
「夏休みになったら、私の方から会いに行くから。だめって言わないでね?」
「言わないよ」
神子になって背負うことになった重たいものは多い。
けど、辛いことばかりでもない。
神子としてこの時代に生まれたからこそ、こうして、リーンの隣にいることができるのだから。
「リーン」
リーンを抱きしめて、ふわふわの栗毛に顔を埋めて囁く。
昔から繰り返し見る夢がある。
夢の中の幼い僕は吟遊詩人の少女に恋をして、告白する。
“僕のお嫁さんになって”
どことなくリーンに似ている少女はふわりと笑って、小指を差し出す。
“私たちが生まれ変わって、また貴方と巡り会えたら。そのときはお嫁さんになるわ”
きっと僕たちは前世で、今と違う形で出会った。
時をこえて生まれ変わり、魂が呼び合って、僕たちはめぐり逢った。
そんな気がする。
夢の中で口にしたのと同じ言葉を声にする。
「僕のお嫁さんになって」
「もちろんよ!」
一瞬の迷いもなく、リーンは太陽みたいにキラキラした笑顔をみせてくれた。
