一章 セツカと時の鎖
心臓の音がうるさい。
冷たい汗が額を背中を伝う。
逃げなきゃ。リーンを連れて。
でも、アイセたちの標的は俺。
俺といるほうが、リーンにとっては危険ということになる。
でも、薬で眠らされたリーンをここに置いて行けるわけが……。
「混乱しているねぇ。そんなにその子が心配? 貴族の子だから……いや、好きな女だから? 泣かせるねぇ」
アイセの表情に、初めて不快感というものが浮かんだ。
アイセはリーンを指差し、座り込んでいた襲撃者の一人に命令する。
「あー、お前でいいや。この子を門の前に転がしてきて。追いかけて来られても迷惑だから」
男は舌打ちし、リーンの後ろ襟に手をかける。意識がないから、抵抗することもできず荷物のように担ぎ上げられた。
「リーンに手を出すな!」
「おっと。お前にはこのまま遺跡まで行ってもらわねーと困るんだよ」
ナイフを構えると、当て身から回復した男たちが立ちはだかる。
「このまま時の遺跡に来てくれるなら、アイリーン・マーズは無事に森の外に出してあげる。きみがもう一度こいつらを攻撃するなら……」
アイセが親指で喉を切る仕草をして微笑む。
リーンに危害を加えられるかもしれない、というのとは別の意味で悪寒が走る。
アイセに会ってから募っていた違和感が、ついに臨界に達した。
「……俺はここに来てから一度もリーンをアイリーンと呼んでいない。リーンも名乗っていない」
「そうだねぇ」
場違いにのんびりとした口調で応じる。
「リーンが貴族の娘だってことも一度も言っていない」
「そうだねぇ」
作り物めいた笑顔を保ったまま、俺の言葉を待っている。
「お前と会ったとき、『フェンさんに似ている』と一瞬考えて……いやに絶妙なタイミングで「一緒にするな」と言ったよな」
「そうだねぇ」
すべてつなぎ合わせると、行き着く答えはーー
「心を読む、魔法」
「ご明察」
乾いた拍手の音が森に響く。
でも、アイセに貴色はない。
魔法書を隅々まで読んだが、自然の魔法に心を読む魔法なんて記載はなかった。
「そうだねぇ。自然の魔法には ないね」
……アイセは、「先代愛の神子は悪魔のようだ」と喩えられたとき激昂した。
貴族のアルデバランに対して、自分のほうが上位だと言ってのけた。
俺を同士 と呼んだ。
同じ生き物だと。
貴色を持たない俺が時の神子なら
「そう。ボクは当代愛の神子。【万物 を愛 せし者 】。きみが時節司る者でセツカだから、真似してみたんだ」
アイセは歌を歌ったあとのように、左胸に手を当てて深くお辞儀をする。
「神域の管理は神子にしかできない。だからボクは、フェンネルに頼まれてツヴォルフにいた」
アイセが港町の人間に恐れられている理由が、やっとわかった。
悪魔と呼ばれた神子の、後継者だから。
「さ、時の遺跡に来てもらうよ。きみは、先代時の神子が犯した罪を償うため……そのためだけに生まれてきたんだから」

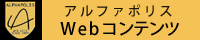


冷たい汗が額を背中を伝う。
逃げなきゃ。リーンを連れて。
でも、アイセたちの標的は俺。
俺といるほうが、リーンにとっては危険ということになる。
でも、薬で眠らされたリーンをここに置いて行けるわけが……。
「混乱しているねぇ。そんなにその子が心配? 貴族の子だから……いや、好きな女だから? 泣かせるねぇ」
アイセの表情に、初めて不快感というものが浮かんだ。
アイセはリーンを指差し、座り込んでいた襲撃者の一人に命令する。
「あー、お前でいいや。この子を門の前に転がしてきて。追いかけて来られても迷惑だから」
男は舌打ちし、リーンの後ろ襟に手をかける。意識がないから、抵抗することもできず荷物のように担ぎ上げられた。
「リーンに手を出すな!」
「おっと。お前にはこのまま遺跡まで行ってもらわねーと困るんだよ」
ナイフを構えると、当て身から回復した男たちが立ちはだかる。
「このまま時の遺跡に来てくれるなら、アイリーン・マーズは無事に森の外に出してあげる。きみがもう一度こいつらを攻撃するなら……」
アイセが親指で喉を切る仕草をして微笑む。
リーンに危害を加えられるかもしれない、というのとは別の意味で悪寒が走る。
アイセに会ってから募っていた違和感が、ついに臨界に達した。
「……俺はここに来てから一度もリーンをアイリーンと呼んでいない。リーンも名乗っていない」
「そうだねぇ」
場違いにのんびりとした口調で応じる。
「リーンが貴族の娘だってことも一度も言っていない」
「そうだねぇ」
作り物めいた笑顔を保ったまま、俺の言葉を待っている。
「お前と会ったとき、『フェンさんに似ている』と一瞬考えて……いやに絶妙なタイミングで「一緒にするな」と言ったよな」
「そうだねぇ」
すべてつなぎ合わせると、行き着く答えはーー
「心を読む、魔法」
「ご明察」
乾いた拍手の音が森に響く。
でも、アイセに貴色はない。
魔法書を隅々まで読んだが、自然の魔法に心を読む魔法なんて記載はなかった。
「そうだねぇ。
……アイセは、「先代愛の神子は悪魔のようだ」と喩えられたとき激昂した。
貴族のアルデバランに対して、自分のほうが上位だと言ってのけた。
俺を
同じ生き物だと。
貴色を持たない俺が時の神子なら
「そう。ボクは当代愛の神子。【
アイセは歌を歌ったあとのように、左胸に手を当てて深くお辞儀をする。
「神域の管理は神子にしかできない。だからボクは、フェンネルに頼まれてツヴォルフにいた」
アイセが港町の人間に恐れられている理由が、やっとわかった。
悪魔と呼ばれた神子の、後継者だから。
「さ、時の遺跡に来てもらうよ。きみは、先代時の神子が犯した罪を償うため……そのためだけに生まれてきたんだから」

