一章 セツカと時の鎖
「ゴメンネ〜。失礼をしたお詫びに、そこでお茶でも一杯奢ろうか」
「いらないわ。私たち忙しいの。行きましょセツカ」
リーンにマントを引っ張られてレストランの扉をくぐった。
港町だからか、食事をしているお客さんはサウザンの民族服や東国イサナキのハカマ姿の人がいる。
「お好きなお席にどうぞ」と店員に言われ、奥の窓際にあるテーブル席を選ぶ。
リーンは俺の隣に座ると、何も見ず店員にオーダーした。
「オススメセットふたつ!」
「……本当に、アーノルドさんとおんなじことするんだな」
メニューを開くのも面倒くさいのか。
そこにアイセが入ってきて、俺の向かいに座った。
「ボクにも二人と同じものを」と言われ、店員がオーダーに書き足した。
「他にも空いているところがあるだろう」
「そう冷たいこと言わないでよ。ちゃんとお詫びしたいからさ」
「おごったら破産するんじゃないの。吟遊詩人は宿代と馬車代がかかるから、旅先で日雇いの仕事をして食いつなぐって、リュート先生が言っていたわ」
基本愛想がいいリーンも、まだ怒っているみたいで辛辣だ。
リュート先生はノーゼンハイムの学校で音楽を担当している。教師になる前は吟遊詩人だったため、よく授業で旅のことを語っている。
ほどなくしてキルシュトルテと紅茶のセットが運ばれてきた。
ティーポットに保温カバー がしてある。
紅茶に口をつけて、俺はリーンに言う。
「リーン。アイセはお金に困っていないと思う」
「そうなの?」
テーブルの上に乗せられた両手の人差し指には純金の指輪。
金に困っている者ならそれを売り飛ばしている。
それに……。食事を待つ間テーブルの上に手を置くのは貴族の習慣だ。
自然に体が動いているようだから、身にしみつくくらいの幼少期に貴族からテーブルマナーを叩き込まれている。
「アイセはすごいお金持ちなの?」
「まさかぁ。冗談キツイよせっちゃん。ボクはカツカツ暮らしの中からなけなしのお金で奢るんだよ」
失礼かもしれないけれど、やっぱりアイセの笑顔は嘘くさい。
「あ、そうだ。セツカ。さっき言ってたわからないことが増えたってなに?」
「アイセの前で聞くか」
「吟遊詩人なら、旅人や町の人にいろんな話聞いてるかもしれないじゃない」
アイセは気にした様子もなく、先を促してくる。
「いいよ。悩みごとを聞こうか」
本人がいいならいいのか。
俺はおばあさんの話と、資料館のことを説明する。
「一八四五が欠けてるからその前後を読んでみたんだけど、年誌を綴る筆跡が変わっていた。時の森が封鎖されたことと関係あるかもしれない」
「私のほうも、そのおばあちゃんと同じ。みーんな悪魔の森に近づくなって言うの」
悪魔なんて実在しないし、おとぎ話にしか出てこない。森にそんなもの住んでいるわけがない。
「あの人たちの様子ってなんだか、スイレン先生と似ている気がする。最近歴史の授業でやったの。悪魔碑文。“先代愛の神子は悪魔のような女だ”って、スイレン先生がーー」
リーンの言葉を遮るように、アイセがティーカップをテーブルに叩きつけた。
まだ湯気のたっている紅茶が大きく揺れ、テーブルクロスに茶色の染みをつくる。
「ごめ〜ん手が滑った。で、先代愛の神子がなんだって。続きをどうぞ?」
口調は軽いままなのに、アイセの顔からは、さっきまでの作り笑いすら消え失せている。
そのかわり、大切なものを傷つけられたような怒りをにじませていた。
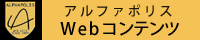


「いらないわ。私たち忙しいの。行きましょセツカ」
リーンにマントを引っ張られてレストランの扉をくぐった。
港町だからか、食事をしているお客さんはサウザンの民族服や東国イサナキのハカマ姿の人がいる。
「お好きなお席にどうぞ」と店員に言われ、奥の窓際にあるテーブル席を選ぶ。
リーンは俺の隣に座ると、何も見ず店員にオーダーした。
「オススメセットふたつ!」
「……本当に、アーノルドさんとおんなじことするんだな」
メニューを開くのも面倒くさいのか。
そこにアイセが入ってきて、俺の向かいに座った。
「ボクにも二人と同じものを」と言われ、店員がオーダーに書き足した。
「他にも空いているところがあるだろう」
「そう冷たいこと言わないでよ。ちゃんとお詫びしたいからさ」
「おごったら破産するんじゃないの。吟遊詩人は宿代と馬車代がかかるから、旅先で日雇いの仕事をして食いつなぐって、リュート先生が言っていたわ」
基本愛想がいいリーンも、まだ怒っているみたいで辛辣だ。
リュート先生はノーゼンハイムの学校で音楽を担当している。教師になる前は吟遊詩人だったため、よく授業で旅のことを語っている。
ほどなくしてキルシュトルテと紅茶のセットが運ばれてきた。
ティーポットに
紅茶に口をつけて、俺はリーンに言う。
「リーン。アイセはお金に困っていないと思う」
「そうなの?」
テーブルの上に乗せられた両手の人差し指には純金の指輪。
金に困っている者ならそれを売り飛ばしている。
それに……。食事を待つ間テーブルの上に手を置くのは貴族の習慣だ。
自然に体が動いているようだから、身にしみつくくらいの幼少期に貴族からテーブルマナーを叩き込まれている。
「アイセはすごいお金持ちなの?」
「まさかぁ。冗談キツイよせっちゃん。ボクはカツカツ暮らしの中からなけなしのお金で奢るんだよ」
失礼かもしれないけれど、やっぱりアイセの笑顔は嘘くさい。
「あ、そうだ。セツカ。さっき言ってたわからないことが増えたってなに?」
「アイセの前で聞くか」
「吟遊詩人なら、旅人や町の人にいろんな話聞いてるかもしれないじゃない」
アイセは気にした様子もなく、先を促してくる。
「いいよ。悩みごとを聞こうか」
本人がいいならいいのか。
俺はおばあさんの話と、資料館のことを説明する。
「一八四五が欠けてるからその前後を読んでみたんだけど、年誌を綴る筆跡が変わっていた。時の森が封鎖されたことと関係あるかもしれない」
「私のほうも、そのおばあちゃんと同じ。みーんな悪魔の森に近づくなって言うの」
悪魔なんて実在しないし、おとぎ話にしか出てこない。森にそんなもの住んでいるわけがない。
「あの人たちの様子ってなんだか、スイレン先生と似ている気がする。最近歴史の授業でやったの。悪魔碑文。“先代愛の神子は悪魔のような女だ”って、スイレン先生がーー」
リーンの言葉を遮るように、アイセがティーカップをテーブルに叩きつけた。
まだ湯気のたっている紅茶が大きく揺れ、テーブルクロスに茶色の染みをつくる。
「ごめ〜ん手が滑った。で、先代愛の神子がなんだって。続きをどうぞ?」
口調は軽いままなのに、アイセの顔からは、さっきまでの作り笑いすら消え失せている。
そのかわり、大切なものを傷つけられたような怒りをにじませていた。
