一章 セツカと時の鎖
借りた部屋に入って、それぞれ荷物を下ろす。
「……行く先は森だから、冬眠前の獣が出ることもあるはずだ。危険だと判断したら素直に屋敷に帰ると約束してくれ。リーンに何かあったら、アーノルドさんが悲しむ」
リーンは真剣な瞳で俺を見つめかえす。
「うん。私、迷惑かけないようにする。それにね、私も時の森に行きたい。時の神さまに仕える神子さまが住んでいるんでしょ。母様のことを知りたいの」
「お母さんのこと?」
リーンの母エレナさんは、十五年前亡くなったと聞いている。
俺は拾われて間もない頃の記憶は曖昧だ。あの頃のことは、リーンのほうがよく覚えているだろう。
「母様はいなくなっちゃった日、『神さまに会いに行ってくる』って言っていたの。海の見える街で。母様がいなくなるのと入れ替わるように、父様がセツカを拾ってきたの。母様のお葬式をしたけど、棺はからっぽで」
「それって」
時の森は、港町ツヴォルフのそばにある。
エレナさんが亡くなった日と、俺が拾われた日が同じ。
遺体のないエレナさん。
俺をアーノルドさんに託した人もまた、遺体も残さず消えた。
「セツカもあの日の母様みたいに急にいなくなってしまったら、嫌だよ」
泣き出すリーンにハンカチを渡す。
どう声をかけるべきかわからなくて、黙ってリーンが泣き止むのを待つ。
「いなくならない。全部終わったら、ちゃんと帰るから。アーノルドさんも、帰ってきていいって言っていた。エレナさんのことを知りたいのはわかったけれど、だからって、こんな無茶はしちゃだめだ」
「……うん。やくそくだよ。一緒に帰ろうね」
指切りして、やっと笑顔を見せてくれた。
森で何があったのか知りたいけれど、ツヴォルフに向かう馬車が来るのは明日の朝だ。
リーンが来たからにはお祭を見たいと言うから、散策に出た。
「よう、旅の兄ちゃん。ツヴァイ農園村のぶどう酒とこの村特産のハーブで作ったグリューワインだよ。一杯四〇ジェムだ」
「じゃあ、一杯もらおうか」
屋台のおじさんに勧められ、グリューワインを一杯買う。
鍋で温めた赤ワインにハチミツとレモンスライス、スターアニス、シナモンを入れた飲み物だ。
湯気とともに甘い香りが鼻腔をくすぐる。
ノーゼンハイムの成人は十八歳。俺は飲めるがリーンは飲めない。
「私も飲みたいよー。飲めない私の前でお酒を飲むなんて」
「別にいいだろう。好物なんだ」
「むー。私も早く十八歳になりたい」
リーンはランタン飾りの方をみて俺のマントを引っ張る。

「ねえねぇセツカ。あのかぼちゃ面白いよ。雪だるまみたいになってる」
「ははは。手足もつけてあるのか。凝ってるなぁ」
腕に見立てた木の枝の先に手袋をかぶせてあって、今にも動き出しそうな躍動感がある。
村の子どもたちが歌いながらかぼちゃのまわりを踊り、まわっている。
リーンは子どもたちの輪に加わって歌いだした。
吐く息が真っ白になるくらいに寒いけれど、なんだかあたたかい。
俺はあんなふうに子どもたちと打ち解けるほど陽気ではないし、こうしてリーンに誘われなければ部屋にこもるタイプだ。
ひとり旅だったら、こんな気持ちにはならなかっただろう。
祭の夜はゆっくりと更けていった。
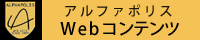


★★★★★
*グリューワイン
日本ではホットワインと呼ばれる。
ワインとスライスしたオレンジやレモンを煮る。オレンジジュースを入れたりもする。
ハチミツや砂糖、シナモン、スターアニスはお好みで。
「……行く先は森だから、冬眠前の獣が出ることもあるはずだ。危険だと判断したら素直に屋敷に帰ると約束してくれ。リーンに何かあったら、アーノルドさんが悲しむ」
リーンは真剣な瞳で俺を見つめかえす。
「うん。私、迷惑かけないようにする。それにね、私も時の森に行きたい。時の神さまに仕える神子さまが住んでいるんでしょ。母様のことを知りたいの」
「お母さんのこと?」
リーンの母エレナさんは、十五年前亡くなったと聞いている。
俺は拾われて間もない頃の記憶は曖昧だ。あの頃のことは、リーンのほうがよく覚えているだろう。
「母様はいなくなっちゃった日、『神さまに会いに行ってくる』って言っていたの。海の見える街で。母様がいなくなるのと入れ替わるように、父様がセツカを拾ってきたの。母様のお葬式をしたけど、棺はからっぽで」
「それって」
時の森は、港町ツヴォルフのそばにある。
エレナさんが亡くなった日と、俺が拾われた日が同じ。
遺体のないエレナさん。
俺をアーノルドさんに託した人もまた、遺体も残さず消えた。
「セツカもあの日の母様みたいに急にいなくなってしまったら、嫌だよ」
泣き出すリーンにハンカチを渡す。
どう声をかけるべきかわからなくて、黙ってリーンが泣き止むのを待つ。
「いなくならない。全部終わったら、ちゃんと帰るから。アーノルドさんも、帰ってきていいって言っていた。エレナさんのことを知りたいのはわかったけれど、だからって、こんな無茶はしちゃだめだ」
「……うん。やくそくだよ。一緒に帰ろうね」
指切りして、やっと笑顔を見せてくれた。
森で何があったのか知りたいけれど、ツヴォルフに向かう馬車が来るのは明日の朝だ。
リーンが来たからにはお祭を見たいと言うから、散策に出た。
「よう、旅の兄ちゃん。ツヴァイ農園村のぶどう酒とこの村特産のハーブで作ったグリューワインだよ。一杯四〇ジェムだ」
「じゃあ、一杯もらおうか」
屋台のおじさんに勧められ、グリューワインを一杯買う。
鍋で温めた赤ワインにハチミツとレモンスライス、スターアニス、シナモンを入れた飲み物だ。
湯気とともに甘い香りが鼻腔をくすぐる。
ノーゼンハイムの成人は十八歳。俺は飲めるがリーンは飲めない。
「私も飲みたいよー。飲めない私の前でお酒を飲むなんて」
「別にいいだろう。好物なんだ」
「むー。私も早く十八歳になりたい」
リーンはランタン飾りの方をみて俺のマントを引っ張る。

「ねえねぇセツカ。あのかぼちゃ面白いよ。雪だるまみたいになってる」
「ははは。手足もつけてあるのか。凝ってるなぁ」
腕に見立てた木の枝の先に手袋をかぶせてあって、今にも動き出しそうな躍動感がある。
村の子どもたちが歌いながらかぼちゃのまわりを踊り、まわっている。
リーンは子どもたちの輪に加わって歌いだした。
吐く息が真っ白になるくらいに寒いけれど、なんだかあたたかい。
俺はあんなふうに子どもたちと打ち解けるほど陽気ではないし、こうしてリーンに誘われなければ部屋にこもるタイプだ。
ひとり旅だったら、こんな気持ちにはならなかっただろう。
祭の夜はゆっくりと更けていった。
★★★★★
*グリューワイン
日本ではホットワインと呼ばれる。
ワインとスライスしたオレンジやレモンを煮る。オレンジジュースを入れたりもする。
ハチミツや砂糖、シナモン、スターアニスはお好みで。
