一章 セツカと時の鎖
御者のおじいさんが手綱を引き、乗り合い馬車が動き出す。
時間を有効活用するため、本を読むことにした。
旅に出るにあたって購入した、魔法大全原典だ。
ノーゼンハイム文字の翻訳版も出版されているが、訳者によって言い回しや意味が微妙に違う。
だから東国文字で書かれている原書を選んだ。
一ページ目に押し花の栞《しおり》を挟んで目次の項目を開く。
「あ、それ私が贈った栞」
誕生日の朝、リーンがくれた栞だ。白薔薇のつぼみが薄紫の台紙に映えている。
「きちんとお礼を言えてなかったな。ありがとうリーン」
「えへ。セツカは本をよく読むから。気に入ってもらえたなら作った甲斐があるわ」
リーンは照れくさそうに頭をかく。
「いつも思うけど、東国文字なんてよく読めるね。でも、なんで魔法書?」
「俺をアーノルドさんに託した人は魔法士のようだから」
「つまり、セツカの家族は貴族なの?」
「それはわからない。全くの他人かもしれないし」
光魔法の章を開いて、文章を指でなぞる。
章の最後まで読みすすめても、人が消える現象については書かれていなかった。
暇なのか、さっきからリーンが隣から本をのぞきこんでいるから、視界のはしにくせっけが入る。
「リーン。退屈なら、君も本を読むといい。本を読むのはためになる」
「えぇー。文字ばかりだと眠くなるわ」
「親子揃って同じこと言うんだな……」
アーノルドさんにも、そっくりそのままのことを言われた。
本当によく似た親子だ。
「知りたいことは載ってた?」
「いいや。もっと違う視点から探したほうが良さそうだ」
本を閉じて革ベルトをはめ、トランクにくくっておく。
他の乗客は寝ていたり、外の景色を見ながら談笑しているから、俺とリーンが話していてもたいして気にしていないように見える。
「途中のゼクス村で降りる。今日はそこで一泊して、明日ツヴォルフ港行きの馬車に乗る」
「まる二日馬車の中なんて、お尻が痛くなっちゃうね」
今も馬の歩調に合わせて小刻みに揺れていて、目の前に座っているおばあさんが腰をさすっている。
熟練者はクッションを持ち込んで揺れを緩和させている。いびきをかいて寝ているおじさんがまさにそれ。
ゼクスに着いたら、収穫祭をやっていた。
陽気な音楽が流れていて、小さな子どもたちが歌い踊る。
村のあちこちにかぼちゃやカブのランタンが飾られていて、村の中心部では大鍋でシチューを作っている。
「わぁ! おいしそ〜!」
「待て待て待て、リーン。宿を取るのが先だ」
シチューを配る列に並ぼうと駆け出すリーンを急いで止める。
「祭ってことは宿が空いてないかもしれない」
「野宿を経験するのも悪くないと思うわ」
リーンは本当にお嬢様なのだろうか。
宿の部屋が空いてなくても気にしないなんて大物だ。
案内看板を頼りに宿を探し、三軒目でようやく空き部屋をひとつだけ見つけた。
「俺は野宿でいいから、リーンが宿に泊まるといい」
「それはだめ。二人で泊まればいいじゃない」
リーンの「野宿も良い」は、二人とも野宿なら。という意味だったらしい。
「俺と同室になるのはリーンのためにならないと思う」
「ねぇ、ジーナたちもそれを言うけど“お嬢様のため”ってなに?マーズ家 のためでしょ? 私の気持ちを無視されてて嫌」
本人の気持ちを蔑ろにされ、リーンは怒る。
そうだ。リーンのためって言いながら、気にしているのはまわりの反応。言い返す言葉が見つからなかった。
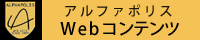


時間を有効活用するため、本を読むことにした。
旅に出るにあたって購入した、魔法大全原典だ。
ノーゼンハイム文字の翻訳版も出版されているが、訳者によって言い回しや意味が微妙に違う。
だから東国文字で書かれている原書を選んだ。
一ページ目に押し花の栞《しおり》を挟んで目次の項目を開く。
「あ、それ私が贈った栞」
誕生日の朝、リーンがくれた栞だ。白薔薇のつぼみが薄紫の台紙に映えている。
「きちんとお礼を言えてなかったな。ありがとうリーン」
「えへ。セツカは本をよく読むから。気に入ってもらえたなら作った甲斐があるわ」
リーンは照れくさそうに頭をかく。
「いつも思うけど、東国文字なんてよく読めるね。でも、なんで魔法書?」
「俺をアーノルドさんに託した人は魔法士のようだから」
「つまり、セツカの家族は貴族なの?」
「それはわからない。全くの他人かもしれないし」
光魔法の章を開いて、文章を指でなぞる。
章の最後まで読みすすめても、人が消える現象については書かれていなかった。
暇なのか、さっきからリーンが隣から本をのぞきこんでいるから、視界のはしにくせっけが入る。
「リーン。退屈なら、君も本を読むといい。本を読むのはためになる」
「えぇー。文字ばかりだと眠くなるわ」
「親子揃って同じこと言うんだな……」
アーノルドさんにも、そっくりそのままのことを言われた。
本当によく似た親子だ。
「知りたいことは載ってた?」
「いいや。もっと違う視点から探したほうが良さそうだ」
本を閉じて革ベルトをはめ、トランクにくくっておく。
他の乗客は寝ていたり、外の景色を見ながら談笑しているから、俺とリーンが話していてもたいして気にしていないように見える。
「途中のゼクス村で降りる。今日はそこで一泊して、明日ツヴォルフ港行きの馬車に乗る」
「まる二日馬車の中なんて、お尻が痛くなっちゃうね」
今も馬の歩調に合わせて小刻みに揺れていて、目の前に座っているおばあさんが腰をさすっている。
熟練者はクッションを持ち込んで揺れを緩和させている。いびきをかいて寝ているおじさんがまさにそれ。
ゼクスに着いたら、収穫祭をやっていた。
陽気な音楽が流れていて、小さな子どもたちが歌い踊る。
村のあちこちにかぼちゃやカブのランタンが飾られていて、村の中心部では大鍋でシチューを作っている。
「わぁ! おいしそ〜!」
「待て待て待て、リーン。宿を取るのが先だ」
シチューを配る列に並ぼうと駆け出すリーンを急いで止める。
「祭ってことは宿が空いてないかもしれない」
「野宿を経験するのも悪くないと思うわ」
リーンは本当にお嬢様なのだろうか。
宿の部屋が空いてなくても気にしないなんて大物だ。
案内看板を頼りに宿を探し、三軒目でようやく空き部屋をひとつだけ見つけた。
「俺は野宿でいいから、リーンが宿に泊まるといい」
「それはだめ。二人で泊まればいいじゃない」
リーンの「野宿も良い」は、二人とも野宿なら。という意味だったらしい。
「俺と同室になるのはリーンのためにならないと思う」
「ねぇ、ジーナたちもそれを言うけど“お嬢様のため”ってなに?
本人の気持ちを蔑ろにされ、リーンは怒る。
そうだ。リーンのためって言いながら、気にしているのはまわりの反応。言い返す言葉が見つからなかった。
