スカリーくんと監督生のなんでもない一日【完結】
監督生さん、素敵な貴方のお名前は?
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
【スカリーくんと監督生がプレゼント交換しているだけ】
毎朝のことだったが、今朝もスカリーはユウよりも早く起きていた。彼にとって、ユウを起こしに行くのは習慣のようなものだった。ユウの一日の始まりに、自分が関われるという些細な喜び。それはスカリーにとって、何よりも大切な時間だった。
廊下には冬の朝らしい冷えた空気が漂っているが、スカリーの足音はそれを切り裂くように軽やかだった。黒い革靴が軋む床板を滑るように進む。制服のジャケットはきちんと整えられ、ネクタイの結び目も完璧だ。柔らかいベストの生地越しに胸元の温もりを感じながら、スカリーはユウの部屋の扉にそっと手を伸ばした。
「おはようございます、ユウさん。」控えめなノックとともに、いつもの声が静かに響いた。その声は柔らかく、冬の冷たさを和らげるような温かさを持っていた。
しばらくして、奥から眠たげな声が返ってきた。「……スカリーくん?また朝から早いね……。」
扉越しの声にスカリーは小さく笑みを浮かべた。「貴方にとっての良き朝の始まりを、我輩が少しお手伝いできればと。それでは、失礼いたします。」そう言いながら扉をゆっくりと開ける。薄暗い部屋の中で、ユウはまだ毛布にくるまり、ぼんやりとした瞳でこちらを見上げていた。
「本当に、毎日ありがとう。」ユウは布団の中から少し顔を出して微笑んだ。
スカリーはその言葉に首を横に振る。「我輩にとっては、貴方の笑顔を見る朝こそが何よりの贈り物でございますから。」そう言って、そっとユウの額に唇を触れさせた。それは挨拶以上に柔らかく、けれど決して重くはない優しさだった。
ユウはその感触に目を丸くし、次の瞬間、赤面しながら慌てて布団を跳ねのけた。「も、もう!スカリーくん、毎朝やってくれるのは嬉しいけど、今日は特に恥ずかしいから!」
スカリーは軽く肩をすくめて微笑みを隠し、「では、談話室で温かい空気に包まれながら、この美しい朝を共に過ごすというのはいかがでしょうか。」と促した。
談話室の中は静まり返り、ツリーの飾り付けが朝の光を受けてきらめいていた。赤や緑のオーナメントが揺れ、その光は壁や天井に小さな虹を映し出している。部屋に漂うシナモンの香りは、昨夜の宴の名残を優しく思い出させた。
スカリーは部屋に入ると、ツリーに目を留めた。「まるで魔法のような朝でございますね。この静けさと美しさが、昨日の喧騒とは対照的で素晴らしい。」
ユウは隣に立ち、視線をツリーに固定したまま小さく頷いた。「……本当に綺麗だね。こうして見ると、頑張って飾り付けしてよかったなぁ。」
声はわずかに震えているようにも聞こえるが、それはスカリーの視線を避けているせいかもしれない。
スカリーは、ふとユウの表情を横目でうかがった。ユウの頬はうっすらと赤く染まり、その瞳は飾り玉の揺れる光を映している。ヤドリギ事件のことを気にしている様子がわずかに伝わるのを見て、スカリーはさらに慎重に言葉を選んだ。
「……昨日の件、本当に、大丈夫でしたか?その、我輩が何か不快な思いをさせたのではないかと。」
ユウはまたもや顔を真っ赤にして、「もう!言わないでってば!」とツリーの影に隠れるようにしゃがみこんだ。声には明らかに照れが混じっていて、ユウの仕草はまるで小動物が危険から逃げ込むようだった。
その可愛らしい反応に、スカリーは胸の内に湧き上がる喜びを必死で抑えた。表情は控えめな微笑を装っていたが、頬の赤みが抑えきれず、彼の気持ちをわずかに滲ませていた。
「お詫びの気持ちを述べるべきかと思いましたが、どうやらそれは逆効果のようでございますね。」スカリーは柔らかく笑いながら、ユウを見下ろした。
「……本当に気にしてないから!わかった?」ユウは顔を上げることなく、壁に視線を落としたまま声を張った。
「承知いたしました。それでは、談話室の穏やかな空気を存分に楽しみましょう。」スカリーの声は穏やかで、どこかユウへの優しいいたわりが込められていた。
*
ユウが「もう、その話は終わり!」と声を張り上げた後、談話室は再び静けさを取り戻した。二人はツリーを囲むように並んだソファに腰を下ろした。クッションの柔らかさが体を包み込み、冬の寒さを忘れさせるような居心地の良さを与えてくれる。
朝の光が窓から差し込み、飾り付けられたツリーを静かに照らしていた。オーナメントが光を反射し、小さな虹色の輝きが部屋を舞っている。シナモンとクローブが混ざり合った香りがふんわりと漂い、昨日の賑やかな夜を名残惜しく思わせた。
ユウは、ふと横目でスカリーを見た。彼はいつも通り背筋を伸ばし、整った制服姿で椅子に腰掛けていたが、どこかリラックスしているように見えた。目元には穏やかな光が宿り、ツリーを見つめる視線は、まるでそこに広がる夢を眺めているようだった。
その横顔に、ユウは小さく息を吐いて意を決したように口を開いた。
「ねえ、スカリーくん。」
彼がゆっくりと振り向く。「はい、なんでしょう、ユウさん?」
ユウは少し照れくさそうに微笑みながら、後ろに隠していた小さな包みを差し出した。白いリボンがかけられた包みからは、ほんのり甘い紙の匂いが漂っていた。
「メリークリスマス!これ、スカリーくんへのプレゼントだよ!」ユウは声を少し弾ませた。
スカリーは目を見張り、思わず体を少し前に乗り出した。「我輩に…!?これは、一体何のために…?」
彼の声は驚きで少し震え、手が自然に伸びて包みを受け取った。彼がその小さな包みを手に取ると、滑らかな包装紙の肌触りが指先に伝わってきた。丁寧にリボンを解くと、中から現れたのは、一枚の手紙と小さなケースだった。
スカリーはまず手紙を手に取った。封を開けると、万年筆で書かれた美しい文字が並んでいる。視線を落とし、一行一行を静かに読み進める。その内容は、ユウが書いた詩だった。
*
マイフェイバリットシングス
私の好きなものたち
バラの庭園でいただくお菓子、グリムのふわふわお腹、
ピカピカの大釜、飛び散る魔法の光の粒。
君の声が響く優しい夜、
二人で過ごす、ちょっぴり特別なひととき。
みんな私の好きなもののいくつか。
君の好きなものたち
ハロウィンの夜、かぼちゃが灯る祝祭、
古びた洋館から漂う香り、恐怖と美しさの絶妙な調和。
オペラの旋律、オーケストラの音色、蝋燭の揺れる光、
そして君の瞳が映す夢の続き。
みんな君の好きなもののいくつか。
私たちの好きなものたち
影のワルツ、暖かな紅茶と夕暮れの光、
ほかほか焼き芋、落ち葉の香りと穏やかな時間。
氷雪の薔薇、ココアに浮かぶマシュマロ、
二人だけの特別な場所オンボロ寮、誰にも邪魔されない瞬間。
みんな私たちのお気に入り。
私が大大大好きなものたち
君のふわふわの髪、カーネリアンの瞳、
君がくれたアンティークの万年筆。
悲しい時、寂しい時
居残りさせられてしまった時、
もう戻れないかもって思った時、
悲しい気持ちになった時には、
私はただ思い出すの。
私の好きなもの、君の好きなもの、
私たちだけのお気に入りの数々を。
そうするとね、なんだか気持ちがふんわり軽くなるの。
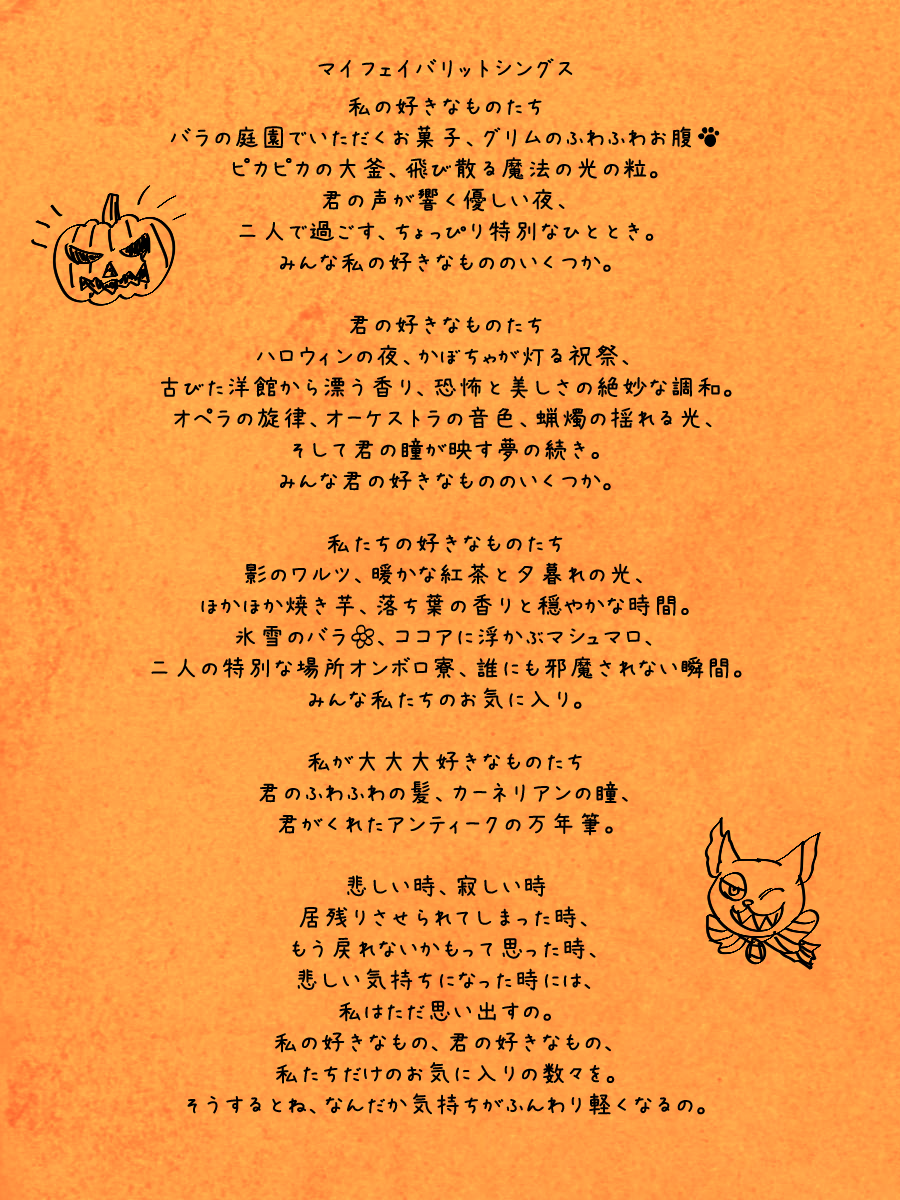
*
スカリーの手がわずかに震えた。詩を読み終えた後、彼は一瞬言葉を失い、ゆっくりと顔を上げた。彼の瞳は普段よりもわずかに潤んでいるようだった。
「……これは…我輩への特別な詩でございますか?」彼の声はいつもより低く、静かだった。
ユウは少し緊張したように頷いた。「うん。この詩はね、私の世界の歌が元になってるんだ。『私の好きなもの(My Favorite Things)』っていう内容で、スカリーくんのことを考えながら書いたの。君がくれた万年筆で……。」
ユウの言葉を聞きながら、スカリーは再び詩に目を落とした。文字に込められた温かさが彼の胸にじんわりと広がっていく。その感触は、朝日の暖かさが冷たい肌を包むような優しさだった。
「これほどの思いを込めてくださったとは……」スカリーは深く息を吐き出し、静かに言葉を続けた。「我輩は、これを一生の宝物とさせていただきます。」
その言葉にユウは少し照れながら笑った。「宝物なんて、大げさだよ。でも、喜んでくれて嬉しい。」
スカリーは再び手元に視線を戻し、今度はもう一つのケースを開けた。中から現れたのは、彼の制服にぴったりなデザインのカフリンクス 。
スカリーはカフリンクスを指先でそっと摘み上げた。黒地に金で縁取られたジャック・オ・ランタンのモチーフが、朝の光を浴びて繊細に輝いている。その美しさに感嘆するだけでなく、それが自分のために選ばれたのだと考えると、胸の奥がじんわりと温かくなった。
「ユウさん……カフリンクスを、我輩に…?」スカリーの声は驚きでわずかに震えていた。
隣のユウは、彼の反応に戸惑ったように首を傾げる。「うん。スカリーくんに似合うかなって思って選んだんだけど……。あ、もしかして、あんまり嬉しくなかった?」
「いえ!」スカリーは思わず声を上げた後、慌てて咳払いをして声のトーンを落とした。「そのようなことは断じてございません。ただ、この贈り物の意味について、貴方が……」
スカリーの言葉が途切れた。何をどう伝えればよいのか、思考が絡まり合う。彼はカフリンクスを手のひらで包み込みながら慎重に言葉を選んだ。
「ユウさん、このカフリンクスには、特別な意味が込められている場合が多いのです。贈り物として選ばれる際、それは……その……『抱きしめてほしい』という気持ちを暗に伝えるサインとも言われております。」
ユウはぽかんとした表情を浮かべ、一拍遅れて「えっ?」と声を上げた。そして視線をさまよわせながら続けた。「そ、そんな意味があるの?全然知らなかった……。」
その言葉を言いながら、ユウの表情は次第に曇り、ユウはカフリンクスに視線を落とした。「……いつも勉強不足でごめんなさい。ほんとに、私ってものを知らなくて……。」申し訳なさそうに目を伏せたユウは、どこか自分を責めているようにも見えた。
「でも、スカリーくんは物知りだよね。いつもいろんなことを教えてくれるし、私が知らないことばかり気づかせてくれる……。」ユウの声は静かだったが、その中にはスカリーへの尊敬が滲んでいた。
スカリーはユウの言葉に一瞬驚いたような表情を浮かべ、それから優しく首を横に振った。「そんなことはございません。我輩が少しばかり知識を持ち合わせているのは、ただ、それを必要としてきたからにすぎません。」
彼は言葉を区切り、ユウを真っ直ぐに見つめた。「貴方の素晴らしさは、知識の量では測れないものです。それを忘れないでくださいませ。」
その言葉に、ユウは驚きながらも、頬にわずかな赤みを浮かべて「ありがとう、スカリーくん……。」と小さく呟いた。
スカリーはカフリンクスを改めて見つめ、その重みを感じながら深く息を吐き出した。「ユウさん……この贈り物が、どれほど我輩にとって特別なものか、貴方はお分かりでしょうか。」
彼の声は静かでありながら、どこか熱を帯びていた。ユウは少し驚いたように目を瞬かせ、「えっと……わからないけど、スカリーくんが喜んでくれるなら、それでいいんだ。」と答えた。
*
スカリーはカフリンクスを握りしめたまま、視線をユウに向けた。ユウの無邪気な言葉――「スカリーくんが喜んでくれるなら、それでいいんだ」――は、心の奥深くに響き渡り、胸の中で静かに広がっていく。
ユウのその無垢な笑顔に対するこの想いを、どう表現すれば伝わるのだろう?どんな言葉を紡いでも、それが不十分であるような気がした。
「ユウさん……。」スカリーの声は低く、けれどどこか震えていた。「この贈り物が、どれほど我輩にとって大切なものか……貴方にお伝えする術を、我輩は持ち合わせておりません。」
ユウはその言葉に驚き、彼の真剣な眼差しに息を呑んだ。ユウの頬がじんわりと赤く染まり、温かさが広がっていく。心臓が早鐘を打つように高鳴り、言葉が出てこなかった。
スカリーは一瞬目を伏せた。次に顔を上げたとき、その瞳には揺るぎない決意が宿っていた。「……では、言葉ではなく、この想いを形にさせていただきます。」
彼はゆっくりと手を伸ばした。その動きは慎重で、まるで宝物に触れるような繊細さだった。手がユウの肩に触れた瞬間、ユウは僅かに肩をすくめたが、拒む様子はなかった。スカリーは一歩近づき、優しくユウを包み込むように抱きしめた。
彼のジャケットの生地が肌に触れ、その冷たさと温もりの交差に、ユウは軽く目を閉じた。スカリーの腕から伝わる静かな力は、まるで風のない穏やかな森に佇むような安心感をもたらした。
「……貴方こそ、我輩の何よりも大切な存在でございます。」スカリーの声が耳元に響く。その一言は、冬の冷たい空気を溶かし、心に春の陽だまりを広げた。
ユウは胸がいっぱいになり、何をどう答えればいいのかわからなかった。ただ、彼の温もりに身を委ねるしかなかった。
やがて、スカリーはユウをそっと離し、少し距離をとった。その瞳には柔らかな輝きが宿り、頬には赤みが差していた。けれど彼の表情は、幸福と誠実さに満ちていた。
「……これほどの贈り物をいただいた我輩には、何をもってお返しすればよいのか。」彼の声は穏やかだったが、その奥には深い感謝と愛情が込められていた。
ユウは顔を赤くしながらも微笑んだ。「そんなの、いらないよ。スカリーくんが喜んでくれるなら、それだけで十分だから。」
スカリーはその言葉に微笑み返し、ユウの手をそっと取った。手のひらの温もりを確かめるように、自分の手で軽く包み込む。
「貴方のそのお言葉こそ、我輩にとって最大の贈り物でございます。」
*
二人が再びソファに腰を下ろすと、静けさが談話室に広がった。ツリーの飾り付けが微かに揺れ、その表面で跳ねた光が壁に小さな虹の影を描く。煌めきはまるで、生きているかのように揺らめき、朝の空気に溶け込んでいた。
ユウはカップに両手を添えるようにして、冷えた指先を温めていた。その仕草を見たスカリーは、ユウが少しずつリラックスしている様子に内心安堵した。先ほどの感動と照れが混じる空気は、今では穏やかに落ち着き、二人の間に温かな空気が漂っている。
スカリーは静かに息を整えながら、ふと問いかけた。「ユウさん、少しお聞きしてもよろしいでしょうか。」
ユウはカップから顔を上げ、「何かな?」と微笑みを浮かべた。
「……先ほど貴方が仰っていた、『メリークリスマス』という言葉の意味や、それに込められた思いについて、我輩は少々無知でございます。それは、一体どのような意義を持つのでしょうか。」
スカリーの瞳には真摯な光が宿っていた。その質問には純粋な興味と、ユウの文化や価値観をもっと知りたいという思いが込められていた。
ユウは少し考え込みながら、「上手く説明できるかわからないけど……」と前置きをした。そして、クリスマスがどのような日で、どのような気持ちが込められているのかを簡単に語った。ユウの言葉は自然体で、柔らかな温かさがあった。
「ほら、昨日もちょっと話したけど、贈り物を交換することが、その一部だっていうのも……ね。」ユウは少し照れたように微笑むと、スカリーの手に目をやった。そこには、先ほどのカフリンクスが丁寧にしまわれている。
スカリーはユウの説明を静かに聞き、しばらくの間目を閉じて思索に耽ったようだった。そして、ゆっくりと口を開く。「……大変興味深い文化でございますね。そのような形で思いを伝える日があるとは……。」
彼の声には感嘆と敬意が滲んでいた。そして一瞬ためらった後、彼は続けた。「そのような日に貴方から贈り物を頂いた我輩としても……何かお返しをしたく存じます。貴方にとって特別な何かを。」
ユウは驚いたように目を瞬かせ、「スカリーくんからは、もうたくさんのものを貰ってるよ!」と笑いながら言ったが、彼の真剣な眼差しを見て、それ以上言葉を続けられなかった。
その時、小さなあくびの声が聞こえた。二人の視線が同時に談話室の入り口へ向くと、毛並みの乱れたグリムが寝ぼけた顔を覗かせていた。彼は体をぐるりと伸ばしながら、二人を交互に見つめた。
「ん~……なんで二人とも朝からそんなに近いんだゾ……。オレ様も寒いから、混ぜろ!」
ユウは思わず吹き出しそうになりながら、「グリム、まだ寝てていいよ。寒いなら毛布持ってくる?」と優しく声をかけた。
しかし、グリムはそのまま二人の間に飛び込むように潜り込み、クッションの上で再び丸くなった。「これで十分なんだゾ。オレ様が真ん中だ!ぬくぬく!」
スカリーは少し困ったようにしながらも、柔らかな笑みを浮かべた。「……グリムさんもまた、このひとときの一部でございますね。」
ユウはその言葉に笑いながら頷き、「そうだね。これ以上ないくらいの……特別な朝だと思う。」とそっと呟いた。
談話室の静けさに、ツリーの飾り付けが揺れる音が微かに重なった。彼らの間には、言葉以上の温かなつながりが満ちていた。冷えた空気の中に漂うシナモンの香りと、グリムの穏やかな寝息が、穏やかな幸福を感じさせる。
ウィンターホリデーの朝、談話室には穏やかで柔らかな幸福が満ちていた。
*
せっかくなのでユウさんの詩、英語verも載せておきます。
きっと魔法の力でお互いが読める文字に変換されているはず!

My Favorite Things
Things I love
Sweets enjoyed in the rose garden, Grim’s fluffy belly,
A shiny cauldron, sparkling bits of magical light,
Your voice resonating in the soft night,
The precious moments we spend together.
These are just a few of my favorite things.
Things you love
The Halloween night, a festival glowing with pumpkins,
The scent drifting from an old mansion, the harmony of fear and beauty,
Opera’s melodies, the orchestra’s tunes, the flickering candlelight,
And the dreams reflected in your carnelian eyes.
These are just a few of your favorite things.
Things we both love
A shadowy waltz, warm tea and the golden light of sunset,
Roasted sweet potatoes, the gentle aroma of fallen leaves.
Snow roses sparkling like frost, marshmallows floating in cocoa,
Our special place where no one can intrude.
These are some of our favorite things.
Things I absolutely, truly adore
Your soft, fluffy hair, your carnelian eyes,
The antique fountain pen you gifted me.
When I’m sad or lonely
When I’m stuck with detention,
When I think I might not be able to return,
When I feel like my heart could break,
I just remember them—
All the things I love, all the things you love,
All the special things we share together.
And then, somehow, everything doesn’t feel so bad anymore.
毎朝のことだったが、今朝もスカリーはユウよりも早く起きていた。彼にとって、ユウを起こしに行くのは習慣のようなものだった。ユウの一日の始まりに、自分が関われるという些細な喜び。それはスカリーにとって、何よりも大切な時間だった。
廊下には冬の朝らしい冷えた空気が漂っているが、スカリーの足音はそれを切り裂くように軽やかだった。黒い革靴が軋む床板を滑るように進む。制服のジャケットはきちんと整えられ、ネクタイの結び目も完璧だ。柔らかいベストの生地越しに胸元の温もりを感じながら、スカリーはユウの部屋の扉にそっと手を伸ばした。
「おはようございます、ユウさん。」控えめなノックとともに、いつもの声が静かに響いた。その声は柔らかく、冬の冷たさを和らげるような温かさを持っていた。
しばらくして、奥から眠たげな声が返ってきた。「……スカリーくん?また朝から早いね……。」
扉越しの声にスカリーは小さく笑みを浮かべた。「貴方にとっての良き朝の始まりを、我輩が少しお手伝いできればと。それでは、失礼いたします。」そう言いながら扉をゆっくりと開ける。薄暗い部屋の中で、ユウはまだ毛布にくるまり、ぼんやりとした瞳でこちらを見上げていた。
「本当に、毎日ありがとう。」ユウは布団の中から少し顔を出して微笑んだ。
スカリーはその言葉に首を横に振る。「我輩にとっては、貴方の笑顔を見る朝こそが何よりの贈り物でございますから。」そう言って、そっとユウの額に唇を触れさせた。それは挨拶以上に柔らかく、けれど決して重くはない優しさだった。
ユウはその感触に目を丸くし、次の瞬間、赤面しながら慌てて布団を跳ねのけた。「も、もう!スカリーくん、毎朝やってくれるのは嬉しいけど、今日は特に恥ずかしいから!」
スカリーは軽く肩をすくめて微笑みを隠し、「では、談話室で温かい空気に包まれながら、この美しい朝を共に過ごすというのはいかがでしょうか。」と促した。
談話室の中は静まり返り、ツリーの飾り付けが朝の光を受けてきらめいていた。赤や緑のオーナメントが揺れ、その光は壁や天井に小さな虹を映し出している。部屋に漂うシナモンの香りは、昨夜の宴の名残を優しく思い出させた。
スカリーは部屋に入ると、ツリーに目を留めた。「まるで魔法のような朝でございますね。この静けさと美しさが、昨日の喧騒とは対照的で素晴らしい。」
ユウは隣に立ち、視線をツリーに固定したまま小さく頷いた。「……本当に綺麗だね。こうして見ると、頑張って飾り付けしてよかったなぁ。」
声はわずかに震えているようにも聞こえるが、それはスカリーの視線を避けているせいかもしれない。
スカリーは、ふとユウの表情を横目でうかがった。ユウの頬はうっすらと赤く染まり、その瞳は飾り玉の揺れる光を映している。ヤドリギ事件のことを気にしている様子がわずかに伝わるのを見て、スカリーはさらに慎重に言葉を選んだ。
「……昨日の件、本当に、大丈夫でしたか?その、我輩が何か不快な思いをさせたのではないかと。」
ユウはまたもや顔を真っ赤にして、「もう!言わないでってば!」とツリーの影に隠れるようにしゃがみこんだ。声には明らかに照れが混じっていて、ユウの仕草はまるで小動物が危険から逃げ込むようだった。
その可愛らしい反応に、スカリーは胸の内に湧き上がる喜びを必死で抑えた。表情は控えめな微笑を装っていたが、頬の赤みが抑えきれず、彼の気持ちをわずかに滲ませていた。
「お詫びの気持ちを述べるべきかと思いましたが、どうやらそれは逆効果のようでございますね。」スカリーは柔らかく笑いながら、ユウを見下ろした。
「……本当に気にしてないから!わかった?」ユウは顔を上げることなく、壁に視線を落としたまま声を張った。
「承知いたしました。それでは、談話室の穏やかな空気を存分に楽しみましょう。」スカリーの声は穏やかで、どこかユウへの優しいいたわりが込められていた。
*
ユウが「もう、その話は終わり!」と声を張り上げた後、談話室は再び静けさを取り戻した。二人はツリーを囲むように並んだソファに腰を下ろした。クッションの柔らかさが体を包み込み、冬の寒さを忘れさせるような居心地の良さを与えてくれる。
朝の光が窓から差し込み、飾り付けられたツリーを静かに照らしていた。オーナメントが光を反射し、小さな虹色の輝きが部屋を舞っている。シナモンとクローブが混ざり合った香りがふんわりと漂い、昨日の賑やかな夜を名残惜しく思わせた。
ユウは、ふと横目でスカリーを見た。彼はいつも通り背筋を伸ばし、整った制服姿で椅子に腰掛けていたが、どこかリラックスしているように見えた。目元には穏やかな光が宿り、ツリーを見つめる視線は、まるでそこに広がる夢を眺めているようだった。
その横顔に、ユウは小さく息を吐いて意を決したように口を開いた。
「ねえ、スカリーくん。」
彼がゆっくりと振り向く。「はい、なんでしょう、ユウさん?」
ユウは少し照れくさそうに微笑みながら、後ろに隠していた小さな包みを差し出した。白いリボンがかけられた包みからは、ほんのり甘い紙の匂いが漂っていた。
「メリークリスマス!これ、スカリーくんへのプレゼントだよ!」ユウは声を少し弾ませた。
スカリーは目を見張り、思わず体を少し前に乗り出した。「我輩に…!?これは、一体何のために…?」
彼の声は驚きで少し震え、手が自然に伸びて包みを受け取った。彼がその小さな包みを手に取ると、滑らかな包装紙の肌触りが指先に伝わってきた。丁寧にリボンを解くと、中から現れたのは、一枚の手紙と小さなケースだった。
スカリーはまず手紙を手に取った。封を開けると、万年筆で書かれた美しい文字が並んでいる。視線を落とし、一行一行を静かに読み進める。その内容は、ユウが書いた詩だった。
*
マイフェイバリットシングス
私の好きなものたち
バラの庭園でいただくお菓子、グリムのふわふわお腹、
ピカピカの大釜、飛び散る魔法の光の粒。
君の声が響く優しい夜、
二人で過ごす、ちょっぴり特別なひととき。
みんな私の好きなもののいくつか。
君の好きなものたち
ハロウィンの夜、かぼちゃが灯る祝祭、
古びた洋館から漂う香り、恐怖と美しさの絶妙な調和。
オペラの旋律、オーケストラの音色、蝋燭の揺れる光、
そして君の瞳が映す夢の続き。
みんな君の好きなもののいくつか。
私たちの好きなものたち
影のワルツ、暖かな紅茶と夕暮れの光、
ほかほか焼き芋、落ち葉の香りと穏やかな時間。
氷雪の薔薇、ココアに浮かぶマシュマロ、
二人だけの特別な場所オンボロ寮、誰にも邪魔されない瞬間。
みんな私たちのお気に入り。
私が大大大好きなものたち
君のふわふわの髪、カーネリアンの瞳、
君がくれたアンティークの万年筆。
悲しい時、寂しい時
居残りさせられてしまった時、
もう戻れないかもって思った時、
悲しい気持ちになった時には、
私はただ思い出すの。
私の好きなもの、君の好きなもの、
私たちだけのお気に入りの数々を。
そうするとね、なんだか気持ちがふんわり軽くなるの。
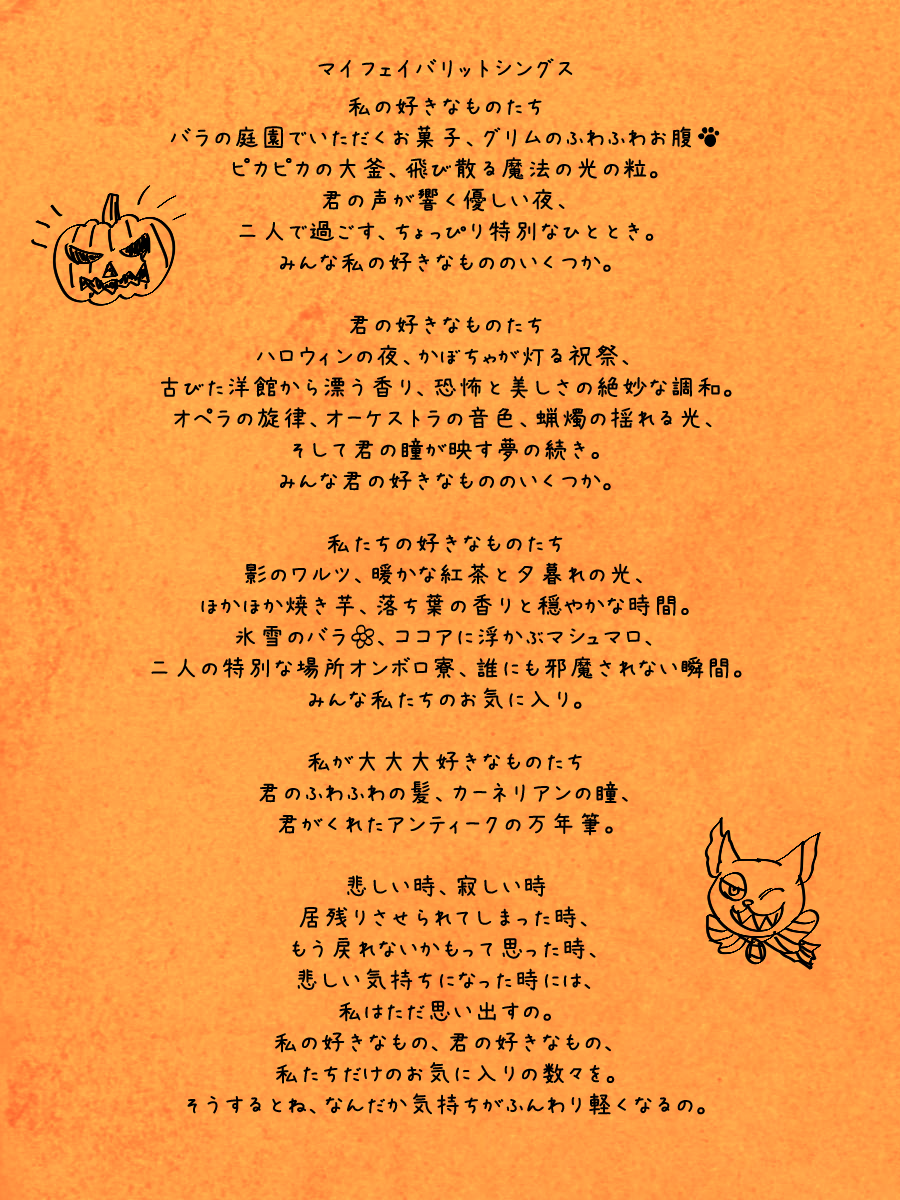
*
スカリーの手がわずかに震えた。詩を読み終えた後、彼は一瞬言葉を失い、ゆっくりと顔を上げた。彼の瞳は普段よりもわずかに潤んでいるようだった。
「……これは…我輩への特別な詩でございますか?」彼の声はいつもより低く、静かだった。
ユウは少し緊張したように頷いた。「うん。この詩はね、私の世界の歌が元になってるんだ。『私の好きなもの(My Favorite Things)』っていう内容で、スカリーくんのことを考えながら書いたの。君がくれた万年筆で……。」
ユウの言葉を聞きながら、スカリーは再び詩に目を落とした。文字に込められた温かさが彼の胸にじんわりと広がっていく。その感触は、朝日の暖かさが冷たい肌を包むような優しさだった。
「これほどの思いを込めてくださったとは……」スカリーは深く息を吐き出し、静かに言葉を続けた。「我輩は、これを一生の宝物とさせていただきます。」
その言葉にユウは少し照れながら笑った。「宝物なんて、大げさだよ。でも、喜んでくれて嬉しい。」
スカリーは再び手元に視線を戻し、今度はもう一つのケースを開けた。中から現れたのは、彼の制服にぴったりなデザインの
スカリーはカフリンクスを指先でそっと摘み上げた。黒地に金で縁取られたジャック・オ・ランタンのモチーフが、朝の光を浴びて繊細に輝いている。その美しさに感嘆するだけでなく、それが自分のために選ばれたのだと考えると、胸の奥がじんわりと温かくなった。
「ユウさん……カフリンクスを、我輩に…?」スカリーの声は驚きでわずかに震えていた。
隣のユウは、彼の反応に戸惑ったように首を傾げる。「うん。スカリーくんに似合うかなって思って選んだんだけど……。あ、もしかして、あんまり嬉しくなかった?」
「いえ!」スカリーは思わず声を上げた後、慌てて咳払いをして声のトーンを落とした。「そのようなことは断じてございません。ただ、この贈り物の意味について、貴方が……」
スカリーの言葉が途切れた。何をどう伝えればよいのか、思考が絡まり合う。彼はカフリンクスを手のひらで包み込みながら慎重に言葉を選んだ。
「ユウさん、このカフリンクスには、特別な意味が込められている場合が多いのです。贈り物として選ばれる際、それは……その……『抱きしめてほしい』という気持ちを暗に伝えるサインとも言われております。」
ユウはぽかんとした表情を浮かべ、一拍遅れて「えっ?」と声を上げた。そして視線をさまよわせながら続けた。「そ、そんな意味があるの?全然知らなかった……。」
その言葉を言いながら、ユウの表情は次第に曇り、ユウはカフリンクスに視線を落とした。「……いつも勉強不足でごめんなさい。ほんとに、私ってものを知らなくて……。」申し訳なさそうに目を伏せたユウは、どこか自分を責めているようにも見えた。
「でも、スカリーくんは物知りだよね。いつもいろんなことを教えてくれるし、私が知らないことばかり気づかせてくれる……。」ユウの声は静かだったが、その中にはスカリーへの尊敬が滲んでいた。
スカリーはユウの言葉に一瞬驚いたような表情を浮かべ、それから優しく首を横に振った。「そんなことはございません。我輩が少しばかり知識を持ち合わせているのは、ただ、それを必要としてきたからにすぎません。」
彼は言葉を区切り、ユウを真っ直ぐに見つめた。「貴方の素晴らしさは、知識の量では測れないものです。それを忘れないでくださいませ。」
その言葉に、ユウは驚きながらも、頬にわずかな赤みを浮かべて「ありがとう、スカリーくん……。」と小さく呟いた。
スカリーはカフリンクスを改めて見つめ、その重みを感じながら深く息を吐き出した。「ユウさん……この贈り物が、どれほど我輩にとって特別なものか、貴方はお分かりでしょうか。」
彼の声は静かでありながら、どこか熱を帯びていた。ユウは少し驚いたように目を瞬かせ、「えっと……わからないけど、スカリーくんが喜んでくれるなら、それでいいんだ。」と答えた。
*
スカリーはカフリンクスを握りしめたまま、視線をユウに向けた。ユウの無邪気な言葉――「スカリーくんが喜んでくれるなら、それでいいんだ」――は、心の奥深くに響き渡り、胸の中で静かに広がっていく。
ユウのその無垢な笑顔に対するこの想いを、どう表現すれば伝わるのだろう?どんな言葉を紡いでも、それが不十分であるような気がした。
「ユウさん……。」スカリーの声は低く、けれどどこか震えていた。「この贈り物が、どれほど我輩にとって大切なものか……貴方にお伝えする術を、我輩は持ち合わせておりません。」
ユウはその言葉に驚き、彼の真剣な眼差しに息を呑んだ。ユウの頬がじんわりと赤く染まり、温かさが広がっていく。心臓が早鐘を打つように高鳴り、言葉が出てこなかった。
スカリーは一瞬目を伏せた。次に顔を上げたとき、その瞳には揺るぎない決意が宿っていた。「……では、言葉ではなく、この想いを形にさせていただきます。」
彼はゆっくりと手を伸ばした。その動きは慎重で、まるで宝物に触れるような繊細さだった。手がユウの肩に触れた瞬間、ユウは僅かに肩をすくめたが、拒む様子はなかった。スカリーは一歩近づき、優しくユウを包み込むように抱きしめた。
彼のジャケットの生地が肌に触れ、その冷たさと温もりの交差に、ユウは軽く目を閉じた。スカリーの腕から伝わる静かな力は、まるで風のない穏やかな森に佇むような安心感をもたらした。
「……貴方こそ、我輩の何よりも大切な存在でございます。」スカリーの声が耳元に響く。その一言は、冬の冷たい空気を溶かし、心に春の陽だまりを広げた。
ユウは胸がいっぱいになり、何をどう答えればいいのかわからなかった。ただ、彼の温もりに身を委ねるしかなかった。
やがて、スカリーはユウをそっと離し、少し距離をとった。その瞳には柔らかな輝きが宿り、頬には赤みが差していた。けれど彼の表情は、幸福と誠実さに満ちていた。
「……これほどの贈り物をいただいた我輩には、何をもってお返しすればよいのか。」彼の声は穏やかだったが、その奥には深い感謝と愛情が込められていた。
ユウは顔を赤くしながらも微笑んだ。「そんなの、いらないよ。スカリーくんが喜んでくれるなら、それだけで十分だから。」
スカリーはその言葉に微笑み返し、ユウの手をそっと取った。手のひらの温もりを確かめるように、自分の手で軽く包み込む。
「貴方のそのお言葉こそ、我輩にとって最大の贈り物でございます。」
*
二人が再びソファに腰を下ろすと、静けさが談話室に広がった。ツリーの飾り付けが微かに揺れ、その表面で跳ねた光が壁に小さな虹の影を描く。煌めきはまるで、生きているかのように揺らめき、朝の空気に溶け込んでいた。
ユウはカップに両手を添えるようにして、冷えた指先を温めていた。その仕草を見たスカリーは、ユウが少しずつリラックスしている様子に内心安堵した。先ほどの感動と照れが混じる空気は、今では穏やかに落ち着き、二人の間に温かな空気が漂っている。
スカリーは静かに息を整えながら、ふと問いかけた。「ユウさん、少しお聞きしてもよろしいでしょうか。」
ユウはカップから顔を上げ、「何かな?」と微笑みを浮かべた。
「……先ほど貴方が仰っていた、『メリークリスマス』という言葉の意味や、それに込められた思いについて、我輩は少々無知でございます。それは、一体どのような意義を持つのでしょうか。」
スカリーの瞳には真摯な光が宿っていた。その質問には純粋な興味と、ユウの文化や価値観をもっと知りたいという思いが込められていた。
ユウは少し考え込みながら、「上手く説明できるかわからないけど……」と前置きをした。そして、クリスマスがどのような日で、どのような気持ちが込められているのかを簡単に語った。ユウの言葉は自然体で、柔らかな温かさがあった。
「ほら、昨日もちょっと話したけど、贈り物を交換することが、その一部だっていうのも……ね。」ユウは少し照れたように微笑むと、スカリーの手に目をやった。そこには、先ほどのカフリンクスが丁寧にしまわれている。
スカリーはユウの説明を静かに聞き、しばらくの間目を閉じて思索に耽ったようだった。そして、ゆっくりと口を開く。「……大変興味深い文化でございますね。そのような形で思いを伝える日があるとは……。」
彼の声には感嘆と敬意が滲んでいた。そして一瞬ためらった後、彼は続けた。「そのような日に貴方から贈り物を頂いた我輩としても……何かお返しをしたく存じます。貴方にとって特別な何かを。」
ユウは驚いたように目を瞬かせ、「スカリーくんからは、もうたくさんのものを貰ってるよ!」と笑いながら言ったが、彼の真剣な眼差しを見て、それ以上言葉を続けられなかった。
その時、小さなあくびの声が聞こえた。二人の視線が同時に談話室の入り口へ向くと、毛並みの乱れたグリムが寝ぼけた顔を覗かせていた。彼は体をぐるりと伸ばしながら、二人を交互に見つめた。
「ん~……なんで二人とも朝からそんなに近いんだゾ……。オレ様も寒いから、混ぜろ!」
ユウは思わず吹き出しそうになりながら、「グリム、まだ寝てていいよ。寒いなら毛布持ってくる?」と優しく声をかけた。
しかし、グリムはそのまま二人の間に飛び込むように潜り込み、クッションの上で再び丸くなった。「これで十分なんだゾ。オレ様が真ん中だ!ぬくぬく!」
スカリーは少し困ったようにしながらも、柔らかな笑みを浮かべた。「……グリムさんもまた、このひとときの一部でございますね。」
ユウはその言葉に笑いながら頷き、「そうだね。これ以上ないくらいの……特別な朝だと思う。」とそっと呟いた。
談話室の静けさに、ツリーの飾り付けが揺れる音が微かに重なった。彼らの間には、言葉以上の温かなつながりが満ちていた。冷えた空気の中に漂うシナモンの香りと、グリムの穏やかな寝息が、穏やかな幸福を感じさせる。
ウィンターホリデーの朝、談話室には穏やかで柔らかな幸福が満ちていた。
*
せっかくなのでユウさんの詩、英語verも載せておきます。
きっと魔法の力でお互いが読める文字に変換されているはず!

My Favorite Things
Things I love
Sweets enjoyed in the rose garden, Grim’s fluffy belly,
A shiny cauldron, sparkling bits of magical light,
Your voice resonating in the soft night,
The precious moments we spend together.
These are just a few of my favorite things.
Things you love
The Halloween night, a festival glowing with pumpkins,
The scent drifting from an old mansion, the harmony of fear and beauty,
Opera’s melodies, the orchestra’s tunes, the flickering candlelight,
And the dreams reflected in your carnelian eyes.
These are just a few of your favorite things.
Things we both love
A shadowy waltz, warm tea and the golden light of sunset,
Roasted sweet potatoes, the gentle aroma of fallen leaves.
Snow roses sparkling like frost, marshmallows floating in cocoa,
Our special place where no one can intrude.
These are some of our favorite things.
Things I absolutely, truly adore
Your soft, fluffy hair, your carnelian eyes,
The antique fountain pen you gifted me.
When I’m sad or lonely
When I’m stuck with detention,
When I think I might not be able to return,
When I feel like my heart could break,
I just remember them—
All the things I love, all the things you love,
All the special things we share together.
And then, somehow, everything doesn’t feel so bad anymore.
