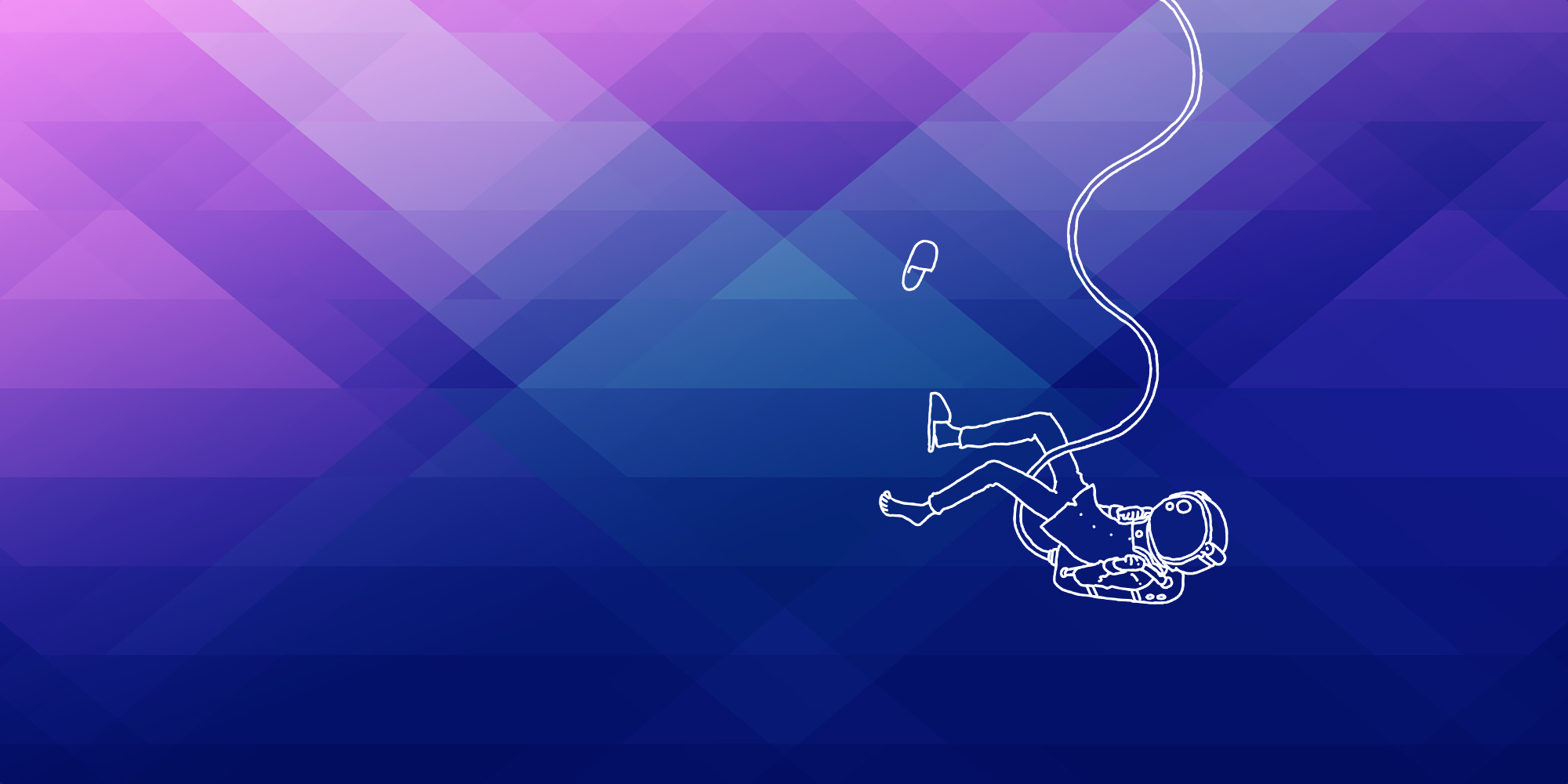素敵な夢になりますように…
darling 6
Name change
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
「…あれは…完全に、見られたよなぁぁ…」
自室に戻った私は、頭を抱えてデスクに伏せていた。
リヴァイは、私とアランが抱き合ってるのを見てどう思ったのだろうか…。
付き合ってる、と思ったかな…
普通、そう、思うよね…
…ショックを、受けるだろうか。
………
……いや、それはないか。
何とも思ってなさそうだ。
…別に、誤解されたからといって弁解するのもおかしいし…
そもそも、弁解する必要なんてないわけで。
…関係なくても、誤解はされたくない。。
「~~っ…はあぁぁ。」
もう何度目か分からない溜め息をつくと、聞き慣れた低い声が耳元を掠めた。
「おい。てめぇは耳がついてねぇのか」
「っう、わっ!?リヴァっ…!?い、いいいいいつの間に…!!
は、入るならノックくらいしてよ!」
「ほざけ。したのに返事もしねぇお前が悪い」
思い悩み過ぎて、いつの間にか目の前にリヴァイがいたことも、ましてやノックをしていたことすらも気付かなかった。
まさか、今まさに悩みの種である本人が目の前にいるとは。
私は若干パニックになりつつ、とにかく落ち着こうと言葉を発した。
「な、な、なんか用?」
動揺は隠せてないが、必死に絞り出した。
すると、少し視野が広がり、リヴァイの持っている物にようやく気が付く。
「…それ、どうしたの…?」
リヴァイは、パンとチーズが盛り合された皿を手に持って立っていた。
「言っとくが、これは食堂の女給仕にお前に持っていけと無理矢理に渡されたもんだ。
…お前、訓練したあとはしっかり食事を摂れ。俺達は身体が資本なんだぞ」
「ご、ごめん…。か、考え事してたら、遅くなっちゃって…。」
正論を諭され、私はまた情けない気持ちになった。
こんなことで周りに迷惑を掛けないようにしなくては…。
…リヴァイも呆れてる…。
…はあ、せっかくこの前、少し認めてもらえたと思ったのに…。何やってんだ私は…。
そう思っていると、リヴァイは大きく息を吐いた。
「…フン、まあいい。…今日はこれ食って、明日の朝はしっかり食え」
「うん…。ほんと、ごめん。」
「……」
「………………?」
…なんだろ…帰らない、の?
なんかめっちゃ睨んでるし。怖いんですけど!?
「おい。」
「っ!な、なに?」
「それ持ってついて来い」
「へ?」
リヴァイは私の聞き返しに答えることなくそのまま部屋を出るから、私は慌てて受け取ったお皿を持って立ち上がった。
・-・-・-・-・-・
「入れ」
「…(ここリヴァイの部屋…だよね)」
「聞こえねぇのか」
「あ、ごめん」
何も話さないリヴァイの後をついていけば、私はリヴァイの部屋に辿り着いた。
中は相変わらず綺麗で整頓されている。
一体、この男はこの忙しい身でいつ掃除をしているのだろう。
そんなどうでもいい事を考えていたら、きっとペトラが、とまた余計な事が思い浮かび私の気持ちは再びダウンしていった。
「おい、何辛気臭ぇ面して突っ立ってやがる。とっとと座れ」
「え、…座れったって…」
リヴァイが何を考えているのかさっぱり分からない私は、先にソファに座っているその無愛想な男を見つめた。
と、よく見ると、その手にはいつの間に持ってきていたのかワインボトルが握られていた。私は、「あ」と声を漏らした。
「それ、…この前言ってたワイン…?」
「そうだ。いつまで経ってもお前が来ねぇから呼びに行ってやったんだ。丁度いいツマミも手に入ったことだしな」
リヴァイはそう言うと、「早く座れ」ともう一度口に出したので、私はしぶしぶリヴァイの隣に腰を下ろした。
目の前のローテーブルに持ってきたお皿を置くと、事前に用意してくれていたのか、テーブルに乗っていたグラスにリヴァイがワインを注いでいく。
どうやらスパークリングワインのようだ。
シュワシュワと音を立てて注がれるその様子を、私はぼーっと見つめていた。
注ぎ終わったグラスをスッと渡され、私は条件反射でそれを受け取る。
そのまま、自分のグラスを持ったリヴァイが私を見てそれを目の高さに持ち上げた。
「これ、何の乾杯?」
私の質問にピクリと片眉を上げたリヴァイは、一瞬考えてすぐに「合同班の初陣の景気づけだ」と答えた。
エルヴィンから、明日は壁外調査に備えて身体を休ませるよう事前に全兵士休みを指示されている。
よって、今日酒盛りをしている兵士達は多い。
私はなるほど、と納得し、グラスを同じように持ち上げワインを含んだ。
「…わ、おいし…」
「ああ。…悪くない」
貴族から貰ったというそのワインは、とても口当たりが良く、程よいマスカットの香りが鼻腔を擽った。
飲みやすくてスイスイ飲んでしまいそうだ。
そう思ってるそばから、私のグラスは空き、隣を見ればリヴァイも二杯目を注いでいる。
私はグラスをリヴァイに差し出すと、リヴァイは眉間の皺を深くしてこっちを見てきた。
「…私もおかわり。」
「早ぇな」
「リヴァイだって」
「俺は元々このペースだ」
「だって美味しいんだもの」
「…潰れたら襲うからな」
「ブフッ」
「汚ぇな」
話しながら注いでくれたワインを口に運んでいたら、リヴァイからの予想外の言葉に思わず咽た。
この男は、なんでこう、いちいち私の心をざわつかせるのか。
しかもペトラという可愛い彼女がいるくせに、なぜ他の女にこう思わせぶりな態度をとるのか。
…ああ、そうだった。こいつは浮気できる男だったな、と私は思い出し、イライラしながら自分のハンカチで口元と少し零れたテーブルを拭いた。
「ご心配なく!ボトル1本で潰れるほど弱くないし」
「は。どーだかな」
よかった。普通に喋れてる…。
私は、ペトラの顔を思い出すとどうしようもなく後ろめたい気持ちになるのに、それでも、今、リヴァイといるこの時間が、ずっと続けばいいのにと願ってしまう。
今、この時だけは。
私とリヴァイだけの時間であってほしい。
は。私も大概、諦めの悪い女だな。
…でも、無理に忘れようとするからツライわけで。
そうだ。自然と忘れられる日がくるはず!
それまでは無理に忘れずにいよう。
私は今はまだ、リヴァイが好きなんだから。
・-・-・-・-・-・-・-・-・-・
「…誰がボトル1本じゃ潰れないんだ、あ?」
「んー…潰れてない、し」
気持ちを切り替え、改めて楽しく飲み始めたNAMEは、空きっ腹に速いペースで飲み進めたことがたたって、ボトルが空く頃には完全に酒にのまれていた。
リヴァイはソファに片足を乗せ、ひじ掛けに背を預けて隣のNAMEに呆れた視線を落とす。
NAMEは反対側のひじ掛けに両手を乗せてその上に頭を擡げている。
うつろな瞳は、眠たいのか今にも閉じそうだ。
しかし、話しかければ返事はする。酔ってなるものか、というNAMEの頑固さが理性を保とうと戦っているのかもしれない。
リヴァイは面倒くさそうに舌打ちを一つすると、グラスに水を入れてNAMEに差し出した。
「飲め」
「ん。ありがと…」
「……」
やはり、こいつは酒に酔うと素直になるんだなと、リヴァイは先日の飲み会を思い出し、頭の中でふと考えていた。
NAMEは凭れていた身体を起こして水を飲み干し、そしてまた同じように頭をひじ掛けへと落とす。
先と同じ位置に座ったリヴァイは、酔ったNAMEをまじまじと見つめた。
今はお互い、兵服は脱いで私服だ。
二人ともTシャツにパンツというラフな格好だが、NAMEに関してはかなり短いショートパンツを履いていた。
NAMEの部屋へ行った時は、NAMEはデスクに座っていた為何を履いているかまではリヴァイには全く分からなかった。
リヴァイはそのままNAMEを見ずに自分の部屋へ来た為、招き入れて改めてNAMEを見た時は思わず心臓が跳ねた。
なんて格好をしてやがる、と。
暑くなってきたとはいえ、まさかそんな脚を出した格好をしているとは思わなかったリヴァイは、今更着替えてこいとも言えず、なるべく目線を下げずにいた。
最早、NAMEの目を気にする必要のなくなった今、リヴァイはNAMEの惜しみなく出されているその脚を眺めた。
白くしなやかな、しかし引き締まったそれはスラっと伸び、上半身を倒しているせいで太腿の先も覗けば見えてしまいそうだ。
リヴァイは生唾を呑み込み、そしてそのまま、視線を脚から全身へと広げていく。
腿と尻の境目がギリギリ見える位置に座っていたリヴァイは、思わずその尻に手が伸びそうになる。
丸く形のいい尻から滑らかな曲線を描いたウエスト。
ゆったりとしたTシャツの為その華奢であろう腰は想像しかできない。
そして胸も同じく今はその服で分からないが、普段の兵服ではベルトに締められその大きさはいつも強調されている。
しかもだ。先日の憲兵団との事件の際に、リヴァイはNAMEの下着姿をしっかり見ている。
NAMEの胸は、巨乳とまではいかないものの、程よい大きさの張りのある、それでいて柔らかそうなそれが、リヴァイの脳裏に焼き付いて離れなかった。
ゆっくりと視線を更に上げれば、トロンと閉じかけている瞳に赤く染まる頬。
そして、艶のある唇がリヴァイを誘っているようだった。
じっとそこを見つめていると、その唇がゆっくりと開かれ、リヴァイはハッと我に返った。
「リヴァイ?」
「…なんだ酔っぱらい」
「………、り、がと…」
「…聞こえねぇ。なんだ」
「…だ、だから、…あ、ありがと…」
「あ?…なんだ、急に」
「…ず、ずっと、言えて、なかったから」
急に出てきたその言葉に、リヴァイは目を丸くした。
NAMEは重たそうな身体をもう一度ゆっくりと起こし、リヴァイと対面するように同じくひじ掛けに背を預け、そして両足をソファに乗せ膝を抱えて座った。
その際、リヴァイはまたショートパンツの奥に一瞬目がいったが、すぐに逸らした。
「…何の礼だ」
「い、色々。…この前も、今日も、パンとか、わざわざ持ってきてくれてありがとう」
「…ああ。…今更だな」
「あ、と…この前、のど飴、くれてありがとう。」
「…いつの話してやがる」
「それと、…憲兵団に連れていかれた時、助けにきてくれてありがとう…。
ごめん、すぐ言わなくて…。」
NAMEはそのまま恥ずかしそうに顔を膝に埋めた。
リヴァイはそれを見ると、あの時、NAMEに飴を渡した時と同じように、柔らかく笑った。
NAMEはその表情につい見とれてしまう。
見とれているうちに、開いていた距離を縮めたリヴァイは、背もたれに腕を置き、NAMEの膝を挟んで目の前に来ていた。
「いつも、そうやって素直でいてくれると助かるんだがな」
その近い距離に、NAMEは思わずたじろぐ。
リヴァイは逃がさない、といった瞳でNAMEのそれを射抜き、言葉を続けた。
「今日、なんで泣いてた」
「えっ…」
「泣いてたろ。…アランと、何かあったのか」
先の出来事を思い出し、NAMEはかぁと顔が熱くなるのを感じた。
抱き合っていたのを見られたと思っていたが、まさか泣いていたことまでバレているとは思わなかった。
だって涙は確かに拭ったはずだったから。
何故?と言っているような瞳に、リヴァイはまた優しく笑う。
「目が腫れてるぞ。さっきも赤かったしな」
「っ…!」
NAMEはバッと片手を目元へ伸ばそうとしたが、その手をリヴァイに掴まれ阻まれた。
リヴァイはじっとNAMEの瞳を見たまま離さない。
「…アランは、お前の恋人になったのか」
「っ違う!」
NAMEはリヴァイの問いに、少し大きめの声で否定した。
自分でもその大きめに出た声に驚いているようだ。
NAMEはパッとリヴァイの瞳から視線を外した。
「…ちょっと、不安に思うことがあって…。アランは、それを心配してくれただけ、だよ。…も、もう大丈夫、だから」
「…そうか。」
チラと、外していた視線を戻しリヴァイを見遣れば、その視線にまた捕まえられNAMEはビクッと肩を揺らした。
突然の問いに、誤解されたくないと思っていた問題が思いがけず解決したのは良かったが、この近付いた距離が変わらず、リヴァイが自分を見つめるその熱の篭った瞳に、せっかく覚めたと思った酔いがまた回ってくるような気になった。
見つめられて顔がどんどん熱くなっていく。
掴まれたままの手首にも、熱が伝わっている気がして、NAMEの心臓はどんどん速くなった。
to be continued...
2/2ページ