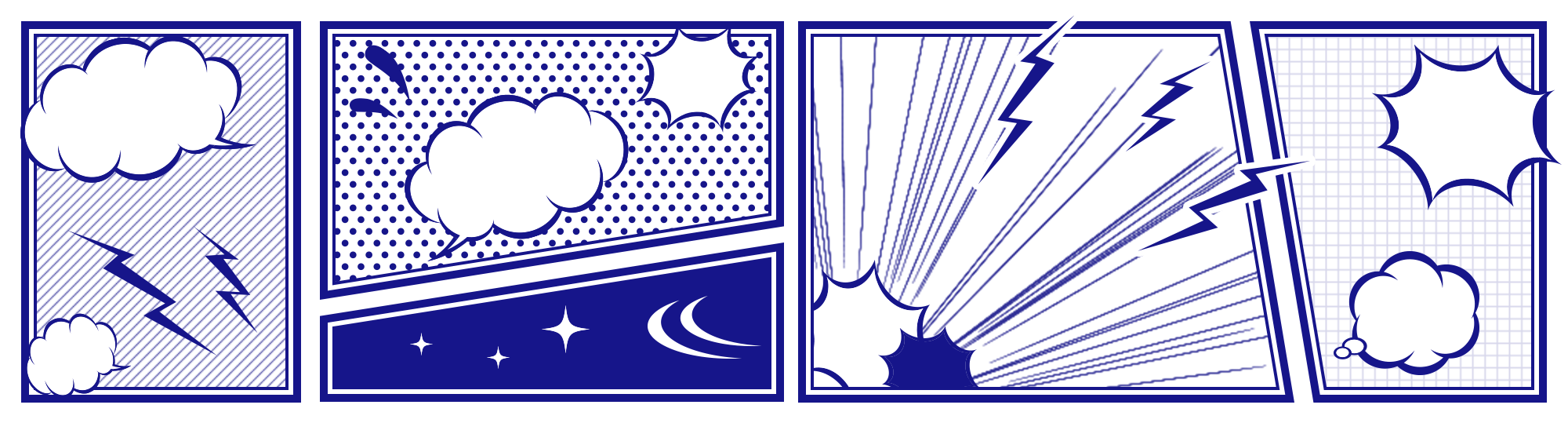我儘
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
※「心の隅に※」の続き
※最赤表現あり
先日、2週間付き合った彼氏に浮気されて振られた。
その前の彼氏には暴力をふるわれて逃げた。
そのまた前はお金の無心をされて断ったら用無しだと追い出された。
更にその前は…うん、もうこれ以上は思い出したくないかな。
「そっかー、またダメだったんだ」
「そうなの。あーあ、楓ちゃんが羨ましいなぁ…最原くん優しいもんね」
休日、久しぶりに会う楓ちゃんとカフェでお茶をしていた。
自然と話題は最近の話へと移り、私はこの間の苦い経験を彼女に伝える。
過去のこともある程度は知っているため驚かれたりはしないものの、しみじみと呟くように感想を言われた。
「もー、何言ってんの。まぁ…優しくしてもらってるけど。…でもさ、なんて言うかなまえちゃんって本当に…男運ないよねぇ…」
「やっぱりそう思う?…はぁ、この前王馬くんにも同じこと言われた」
「ふふ、言いそう。そういえば、王馬くんともずっと仲良いよねー。よく家にも遊びに行くんでしょ?」
「うん、家に行くのはそこまで頻繁ではないけど…好きな時に来ればって言われるから」
「なんかさー、それもちょっとドキドキするシチュエーションじゃない?」
楓ちゃんの言葉に首を傾げる。
確かにお互いに意識し合っている関係ならそうかもしれない。
でも、私と王馬くんは生憎そんな色気のある関係ではないのだ。
本当に、ただの友達。
彼から私を異性として認識している素振りを感じたことすらない。きっとそんな風には見られていない。
「私と王馬くんはそういうのじゃないよー。だってさ、私が映画見て泣いてたらブスに磨きがかかってるとか言ってくるんだよ?絶対そんな対象だと思われてないってば」
「あはは、それはもう王馬くんの性格でしょ。でもほら、しんどい時慰めてくれたりもするんでしょ?案外優しいとこあるよね。私、学生の頃はそんな一面があるなんて全然知らなかったよ」
「うん、優しいよ。なんで彼女いないのか不思議なくらい」
「ふふ、私としてはこのまま2人がくっついてくれたら安心なんだけどなー」
私と王馬くんが…?
そう言われてしまうとついつい恋人っぽいことをしている場面を想像してしまって、浮かんできた考えを慌ててかき消す。
楓ちゃんはニヤニヤしながらそんな私の様子を見ていた。
「や、やめてよー、今度会う約束してるのに変に想像しちゃうじゃん!」
「えー?いいじゃーん、なにか進展あったら教えてね!」
「ないない!ふふ、もう…そんな期待した顔しないでってばー」
*****
「みょうじちゃん?おーい、聞いてる?」
「へっ?あ…ごめんね、何だっけ?」
「もー、お昼何処で食べよっかって話!…なんか今日やけにぼーっとしてない?具合でも悪いの?」
「う、ううん、大丈夫!ちょっと次の仕事のこと考えてただけ」
数日前に楓ちゃんに言われたことが頭をよぎって、ついつい意識しそうになってしまう。
王馬くんは訝しげに私を見て、ずいっと顔を寄せてきた。
「ふーん、みょうじちゃんいい度胸だね。オレに嘘ついちゃうんだ?」
「え…」
王馬くんは怒っているのかも分からない、感情の見えない目で私を見つめる。
恐怖とまではいかないが、何故か足がすくんで逃げられないと錯覚するような感覚。
もう彼とは数年の付き合いになるけど、彼の総統としての部分を初めて垣間見た気がした。
「そんな見え透いた嘘で隠し通せるわけないでしょ。ほら、今白状して正直に話すなら許してあげるけどどうする?」
「は、話します…ごめんなさい…」
近くにあった公園のベンチに腰掛け、ぽつぽつと数日前の出来事を話した。
きっとこんなこと言っても呆れるか笑われるだけ、そう思っていたけど王馬くんは茶化すことなく私の話を黙って聞いていた。
「…ということがあって。ご、ごめんね?そんな風に思われても王馬くんも困っちゃうよね!私も最近言われたばっかりでつい意識しちゃったけど、きっとすぐ元に戻ると思うから…」
「別に困らないけど?」
私の言い訳を遮るように、あっさりと王馬くんはそう言った。
驚いて彼の方を見るといつものにやけ顔ではなくいたって真面目な顔をしており、想像とかけ離れた反応に思わず心臓が跳ねる。
「みょうじちゃんがオレを男として見るようになったとして、それでなんでオレが困ると思ったの?」
「だって…私たち、友達だし…。王馬くんも、女として見てない人から急に異性として見られても困るかなって」
「んー、それは確かにそうかもね。…オレがみょうじちゃんを女として見てなかったらの話だけど」
なんだかそれってまるで、今は女として見てるみたいな言い方。
そう思ったけど、追及してしまうと後戻りできない気がして声にはならなかった。
「あーあ、こんなこと言うつもりさらさらなかったのに。赤松ちゃんもやってくれたよねー」
王馬くんは自嘲気味に、空を見上げながら呟いた。
その言葉の意味するところは…と考えてしまう。
顔に熱が集まってきて、心臓がうるさいくらいに鳴り始める。
「…ずっと見てたよ、みょうじちゃんのこと」
「それって…その…」
「あー…友達として見てたことなんてただの1度もないよ。ずっと女の子として見てたし、ずっと好きだった。…なんてさ、一生言わない気でいたのになんでこんなこと口走ってんだろうなー、オレ」
「本当、なの…?」
頭の中にはこれまでの思い出が巡る。
もし本当に王馬くんが私の事を好きだったなら、私がしてきたことは…ずっと彼を苦しめる行為だったのかもしれない。
「ごめん、今回は嘘じゃない。あーでも、やっぱり嘘ってことにしておこうかな。そうしたらみょうじちゃんはそんな顔しなくて済むんだもんね」
「そんなの、いくらなんでも嘘だなんて思えないよ…」
「たはー…だよね。もー、なんでみょうじちゃんが泣くのさ?こんな想定外の暴露しちゃって、泣きたいのはオレの方なんだよー?」
「ごめん、ごめんね…」
王馬くんはどこか悲しそうな笑顔を浮かべながら、私の頬に滲む涙を指で拭う。
こんな時でも彼の優しさに甘えてしまっている自分が嫌になる。
「私、今まで全然気づいてなくて…、王馬くんにひどいこと…」
「みょうじちゃんのくせにオレの心配するなんて100年早いんじゃない?大丈夫だよ。…分かっててそのポジションを選んだのはオレなんだからさ」
「だけど…」
「でもそれも今日までかなー。笑っちゃうよね、自分で自分の守ってきた場所壊しちゃうなんてさ。…初めてみょうじちゃんがオレのことちょっとでも意識してるんだって思ったら、急に我慢できなくなっちゃったみたい」
王馬くんはそっと立ち上がって、私の方を振り返る。
「ごめんね、みょうじちゃん。もう次からは慰めてあげられないけど…元気でね」
強ばった笑顔でそう言ってから、私のいる方とは反対に向き直り歩き始める。
これで、さよならってこと?そんなの嫌だ。
でも、ここで呼び止めたらきっと優しい彼をもっと苦しめる事になってしまう。
そう思うと遠ざかっていく背中に声をかけるのがはばかられる。
この先もう会えないかもしれない。
私の日常から彼の姿が消えていく。
なんだか全ての物が色褪せていくような、言い知れぬ虚無感。
どうしてこんなに苦しくなるんだろう、どうして今も涙が止まらないんだろう。
なんで私、今になって気がついたんだろう。
こんなに大切だって思っていたことに。
「王馬くん…!待って、お願い…」
大きいとは言えないその声は彼に届かない。
気がついたら私は彼の背中を追いかけていた。
走って、後ろから勢いよく彼の背中を捕まえる。
「…おっと…って、みょうじちゃん…。何、最後に言い残したことでもあった?」
最後という言葉に胸が痛む。
やっぱり今じゃなきゃ、もう伝えられないんだ。
私は意を決して口を開く。
「ある、いっぱい。言い残したことだらけ」
「もーしょうがないなぁ、そんな声で言われたら断れないじゃん。聞いてあげるよ、どんなこと?」
「私…王馬くんがいなくなるのは嫌だよ。ずっと、私のことそばで慰めてくれるのは…これから先も王馬くんがいい」
「……うん」
「今さら何言ってるんだって思われるかもしれないし、信じてもらえないかもしれない…けど…私、…王馬くんのこと、好きだったみたい…」
「……」
「………あの、王馬くん…?」
「はぁ…みょうじちゃんって、ホント我儘で面倒臭くて手がかかる子だよね」
「…ご、ごめんなさい」
「そんな子の相手してあげられるのって、多分オレくらいだと思うよ」
王馬くんは振り返って、私の顔をじっと見て笑った。
ぐちゃぐちゃでひどい顔、なんていつもみたいな憎まれ口を叩きながら、いつもよりも優しく私の頬を撫でる。
「王馬くん、私…ごめんね。今までのことも、今のことも…全部」
「それはもういいから泣かないでよー。オレの手がぶよぶよにふやけちゃってもいいの?」
「…ふふ」
「……ねぇ、みょうじちゃん」
「何?」
「なんかオレ、今すごい幸せかも」
ぽつりとそう呟く王馬くんに、思わず笑みがこぼれる。
ずっと近くにいたはずなのに、初めて見る表情、声色、仕草…今までよりも距離が近づいた気がして嬉しくなった。
「何笑ってんの」
「ふふ、何でもない」
「にしし、変なみょうじちゃん。でもさ…そういうとこも含めて、好きだよ」
「うん。私も…好きだよ、王馬くん」
ずっと友達だった人が恋人になった日。
まさかこんな日が来るなんて少し前まで想像もしていなかったけど、今まで感じたことの無い安心感で満たされる。
今度こそ私、きっと幸せになれる…そんな予感を感じながら私たちは手を繋いで歩き始めた。
1/1ページ