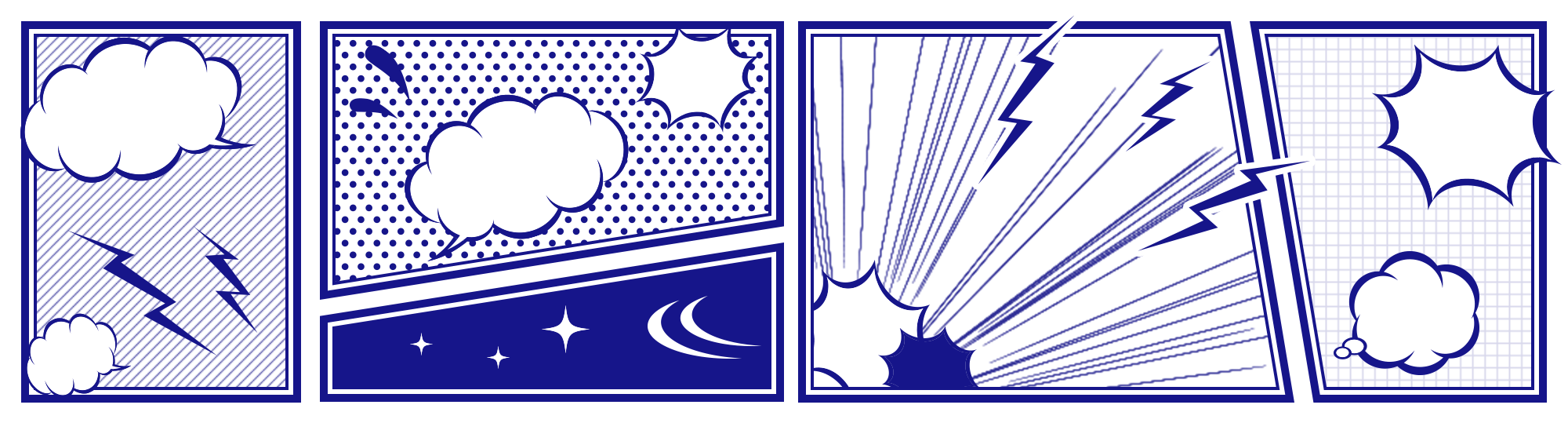前髪を切ったあの子
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
※王馬視点
※ 前髪を切った日の続き
全部全部、始まりはただの気まぐれだった。
いつもおどおどして、『コミュ障です』と張り紙でもされてるんじゃないかと思う女の子を執拗に構い始めたことも。
どんな反応をするのか見てみたいという理由で、彼女のことを半ば強引に『なまえちゃん』と呼び始めたことも。
「切った方が可愛いと思うんだけどなぁ。なまえちゃん」
少し前に改めてなまえちゃんの顔を見た時、笑っちゃうくらいに彼女の瞳が見えなくて。
こっちからは見えてないのに、あの子からはちゃんと見えてるの?と、純粋に疑問に思った。
そういえばオレは、この子の瞳の色も知らない。
一度考え始めると気になってしまう性分故か。
勝手に近づいて、勝手に前髪を避けて、そうやって初めて彼女と目が合ったことに、浮かれていたのかもしれない。
独り言のつもりだった言葉は、無意識に口をついて外に出て行った。
「え…」
小さな小さな、彼女が驚いた時に出す声。
部屋に流れる映画の音量より遥かに小さいはずのそれが、妙に鮮明に聞こえた。
そうして初めて、自分の失態に気がつく。
「嘘だけどね!」といつものように続ければ良かったものを、何故かそんな簡単なこともこの時のオレは思いつかなかった。
ただただ、そっぽを向いて動揺した顔を見られないようにすることしか出来なかった。
「…似合う、でしょうか」
「え?」
「前髪…です。切っても、似合うでしょうか?」
そんなこと言われても、分かるわけないじゃん。
さっき初めてキミの目を見たばかりのオレに。
…だけど、どうせもう冗談だと流すことも出来ないのなら。
「知らなーい。…けど、似合うんじゃない?」
なまえちゃんがいつも、どんな目で何を見ているのか、少しは興味が湧いたから。
それだけの理由だと、心の中で言い訳をしながら無愛想にそう答えた。
*****
「お、おはようございますっ…」
翌日、いつものように食堂で朝食を食べていた時だった。
背後にある扉から、笑っちゃうくらい緊張が丸見えのなまえちゃんの声が聞こえる。
余程力んでいたのか、若干上擦った声で放たれたその挨拶。
おはようって言うだけでも、コミュ障のなまえちゃんにはいっぱいいっぱいだよね。
可哀想だから早めに返事をして、ついでに笑ってあげる…なんて、そんな気持ちで振り返りながら声をかけることにした。
「なまえちゃん、おは………」
「お、王馬くん…?」
近寄ってきた彼女の姿を目にした途端、続く言葉を失う。
昨日まであったはずの、オレと彼女を隔てていたものが綺麗さっぱりなくなっていたから。
ホントに切ってきたの?
…オレが似合うって言ったから?
なんか、それって…。
得体の知れないむず痒い感情。
けれども、明らかにオレの感想待ち状態のなまえちゃんから浴びせられる、そわそわした視線は悪くないと思えた。
「切ったんだ、前髪」
「は、はい…。あのっ」
「へぇ、やっぱり⎯⎯⎯⎯」
オレの言った通りじゃん。
と、そう伝えるつもりだった。
「みょうじさん、おはよう!…あっ、髪切ったんだ!可愛いね」
オレが伝える予定だった言葉よりも先に、赤松ちゃんの素直な褒め言葉が食堂内に響く。
そうしてあれよあれよという間に、なまえちゃんは赤松ちゃんを始め色んな人に囲まれて…。
「似合う」
「可愛い」
そんな褒め言葉に包まれて、彼女は俯き気味にはにかんだ。
そんな表情もできること、知らなかったなぁ。
…当たり前か。オレ、キミの瞳の色すら昨日知ったばかりなんだもんね。
和気あいあいとした暖かな空間は妙に居心地が悪く感じられて、オレはそっとその場を抜け出した。
*****
ぼふん。
わざと大きめの音を立てるようにベッドに沈み込む。
「はぁ…」
聞かせる相手もいないのに、これまたわざとらしく大きなため息をついた。
いや…。
いやいやいや…え?
オレ、何やってんの?
一息ついてみれば、まるで拗ねた子どものような自らの行動が今更疑問になってくる。
さっきの状況は、どこにも誰にも悪いところなんかなかったはずだった。
なまえちゃんはあの邪魔くさい前髪を切って、めでたくイメチェンに成功した…っていう、ただそれだけ。
みんなにも褒められてたみたいだし、なまえちゃんも嬉しそうだったし。
ほらね?どこにも悪い要素なんかないじゃん。
ふと時計を見上げると、知らぬ間に時刻は自由時間に突入していた。
なまえちゃん、あの調子だとほかの皆とも仲良くなったのかな。
今頃…そうだな、赤松ちゃん辺りと一緒に遊んでたりして。
それで気がついたら、オレの他にも『なまえちゃん』って呼ぶ相手が出来たりしてさ。
別に、そうだったからって何があるわけでもないんだけど。
「あー…意味分かんな」
そもそも彼女を誘ったのだって、呼び方を変えてみたのだって、ただの暇つぶしで気まぐれに行動しただけのこと。
それがこんなにモヤモヤする結果になるのなら、あんなことを言わなければ良かったのか。
なまえちゃんが、前髪を切るきっかけになるような、あんなことを。
ピンポーン
「…はいはーい」
ゴン太か、入間ちゃんか……それとも最原ちゃんの可能性もあるか?
よっぽどつまらなくない提案でもされない限り、今日は絶対付き合ってやらないからな。
重い足取りで玄関へと向かい、扉を開いた。
「お、王馬くんっ…。あの、これ…その…」
「…は?」
そこに居たのは、予想した内の誰でもなかった。
しどろもどろになりながらデートチケットを差し出すなまえちゃん。
いつも表情を隠していた前髪が無くなったせいで、これでもかというほど赤く染まった頬が丸見えだった。
「い、いつも誘ってもらってばかりっ…なので!お返し…と言いますか…。お誘いに、来ました…」
「ふーん…そう。一応、ありがと?」
必死な様子に思わずチケットを受け取ると、なまえちゃんは少しほっとしたように肩の力を抜いた。
それから何やらもじもじとした様子で、空になった両手を胸の前で遊ばせ始める。
「…どうしたの?」
「い、いえっ…その…。この後、どうしたらいいんでしょうか…。そのチケットも、どう使用していいのか分からなくて」
なまえちゃんはどうやら、本当にただ勢い任せに行動を取ったらしい。
どこへ遊びに行くかも決めず、デートチケットの使い方を調べることもせず、突発的にここに来た…と、彼女の様子からそれだけは伝わった。
なんなんだろうなぁ。ホント、変な子…っていうか。
「ぷっ…あははは!」
「う…不慣れなもので…すみません…」
「はぁ、なまえちゃんってホント…。しょうがないなー。じゃあ、今日はオレの行きたいとこ連れ回してあげる」
「へっ?あの…それはつまり、全くもっていつも通りということでは…」
「いいじゃん別に。それに、全部が全部いつも通りじゃないでしょ?」
「え、えっと…?」
きょとんとした顔をするなまえちゃんの眉間を、人差し指で思い切り押してやった。
「何するんですか!」と押された箇所を押さえながら抗議してくる彼女の瞳は、初めて目が合った時とは違い、揺れ動くことなく真っ直ぐにオレを見つめている。
「やっぱり、思ってた通り…可愛いじゃん」
「は、はいっ………えっ!?」
青くなったり赤くなったり、なまえちゃんは案外ころころと表情が変わるタイプだったらしい。
そんなこと、今の今まで知らなかった。
あんなにモヤモヤしていた気分は知らぬ間に晴れていて、結局のところ原因はよく分からないままだ。
それでも今は、なまえちゃんの変化をじっくり観察するのに忙しいから…とでも理由をつけることにして、原因探しはまだ後でいいかな、と、そんなことを考えながら彼女の手を引いて歩き出した。
※ 前髪を切った日の続き
全部全部、始まりはただの気まぐれだった。
いつもおどおどして、『コミュ障です』と張り紙でもされてるんじゃないかと思う女の子を執拗に構い始めたことも。
どんな反応をするのか見てみたいという理由で、彼女のことを半ば強引に『なまえちゃん』と呼び始めたことも。
「切った方が可愛いと思うんだけどなぁ。なまえちゃん」
少し前に改めてなまえちゃんの顔を見た時、笑っちゃうくらいに彼女の瞳が見えなくて。
こっちからは見えてないのに、あの子からはちゃんと見えてるの?と、純粋に疑問に思った。
そういえばオレは、この子の瞳の色も知らない。
一度考え始めると気になってしまう性分故か。
勝手に近づいて、勝手に前髪を避けて、そうやって初めて彼女と目が合ったことに、浮かれていたのかもしれない。
独り言のつもりだった言葉は、無意識に口をついて外に出て行った。
「え…」
小さな小さな、彼女が驚いた時に出す声。
部屋に流れる映画の音量より遥かに小さいはずのそれが、妙に鮮明に聞こえた。
そうして初めて、自分の失態に気がつく。
「嘘だけどね!」といつものように続ければ良かったものを、何故かそんな簡単なこともこの時のオレは思いつかなかった。
ただただ、そっぽを向いて動揺した顔を見られないようにすることしか出来なかった。
「…似合う、でしょうか」
「え?」
「前髪…です。切っても、似合うでしょうか?」
そんなこと言われても、分かるわけないじゃん。
さっき初めてキミの目を見たばかりのオレに。
…だけど、どうせもう冗談だと流すことも出来ないのなら。
「知らなーい。…けど、似合うんじゃない?」
なまえちゃんがいつも、どんな目で何を見ているのか、少しは興味が湧いたから。
それだけの理由だと、心の中で言い訳をしながら無愛想にそう答えた。
*****
「お、おはようございますっ…」
翌日、いつものように食堂で朝食を食べていた時だった。
背後にある扉から、笑っちゃうくらい緊張が丸見えのなまえちゃんの声が聞こえる。
余程力んでいたのか、若干上擦った声で放たれたその挨拶。
おはようって言うだけでも、コミュ障のなまえちゃんにはいっぱいいっぱいだよね。
可哀想だから早めに返事をして、ついでに笑ってあげる…なんて、そんな気持ちで振り返りながら声をかけることにした。
「なまえちゃん、おは………」
「お、王馬くん…?」
近寄ってきた彼女の姿を目にした途端、続く言葉を失う。
昨日まであったはずの、オレと彼女を隔てていたものが綺麗さっぱりなくなっていたから。
ホントに切ってきたの?
…オレが似合うって言ったから?
なんか、それって…。
得体の知れないむず痒い感情。
けれども、明らかにオレの感想待ち状態のなまえちゃんから浴びせられる、そわそわした視線は悪くないと思えた。
「切ったんだ、前髪」
「は、はい…。あのっ」
「へぇ、やっぱり⎯⎯⎯⎯」
オレの言った通りじゃん。
と、そう伝えるつもりだった。
「みょうじさん、おはよう!…あっ、髪切ったんだ!可愛いね」
オレが伝える予定だった言葉よりも先に、赤松ちゃんの素直な褒め言葉が食堂内に響く。
そうしてあれよあれよという間に、なまえちゃんは赤松ちゃんを始め色んな人に囲まれて…。
「似合う」
「可愛い」
そんな褒め言葉に包まれて、彼女は俯き気味にはにかんだ。
そんな表情もできること、知らなかったなぁ。
…当たり前か。オレ、キミの瞳の色すら昨日知ったばかりなんだもんね。
和気あいあいとした暖かな空間は妙に居心地が悪く感じられて、オレはそっとその場を抜け出した。
*****
ぼふん。
わざと大きめの音を立てるようにベッドに沈み込む。
「はぁ…」
聞かせる相手もいないのに、これまたわざとらしく大きなため息をついた。
いや…。
いやいやいや…え?
オレ、何やってんの?
一息ついてみれば、まるで拗ねた子どものような自らの行動が今更疑問になってくる。
さっきの状況は、どこにも誰にも悪いところなんかなかったはずだった。
なまえちゃんはあの邪魔くさい前髪を切って、めでたくイメチェンに成功した…っていう、ただそれだけ。
みんなにも褒められてたみたいだし、なまえちゃんも嬉しそうだったし。
ほらね?どこにも悪い要素なんかないじゃん。
ふと時計を見上げると、知らぬ間に時刻は自由時間に突入していた。
なまえちゃん、あの調子だとほかの皆とも仲良くなったのかな。
今頃…そうだな、赤松ちゃん辺りと一緒に遊んでたりして。
それで気がついたら、オレの他にも『なまえちゃん』って呼ぶ相手が出来たりしてさ。
別に、そうだったからって何があるわけでもないんだけど。
「あー…意味分かんな」
そもそも彼女を誘ったのだって、呼び方を変えてみたのだって、ただの暇つぶしで気まぐれに行動しただけのこと。
それがこんなにモヤモヤする結果になるのなら、あんなことを言わなければ良かったのか。
なまえちゃんが、前髪を切るきっかけになるような、あんなことを。
ピンポーン
「…はいはーい」
ゴン太か、入間ちゃんか……それとも最原ちゃんの可能性もあるか?
よっぽどつまらなくない提案でもされない限り、今日は絶対付き合ってやらないからな。
重い足取りで玄関へと向かい、扉を開いた。
「お、王馬くんっ…。あの、これ…その…」
「…は?」
そこに居たのは、予想した内の誰でもなかった。
しどろもどろになりながらデートチケットを差し出すなまえちゃん。
いつも表情を隠していた前髪が無くなったせいで、これでもかというほど赤く染まった頬が丸見えだった。
「い、いつも誘ってもらってばかりっ…なので!お返し…と言いますか…。お誘いに、来ました…」
「ふーん…そう。一応、ありがと?」
必死な様子に思わずチケットを受け取ると、なまえちゃんは少しほっとしたように肩の力を抜いた。
それから何やらもじもじとした様子で、空になった両手を胸の前で遊ばせ始める。
「…どうしたの?」
「い、いえっ…その…。この後、どうしたらいいんでしょうか…。そのチケットも、どう使用していいのか分からなくて」
なまえちゃんはどうやら、本当にただ勢い任せに行動を取ったらしい。
どこへ遊びに行くかも決めず、デートチケットの使い方を調べることもせず、突発的にここに来た…と、彼女の様子からそれだけは伝わった。
なんなんだろうなぁ。ホント、変な子…っていうか。
「ぷっ…あははは!」
「う…不慣れなもので…すみません…」
「はぁ、なまえちゃんってホント…。しょうがないなー。じゃあ、今日はオレの行きたいとこ連れ回してあげる」
「へっ?あの…それはつまり、全くもっていつも通りということでは…」
「いいじゃん別に。それに、全部が全部いつも通りじゃないでしょ?」
「え、えっと…?」
きょとんとした顔をするなまえちゃんの眉間を、人差し指で思い切り押してやった。
「何するんですか!」と押された箇所を押さえながら抗議してくる彼女の瞳は、初めて目が合った時とは違い、揺れ動くことなく真っ直ぐにオレを見つめている。
「やっぱり、思ってた通り…可愛いじゃん」
「は、はいっ………えっ!?」
青くなったり赤くなったり、なまえちゃんは案外ころころと表情が変わるタイプだったらしい。
そんなこと、今の今まで知らなかった。
あんなにモヤモヤしていた気分は知らぬ間に晴れていて、結局のところ原因はよく分からないままだ。
それでも今は、なまえちゃんの変化をじっくり観察するのに忙しいから…とでも理由をつけることにして、原因探しはまだ後でいいかな、と、そんなことを考えながら彼女の手を引いて歩き出した。
1/1ページ