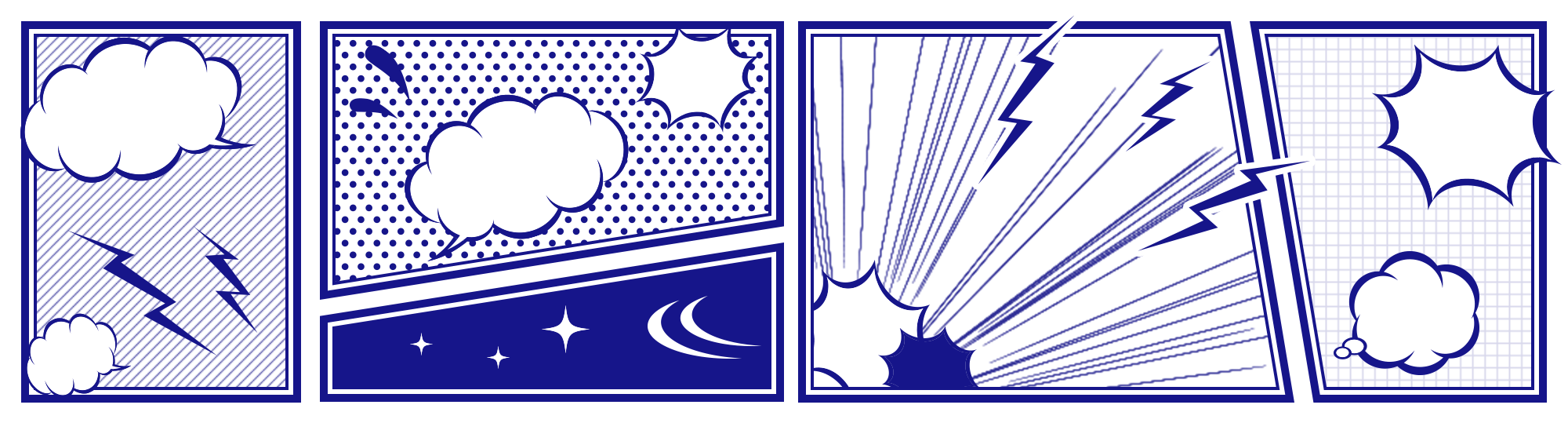ホワイトデーの仕返し
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
※ 本命チョコの続き
あの日、私は好きな人にチョコを渡した。
…渡したと言うよりは、奪われた?とか…渡さざるを得なかった?とか、そんな風にも言うかもしれない。
なんとも情けないが、つまりは思っていた渡し方とは状況が大きく違っていたのだ。
けれども、『好きな子以外の本命チョコは受け取らない主義』の王馬くんが、私の本命チョコを口に入れるのをこの目で確かに見た。
だから多分、渡せたことになっているし、彼もまた受け取ったことになっている…はずだ。
「…………えっ、それだけ?」
「そう…だね」
今年こそは!と友人である楓ちゃんに意気込みを伝えて望んだバレンタイン。
そのイベントが終われば、張り切って準備していたことを知る人から「どうだった?」と結果を尋ねられるのは当然の流れだろう。
ちょーっと思ってた感じとは違ったかな…?
なんて、日和った前置きと共に当日の出来事を話した結果が先の反応だ。
「好きって言ったり言われたりは!?」
「……あ、そういえば言ってないや」
「もー、なにそれ!一応チョコは渡せた…んでしょ?なのに…う~~~、もったいない!」
なまえちゃん、こういうイベントに乗っからないと絶対告白なんて出来ないのに!
痛いほど的を得た彼女の発言に返す言葉もない。
予定では告白をして、付き合うか振られるかのどちらかになっているはずだった。
それが、「一応両思い…なのかな?」等という宙ぶらりんな関係になってしまったのだから目も当てられない。
だってだって、あの日はあれで精一杯だったんだもの。
心の中で駄々をこねても、私と彼の関係が変わるはずもない。
そう分かっていても、脳内には次から次へと言い訳じみた言葉ばかりが浮かんでくる。
楓ちゃんに向かってうだうだと後悔や自分への慰めの言葉を呪詛のように呟いていると、ガラガラと音を立てて教室の扉が開かれた。
「あっ、王馬くんおはよう!」
「ゴン太おはよー」
ゴン太くんの言葉に反射的に顔を上げると、大きなあくびをしながら中へと入ってくる王馬くんとバッチリと目が合った。
横からは楓ちゃんからの「行け!」という視線を痛いほど感じるが、当の私は口をパクパクしながら挙動不審に目を泳がせることしかできない。
「あっ、あのっ…え、えっと…」
「おはよ、みょうじちゃん。赤松ちゃんも」
「お、おはよう!」
「おっ…おはよう、ございます…」
楓ちゃんの挨拶からワンテンポ遅れてしどろもどろな挨拶を返せば、王馬くんはいつもの様に意地悪な笑顔を浮かべて口を開く。
「にしし、変なみょうじちゃん!朝ごはん、変なものでも食べた?もー、ダメだよー拾い食いは。失うのは人としての尊厳だけじゃないんだからさ!」
「なっ…そんなことしないわ!」
「ホント?日頃のしつけの賜物だねー」
ひらひらと手を振って自分の席へと向かう王馬くんの後ろ姿を、シャーッと威嚇しながら睨みつける。
そういう光景ももはやお約束と化しているためか、教室にいた他のクラスメイト達は「またやってるよー」なんて視線を向けてくるだけだ。
けれども、そんないつも通りの裏で、いつも通りではない出来事があったことを知っている楓ちゃんだけは、ちょいちょいと私の肩をつついてから耳元に顔を寄せる。
「なんか、普段通り…って感じだったね?」
「た、確かに…」
「まぁでも、さすがに教室だしね。昼休みとか放課後とか、何かあるかもしれないよ」
「そう…かなぁ。え、えへへ…」
お昼を一緒に食べている時に、オレたち付き合う?とサラッと言われたりだとか。
放課後呼び出されて、この前はちゃんと言えなかったけど…と愛の告白をされたりだとか。
ふわふわと浮かんできた妄想につい口元が緩む。
それから落ち着かない気持ちで昼休みが過ぎ、放課後になり、ほとんどの生徒が帰宅した時間になったって私には何のイベントも起こらなかった。
もしかしたら明日?それとも明後日?
そうして日々を過ごしていたけれど、一向に期待していたイベントは発生しない。
気がつけばあの出来事から1ヶ月が経つが、以前として私と彼の関係は何も変わっていないままだ。
「つまり、フラグが立ってないってこと!?」
「フラグって…そんな、ゲームじゃないんだから」
昼休み、やはり今日も何も無い予感がして仕方がない私は、楓ちゃんに思いの丈をぶちまけていた。
楓ちゃんもこの1ヶ月で私が情緒不安定な時のあしらい方に慣れてきたらしい。
なんて事ない顔で突っ込みを入れつつ、パックジュースを啜っている。
「でもでも、あれから本当に何事もないよ!?なさすぎるよ!?」
「んー…まぁ、そうだよね。…でもねなまえちゃん、今日が何の日か知ってる?」
「え…あの日から1ヶ月何も無かった記念日、ですか?」
「卑屈になり過ぎてるよ!…もう、そうじゃなくて!ホワイトデーだよ、ホワイトデー!」
「ホワイトデー」
得意げな表情でそう言う楓ちゃんの後から、復唱するように呟いた。
ホワイトデー。
バレンタインデーのお返しをする日。
お返し。…と、いうことは。
「わ、私…お返し、貰える?」
「一応渡せた…というか、王馬くんの手には渡ったんでしょ?なら、さすがに用意してくれてるはずだよ!」
浮ついた気持ちで食堂から教室への道を歩いていると、確かに至る所で男の子から女の子へ何かを贈っている様子を確認することができる。
私もあの中の1組に…?
教室へ帰れば、楓ちゃんも男の子からお返しとしてラッピングされたお菓子の包みをいくつか貰っていた。
「義理チョコでもこうやってお返しくれるんだから、なまえちゃんもきっと貰えるよ」
「そ、そっか…!」
目の前がぱぁっと明るくなって、ソワソワしながら自席へ戻る。
午後からも休み時間の度、教室や廊下で『お返し』のやり取りをしている場面を何度か目撃した。
私の番はいつかな?
上機嫌に午後の授業を乗り切り、気がつけばすっかり放課後になっていた。
「あ、あれ…?」
「放課後にってパターンもある…よね、きっと」
「でも王馬くんもう帰ったよね…?」
「………帰って…るね」
ガーン、と鈍い音が頭に響く。
ショックのままよろよろと教室を出ようとした私を、楓ちゃんがぐいっと腕を掴んで引き止めた。
「なまえちゃん!こうなったら、当たって砕けるしかないよ!」
「えっ…」
別に砕けたくはないんだけどな。
口元まで出かかったが、楓ちゃんがあまりにも力強い瞳でこちらを見ていたものだから何も言えなかった。
「時間的に、まだ学校のどこかにいるかも!直接会ってあの時の話、してみよう?」
そうしないと、ずっと宙ぶらりんのままだよ!
楓ちゃんの言葉に、ゴクリと息を飲んだ。
そういう話を持ち出すのが恥ずかしくて、勘違いだったらと思うと怖くて、そうやってずっと引き伸ばしていたけれど。
やっぱり宙ぶらりんは嫌、だよね。
「……私、探してくる!……もし振られたら、明日慰めてくれる?」
「もちろん!…って、私は振られるなんて思ってないけど!」
行ってらっしゃい!
友人の明るい声に背中を押されて、荷物を掴んで教室を飛び出した。
屋上とか食堂とか、比較的いそうな場所を回ってみたが王馬くんらしき人影は見当たらない。
遅かったのかな…。と、少しだけ後ろ向きな気持ちが芽生えた頃に、不安げな表情の私を心配してくれたゴン太くんから声をかけられた。
「みょうじさん、大丈夫?どこか痛い?」
「だっ…大丈夫!怪我したわけじゃないんだ」
「そう、それなら良かったよ。…でも、どうしたの?息も切れてるみたいだけど…」
「えっと…その、王馬くん…探してて」
「えっ?王馬くん?」
王馬くんなら、忘れ物したって教室に取りに行ったよ。
い、いつ?
ついさっきだよ。
そんな言葉を交わし、ゴン太くんへのお礼の言葉を述べながら足は早くも教室へと向かっている。
まだ間に合うかな、入れ違いにならないかな。
焦って踏み出した足がもつれそうになるのも構わずに走って、教室の扉を勢いよく開いた。
「あ、みょうじちゃん。やっと来たねー」
私が中の様子を確認するよりも先に、至って普段通りな王馬くんの声が聞こえてくる。
驚いて声のする方を見れば、教室の自分の席に座って頬杖をつく彼の姿があった。
その様子はとても『忘れ物を取りに来た』ようには見えない。
「前、座りなよ」
「う、うん…?」
言われるがまま王馬くんの席の前の椅子に腰掛ける。
よしよし、とまるで犬でも褒めるような物言いの彼は、先程から何やらゴソゴソと鞄の中を漁っていた。
「あんまり遅いと帰っちゃうところだったよー」
「え?いや…でも、何も約束とかしてない、よね?」
「にしし、まぁね」
いや…まぁね、じゃなくて。
色々と確認したいことはあるが、状況が飲み込めていない私の頭にはいくつもの『?』ばかりが浮かんでいる。
こちらの本題に入る前に、一体何から聞いていけばいいんだろう。
まとまらない思考をなんとか形にしようと唸っていると。
「はい」
「……はい?」
目の前に、プレゼントの箱のようなものを差し出された。
私自身を指さして、ジェスチャーで『私に?』と確認すると、王馬くんもまたジェスチャーでどうぞどうぞと言わんばかりに手のひらを向けてくる。
「も、もしかしてホワイトデーの…?」
「にしし、そうだよ!」
「それなら昼休みとかに渡してくれたら良かったのに…!」
「えー?だって、みょうじちゃんだってバレンタイン普通にはくれなかったじゃん?」
オレだけ普通に渡したら不公平でしょ?
そんな謎の理論で、王馬くんは昼休みも休み時間も、放課後に教室にいた時でさえスルーを決め込んでいたらしい。
「なにそれぇ」
なんだか力が抜けてきて、へなへなと椅子の背もたれに倒れ込んだ。
彼のおかげで、私は午後からずっとソワソワし続けたというのに。
「あは、仕返し大成功~」
「仕返し?…お返しじゃなくて?」
「うん、仕返し。みょうじちゃんがバレンタインの時、素直にチョコくれてたらお返しだっただろうけど!」
「だからって………ねぇ、もし私が先に帰っちゃったらどうするつもりだったの?」
「んー?それはないよ。だって、協力者がいたからねー」
協力者…?そんな人、どこに。
ポカンとしている私を見て、王馬くんは楽しげに笑う。
「にしし…みょうじちゃんは、誰に何を言われてこんなところに来たんだっけ?」
「ご、ゴン太くん…?」
「半分正解~。あとは…そうだね、さっさと帰らずにオレを探そうと思ったきっかけって何だった?」
「えっ…………まさか、楓ちゃん!?」
「あはは、全問正解!おめでとう~」
ぱちぱちぱち、と王馬くんが拍手をする音が誰もいない教室に響く。
た、確かに思い返せば楓ちゃんもやや強引な持っていき方だったし、ゴン太くんもやけにタイミングが良かったけど…!
全然気が付かなかった…。
してやられたなぁ、と王馬くんをちらりと見れば、視線に気づいた彼からにっこりと笑顔を返され、恥ずかしさから思わず目を逸らした。
「…でさ。よく考えたらオレ、バレンタインに貰い忘れたものがある気がするんだよね」
「えっ…」
「今それくれたら、オレからもうひとつお返しあげるよ」
何だか分かる?
窓から差し込む夕日に照らされた王馬くんが、少しだけ首をかしげて私に笑いかける。
バレンタインに私があげていないもの。
そんなの、散々後悔したんだから…分からないはずがなかった。
「わ、私…王馬くんのことがっ…好き、です」
「にしし、ありがとー。オレもみょうじちゃんが好きだよ」
にやけ顔を見られるのが照れくさくて、咄嗟にそっぽを向いた。
その結果、「耳まで真っ赤だー」と彼に大笑いされるとは思わなかったから。
思っていたのと違ったバレンタインから1ヶ月。
お返しだけじゃなくて、仕返しまで貰ったのなんて、きっとどこを探しても私だけなんじゃないだろうか。
と、そんなことを考えて、ふふ、と口から笑みが零れた。
*****
「おはよう、なまえちゃん!」
「楓ちゃん…!お、おは…」
翌日、楓ちゃんは登校するなり私を見つけて駆け寄って来た。
彼女には、聞きたいことも言いたいこともたくさんある。
いつもよりソワソワした気持ちで挨拶を返そうとした時だった。
「おっはよー、みょうじちゃん!……と、赤松ちゃんもおはよ」
露骨に『ついで』といった様子の挨拶をされた楓ちゃんは、一瞬面食らったような顔をした後私に視線を移し、意味深に笑う。
「お、おはよう」
「ふふ、王馬くんおはよ!」
自席に向かう彼の様子を、楓ちゃんと二人見守った後。
「良かったね、なまえちゃん」
こそっと耳打ちされた言葉に思わず頬を染めた。
やっぱり、分かっちゃう…よね?
嬉しいような、むず痒いような。
そんな気持ちで、にへ、と少し気持ち悪い笑みを浮かべていると。
「………まぁ、今ので…私以外の人にも、その」
「えっ?」
途切れ途切れの楓ちゃんの言葉に疑問を感じて周囲を見渡せば、興味津々といった様子のクラスメイト達がこちらを見つめていた。
恋バナに飢えた彼女らに取り囲まれる寸前、「王馬くんのせいで!」という気持ちを込めて彼に視線を送る。
その視線を受け取った彼は、一瞬だけ私を見てチラリと舌を見せて笑っていた。
あの日、私は好きな人にチョコを渡した。
…渡したと言うよりは、奪われた?とか…渡さざるを得なかった?とか、そんな風にも言うかもしれない。
なんとも情けないが、つまりは思っていた渡し方とは状況が大きく違っていたのだ。
けれども、『好きな子以外の本命チョコは受け取らない主義』の王馬くんが、私の本命チョコを口に入れるのをこの目で確かに見た。
だから多分、渡せたことになっているし、彼もまた受け取ったことになっている…はずだ。
「…………えっ、それだけ?」
「そう…だね」
今年こそは!と友人である楓ちゃんに意気込みを伝えて望んだバレンタイン。
そのイベントが終われば、張り切って準備していたことを知る人から「どうだった?」と結果を尋ねられるのは当然の流れだろう。
ちょーっと思ってた感じとは違ったかな…?
なんて、日和った前置きと共に当日の出来事を話した結果が先の反応だ。
「好きって言ったり言われたりは!?」
「……あ、そういえば言ってないや」
「もー、なにそれ!一応チョコは渡せた…んでしょ?なのに…う~~~、もったいない!」
なまえちゃん、こういうイベントに乗っからないと絶対告白なんて出来ないのに!
痛いほど的を得た彼女の発言に返す言葉もない。
予定では告白をして、付き合うか振られるかのどちらかになっているはずだった。
それが、「一応両思い…なのかな?」等という宙ぶらりんな関係になってしまったのだから目も当てられない。
だってだって、あの日はあれで精一杯だったんだもの。
心の中で駄々をこねても、私と彼の関係が変わるはずもない。
そう分かっていても、脳内には次から次へと言い訳じみた言葉ばかりが浮かんでくる。
楓ちゃんに向かってうだうだと後悔や自分への慰めの言葉を呪詛のように呟いていると、ガラガラと音を立てて教室の扉が開かれた。
「あっ、王馬くんおはよう!」
「ゴン太おはよー」
ゴン太くんの言葉に反射的に顔を上げると、大きなあくびをしながら中へと入ってくる王馬くんとバッチリと目が合った。
横からは楓ちゃんからの「行け!」という視線を痛いほど感じるが、当の私は口をパクパクしながら挙動不審に目を泳がせることしかできない。
「あっ、あのっ…え、えっと…」
「おはよ、みょうじちゃん。赤松ちゃんも」
「お、おはよう!」
「おっ…おはよう、ございます…」
楓ちゃんの挨拶からワンテンポ遅れてしどろもどろな挨拶を返せば、王馬くんはいつもの様に意地悪な笑顔を浮かべて口を開く。
「にしし、変なみょうじちゃん!朝ごはん、変なものでも食べた?もー、ダメだよー拾い食いは。失うのは人としての尊厳だけじゃないんだからさ!」
「なっ…そんなことしないわ!」
「ホント?日頃のしつけの賜物だねー」
ひらひらと手を振って自分の席へと向かう王馬くんの後ろ姿を、シャーッと威嚇しながら睨みつける。
そういう光景ももはやお約束と化しているためか、教室にいた他のクラスメイト達は「またやってるよー」なんて視線を向けてくるだけだ。
けれども、そんないつも通りの裏で、いつも通りではない出来事があったことを知っている楓ちゃんだけは、ちょいちょいと私の肩をつついてから耳元に顔を寄せる。
「なんか、普段通り…って感じだったね?」
「た、確かに…」
「まぁでも、さすがに教室だしね。昼休みとか放課後とか、何かあるかもしれないよ」
「そう…かなぁ。え、えへへ…」
お昼を一緒に食べている時に、オレたち付き合う?とサラッと言われたりだとか。
放課後呼び出されて、この前はちゃんと言えなかったけど…と愛の告白をされたりだとか。
ふわふわと浮かんできた妄想につい口元が緩む。
それから落ち着かない気持ちで昼休みが過ぎ、放課後になり、ほとんどの生徒が帰宅した時間になったって私には何のイベントも起こらなかった。
もしかしたら明日?それとも明後日?
そうして日々を過ごしていたけれど、一向に期待していたイベントは発生しない。
気がつけばあの出来事から1ヶ月が経つが、以前として私と彼の関係は何も変わっていないままだ。
「つまり、フラグが立ってないってこと!?」
「フラグって…そんな、ゲームじゃないんだから」
昼休み、やはり今日も何も無い予感がして仕方がない私は、楓ちゃんに思いの丈をぶちまけていた。
楓ちゃんもこの1ヶ月で私が情緒不安定な時のあしらい方に慣れてきたらしい。
なんて事ない顔で突っ込みを入れつつ、パックジュースを啜っている。
「でもでも、あれから本当に何事もないよ!?なさすぎるよ!?」
「んー…まぁ、そうだよね。…でもねなまえちゃん、今日が何の日か知ってる?」
「え…あの日から1ヶ月何も無かった記念日、ですか?」
「卑屈になり過ぎてるよ!…もう、そうじゃなくて!ホワイトデーだよ、ホワイトデー!」
「ホワイトデー」
得意げな表情でそう言う楓ちゃんの後から、復唱するように呟いた。
ホワイトデー。
バレンタインデーのお返しをする日。
お返し。…と、いうことは。
「わ、私…お返し、貰える?」
「一応渡せた…というか、王馬くんの手には渡ったんでしょ?なら、さすがに用意してくれてるはずだよ!」
浮ついた気持ちで食堂から教室への道を歩いていると、確かに至る所で男の子から女の子へ何かを贈っている様子を確認することができる。
私もあの中の1組に…?
教室へ帰れば、楓ちゃんも男の子からお返しとしてラッピングされたお菓子の包みをいくつか貰っていた。
「義理チョコでもこうやってお返しくれるんだから、なまえちゃんもきっと貰えるよ」
「そ、そっか…!」
目の前がぱぁっと明るくなって、ソワソワしながら自席へ戻る。
午後からも休み時間の度、教室や廊下で『お返し』のやり取りをしている場面を何度か目撃した。
私の番はいつかな?
上機嫌に午後の授業を乗り切り、気がつけばすっかり放課後になっていた。
「あ、あれ…?」
「放課後にってパターンもある…よね、きっと」
「でも王馬くんもう帰ったよね…?」
「………帰って…るね」
ガーン、と鈍い音が頭に響く。
ショックのままよろよろと教室を出ようとした私を、楓ちゃんがぐいっと腕を掴んで引き止めた。
「なまえちゃん!こうなったら、当たって砕けるしかないよ!」
「えっ…」
別に砕けたくはないんだけどな。
口元まで出かかったが、楓ちゃんがあまりにも力強い瞳でこちらを見ていたものだから何も言えなかった。
「時間的に、まだ学校のどこかにいるかも!直接会ってあの時の話、してみよう?」
そうしないと、ずっと宙ぶらりんのままだよ!
楓ちゃんの言葉に、ゴクリと息を飲んだ。
そういう話を持ち出すのが恥ずかしくて、勘違いだったらと思うと怖くて、そうやってずっと引き伸ばしていたけれど。
やっぱり宙ぶらりんは嫌、だよね。
「……私、探してくる!……もし振られたら、明日慰めてくれる?」
「もちろん!…って、私は振られるなんて思ってないけど!」
行ってらっしゃい!
友人の明るい声に背中を押されて、荷物を掴んで教室を飛び出した。
屋上とか食堂とか、比較的いそうな場所を回ってみたが王馬くんらしき人影は見当たらない。
遅かったのかな…。と、少しだけ後ろ向きな気持ちが芽生えた頃に、不安げな表情の私を心配してくれたゴン太くんから声をかけられた。
「みょうじさん、大丈夫?どこか痛い?」
「だっ…大丈夫!怪我したわけじゃないんだ」
「そう、それなら良かったよ。…でも、どうしたの?息も切れてるみたいだけど…」
「えっと…その、王馬くん…探してて」
「えっ?王馬くん?」
王馬くんなら、忘れ物したって教室に取りに行ったよ。
い、いつ?
ついさっきだよ。
そんな言葉を交わし、ゴン太くんへのお礼の言葉を述べながら足は早くも教室へと向かっている。
まだ間に合うかな、入れ違いにならないかな。
焦って踏み出した足がもつれそうになるのも構わずに走って、教室の扉を勢いよく開いた。
「あ、みょうじちゃん。やっと来たねー」
私が中の様子を確認するよりも先に、至って普段通りな王馬くんの声が聞こえてくる。
驚いて声のする方を見れば、教室の自分の席に座って頬杖をつく彼の姿があった。
その様子はとても『忘れ物を取りに来た』ようには見えない。
「前、座りなよ」
「う、うん…?」
言われるがまま王馬くんの席の前の椅子に腰掛ける。
よしよし、とまるで犬でも褒めるような物言いの彼は、先程から何やらゴソゴソと鞄の中を漁っていた。
「あんまり遅いと帰っちゃうところだったよー」
「え?いや…でも、何も約束とかしてない、よね?」
「にしし、まぁね」
いや…まぁね、じゃなくて。
色々と確認したいことはあるが、状況が飲み込めていない私の頭にはいくつもの『?』ばかりが浮かんでいる。
こちらの本題に入る前に、一体何から聞いていけばいいんだろう。
まとまらない思考をなんとか形にしようと唸っていると。
「はい」
「……はい?」
目の前に、プレゼントの箱のようなものを差し出された。
私自身を指さして、ジェスチャーで『私に?』と確認すると、王馬くんもまたジェスチャーでどうぞどうぞと言わんばかりに手のひらを向けてくる。
「も、もしかしてホワイトデーの…?」
「にしし、そうだよ!」
「それなら昼休みとかに渡してくれたら良かったのに…!」
「えー?だって、みょうじちゃんだってバレンタイン普通にはくれなかったじゃん?」
オレだけ普通に渡したら不公平でしょ?
そんな謎の理論で、王馬くんは昼休みも休み時間も、放課後に教室にいた時でさえスルーを決め込んでいたらしい。
「なにそれぇ」
なんだか力が抜けてきて、へなへなと椅子の背もたれに倒れ込んだ。
彼のおかげで、私は午後からずっとソワソワし続けたというのに。
「あは、仕返し大成功~」
「仕返し?…お返しじゃなくて?」
「うん、仕返し。みょうじちゃんがバレンタインの時、素直にチョコくれてたらお返しだっただろうけど!」
「だからって………ねぇ、もし私が先に帰っちゃったらどうするつもりだったの?」
「んー?それはないよ。だって、協力者がいたからねー」
協力者…?そんな人、どこに。
ポカンとしている私を見て、王馬くんは楽しげに笑う。
「にしし…みょうじちゃんは、誰に何を言われてこんなところに来たんだっけ?」
「ご、ゴン太くん…?」
「半分正解~。あとは…そうだね、さっさと帰らずにオレを探そうと思ったきっかけって何だった?」
「えっ…………まさか、楓ちゃん!?」
「あはは、全問正解!おめでとう~」
ぱちぱちぱち、と王馬くんが拍手をする音が誰もいない教室に響く。
た、確かに思い返せば楓ちゃんもやや強引な持っていき方だったし、ゴン太くんもやけにタイミングが良かったけど…!
全然気が付かなかった…。
してやられたなぁ、と王馬くんをちらりと見れば、視線に気づいた彼からにっこりと笑顔を返され、恥ずかしさから思わず目を逸らした。
「…でさ。よく考えたらオレ、バレンタインに貰い忘れたものがある気がするんだよね」
「えっ…」
「今それくれたら、オレからもうひとつお返しあげるよ」
何だか分かる?
窓から差し込む夕日に照らされた王馬くんが、少しだけ首をかしげて私に笑いかける。
バレンタインに私があげていないもの。
そんなの、散々後悔したんだから…分からないはずがなかった。
「わ、私…王馬くんのことがっ…好き、です」
「にしし、ありがとー。オレもみょうじちゃんが好きだよ」
にやけ顔を見られるのが照れくさくて、咄嗟にそっぽを向いた。
その結果、「耳まで真っ赤だー」と彼に大笑いされるとは思わなかったから。
思っていたのと違ったバレンタインから1ヶ月。
お返しだけじゃなくて、仕返しまで貰ったのなんて、きっとどこを探しても私だけなんじゃないだろうか。
と、そんなことを考えて、ふふ、と口から笑みが零れた。
*****
「おはよう、なまえちゃん!」
「楓ちゃん…!お、おは…」
翌日、楓ちゃんは登校するなり私を見つけて駆け寄って来た。
彼女には、聞きたいことも言いたいこともたくさんある。
いつもよりソワソワした気持ちで挨拶を返そうとした時だった。
「おっはよー、みょうじちゃん!……と、赤松ちゃんもおはよ」
露骨に『ついで』といった様子の挨拶をされた楓ちゃんは、一瞬面食らったような顔をした後私に視線を移し、意味深に笑う。
「お、おはよう」
「ふふ、王馬くんおはよ!」
自席に向かう彼の様子を、楓ちゃんと二人見守った後。
「良かったね、なまえちゃん」
こそっと耳打ちされた言葉に思わず頬を染めた。
やっぱり、分かっちゃう…よね?
嬉しいような、むず痒いような。
そんな気持ちで、にへ、と少し気持ち悪い笑みを浮かべていると。
「………まぁ、今ので…私以外の人にも、その」
「えっ?」
途切れ途切れの楓ちゃんの言葉に疑問を感じて周囲を見渡せば、興味津々といった様子のクラスメイト達がこちらを見つめていた。
恋バナに飢えた彼女らに取り囲まれる寸前、「王馬くんのせいで!」という気持ちを込めて彼に視線を送る。
その視線を受け取った彼は、一瞬だけ私を見てチラリと舌を見せて笑っていた。
1/1ページ