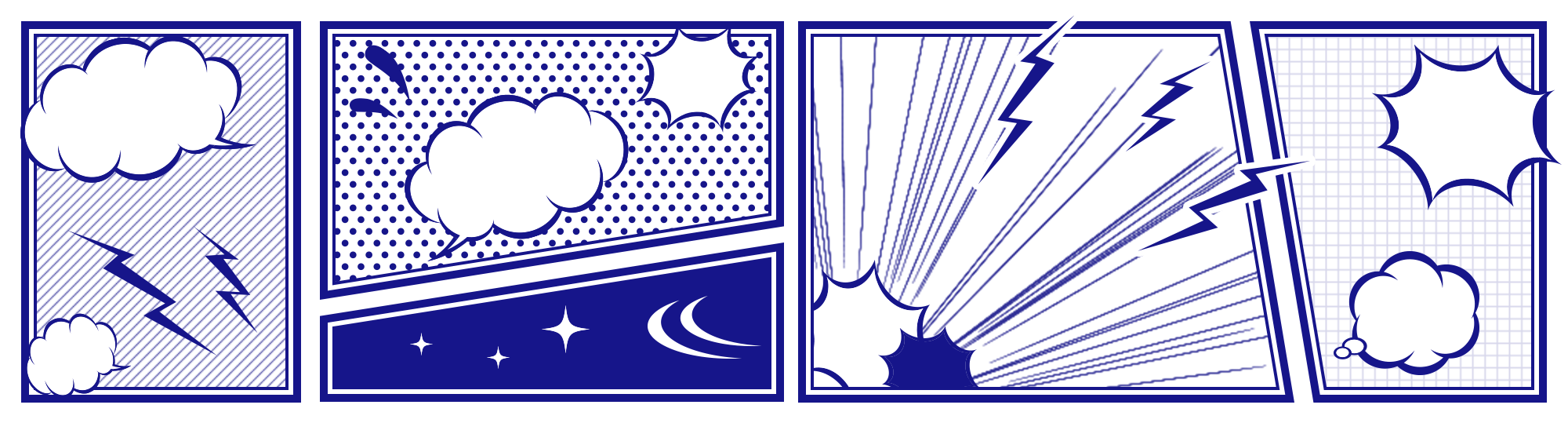架空のライバル
おなまえ
ご利用の端末、あるいはブラウザ設定では夢小説機能をご利用になることができません。
古いスマートフォン端末や、一部ブラウザのプライベートブラウジング機能をご利用の際は、機能に制限が掛かることがございます。
放課後、今日の日直だった私たちが教室で日誌を書いている時だった。
…と言っても、それを書いているのは私だけで、もう1人の日直である王馬くんは、椅子に座って退屈そうに足を揺らしているだけだったけれど。
「あー、彼女ほしー。この際女の子なら誰でもいいかも」
少しずつ埋まっていく日誌のページをつまらなそうに眺めながら、覇気のない声で王馬くんはそう言った。
「とか言って、誰でもよくはないくせに」
「そんなことないよ?可愛いくてつまらなくない子なら誰でも!」
「もう…それ、全然誰でもいいとは言えないよ」
ただ単純に誰かに構われたいだけだったのか、適当な返事をしたのにも関わらず彼は楽しげに笑った。
きっとこれは暇つぶし。彼にとっては本当にそれだけなんだと思う。
けれども密かに思いを寄せる私にとっては、今の数分の出来事だけで日記が1ページ埋まってしまうような、それくらい大きな出来事だった。
「んー、じゃあさっきの無しね。そうだなぁ…つまらなくない彼女が欲しいなー。あとオレのことが大好きで、いつ連絡しても返事が来て、どこにでもすぐ駆けつけてくれるような」
「…それって彼女って言うより、都合のいい女?」
「たはー、そうかも!…あ、そうだ」
みょうじちゃん、なってみる?
そんなからかうような言葉も、脳内のフィルターがほんの少しの甘さを加えて私の心に入ってきた。
これは冗談だと分かりきっているのに、つい本気で答えてしまいそうになる。
結局、一瞬言葉に詰まった私の返事より、「嘘だけどね!」と彼が笑い飛ばす方が先で。
私の中の『もしあの時こうしていたら』リストの項目が新たに更新される結果となった。
「ま、彼女が欲しいのはホントだけどー」
「…どうして急に、彼女が欲しくなったの?」
「百田ちゃんも最原ちゃんも、彼女優先でつまんないから」
「なんだ、そういうこと」
確かに王馬くんは名前の挙がった2人とよく遊んでいて、2人とも最近隣のクラスの女の子とお付き合いを始めたと風の噂で聞いていた。
『誰でもいい』なんて言いながら、その裏には特定の誰かが隠されていて…という展開ではなかったことに安堵する。
そうだよね、この人に限って好きな人なんて…。
「まぁ好きな子ならいるんだけどさ」
「えっ」
「何その顔、オレに恋愛感情なんてないと思ってた?心外だなぁ」
「や、あの、そんなつもりじゃなくて」
「じゃあ何?」
「誰でもいいって、さっき言ってたから…」
「ふーん、そっか」
ショックと動揺で日誌を書く手が止まる。
好きな子って誰なんだろう。
いつどこで知り合った、どんな人なの?
いつから好きなの?どれくらい好きなの?
先程からそんな事しか頭に浮かばない。
「…みょうじちゃん、手止まってるよ?書くの代わってあげよっか」
「い、いいよ。大丈夫」
代わるも何も、そもそもこれは日直2人に与えられた仕事なんだけど。
そう思いつつも、私は冷静にその申し出を断った。
前に一度彼に日誌を頼んだ時、嘘八百を並べられて書き直しを命じられたことがあったからだ。
ペンを持ち直してサラサラと紙の上を滑らせれば、王馬くんはまた黙って、足を揺らしながらつまらなそうにそのペン先を見つめている。
嘘か本当かも分からない一言によって燻る私の胸の内なんて、王馬くんは知りもしないで呑気な顔をしている。
知りもしないで、ではなくて、本当は知る術も無いのだと分かっているのに。
付き合っていないどころか、告白する勇気すらなかったのに、彼が私の胸の内を知るはずがないのだから。
「ね、どんな子だと思う?オレの好きな子」
「…つまらなくない子?」
「にしし、それは前提条件!えっとねー、女の子でー、可愛くてー」
成績は普通で、おとなしくて、悪ふざけにも付き合ってくれて、ちょっと気弱で。
そんな風に続く彼の言葉を、聞きたくないのに防ぐ手段が思い浮かばなかった。
与えられる情報から勝手に作り上げられた空想上の女の子に、惨めな嫉妬なんてしたくない。
心の中では大声でそう叫んでいるのに、現実の私は時折相槌を打ちながら涼しい顔で日誌の空白を埋めるだけだ。
「…そんな子、どこにいるんだろうね?」
「えっ、もしかして適当言ってたの?」
「さぁ、どうかな。みょうじちゃんの都合のいいように解釈してくれていいよ!」
嘘か本当かどちらで解釈したとしても、どの道モヤモヤが残るような言い方だ。
どちらが正解なのか問いただしたって無駄だろうし、きっと私はしばらくの間、事ある毎に今日の出来事を思い出して一人悶々とすることになる。
それに、もし彼に真意を求めてしまったら、それはもう『あなたが好きです』と言ったも同然だ。
『好き』を伝える勇気が無いばかりか、それ以外の言葉ですら言えないなんて。
さっき頭の中で勝手に生まれたばかりの架空の女の子が、私を見下している気がした。
「…あーもう、そんなに思い詰めた顔しないでよ」
突然頭をくしゃくしゃと掻き回されて、意識が現実に戻される。
「べ、別に思い詰めてなんて…!」
乱された髪を整えながら平静を装うと、王馬くんはいつものように悪戯っぽい笑みを浮かべていた。
「はいはい。ねぇ、オレ知らなかったんだけどさ…みょうじちゃんって、思ってたより強情なんだね」
「なっ…王馬くんに言われたくないよ」
「にしし。あと、思ってたより気弱じゃないかも!」
その後は日誌を書き終えるまで私をからかうような言葉が続いて、彼女とか好きな子とか、そんな話が王馬くんから出てくることはなかった。
結局、あの話のどこまでが本当でどこまでが嘘なのか私は知らない。
私が心の中でひっそりと、あの架空の女の子に「負けないぞ」と宣戦布告したことを王馬くんが知らないのと同じように。
…と言っても、それを書いているのは私だけで、もう1人の日直である王馬くんは、椅子に座って退屈そうに足を揺らしているだけだったけれど。
「あー、彼女ほしー。この際女の子なら誰でもいいかも」
少しずつ埋まっていく日誌のページをつまらなそうに眺めながら、覇気のない声で王馬くんはそう言った。
「とか言って、誰でもよくはないくせに」
「そんなことないよ?可愛いくてつまらなくない子なら誰でも!」
「もう…それ、全然誰でもいいとは言えないよ」
ただ単純に誰かに構われたいだけだったのか、適当な返事をしたのにも関わらず彼は楽しげに笑った。
きっとこれは暇つぶし。彼にとっては本当にそれだけなんだと思う。
けれども密かに思いを寄せる私にとっては、今の数分の出来事だけで日記が1ページ埋まってしまうような、それくらい大きな出来事だった。
「んー、じゃあさっきの無しね。そうだなぁ…つまらなくない彼女が欲しいなー。あとオレのことが大好きで、いつ連絡しても返事が来て、どこにでもすぐ駆けつけてくれるような」
「…それって彼女って言うより、都合のいい女?」
「たはー、そうかも!…あ、そうだ」
みょうじちゃん、なってみる?
そんなからかうような言葉も、脳内のフィルターがほんの少しの甘さを加えて私の心に入ってきた。
これは冗談だと分かりきっているのに、つい本気で答えてしまいそうになる。
結局、一瞬言葉に詰まった私の返事より、「嘘だけどね!」と彼が笑い飛ばす方が先で。
私の中の『もしあの時こうしていたら』リストの項目が新たに更新される結果となった。
「ま、彼女が欲しいのはホントだけどー」
「…どうして急に、彼女が欲しくなったの?」
「百田ちゃんも最原ちゃんも、彼女優先でつまんないから」
「なんだ、そういうこと」
確かに王馬くんは名前の挙がった2人とよく遊んでいて、2人とも最近隣のクラスの女の子とお付き合いを始めたと風の噂で聞いていた。
『誰でもいい』なんて言いながら、その裏には特定の誰かが隠されていて…という展開ではなかったことに安堵する。
そうだよね、この人に限って好きな人なんて…。
「まぁ好きな子ならいるんだけどさ」
「えっ」
「何その顔、オレに恋愛感情なんてないと思ってた?心外だなぁ」
「や、あの、そんなつもりじゃなくて」
「じゃあ何?」
「誰でもいいって、さっき言ってたから…」
「ふーん、そっか」
ショックと動揺で日誌を書く手が止まる。
好きな子って誰なんだろう。
いつどこで知り合った、どんな人なの?
いつから好きなの?どれくらい好きなの?
先程からそんな事しか頭に浮かばない。
「…みょうじちゃん、手止まってるよ?書くの代わってあげよっか」
「い、いいよ。大丈夫」
代わるも何も、そもそもこれは日直2人に与えられた仕事なんだけど。
そう思いつつも、私は冷静にその申し出を断った。
前に一度彼に日誌を頼んだ時、嘘八百を並べられて書き直しを命じられたことがあったからだ。
ペンを持ち直してサラサラと紙の上を滑らせれば、王馬くんはまた黙って、足を揺らしながらつまらなそうにそのペン先を見つめている。
嘘か本当かも分からない一言によって燻る私の胸の内なんて、王馬くんは知りもしないで呑気な顔をしている。
知りもしないで、ではなくて、本当は知る術も無いのだと分かっているのに。
付き合っていないどころか、告白する勇気すらなかったのに、彼が私の胸の内を知るはずがないのだから。
「ね、どんな子だと思う?オレの好きな子」
「…つまらなくない子?」
「にしし、それは前提条件!えっとねー、女の子でー、可愛くてー」
成績は普通で、おとなしくて、悪ふざけにも付き合ってくれて、ちょっと気弱で。
そんな風に続く彼の言葉を、聞きたくないのに防ぐ手段が思い浮かばなかった。
与えられる情報から勝手に作り上げられた空想上の女の子に、惨めな嫉妬なんてしたくない。
心の中では大声でそう叫んでいるのに、現実の私は時折相槌を打ちながら涼しい顔で日誌の空白を埋めるだけだ。
「…そんな子、どこにいるんだろうね?」
「えっ、もしかして適当言ってたの?」
「さぁ、どうかな。みょうじちゃんの都合のいいように解釈してくれていいよ!」
嘘か本当かどちらで解釈したとしても、どの道モヤモヤが残るような言い方だ。
どちらが正解なのか問いただしたって無駄だろうし、きっと私はしばらくの間、事ある毎に今日の出来事を思い出して一人悶々とすることになる。
それに、もし彼に真意を求めてしまったら、それはもう『あなたが好きです』と言ったも同然だ。
『好き』を伝える勇気が無いばかりか、それ以外の言葉ですら言えないなんて。
さっき頭の中で勝手に生まれたばかりの架空の女の子が、私を見下している気がした。
「…あーもう、そんなに思い詰めた顔しないでよ」
突然頭をくしゃくしゃと掻き回されて、意識が現実に戻される。
「べ、別に思い詰めてなんて…!」
乱された髪を整えながら平静を装うと、王馬くんはいつものように悪戯っぽい笑みを浮かべていた。
「はいはい。ねぇ、オレ知らなかったんだけどさ…みょうじちゃんって、思ってたより強情なんだね」
「なっ…王馬くんに言われたくないよ」
「にしし。あと、思ってたより気弱じゃないかも!」
その後は日誌を書き終えるまで私をからかうような言葉が続いて、彼女とか好きな子とか、そんな話が王馬くんから出てくることはなかった。
結局、あの話のどこまでが本当でどこまでが嘘なのか私は知らない。
私が心の中でひっそりと、あの架空の女の子に「負けないぞ」と宣戦布告したことを王馬くんが知らないのと同じように。
1/1ページ